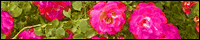
スカイブルーはマリンブルーに恋をした
暑い。
暑い暑い暑い暑い。暑い。
あたりで見下ろした足元だけが暗い。雲一つない空は、障害物がない限り地上を明るく、それ以上に熱く照らした。
夏だな、と財前は思った。
ネットを隔ててしまえば人っ子一人どころか影すらない一人ぼっちのテニスコートは妙に広く、暑苦しくて何も近づけたくないと感じる反面、なんだかさみしい。
暑いのは苦手だ。低体温が影響しているのだろう。変な体質にせいで寒くない季節でも冷え性に悩まされる。それにしては今グリップを握る手がじっとりと暑い。
顔を上げる。顔面を容赦なく日光が照らす。短パンのポケットに手を入れる。ゆったりとしたポケットは、少しだけひんやりとしている。そこからボールを取り出す。ネットの先にいる先輩が揺らいで見える。
そういえば今日の練習相手は誰だっただろう。自分と練習するのはレギュラー陣がほとんどだ。だからきっと先輩の誰かなのだろう。どうでもよい。
ボールを天高く放る。青い空が痛いほどに輝く。体をひねってラケットを振り上げる。湿って重い空気が左腕にまとわりつく。暑苦しい。勢いのままに、体の覚えた動きのままにボールを打つ。小気味よい音と同時に、腕に衝撃が走る。ボールはネットの向こうに飛んだ。
すぐにボールが返ってくる。もう走りたくない。暑くて暑くて仕方がないのだ。それでも体は勝手に動く。涼しいところに行きたい。もはや反射的にボールを返す。暑い。休みたい。次のボールに備えて構える。それなのになかなかボールが返ってこない。おかしい。暑い。
「…ぃぜん!財前!!」
声が近づいてくる。周りには誰もいなかったはずなのに、おかしい。暑い。声に反応して棒立ちになった自分の、やり場もなくぶらりと垂れ下がった腕を誰かがつかんだ。熱い。離してほしい。嫌ではない。不快というわけではない。ただ暑くて熱くてどうしようもないだけなのだ。
頭がぐわんぐわんする。そうえいば名前を呼んでくれたのは練習相手ではなかったか。わからない。何も考えられない。考えたくない。考えた先から矛盾してばかりだ。訳が分からない。もはや握力をなくした腕から滑り落ちらラケットがカランカランと鳴ることだけが、はっきりと知覚できる唯一だった。
目を開くと、視界一面に青が広がっていた。それでも先ほどのような痛々しい青ではなく、少し濃くて、暗くて、それでも優しい色。
不自然に規則的な風がそよぐ。先ほどよりは和らいだもののまだ暑い中、風のあたるところだけが涼しい。頭の後ろには固いようで柔らかい感触があり、目前には青い色以外に何も見えない。
どういうことだろう。自分は今どうなっているのだろう。起き上がろうとして、自分が寝転がっていたことに初めて気づいた。完全に起き上がる前に視界が晴れる。しかしあたりを見渡す前に、頭にズキリとした痛みが走り、立ちくらみのように視界が瞬いた。
「無理せんとき」
頭上から声がする。それとともにいささか乱暴に頭を押さえつけられ、再び後頭部に独特な感触が当たる。それから真っ白な視界が一瞬にして暗くなる。
立ちくらみのような様子が落ち着くまでおとなしくしていると、少しは現実を受け入れることができた。まず、頭に乗っているのは青いタオルらしい。どれだけの時間かぶっていたのだろう、いささか湿っているような気がする。頭に敷いているのは誰かの脚、いわゆる膝枕された状態らしい。しかし女子にされているといううらやましい状況ではない。母親以外にされた覚えなどないが、女子特有の柔らかさがないのだ。では誰だろうか。それは先ほど声をかけ、再び寝かしつけてくれた人に違いない。
まだ頭には鈍痛が走るが、ゆっくりと手を動かして顔にかけられたタオルを取って胸に置く。予想していた通りの人と目があった。
「…ユウジ先輩」
「落ち着いた?」
「ええ、まあ」
やたらと神妙な面持ちの先輩に返事をすれば、その顔がぱっと明るくなった。
「しかし驚いたわー!なんや変だと思って手ェつかんだら倒れるんやもん」
「はあ」
「自分暑いの苦手なんやったら無理したらあかんで?倒れる前に言わな…あ、財前の分のスポドリ持ってきてあるから、さっき意識朦朧なところに無理やり飲ませたけどもっと飲んどき」
「すんません」
おかんか!と突っ込みたくなったが、そういう気分ではなく、適当に返事をする。そこでようやく自分は朝練の最中に熱中症か何かで倒れたのだろうと知った。そういえば今朝はやけに暑かったような気がする。思い出そうとしてもその時の記憶はもやがかかっているようではっきりとしない。
それにしても先輩が近い。先ほどうらやましい状況ではないと表したが、嘘だ。確かに男が男に膝枕されてもうれしくはないかもしれない。しかしそれが好きな人だったら、恋人だったらどうだろうか。つまり自分たちはそういう関係なのだ。
遠くからボールの弾む音がする。まだ朝練中なのだろう。自分が気を失っていた時間はそう長くはないらしい。そうだとしたら今の状況はあり得ない。部員の目が光っているうちに二人きりになることなどあるはずがないのだ。というのも、この関係は他の部員、少なくともレギュラー陣には明らかであるといっても過言ではない。自ら報告したわけではないのだが、いつの間にか周知のものであった。一般的にあまり認められた関係ではないが、受け入れてくれた。それだけならばまだよかったのだが「リア充爆発しろ!」がと茶々を入れられてばかりだ。もともとおおっぴらにイチャイチャする気などないのだが、なんというか、面倒な感じになってしまっているのだ。
「なんか珍しいっすね」
「何が?」
「先輩たちに邪魔されないの」
そう言うと、先輩は驚いたような合点がいったような表情で口を開いた。それから悪戯っぽく、とてもとてもかわいらしくニッと笑う。まぶしい。頭がくらくらして全身がカッと熱くなる。嫌な感じはしなかった。
「今日は、ほら、自分の誕生日やんな」
「あ」
言われて初めて気づき、その様子に先輩は笑みを濃くした。サプライズ成功といったところか。ただでさえツリ目がちな目がさらにつり上がる。狐のようだが、子どもっぽくもある。かわいい。惚れた弱みかもしれないが、今の自分にはかわいくて仕方がない。
かわいいかわいい恋人が手を伸ばし、膝の上の頭を抱える。かなり苦しい体勢を強いられ、その勢いで額の汗が飛ぶ。こんなに汗だくだというのに密着しないでほしい。そういえば先輩は汗だくでぶっ倒れたような男の頭を膝に乗せ、介抱してくれていたんだっけ。何だこの人俺のこと大好きだな、なんて考えてしまうのは混乱している証拠か。
頭が解放され、再び膝の上に降ろされる。やはり気持ち良い柔らかさというわけではないが、心地よい。それに抱えられている時は見られなかった顔を見ることができる。顔が好きで付き合っているというわけではないが、表情を見たいと思うのは仕方ないだろう。
しかし先輩の顔が赤い。目が泳いでいる。照れるくらいならあんなことしなければよかったのに。いや、最近は部活で忙し(く、先輩たちに邪魔をされて恋人らしいことなど何一つできてはいな)かったため、久しぶりにくっつくことができてうれしかったのだけれど。
ついこちらまで照れてしまい、目をそらせようと思ったところで、先輩がこちらを向き直った。思わずドキリとした。全身から熱が引かない。
「誕生日なんに朝から災難やったけど…おめでとう」
今度はふわりと笑って見せる。笑い方のために眼尻が下がってはいるが、元のツリ目のせいでやはり狐っぽさがぬぐえない。それでも先ほどの笑みを小悪魔とするなら、今の笑みは天使だ。俺だけの天使だ。
暑い。いや、熱いのか。わけがわからない。何も考えられない。そういえば朝にもこんな感覚に陥った気がする。まぶしい。でも真夏の太陽のように痛くはない。痛いのかもしれない。胸が苦しい。苦しいけれど不快ではない。
胸に置いていたタオルがない。抱えられたときに落ちたらしい。すぐ横に落ちていたタオルを拾い上げ、先輩に負けず真っ赤であろう顔を隠す。先輩を見えなくなるのは残念だが、もう見ていられない。目の前に青が広がった。
「今日はほんまあついっすわ」
それは、あついあつい夏の日のできごと。14歳の誕生日。