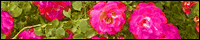
純情ストレートボーイ
「なあユウジ、こんなおまじない知っとるか?」
「なになに、『今月号はおしゃかわステーショナリー特集!消しゴムのおまじないで気になるカレのハートを射止めちゃおう!』なんやコレ」
「あんな、消しゴムの底に緑のペンで好きな奴の名前を書いて、最後の一文字になるまで使い切ったらそいつと付き合えるらしいで!あまずっぱいわー青春やわー」
「アホか」
「アホっすね」
「おい財前、途中参加の奴がいちゃもん付けんなや!」
「女子向けの雑誌を部室で堂々と広げる謙也さんが悪いんすわ」
「それに、そんなん信じる奴がどこの世界におんねん」
「でもな、その消しゴムを誰かに見られたら、そいつと付き合うどころか仲良うなることもできんらしいで。都合のええことばかりやないのが本物の証拠や!」
「手軽なおまじないのクセに一か八かすぎません?それに、」
「それで恋が叶ったら世の中の乙女は苦労せんやろ」
「それは……そうやけど……」
「せやろ?嘘っぱちや、嘘っぱち。ほなな、謙也ー」
「お先っすわ」
「ちょ、そんな……」
昼休みに訪れた3年8組。ユウジさんの席にいたのは、
「何してはるんですか、千歳先輩」
「こいつが今日提出の宿題やってへんって言うから、手伝ってんねん」
歩み寄る俺に代わりに返事をしたのは、ひとつ前の席に座るユウジ先輩だった。椅子を千歳先輩の方に向けて、足を広げて座っている。
宿題の指導を受けているはずの千歳先輩はといえば、ユウジ先輩のシャーペンを握り、ユウジ先輩の教科書を広げ、白紙のプリント(名前だけは書いてある)の上に突っ伏している。
自分の筆箱すら持ってこんで、何しに学校に来てんねん。
俺が小さくため息をついた事に気付き、ユウジ先輩が椅子ごと体を向けた。
「光こそどないしたん」
「義姉さんが『もう見ないからユウジくんにあげたら?』って」
そう言って俺が差し出したのは、お笑いのDVD。詳しくは知らないが、マニア好みの一品でなかなか入荷しないらしい。
言い終わらないうちに、先輩の表情が鬼気迫るオーラを帯びはじめた。
「こ、これはあの伝説の……!!!ありがとう、本当にありがとうございます!感謝してもしきれません財前先輩!!!」
「テンション暑苦しいっすわ」
先輩が始めた茶番によってとうとう完全に放置された千歳先輩は、だるそうにゆっくりと腕を動かし、ユウジ先輩の筆箱で遊び始めた。宿題をやれ、宿題を。
チャックを高速で開けたり閉めたり、シャーペンの芯を補充したり、消しゴムのカバーを外したり――
「ユウジ、なんね、これ。人に消しゴム借りたら返さんといかんたい」
千歳先輩がしげしげと眺めているのは、使いかけの消しゴム。
その底にうっすらと文字が書いてある。
緑色の文字で「財前光」と。
空気がびしりと音を立てて凍った。厳密に言えば、ユウジ先輩の周りの空気だけが。
謙也さんも真っ青な、残像が見えるくらいのスピードでユウジ先輩が消しゴムをひったくった。
「光、もしかして………………見たか?」
息も絶え絶えの問いに俺は答えた。
「見ました」
極端にシンプルな返答を聞いた先輩の目には、みるみるうちに涙が溜まっていく。そして、
「ち、ちち、ち、ちとせの、どアホおおおおおおおおぉぉぉぉぉ!!!!!」
叫びながら教室を駆け出していった。
「俺、なんかマズイことしたと?」
のんきな発言で俺は我に帰り、ワンテンポ遅れて先輩の背中を追った。
教室には、事情をこれっぽっちも知らない千歳先輩が残された。
西階段の3段目に、うずくまるように腰掛ける無言の背中に声をかけた。
「ユウジ先輩」
ひざの間に頭を埋めている先輩がこちらに顔を向けることはなかった。
「ここにいるって分かりました」
「…………」
「先輩、元気ないときいつもここで体育座りしてはるから」
「…………」
俺は、先輩の隣に腰を下ろした。
人通りの少ない階段は、昼休みの喧騒が嘘みたいにひんやりとした空気を湛えている。
踊り場に響くのは、遠くから運ばれてくる野球部の微かなノック音と、隣にいる先輩が鼻をすする音だけ。
ノック音が途絶える。昼錬が終わったのだろう。見計らったかのようなタイミングで、先輩が呟く。
「……見られた。もう終わりや」
「見られた、って……」
さっきの消しゴムか。使いかけだったけどまだ新品に近くて、緑の文字で俺の名前が――。
『誰かに見られたら、そいつと付き合うどころか仲良うなることもできんらしいで』
謙也さんの言葉がよぎる。そんなこと。そんなこと気にしとったんか。そんなことでくよくよするなんて、可愛いとこあるやん。
「別に、おまじないが何ですか。俺はユウジ先輩とずっと一緒におりたいし、別れるつもりなんて……」
「ちゃうわ」
俺の言葉を制するように先輩が声を上げ、学ランの裾をぎゅっと握り締めた。
「光こないだ、おまじないのことバカにしとったやん」
確かに、ケンヤさんが目をキラキラさせて語った話に、2人してアホだのなんだのとケチをつけた。
「ユウジ先輩も言うとったやないですか」
「……せやからますます、その……」
「その、何ですか」
「……恥ずかしいやん」
「……へ?」
思いがけない言葉に拍子抜けし、思いがけない間抜けな声が出た。
たった今までいじけていた先輩は、キッと俺を睨んで立ち上がった。
「せやからなあ!あんなデタラメ以外の何物でもないおまじないをもしかしたらってほんのちょっとでも信じてもうてもっと仲良うなりたいからって好きな奴の名前なんてホイホイ書いてまう俺のことも、光が、バカにするかもって、おもったら、お、お、おれ……」
矢継ぎ早にまくしたてた勢いはどこへやら、後半はほとんど泣き声混じりに語った先輩は、再びしゃがみこみ背中を丸めた。
俺だけ隠してるのはフェアやない、か。ホンマは見せたくなかったんやけど、しゃーないわ。
学ランの内ポケットからある物を取り出す。
その手を、先輩の手に重ねた。
「先輩、これ」
先輩の右手に、殆ど使い切った米粒サイズの消しゴムを握らせた。
緑色でたった一文字、「ジ」と書いてある消しゴムを。
体育座りでうつむいていた先輩は、右手を開いて虚ろな視線を落とした。
そしてがばっと顔を上げ、口をパクパクさせる。
「これ、え、これって」
ちびた消しゴムと俺の顔とをせわしなく行き来する視線がむずがゆい。
むずがゆいから、お返しに真正面から視線を合わせてやった。
「このおまじない、先に俺が成功してるんで先輩がミスったのはノーカンっすわ。多分」
目をそらさず、きっぱりと言い放つ。「多分」ってセリフも自信満々で言い切ったのは、後々考えたらアカンかった。
だけど、目を真っ赤にして鼻をすすり続ける先輩は、最後の一言に注意を払う余裕なんて無かったらしい。
先輩の目から、涙がぼろぼろ零れてくる。
「ひかるううううううう」
言いながら、飛びかからんばかりの勢いで抱きついてきた。
ぐしゃぐしゃになった顔を躊躇うことなく俺の胸にうずめた先輩を、全身全霊の力で抱きしめ返す。
「汚いっすわ」
「すまん」
「はあ」
「ひかる」
「なんですか」
「この消しゴムくれ」
「ええですけど」
「肌身離さず一生のお守りにする」
「キモいっすわ」
「うっさい」
「すんません」
おまじないなんて100%デタラメや。消しゴムが叶えてくれる、お手軽な想いなんて存在しない。
ただ、無駄じゃなかった。
俺のデタラメも、先輩のも。