<概略>
自慰表現有り/首絞め(窒息)プレイ/フェチ/DV/殺伐/
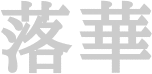
落ちる。茜さす空に見付からぬよう。落ちて、落ちて、落ちて──落ち続けて、ゆく。暗闇。其処はまるで底の無い沼のようだ。有益なものは何も存在しない。胸から下腹へ斬り開く、そんな夢を見る。残酷と片付けられぬ。だが多分、片付けても良いのだろう。自由には色があって、それはいつもエレンの蜂蜜のような瞳の色と同じだった。だから離せなかったのだ。だから何度も終わらなかったのだ。エレンは誰にでも平等に笑顔でじゃれつく。リヴァイはそれを面白くないと憤怒する──憤怒している、振りを、する。そうして折檻する。躾と謂う、名ばかりの暴力を。それを奮えば奮う度エレンは泣く──深く傷付き、泣いている、振りをする。必要性の有が無いので地下室の首輪は鍵もどこかにやりエレンは拘束されていない。が、エレンが自らそれを装着し、リヴァイに殺される場面を想像しながら抜いていることをリヴァイは知っていて、エレンが加減なく果物ナイフで手首を深く切り付ける癖を持っていることも知っていたし、かろうじて息継ぎが出来るか、出来ないか、のところまで──きりきりと喉を締め付け、鎖の長さを調整し首輪を引き伸ばし、て、縛り付けて自慰行為に励んでいるということも重々知っていた。その様は端的に云って異様だった。若いペニスは硬く勃起し、エレンの顔は徐々に青ざめていく。深々と刺したディルドを抜き差ししながら、その度に赤い肉がそれに絡み付いて蠢いた。エレンのペニスはひくりひくりと脈打ち、粘っこい先走り汁を溢れさせる。その美しい金色の双眸は鈍く曇り、呼吸は小さなものへと変わっていく。射精が近くなると、きゅう、と縮みあがり、惜し気もなく脚を開いて痴態を晒していた。おそらくは、リヴァイが観ているのは知らないのだろうが、観ているリヴァイからすればつくづく億劫だ。薄暗闇でエレンの奇行だけが瞼に焼き付く。まるでこの子供の血液はペニスと睾丸にしか通っていないのでは無いのか、とリヴァイが思わざるを得ない程度には──エレン自身の躰はどんどん血の気が失せた色になり、薄い陰毛のなかに聳える薄紅のペニスは、ぐっしょりと濡れそぼり、睾丸は痛々しく土気色に近付き、今にも爆発しそうな程に張り詰めている。首には首輪が巻き付いて、それなのに射精寸前だなどとあんまりだ。あんまりの光景にくらくらする。エレンの脚はだらりとシーツを這うようにぐったりと垂れている。
「っんんぅ、…ア! ああッ!」
あァそろそろいくな、こいつ──リヴァイがそう思った直後に、エレンは射精し、また、その射精は力無く、呆気ないものだった。エレンの腹に向けて噴出されたものが、とろとろと白濁を帯びる粘液が、溢れ、零れ落ちる。リヴァイは一連のそれを眺めて、自身の猛ったペニスを沈めるべくエレンへの罵倒の言葉を、頭のなかいっぱいに唱える。決して小さな声にさえ出さぬように、あくまで脳内だけでエレンを呪う。特に呪う理由も原因も無いのに、呪う。そして先程までのものが吹き飛び消滅する様を確認し、漸くリヴァイの下半身はある程度、秩序に近いものを護ろうとする。萎えていく自身に、安堵なのか解らぬ溜息を、1つ吐く。
「……レン、エレン、おい、エレン」
如何せん真っ当な人間には理解し難いが、どうせ死ねないくせに繰り返される、エレンの自殺ごっこにも似た自慰行為が終わり、そもそもこいつはいったい何がしてえんだ、とリヴァイは悦楽の余韻を、意識を飛ばす寸前の酩酊状態を保つことで味わうエレンを、容赦なく蹴り起こした。
「おい。とうとう死んだか? おめでとう」
「…………生き、てま、す。残念…ながら」
むくりと起き上がるだけで無防備に晒される、子供の細い躰は、いつも外気に翻弄される。それはリヴァイにも。どの日にあっても違和感の無い光が、地下にあるこの部屋にだけはどうしても届きはしない。馴染みたくて無理をした、エレンはただ愛を知りたくて嘘をつく。
「…兵長に…看取られるなら、本望ですけど……取り敢えず、服、着ていいですか? ……寒い」
「駄目だ。二度手間になるじゃねえか。どうせ脱ぐんだ、その惨めなままでいろ」
「別に俺…真っ裸でも、惨めも何も、思いませ、んが……」
ほんとうはエレンにもリヴァイにも手の届かないところにある、何か。無言で説得したくてそっぽを向いた。きっとそうだろう、誰だって、優しいヒトに優しくされたい。だがたったそれだけのことが出来ないので、優しくしないし、優しくされたくないふうを装う。不完全で不毛だ。『自虐』と『誠意』を間違えたままの子供の、汗が滲む額を、リヴァイの冷たい指先がなぞった。完璧だ、もう何も要らないと、エレンは平気で思ってもいないことを思っている。昼をも欺く夕闇の胡乱な眩さは、エレンを救うことなんぞわけが無いのだ。リヴァイは別に、エレンにも、エレンの愚かな行為にも、何にも、怒ってはいないのだ。呆れているわけでも無い。いっそ愛らしいとさえ、思っている。自身の生死を自在に操っている気になっているエレンが、滑稽で、ひどく愛おしい。リヴァイはエレンが死にたがっているのを知っている。知っているが見ない振りをする。もっと云えばエレンがリヴァイに殺されたがっているのをリヴァイは知っている。それも、知らぬ振りをする。おそらく、エレンはそろそろジャンやアルミンあたりと、セックスでもしたりするのかも知れない。きっとリヴァイはそれを見て面白くない振りをするだろう。そうしてリヴァイが与える折檻に、エレンは律儀に傷付く──傷付く振りを、する。エレンを、殺すのだ。死なない程度に。リヴァイは、エレンが、また死ねなかったと、こうべを垂れる都度こう思う。死なせてやるものか、と。楽になぞさせてやるものか、と。実際、ほんとうにそうなったら、エレンは深く傷付くのだろう。或いは、傷付いた、振りを、するのかも知れない。リヴァイはエレンをめちゃくちゃに嬲りながら、いつも死なない程度に痛め付ける。瑣末で良い、エレンの記憶に残るように──翌朝にはエレンの躰が傷を癒そうが事実として刻み込めるように。また死ねなかったと悲しい目をする、こんじきの硝子玉のような双眸を思い出して身震いがした。ほんとうのところエレンにはリヴァイしか居ないと謂う訳では無いし、リヴァイにもエレンしか居ないと謂う訳でも無い。けれど死ぬなんて赦さない。リヴァイはエレンを楽にしてやる気など更々無いのだ。エレンが望むものであるのならば、死、以外のすべてをやろう。『幸せ』も、『愛情』も、『優しさ』も、『快楽』も、『失望』も、『絶望』も、『痛み』も、『恐怖』も。自分以外のどこかの誰かが、それらを与えるのを赦さない。そういう事実が欲しいだけだった。つまりはそういう触れ方だ。誰も悲しませない。揺さぶられぬ感情は、何の為だとエレンに問う。答えられぬエレンのまなこに、なぜ黙るのかと質したい。
「気持ち悪ィな、エレンおまえ。ほんとうに気持ち悪ィ。それでもおまえを好きな奴が存在するのが不思議でならねえよ」
「…はあ。…………俺は…わりと、好きですけど、……貴方の顔とか」
「顔ってのは心外だが」
「じゃあ、強い、ところ、とか…? あと…俺を、憐れまないところ、とか……」
「じゃあとは何だ。じゃあ、とは。だが俺はおまえが思っている程、強くもねえし、確りおまえを憐れんでいる。エレンよ」
「それなら──それなら兵長は、こんな化け物で変態な俺を、憐れに思いながら抱くんですか? それこそものすごく気持ち悪ィ」
「まるで俺まで変態みてえな言い草だな」
「そう言ってる、んですよ。…解りませんでしたか」
「もうおまえは嬌声以外口に出すな」
「え。…ふつうに無理ですけど?」
「黙れ。命令だ」
エレンが態とらしく微笑んでみると、リヴァイの指が信じられぬ程に優しく、未だ間抜けな姿のエレンの、髪をゆっくりと梳いた。重力に従い、水のようにさらりと落ちる猫っ毛。まだエレンが入団してから、差程、長いことは経っていない筈であるのに、もっと昔からリヴァイの傍らに在ったような気がして、その──嘘をつくとすぐ真っ赤に染まる子供の耳に軽いキスを落として、齧る。鍵の閉まっていない首輪を外し、まだ柔肌に残る、赤い痣を、確認するかのように舌先で舐め辿った。エレンはおとなしく抱かれる。ふたりで横たわるには狭くてきつい、エレンのシングルベッドの上で、ゆっくりと体温を分かち合うかの如くリヴァイはエレンの裸体を見詰めながら、薄い背にその手をまわした。エレンから匂う生臭い残り香は、きちんと処理すれば簡単に出来た筈なのに、つい今し方行われていた自慰の後始末を、態としていない。エレンの下腹には精液の残骸、タンパク質の粘ついたそれが残っている。リヴァイは少しだけ嗤って、それ以上に眉を顰め、嫌悪の眼差しでもってエレンを憐れんだ。何も知らず観てもいない振りをして、リヴァイは手の平でエレンの乳首を転がして遊ぶ。どちらが搦め捕ったかなんぞ、存外、それはたいして意味の無いことなのかも知れない。堕ちる。茜さす空に見付からぬよう。堕ちて、堕ちて、堕ちて、堕ちるところまで──落ち続けて、ゆく。リヴァイがエレンの尻をバチン、バチン、音がする程に平手で打った。
「あっあっあっい、ッ…てえ! あああぁぁ!」
エレンの白い肌に赤い手型が浮き上がるまで何度も何度も。痛いです、へいちょう。エレンは泣く。煩く喚き倒す。両腕を伸ばし、全身でリヴァイに縋り付こうとする。すると、リヴァイは、エレンの手を雑に払いのけ、何だおまえ、叩かれて悦いのか? と口角を上げ、次はエレンの顔をめちゃくちゃに殴る。鼻血が出てしまおうとも構わない。かとしたら、一瞬後には、リヴァイは、おまえなんかはやく死ねばいい、と口にしながら、エレンを優しく抱き締めるのだ。おそらくどちら共ほんとうの気持ちなのだろう。矛盾しているようでいて、ほんとうは何も矛盾していない。きっと他人から見れば、よく判らない感情や行動。だがエレンとリヴァイには相違無く理解し合えている何かだ。リヴァイはただ赦されたい。誰でもいいから赦されたい。出来ることならエレンに赦されたい。エレンはただ赦されたい。誰でもいいから赦されたい。出来ることならリヴァイに赦されたい。こんな、無様で、倒錯的なセックスが、何ら贖罪にならぬとしても。嗤ったり泣いたり、エレンの表情筋は忙しなく変化した。
「ぅ、ぐっ…あ、あっ……ッ、う、いってェ…」
「痛えだと? 嘘つけ。殴られるのが好きなんだろう? 殴られて喘ぐ奴なんざ、おまえくらいだ」
「がっ…は、んんっ…んぅ!」
エレンがへらへらするのも、愛想笑いもやめると、リヴァイは普段以上に無表情になった。セックスは、理性のペルソナを脱ぎ捨てる行為なのでそうする。だから互いにいろんな表情と欲望を見せ付け合う。
「チ、……汚ねえな。おまえの血が着いちまったじゃねえか」
「へい、ちょうが…思い切り、ぶん、殴るから、でしょ…」
「あ? 俺にどつきまわされて興奮するんだろ、おまえは。脳みそ入ってんのか、その粗末な頭ンなかには」
「けほっ…………あー…もう、鼻血が気管に、入った…つら、い……、けほっ、げほっ、ごほっ…」
「そうかよ。俺には関係ねえ」
などと言いながらも、リヴァイの手のひらはエレンの背中を優しくさする。調査兵団兵士長、人類最強、などという薄皮を1枚1枚剥いだ中身のリヴァイは、優しく、冷徹で、甘くて、サディスティックだった。こんなもの、大切にしてどうなるのだ。大切なものを辞書に探すような子供だ。そのくせ光るものを疑って、暗闇に引き摺り込むような奴だ。おまえの幸せを願えずに、いっしょに落ちろと言って、受け入れられて尚、泣かない奴だ。まだ年端もいかぬガキのくせに。エレンは頭がおかしいのだ。だからリヴァイの暴力を悦び、平気に笑うのだ。嬉しいとか幸せだとか言うのだ。そんなエレンをリヴァイは心から羨ましいと思うから、はやく壊れて欲しいとも思った。リヴァイが知らぬ存ぜぬところで、エレンが傷つけられるのは嫌だ。太陽の下で、屈託無く笑って、知らない奴に曇らされるのは我慢がならない。考えたくもないのに何億回も考えてしまって、1度で済むのならば数として正しいので、今からエレンの欲望を解放する。理由なぞ無いのだ。敢えてつくらなければ。意味さえも。リヴァイもエレンも互い、器用になれぬ(ならなくて良い、このままで良い)。エレンが言うのを知って待っている。リヴァイの小さな──ほんとうに小さな臆病さで、エレンは隙あらばいつでも消えたい。死ぬにはまだ、あまりに大掛かりなのだ。
「……貴方に残る方法が見つからない」
毒にも薬にもならない純情が、たった1つの爪痕を残したくて、生まれ変わるくらいしてみせると豪語する。底のない沼のような牢獄は、空っぽのくせに吸い込んでくれやしない。エレンの腕や脚や眼球などを吸い込んでくれもしない。消えてしまえ、死んでしまえ、この化け物──言われなくても、願っていた。誰よりも、エレン自身が願っていた。誰かこの力を横取りしてくれまいか、そういつも、つよく願っていた。そうすれば心臓を、譲渡出来る。唐突にリヴァイが言うのでエレンは、まさか、と回答した。
「だが、おまえはいつも譲渡したがっているじゃあねえか。なぜ知らない振りをして、はぐらかすんだ。無意味だろ」
「……俺にとっては、無意味じゃあ…無い、です」
友達でも無い、恋人では更に無い。リヴァイは、エレンへ緻密な計画を話す。抜け漏れ無くはなくとも、完璧はイコール偽物だと。片目をつむったほうが真っ直ぐに歩けるのだと──そんなことすら知らぬ程、エレンは無知な子供では無い。
「俺に譲渡してみろ、消えるんじゃあ無くて。誰かに奪われたり、売りつけたりするんじゃあ無くて。ただ、譲渡するんだ。夜に。皆が寝静まった頃に」
「……貴方には何もあげたくない」
ぺっ、と吐き出した血の塊。殴られた痣は殆どもう、早くも消え失せている。いよいよ化け物染みていく躰を、リヴァイがエレンを殴ることによって突き付けられ証明された。ごふっ! エレンは汚らしく声を上げ血と共に胃液を吐いた。リヴァイのこぶしが、エレンの鳩尾に当然の如く落とされたせいだ。だが受けた衝撃も、激昂さえ、跡形も無く、そのうち傷痕ごと消える。夢であるかのように。リヴァイを嘲笑うかのように。それでも、傷が見る見る消え果てても、痛みだけはずっと残っていくのだ。エレンは泣いた。痛みすら残らないよりずっと良いのだと。リヴァイに与えられる痛みだけが真実、唯一消えぬ本物だった。
「痛えか」
リヴァイは幼い子供をあやすような仕草でもって、エレンの髪の毛を掬って撫でた。リヴァイの膝に抱かれ、エレンは嗚咽混じりに声を漏らす。ように、答える。そりゃあ痛いけれど、そんなことで泣いてるんじゃあないです。リヴァイがエレンの躰につけた痣が全部、何もかも、無かったかのように消えるのが悲しいのだ。確かに有ったのに。臀を叩かれるのも顔面を殴られるのも、とても痛かった。ここで手を切断しても生えてくるのだろうそんな偽物の躰に。エレンはそういうことを言いたかった。だけれど言えない。代わりに懺悔する。
「すきですよ、兵長……貴方が。だからもっと…欲しい……」
エレンがそう言うと、リヴァイは虚をつかれたように切れ長の目をおおきく丸く見開いた。その顔が好きだ。もっと見ていたい。と、思う。何度でも、もっと近くで、もっと、もっと。
「痛くされたほうが好きなんて、変態でしかねえな。なァ? エレンよ」
「ッ……ア、んう、……は、は…っ」
「その可愛い口で言ってみろよ、ほら」
「は、ぃ……んんッ…あ、あぁ…俺は、へんたいで、…す! 痛くっ…された、ほうが……すき…っうぅあ、あっ……く、ン!」
「はっ…馬鹿みてえだな。あァいや、おまえは元から馬鹿だったか」
「へいちょうが、言わせたんじゃ…ないですかっ……」
「おまえが言いたそうだったからな」
「っそ…、んな、の…ッ」
全然違う、とは、エレンには言えない。臀を張られて痛くて気持ち悦い。鼻が折れる寸前まで顔を強打されて、気持ち悦い。リヴァイになら、何をされても気持ち悦い。し、おかしくなる程ひどく興奮する。リヴァイの、存外おおきな、手。かさついて、剣だこが潰れて硬くなったそれをなぞる。エレンの真っ直ぐな指にはまだそれが無い。そういう小さな事実が、ブレードを持って闘ってきた歳月の差であるのだ。今日のリヴァイの折檻は、比較的甘く優しい。視線こそ鋭いが散々に甚振ったエレンに今は膝を貸し与え、尻穴をゆるゆると撫でているので、こそばゆい。酷いときならばもっと、エレンの肋や鼻が折れるくらいには平然と暴力を振るうのだ。どうすればリヴァイが怒るか。どうすればリヴァイは眉を顰めるか。どうすればリヴァイがエレンを抱き締めセックスしてくれるのか。エレンは何となく判ってきていた。『喜び』を軽蔑し、『感触』を軽蔑し、『悲劇』を軽蔑し、『自由』を軽蔑し、『貞節』を軽蔑し、『希望』を軽蔑し、『休息』を軽蔑し、『優しさ』を軽蔑し、『光』を軽蔑し、『幸福』を軽蔑し、『夢』を軽蔑し、『愛情』を軽蔑し、『恋慕』を軽蔑し、『憧れ』を軽蔑している、大人を。
「エレン。剥がすぞ」
「……な、にを」
「解ってやがるくせに訊くんじゃあねえよ」
優しい優しいリヴァイの声。ほぼ同時にエレンは哭声をあげる。
「ゔっあぁっ! あ、ぁあ゙あ゙あ゙あ゙あ゙あ゙あ゙────…ッ!!」
小振りのペンチで剥がれた爪が落ちる。桜貝のようなエレンの爪が。残る白い半月は抉り取る。真っ赤な肉がめくれあがったそこから見える、脈打つエレンの血液は沸騰したかのようだった。それを1本1本と、計10本。爪を剥がれる。その度にあがるエレンの悲鳴で、地下室が満たされていく。
「あぎ、くっぐううぅ…!」
「こんなただの拷問、それでちんぽ勃たせて変態以外の何だってんだよ」
「ゔあ、んっん゙ん、…っぅ゙ああああっ!」
剥がし終えた10枚の爪を、リヴァイは大切そうに拭って小瓶に保管する。小瓶には既に、10や20では無い数の、エレンの爪が詰められていた。相変わらず綺麗な欠片だ、リヴァイは少々満足げに、コレクションを自慢するようにエレンの目の前でちらつかせ、ポケットに仕舞った。変なの。エレンは泣きながら思う。そんなものを集めてどうするのだ。貴方には何も譲渡したくないと言った筈が、リヴァイは勝手に奪い据ぎ取ってゆく。エレンには理解が出来ないのでリヴァイの単なるフェチズムの1つかも知れぬと自由解釈で納得をする。
「ゔぐ、…ふ、っぅ゙ああ゙っう、ぅ」
「ほら、腹に力入れろ」
「はっ…は、はあ、はあ……──うぐッ!!」
鳩尾に落とされた踵。げほげほと咳込んで、引きちぎらんばかりに乳首を引っ張られ、つい先刻ディルドを挿入していたこともあり、慣らしてはいてもまだ充分では無い尻穴に無理矢理リヴァイのペニスを捩込まれても出血はしなかった。こぶしを突っ込まれなかった分、リヴァイももしかしたらただ愉しんでいるだけなのかも知れない。アルミンとミカサとじゃれあっているところを──リヴァイに見られた。否、エレンは態と見せ付けた。久しぶりだと駆け寄って、飛び込むようなハグをして、頬にキスをし合って笑い合った。幼い子供の頃のように。リヴァイには決して見せぬ、気安い無邪気な笑顔で。リヴァイは少しだけ驚いたように瞠目し、直ぐに顔を歪めた。面白い筈が無い。
「おい、エレンよ。どうして欲しい? 首を絞めてやろうか」
「んっ…んぐ、ぅぐ……」
己の呼吸さえ制御出来ず、それでも必死にエレンはこくこく頷く。優しく触れられるくらいならば、もっともっと酷薄で、刹那的に、支配的に冒涜されたい。リヴァイの手のひらがエレンの首に絡み付いてゆく。初めはゆるりと、たいした力を込めるわけでも無い、お遊び程度で絞められる、白く頼りない首筋。いつかリヴァイが殺してくれるだろう日を夢見て、自慰行為に耽るのは背徳感が背をぞくぞくと駆け巡る──それが具現化されていく、と謂う快感に。日を置かずにリヴァイと体を繋げ合わせている上に首輪を用いた自慰も欠かさぬからか、薄い色をした精液が少量噴く程度だが、幾度めか判らぬ空イキをしていると、頸動脈と椎骨動脈を同時に抑えられれば、脳が溶けいくような、甘やかな低酸素症でぼんやりとしてくる。
「あっ、ッ、……はぁ…、」
「っ…すげえ締まりだな。そんなに悦いかよ」
「ゔぐ、…ふ、っぅ゙ああ゙っう、ぅ」
呼吸がつっかえ、競り上がる悦楽にエレンは身震いした。徐々にリヴァイの抽挿はスピードをあげて、それに相俟って喉に食い込む指に力が入ってゆく。エレンは夢中で擦りあげて、先走りで滑りのいい自らのペニスを、根本から扱く。
「ゔむぐッん゙ん゙ん゙ん゙ん゙ん゙…!」
じわりと額に汗をかきながら、エレンは、リヴァイがエレンの首を刎ねる姿を頭のなかいっぱいに夢想する。この、無駄に治癒力の高いエレンの躰は、ふつうの遣り方では簡単に死ねないだろう。それでも、リヴァイがいつかうなじを削ぎ、殺してくれるところを思い描く。例えばこめかみなんかを銃で撃ったところで、おそらく脳みそが僅かに飛び出る程度で傷は塞がってしまうであろう忌ま忌ましい躰だ。そんなふうにエレンが潸潸しているうちに、近かった射精が1歩遠退いて、リヴァイはチ、と小さく舌打ちをし、自分の下で鳴くエレンに思いを巡らせる。リヴァイは、この部屋には存在しない昼間の太陽の匂いを思い出すかのように鼻をひくつかせた。脳裏に浮かぶ、咲うだけで向日葵を思い起こす整った顔立ちの子供が掠れた声で、へいちょう、と明るい声で呼ぶところを思い出し、その官能に火を灯す。リヴァイは込み上げて来る嗤いを堪え、淡々とエレンに告げた。
「ガキが1丁前に男を誘って…いったい今までに、誰に抱かれてきたんだ? 穢えな」
もう届いている、エレンが言う。
「あっ…ふぁ……、かはっ……そんな、の、もう、」
覚えていない。数なんて。
どうでも良いことだ。今この手はもう届かせられる。もし届かないのなら、それはリヴァイが拒んでいるだけだ。ほんとうは途中が気持ち悦いだけ。エレンは解らない。いつまでも解らない。解らないでいたい。痛みを消す理由を、知りたくないのだ。また交わるように信じてもいる。
「ひっ、…く、はぁ…、もっと、もっ…と、締めて……あふっ、首…ッ」
「息継ぎも出来なくなるくらいにか」
「そ、う、息継ぎ…なんて……したくない……」
「変態」
「ああっ……、ん、んんぅっふ、あっ」
「……随分お幸せそうだな? おまえだけ」
「んんんッ」
頸動脈と椎骨動脈を最早殆ど機能しない程のつよい力で抑えれば、エレンは心底恍惚とした表情を浮かべた。エレンの首が締まる度、アナルの入口もきつく締まっていくものだからリヴァイはハメた穴のなかでペニスが痛い程だった。女の締まりより余程締まる。子供の爛れたアナルはリヴァイのペニスを奥深くまで飲み込み、決して離すまいと躍起になる。
「ァア、は、はっんんっ…うぅうん、ふ、ふあ」
「ずっとイキっ放しで苦しくねえのか。すげえな」
「んむんん…んぁ、んっんっんんん…っ」
もうエレンは透明な汁を零すだけで射精をしなくなっていた。迸る悦楽は、生死の境目。空イキばかりを間断なく繰り返し、その寸隙に生きているのか死んでいるのか判別し難い蜂蜜色が蕩けてリヴァイの後ろあたりを見詰める。堕ちる。茜さす空に見付からぬよう。堕ちて、堕ちて、堕ちて、堕ちるところまで──落ち続けて、ゆく。痛えな。リヴァイは締め付け過ぎだと謂う意を込め、エレンの臀をまた平手で打った。途端エレンの喉が、ひゅ、と鳴る。反射的に吸い込んだ息を吐けずにいるのだ。じんと熱を持つ臀がひりつく。エレンがリヴァイの与えるものすべてに呼応し、何れ程交わっていても関係無く、それらは、ただの平行線となって温度差を顕著なものにした。だが平行線は少し歪んでいて、子供の言い訳を通用させる。子供の孤独を飽和させる。だからいつまでも現実を見ない、エレンは、赦されないことを赦していた。光と影が輪舞する空間。併存、不覚にも、深く、愛されない今を、とても愛している。
自慰表現有り/首絞め(窒息)プレイ/フェチ/DV/殺伐/
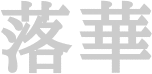
落ちる。茜さす空に見付からぬよう。落ちて、落ちて、落ちて──落ち続けて、ゆく。暗闇。其処はまるで底の無い沼のようだ。有益なものは何も存在しない。胸から下腹へ斬り開く、そんな夢を見る。残酷と片付けられぬ。だが多分、片付けても良いのだろう。自由には色があって、それはいつもエレンの蜂蜜のような瞳の色と同じだった。だから離せなかったのだ。だから何度も終わらなかったのだ。エレンは誰にでも平等に笑顔でじゃれつく。リヴァイはそれを面白くないと憤怒する──憤怒している、振りを、する。そうして折檻する。躾と謂う、名ばかりの暴力を。それを奮えば奮う度エレンは泣く──深く傷付き、泣いている、振りをする。必要性の有が無いので地下室の首輪は鍵もどこかにやりエレンは拘束されていない。が、エレンが自らそれを装着し、リヴァイに殺される場面を想像しながら抜いていることをリヴァイは知っていて、エレンが加減なく果物ナイフで手首を深く切り付ける癖を持っていることも知っていたし、かろうじて息継ぎが出来るか、出来ないか、のところまで──きりきりと喉を締め付け、鎖の長さを調整し首輪を引き伸ばし、て、縛り付けて自慰行為に励んでいるということも重々知っていた。その様は端的に云って異様だった。若いペニスは硬く勃起し、エレンの顔は徐々に青ざめていく。深々と刺したディルドを抜き差ししながら、その度に赤い肉がそれに絡み付いて蠢いた。エレンのペニスはひくりひくりと脈打ち、粘っこい先走り汁を溢れさせる。その美しい金色の双眸は鈍く曇り、呼吸は小さなものへと変わっていく。射精が近くなると、きゅう、と縮みあがり、惜し気もなく脚を開いて痴態を晒していた。おそらくは、リヴァイが観ているのは知らないのだろうが、観ているリヴァイからすればつくづく億劫だ。薄暗闇でエレンの奇行だけが瞼に焼き付く。まるでこの子供の血液はペニスと睾丸にしか通っていないのでは無いのか、とリヴァイが思わざるを得ない程度には──エレン自身の躰はどんどん血の気が失せた色になり、薄い陰毛のなかに聳える薄紅のペニスは、ぐっしょりと濡れそぼり、睾丸は痛々しく土気色に近付き、今にも爆発しそうな程に張り詰めている。首には首輪が巻き付いて、それなのに射精寸前だなどとあんまりだ。あんまりの光景にくらくらする。エレンの脚はだらりとシーツを這うようにぐったりと垂れている。
「っんんぅ、…ア! ああッ!」
あァそろそろいくな、こいつ──リヴァイがそう思った直後に、エレンは射精し、また、その射精は力無く、呆気ないものだった。エレンの腹に向けて噴出されたものが、とろとろと白濁を帯びる粘液が、溢れ、零れ落ちる。リヴァイは一連のそれを眺めて、自身の猛ったペニスを沈めるべくエレンへの罵倒の言葉を、頭のなかいっぱいに唱える。決して小さな声にさえ出さぬように、あくまで脳内だけでエレンを呪う。特に呪う理由も原因も無いのに、呪う。そして先程までのものが吹き飛び消滅する様を確認し、漸くリヴァイの下半身はある程度、秩序に近いものを護ろうとする。萎えていく自身に、安堵なのか解らぬ溜息を、1つ吐く。
「……レン、エレン、おい、エレン」
如何せん真っ当な人間には理解し難いが、どうせ死ねないくせに繰り返される、エレンの自殺ごっこにも似た自慰行為が終わり、そもそもこいつはいったい何がしてえんだ、とリヴァイは悦楽の余韻を、意識を飛ばす寸前の酩酊状態を保つことで味わうエレンを、容赦なく蹴り起こした。
「おい。とうとう死んだか? おめでとう」
「…………生き、てま、す。残念…ながら」
むくりと起き上がるだけで無防備に晒される、子供の細い躰は、いつも外気に翻弄される。それはリヴァイにも。どの日にあっても違和感の無い光が、地下にあるこの部屋にだけはどうしても届きはしない。馴染みたくて無理をした、エレンはただ愛を知りたくて嘘をつく。
「…兵長に…看取られるなら、本望ですけど……取り敢えず、服、着ていいですか? ……寒い」
「駄目だ。二度手間になるじゃねえか。どうせ脱ぐんだ、その惨めなままでいろ」
「別に俺…真っ裸でも、惨めも何も、思いませ、んが……」
ほんとうはエレンにもリヴァイにも手の届かないところにある、何か。無言で説得したくてそっぽを向いた。きっとそうだろう、誰だって、優しいヒトに優しくされたい。だがたったそれだけのことが出来ないので、優しくしないし、優しくされたくないふうを装う。不完全で不毛だ。『自虐』と『誠意』を間違えたままの子供の、汗が滲む額を、リヴァイの冷たい指先がなぞった。完璧だ、もう何も要らないと、エレンは平気で思ってもいないことを思っている。昼をも欺く夕闇の胡乱な眩さは、エレンを救うことなんぞわけが無いのだ。リヴァイは別に、エレンにも、エレンの愚かな行為にも、何にも、怒ってはいないのだ。呆れているわけでも無い。いっそ愛らしいとさえ、思っている。自身の生死を自在に操っている気になっているエレンが、滑稽で、ひどく愛おしい。リヴァイはエレンが死にたがっているのを知っている。知っているが見ない振りをする。もっと云えばエレンがリヴァイに殺されたがっているのをリヴァイは知っている。それも、知らぬ振りをする。おそらく、エレンはそろそろジャンやアルミンあたりと、セックスでもしたりするのかも知れない。きっとリヴァイはそれを見て面白くない振りをするだろう。そうしてリヴァイが与える折檻に、エレンは律儀に傷付く──傷付く振りを、する。エレンを、殺すのだ。死なない程度に。リヴァイは、エレンが、また死ねなかったと、こうべを垂れる都度こう思う。死なせてやるものか、と。楽になぞさせてやるものか、と。実際、ほんとうにそうなったら、エレンは深く傷付くのだろう。或いは、傷付いた、振りを、するのかも知れない。リヴァイはエレンをめちゃくちゃに嬲りながら、いつも死なない程度に痛め付ける。瑣末で良い、エレンの記憶に残るように──翌朝にはエレンの躰が傷を癒そうが事実として刻み込めるように。また死ねなかったと悲しい目をする、こんじきの硝子玉のような双眸を思い出して身震いがした。ほんとうのところエレンにはリヴァイしか居ないと謂う訳では無いし、リヴァイにもエレンしか居ないと謂う訳でも無い。けれど死ぬなんて赦さない。リヴァイはエレンを楽にしてやる気など更々無いのだ。エレンが望むものであるのならば、死、以外のすべてをやろう。『幸せ』も、『愛情』も、『優しさ』も、『快楽』も、『失望』も、『絶望』も、『痛み』も、『恐怖』も。自分以外のどこかの誰かが、それらを与えるのを赦さない。そういう事実が欲しいだけだった。つまりはそういう触れ方だ。誰も悲しませない。揺さぶられぬ感情は、何の為だとエレンに問う。答えられぬエレンのまなこに、なぜ黙るのかと質したい。
「気持ち悪ィな、エレンおまえ。ほんとうに気持ち悪ィ。それでもおまえを好きな奴が存在するのが不思議でならねえよ」
「…はあ。…………俺は…わりと、好きですけど、……貴方の顔とか」
「顔ってのは心外だが」
「じゃあ、強い、ところ、とか…? あと…俺を、憐れまないところ、とか……」
「じゃあとは何だ。じゃあ、とは。だが俺はおまえが思っている程、強くもねえし、確りおまえを憐れんでいる。エレンよ」
「それなら──それなら兵長は、こんな化け物で変態な俺を、憐れに思いながら抱くんですか? それこそものすごく気持ち悪ィ」
「まるで俺まで変態みてえな言い草だな」
「そう言ってる、んですよ。…解りませんでしたか」
「もうおまえは嬌声以外口に出すな」
「え。…ふつうに無理ですけど?」
「黙れ。命令だ」
エレンが態とらしく微笑んでみると、リヴァイの指が信じられぬ程に優しく、未だ間抜けな姿のエレンの、髪をゆっくりと梳いた。重力に従い、水のようにさらりと落ちる猫っ毛。まだエレンが入団してから、差程、長いことは経っていない筈であるのに、もっと昔からリヴァイの傍らに在ったような気がして、その──嘘をつくとすぐ真っ赤に染まる子供の耳に軽いキスを落として、齧る。鍵の閉まっていない首輪を外し、まだ柔肌に残る、赤い痣を、確認するかのように舌先で舐め辿った。エレンはおとなしく抱かれる。ふたりで横たわるには狭くてきつい、エレンのシングルベッドの上で、ゆっくりと体温を分かち合うかの如くリヴァイはエレンの裸体を見詰めながら、薄い背にその手をまわした。エレンから匂う生臭い残り香は、きちんと処理すれば簡単に出来た筈なのに、つい今し方行われていた自慰の後始末を、態としていない。エレンの下腹には精液の残骸、タンパク質の粘ついたそれが残っている。リヴァイは少しだけ嗤って、それ以上に眉を顰め、嫌悪の眼差しでもってエレンを憐れんだ。何も知らず観てもいない振りをして、リヴァイは手の平でエレンの乳首を転がして遊ぶ。どちらが搦め捕ったかなんぞ、存外、それはたいして意味の無いことなのかも知れない。堕ちる。茜さす空に見付からぬよう。堕ちて、堕ちて、堕ちて、堕ちるところまで──落ち続けて、ゆく。リヴァイがエレンの尻をバチン、バチン、音がする程に平手で打った。
「あっあっあっい、ッ…てえ! あああぁぁ!」
エレンの白い肌に赤い手型が浮き上がるまで何度も何度も。痛いです、へいちょう。エレンは泣く。煩く喚き倒す。両腕を伸ばし、全身でリヴァイに縋り付こうとする。すると、リヴァイは、エレンの手を雑に払いのけ、何だおまえ、叩かれて悦いのか? と口角を上げ、次はエレンの顔をめちゃくちゃに殴る。鼻血が出てしまおうとも構わない。かとしたら、一瞬後には、リヴァイは、おまえなんかはやく死ねばいい、と口にしながら、エレンを優しく抱き締めるのだ。おそらくどちら共ほんとうの気持ちなのだろう。矛盾しているようでいて、ほんとうは何も矛盾していない。きっと他人から見れば、よく判らない感情や行動。だがエレンとリヴァイには相違無く理解し合えている何かだ。リヴァイはただ赦されたい。誰でもいいから赦されたい。出来ることならエレンに赦されたい。エレンはただ赦されたい。誰でもいいから赦されたい。出来ることならリヴァイに赦されたい。こんな、無様で、倒錯的なセックスが、何ら贖罪にならぬとしても。嗤ったり泣いたり、エレンの表情筋は忙しなく変化した。
「ぅ、ぐっ…あ、あっ……ッ、う、いってェ…」
「痛えだと? 嘘つけ。殴られるのが好きなんだろう? 殴られて喘ぐ奴なんざ、おまえくらいだ」
「がっ…は、んんっ…んぅ!」
エレンがへらへらするのも、愛想笑いもやめると、リヴァイは普段以上に無表情になった。セックスは、理性のペルソナを脱ぎ捨てる行為なのでそうする。だから互いにいろんな表情と欲望を見せ付け合う。
「チ、……汚ねえな。おまえの血が着いちまったじゃねえか」
「へい、ちょうが…思い切り、ぶん、殴るから、でしょ…」
「あ? 俺にどつきまわされて興奮するんだろ、おまえは。脳みそ入ってんのか、その粗末な頭ンなかには」
「けほっ…………あー…もう、鼻血が気管に、入った…つら、い……、けほっ、げほっ、ごほっ…」
「そうかよ。俺には関係ねえ」
などと言いながらも、リヴァイの手のひらはエレンの背中を優しくさする。調査兵団兵士長、人類最強、などという薄皮を1枚1枚剥いだ中身のリヴァイは、優しく、冷徹で、甘くて、サディスティックだった。こんなもの、大切にしてどうなるのだ。大切なものを辞書に探すような子供だ。そのくせ光るものを疑って、暗闇に引き摺り込むような奴だ。おまえの幸せを願えずに、いっしょに落ちろと言って、受け入れられて尚、泣かない奴だ。まだ年端もいかぬガキのくせに。エレンは頭がおかしいのだ。だからリヴァイの暴力を悦び、平気に笑うのだ。嬉しいとか幸せだとか言うのだ。そんなエレンをリヴァイは心から羨ましいと思うから、はやく壊れて欲しいとも思った。リヴァイが知らぬ存ぜぬところで、エレンが傷つけられるのは嫌だ。太陽の下で、屈託無く笑って、知らない奴に曇らされるのは我慢がならない。考えたくもないのに何億回も考えてしまって、1度で済むのならば数として正しいので、今からエレンの欲望を解放する。理由なぞ無いのだ。敢えてつくらなければ。意味さえも。リヴァイもエレンも互い、器用になれぬ(ならなくて良い、このままで良い)。エレンが言うのを知って待っている。リヴァイの小さな──ほんとうに小さな臆病さで、エレンは隙あらばいつでも消えたい。死ぬにはまだ、あまりに大掛かりなのだ。
「……貴方に残る方法が見つからない」
毒にも薬にもならない純情が、たった1つの爪痕を残したくて、生まれ変わるくらいしてみせると豪語する。底のない沼のような牢獄は、空っぽのくせに吸い込んでくれやしない。エレンの腕や脚や眼球などを吸い込んでくれもしない。消えてしまえ、死んでしまえ、この化け物──言われなくても、願っていた。誰よりも、エレン自身が願っていた。誰かこの力を横取りしてくれまいか、そういつも、つよく願っていた。そうすれば心臓を、譲渡出来る。唐突にリヴァイが言うのでエレンは、まさか、と回答した。
「だが、おまえはいつも譲渡したがっているじゃあねえか。なぜ知らない振りをして、はぐらかすんだ。無意味だろ」
「……俺にとっては、無意味じゃあ…無い、です」
友達でも無い、恋人では更に無い。リヴァイは、エレンへ緻密な計画を話す。抜け漏れ無くはなくとも、完璧はイコール偽物だと。片目をつむったほうが真っ直ぐに歩けるのだと──そんなことすら知らぬ程、エレンは無知な子供では無い。
「俺に譲渡してみろ、消えるんじゃあ無くて。誰かに奪われたり、売りつけたりするんじゃあ無くて。ただ、譲渡するんだ。夜に。皆が寝静まった頃に」
「……貴方には何もあげたくない」
ぺっ、と吐き出した血の塊。殴られた痣は殆どもう、早くも消え失せている。いよいよ化け物染みていく躰を、リヴァイがエレンを殴ることによって突き付けられ証明された。ごふっ! エレンは汚らしく声を上げ血と共に胃液を吐いた。リヴァイのこぶしが、エレンの鳩尾に当然の如く落とされたせいだ。だが受けた衝撃も、激昂さえ、跡形も無く、そのうち傷痕ごと消える。夢であるかのように。リヴァイを嘲笑うかのように。それでも、傷が見る見る消え果てても、痛みだけはずっと残っていくのだ。エレンは泣いた。痛みすら残らないよりずっと良いのだと。リヴァイに与えられる痛みだけが真実、唯一消えぬ本物だった。
「痛えか」
リヴァイは幼い子供をあやすような仕草でもって、エレンの髪の毛を掬って撫でた。リヴァイの膝に抱かれ、エレンは嗚咽混じりに声を漏らす。ように、答える。そりゃあ痛いけれど、そんなことで泣いてるんじゃあないです。リヴァイがエレンの躰につけた痣が全部、何もかも、無かったかのように消えるのが悲しいのだ。確かに有ったのに。臀を叩かれるのも顔面を殴られるのも、とても痛かった。ここで手を切断しても生えてくるのだろうそんな偽物の躰に。エレンはそういうことを言いたかった。だけれど言えない。代わりに懺悔する。
「すきですよ、兵長……貴方が。だからもっと…欲しい……」
エレンがそう言うと、リヴァイは虚をつかれたように切れ長の目をおおきく丸く見開いた。その顔が好きだ。もっと見ていたい。と、思う。何度でも、もっと近くで、もっと、もっと。
「痛くされたほうが好きなんて、変態でしかねえな。なァ? エレンよ」
「ッ……ア、んう、……は、は…っ」
「その可愛い口で言ってみろよ、ほら」
「は、ぃ……んんッ…あ、あぁ…俺は、へんたいで、…す! 痛くっ…された、ほうが……すき…っうぅあ、あっ……く、ン!」
「はっ…馬鹿みてえだな。あァいや、おまえは元から馬鹿だったか」
「へいちょうが、言わせたんじゃ…ないですかっ……」
「おまえが言いたそうだったからな」
「っそ…、んな、の…ッ」
全然違う、とは、エレンには言えない。臀を張られて痛くて気持ち悦い。鼻が折れる寸前まで顔を強打されて、気持ち悦い。リヴァイになら、何をされても気持ち悦い。し、おかしくなる程ひどく興奮する。リヴァイの、存外おおきな、手。かさついて、剣だこが潰れて硬くなったそれをなぞる。エレンの真っ直ぐな指にはまだそれが無い。そういう小さな事実が、ブレードを持って闘ってきた歳月の差であるのだ。今日のリヴァイの折檻は、比較的甘く優しい。視線こそ鋭いが散々に甚振ったエレンに今は膝を貸し与え、尻穴をゆるゆると撫でているので、こそばゆい。酷いときならばもっと、エレンの肋や鼻が折れるくらいには平然と暴力を振るうのだ。どうすればリヴァイが怒るか。どうすればリヴァイは眉を顰めるか。どうすればリヴァイがエレンを抱き締めセックスしてくれるのか。エレンは何となく判ってきていた。『喜び』を軽蔑し、『感触』を軽蔑し、『悲劇』を軽蔑し、『自由』を軽蔑し、『貞節』を軽蔑し、『希望』を軽蔑し、『休息』を軽蔑し、『優しさ』を軽蔑し、『光』を軽蔑し、『幸福』を軽蔑し、『夢』を軽蔑し、『愛情』を軽蔑し、『恋慕』を軽蔑し、『憧れ』を軽蔑している、大人を。
「エレン。剥がすぞ」
「……な、にを」
「解ってやがるくせに訊くんじゃあねえよ」
優しい優しいリヴァイの声。ほぼ同時にエレンは哭声をあげる。
「ゔっあぁっ! あ、ぁあ゙あ゙あ゙あ゙あ゙あ゙あ゙────…ッ!!」
小振りのペンチで剥がれた爪が落ちる。桜貝のようなエレンの爪が。残る白い半月は抉り取る。真っ赤な肉がめくれあがったそこから見える、脈打つエレンの血液は沸騰したかのようだった。それを1本1本と、計10本。爪を剥がれる。その度にあがるエレンの悲鳴で、地下室が満たされていく。
「あぎ、くっぐううぅ…!」
「こんなただの拷問、それでちんぽ勃たせて変態以外の何だってんだよ」
「ゔあ、んっん゙ん、…っぅ゙ああああっ!」
剥がし終えた10枚の爪を、リヴァイは大切そうに拭って小瓶に保管する。小瓶には既に、10や20では無い数の、エレンの爪が詰められていた。相変わらず綺麗な欠片だ、リヴァイは少々満足げに、コレクションを自慢するようにエレンの目の前でちらつかせ、ポケットに仕舞った。変なの。エレンは泣きながら思う。そんなものを集めてどうするのだ。貴方には何も譲渡したくないと言った筈が、リヴァイは勝手に奪い据ぎ取ってゆく。エレンには理解が出来ないのでリヴァイの単なるフェチズムの1つかも知れぬと自由解釈で納得をする。
「ゔぐ、…ふ、っぅ゙ああ゙っう、ぅ」
「ほら、腹に力入れろ」
「はっ…は、はあ、はあ……──うぐッ!!」
鳩尾に落とされた踵。げほげほと咳込んで、引きちぎらんばかりに乳首を引っ張られ、つい先刻ディルドを挿入していたこともあり、慣らしてはいてもまだ充分では無い尻穴に無理矢理リヴァイのペニスを捩込まれても出血はしなかった。こぶしを突っ込まれなかった分、リヴァイももしかしたらただ愉しんでいるだけなのかも知れない。アルミンとミカサとじゃれあっているところを──リヴァイに見られた。否、エレンは態と見せ付けた。久しぶりだと駆け寄って、飛び込むようなハグをして、頬にキスをし合って笑い合った。幼い子供の頃のように。リヴァイには決して見せぬ、気安い無邪気な笑顔で。リヴァイは少しだけ驚いたように瞠目し、直ぐに顔を歪めた。面白い筈が無い。
「おい、エレンよ。どうして欲しい? 首を絞めてやろうか」
「んっ…んぐ、ぅぐ……」
己の呼吸さえ制御出来ず、それでも必死にエレンはこくこく頷く。優しく触れられるくらいならば、もっともっと酷薄で、刹那的に、支配的に冒涜されたい。リヴァイの手のひらがエレンの首に絡み付いてゆく。初めはゆるりと、たいした力を込めるわけでも無い、お遊び程度で絞められる、白く頼りない首筋。いつかリヴァイが殺してくれるだろう日を夢見て、自慰行為に耽るのは背徳感が背をぞくぞくと駆け巡る──それが具現化されていく、と謂う快感に。日を置かずにリヴァイと体を繋げ合わせている上に首輪を用いた自慰も欠かさぬからか、薄い色をした精液が少量噴く程度だが、幾度めか判らぬ空イキをしていると、頸動脈と椎骨動脈を同時に抑えられれば、脳が溶けいくような、甘やかな低酸素症でぼんやりとしてくる。
「あっ、ッ、……はぁ…、」
「っ…すげえ締まりだな。そんなに悦いかよ」
「ゔぐ、…ふ、っぅ゙ああ゙っう、ぅ」
呼吸がつっかえ、競り上がる悦楽にエレンは身震いした。徐々にリヴァイの抽挿はスピードをあげて、それに相俟って喉に食い込む指に力が入ってゆく。エレンは夢中で擦りあげて、先走りで滑りのいい自らのペニスを、根本から扱く。
「ゔむぐッん゙ん゙ん゙ん゙ん゙ん゙…!」
じわりと額に汗をかきながら、エレンは、リヴァイがエレンの首を刎ねる姿を頭のなかいっぱいに夢想する。この、無駄に治癒力の高いエレンの躰は、ふつうの遣り方では簡単に死ねないだろう。それでも、リヴァイがいつかうなじを削ぎ、殺してくれるところを思い描く。例えばこめかみなんかを銃で撃ったところで、おそらく脳みそが僅かに飛び出る程度で傷は塞がってしまうであろう忌ま忌ましい躰だ。そんなふうにエレンが潸潸しているうちに、近かった射精が1歩遠退いて、リヴァイはチ、と小さく舌打ちをし、自分の下で鳴くエレンに思いを巡らせる。リヴァイは、この部屋には存在しない昼間の太陽の匂いを思い出すかのように鼻をひくつかせた。脳裏に浮かぶ、咲うだけで向日葵を思い起こす整った顔立ちの子供が掠れた声で、へいちょう、と明るい声で呼ぶところを思い出し、その官能に火を灯す。リヴァイは込み上げて来る嗤いを堪え、淡々とエレンに告げた。
「ガキが1丁前に男を誘って…いったい今までに、誰に抱かれてきたんだ? 穢えな」
もう届いている、エレンが言う。
「あっ…ふぁ……、かはっ……そんな、の、もう、」
覚えていない。数なんて。
どうでも良いことだ。今この手はもう届かせられる。もし届かないのなら、それはリヴァイが拒んでいるだけだ。ほんとうは途中が気持ち悦いだけ。エレンは解らない。いつまでも解らない。解らないでいたい。痛みを消す理由を、知りたくないのだ。また交わるように信じてもいる。
「ひっ、…く、はぁ…、もっと、もっ…と、締めて……あふっ、首…ッ」
「息継ぎも出来なくなるくらいにか」
「そ、う、息継ぎ…なんて……したくない……」
「変態」
「ああっ……、ん、んんぅっふ、あっ」
「……随分お幸せそうだな? おまえだけ」
「んんんッ」
頸動脈と椎骨動脈を最早殆ど機能しない程のつよい力で抑えれば、エレンは心底恍惚とした表情を浮かべた。エレンの首が締まる度、アナルの入口もきつく締まっていくものだからリヴァイはハメた穴のなかでペニスが痛い程だった。女の締まりより余程締まる。子供の爛れたアナルはリヴァイのペニスを奥深くまで飲み込み、決して離すまいと躍起になる。
「ァア、は、はっんんっ…うぅうん、ふ、ふあ」
「ずっとイキっ放しで苦しくねえのか。すげえな」
「んむんん…んぁ、んっんっんんん…っ」
もうエレンは透明な汁を零すだけで射精をしなくなっていた。迸る悦楽は、生死の境目。空イキばかりを間断なく繰り返し、その寸隙に生きているのか死んでいるのか判別し難い蜂蜜色が蕩けてリヴァイの後ろあたりを見詰める。堕ちる。茜さす空に見付からぬよう。堕ちて、堕ちて、堕ちて、堕ちるところまで──落ち続けて、ゆく。痛えな。リヴァイは締め付け過ぎだと謂う意を込め、エレンの臀をまた平手で打った。途端エレンの喉が、ひゅ、と鳴る。反射的に吸い込んだ息を吐けずにいるのだ。じんと熱を持つ臀がひりつく。エレンがリヴァイの与えるものすべてに呼応し、何れ程交わっていても関係無く、それらは、ただの平行線となって温度差を顕著なものにした。だが平行線は少し歪んでいて、子供の言い訳を通用させる。子供の孤独を飽和させる。だからいつまでも現実を見ない、エレンは、赦されないことを赦していた。光と影が輪舞する空間。併存、不覚にも、深く、愛されない今を、とても愛している。