<概略>
エイプリルフールは疾っくに過ぎました。久々の殺伐。あと、どうとでも取れる話にしたくて。地雷がある方はご注意を。
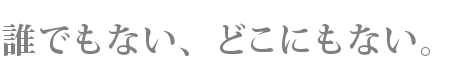
ねえ、兵長。聞いてください。などと如何にも真面目な様子でエレンが言うので、リヴァイは態々ペンを止めてまで書類から顔を上げてやったと謂うに、その直後、続けられた台詞は──ほんとうは『俺』がここに存在しているなんて嘘なんです、と云う、わけの理解らぬものだった。ゆえに、らしくも無くリヴァイはぽかんと口を開けた。上官にそんな表情をさせている当のエレンは、少しだけ、困ったような笑顔を浮かべ、リヴァイの顔を見ている。どうやらリヴァイのネイビーブルーを見詰めているらしい。言っていることそのものは馬鹿馬鹿しいのに、エレンの視線があまりにも真っ直ぐで真摯なものであるせいで、リヴァイはエレンの滑らかな肌の、顎の真ん中辺りにぽつん、と小さく出来ている、ニキビ痕へと目を逸らした。いったい今日と云う日に何か意味があるのかをリヴァイは識らないが、ふつうに考えて、部下が上官に嘘や冗談を言っても良い日などこの世界には絶無である。だがリヴァイは、エレンが言った言葉について、さて俺を騙そうと思って口にした言葉か、揶揄おうと口にした言葉か、何も考えず口にした言葉か、と考えてみて、しかしてそのどれに当たるものであったのかがまるで理解らなかったため、続くだろうエレンの言葉を待つことにした。エレン・イェーガーと謂う、リヴァイ・アッカーマンにとって不可解な生き物は、時折、子供らしく『炎の水』や、『氷の大地』、『砂の雪原』等々という夢のなかの産物のような、そういう聞いたことも無い単語をこの上無く嬉しそうに、おおきな蜂蜜色を煌めかせ口走るが、基本的に嘘は吐かない。否、嘘を吐くことも見抜くことも不得手な、実直に過ぎる程思考や感情が隠せぬ子供なのだけれども──もしかするとその無邪気ささえ上手く、嘘で塗り固めているのかも知れない。万が一そうであるならば、リヴァイはますますエレンを理解出来ぬであろうし、エレンがリヴァイに言う言葉の1から100までが全部、嘘であったのだとすればリヴァイは嘘発見機では無いので、そんな姑息且つ聡明で陰険な、子供の言葉の真偽を理解することは、絶対に不可能だ。だからこそリヴァイには、確実にこいつは嘘を言うことはないだろうと、そう信じてやる外に術は無いのだ。
「俺は、実は既に死んでいるんです。兵長。だから、今、ここにいるのも嘘なんです。ほんとうは」
冗談にしては笑えない内容だった。そしてやはり、リヴァイには意味が理解らない。エレンが何を意図し、こんなくだらない嘘を吐く必要があるのか、理由どころか、雰囲気すら伝わらない。ただひとつだけ、理解ったことは、馬鹿馬鹿しい程エレンはリヴァイを笑わせたいわけでも、驚かせたいわけでも、騙したいわけでも無いらしい、と謂うことだった。ただ言いたいから言う、そんな身勝手さだけが、犇々と伝わりリヴァイはひどく不愉快だった。当然ながら、エレンが似合いもせぬ嘘を吐いていることは、敢えて確認する必要性なぞ無いことだ。なぜならエレン・イェーガーは生きている。生きて、馬鹿馬鹿しい嘘をなぜだかリヴァイへと吐いている。それでも或いはエレンが死んでいると云うなら、リヴァイは今、エレンの幽霊と話していることになってしまう。リヴァイには霊感は無い、と云うかそもそも信じたことが無かった。例えばそのようなスキルをリヴァイが持ち合わせているとしたら、今までに喪い続けてきた夥しい程の人数分、仲間や部下たちとのこういった場面が、1度も無かったのはおかしいし、まず、それ以前にエレンには影が有り脚も有った。話しながらその薄っぺらな胸筋が上下しているのも、呼吸を挟んでいるのも、瞳の表面が乾かぬよう自然と何度も瞬きしているのも、確りと目視出来ている。それらは死んだ人間には不必要な動作だ。
くだらねえことで仕事の邪魔しやがってクソガキ。
段々腹立たしくなり、眉を寄せて不快げにしているリヴァイに漸く気付いたエレンは、今度はどこか嬉しそうに頬を緩ませ微笑んだ。わりに、楽しくて笑っているようでは無かった。ずっと、もっと、泣いてしまいそうだった。
「あァもう、信じていないでしょう。兵長」
「馬鹿には付き合ってられねえだけだ」
「酷いなあ」
「酷えのはてめえだろ、この愚図。とっとと仕事に戻れ」
「ええー…俺死んでいるので戻れませんよ」
「こんなクソな嘘を信じる無駄な時間があると思ってんのか、クソが」
もうこれ以上付き合っていられない。リヴァイは嘆息した。こんなにも馬鹿馬鹿しい会話を信じて無益さに辟易しつつ尚、続ける暇は自分たちには無いのだ。それでもまだエレンを信じるならばそれは本物の馬鹿か、病的なお人好しであるので、病院に罹ったほうが良いだろう。けれどリヴァイは真っ当な教育を受け育っていないだけで馬鹿でもクソでも無く、お人好しでなどもっと無く──仮にだ、お人好しだったとしてエレンのこんな毒にも薬にもならぬ馬鹿馬鹿しい話にとことん付き合ってやろうと考える気持ちに──微塵もならなかった。ついぞ観念し、おまえが理解らん、と、溜息混じり、リヴァイが困り果てると、エレンはどこか、嬉しいが素直に喜べない、と云わんばかりの、そんな顔をして、唇の端を持ち上げ子供には似合わぬ苦笑を見せた。その笑い方はリヴァイからすると不愉快に過ぎて、面白くない、を通り越し最早何も言わずに横っ面へとハイキックを繰り出してやりたくさえ成るものであった。おい、エレンよ。呼びながら椅子を立とうとしたリヴァイを遮って、
「兵長が信じてくれなければ、成立しないじゃあ無いですか」
「…何がだ」
「先程の、話がですよ」
成立させようとしたのか、成立させたかったのか。
何れにせよおまえは馬鹿か、そうだった馬鹿だったな、ついでにどうしようも無くクソガキだった、とリヴァイは小さく呟き、椅子に座り直すと再度ペンを取った。懲りずに話し掛けてくる部下がエレンで無ければ無碍にするにも胸が傷んだかも知れないが、リヴァイは現在のエレンに対し真面目に対応しないと決めた。リヴァイにとって興味の無い──寧ろ有害にも値する──無意味な時間は、リヴァイにとって対応する価値も無いので、つまりはリヴァイは無反応を決め込むことにしたのだ。要するに無視だ。
「兵長が俺の話を信じてくれなかったら、誰が信じてくれるんですか」
一瞬のみ書類に目を落としたは良いが、結局話し掛けられているのは己であるのだ。リヴァイの手は動かなかった。代わり、意味も無く、淡つかに、母親似だと云う見目の良い子供の横顔を見詰めているリヴァイに遠くを見るエレンはそう言って、自身の輪郭を、確かめるかの如く指先でなぞった。ほんとうに、黙ってさえいるのなら、つくりもののようにきれいな横顔をして、浮かべている笑顔は道端に転がる犬のクソよりも穢い。吐き出す声は水のように澄んで、吐いている言葉はどろどろに濁り切っているような。今日のエレンは殆、気持ちが悪いものだった。
「ねえ、兵長。貴方が信じてくれたなら、俺の言葉はほんとうになって──」
『炎の水』や、『氷の大地』、『砂の雪原』等々という夢のなかの産物のような、そういう聞いたことも無い単語をこの上無く嬉しそうに、おおきな蜂蜜色を煌めかせ口走るときの夢を語る無邪気な子供の顔で、今日は頭の螺子が飛んでしまったかのような戯言を口にする。
「俺、は、死んだ、ことに、なって、」
ところどころに挟まれる喜びにすら似た呼気が、やはり気持ち悪い。
「貴方に存在を否定されたら、きっともう俺はここに立つことすら出来ない」
そうしてリヴァイに否定されたいような口振りで、リヴァイに縋り付くような瞳で、けれどもエレンは疾うにリヴァイを見ていない。
「そういうのって何だかとても、素敵なことだと思いませんか?」
不意に、もう1度交差した、その視線の先には、何も無かった。俺に存在を否定されてえのか、とリヴァイが問いかけると、エレンは数秒間だけ考えるような素振りを見せ、て、遅れて首を曖昧に傾けた。角度によっては否定とも肯定ともとれる。が、浮かべている表情は複雑で、リヴァイはその傾きが何を示すのかまったく理解出来なかった。
兵長は知らないことかも知れませんが──俺だって結構、嘘吐きなので。エレンはそう付け足して、まるで何も無かったかのようにニコリと大人びた笑みをも浮かべる。
「実は死にたかったのか」
「……ええと、」
「戦うことに疲れていたりするのか」
「それはどうでしょう」
「なら、炎の水やら云々の夢はもう良いのか」
「さァ」
「繰り返すが、今のおまえはまるきりわけが理解らん」
「そうですね。俺も」
「エレン、おまえは」
ほんとうに、リヴァイは心底、面倒臭かった。今ここに存在しているエレンと話すことが面倒臭い。だからもう何でも良かった。対応するだけで疲弊し失望するのならば、もう話さなければいいと敗北感は癪だが、疾疾リヴァイはそれきり口を閉ざす。エレンの手が許可も無くリヴァイの手首にふれる。そんなふうに、まるで縋るようにしてまでリヴァイの手首にふれたくせに、エレンのその指先は、あたかもほんの1秒でもはやくリヴァイから離れたいとでも云うかの如く、ただただ、小刻みに──震えていた。エレンはほんとうのことばかりを話す嘘吐きだった。かわいそうな奴め、とリヴァイは内心呆れ返りながら、馬鹿じゃねえのか、と独りごちた。何という無駄だ。そうだった馬鹿だったな、ついでにどうしようも無くエレンはクソガキだった。なのでリヴァイは労力を要してまで、エレンを慰めたりする気にはならなかった。誰かに慰められたいのであれば、人選を誤らぬことだ。ほんとうの嘘などまったく録なものでは無い。リヴァイは靜か、仕事を再開する。そして思う──おまえみてえなガキが、おまえみてえなガキの言葉が、やたらとあれこれ、重かったり軽かったり、面倒臭かったり、そのわりに突き放せない言葉で、あァほら、だから面倒なのだと。けれど感じることがある。笑われてもほんとうはこれより先があって、無いものも有るものも言葉の欠片は欠片のまま、この世界よりもっと残酷であるのだと云うことを、子供の指がリヴァイのこころの輪郭を辿り不躾にふれるとき、或いはいつか胸の傷をそうっとやさしくなぞるとき。
(おまえは指の1本だけでも簡単に、俺の全体にふれることが出来るじゃねえか)
頼んでも、いない、のに。
エイプリルフールは疾っくに過ぎました。久々の殺伐。あと、どうとでも取れる話にしたくて。地雷がある方はご注意を。
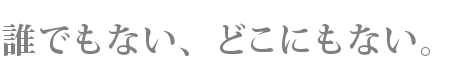
ねえ、兵長。聞いてください。などと如何にも真面目な様子でエレンが言うので、リヴァイは態々ペンを止めてまで書類から顔を上げてやったと謂うに、その直後、続けられた台詞は──ほんとうは『俺』がここに存在しているなんて嘘なんです、と云う、わけの理解らぬものだった。ゆえに、らしくも無くリヴァイはぽかんと口を開けた。上官にそんな表情をさせている当のエレンは、少しだけ、困ったような笑顔を浮かべ、リヴァイの顔を見ている。どうやらリヴァイのネイビーブルーを見詰めているらしい。言っていることそのものは馬鹿馬鹿しいのに、エレンの視線があまりにも真っ直ぐで真摯なものであるせいで、リヴァイはエレンの滑らかな肌の、顎の真ん中辺りにぽつん、と小さく出来ている、ニキビ痕へと目を逸らした。いったい今日と云う日に何か意味があるのかをリヴァイは識らないが、ふつうに考えて、部下が上官に嘘や冗談を言っても良い日などこの世界には絶無である。だがリヴァイは、エレンが言った言葉について、さて俺を騙そうと思って口にした言葉か、揶揄おうと口にした言葉か、何も考えず口にした言葉か、と考えてみて、しかしてそのどれに当たるものであったのかがまるで理解らなかったため、続くだろうエレンの言葉を待つことにした。エレン・イェーガーと謂う、リヴァイ・アッカーマンにとって不可解な生き物は、時折、子供らしく『炎の水』や、『氷の大地』、『砂の雪原』等々という夢のなかの産物のような、そういう聞いたことも無い単語をこの上無く嬉しそうに、おおきな蜂蜜色を煌めかせ口走るが、基本的に嘘は吐かない。否、嘘を吐くことも見抜くことも不得手な、実直に過ぎる程思考や感情が隠せぬ子供なのだけれども──もしかするとその無邪気ささえ上手く、嘘で塗り固めているのかも知れない。万が一そうであるならば、リヴァイはますますエレンを理解出来ぬであろうし、エレンがリヴァイに言う言葉の1から100までが全部、嘘であったのだとすればリヴァイは嘘発見機では無いので、そんな姑息且つ聡明で陰険な、子供の言葉の真偽を理解することは、絶対に不可能だ。だからこそリヴァイには、確実にこいつは嘘を言うことはないだろうと、そう信じてやる外に術は無いのだ。
「俺は、実は既に死んでいるんです。兵長。だから、今、ここにいるのも嘘なんです。ほんとうは」
冗談にしては笑えない内容だった。そしてやはり、リヴァイには意味が理解らない。エレンが何を意図し、こんなくだらない嘘を吐く必要があるのか、理由どころか、雰囲気すら伝わらない。ただひとつだけ、理解ったことは、馬鹿馬鹿しい程エレンはリヴァイを笑わせたいわけでも、驚かせたいわけでも、騙したいわけでも無いらしい、と謂うことだった。ただ言いたいから言う、そんな身勝手さだけが、犇々と伝わりリヴァイはひどく不愉快だった。当然ながら、エレンが似合いもせぬ嘘を吐いていることは、敢えて確認する必要性なぞ無いことだ。なぜならエレン・イェーガーは生きている。生きて、馬鹿馬鹿しい嘘をなぜだかリヴァイへと吐いている。それでも或いはエレンが死んでいると云うなら、リヴァイは今、エレンの幽霊と話していることになってしまう。リヴァイには霊感は無い、と云うかそもそも信じたことが無かった。例えばそのようなスキルをリヴァイが持ち合わせているとしたら、今までに喪い続けてきた夥しい程の人数分、仲間や部下たちとのこういった場面が、1度も無かったのはおかしいし、まず、それ以前にエレンには影が有り脚も有った。話しながらその薄っぺらな胸筋が上下しているのも、呼吸を挟んでいるのも、瞳の表面が乾かぬよう自然と何度も瞬きしているのも、確りと目視出来ている。それらは死んだ人間には不必要な動作だ。
くだらねえことで仕事の邪魔しやがってクソガキ。
段々腹立たしくなり、眉を寄せて不快げにしているリヴァイに漸く気付いたエレンは、今度はどこか嬉しそうに頬を緩ませ微笑んだ。わりに、楽しくて笑っているようでは無かった。ずっと、もっと、泣いてしまいそうだった。
「あァもう、信じていないでしょう。兵長」
「馬鹿には付き合ってられねえだけだ」
「酷いなあ」
「酷えのはてめえだろ、この愚図。とっとと仕事に戻れ」
「ええー…俺死んでいるので戻れませんよ」
「こんなクソな嘘を信じる無駄な時間があると思ってんのか、クソが」
もうこれ以上付き合っていられない。リヴァイは嘆息した。こんなにも馬鹿馬鹿しい会話を信じて無益さに辟易しつつ尚、続ける暇は自分たちには無いのだ。それでもまだエレンを信じるならばそれは本物の馬鹿か、病的なお人好しであるので、病院に罹ったほうが良いだろう。けれどリヴァイは真っ当な教育を受け育っていないだけで馬鹿でもクソでも無く、お人好しでなどもっと無く──仮にだ、お人好しだったとしてエレンのこんな毒にも薬にもならぬ馬鹿馬鹿しい話にとことん付き合ってやろうと考える気持ちに──微塵もならなかった。ついぞ観念し、おまえが理解らん、と、溜息混じり、リヴァイが困り果てると、エレンはどこか、嬉しいが素直に喜べない、と云わんばかりの、そんな顔をして、唇の端を持ち上げ子供には似合わぬ苦笑を見せた。その笑い方はリヴァイからすると不愉快に過ぎて、面白くない、を通り越し最早何も言わずに横っ面へとハイキックを繰り出してやりたくさえ成るものであった。おい、エレンよ。呼びながら椅子を立とうとしたリヴァイを遮って、
「兵長が信じてくれなければ、成立しないじゃあ無いですか」
「…何がだ」
「先程の、話がですよ」
成立させようとしたのか、成立させたかったのか。
何れにせよおまえは馬鹿か、そうだった馬鹿だったな、ついでにどうしようも無くクソガキだった、とリヴァイは小さく呟き、椅子に座り直すと再度ペンを取った。懲りずに話し掛けてくる部下がエレンで無ければ無碍にするにも胸が傷んだかも知れないが、リヴァイは現在のエレンに対し真面目に対応しないと決めた。リヴァイにとって興味の無い──寧ろ有害にも値する──無意味な時間は、リヴァイにとって対応する価値も無いので、つまりはリヴァイは無反応を決め込むことにしたのだ。要するに無視だ。
「兵長が俺の話を信じてくれなかったら、誰が信じてくれるんですか」
一瞬のみ書類に目を落としたは良いが、結局話し掛けられているのは己であるのだ。リヴァイの手は動かなかった。代わり、意味も無く、淡つかに、母親似だと云う見目の良い子供の横顔を見詰めているリヴァイに遠くを見るエレンはそう言って、自身の輪郭を、確かめるかの如く指先でなぞった。ほんとうに、黙ってさえいるのなら、つくりもののようにきれいな横顔をして、浮かべている笑顔は道端に転がる犬のクソよりも穢い。吐き出す声は水のように澄んで、吐いている言葉はどろどろに濁り切っているような。今日のエレンは殆、気持ちが悪いものだった。
「ねえ、兵長。貴方が信じてくれたなら、俺の言葉はほんとうになって──」
『炎の水』や、『氷の大地』、『砂の雪原』等々という夢のなかの産物のような、そういう聞いたことも無い単語をこの上無く嬉しそうに、おおきな蜂蜜色を煌めかせ口走るときの夢を語る無邪気な子供の顔で、今日は頭の螺子が飛んでしまったかのような戯言を口にする。
「俺、は、死んだ、ことに、なって、」
ところどころに挟まれる喜びにすら似た呼気が、やはり気持ち悪い。
「貴方に存在を否定されたら、きっともう俺はここに立つことすら出来ない」
そうしてリヴァイに否定されたいような口振りで、リヴァイに縋り付くような瞳で、けれどもエレンは疾うにリヴァイを見ていない。
「そういうのって何だかとても、素敵なことだと思いませんか?」
不意に、もう1度交差した、その視線の先には、何も無かった。俺に存在を否定されてえのか、とリヴァイが問いかけると、エレンは数秒間だけ考えるような素振りを見せ、て、遅れて首を曖昧に傾けた。角度によっては否定とも肯定ともとれる。が、浮かべている表情は複雑で、リヴァイはその傾きが何を示すのかまったく理解出来なかった。
兵長は知らないことかも知れませんが──俺だって結構、嘘吐きなので。エレンはそう付け足して、まるで何も無かったかのようにニコリと大人びた笑みをも浮かべる。
「実は死にたかったのか」
「……ええと、」
「戦うことに疲れていたりするのか」
「それはどうでしょう」
「なら、炎の水やら云々の夢はもう良いのか」
「さァ」
「繰り返すが、今のおまえはまるきりわけが理解らん」
「そうですね。俺も」
「エレン、おまえは」
ほんとうに、リヴァイは心底、面倒臭かった。今ここに存在しているエレンと話すことが面倒臭い。だからもう何でも良かった。対応するだけで疲弊し失望するのならば、もう話さなければいいと敗北感は癪だが、疾疾リヴァイはそれきり口を閉ざす。エレンの手が許可も無くリヴァイの手首にふれる。そんなふうに、まるで縋るようにしてまでリヴァイの手首にふれたくせに、エレンのその指先は、あたかもほんの1秒でもはやくリヴァイから離れたいとでも云うかの如く、ただただ、小刻みに──震えていた。エレンはほんとうのことばかりを話す嘘吐きだった。かわいそうな奴め、とリヴァイは内心呆れ返りながら、馬鹿じゃねえのか、と独りごちた。何という無駄だ。そうだった馬鹿だったな、ついでにどうしようも無くエレンはクソガキだった。なのでリヴァイは労力を要してまで、エレンを慰めたりする気にはならなかった。誰かに慰められたいのであれば、人選を誤らぬことだ。ほんとうの嘘などまったく録なものでは無い。リヴァイは靜か、仕事を再開する。そして思う──おまえみてえなガキが、おまえみてえなガキの言葉が、やたらとあれこれ、重かったり軽かったり、面倒臭かったり、そのわりに突き放せない言葉で、あァほら、だから面倒なのだと。けれど感じることがある。笑われてもほんとうはこれより先があって、無いものも有るものも言葉の欠片は欠片のまま、この世界よりもっと残酷であるのだと云うことを、子供の指がリヴァイのこころの輪郭を辿り不躾にふれるとき、或いはいつか胸の傷をそうっとやさしくなぞるとき。
(おまえは指の1本だけでも簡単に、俺の全体にふれることが出来るじゃねえか)
頼んでも、いない、のに。