<概略>
エレンをそう好きでは無い兵長/兵長をそう好きでは無いエレン/それでもお互いが生きるにはお互いが必要なふたり/
バレンタイン用に書いた筈がバレンタインあんまり関係無かった…。
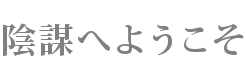
「おまえはずっと、俺の傍にいるだろ」
問い掛けでは無い。懇願でも無い。当然のように断定されたその言葉を、エレンは唖然としてただ聞くしかなかった。規則正しい不規則の規則は正しい。どこにも隙間が見当たらない。満たされたことなぞ1度も無いのに、どこにも余白が見い出せないのだ。優しげな母子の姿──そのかげろうにエレンはむやみに贖罪の意識を覚える。淡い魂を喰らい容赦なく輝ける夕陽さえ1日の終わりには霞むだろう。遠く船の汽笛がする。ざらざらとした耳障りなノイズ。完璧な室温。深い襟首のシャツでは口許を覆わせられない。リヴァイは、椅子に座った前屈みの姿勢で、眠そうな目を擦っている。エレンよりおおきなその手を取って、何か言葉を掛けるべきかとは思う、のにリヴァイの手はエレンの気持ちには気付かず点滴の位置だけ確かめる。今日もこの肺は呼吸している。心臓は脈打っている。時間は消えた。あの日リヴァイがどこかへ隠してしまった。この薄暗い部屋と空とを繋ぐ唯一の窓は、厚いカーテンに閉ざされたままだ。何日も──そう、もう何日も。
「今日は、何日ですか?」
その問いにリヴァイは、2月14日だ、と答えた。
「愛を伝える日ですね」
「違う。どこぞの誰かの死んだ日だ」
「そんなこと言っていたら、365日毎日、どなたかの命日になるじゃないですか」
「そうだ。だから何も特別じゃあねえ」
ブルネットより深い黒檀の、さらさらと流れるようなその髪に触れたい。
「兵長の髪にさわりたいです」
「気色の悪いことを言うな、ガキが」
リヴァイは思い切り眉を顰めながらも、エレンに顔を近付けてくれた。エレンは思い通りにならない指で、瞼や唇や、リヴァイのそんなところにばかり触れた。
「翡翠は、元気ですか? 兵長、ちゃんと、餌とか水とか、世話してくれてます?」
「訊かずとも、翡翠はおまえより元気だ」
それはエレンの小鳥の名前だった。碧い羽を持っていたから翡翠。幸せの碧い鳥だ。だがエレンはもう何日もその姿を見ていないし、声も聴いていない。その小鳥のことを、エレンはもうじき忘れてしまうかも知れないのに。既に思い出せないことはたくさんある。自分の名前。ついさっき交わした話の内容。笑顔の切っ掛け。なぜこんなにも物を忘れてしまうのか、それすら判らぬ。或いは、覚えていない。記憶が乾いた砂のように指の隙間からさらさら零れる。そして2度と元の場所に戻らない。しかし、いつかほんとうにすべてを忘れてしまうときがくるとしても、最後まで残っているものがリヴァイの姿ならば良い。リヴァイの名前ならば良い。そう願うので、何度でも呼びかけるのだ──リヴァイ兵長、と。
「さっきから何してるんですか、兵長」
流しに立ったリヴァイの手は、何かを迷い無く切っている。真新しい銀の鋏が切り落とすものは、何だろう? 瑞々しい、しなやかな、誰かの細い──指先のような。エレンは近頃眼球がうまく動かせない。限られた視界のその隅で、エレンはリヴァイの姿を常々探す。それが今日はなぜかいつもより寂しくて堪らない。リヴァイが近くにいないと、怖くて怖くて堪らないのだ。いつからエレンはこんなにも、臆病になってしまったのだろう。自身でも判らない。
「ほらエレン。おまえの好きな花だ」
振り返ったリヴァイは、花を挿した瓶をエレンに差し出す。
「『エレン』? 誰ですか、それ」
態とそんなことを言い、エレンはリヴァイを哀しませようとする。寝台脇の棚に瓶を置き、努めてリヴァイは何事も無かったかのようにエレンの点滴の位置を確かめる。その瞬間の世界が嫌いだ。すべてがエレンを拒んでいるような気がする。ならば忘れたふりなどしなければ良いのに──やめられない。悪い癖だ。リヴァイの眸は時々、魚の鱗のように美しく光る。その眼の下には隈が出来ている。ろくに寝ていない。あの夜から、1度も熟睡していないのだ。それを思うとエレンは、自分が早く消えてしまえば良いのにと願わずにいられない。
「……ねえ、兵長?」
「何だ」
「もしも。もしも、の話ですよ? もしも俺が貴方を遺して死んだら、棺なんかには入れずに、裸にして、手向けの花も握らせないで、巨大樹の森の、奥の、冷たい土のなかに埋めて、そこには墓標も立てないで、兵長は泣いたりなんかしないで、何事も無かったみたいに去ってください。俺は穢く腐りたい。動物の死骸みたいに、枝を離れた枯れ葉みたいに。雨に打たれながら、虫に喰われながら、なるべく時間をかけて、土に戻りたいんです」
狡い言葉だ。リヴァイが相槌なぞ打てないと重々既知している上で、何かから解き放たれたような面持ちで、自分ばかりが美しいふりをする。それなのにリヴァイの指は、黙ってエレンの眦をなぞってくれる。あァ、この優しい微熱、ほんとうは誰にも渡したく無い。誰にも渡したくは無いのに。いま、エレンの枕の下には、回転式の小銃がある。
「……もしも、の話です」
エレンは、自覚している以上に、狡い。暗い天井ばかり眺めているものだから、目は段々と光を忘れていく。そんなときでもリヴァイの姿だけは紛れもなく鮮やかで、他はみな、死んでしまった。遠く船の汽笛が聞こえる。ざらざらした雑音。心地好く、完璧と呼んで差し支え無い室温。迫り上がる悲愴に身じろぎしながら眠ることも出来ず、に、寝返りを打ちつつエレンは何度も、リヴァイの名前ばかり呟いている。カーテンの僅かな隙間を掠めてこの部屋に刺す光は、あれはそう、灯台か。ここから海はそれ程遠くないのかも知れない。耳障りな雑音だとばかり思っていた音も、実は優しい波の音だったのかも知れない。エレンはかなりの時間をかけ寝台の上で躰を起こし、繋がる点滴の針を、また、かなりの時間をかけて引き抜いた。寝てばかりいたので足に全然ちからが入らない。蹌踉めく躰を結局寝台に横たわらせる。今度は、エレンのベッドに突っ伏しているリヴァイを、暫く見詰めた。瞼を閉じた青い頬を、誤ってこの部屋に迷い込んだ光がずっと撫でている。生きていないような肌だ。初めて逢った頃からリヴァイはずっと、そんな肌をしていた。エレンのような派手さは無いが、幸せになるべくして産まれた、そう形容したくなるような美しく整った顔。眸は濃い茶に一筋だけ深いネイビーブルーをぽとりと落として混ぜたような、珍しい色をしていた。黒い髪と同色の睫毛は長くは無いが密で、触れると存外やわらかだった。小造りな人形のようなリヴァイがエレンを調査兵団に入れてくれて、ひとつずつ些細な何かを知る度に警戒心を削いでいった経緯も、もう思い出せぬ。もっと光が欲しい。と──エレンはカーテンを開けようとし、やめた。
「外が見たいです」
いつかそう告げたことがある。難題を言ったつもりは無かった。けれどリヴァイはエレンのその欲求に、ひどく困った顔をした。
「兵長。空が見えなくて、怖い」
続きリヴァイはますます哀しい顔をして、それでも何とか表情筋を動かし、今日は曇っている、と言った。エレンは曇りでも良い、雨でも良い、いつかいっしょに見上げた空が、今もちゃんとそこに有るのかどうか、それさえ確かめられれば良かったのだ。それでもその望みは、あのときのリヴァイの絶望程は強く無かった。きっと。だからもう望むことをやめたのだった。
思い出せない何かを思い出そうとしながら、リヴァイの頬に手をあてていると、リヴァイがいつか綺麗だと褒めてくれた蜂蜜色の双眸から、涙が出てきた。でもそこから溢れる涙はただの透明な水であったし、エレン自身どうして自分が泣いているのか理由が解らない。あたたかかったから、というのが最も適切で正しい気がする。頬が、額が、あたたかい。リヴァイは、確かに生きている。これからも、このぬくもりを持ち生きていくのだ。それはエレンが傍に居ても居なくても 、変わらない。こればかりは誰にも奪えない。例えば──リヴァイが死なない限りは。エレンは己の下唇を切れるほど噛み、枕の下にそっと手を入れた。取り出した小銃はその手のなかで、黒光りしていた。前に持ったときよりも重さを増した気がする。エレンはゆっくりと、その銃口を己のこめかみの高さまでかかげていく。やがて静かに目を瞑り、安全装置を外そうとし、
「よせ」
外し損ねた。まさか気が付くなんて思っていなかった。目覚めたばかりでいつもよりきつい目が、不満げにエレンを見ていた。まだ虚ろな眼差しは焦点が定まっていないのかひどく頼りない。なのにエレンを引き止めるには充分だった。
「……どうして、兵長」
耳に届いた声がその声で無ければエレンは、彼をリヴァイだと判らなかっただろう。彼はもう殆ど別人のようだった。エレンは知らない、こんなに怒気を顕わにしたリヴァイを。汽笛が強く鳴ったせいかも知れない。ノイズが聞こえる夜だから。疲れた脳を掻き乱すように。その目は語っていた。知っていた、と。エレンの隠し持つ切り札の存在などずっと前から知っていた、と。
「……独りでそうしようとするくらいなら、なぜ俺に、いっしょに死んでくれと言わねえんだ。エレンよ」
リヴァイの顔を覆う手は痩せ、指の隙間から、エレンが初めて見るリヴァイの涙が零れ落ちた。呼吸が止まる、と思った。小銃は冷えた床に呆気なく落下し鈍い音を立てた。閉ざされたカーテンの向こうにあるのものは、もう碧い空なぞでは無い。耳障りなノイズの出所は銃声で、瞬く光は森を焼き払う閃光だ。遠く鳴る汽笛は、逃げる者たちだけを乗せたノアの方舟。廃墟と化したこの国にはもう、エレンを埋められる森など無い。
「世界は終焉する。愛を伝えながら、おそらくは」
2月の14日、寒い、それが何かを意味するところを知りたくなんか無い。リヴァイが嘲けっているのはエレンなのか彼自身なのか、それとももっと別の何かなのか、エレンは知る術を持たぬ。知りたいとも──思わない。何も考えたく無いのだ。もう、何も。
「翡翠は、逃がしてくれましたか? ちゃんと、逃がしてくれたんですか?」
エレンは震えの止まらない指を、真っ白いシーツの下に隠そうとした。だがリヴァイはそれを赦さず、痩せた手でもっと強く握り締めてきた。覗き込んでくる瞳の奥で輝いているリヴァイのネイビーブルー、エレンはもうすべて委ねてしまう。
「鍵は疾うに外してある。ほんとうに生きたいのなら、自力で飛んでいくだろう。翡翠なら。だから心配は要らねえ。……なァエレンよ、あのカーテンの向こうには何もねえんだ。毒と鉄骨、灰の闇だけがすべてだ。飢えた野良犬は逃げ遅れた病人を喰らっている、噛み千切られたその腹からは子供の指なんぞが出てくる。気を違えた母親が赤ん坊の頭皮を毟って。感覚の麻痺した他人同士が、互いの四肢を千切り合っている。すべては愚かな人類が引き起こした、悪夢みてえなもんだ。だからどうしようもねえ、ほんとうにもう、どうしようもねえんだ」
話しているリヴァイが顔を顰める。ならばすべてはほんとうのことなのだろう、とエレンは思う。それだって、真理のすべてでは無いだろうけれども。
「世界は、いつから変わってしまったんですか」
「たぶんずっと昔から、こうだったんだろうよ。もう誰も覚えちゃいねえくらい、昔から。金のある豚共は新天地へ逃げた。貧しい者につくらせた方舟で。実際の方舟づくりに関わった者で、その方舟に乗れた者なんざ唯の1人もいねえ筈だ。重量の限られた方舟に乗るには、生き残るに相応しいのだと認められなければならない。そしてその選出には、多額の金が必要だ。理由なんぞ何れを取っても醜いが、それが偶々、金だっただけだ。安心しろ、おまえの馴染みは全員無事だ。ミカサは最後までここに残ると駄々を捏ねたが、アッカーマンの血を絶やすわけにはいかねえと薬を盛られ寝ているところを無理矢理乗せられた。そしてアルミンも含め、兵団員はみな護衛として乗せられた。或いはあちらに裏切られた場合でも対処可能なように。保険というやつだな」
「……兵長、だったら貴方こそ新天地に必要だ。兵長はその方舟に、ほんとうは乗れたんでしょう? それなのにどうして貴方は、まだここに居ようとするんですか」
そうして矢張りエレンは、それをリヴァイに言わせるのだ。
「エレン。おまえがここを出られないからだ」
それは起こった。凄まじい震動に崩れ落ちていく。何もかも──何もかもが、轟音を立てて崩れ落ちていく。過去も未来も、今この瞬間ですら。最初の爆音にエレンの右耳の鼓膜は破れてしまっていた。リヴァイの胸に左の耳を当てたなら、まだ思い出せる。色と、熱と、日々。瓦礫の下のエレンはぼんやりと、遠い時間を巻き戻していた。小さな翡翠を拾った時の碧空。不吉な予感を微塵も感じさせない、陽だまり。ふたりを隔てるものなど何ひとつとして無かったのだ。階級も出身も関係無い。緑の風は髪を舞わせるだけ。時間は静かに過ぎてゆくだけ。何も否定せず、何も肯定せず。リヴァイの碧白い手を握るのが、ひどく汚れたエレンの手でも、すべては自然のなかで赦されていた。ずっと続くのだと疑いもしなかった。誰しもを取り巻く幸せな日々。何回も巻き戻しては、飽きもせず見続けた、硝子の眸でふたりはずっと。干乾びることが無いのなら、ここはもう水底かも知れないけれど。夜の海に浮かぶ。模したのは胎児か亡骸か。裏側から月に照らされた雲が金銀を散りばめた星雲のように発光している。エレンは浮遊している。無意識的に、どちらからそうしたのかも判らぬ口付けは、それだけでは吐き出してしまいそうな程とても苦く、そして砂糖菓子のように只管甘いだけだった。ただ、それだけだった。
「おまえはずっと、俺の傍にいるだろ」
苦虫を噛み潰しているかの如く苦笑を飲み込む、リヴァイの手は、エレンの知らぬ存ぜぬうちに、翡翠の風切り羽を容易く手折っていたのだった。だから未だ鳥籠のなか、鍵と扉を開けていようとも、翡翠は最早どこにも飛んでゆけない。伝える愛など何処を捜そうと微塵も無いのだ。何しろ互い、どちらが根負けし、て、泡沫と消えてゆけるのか、競い合っているかのようなものなのだから。胸焼けがする。飛び立つことも出来ずに。救えない。幸せの碧い鳥を探す旅に出る人間の幸せは、初めから傍に有った、と謂う落ちは在り来りな話だが、幸せの碧い鳥は、エレンの翡翠は、飛び立てずとも、まだ生きている。
エレンをそう好きでは無い兵長/兵長をそう好きでは無いエレン/それでもお互いが生きるにはお互いが必要なふたり/
バレンタイン用に書いた筈がバレンタインあんまり関係無かった…。
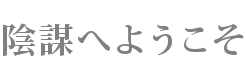
「おまえはずっと、俺の傍にいるだろ」
問い掛けでは無い。懇願でも無い。当然のように断定されたその言葉を、エレンは唖然としてただ聞くしかなかった。規則正しい不規則の規則は正しい。どこにも隙間が見当たらない。満たされたことなぞ1度も無いのに、どこにも余白が見い出せないのだ。優しげな母子の姿──そのかげろうにエレンはむやみに贖罪の意識を覚える。淡い魂を喰らい容赦なく輝ける夕陽さえ1日の終わりには霞むだろう。遠く船の汽笛がする。ざらざらとした耳障りなノイズ。完璧な室温。深い襟首のシャツでは口許を覆わせられない。リヴァイは、椅子に座った前屈みの姿勢で、眠そうな目を擦っている。エレンよりおおきなその手を取って、何か言葉を掛けるべきかとは思う、のにリヴァイの手はエレンの気持ちには気付かず点滴の位置だけ確かめる。今日もこの肺は呼吸している。心臓は脈打っている。時間は消えた。あの日リヴァイがどこかへ隠してしまった。この薄暗い部屋と空とを繋ぐ唯一の窓は、厚いカーテンに閉ざされたままだ。何日も──そう、もう何日も。
「今日は、何日ですか?」
その問いにリヴァイは、2月14日だ、と答えた。
「愛を伝える日ですね」
「違う。どこぞの誰かの死んだ日だ」
「そんなこと言っていたら、365日毎日、どなたかの命日になるじゃないですか」
「そうだ。だから何も特別じゃあねえ」
ブルネットより深い黒檀の、さらさらと流れるようなその髪に触れたい。
「兵長の髪にさわりたいです」
「気色の悪いことを言うな、ガキが」
リヴァイは思い切り眉を顰めながらも、エレンに顔を近付けてくれた。エレンは思い通りにならない指で、瞼や唇や、リヴァイのそんなところにばかり触れた。
「翡翠は、元気ですか? 兵長、ちゃんと、餌とか水とか、世話してくれてます?」
「訊かずとも、翡翠はおまえより元気だ」
それはエレンの小鳥の名前だった。碧い羽を持っていたから翡翠。幸せの碧い鳥だ。だがエレンはもう何日もその姿を見ていないし、声も聴いていない。その小鳥のことを、エレンはもうじき忘れてしまうかも知れないのに。既に思い出せないことはたくさんある。自分の名前。ついさっき交わした話の内容。笑顔の切っ掛け。なぜこんなにも物を忘れてしまうのか、それすら判らぬ。或いは、覚えていない。記憶が乾いた砂のように指の隙間からさらさら零れる。そして2度と元の場所に戻らない。しかし、いつかほんとうにすべてを忘れてしまうときがくるとしても、最後まで残っているものがリヴァイの姿ならば良い。リヴァイの名前ならば良い。そう願うので、何度でも呼びかけるのだ──リヴァイ兵長、と。
「さっきから何してるんですか、兵長」
流しに立ったリヴァイの手は、何かを迷い無く切っている。真新しい銀の鋏が切り落とすものは、何だろう? 瑞々しい、しなやかな、誰かの細い──指先のような。エレンは近頃眼球がうまく動かせない。限られた視界のその隅で、エレンはリヴァイの姿を常々探す。それが今日はなぜかいつもより寂しくて堪らない。リヴァイが近くにいないと、怖くて怖くて堪らないのだ。いつからエレンはこんなにも、臆病になってしまったのだろう。自身でも判らない。
「ほらエレン。おまえの好きな花だ」
振り返ったリヴァイは、花を挿した瓶をエレンに差し出す。
「『エレン』? 誰ですか、それ」
態とそんなことを言い、エレンはリヴァイを哀しませようとする。寝台脇の棚に瓶を置き、努めてリヴァイは何事も無かったかのようにエレンの点滴の位置を確かめる。その瞬間の世界が嫌いだ。すべてがエレンを拒んでいるような気がする。ならば忘れたふりなどしなければ良いのに──やめられない。悪い癖だ。リヴァイの眸は時々、魚の鱗のように美しく光る。その眼の下には隈が出来ている。ろくに寝ていない。あの夜から、1度も熟睡していないのだ。それを思うとエレンは、自分が早く消えてしまえば良いのにと願わずにいられない。
「……ねえ、兵長?」
「何だ」
「もしも。もしも、の話ですよ? もしも俺が貴方を遺して死んだら、棺なんかには入れずに、裸にして、手向けの花も握らせないで、巨大樹の森の、奥の、冷たい土のなかに埋めて、そこには墓標も立てないで、兵長は泣いたりなんかしないで、何事も無かったみたいに去ってください。俺は穢く腐りたい。動物の死骸みたいに、枝を離れた枯れ葉みたいに。雨に打たれながら、虫に喰われながら、なるべく時間をかけて、土に戻りたいんです」
狡い言葉だ。リヴァイが相槌なぞ打てないと重々既知している上で、何かから解き放たれたような面持ちで、自分ばかりが美しいふりをする。それなのにリヴァイの指は、黙ってエレンの眦をなぞってくれる。あァ、この優しい微熱、ほんとうは誰にも渡したく無い。誰にも渡したくは無いのに。いま、エレンの枕の下には、回転式の小銃がある。
「……もしも、の話です」
エレンは、自覚している以上に、狡い。暗い天井ばかり眺めているものだから、目は段々と光を忘れていく。そんなときでもリヴァイの姿だけは紛れもなく鮮やかで、他はみな、死んでしまった。遠く船の汽笛が聞こえる。ざらざらした雑音。心地好く、完璧と呼んで差し支え無い室温。迫り上がる悲愴に身じろぎしながら眠ることも出来ず、に、寝返りを打ちつつエレンは何度も、リヴァイの名前ばかり呟いている。カーテンの僅かな隙間を掠めてこの部屋に刺す光は、あれはそう、灯台か。ここから海はそれ程遠くないのかも知れない。耳障りな雑音だとばかり思っていた音も、実は優しい波の音だったのかも知れない。エレンはかなりの時間をかけ寝台の上で躰を起こし、繋がる点滴の針を、また、かなりの時間をかけて引き抜いた。寝てばかりいたので足に全然ちからが入らない。蹌踉めく躰を結局寝台に横たわらせる。今度は、エレンのベッドに突っ伏しているリヴァイを、暫く見詰めた。瞼を閉じた青い頬を、誤ってこの部屋に迷い込んだ光がずっと撫でている。生きていないような肌だ。初めて逢った頃からリヴァイはずっと、そんな肌をしていた。エレンのような派手さは無いが、幸せになるべくして産まれた、そう形容したくなるような美しく整った顔。眸は濃い茶に一筋だけ深いネイビーブルーをぽとりと落として混ぜたような、珍しい色をしていた。黒い髪と同色の睫毛は長くは無いが密で、触れると存外やわらかだった。小造りな人形のようなリヴァイがエレンを調査兵団に入れてくれて、ひとつずつ些細な何かを知る度に警戒心を削いでいった経緯も、もう思い出せぬ。もっと光が欲しい。と──エレンはカーテンを開けようとし、やめた。
「外が見たいです」
いつかそう告げたことがある。難題を言ったつもりは無かった。けれどリヴァイはエレンのその欲求に、ひどく困った顔をした。
「兵長。空が見えなくて、怖い」
続きリヴァイはますます哀しい顔をして、それでも何とか表情筋を動かし、今日は曇っている、と言った。エレンは曇りでも良い、雨でも良い、いつかいっしょに見上げた空が、今もちゃんとそこに有るのかどうか、それさえ確かめられれば良かったのだ。それでもその望みは、あのときのリヴァイの絶望程は強く無かった。きっと。だからもう望むことをやめたのだった。
思い出せない何かを思い出そうとしながら、リヴァイの頬に手をあてていると、リヴァイがいつか綺麗だと褒めてくれた蜂蜜色の双眸から、涙が出てきた。でもそこから溢れる涙はただの透明な水であったし、エレン自身どうして自分が泣いているのか理由が解らない。あたたかかったから、というのが最も適切で正しい気がする。頬が、額が、あたたかい。リヴァイは、確かに生きている。これからも、このぬくもりを持ち生きていくのだ。それはエレンが傍に居ても居なくても 、変わらない。こればかりは誰にも奪えない。例えば──リヴァイが死なない限りは。エレンは己の下唇を切れるほど噛み、枕の下にそっと手を入れた。取り出した小銃はその手のなかで、黒光りしていた。前に持ったときよりも重さを増した気がする。エレンはゆっくりと、その銃口を己のこめかみの高さまでかかげていく。やがて静かに目を瞑り、安全装置を外そうとし、
「よせ」
外し損ねた。まさか気が付くなんて思っていなかった。目覚めたばかりでいつもよりきつい目が、不満げにエレンを見ていた。まだ虚ろな眼差しは焦点が定まっていないのかひどく頼りない。なのにエレンを引き止めるには充分だった。
「……どうして、兵長」
耳に届いた声がその声で無ければエレンは、彼をリヴァイだと判らなかっただろう。彼はもう殆ど別人のようだった。エレンは知らない、こんなに怒気を顕わにしたリヴァイを。汽笛が強く鳴ったせいかも知れない。ノイズが聞こえる夜だから。疲れた脳を掻き乱すように。その目は語っていた。知っていた、と。エレンの隠し持つ切り札の存在などずっと前から知っていた、と。
「……独りでそうしようとするくらいなら、なぜ俺に、いっしょに死んでくれと言わねえんだ。エレンよ」
リヴァイの顔を覆う手は痩せ、指の隙間から、エレンが初めて見るリヴァイの涙が零れ落ちた。呼吸が止まる、と思った。小銃は冷えた床に呆気なく落下し鈍い音を立てた。閉ざされたカーテンの向こうにあるのものは、もう碧い空なぞでは無い。耳障りなノイズの出所は銃声で、瞬く光は森を焼き払う閃光だ。遠く鳴る汽笛は、逃げる者たちだけを乗せたノアの方舟。廃墟と化したこの国にはもう、エレンを埋められる森など無い。
「世界は終焉する。愛を伝えながら、おそらくは」
2月の14日、寒い、それが何かを意味するところを知りたくなんか無い。リヴァイが嘲けっているのはエレンなのか彼自身なのか、それとももっと別の何かなのか、エレンは知る術を持たぬ。知りたいとも──思わない。何も考えたく無いのだ。もう、何も。
「翡翠は、逃がしてくれましたか? ちゃんと、逃がしてくれたんですか?」
エレンは震えの止まらない指を、真っ白いシーツの下に隠そうとした。だがリヴァイはそれを赦さず、痩せた手でもっと強く握り締めてきた。覗き込んでくる瞳の奥で輝いているリヴァイのネイビーブルー、エレンはもうすべて委ねてしまう。
「鍵は疾うに外してある。ほんとうに生きたいのなら、自力で飛んでいくだろう。翡翠なら。だから心配は要らねえ。……なァエレンよ、あのカーテンの向こうには何もねえんだ。毒と鉄骨、灰の闇だけがすべてだ。飢えた野良犬は逃げ遅れた病人を喰らっている、噛み千切られたその腹からは子供の指なんぞが出てくる。気を違えた母親が赤ん坊の頭皮を毟って。感覚の麻痺した他人同士が、互いの四肢を千切り合っている。すべては愚かな人類が引き起こした、悪夢みてえなもんだ。だからどうしようもねえ、ほんとうにもう、どうしようもねえんだ」
話しているリヴァイが顔を顰める。ならばすべてはほんとうのことなのだろう、とエレンは思う。それだって、真理のすべてでは無いだろうけれども。
「世界は、いつから変わってしまったんですか」
「たぶんずっと昔から、こうだったんだろうよ。もう誰も覚えちゃいねえくらい、昔から。金のある豚共は新天地へ逃げた。貧しい者につくらせた方舟で。実際の方舟づくりに関わった者で、その方舟に乗れた者なんざ唯の1人もいねえ筈だ。重量の限られた方舟に乗るには、生き残るに相応しいのだと認められなければならない。そしてその選出には、多額の金が必要だ。理由なんぞ何れを取っても醜いが、それが偶々、金だっただけだ。安心しろ、おまえの馴染みは全員無事だ。ミカサは最後までここに残ると駄々を捏ねたが、アッカーマンの血を絶やすわけにはいかねえと薬を盛られ寝ているところを無理矢理乗せられた。そしてアルミンも含め、兵団員はみな護衛として乗せられた。或いはあちらに裏切られた場合でも対処可能なように。保険というやつだな」
「……兵長、だったら貴方こそ新天地に必要だ。兵長はその方舟に、ほんとうは乗れたんでしょう? それなのにどうして貴方は、まだここに居ようとするんですか」
そうして矢張りエレンは、それをリヴァイに言わせるのだ。
「エレン。おまえがここを出られないからだ」
それは起こった。凄まじい震動に崩れ落ちていく。何もかも──何もかもが、轟音を立てて崩れ落ちていく。過去も未来も、今この瞬間ですら。最初の爆音にエレンの右耳の鼓膜は破れてしまっていた。リヴァイの胸に左の耳を当てたなら、まだ思い出せる。色と、熱と、日々。瓦礫の下のエレンはぼんやりと、遠い時間を巻き戻していた。小さな翡翠を拾った時の碧空。不吉な予感を微塵も感じさせない、陽だまり。ふたりを隔てるものなど何ひとつとして無かったのだ。階級も出身も関係無い。緑の風は髪を舞わせるだけ。時間は静かに過ぎてゆくだけ。何も否定せず、何も肯定せず。リヴァイの碧白い手を握るのが、ひどく汚れたエレンの手でも、すべては自然のなかで赦されていた。ずっと続くのだと疑いもしなかった。誰しもを取り巻く幸せな日々。何回も巻き戻しては、飽きもせず見続けた、硝子の眸でふたりはずっと。干乾びることが無いのなら、ここはもう水底かも知れないけれど。夜の海に浮かぶ。模したのは胎児か亡骸か。裏側から月に照らされた雲が金銀を散りばめた星雲のように発光している。エレンは浮遊している。無意識的に、どちらからそうしたのかも判らぬ口付けは、それだけでは吐き出してしまいそうな程とても苦く、そして砂糖菓子のように只管甘いだけだった。ただ、それだけだった。
「おまえはずっと、俺の傍にいるだろ」
苦虫を噛み潰しているかの如く苦笑を飲み込む、リヴァイの手は、エレンの知らぬ存ぜぬうちに、翡翠の風切り羽を容易く手折っていたのだった。だから未だ鳥籠のなか、鍵と扉を開けていようとも、翡翠は最早どこにも飛んでゆけない。伝える愛など何処を捜そうと微塵も無いのだ。何しろ互い、どちらが根負けし、て、泡沫と消えてゆけるのか、競い合っているかのようなものなのだから。胸焼けがする。飛び立つことも出来ずに。救えない。幸せの碧い鳥を探す旅に出る人間の幸せは、初めから傍に有った、と謂う落ちは在り来りな話だが、幸せの碧い鳥は、エレンの翡翠は、飛び立てずとも、まだ生きている。