<概略>
リヴァエレ前提と呼んでも良いものか不明なリヴァイとエレン/転生現パロ/前世でエレンは処刑されています/両者前世記憶持ち/援交びっちエレンから派生/モブエレ→リヴァエレ/首絞め/一応落ち着く結果に/
先にこちら→『金魚救い』→『ひとり』をお読みくださると捗ります。

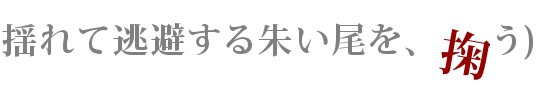
『コウモリであるとはどのようなことか』──アメリカの哲学者トマス・ネーゲルが1974年に発表した哲学の論文、及び同論文を収録した書籍である。ネーゲルはこの論文で『コウモリであるとはどのようなことであるか』を問うている。コウモリがどのような主観的体験を持っているのか=『コウモリであるとはどのようなことか』と謂う問題は、コウモリの生態や神経系の構造を調査するといった客観的、物理主義的な方法論では辿り着くことが出来ない事実であり、意識の主観的な性質は、科学的な客観性のなかには還元することが出来ぬ問題であると主張した。この論文は、心身問題の中心が意識の主観的側面(意識の現象的側面)にあることを述べた有名な論文であり、表題の問いは、よく知られた問い、または思考実験のひとつとして、現代のこころの哲学者たちの間でしばしば議論に上る。この問いに関するひとつの留意点は、ネーゲルが問うているのは『コウモリにとって、コウモリであるとはどのようなことか』という点である。つまり、この問いは人間が、例えば俺が、人間としての脳──人間の思考回路や本能を保ったまま、コウモリの躰を得て、コウモリの暮らし振りをした場合にどう感じるかを問うているのでは無い。もし、俺が人間としての脳だけを保ったまま、コウモリの躰でもってコウモリの生活をしてみたのなら『空を飛ぶことは怖い。けれどちょっと慣れると楽しい』とか、『昆虫を食べるだなんて気持ちが悪い。でも食べなきゃ死ぬ』とか、『洞窟の天井にぶら下がって眠るなんて変な眠り方だなァ。落っこちねえのかな』などと思い至ることだろう。しかし、ネーゲルが問うているのは、そうしたヒトがコウモリになった場合の感情や印象、世界の捉え方ということでは無く『コウモリにとって、コウモリであるとはどのようなことか』である。つまり、コウモリの躰とコウモリの脳を持った生物が、どのように世界を感じているのか、であった。コウモリはその特質から、くちから超音波を発し、その反響音をもとに周囲の状態を把握している(反響定位)。コウモリは、この反響音をいったい『見える』ようにして感じ取るのか、それとも『聞こえる』ようにして感じ取るのか、またはまったく違ったふうに感じているのか(ひょっとすると何ひとつ感じていないかも知れない)。ネーゲルが問うているのは、こうしたコウモリ自身の主観的経験である。このようにコウモリの感じ方、といったことを問うこと自体は容易にして可能ではある。だが結局のところ我々ヒトはその答え『コウモリであるとはどのようなことか』を知る術は持っていない、とネーゲルは言う。ネーゲルが対象とする動物としてコウモリを選んだのには、コウモリが哺乳類に属しており、系統樹のなかでは、ある程度人間に近い位置にある生物であること。とは云え同時に、翼があったり超音波で周囲の状況を把握したりと、運動器官や感覚器官に関して人間とは距離のある生物であるため、としている。つまりあまり人間に近い生物だと問題を鮮やかに示すのが難しく、かといってこれ以上系統樹を下って進んでいく(例として蜂や蟻まで行く)と、そもそもそこに意識体験があるのかどうか疑念が出てくるという難点がある。そこでコウモリという中間的な距離の生物を選んだ、としている。この論文が持った重要な影響のひとつとしては、意識の主観性の定義として『〜であるとはどのようなことか』という表現を用いた方法を有名にしたことにある。以下、論文の序盤でネーゲルが主観的な意識体験として意識を定義している部分の文章である。文献第12章『コウモリであるとはどのようなことか』──ネーゲルの論文は1974年に『The Philosophical Review』誌で発表されその後、1979年に出版されたネーゲルの論文集『Mrtal Questions』の第12章に収録される。『コウモリであるとはどのようなことか』という論文は、ほんの15ページ程の簡潔な構成であり、ネーゲルの思考内容は、その概要がごく簡素に示されているのみである。ネーゲルの主観性の問題に関する詳細な思考内容は、1986年に出版された『The View from Nowhere』にて述べられている。200ページを超えるこの書籍は、『中心を持たないどこからの眺めでもない視点』である客観と、『今、ここからの視点』である主観との間の葛藤を扱っており、そのなかで『〜であるとはどのようなことか』という題目が、この書籍のなかでは『頭のなかのこと』という表現で換言されている。ネーゲルが『コウモリであるとはどのようなことか』について、どういうことが言いたかったのかを考察することが出来る。おそらく意識体験は、宇宙全体に渡って他の太陽系の他の諸々の惑星上に、我々ヒトにはまったく想像もつかないような無数の形態をとって生じているのである。しかし、その形態がどれほど多様であろうとも、ある生物がおよそ意識体験を持つという事実の意味は一定であり、それは根本的には、その生物であることはそのようにあることであるようなその何かが存在する、という意味なのである。意識体験という形態には、これ以上の意味が含まれているかも知れない。生物の行動に関 する意味さえ(疑わしく思われるのだが)含まれているのかも知れない。しかし根本的には、ある生物が意識を伴う心的諸状態をもつのは、その生物であることはそのようにあることであるようなその何かが──しかもその生物にとってそのようにあることであるようなその何かが──存在している場合であり、またその場合だけなのである。
と、云うことについて俺の感想は、哲学者って暇なのな、とその程度のことなのだった。俺はコウモリじゃあ無いから飛ばないし虫を食わないし洞窟で逆さにぶら下がって寝たりもしない。けれど化け物の思考だって化け物にしか解らないんだろう。
誰かに言いたくて、聞いて欲しくて理解して欲しくて、でも、絶対に言えないことがある──今の俺には前世の記憶が有りそれがあまりに壮絶なものであること。次に、当時の俺と記憶を取り戻した現在の俺では性格や思考や言動が随分と違うこと。なので、誰にもバレてはいけなくて、嘘をつき続けてでも誤魔化し続けなければならないことがある──記憶を取り戻した俺にとって、この安穏とした退屈で平和なだけの世界なんてひどくどうでも良いと思ってしまっていること。平和ボケしているこの今の世界は無関心で暴力的でヒトに対して徹底的に冷たいもので、逆に、俺のほうから見た世界も、そういうものであって、所謂『社会不適合者』と呼んで差し支えない俺は、今日もこのどうでも良い、痛くて、好きなものも見付けられない世界にくるまり、のうのうと生を謳歌している。
あの夜。駅を抜けてその先にある住宅街よりもずっと向こうまで、行くと、街灯が極端に少なくなり、暗くて危うい。ので。そこまで進んでひとりになりたかった。のに。俺は結局浅瀬でぴちゃぴちゃと波に裸足を撫でられるだけでどうしてもその先へ動けずに、何も変わらぬまま自宅に戻った。そして前世の俺ではまったく出来なかったろう嘘泣きで両親に泣き付き、援助交際の事実も男と性行為をするような事実も皆無ですべてはあの男の妄想でしか無く、ストーキング被害にあっていたのだと云うことにして、ヒトひとりの人生を狂わせた。俺は今までも(多分これからも)童貞だし、と云う現実。嘘をつくコツは必ず真実を混ぜておくことだ。彼は今ストーカー犯罪者として扱われ心神喪失のため閉鎖病棟の鉄格子付きの部屋に措置入院している。別に罪悪感は全然無い。寧ろ自業自得だとさえ思う。金を払ってヒトを買う、と、云うことの意味を彼は根本的に理解っていなかったのだ。そこに愛やら恋やらが滑り込む隙間など1ミクロンも有り得る筈が無いのに。が、こちらも無傷とはいかず、俺は取り敢えず転校を余儀なくされ家は引っ越した。し、こころのケアだとかで俺は現在カウンセリングを受けている。けれどもヒトの縁と云うものは不思議なもので、小説より奇なり。ケアワーカーの職場は俺を破格値で買う上質なリピーターの──俺のこころのなかに有るらしき部屋にはドアも窓も無い、と、笑った──精神科医が開業医をしている病院だった。初めまして、なんて握手をした瞬間はもう互いに笑いを全力で堪えて、いて、もう何と言うか俺は愉快さに転げ回ってしまいそうな程で。それでも、俺のようなヒトとしての欠陥品が正気を保ってふつうの生活を送っていられる人間であるのだと擬態し生きるためには、そうなのだ、全身全霊でもってこのくだらない世界で、こんな世界に存在し受け入れられ生きている人間に、欲望のまま求められればそれに応えるという義務を、出来得る限りの高い値札をぶら下げて、果たさねばならない。そうでもしないと俺は本気で狂って、きっと無差別大量殺人でも犯してから、死んでしまうに違いない。だから──そうならないためにも俺はまだ、
「そう言えば、きみは、自分からは何も求めないね。エレン」
この人が俺を抱くために連れて行ってくれるホテルはいつも違うホテルだ。アシがつかなくて良い。まず俺と利害は一致しているし、何よりセックスのあとのルームサービスにハズレが無い。そこもこの人と寝る利点だ。俺を買う男がみんなこの人みたいなら楽なのに、と思う。思うから俺は今のところこの人以外に客を取っていないのだ。
「求める、って…何をですか?」
既に充分、躰を求めていると思っている俺はフォークに刺したオレンジの風味がかすかにするローストビーフを頬張る。
「自分だけをこころから愛して欲しいとか、独り占めしてみたいとか、そういうことだよ」
咀嚼して飲み込んだ肉が喉を通過しごくん、と鳴った。
「えー……まさかそれ本気で言ってます? そんな殊勝さがあれば、俺もう貴方とセックスするために態々こうして会ったりして無いと思うんですけど」
「そうだね。私は妻をこころから愛しているから」
「なんだ、ただの惚気でしたか」
「はは。貞淑で美しくて、穢さとは無縁の女性だから、惚気たくもなるんだよ」
「俺とは真逆ですね。そんな素敵な女性が居て何で俺なんかを愛人に選んだのか疑問ですけど」
俺が興味無さげにそう言うと、先生は、だって、と悪戯な子供のように言う。
「だって汚れたがっているきみ相手になら何だって出来るし、何だってさせられるだろう? 妻には到底出来ないことを。堪らないじゃあ無いか。きみのような美少年が、私の要望通りに縋ってくるんだよ? その顔で。その瞳を蕩けさせて。更にその上、男の夢を具現化したように全部覚えて実行してさえくれる」
そう言えば。
そう言えば、と俺は思う。まだ男同士のセックスに慣れていなかった頃、相手任せが主だった俺に優しく、騎上位のときに両手を躰より後ろについて、腰を振るのを初めて教えてくれたのもそう言えばこの人だったなァ、と。
「お陰さまで。商売繁盛でしたよ」
「綺麗だったものが、汚れていくのを見るのは楽しいよ。それも私の思い通りに。育てると云う行為は単純な性行為より、ずっと楽しい。上手く育ってくれたら嬉しくなる」
「へえ。先生は俺と寝て嬉しいんですか」
「当然だろう、嬉しいさ。何より、繰り返すけれど、愛する妻にはとても出来ないことが出来るんだ」
「でもコレ浮気ですけどね」
「浮気? とんでもない。浮気なんかじゃあ無いさ。本気でも、無いけれど」
そうして立ち上がった先生に腕を引かれる。
「よくわかりません」
「もっと大人になれば理解るようになるよ。若しくは、きみがこころから“愛して欲しい”と思える誰かと出逢ったなら」
愛して欲しい? 『コウモリであるとはどのようなことか』をわからないように、ほんとうの愛を知らないまま何が愛なのかも俺にはわからないのに?
そうこうしているうちに再びベッドへと招かれた。先生の笑みはやわらかく、優しい。いつもそうだ。することは結構えげつないくせして、俺にふれる指や手のひらはあたたかい。いつもそうだ。いつも。
「……っふ、」
甘やかなキスを受けながら俺は考える。だったら、貴方が俺を、躰だけじゃ無く愛してくださいよ。言ってみようか。言わなくとも、言っても無駄だとそれだけは理解出来る。だってこの人にはちゃんと愛している人が存在するのだ。且つ、俺は空っぽで何も無い。何も持たない──そう決めたのは、誰でも無い、俺自身だった。 俺は俺のこころのなかに有るらしき部屋とやらから摩耗した愛憎を放り投げ、棄てて、そしてそれは奪われ削られていく。
「きみはもう少し自分の価値を把握したほうが良いよ」
「充分しているつもりですけど」
「なら、もっと、」
「“自分を大切にしたほうが良い”?」
「よく解ったね」
「言われ慣れているので」
「それでいて私に抱かれたがるんだから、矢張りきみは可愛いよ。愚かで」
「こんな躰、幾らめちゃくちゃに汚したって、」
それ以上は言葉にしなかった。気持ち悦ければそれで良い。俺を抱くこの人の腕のなかはひどく気持ち悦く俺を穢し、あの夏の日にめちゃくちゃになってしまった俺を、まるでこの退屈な世界にとどめるかのように、めちゃくちゃにしてくれる。俺はぼんやりと、しかし急かすようにも、俺の躰を組みし抱く男の躰を見ていた。筋肉の薄さは俺と大して相違無く、背の高さだけほんの少し、俺のほうが劣っている。肉欲と焦燥に駆られた大人の雄の双眸が俺を見詰めている。羽織っていたバスローブがばさり、落ちる音がして、あァもう焦れったい程に、俺は叫びだしたいくらいの安堵感に満たされてゆくのだった。
◆
燃えるような赤い色をした夕焼けが眩しくて、足許に広がる黒い影を踏み締めている。化け物だから逢魔が時も怖くない。雑踏のなか、どこか遠く聞こえる赤の他人の声やいろんな音がすべてノイズとして響いて、無感動な俺の脳髄に沁みては蒸発していく。どこへ? どこかへ。俺の知らないどこかへ。正体を消せば、風の音がよく聞こえる。正体を知られれば、誰とも視線はもう交わせない。すっかり熱が冷め倦怠感だけが残る躰を引き摺るようにしながらも、人混みを避け車道側ぎりぎりの歩道を歩く。途端それを見計らったかのように歩道側へと寄せて来た車がクラクションを鳴らしたので、うるっせえな、と見遣れば、その高級車の運転手が見覚えの有り過ぎる人物で、俺は反射的に顔を顰めた。
「…………何で居るんですか。俺にGPSでも付けてんですか」
まじで。真面目に怖いんですけど。何なんだろうかこの人は。
「リヴァイさん」
と、俺は嫌悪感たっぷりにその人の名前を口にした。リヴァイさん。リヴァイ兵長。俺にXデーを齎した諸悪の根源とも云える。
「乗れ。エレン」
前世では散々関わり深かったのでもう今更また関わりたくないのはきっとお互い同じであるだろうに、リヴァイさんは命令口調で俺を呼ぶ。その声は確かに俺を咎めていて、面倒臭い。
「やですよ…ご用があるならそこでどうぞ」
俺はいっそ投げやり気味の調子で言い、全開にされた窓から身を乗り出さんとするリヴァイさんの、目付きの悪い顔に隠すこと無く溜息をついた。そんな声で咎められずとも用件など殆ど理解っている。その証拠にリヴァイさんの瞳はいつに増して鋭く、俺を冷たく睥睨していた。外気はちっとも冷たくなんて無いのに、俺とリヴァイさんの間を漂う空気は凍りそうな程冷たくて、張り詰めてさえいるのだ。
「良いのか? 外で話しても。俺は一応おまえのプライバシー保護のために、車に乗れと言っているんだがな。なァ? エレン」
不自然な程にきっちりと閉められた制服の襟を捕まれ、あんたにゃ関係ねえだろとも思いつつ、リヴァイさんの手を払い除け、助手席側へとまわった。
俺はリヴァイさんの車に乗り込む。最早どうでも良かった。いつものことなのだ。この人に見付かったら、俺にはどうしようもない。目を閉じて開けたら世界や記憶が変わる魔法なんかどこにも無い。
「いつになれば諦めてくださるんです? ストーカーですか、貴方は」
「誰がストーカーだふざけんな。おまえこそ、いつになりゃあ懲りるんだ」
「最近は漁ってまーせーんー」
「馬鹿言え。穢え雄の匂いがぷんぷんするんだよ」
「そりゃまァ、今してきたとこですからねえ。でもちゃんとお風呂入って来ましたよ? 始める前に1回とルームサービス前に1回、最後に部屋から出る直前にもう1回。ほら、3回も綺麗にしてます」
「結果2回に分けてセックスしてきたんじゃねえか」
不快げにそう言い放ったリヴァイさんは再び俺の襟首を掴み、引きちぎられるかと思う程の乱暴さで俺の制服をはだけさせた。鎖骨の上辺りから胸にかけて、夥しい量の鬱血痕、が、顕わになる。
「ちょ、いきなり何するんですか。セクハラですよリヴァイさん。訴えますよ」
慌て制服を握り締める俺にリヴァイさんが溜息をつく。
「それで崩壊したんだろうが……おまえんちは…──」
「それこそ貴方に関係ない話でしょう」
「…………隠れねえ部分にも付いてるぞ。耳の下、首筋と。…喉には、何だそれは……噛み痕か?」
「うわ」
あァまた今日も家に帰れない。けれどそれはもう疾うに決まっていることでもあった。もっと言えばあの夏のXデーから。異物で化け物の俺に居場所など無いのだ。現在の新居だって転校だってカウンセリング通いだって勘違い野郎への措置にしたって、それは傍目には態々明るみにしない限り何の問題も無い家庭に見えるのだろうが、おまえの話を聞く前に怒鳴りつけて悪かった、と謝ってくれた父も、怖い思いをしていたのね、と泣いて抱き締めてくれた母も、それらはどこか義務染みていて、今や食卓ですら俺と彼らとの会話は無い。沈黙。ただただ重苦しい空気が漂っている。俺が家を空けようと何も言われない。矢張り俺はあの家での異物であるのだ。歩み寄れないのは仕方の無いことだ。俺だって、俺に、歩み寄れないのだから。でも同じ顔で同じ声で、それでも前世の両親を知っている俺としては、幼い俺とミカサを逃がし巨人に喰われた母さん、大切なものを救えと自らの命を捨て俺に喰われてまで俺を巨人化する生き物にした父さん、そんなふたりとは掛け離れている現世の平和さと比べて、比べても意味が無いのに比べてしまう俺は、俺自身も前世の自分とは掛け離れていることを棚に上げて、この世界は無関心で暴力的でヒトに対して徹底的に冷たいものであるのだと、そしてその逆も然りと諦めてしまった。にも関わらず、この人は──兵長じゃあ無いただのリヴァイさんだけはこうして執拗に未だ俺を見付ける。正直なところ、鬱陶しいし邪魔なので諦めて欲しいと本心から思うのだけれど、俺が切り売りする俺をただひとり悼んでいる。部下だった俺を。現在の俺を。矛盾だらけで叱り飛ばす。そんな権利は、リヴァイさんだけには絶対に無い筈であるのにだ。
「身売りはするなと、何度言わせれば気が済むんだ」
そう、こんなふうに。
「回数なんか疾っくに数え忘れました」
「相変わらず出来の悪ィ頭だな」
「よ、く、言、う。貴方がそんなこと言えた義理ですか兵長」
「だから俺はもう兵長じゃねえ。何回言わせる気だ」
「う、……っぜええ。死ぬまで勝手に言っててください。つうかはやく死んでください」
こういう遣り取りも最早幾度めになるのかわからない。兵長は死なないしリヴァイさんも死なないのだ。そして別に何かをして欲しいわけじゃあ無いが、何ら贖罪もしない。
「俺に構うってことは今夜だけで良いので泊めてくださるってことで構いませんか」
「どこに」
「どこでも。リヴァイさんの部屋でもホテルでも。何ならこの車のなかでも良いですよ。こんな歯型付けたまま、俺は自分ちに帰宅出来ないんで。無理なら下ろしてください」
「それでその足で泊めてくれそうな男を探すんだろう」
「他にしょうがないでしょ。だって独りぼっちは寂しいですもん」
「……チ、」
リヴァイさんの舌打ちと同時に車が発進しどこかへ向かう。おそらく駅近のホテルだろうな、と俺は思っていたのだ。なぜなら今世の俺は平気で嘘と肌を重ねられる穢らわしい生き物だから。リヴァイさんにとって俺は生ゴミみたいなものなのだ。そして潔癖なリヴァイさんは決して自宅へ生ゴミを持ち帰らない。その筈だった。なのに車が入った駐車場はホテルでもどこでも無く、て。
「……どこですかここは」
「マンションだ」
「いやそんな見りゃわかることは訊いてませんけど」
素直に謂って俺は思い切り驚愕していた。このタワーマンションの1室にたぶんリヴァイさんの部屋が有るんだろう。けれど。えー……生ゴミ持ち帰るんだ、この人。みたいな気分で呆然となる。そんな俺の頭を軽くはたいたリヴァイさんは言う。
「何を呆けてやがる。さっさと車から降りろ」
「え。あ。はい?」
「はやくしねえと置いて行くぞ」
「いやいやいや、車中泊では無く?」
「は? 何で態々そんなことをさせるんだ。風邪ひくぞ。ふつうに俺の部屋で良いだろう。ほら、着いてこい愚図」
ええええ? もう俺は何が何だかわけがわからなかった。それでも仕方無くリヴァイさんの後ろを着いていく。カードキーで開けられたお高い部屋に連れ込まれて、あァもうこの部屋リヴァイさんの匂いでいっぱいで、すげえ腹立つ。とか現実逃避的なことを考えてぼおっと、スーツを脱ぐリヴァイさんの背中を見ていた。少し、面白くない。見た目は低身長で、服の上からではえらく華奢みたいな印象なのにも関わらず、ふれてみればこんなにも差がついてしまうことが未だ成長中ながらに面白くない。こんなん、肩とかどうやったら筋肉つくんだよ。さわわ、無意識にふれた肩はそろりと伸ばされた腕と連動し、手のなかで動く。
「おい。さわるな」
「いいじゃないですか別に。減るものじゃ無いし。筋肉、こことここもどういう鍛え方すりゃあつくんですか。どういう構造でこんなんなるんですか」
さわさわ。リヴァイさんの筋肉をあちこちさわる。
「やめろ。減る。穢らわしい」
「ふうん。リヴァイさんも、俺みたいな精液便器相手に勃つんですね。いやいやまさか。淫乱変態野郎と俺を罵る貴方が!? って話ですよ。それともそれって、男の頭と下半身は別物ってやつですか。ふんふん。ちょっと面白いですね」
悪趣味な笑みで笑うな、と言われたことを思い出して、目一杯笑ってみせた。立っているリヴァイさんの前に跪き、膝立ちになる。スラックスの布越しに指でなぞり、それが縫い目まで辿り着いたところで掬い上げるように下から上へ直線を引けば、過剰な分泌による唾液を嚥下した、俺の喉が細く鳴った。跪いた俺の目線の先、存在する、その両腕も両脚も、誰も何ら拘束なんかしてはいない。貼り付けた深い笑み。蠱惑的に歪むそれを前にして、俺の手を払うことも後退り離れることも、それより何よりその手で刃を抜くことすら自由な筈の、目前のリヴァイさんはただ直立不動で動かない。継いでベルトの金具に手をかければ、流石にまずいと云わんばかりにリヴァイさんの手のひらが俺の手を覆った、が、けれどそんなささやかな仕草が抵抗になどまるでならないことを、抱いた女の数も数えられないだろう歳であるリヴァイさんには、よく理解っているに決まっているのだ。ベルトを外し、ボタンを外し、ジッパーを下げる俺の手が、微塵も震えていないことに、リヴァイさんが気付かぬ筈が無い。上目遣いで合わせたネイビーブルーの三白眼は、泳いでさえいなかった。
「こんな化け物にも欲情出来るなんて、リヴァイさんも充分変態ですよ」
出来得る限りいやらしく見えるよう、にやりと笑って床に膝をついているそのままに、俺はリヴァイさんのペニスを銜えた。別に初めてする行為でも何でも無いが今くちにしたそれは、味がどうだとか匂いがどうだとか何とか云うより先に、俺の喉奥を刺激して、反射的に嘔吐きかける。そうして俺は漸く、ああ、今自分は吐き気を催すような醜悪なる行為を行っているのだと気付き、ますます吐き気が増して気持ちが悪くなった。おそらく俺の頭を叩き飛ばそうとしてぶつかってきたリヴァイさんの手が、髪に触れたところで思いとどまった。俺の喉が、口内に溜まった唾液を嚥下すれば、はずみでそれを刺激したのか、くちのなかでぴくりと震えた。歯を立てないように唇で挟んで舌を動かしてみる。俺は何の自慢にもならないが性交に手慣れてはいる。それだけを思ってくれれば良いと俺は思っていた。困惑しているのは自分だけだと、頭のおかしい蜂に刺されたんだと、一生思っていれば良い。舌に力を込めて這わせる。先のほうを何度も舐める。俺の舌が動く度に、大きな手のひらが、長くて節くれだった五本の指が、俺の髪の毛をかき分け頭を押さえ込む。
端から見たら感じているように、そうして互いを愛おしんでいるように、見えるだろうか。
しかしリヴァイさんにはきっと理解っている。俺が上を見るのを拒絶している。見上げた俺と視線が合うのを、リヴァイさんは己の股間に顔を突っ込み性器を銜えている俺の顔を直視するのを拒絶している。殆ど無意識に俺はリヴァイさんを、リヴァイさんは俺を、躰で拒絶している。本能で拒絶している。本能はいつだって絶対的に正しい。特にリヴァイさんのほうは。だから、俺が拒絶されぬ道理はない。おえっおえっとおおきく2回程嘔吐き口内のペニスを吐き出しそうになりながら、頭を押さえ付けられて息を吸うことさえ出来なかった。俺の感情とはまったく無関係に涙がぼろぼろ湧いて出て、このまま窒息してしまうと思った。リヴァイさんに殺される。それは恐怖では無かったけれども、でも、欣幸なんかでも無かった。喉の奥を圧迫していたものが急に消え、くちのなかが涼しくなり、俺は何が起こったのかをうっすら理解した。糸を引く白濁を何だか生き物の尾みたいだと思った。精液なんて幾らでも出せるもんな。目の前でニヤニヤ嗤って飲み込んでやろうか、それともそのご清潔な顔に吐きかけてやろうかと考えていたのに、実際には開いたままのくちの端から涎といっしょにどろどろとこぼれ出てしまった。下半身のほうさえ思うように出来ないなんて、これはちょっと間抜けだな。勝手に出てくる涙は止まらないし、開いたくちは塞がらないし、涎と精液の混合液は制服の襟からなかに入って胸の真ん中を伝っていく。
確かに俺はこの人に今まさに欲情していたし、率直に言ってやりたいと思っていた。それは認める。認めるけれど、何だこれ。リヴァイさんは何をとち狂ったのか俺の胸倉を掴み強引に立たせると、乱暴な、噛み付くようなキスをする。なのでそれに便乗し、態と水音を立て、こちらからも舌に噛み付いてやれば、嫌そうだったネイビーブルーの瞳孔がぐうと開き、雄特有の妖しい色気が滲み出す。俺がのりだしてきたところで、リヴァイさんは唇を1度離した。見ると、まだ物足りない、とでも云うふうに、リヴァイさんは唇を垂れる唾液を舐めている。
「もう終わりか?」
爛々と光る、熱を孕んで潤んだ目で、挑発するリヴァイさんを見詰めた。先程とはまるで別人のようだと思った。途端、リヴァイさんは口角を歪めると、俺の脚を蹴って、そのままフローリングに転がした。痛い。熱くてぬるぬるした何かが首の横を上下している。リヴァイさんの舌だと気付いたときにはもう遅かった。偶に耳を掠める息が温くて荒くて、リヴァイさんは本気なんだなと、漸く思い至った。男の俺──ばかりか国家予算以上の金を積まれても汚ねえ精液便器なんざ欲しくない、とか何とか、いつぞや吐き捨てたこの人が、本気で俺に欲情するなんて、どうかしているんじゃなかろうか。とか、唖然としていたらいつの間にか襟がおっぴろげられていておおきな手の平が這っていく。さっきまで鼻についていたリヴァイさんの清潔で潔癖な洗剤の匂いはどこかに消えて汗臭さにくらくらする。その手はあちこちが硬く盛り上がっていて、それが胸の辺を擦る度に俺のくちから勝手に、は、とか、ん、とか息が漏れた。太ももの内側に指が触れて、反射的に両足の爪先が跳ね上がった。そこからは、もう、駄目だった。気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い何だこれ何だこれ何されてんだ、頭のなかはそんなふうでいっぱいなのに、俺の唇は、はんはんAVみたいな声を出し続けるし、躰はぴんぴん跳ね上がる。あのネイビーブルーの目がくっつきそうな程そばで俺の目玉を覗き込んだとき、初めて怖くなった。視界いっぱいがあの目で覆われて、逸らす逃げ場さえ無くなった。あ、犯されるんだ、と思った。この人は本気で俺と『セックス』する気なんだ。神様たすけて。今まであんたにかけた願掛けは全部撤回します神様。俺に正しく発情するような、そんなリヴァイさんは要らない。自分の声を聞きたくなくて、俺はずっと──丁度、親指と人差し指の付け根あたりを噛んでいた。だけど巨人にはなれない。リヴァイさんはそのまま俺の躰に馬乗りになって首を絞めるように俺の喉へ手を添える。と、俺は何だか、この期に及んで何かを期待しているような気分が浮上してくる。
「っ、ぁ、」
ぎりぎりとヒトの手垢がついた俺の喉をリヴァイさんが絞めると、俺の口端からは短く細切れになった息が押し出される。俺の双眸はもっと潤み、きっと色が濃くなっている。酸素が遮断される感覚に苦しみながらも、リヴァイさんの手を掴む俺の指には、殆ど力がこもっていない。俺は幻覚を見ている。慢性的な低酸素症によって齎される幻覚状態に関して、確か、ロイド博士は登山者が高地で経験する幻覚と類似している点を挙げていた。彼は更に、そのような状態は高高度での航空機の急激な減圧によって齎される低酸素症では引き起こされないことをも注記した。これらの調査結果は、酸素の欠乏のみが興奮の増大に至らせる要因であるわけでは無いことを示唆していた。そこで低酸素症の研究について調査したところ、『脳の神経化学の異常が相互に連結した神経伝達物質であるドーパミン、セロトニン、β-エンドルフィンのうちひとつ以上を含んでいることが、幻覚と関係したすべての状況で報告されている』と謂うことを発見したのである。と脱線せざるを得ない程、俺は今アホ面を晒しリヴァイさんとリヴァイ兵長を重ねて見ている。良くも悪くも、この人は何にも変わっちゃいないのだ。
そうして漸く約束は果たされるのだろうか。そう思うと愉楽的な思いが嬉々として込み上げて、俺は無意識的に薄く笑っていた。
「ぁ……っは…」
「悦がるなよ。エロガキ。死ぬぞ」
「……そ、の……変……態、の、エロガキに…っ、惚れ、てるんでしょ…う…?」
「………よく解ったな」
まったくもってお互いにイカレている。俺もリヴァイさんも、互いに狂気じみた笑みを浮かべた。リヴァイさんは首を絞めたまま、俺の唇にキスを落とす。俺の手が、リヴァイさんの背にゆっくりと回された。ゆっくり──脆く大切な何かをそうっと掬いあげるように──それを愛だ何だと云えば美しいだろう。だが、そう云えないからこそ、胸の内側で淀んで粘つく想いは苦しく不快だった。呪いより滑稽で酷い、運命劇場の終演に、俺はもうこれ以上何を棄てれば良いのかが解らない。世界なんてどうでもいい。他人に好かれる努力も、値札もいらない。生きていくことすら──どうでもいい。だから今日も欠陥製品たちは、世界を横目に笑っていられるのだ。どうせ全人類何らかの病気だろう。これでは告白と言うよりも告解だなと自嘲する。世界は意地悪だが、完全に切り離されては生きていけない。リヴァイさん同様に俺にも罪はある。だからヒトは本来、大罪をシェアし合って生きるのだ。タグもランキングも入れ替え可能で明日にはもう読み替えられる。絶対と云う言葉の意味が変化したら、絶対なんて絶対に有り得ないってくらい。それくらいの自覚は持っているだろう? 何も俺の気を引かないとき書棚のあいだを歩き回っても響いてこないとき、そのために作った闇の空間で迷子になってみる。この状況は案外と気が楽だと気付いている。俺のこころのなかに有るらしき部屋にはあの頃の古城のような地下室が無い。だから俺は空っぽの部屋の下、つまりは俺のこころのなかに有るらしき部屋の地面、に、押し潰されている。もう最低限、ヒトならば持っているべき激情的な気概も荷物さえも、俺は持てない、のに。
「エレン、」
正気に戻った臆病者が、自己嫌悪と後悔で満ち満ちた声で俺を呼ぶ。それだけで俺はびくりと反射的に縮こまって耳をふさいだ。すまなかった、なんて言われたらそれこそこんなことでは、すまなかった。だのに俺の両耳は脳より優秀で、『コウモリであるとはどのようなことか』を考えようとしている頭を無視して荒くなった必死な吐息のほうを拾い上げようとするから始末に負えない。俺はコウモリじゃあ無いから飛ばないし虫を食わないし洞窟で逆さにぶら下がって寝たりもしないのだ。けれど化け物相手に優しく囁くような声音で名前を呼ばれて、切実な真摯さで今更。『エレン・イェーガーがエレン・イェーガーであることはどういうことか』──それを俺はずっと探している気がする。
「エレン、」
「ぁ…殺し、てくださ…い…今度こそ……ッへ、いちょう、」
兵長、兵長、兵長とそれ以外は全部不確かなもののように繰り返していた。酸欠でリヴァイさんの輪郭が曖昧になっていく。脳裏で兵長とリヴァイさんが錯綜し、朧気になっていく。こんなにも馬鹿なことって有るか? 俺は知らない。もうこれ以上どうしようもねえなと笑おうとしたら、目の前を黒いものが覆った。それがリヴァイさんだと理解するまでに暫く時間が掛かったのは、意識が朦朧としている上に涙で視界が滲んでいたからだ。リヴァイさん、これじゃあまるで抱き締めているみたいじゃ無いですか。言えなかったのは開いたくちの閉じ方を思い出せずにいたからだ。下半身もろ出しの情けない姿で、人類最強だった筈のリヴァイさんは正しい両腕を俺の背中にまわしてぎゅっと絞めた。やめて欲しい。俺の心臓は戦き躰がばらばらになりそうなやさしい抱擁。
「……俺におまえは殺せねえ」
乾いて掠れた風が耳の側を通り抜けて、爛れた傷口を癒すみたいに、そよ風が通り過ぎたようだった。そんな優しいキスだった。俺にもう1度ふれようとする手は躊躇しながら頼りなく、でも、ふれてしまえば力強く抱き締められる。苛立ちを抑えられずに軽蔑する。ひどい無責任さだ、化け物ひとり殺せないなんてな。体内で迸る流れは清く、指先は痙攣しそうな程気が興じているのに、この人はこの恍惚を俯瞰してふれるかふれないかの愛撫しか施さない。
「俺は、おまえに酷いことばかりを強いているな。昔も、今も」
「……はっ、そうやって、ずっと、勝手に苦しん、でろ、よ」
「帰って来い。エレン」
「…………どこへ?」
理解し難い異質な大粒の涙が、ぼろりと出た。兵長と同じく俺の切望をあっさり裏切る、この人だけがこころの底から俺を愛している。俺のこころに有るらしき部屋を破壊したがっている。無意味に無駄に、勝手に傷付いているのだから嗤える。
「ざまあみろ。──リヴァイ・アッカーマン」
稚拙な睦言に稚拙な誘い方。理解っていて、まだやさしくキスをするリヴァイさん、と、リヴァイ兵長。前世と今世を上手く行き来出来る神経は流石だとしか言い様が無い。
俺は繰り返す。吃逆しながら嗤ってこの人だけを傷付け続ける。だからはやく俺に見切りを付けて、俺の知らないどこかで、俺の知らない誰かと、勝手にお幸せにでもなれば良い。ふつうに。なのにどうしてまだ俺に執着する? それじゃあ意味が無いんだよ。『リヴァイ・アッカーマンがリヴァイ・アッカーマンであることはどういうことか』解らずに俺はまた繰り返す。
「ざまあみろ」
それでも俺を抱き締めていようとする手はあたたかで、綺麗な匂いを纏っている。そんなだから俺は『エレン・イェーガーがエレン・イェーガーであることはどういうことか』の正解にいつまで経っても辿り着けないのだ。
ねえ、あんたほんとうは、ただの馬鹿なんじゃねえの。
頼まれてもいないのに勝手に『about joker』の志麻さんへ捧げます。いや『金魚救い』の続きをね、志麻さんが書いてくださって(しかもハッピーエンドになった!)触発され『ひとり』を書いたのですが、何かしっくりこなくて…リベンジにチャレンジするぜと当時から意気込んでいました。これが私のハッピーエンドです。お納めくださると嬉しいです。志麻さんを大好き過ぎる佐藤より。
リヴァエレ前提と呼んでも良いものか不明なリヴァイとエレン/転生現パロ/前世でエレンは処刑されています/両者前世記憶持ち/援交びっちエレンから派生/モブエレ→リヴァエレ/首絞め/一応落ち着く結果に/
先にこちら→『金魚救い』→『ひとり』をお読みくださると捗ります。

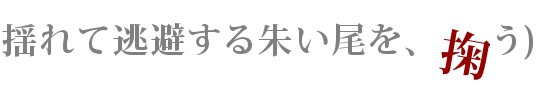
『コウモリであるとはどのようなことか』──アメリカの哲学者トマス・ネーゲルが1974年に発表した哲学の論文、及び同論文を収録した書籍である。ネーゲルはこの論文で『コウモリであるとはどのようなことであるか』を問うている。コウモリがどのような主観的体験を持っているのか=『コウモリであるとはどのようなことか』と謂う問題は、コウモリの生態や神経系の構造を調査するといった客観的、物理主義的な方法論では辿り着くことが出来ない事実であり、意識の主観的な性質は、科学的な客観性のなかには還元することが出来ぬ問題であると主張した。この論文は、心身問題の中心が意識の主観的側面(意識の現象的側面)にあることを述べた有名な論文であり、表題の問いは、よく知られた問い、または思考実験のひとつとして、現代のこころの哲学者たちの間でしばしば議論に上る。この問いに関するひとつの留意点は、ネーゲルが問うているのは『コウモリにとって、コウモリであるとはどのようなことか』という点である。つまり、この問いは人間が、例えば俺が、人間としての脳──人間の思考回路や本能を保ったまま、コウモリの躰を得て、コウモリの暮らし振りをした場合にどう感じるかを問うているのでは無い。もし、俺が人間としての脳だけを保ったまま、コウモリの躰でもってコウモリの生活をしてみたのなら『空を飛ぶことは怖い。けれどちょっと慣れると楽しい』とか、『昆虫を食べるだなんて気持ちが悪い。でも食べなきゃ死ぬ』とか、『洞窟の天井にぶら下がって眠るなんて変な眠り方だなァ。落っこちねえのかな』などと思い至ることだろう。しかし、ネーゲルが問うているのは、そうしたヒトがコウモリになった場合の感情や印象、世界の捉え方ということでは無く『コウモリにとって、コウモリであるとはどのようなことか』である。つまり、コウモリの躰とコウモリの脳を持った生物が、どのように世界を感じているのか、であった。コウモリはその特質から、くちから超音波を発し、その反響音をもとに周囲の状態を把握している(反響定位)。コウモリは、この反響音をいったい『見える』ようにして感じ取るのか、それとも『聞こえる』ようにして感じ取るのか、またはまったく違ったふうに感じているのか(ひょっとすると何ひとつ感じていないかも知れない)。ネーゲルが問うているのは、こうしたコウモリ自身の主観的経験である。このようにコウモリの感じ方、といったことを問うこと自体は容易にして可能ではある。だが結局のところ我々ヒトはその答え『コウモリであるとはどのようなことか』を知る術は持っていない、とネーゲルは言う。ネーゲルが対象とする動物としてコウモリを選んだのには、コウモリが哺乳類に属しており、系統樹のなかでは、ある程度人間に近い位置にある生物であること。とは云え同時に、翼があったり超音波で周囲の状況を把握したりと、運動器官や感覚器官に関して人間とは距離のある生物であるため、としている。つまりあまり人間に近い生物だと問題を鮮やかに示すのが難しく、かといってこれ以上系統樹を下って進んでいく(例として蜂や蟻まで行く)と、そもそもそこに意識体験があるのかどうか疑念が出てくるという難点がある。そこでコウモリという中間的な距離の生物を選んだ、としている。この論文が持った重要な影響のひとつとしては、意識の主観性の定義として『〜であるとはどのようなことか』という表現を用いた方法を有名にしたことにある。以下、論文の序盤でネーゲルが主観的な意識体験として意識を定義している部分の文章である。文献第12章『コウモリであるとはどのようなことか』──ネーゲルの論文は1974年に『The Philosophical Review』誌で発表されその後、1979年に出版されたネーゲルの論文集『Mrtal Questions』の第12章に収録される。『コウモリであるとはどのようなことか』という論文は、ほんの15ページ程の簡潔な構成であり、ネーゲルの思考内容は、その概要がごく簡素に示されているのみである。ネーゲルの主観性の問題に関する詳細な思考内容は、1986年に出版された『The View from Nowhere』にて述べられている。200ページを超えるこの書籍は、『中心を持たないどこからの眺めでもない視点』である客観と、『今、ここからの視点』である主観との間の葛藤を扱っており、そのなかで『〜であるとはどのようなことか』という題目が、この書籍のなかでは『頭のなかのこと』という表現で換言されている。ネーゲルが『コウモリであるとはどのようなことか』について、どういうことが言いたかったのかを考察することが出来る。おそらく意識体験は、宇宙全体に渡って他の太陽系の他の諸々の惑星上に、我々ヒトにはまったく想像もつかないような無数の形態をとって生じているのである。しかし、その形態がどれほど多様であろうとも、ある生物がおよそ意識体験を持つという事実の意味は一定であり、それは根本的には、その生物であることはそのようにあることであるようなその何かが存在する、という意味なのである。意識体験という形態には、これ以上の意味が含まれているかも知れない。生物の行動に関 する意味さえ(疑わしく思われるのだが)含まれているのかも知れない。しかし根本的には、ある生物が意識を伴う心的諸状態をもつのは、その生物であることはそのようにあることであるようなその何かが──しかもその生物にとってそのようにあることであるようなその何かが──存在している場合であり、またその場合だけなのである。
と、云うことについて俺の感想は、哲学者って暇なのな、とその程度のことなのだった。俺はコウモリじゃあ無いから飛ばないし虫を食わないし洞窟で逆さにぶら下がって寝たりもしない。けれど化け物の思考だって化け物にしか解らないんだろう。
誰かに言いたくて、聞いて欲しくて理解して欲しくて、でも、絶対に言えないことがある──今の俺には前世の記憶が有りそれがあまりに壮絶なものであること。次に、当時の俺と記憶を取り戻した現在の俺では性格や思考や言動が随分と違うこと。なので、誰にもバレてはいけなくて、嘘をつき続けてでも誤魔化し続けなければならないことがある──記憶を取り戻した俺にとって、この安穏とした退屈で平和なだけの世界なんてひどくどうでも良いと思ってしまっていること。平和ボケしているこの今の世界は無関心で暴力的でヒトに対して徹底的に冷たいもので、逆に、俺のほうから見た世界も、そういうものであって、所謂『社会不適合者』と呼んで差し支えない俺は、今日もこのどうでも良い、痛くて、好きなものも見付けられない世界にくるまり、のうのうと生を謳歌している。
あの夜。駅を抜けてその先にある住宅街よりもずっと向こうまで、行くと、街灯が極端に少なくなり、暗くて危うい。ので。そこまで進んでひとりになりたかった。のに。俺は結局浅瀬でぴちゃぴちゃと波に裸足を撫でられるだけでどうしてもその先へ動けずに、何も変わらぬまま自宅に戻った。そして前世の俺ではまったく出来なかったろう嘘泣きで両親に泣き付き、援助交際の事実も男と性行為をするような事実も皆無ですべてはあの男の妄想でしか無く、ストーキング被害にあっていたのだと云うことにして、ヒトひとりの人生を狂わせた。俺は今までも(多分これからも)童貞だし、と云う現実。嘘をつくコツは必ず真実を混ぜておくことだ。彼は今ストーカー犯罪者として扱われ心神喪失のため閉鎖病棟の鉄格子付きの部屋に措置入院している。別に罪悪感は全然無い。寧ろ自業自得だとさえ思う。金を払ってヒトを買う、と、云うことの意味を彼は根本的に理解っていなかったのだ。そこに愛やら恋やらが滑り込む隙間など1ミクロンも有り得る筈が無いのに。が、こちらも無傷とはいかず、俺は取り敢えず転校を余儀なくされ家は引っ越した。し、こころのケアだとかで俺は現在カウンセリングを受けている。けれどもヒトの縁と云うものは不思議なもので、小説より奇なり。ケアワーカーの職場は俺を破格値で買う上質なリピーターの──俺のこころのなかに有るらしき部屋にはドアも窓も無い、と、笑った──精神科医が開業医をしている病院だった。初めまして、なんて握手をした瞬間はもう互いに笑いを全力で堪えて、いて、もう何と言うか俺は愉快さに転げ回ってしまいそうな程で。それでも、俺のようなヒトとしての欠陥品が正気を保ってふつうの生活を送っていられる人間であるのだと擬態し生きるためには、そうなのだ、全身全霊でもってこのくだらない世界で、こんな世界に存在し受け入れられ生きている人間に、欲望のまま求められればそれに応えるという義務を、出来得る限りの高い値札をぶら下げて、果たさねばならない。そうでもしないと俺は本気で狂って、きっと無差別大量殺人でも犯してから、死んでしまうに違いない。だから──そうならないためにも俺はまだ、
「そう言えば、きみは、自分からは何も求めないね。エレン」
この人が俺を抱くために連れて行ってくれるホテルはいつも違うホテルだ。アシがつかなくて良い。まず俺と利害は一致しているし、何よりセックスのあとのルームサービスにハズレが無い。そこもこの人と寝る利点だ。俺を買う男がみんなこの人みたいなら楽なのに、と思う。思うから俺は今のところこの人以外に客を取っていないのだ。
「求める、って…何をですか?」
既に充分、躰を求めていると思っている俺はフォークに刺したオレンジの風味がかすかにするローストビーフを頬張る。
「自分だけをこころから愛して欲しいとか、独り占めしてみたいとか、そういうことだよ」
咀嚼して飲み込んだ肉が喉を通過しごくん、と鳴った。
「えー……まさかそれ本気で言ってます? そんな殊勝さがあれば、俺もう貴方とセックスするために態々こうして会ったりして無いと思うんですけど」
「そうだね。私は妻をこころから愛しているから」
「なんだ、ただの惚気でしたか」
「はは。貞淑で美しくて、穢さとは無縁の女性だから、惚気たくもなるんだよ」
「俺とは真逆ですね。そんな素敵な女性が居て何で俺なんかを愛人に選んだのか疑問ですけど」
俺が興味無さげにそう言うと、先生は、だって、と悪戯な子供のように言う。
「だって汚れたがっているきみ相手になら何だって出来るし、何だってさせられるだろう? 妻には到底出来ないことを。堪らないじゃあ無いか。きみのような美少年が、私の要望通りに縋ってくるんだよ? その顔で。その瞳を蕩けさせて。更にその上、男の夢を具現化したように全部覚えて実行してさえくれる」
そう言えば。
そう言えば、と俺は思う。まだ男同士のセックスに慣れていなかった頃、相手任せが主だった俺に優しく、騎上位のときに両手を躰より後ろについて、腰を振るのを初めて教えてくれたのもそう言えばこの人だったなァ、と。
「お陰さまで。商売繁盛でしたよ」
「綺麗だったものが、汚れていくのを見るのは楽しいよ。それも私の思い通りに。育てると云う行為は単純な性行為より、ずっと楽しい。上手く育ってくれたら嬉しくなる」
「へえ。先生は俺と寝て嬉しいんですか」
「当然だろう、嬉しいさ。何より、繰り返すけれど、愛する妻にはとても出来ないことが出来るんだ」
「でもコレ浮気ですけどね」
「浮気? とんでもない。浮気なんかじゃあ無いさ。本気でも、無いけれど」
そうして立ち上がった先生に腕を引かれる。
「よくわかりません」
「もっと大人になれば理解るようになるよ。若しくは、きみがこころから“愛して欲しい”と思える誰かと出逢ったなら」
愛して欲しい? 『コウモリであるとはどのようなことか』をわからないように、ほんとうの愛を知らないまま何が愛なのかも俺にはわからないのに?
そうこうしているうちに再びベッドへと招かれた。先生の笑みはやわらかく、優しい。いつもそうだ。することは結構えげつないくせして、俺にふれる指や手のひらはあたたかい。いつもそうだ。いつも。
「……っふ、」
甘やかなキスを受けながら俺は考える。だったら、貴方が俺を、躰だけじゃ無く愛してくださいよ。言ってみようか。言わなくとも、言っても無駄だとそれだけは理解出来る。だってこの人にはちゃんと愛している人が存在するのだ。且つ、俺は空っぽで何も無い。何も持たない──そう決めたのは、誰でも無い、俺自身だった。 俺は俺のこころのなかに有るらしき部屋とやらから摩耗した愛憎を放り投げ、棄てて、そしてそれは奪われ削られていく。
「きみはもう少し自分の価値を把握したほうが良いよ」
「充分しているつもりですけど」
「なら、もっと、」
「“自分を大切にしたほうが良い”?」
「よく解ったね」
「言われ慣れているので」
「それでいて私に抱かれたがるんだから、矢張りきみは可愛いよ。愚かで」
「こんな躰、幾らめちゃくちゃに汚したって、」
それ以上は言葉にしなかった。気持ち悦ければそれで良い。俺を抱くこの人の腕のなかはひどく気持ち悦く俺を穢し、あの夏の日にめちゃくちゃになってしまった俺を、まるでこの退屈な世界にとどめるかのように、めちゃくちゃにしてくれる。俺はぼんやりと、しかし急かすようにも、俺の躰を組みし抱く男の躰を見ていた。筋肉の薄さは俺と大して相違無く、背の高さだけほんの少し、俺のほうが劣っている。肉欲と焦燥に駆られた大人の雄の双眸が俺を見詰めている。羽織っていたバスローブがばさり、落ちる音がして、あァもう焦れったい程に、俺は叫びだしたいくらいの安堵感に満たされてゆくのだった。
◆
燃えるような赤い色をした夕焼けが眩しくて、足許に広がる黒い影を踏み締めている。化け物だから逢魔が時も怖くない。雑踏のなか、どこか遠く聞こえる赤の他人の声やいろんな音がすべてノイズとして響いて、無感動な俺の脳髄に沁みては蒸発していく。どこへ? どこかへ。俺の知らないどこかへ。正体を消せば、風の音がよく聞こえる。正体を知られれば、誰とも視線はもう交わせない。すっかり熱が冷め倦怠感だけが残る躰を引き摺るようにしながらも、人混みを避け車道側ぎりぎりの歩道を歩く。途端それを見計らったかのように歩道側へと寄せて来た車がクラクションを鳴らしたので、うるっせえな、と見遣れば、その高級車の運転手が見覚えの有り過ぎる人物で、俺は反射的に顔を顰めた。
「…………何で居るんですか。俺にGPSでも付けてんですか」
まじで。真面目に怖いんですけど。何なんだろうかこの人は。
「リヴァイさん」
と、俺は嫌悪感たっぷりにその人の名前を口にした。リヴァイさん。リヴァイ兵長。俺にXデーを齎した諸悪の根源とも云える。
「乗れ。エレン」
前世では散々関わり深かったのでもう今更また関わりたくないのはきっとお互い同じであるだろうに、リヴァイさんは命令口調で俺を呼ぶ。その声は確かに俺を咎めていて、面倒臭い。
「やですよ…ご用があるならそこでどうぞ」
俺はいっそ投げやり気味の調子で言い、全開にされた窓から身を乗り出さんとするリヴァイさんの、目付きの悪い顔に隠すこと無く溜息をついた。そんな声で咎められずとも用件など殆ど理解っている。その証拠にリヴァイさんの瞳はいつに増して鋭く、俺を冷たく睥睨していた。外気はちっとも冷たくなんて無いのに、俺とリヴァイさんの間を漂う空気は凍りそうな程冷たくて、張り詰めてさえいるのだ。
「良いのか? 外で話しても。俺は一応おまえのプライバシー保護のために、車に乗れと言っているんだがな。なァ? エレン」
不自然な程にきっちりと閉められた制服の襟を捕まれ、あんたにゃ関係ねえだろとも思いつつ、リヴァイさんの手を払い除け、助手席側へとまわった。
俺はリヴァイさんの車に乗り込む。最早どうでも良かった。いつものことなのだ。この人に見付かったら、俺にはどうしようもない。目を閉じて開けたら世界や記憶が変わる魔法なんかどこにも無い。
「いつになれば諦めてくださるんです? ストーカーですか、貴方は」
「誰がストーカーだふざけんな。おまえこそ、いつになりゃあ懲りるんだ」
「最近は漁ってまーせーんー」
「馬鹿言え。穢え雄の匂いがぷんぷんするんだよ」
「そりゃまァ、今してきたとこですからねえ。でもちゃんとお風呂入って来ましたよ? 始める前に1回とルームサービス前に1回、最後に部屋から出る直前にもう1回。ほら、3回も綺麗にしてます」
「結果2回に分けてセックスしてきたんじゃねえか」
不快げにそう言い放ったリヴァイさんは再び俺の襟首を掴み、引きちぎられるかと思う程の乱暴さで俺の制服をはだけさせた。鎖骨の上辺りから胸にかけて、夥しい量の鬱血痕、が、顕わになる。
「ちょ、いきなり何するんですか。セクハラですよリヴァイさん。訴えますよ」
慌て制服を握り締める俺にリヴァイさんが溜息をつく。
「それで崩壊したんだろうが……おまえんちは…──」
「それこそ貴方に関係ない話でしょう」
「…………隠れねえ部分にも付いてるぞ。耳の下、首筋と。…喉には、何だそれは……噛み痕か?」
「うわ」
あァまた今日も家に帰れない。けれどそれはもう疾うに決まっていることでもあった。もっと言えばあの夏のXデーから。異物で化け物の俺に居場所など無いのだ。現在の新居だって転校だってカウンセリング通いだって勘違い野郎への措置にしたって、それは傍目には態々明るみにしない限り何の問題も無い家庭に見えるのだろうが、おまえの話を聞く前に怒鳴りつけて悪かった、と謝ってくれた父も、怖い思いをしていたのね、と泣いて抱き締めてくれた母も、それらはどこか義務染みていて、今や食卓ですら俺と彼らとの会話は無い。沈黙。ただただ重苦しい空気が漂っている。俺が家を空けようと何も言われない。矢張り俺はあの家での異物であるのだ。歩み寄れないのは仕方の無いことだ。俺だって、俺に、歩み寄れないのだから。でも同じ顔で同じ声で、それでも前世の両親を知っている俺としては、幼い俺とミカサを逃がし巨人に喰われた母さん、大切なものを救えと自らの命を捨て俺に喰われてまで俺を巨人化する生き物にした父さん、そんなふたりとは掛け離れている現世の平和さと比べて、比べても意味が無いのに比べてしまう俺は、俺自身も前世の自分とは掛け離れていることを棚に上げて、この世界は無関心で暴力的でヒトに対して徹底的に冷たいものであるのだと、そしてその逆も然りと諦めてしまった。にも関わらず、この人は──兵長じゃあ無いただのリヴァイさんだけはこうして執拗に未だ俺を見付ける。正直なところ、鬱陶しいし邪魔なので諦めて欲しいと本心から思うのだけれど、俺が切り売りする俺をただひとり悼んでいる。部下だった俺を。現在の俺を。矛盾だらけで叱り飛ばす。そんな権利は、リヴァイさんだけには絶対に無い筈であるのにだ。
「身売りはするなと、何度言わせれば気が済むんだ」
そう、こんなふうに。
「回数なんか疾っくに数え忘れました」
「相変わらず出来の悪ィ頭だな」
「よ、く、言、う。貴方がそんなこと言えた義理ですか兵長」
「だから俺はもう兵長じゃねえ。何回言わせる気だ」
「う、……っぜええ。死ぬまで勝手に言っててください。つうかはやく死んでください」
こういう遣り取りも最早幾度めになるのかわからない。兵長は死なないしリヴァイさんも死なないのだ。そして別に何かをして欲しいわけじゃあ無いが、何ら贖罪もしない。
「俺に構うってことは今夜だけで良いので泊めてくださるってことで構いませんか」
「どこに」
「どこでも。リヴァイさんの部屋でもホテルでも。何ならこの車のなかでも良いですよ。こんな歯型付けたまま、俺は自分ちに帰宅出来ないんで。無理なら下ろしてください」
「それでその足で泊めてくれそうな男を探すんだろう」
「他にしょうがないでしょ。だって独りぼっちは寂しいですもん」
「……チ、」
リヴァイさんの舌打ちと同時に車が発進しどこかへ向かう。おそらく駅近のホテルだろうな、と俺は思っていたのだ。なぜなら今世の俺は平気で嘘と肌を重ねられる穢らわしい生き物だから。リヴァイさんにとって俺は生ゴミみたいなものなのだ。そして潔癖なリヴァイさんは決して自宅へ生ゴミを持ち帰らない。その筈だった。なのに車が入った駐車場はホテルでもどこでも無く、て。
「……どこですかここは」
「マンションだ」
「いやそんな見りゃわかることは訊いてませんけど」
素直に謂って俺は思い切り驚愕していた。このタワーマンションの1室にたぶんリヴァイさんの部屋が有るんだろう。けれど。えー……生ゴミ持ち帰るんだ、この人。みたいな気分で呆然となる。そんな俺の頭を軽くはたいたリヴァイさんは言う。
「何を呆けてやがる。さっさと車から降りろ」
「え。あ。はい?」
「はやくしねえと置いて行くぞ」
「いやいやいや、車中泊では無く?」
「は? 何で態々そんなことをさせるんだ。風邪ひくぞ。ふつうに俺の部屋で良いだろう。ほら、着いてこい愚図」
ええええ? もう俺は何が何だかわけがわからなかった。それでも仕方無くリヴァイさんの後ろを着いていく。カードキーで開けられたお高い部屋に連れ込まれて、あァもうこの部屋リヴァイさんの匂いでいっぱいで、すげえ腹立つ。とか現実逃避的なことを考えてぼおっと、スーツを脱ぐリヴァイさんの背中を見ていた。少し、面白くない。見た目は低身長で、服の上からではえらく華奢みたいな印象なのにも関わらず、ふれてみればこんなにも差がついてしまうことが未だ成長中ながらに面白くない。こんなん、肩とかどうやったら筋肉つくんだよ。さわわ、無意識にふれた肩はそろりと伸ばされた腕と連動し、手のなかで動く。
「おい。さわるな」
「いいじゃないですか別に。減るものじゃ無いし。筋肉、こことここもどういう鍛え方すりゃあつくんですか。どういう構造でこんなんなるんですか」
さわさわ。リヴァイさんの筋肉をあちこちさわる。
「やめろ。減る。穢らわしい」
「ふうん。リヴァイさんも、俺みたいな精液便器相手に勃つんですね。いやいやまさか。淫乱変態野郎と俺を罵る貴方が!? って話ですよ。それともそれって、男の頭と下半身は別物ってやつですか。ふんふん。ちょっと面白いですね」
悪趣味な笑みで笑うな、と言われたことを思い出して、目一杯笑ってみせた。立っているリヴァイさんの前に跪き、膝立ちになる。スラックスの布越しに指でなぞり、それが縫い目まで辿り着いたところで掬い上げるように下から上へ直線を引けば、過剰な分泌による唾液を嚥下した、俺の喉が細く鳴った。跪いた俺の目線の先、存在する、その両腕も両脚も、誰も何ら拘束なんかしてはいない。貼り付けた深い笑み。蠱惑的に歪むそれを前にして、俺の手を払うことも後退り離れることも、それより何よりその手で刃を抜くことすら自由な筈の、目前のリヴァイさんはただ直立不動で動かない。継いでベルトの金具に手をかければ、流石にまずいと云わんばかりにリヴァイさんの手のひらが俺の手を覆った、が、けれどそんなささやかな仕草が抵抗になどまるでならないことを、抱いた女の数も数えられないだろう歳であるリヴァイさんには、よく理解っているに決まっているのだ。ベルトを外し、ボタンを外し、ジッパーを下げる俺の手が、微塵も震えていないことに、リヴァイさんが気付かぬ筈が無い。上目遣いで合わせたネイビーブルーの三白眼は、泳いでさえいなかった。
「こんな化け物にも欲情出来るなんて、リヴァイさんも充分変態ですよ」
出来得る限りいやらしく見えるよう、にやりと笑って床に膝をついているそのままに、俺はリヴァイさんのペニスを銜えた。別に初めてする行為でも何でも無いが今くちにしたそれは、味がどうだとか匂いがどうだとか何とか云うより先に、俺の喉奥を刺激して、反射的に嘔吐きかける。そうして俺は漸く、ああ、今自分は吐き気を催すような醜悪なる行為を行っているのだと気付き、ますます吐き気が増して気持ちが悪くなった。おそらく俺の頭を叩き飛ばそうとしてぶつかってきたリヴァイさんの手が、髪に触れたところで思いとどまった。俺の喉が、口内に溜まった唾液を嚥下すれば、はずみでそれを刺激したのか、くちのなかでぴくりと震えた。歯を立てないように唇で挟んで舌を動かしてみる。俺は何の自慢にもならないが性交に手慣れてはいる。それだけを思ってくれれば良いと俺は思っていた。困惑しているのは自分だけだと、頭のおかしい蜂に刺されたんだと、一生思っていれば良い。舌に力を込めて這わせる。先のほうを何度も舐める。俺の舌が動く度に、大きな手のひらが、長くて節くれだった五本の指が、俺の髪の毛をかき分け頭を押さえ込む。
端から見たら感じているように、そうして互いを愛おしんでいるように、見えるだろうか。
しかしリヴァイさんにはきっと理解っている。俺が上を見るのを拒絶している。見上げた俺と視線が合うのを、リヴァイさんは己の股間に顔を突っ込み性器を銜えている俺の顔を直視するのを拒絶している。殆ど無意識に俺はリヴァイさんを、リヴァイさんは俺を、躰で拒絶している。本能で拒絶している。本能はいつだって絶対的に正しい。特にリヴァイさんのほうは。だから、俺が拒絶されぬ道理はない。おえっおえっとおおきく2回程嘔吐き口内のペニスを吐き出しそうになりながら、頭を押さえ付けられて息を吸うことさえ出来なかった。俺の感情とはまったく無関係に涙がぼろぼろ湧いて出て、このまま窒息してしまうと思った。リヴァイさんに殺される。それは恐怖では無かったけれども、でも、欣幸なんかでも無かった。喉の奥を圧迫していたものが急に消え、くちのなかが涼しくなり、俺は何が起こったのかをうっすら理解した。糸を引く白濁を何だか生き物の尾みたいだと思った。精液なんて幾らでも出せるもんな。目の前でニヤニヤ嗤って飲み込んでやろうか、それともそのご清潔な顔に吐きかけてやろうかと考えていたのに、実際には開いたままのくちの端から涎といっしょにどろどろとこぼれ出てしまった。下半身のほうさえ思うように出来ないなんて、これはちょっと間抜けだな。勝手に出てくる涙は止まらないし、開いたくちは塞がらないし、涎と精液の混合液は制服の襟からなかに入って胸の真ん中を伝っていく。
確かに俺はこの人に今まさに欲情していたし、率直に言ってやりたいと思っていた。それは認める。認めるけれど、何だこれ。リヴァイさんは何をとち狂ったのか俺の胸倉を掴み強引に立たせると、乱暴な、噛み付くようなキスをする。なのでそれに便乗し、態と水音を立て、こちらからも舌に噛み付いてやれば、嫌そうだったネイビーブルーの瞳孔がぐうと開き、雄特有の妖しい色気が滲み出す。俺がのりだしてきたところで、リヴァイさんは唇を1度離した。見ると、まだ物足りない、とでも云うふうに、リヴァイさんは唇を垂れる唾液を舐めている。
「もう終わりか?」
爛々と光る、熱を孕んで潤んだ目で、挑発するリヴァイさんを見詰めた。先程とはまるで別人のようだと思った。途端、リヴァイさんは口角を歪めると、俺の脚を蹴って、そのままフローリングに転がした。痛い。熱くてぬるぬるした何かが首の横を上下している。リヴァイさんの舌だと気付いたときにはもう遅かった。偶に耳を掠める息が温くて荒くて、リヴァイさんは本気なんだなと、漸く思い至った。男の俺──ばかりか国家予算以上の金を積まれても汚ねえ精液便器なんざ欲しくない、とか何とか、いつぞや吐き捨てたこの人が、本気で俺に欲情するなんて、どうかしているんじゃなかろうか。とか、唖然としていたらいつの間にか襟がおっぴろげられていておおきな手の平が這っていく。さっきまで鼻についていたリヴァイさんの清潔で潔癖な洗剤の匂いはどこかに消えて汗臭さにくらくらする。その手はあちこちが硬く盛り上がっていて、それが胸の辺を擦る度に俺のくちから勝手に、は、とか、ん、とか息が漏れた。太ももの内側に指が触れて、反射的に両足の爪先が跳ね上がった。そこからは、もう、駄目だった。気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い何だこれ何だこれ何されてんだ、頭のなかはそんなふうでいっぱいなのに、俺の唇は、はんはんAVみたいな声を出し続けるし、躰はぴんぴん跳ね上がる。あのネイビーブルーの目がくっつきそうな程そばで俺の目玉を覗き込んだとき、初めて怖くなった。視界いっぱいがあの目で覆われて、逸らす逃げ場さえ無くなった。あ、犯されるんだ、と思った。この人は本気で俺と『セックス』する気なんだ。神様たすけて。今まであんたにかけた願掛けは全部撤回します神様。俺に正しく発情するような、そんなリヴァイさんは要らない。自分の声を聞きたくなくて、俺はずっと──丁度、親指と人差し指の付け根あたりを噛んでいた。だけど巨人にはなれない。リヴァイさんはそのまま俺の躰に馬乗りになって首を絞めるように俺の喉へ手を添える。と、俺は何だか、この期に及んで何かを期待しているような気分が浮上してくる。
「っ、ぁ、」
ぎりぎりとヒトの手垢がついた俺の喉をリヴァイさんが絞めると、俺の口端からは短く細切れになった息が押し出される。俺の双眸はもっと潤み、きっと色が濃くなっている。酸素が遮断される感覚に苦しみながらも、リヴァイさんの手を掴む俺の指には、殆ど力がこもっていない。俺は幻覚を見ている。慢性的な低酸素症によって齎される幻覚状態に関して、確か、ロイド博士は登山者が高地で経験する幻覚と類似している点を挙げていた。彼は更に、そのような状態は高高度での航空機の急激な減圧によって齎される低酸素症では引き起こされないことをも注記した。これらの調査結果は、酸素の欠乏のみが興奮の増大に至らせる要因であるわけでは無いことを示唆していた。そこで低酸素症の研究について調査したところ、『脳の神経化学の異常が相互に連結した神経伝達物質であるドーパミン、セロトニン、β-エンドルフィンのうちひとつ以上を含んでいることが、幻覚と関係したすべての状況で報告されている』と謂うことを発見したのである。と脱線せざるを得ない程、俺は今アホ面を晒しリヴァイさんとリヴァイ兵長を重ねて見ている。良くも悪くも、この人は何にも変わっちゃいないのだ。
そうして漸く約束は果たされるのだろうか。そう思うと愉楽的な思いが嬉々として込み上げて、俺は無意識的に薄く笑っていた。
「ぁ……っは…」
「悦がるなよ。エロガキ。死ぬぞ」
「……そ、の……変……態、の、エロガキに…っ、惚れ、てるんでしょ…う…?」
「………よく解ったな」
まったくもってお互いにイカレている。俺もリヴァイさんも、互いに狂気じみた笑みを浮かべた。リヴァイさんは首を絞めたまま、俺の唇にキスを落とす。俺の手が、リヴァイさんの背にゆっくりと回された。ゆっくり──脆く大切な何かをそうっと掬いあげるように──それを愛だ何だと云えば美しいだろう。だが、そう云えないからこそ、胸の内側で淀んで粘つく想いは苦しく不快だった。呪いより滑稽で酷い、運命劇場の終演に、俺はもうこれ以上何を棄てれば良いのかが解らない。世界なんてどうでもいい。他人に好かれる努力も、値札もいらない。生きていくことすら──どうでもいい。だから今日も欠陥製品たちは、世界を横目に笑っていられるのだ。どうせ全人類何らかの病気だろう。これでは告白と言うよりも告解だなと自嘲する。世界は意地悪だが、完全に切り離されては生きていけない。リヴァイさん同様に俺にも罪はある。だからヒトは本来、大罪をシェアし合って生きるのだ。タグもランキングも入れ替え可能で明日にはもう読み替えられる。絶対と云う言葉の意味が変化したら、絶対なんて絶対に有り得ないってくらい。それくらいの自覚は持っているだろう? 何も俺の気を引かないとき書棚のあいだを歩き回っても響いてこないとき、そのために作った闇の空間で迷子になってみる。この状況は案外と気が楽だと気付いている。俺のこころのなかに有るらしき部屋にはあの頃の古城のような地下室が無い。だから俺は空っぽの部屋の下、つまりは俺のこころのなかに有るらしき部屋の地面、に、押し潰されている。もう最低限、ヒトならば持っているべき激情的な気概も荷物さえも、俺は持てない、のに。
「エレン、」
正気に戻った臆病者が、自己嫌悪と後悔で満ち満ちた声で俺を呼ぶ。それだけで俺はびくりと反射的に縮こまって耳をふさいだ。すまなかった、なんて言われたらそれこそこんなことでは、すまなかった。だのに俺の両耳は脳より優秀で、『コウモリであるとはどのようなことか』を考えようとしている頭を無視して荒くなった必死な吐息のほうを拾い上げようとするから始末に負えない。俺はコウモリじゃあ無いから飛ばないし虫を食わないし洞窟で逆さにぶら下がって寝たりもしないのだ。けれど化け物相手に優しく囁くような声音で名前を呼ばれて、切実な真摯さで今更。『エレン・イェーガーがエレン・イェーガーであることはどういうことか』──それを俺はずっと探している気がする。
「エレン、」
「ぁ…殺し、てくださ…い…今度こそ……ッへ、いちょう、」
兵長、兵長、兵長とそれ以外は全部不確かなもののように繰り返していた。酸欠でリヴァイさんの輪郭が曖昧になっていく。脳裏で兵長とリヴァイさんが錯綜し、朧気になっていく。こんなにも馬鹿なことって有るか? 俺は知らない。もうこれ以上どうしようもねえなと笑おうとしたら、目の前を黒いものが覆った。それがリヴァイさんだと理解するまでに暫く時間が掛かったのは、意識が朦朧としている上に涙で視界が滲んでいたからだ。リヴァイさん、これじゃあまるで抱き締めているみたいじゃ無いですか。言えなかったのは開いたくちの閉じ方を思い出せずにいたからだ。下半身もろ出しの情けない姿で、人類最強だった筈のリヴァイさんは正しい両腕を俺の背中にまわしてぎゅっと絞めた。やめて欲しい。俺の心臓は戦き躰がばらばらになりそうなやさしい抱擁。
「……俺におまえは殺せねえ」
乾いて掠れた風が耳の側を通り抜けて、爛れた傷口を癒すみたいに、そよ風が通り過ぎたようだった。そんな優しいキスだった。俺にもう1度ふれようとする手は躊躇しながら頼りなく、でも、ふれてしまえば力強く抱き締められる。苛立ちを抑えられずに軽蔑する。ひどい無責任さだ、化け物ひとり殺せないなんてな。体内で迸る流れは清く、指先は痙攣しそうな程気が興じているのに、この人はこの恍惚を俯瞰してふれるかふれないかの愛撫しか施さない。
「俺は、おまえに酷いことばかりを強いているな。昔も、今も」
「……はっ、そうやって、ずっと、勝手に苦しん、でろ、よ」
「帰って来い。エレン」
「…………どこへ?」
理解し難い異質な大粒の涙が、ぼろりと出た。兵長と同じく俺の切望をあっさり裏切る、この人だけがこころの底から俺を愛している。俺のこころに有るらしき部屋を破壊したがっている。無意味に無駄に、勝手に傷付いているのだから嗤える。
「ざまあみろ。──リヴァイ・アッカーマン」
稚拙な睦言に稚拙な誘い方。理解っていて、まだやさしくキスをするリヴァイさん、と、リヴァイ兵長。前世と今世を上手く行き来出来る神経は流石だとしか言い様が無い。
俺は繰り返す。吃逆しながら嗤ってこの人だけを傷付け続ける。だからはやく俺に見切りを付けて、俺の知らないどこかで、俺の知らない誰かと、勝手にお幸せにでもなれば良い。ふつうに。なのにどうしてまだ俺に執着する? それじゃあ意味が無いんだよ。『リヴァイ・アッカーマンがリヴァイ・アッカーマンであることはどういうことか』解らずに俺はまた繰り返す。
「ざまあみろ」
それでも俺を抱き締めていようとする手はあたたかで、綺麗な匂いを纏っている。そんなだから俺は『エレン・イェーガーがエレン・イェーガーであることはどういうことか』の正解にいつまで経っても辿り着けないのだ。
ねえ、あんたほんとうは、ただの馬鹿なんじゃねえの。
頼まれてもいないのに勝手に『about joker』の志麻さんへ捧げます。いや『金魚救い』の続きをね、志麻さんが書いてくださって(しかもハッピーエンドになった!)触発され『ひとり』を書いたのですが、何かしっくりこなくて…リベンジにチャレンジするぜと当時から意気込んでいました。これが私のハッピーエンドです。お納めくださると嬉しいです。志麻さんを大好き過ぎる佐藤より。