途中で文章が切れる方は→こちら
<概略>
リヴァエレ/監禁/血表現・嘔吐表現有り/微妙なグロとカニバ/
鬼畜、SM、DVだけが痛い愛では無いと証明しようとしてラブくなりました。

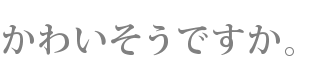
何に迷うか決まらない。迷いたいとは思っているのだが、何に迷おうか決まらないのだ。エレンはずっと己が尖ったふりをしてきた自意識があった。その実なまぬるく、我儘で、脆く頑固で、泣き虫で、半端な破壊願望に捕われて。そうでも無ければ生きられないと思い込んで今まで生きた。だから証明出来ない。エレンは今日もエレン自身を欺いているのかも知れない。証明され得ない。だからエレンは昨日エレン自身を死なせたのかも知れない。
「生きたいと言え」
なのでリヴァイにそう命じられたそのときエレンは、特に何の他意も無く、はァと濁して、曖昧に頷くことで流した。生きたいです、とは言わなかった。それが然こそ劣等であったのかも知れない。おそらく最後の壁外調査となる──壁外に居る巨人と直接闘うのはこれで終わりになるだろうという意味で──予定されている作戦は巨人化したエレンを餌に、群がる残り少ない巨人たちを一斉討伐すると云うもので、即ちエレンはいつかの如く足止めと生きたまま彼ら巨人たちに喰い尽くされる重要且つ不可欠な役を担うことになる。無論104期生を始めとする決して少なくは無い仲間である兵士たちからは非難の声があがったが、エレンはただ、永く続いた仲間たちの命の遣り取りが取り敢えず漸く落ち着くだろうことのほうに晏然としており、来たる作戦執行の日を前にして、あと何日くらい生きていられるんだっけ、と指折り数えながら平静的に日々を過ごし、憧れ敬愛し続けてきた兵士長に、部下として命の最期に何か、ひと言ふた言で良いので言葉を掛けて欲しかっただけであったのだ。兵士として生きて死ぬ者たちの左胸に心臓が無いようにエレンの左胸はがらんどうで心はどこにも無く、どこにでも有る。それが躰のなかの、どこであるのかがわからない。誰にも心臓を捧げぬリヴァイとは違いエレンの心臓はエレンのものでは無いのだ。人権も尊厳も根刮ぎ失って日々を経てきた今になり、何がどうしてこうなったのかと。誰も彼も拾うより手放す瞬間を快感と感じるよう造られた筈だった。
一見鋭利さだけが目立ち解り難いがよく見れば深く優しい色をしているリヴァイのネイビーブルーの瞳を覗き、そこに有るべき厳しさを求めたエレンにはリヴァイが何を考えているかなど考えもしていなかった。し、エレン自身、自分でも自分が何を考えているかをいまいち理解していなかったのだ。それにまさか規律も指示も約束も律儀な程に守り通すリヴァイが、このような謀反的とも呼べることをするとはまったく思い付きさえしなかったのである。
と云うわけで、エレンは己の命日になる筈であった日を、旧本部の古城でも無く無論調査兵団本部や審議所でも何でも無い、いったいここはどこなのか心当たりも無い、見知らぬ薄暗い地下室で迎えた。土壇場で起きたエレン・イェーガー失踪事件。兵士としてこの上無く不名誉なことに幾ら尖り吠えてはいても所詮齢15の少年兵、怖気付いたエレンによる逃亡かとも思われたそれをエレンは知り得ない。だが勿論それは、断じてエレンが自ら望み選んだわけではまるで無かった。死ぬために壁外へ行くのでは無い、救うために死ぬのだと、その前日、各兵団を掌握している上層部による温情によって、丸1日もの休息日となった。最期の。準備を終えたエレンはリヴァイの執務室へと自然に脚が向き最期の言葉を強請った、そんな殊勝なるエレンの後頭部を首ごと刈り取る勢いで蹴り上げて、昏倒させ、エレンを攫い拉致したのは兵士長たるリヴァイその人であったのだからエレンにはわけがわからない。
繰り返すがリヴァイという男はそれが如何に非人道的であったとしても、果たして自身が納得のいくものであれば、例えそれが最愛の恋人や妻子を殺す結果になろうと迷わずブレードを翳し振り下ろす男である。ましてやエレンはリヴァイ直属の部下には違いないが同じく生死の腹を括っている調査兵団組織の兵士なのだ。恋人でも無ければ妻子でも無く、生き別れで出逢った弟なぞと云うオチも無い。ただ性的な躰の関係ならば持っていたが。それも皆目、甘やかな逢瀬では無く時々互いに性欲を発散するためだけの、自慰行為の代用に過ぎぬ、単にそういうものだった。上官と部下で在りながら、監視役と監視対象で在りながら、ふたりがそういうことをする間柄になったのは、丁度ペトラたちの居た精鋭リヴァイ班が壊滅してしまってからだ。正確には思い出せない。それでいて丁度、などと云えるのはそれがいつまで経っても泣きやまぬエレンが、彼らの遺品をせめて遺族へ届けられるようにしたいとひとつひとつ大事そうに握り締め整理しながら、目を伏せる度に蜂蜜色の双眸を隠す、瞼を、真っ赤に腫らしていた介然たる姿に、リヴァイのほうが我慢ならなかったからであった。どう考えても真っ当では無い。けれどもそんなことを言い始めれば、真っ当かどうかなど引っ繰り返せば左右も前後も容易く変わる盤上の正義と均しく、どうでも良いことでは無いのかとリヴァイには思える。ひとりにつきたったひとつ限りの命を犠牲にすることが、それで大勢の人類の未来のための礎と成ることが、尊いだなんて戯言を、自らの命さえ賭けもしないで、誰が決めた。かたく信頼を寄せた最早数え切れない部下たちや仲間たちが無惨に殺されていくのが赦し難くて、巨人の正体が人間であったと解ってからも殺戮をやめなかった。殺戮は日常とイコールに、調査兵団に入団するよりずっと以前から、それこそ物心がつく頃からリヴァイの手は殺戮による穢らわしい返り血でいつも汚れていた。何れ程丁寧に洗い拭っても拭っても、それはずっと纏わりつく。おそらく死んでも。だから1番手近に存在し、1番死に急いでいるが1番この世界で、敵からも味方からも欲され必要とされ、つまり、1番死にそうに無い子供をリヴァイは自らの傍らに置いて寝るようになっていた。手っ取り早く。易きにつきて。そういうことであるのであれば、そういうことで良いと、エレンはすんなり受け入れた。互いにとって大切なのは、なるべく死なないものが寄り添うと云うことだけ、それに尽きた。だがそれは思うより意義深かった。その点では互いに幸いにも、相手を、1番手近な、1番、殺しても死ななそうなものだと、同じことを考えていたわけである。しかしながらまだ多少暴走気味に突っ走る傾向が有るエレンは、追い詰められると何を仕出かすか予測しづらい。とリヴァイは思っていたのだが、存外、癇癪を起こすことも無く、エレンはあくまでエレンだった。
「…あの。兵長」
エレンは上官であるリヴァイが手ずから整えた清潔なベッドの上で、両手を後ろ手に束ね碌に身動き出来ぬ状態でそれでも尋ねる。自由に動かせない。動けない不自由。ベッドの足許へと伸びている長い鎖がじゃらんと哭くがそこに繋がれているエレンの首輪はきつく締められてはいないので、然程、見目程の息苦しさは無い。寧ろ態々首周りを測り誂えたかのような剴切さだった。
「兵長、兵長、兵長って、」
「…うるせえな。何度も呼ぶな。何か用でも有るのか」
「用…っていうか……ええと…俺も躾覚悟で、失礼ながら申し上げますが。兵長、今、頭の悪い俺から見ても、残念過ぎるくらい、すっげえ頭悪そうなんですけれど。まるで悪夢でも見ている気分です」
ベッドに腰を掛けながら脚を揺らしているエレンの顎先を、未だ反抗期を脱していないエレンよりもずっと長くも過酷なる、道無き道を闘って進んできたのだと触れるだけで理解る、リヴァイの節榑立った無骨な指が緩慢に、丁重に、つうと撫でる。
「……あァ、残念なことに、俺自身、そう思う」
その言葉にエレンは悲しい程はっきりと蜂蜜色の瞳を攪動させた。その理由さえリヴァイにも理解りきっていた。
「でしたら。いつもの、聡明でつよくて、実は情に厚く巨人討伐は勿論、あらゆる才能に溢れた人類最強兵士であるリヴァイ兵士長に、はやく戻ってください。お願いですから」
「は。誰だそれは」
「貴方以外にそんな超人が居るわけ無いでしょう、兵長。ていうか兵長は、作戦において団長の判断には全面的に従うんじゃあ無かったんですか」
だがエレンはリヴァイが成し遂げた努力を悉皆にも知らず、リヴァイはリヴァイで何も説明さえしていない──しないでいられる限りはしたくない──ので、似合わない仏頂面をしたエレンから不満顕わに問われるのは仕方が無い。エレンは長い鎖で繋がれベッドの脚に結わえつけられている首輪の先を如何にも億劫そうに蹴っている。
「エレン、顔を上げろ」
「別に俺、俯いていませんが」
「違え。俺の顔を見上げろっつってんだ。クソガキ。目ェ逸らしてんじゃねえよ」
「……Jawohl , Herr Levi」
イエッサー、リヴァイ殿。
態と嫌味を込め恨みがましく、敢えて上官命令に従う部下らしく応えたエレンの逃れられない唇に、溜息をつきそれでもリヴァイは口付ける。ただのバードキスでは無い。舌を捩じ込み割った歯列の裏側から頬裏の粘膜までこそぐような、あついディープキスだった。それは旧本部の古城にてセックスに及ぶ際でも、そうそう滅多に落とされた覚えもあまり無い、喰いつくような口付けだ。途端狼狽するエレンにそのまま腰を押し付けてきたと思ったら押し倒され、そうやってリヴァイはエレンの躰の上に乗りかかり、らしくも無く非常に退廃的な表情でぐしゃりと皺になる程乱暴な仕種で自分のスカーフを握って引き抜く。
「えっ…兵長?」
警戒もせず呼び掛けながら、エレンは、やべえどうしようこれは本格的に兵長まじなんじゃねえのかよ、と思い痩身を強張らせた。まさかと思いたくも無い悪い予感が頭を過る。兵長は本格的に団長に──ひいては調査兵団や人類すべてに背いて俺を監禁するつもりなのかも知れない、と。
「そのクソ生意気な口は、幾ら躾けてやろうがいつまで経っても覚えが悪ィな。おい、エレン」
「はっ、…なっン、っ……ん、んぁ、あっふ……兵、長っ!」
深い口付けに気を抜けば意識を奪われてしまいそうなさなか、あれ? ちょっと待てよ、まじでこの人ほんとうにリヴァイ兵長なのか? 俺の知っている兵長で合ってんのか? 実は兵長のそっくりさん、とか、馬鹿か俺はこんな人が他にも居て堪るか誰だあんた。ふと、だがエレンはわりと真剣にそう思った。だって今までに及んだセックスは、いつも、どのようなときも、エレンが耐えきれずもう無理ですと泣いて拒まざるを得ない程度に、リヴァイは戦闘時と同様、発情すれば遣り過ぎるきらいはあったのだけれども、エレンの見てきた上官としてのリヴァイは地下街出身ゆえにまともな教育を受ける機会が無かっただのと宣うそのわりに、エルヴィンやハンジたちと代わり映えしない如何許りか頭がキレて機転が効いて、その場その場で要領良く合理的に対応する柔軟さも持ち合わせており、何より、言葉にも文書にもしないエルヴィンの真意まで正確に見抜き、読み取り、理解し、先々を見通し実行する、実戦では言わずもがな誰も追い付けぬレベルの実力派であって、商会を牛耳っていた基本的に金銭契約以外は信用しない肥え太った商人さえも、信頼に足る男だと賞賛したらしい程、常に任務に忠実であった、あのリヴァイが。そんなリヴァイが最後に必要だった作戦に使用する兵器であるエレンを掻っ攫い監禁している。などとそんなことは有り得ない。有ってはならないことだ。あまりの不審さに認められぬ思いを抱え込みながら、避けようも無く執拗な、深過ぎて息が詰まる口付けを受け取らされ、舌を絡め取られるがまま、エレンがリヴァイのブーツの脛あたりを裸足で──この地下室で目を醒ましたその時点でエレンは全裸に剥かれていた──とん、と合図のように軽く蹴るとリヴァイは驚愕した顔で漸くエレンから唇を小面倒に離した。視線が交わるとリヴァイもまさに、もしやおまえエレンじゃねえな? おい、てめえ本物のエレンをどこへやりやがった、とでも今にも吐き捨てそうな、疑心に満ち満ちた奇妙な表情を浮かべエレンを見ていた。そうなのだ。有り得る筈が無いのだ。本来のリヴァイが兵士長としての職務を放棄し、エレンを監禁なぞしないように。本来のエレンも兵士としての本分を放棄して、おとなしくリヴァイに監禁されたりしないに決まっている。だがそれにも拘らずふたりは結局そのまま色事に及んだ。火の点いた官能の濁流に抗う術無く呑み込まれる。動く度無粋にも錆びた音を立てる鎖へと、じゃらじゃらじゃらじゃらうるせえんだよクソが、などと自分で付けたくせにエレンの首輪から伸びるそれを邪魔臭そうにしていたが、リヴァイは最後まで、エレンを繋いでいる首輪の鍵を開け外してはくれなかった。けれど首輪を外す以外のことは何もかも全部、全部して、エレンを自力で浮上出来ない快楽の海に溺れさせた。理不尽にもエレンには、てめえが勃たせろと、容赦無く喉奥にペニスをぶち込み叩き付けてでもさせてきたくせに、その逆はいつだって、そんな汚えもん舐められるかよ、のひと声で絶対にリヴァイ自らはしようともしなかったフェラチオすら、した。普段から兵士らしからぬ佇まいである潔癖症で、性行為の最中であっても零すことを赦さない、アナルにペニスを突き入れられると直ぐに足腰から力が抜けて教え込まれた悦楽に、ぐにゃぐにゃになってしまうエレンとは真逆にも、絶倫な程続く体力で汗ひとつかかずに常々涼しい顔でエレンを苛んできたリヴァイが、このとき初めてエレンにも解る程の汗を均整の取れたその全身に滲ませ、懸命に、エレンの尻孔の内側、排泄器官に在るエレンの悦いところを探るよう動いて、エレンが何れだけ耐えようと堪えようと、喘ぎを奥歯で噛み締めてもその都度目敏く奥の奥まで穿ち、だらしのない若いペニスから迸る涎のような先走り汁と、達する度に散ってしまう、否応無き精液による汚れさえ咎めること無く抱く、優し過ぎる愛撫と激しい劣情の連続にエレンは意識を飛ばした。まさしく為落され巨人のことも作戦のことも頭から無理矢理に締め出されそうになる程、目の前が皓白に塗り潰される威烈なまでのセックスに、エレンはぐずぐずに蕩けて蕩けまくったのだった。
そうして、それから始まった監禁生活は数ヶ月にも数年にも把握出来ぬ期間に及ぶこととなる。
その間、リヴァイはずっとそのように努め、一途で、献身的に、今や手配書が出回っているエレンへと接していた。1番手近で、1番、死ななそうな相手。手っ取り早く。易きにつきて。女では無いためどう扱おうと孕む心配も要らず。合意の上であるので面倒も無い。それらはきっともう誰にも通じぬ言い訳となった。エレンは、実はこの人はほんとうは物凄く、物凄く、俺を欲していたのだろうか、欲してくれていたのだろうか、そんな馬鹿な話があるかよ嘘だ全部、と、監禁初日の翌朝、重くて立ち上がるどころかベッドの上で身じろぎするのもままならぬ、しかしそれでもまだ甘さの消えない腰をさすりつつ、不様に小さく唸りを漏らしながら、やっと気付いたのだった。腰と云わず首許と云わず尻と云わず喉も頭も全部含めて、体中が、叫びだしたい程到堪れずに、痛かった。
1日に1度だけ、必ずと云って良い頻度で、リヴァイはエレンへと食事と水差しを持って訪れた。それすら出来ないときは日持ちのする携帯固形食を、封を切り犬でも齧り付ける状態にして、多めに置いていく。監禁したエレンに対しいたずらに空腹感を与え態と何日も放置してみたり、暴力を振るってみたり、罵倒してみたり、等々の支配的な行為は一切しなかった。ばかりか暫く来られなくなるときには、それがどのくらいの日にちでどういう理由からであるかをいつも言い置き、約束をやぶることは仮にも倦憊する様子も無かった。監禁されている地下室の隅には小さめだが立派にバスタブが設置されており、そこにある壁に引っ掛けられているシャワーホースからは真水も適温の湯もきちんと出る。贅沢品である石鹸やら、ふかふかのタオルやらまで揃っている。ベッドから繋がれている首輪についた鎖は絶妙な長さで、エレンが跳ねてみようとも換気扇と出入り口にだけは届かない。ただ、後ろ手のままでは何れもエレンひとりではままならないため、リヴァイがエレンを驚く程優しく壊れ物を磨くような手付きで、背丈ばかりの未発達な躰のその隅々までを泡立てた手のひらでやわく包み撫ぜて清潔に洗い、トイレの世話までこなす。至れり尽くせりにも程がある。ベッドの傍にはご丁寧なことに深みのある簡易トイレのような、貴族が飼うペット用の吸収剤を敷き詰めた専用容器と、柔らかく上質な紙を切らさず用意されていた。勿論その取り替えすらリヴァイがするのだ。どうしてここまでするのだろう、エレンにはまったく意味が理解らなかったが、鎖の長さはエレンの身長と跳躍力から割り出された正確さで地下室から出られない。折につけ、リヴァイはエレンが望めば新聞を読み聞かせてくれるなど、甲斐甲斐しく、あたかも年端もいかぬ主人に仕える執事にでもなったかの如く、只々エレンに尽くす。外の情報を知り得ることはエレンにとって暇潰し以上に随分と有り難く意義の有ることだった。予定されていた最終決戦なる壁外調査は、エレンの不在により中止されていて、仲間の誰かが危険にさらされることも命を落とすことも、無かったらしい。それを知れただけでもエレンは胸を撫で下ろす気持ちであった。その上、当初は逃亡したと見られていたエレンの扱いも、新聞によるといつの間にか新たな組織による誘拐、拉致、となっていた。それは、別に新たな組織による犯行では無いと云うだけで、何ら間違いでは無いので、エレンとしては、へえ、と呟くくらいしか出来ないのだが。しかしてそのせいで調査兵団が、エレンの捜索に尽力しつつ通常任務や訓練をもこなさ無ければならざるを得なくなっている、と云うことについては吹っ切れぬ申し訳無さに罪悪感が募る。
兎に角エレンはリヴァイによって監禁され、そしてリヴァイは殆ど毎晩、可能な限りエレンの元へやって来ては食事から排泄まで世話を焼き、エレンを抱いた。古城に居た頃ですらされたことの無いことをされている。それでいてリヴァイは昼間、調査兵団の兵士長として行動し、誰の目にも、行方不明になった部下で有り調査兵団の最終兵器でも有るエレン・イェーガーのその身を案じながらも捜索を続ける、と云う無駄で無意味な演技を続けなければならない。そう思えば、よく心身共にもつなァ兵長タフ過ぎる、とエレンはいっそ感心さえしてしまう安穏とした非日常だ。けれど、も。
「兵長。いつになれば俺をここから出してくださるんですか?」
ものには限度と云うものがあるのだ。或る夜1度、セックスのあとで試しに尋ねてみれば、リヴァイは鬱陶しそうに舌打ちを響かせ、それまでエレンに覆いかぶさるようにしてベッドについていた手を離し美しく筋肉のついた小柄な躰を起こした。
「ふつう、そういう質問は初日にするもんじゃねえのか」
「兵長のことですから何か凄く特別な秘策や目的が有ってのことなのかな、って。でもどうやら違うようなので」
「あァ、違う。なら──俺が、エレンおまえを監禁することで独占したいだけだ、とでも言えば信じて納得するのか?」
「そもそも俺は兵長を敬愛はしていても、貴方のつよさ以外は信じていません」
「口の減らねえガキだな。何れだけ躾けても躾がなってねえのは、俺の責任か?」
「…赦されませんよ、こんなこと。幾ら貴方が兵士長であっても。つうか俺としては、とっとと巨人を殲滅したいので、はやく出して頂きたいんですが」
「元々おまえみてえな死に急ぎのクソガキなんざ居なくとも、俺が居ればあの程度の数の巨人、殲滅出来る」
「う、わァ……」
「何だよ」
「いや、嘘でしょう。嘘だ、勘違いだ。心から、俺の勘違いであって欲しいんですが。…まさかこの監禁、俺を殺されたくない兵長の、や、優しさ? とか云うやつ、ですか」
「今頃気付いたのか?」
「え、えー……? やっべえ…鳥肌立つくらい気持ち悪い」
「てめえの自業自得だ」
「何を仰っているんですか。兵長。…本気で気持ち悪いです。吐き気がします」
優しさ。優しさだと? それは独占欲よりずっとたちの悪いものである──エレンは全身に戦慄が疾る感覚を覚えた。正直に云って怖かった。リヴァイが何もかもを賭している。怖過ぎて、拘束されている現状に、勝手に怯える躰の震えが一向に止まらない。怖い。だが、怖い、という感情はつまり、自分に価値があると信じているから沸き起こるものであるのだ。信じられない、とエレンは思った。そんなものは疾うに、棄てたつもりでいた筈だからだ。女型に班を壊滅させられ、正体を暴かれたアニを追い詰め壁内で闘ったとき同時に、信じること自体すら、あの破壊された地下道に棄ててきた筈だったのだ。エレンはそれが怖くて、怖くて、仕方が無い(だって何をどうしようがそんな、そんなきれいには、いかない)。花では無いのだ。煽るように吹き荒ぶ風に弄ばれ、希望の光にも似た何かに、彷徨わされていただけであったのだとしても。はらはらはらりと、儚くきれいに散ることも出来ない。そう望めば望み通りに棄てることが出来るのだと思っていたのだ。何だって単純明快に手放せるのだと、それはまだ何も知らずにいられた先刻までのことだ。エレンはリヴァイに、生きたいと言え、と命じられたあのとき、生きたい、とは思わなかった。そんなことよりも、もう少しで仇が取れるのだと、もう少しで死ぬことを赦されるのだと、思い浮かべるその歓喜に目が眩みそうな愉悦を持った。それなのに。
エレンは考える。自分は、リヴァイの、まだ何を信じていてみたかったのだろうかと。まるで呪われているような地獄の門の手前で、用意された死へと堕ちていくのはまったく少しも怖くなど無かったのに──そうだエレンは今、リヴァイに鮮々しく恐怖している。
「……まともじゃ、無い」
震える声でエレンが言った。リヴァイは、はっ、と、馬鹿な子供を鼻であしらうように、嗤う。
「貴方は。…こんなのは、まともじゃあ無い……それくらい、貴方が最もよく、理解っている筈です。兵長」
「さァな? どうだか。おまえは俺を買い被り過ぎている。エレン。おまえは今、俺がまともじゃあ無いと言ってやがるわけだが、だったら、この世界で何がまともだったんだ? 俺はおまえの倍以上の歳月を生きちゃいるが生まれてこのかたただの1度も、未だにまともなものを見たことがねえ。なァおい、この世界にまともなものが、ひとつでもあったか?」
「少なくとも、俺が敬愛し続けていた兵長は、まともでした。でも、今それについては訂正します。──俺は、兵長を、貴方を、敬愛していたんじゃ無い、畏敬していたんだ」
束の間の大袈裟。くそったれ。巨人化する化け物として罪深く生きてきて、せめて最期くらいは誰かの役に立つ死に方で死ぬつもりでいたエレンを今更、人間だと思ってどうするのだ。
兵長、貴方は俺に。
「さっさとくたばれ。と、貴方は俺に。そう言うべきだ」
眉のひとつを顰めるわけでも無く首を振るわけでも無く、視線をリヴァイから外さずにじっと見ている、蜂蜜色の、大きな瞳。だからどうしようと証明出来ない。信じるほうが楽だなどと云うことが証明出来ない。あと何回を繰り返せば騙されないだとかそんなことすら。
「優しさは要りません。無意味に生かしたまま、腐って死ねってことですか。俺は、そんなこと1度だって、望んで無い、のに」
何なら土下座したって、構わない。その程度には。エレンが知るリヴァイとはそんな人間ではいけないのだ。どういう方法でも良い、エレンを痛め付けて、踏み躙り、時として嘘をつくような愛し方で。エレンにとって痛みを感じると云うことは、生きている実感を齎す実に簡単な方法なのだ。だからそうしていて欲しかった。リヴァイに優しくされる、その惨めさに泣きたくなる。どうか呼ばないで欲しい、愛さないで欲しい。エレンはリヴァイへとそれを伝えるためだけにこの場に存在しているのだ。いつか満たされるような、そんな謙虚さは生憎持ち合わせていないのだからと。
「成る程。まともじゃねえのは、てめえのほうだろう。違うか、エレン。まずはクソみてえに馬鹿げたハンストを、いい加減よせ。苛々する」
「してませんよ。ハンストなんか」
「ほう、よくもそんな虚言を吐けるもんだな。なぜ何も食わねえ」
「俺には必要の無いものだからです」
決然と言い放ちそれから視線を緩く逸らす、エレンは無駄に無意味に生き延びることには興味も無いしそれが生命ならば欲しくも無いのだと云うことを、宛ら、リヴァイにならば絶対に理解されるものである筈だと言外にはっきりと伝え続けてきたのだ。それがエレンによる、リヴァイへの精一杯の甘えなのでは無く、ただ呆気無く信用を棄てた傲慢であるのだと。いつだったろう、リヴァイは知っていた。気付いていた。それさえ見過ごしてきてやったのだ。こんなにも──永く。
リヴァイが提供し続けた食事をエレンが食べようとすることは無かった。1度も。無体に力任せに、スプーンを口のなかへ捩じ込もうともエレンはそれを飲み込まない。仕方が無いのでセックスの合間、キスといっしょに口移しで水を飲ませてはいたが、上官命令に替えようとそれだけは拒絶する。エレンは知ろうともしないのだ。リヴァイを舐めきったその蜂蜜色の眼球を抉り出して冷たく固い石床へと引き摺り倒したい、激情を、リヴァイが何れ程つよい意志で、堪えてきたのかを。
エレンは狂気と云うものを知らなかった。自身が狂気を孕んでいるのだと、いっそエレン自身が狂気のかたまりであるのだと。知らないままに初めて審議所の地下室でリヴァイに見せた両の目で、壮絶なまでの憎悪にぎらついたような、狂人足る笑みをも有識せずに零していた。それが狂気そのものであるのだと自覚することも無く。それを見ながら、その濁った双眸に見られながら、リヴァイは満足してもいた。そうなのだろう。なぜなら狂気と云うものは、ぞっとする程に、美しい。
「おまえの主張なんぞ知ったことか。俺が食えと言ったら食え。エレン」
それでも1番、食べやすそうである物を無意識に選んだリヴァイの右手は心底可笑しな物体であった。誰が死のうが生きようが何も変わらないのだと告げるようにエレンが居ようと居まいと変わらず同じ日を繰り返し、困窮し続ける世界で、身分の高い者だけにしか行き渡っていないバスタブを初めとする身の周りの贅沢な物品を、どこからこんなものが調達出来ているのかエレンには知る由も無いままに、小奇麗な皿に入った冷製シチューの具を汁ごと鷲掴み、それを捻じ付けるような強引さでエレンの口内に押し込む。とても潔癖症とは思えぬ程に汚くも、その指先とエレンの唇とでそれをそこで散々ぐちゃぐちゃに潰してから腕を引く。まるで血飛沫をきるようにしてリヴァイが腕を軽く振れば、そこからは赤色では無く牛乳とチーズをふんだんに使いつくられたクリームの白い水気と肉の欠片が僅かに石床に散った。もうそれだけで、取り敢えず嫌悪感に一杯になる程たくさんだった。
「てめえは時折、本気で張り倒したくなる程ずっと強情に過ぎやがる。頭の悪いクソガキだ」
言いながらリヴァイは立ち上がりシャワーホースへと歩みそこで手を洗い、拭う。何れ程執拗に潔癖を保とうとも辿り着く先は相も変わらずに、不衛生で、不健康で、不徹底な機械的唯物論。
「……だから、食いたく無いんですって」
「知っている。俺はおまえの上官として命じてんだよ」
「聞けません」
「ここまで譲歩してやったんだ。おまえに拒否権がまだ有るとでも思ってんのか?」
「聞きたく、ありません」
エレンは汚れた口許を拭うことも出来ずに口内に入ってしまったものをそこらへんに吐き棄て、言った。離れたリヴァイがすぐさま近付き、エレンとの距離を詰めてくる。いつだってこんなくだらぬことにのみ互い躍起になる。いったいこんなところで何ゆえ兵士がふたりして、戦のひとつもせずに挙句何をしているのだろうかとつくづくうんざりとするが、いつだってそれらの最中には何ひとつとして何もかもがすっぽ抜け引っ掛からないのだから、酷く可笑しい。エレンはもう少しばかりリヴァイに対し露骨に従順であるべきか、或いはもっと一欠片の感情もリヴァイに向けずに、媚びずにいるべきなのである。
「──だから俺は、作戦決行の前日に、生きたいと言え、と言ってやったんだ」
何が、だから、なのかとエレンは思う。生きたいなぞと思ってもいないときに、生きたいと言え、と言われたところで適当に相槌を返すより外に何があったろう。エレンは口端を上げたまま、リヴァイに、だが淡つかに言う。
「兵長は、俺を馬鹿にしているんですか。若しくはこのすべてが俺を馬鹿にしている行為だと理解っていて、まだ続けるんですか」
「おまえは元から馬鹿な上に頭のおかしい化け物だろうが。おまえこそその目で、俺を馬鹿にしてやがる。不敬罪で吊るしてやりてえ」
「……それもう根本的なところで何もかも間違ってらっしゃいますよ。兵長」
「今更だ。自業自得だと言っただろう。おまえも、俺も」
感慨深くそう言い募るリヴァイに、エレンは唾棄するようにたぶんリヴァイは今更だと思っていないだろうことを思い付く。
「では兵長。もし俺が貴方を心底嫌い憎めば、貴方はどうするんですか」
──その一瞬にリヴァイが浮かべた表情は、とてもでは無いがどうにもエレンには説明出来ない。ただそれはどのように形容しようとしても、エレンが蓋然的に想定していたものとは愈愈違った。
「クソが。……今のてめえにはもう俺しかいねえんだから、そんなことにはならねえだろうよ」
その言葉自体はどう聞いてもおかしいのに、じっとリヴァイの深いネイビーブルーを見ていたエレンにとって、それは然して問題にならなかった。相手の瞳から目が離せない。そのことには互いに気付いていたが、しかしそれまでふらふら迷っていた浮気なるエレンの瞳は、このときにして且つ且つと、リヴァイという人間そのものを理解するために根気よく見据え、見詰めることを、拒めていなかった。どうしても。
要らぬものだと言って幅からぬエレンが何も食べない。それは、エレンが巨人化能力のオプションとして持つ異常治癒力と同等のものであるのだろうと思われる仮説的な能力によって、簡単に云えば、食事をしないことがそのまま直ぐには餓死に直結しないのだから、リヴァイは苛立ちながらも別段、悩んではいないのだ。ただ巨人化しないままでは緩やかに衰弱していく。死がふつうの人間よりは遠くに在る、と云うだけで。しかしリヴァイはそんなことすらどうでも良い、只々只管、エレンのその頑なさが気に入らない。幾らエレンが化け物であろうとも、死ねばもうどこへも戻って来られない。の、に。
生かされる恐怖に震えているのだとエレン自身自覚している、そこに触れずともリヴァイには見透かされている、エレンの、その、手で、掴めるものなど何も無い。それは死を懇望されることよりも、思い付く限りの残忍な方法で殺されることよりも、おぞましくも重々しく、恐ろしく、て。どこまでいつまで互いに互いを愛しているふりを続けられるか。率直な問題はそこにあった。舞い上がる土埃も憎悪さえも無いままに。からっぽ、に。けれど真っ直ぐな臆病さに怯むのは、切り裂かれた過去と暴かれる皮膚の下に潜み在る、最果てだ。
「……なるべくなら話したく無かったんだが。おまえがあまりに喧しく憐れ過ぎるからもう良いだろ。教えてやる」
リヴァイは深々ともう何度めかもわからぬ溜息をついた。呆れさえ既に通り越し思い頽れる程の気分だった。エレンは訝しみながら瞬いた。
「何を、ですか」
「エレン・イェーガー失踪及び誘拐はエルヴィンの指示だ。そこに俺の意思は露とも含まれちゃいねえ」
「………………は?」
たぶやかに間を開けて、間の抜けた表情で、蜂蜜色の眼球が零れ落ちるのではあるまいかとリヴァイに思わせる程に両眼を見開き、エレンは尋ね返した。当然だ。リヴァイは厭いつつ物憂いし息嘯を漏らす。これから自分は大人げも無く、エレンを絶望させ傷付ける。
「最終目的はエレン・イェーガーの存在を大衆に忘れさせることだ。最初から、エレン・イェーガー含め、巨人化する面妖な兵士共なんざ、存在しなかったと事を進められるように。大体あんな阿呆でも思い付く馬鹿馬鹿しい作戦に、狡猾なエルヴィンの野郎が納得して乗ると本気で思うのか? 今までもずっと水面下で、そして現在においても、俺たちがしていることは、夥しく壁に硬化し塗り込まれた50m級の巨人を1匹残らずすべて、壁外の残党巨人共も合わせて、元の人間に戻してやる方法の模索と研究だ。そうするに当たり駆逐脳なおまえは邪魔でしかねえからな、事が落ち着くまでは監禁すると云うことになっていた。だが何も知らねえガキにそれは酷なんじゃねえのかと、幾ら何でも一方的過ぎやしねえかと、態々チャンスをくれてやったのに、それでもおまえは生きたいと言わなかった。寧ろ死んでいくことに歓喜してさえいるように見えた。…つまりは不合格、失格、だな」
「誤魔化さないでください」
初めから。初めから貴方は。俺がどう答えていようとも──。
「すべてが団長の指示だとはとても思えません。もしも仮に、巨人を人間に戻すことが出来たとしたら、覚えも無いまま人を喰らって、俺のようになる奴が絶対出てきますよ」
「だろうな。自傷行為で自ら巨人化する奴が」
「当たり前です。しかも超大型巨人や女型や鎧たちのように、意志と理由を持って人類を滅ぼそうとする奴らさえ出てくるかも知れない。それを懸念しない団長では無いでしょう? 壁内が大混乱になるだけの話では済まない」
「それこそ疾っくに想定済みだ。エルヴィンも、俺も、調査兵団幹部はな。結論から言って、そうなるならなったで構わん。いっそ自分の意志で巨人化して暴れてくれりゃあ、王政も全人類も合わせて何もかも、平等に更地になるだろう。更地になれば掃除もし易い」
「……そ、れは…もう、人類の存続を、諦めるって、ことですか」
「少し違う。が、おまえはそうとしか考えられねえんだろう、エレンよ。だったらもう、それで良い」
「なに、を……何…言って…………ッ何でそんな! そんなことになったら何れだけの罪無き人類が、犠牲になると思ってる!」
「うるせえ、吠えるな。吠えればそれだけ弱く見えるぞ、駄犬。勿論そいつらが民間人を襲いだせば直ちに調査兵団が、俺が、人間やめたそいつらを迷わず削ぎ殺す。だがエレン、これだけは覚えておけよ。人類のなかに、罪無き者なんざひとりも居ねえ。俺もおまえも同様にな」
エレンは以前にリヴァイについて、よく心身共にもつなァだの何だのとリヴァイのタフさに安穏と感心していたが、ぎりぎりのラインでかろうじて平静を装っていたのはいつもエレンのほうだった。昼間リヴァイが地下室に居ない間エレンは、癇癪を起こし暴れまわることこそ無かったが、ひとしきり髪を振り乱し左胸を爪に赤い皮膚が詰まる程掻き毟ってから、瀕死の重傷でも負っているかのように唸ったり呻いたり言葉にすらなっていない何かを喚いたりと相当情緒不安定で、果たしてこのような状態で突然に解放されたとしても、地上で正常な自分自身で有り続けることが可能であるのか、全身が痙攣を起こす程に甚だ疑問で自信も無かったのだ。だがエレンは、リヴァイの前でのみ完璧に欺き通していたつもりでいた。浅薄にも。そんなことは目にするまでも無くリヴァイには筒抜けであるに決まっているのに。嘘も上手くつけぬエレンに、リヴァイを欺くことなど、出来得る筈が無い。
「……ふざ、けんな…!」
握り締めた拳の内側を爪の先が傷付ける。
「それはこっちの台詞だ。てめえこそふざけんな」
リヴァイは徐ろに鍵を取り出し、エレンの目の前に置いた。
「何ですか今更、何のつもりで」
リヴァイはエレンの問いになぞ答えずに、けれどエレンの隣にぎしりと座っていた。身長差ゆえにどうしても上目遣いに見上げることになるそのネイビーブルーの双眸には、いつの間にか、エレンが狂気だと想像していた色が宿っている。もう。何もかもを信じたく無い。終わらせたい。終わりたい。エレンは黙って自分を見上げる三白眼のネイビーブルーを見る。見る、と云うことは同時に、見られている、と云うことと同義だ。リヴァイの舌がべろりとエレンの眼球を舐めた。蜂蜜のように甘そうでいてほんの少しも甘く無い。生理的な涙を含んだ粘膜の、塩っけのある不気味な味しかしない。エレンの手は鍵を拾わなかった。代わり、リヴァイが諦めたようにそれを拾った。そして、ガツン! と音がする程につよく、その鍵をエレンの頭に叩き付けぶつける、けれどもエレンは顔を横に背けただけだった。
「……たぶん俺は、おまえを愛している。と、思う」
リヴァイの薄い唇によって紡がれたその言葉は、エレンを那落へと突き落とした。言われたエレンのみならず、言ったリヴァイ本人さえもが瞠目し、ほんとうに驚いている。自分が相手に対して相手のようになれたなら、楽なのかも知れない。互いに何の興味をも持たなくなれば、互いのことを一縷も考えずに済むのであれば、その姿を見ずにいられるのであれば、楽なのかも知れない。相手が自分や他の人間に対してそうであるように、そう出来るので、あれば。
「無理だ」
たった今エレンに愛を囁いた口のなか、そっとリヴァイは呟いた。静寂が耳に痛い。今の声がこの地下室から外に漏れる筈が無い、けれども漏れなかったのかを知る方法も今は無い、それはエレンにもリヴァイにも判断は付かなかった。諦めの慨嘆が不快な吐息の塊となって、かすかに唇から漏れた気がした。
「命令を変える。──その両腕を、俺の前で無意味にも後ろ手に隠すのを、直ちにやめろ。エレン・イェーガー」
首輪の鍵さえ有れば楽々と外し出てゆける。鍵が無いとしても両手を使えば首輪くらいどうとでも出来る。最初から、リヴァイはエレンを圧抑なぞしていなかった。手錠を掛けていたわけでも、荒縄で手首を縛り付けていたわけでも無い、自由なエレンの両手は、この狭い地下室のなか、いつだって不自由さを選んでいた。何もかもを信じたく無い。終わらせたい。終わりたい。なのに終わりたくない。傍にいたい。矛盾したエレンの。そういう可哀想な子供の虚勢的で悲況で卑怯なる態度が、リヴァイには理解出来ずにそれでも黙して指摘することをしないでいたのは、茶番に付き合ってやれた程度には、苛立つくらい愛してみたかったからだった。憤懣やる方無いのだ。虫酸が走る程。だがもうそれもこれ以上は。
無理──だ。
力を抜き、だらんと垂らされたエレンの両腕は自由であるのに不自由そのものを如実に。リヴァイはその手を握る。
リヴァイの前でエレンはいつだって自身で演じる疑似拘束に陶然としていた。例えばいつも、朝の随分早い時間から夢現にもエレンは急に飛び起きた。と思うと気が狂ったかのように自らの体躯を手弄りその未成熟な自身の肢体を、胸を、腹を、頭を、そうして順繰りと撫でまわしてみる後になって、漸く大きく深い呼吸をして、それから暫くし安堵した顔で再びベッドのなかへ潜り込む。それを、リヴァイは直ぐ傍でエレンの薄い肩越しに眺めながら何も言わずに、やがてまたベッドを軋ませ沈む背を、心底、穢らわしいと思い、憐れだと思い、憐れんでやることすら勿体無い程憐れ以上に憐れだと思い、そうしていつしか、この分かり易く可哀想な化け物の子供はほんとうに狂っていくのだろうと云う確固たる確信を持ち始める。はやくそうなれば良いといつも思っていた。眠っている振りを続けながら。エレンが狂っていくさまを夢想してはどんどん愉快な気分に浸るようになる。勇ましく尖りを帯びたエレン・イェーガーは分かり易過ぎる程に可哀想なので、そのうち死んで、依存的で、臆病で、儚く散ってしまいそうな脆弱な何かに、容易く手折られ飾られるだけの、やがて枯れて落ちる花で良い、リヴァイの傍らで生まれ変わってそしてやっと生きる。そういうものに成れば良い。いつかきっとそう成ると疑う余地も無くリヴァイはそう信じている。だのにまだエレン・イェーガーはいったい何を捜しているのだろうか。金色の瞳のふちを赤くして、丁度、あのときのように、目を伏せる度に蜂蜜色の双眸を隠す、瞼を、真っ赤に腫らすまで泣きだすような哀しい眼をして、何をそんなにも必死に睨む必要が有る。まだ何を捜して何を待っているのだろうか。月明かりさえ届かぬ冷たい地下室で毎朝そうして自分の腕で自分の体躯を、その輪郭を確かめて、いったい何を捜しては、そこから、自分自身から、何が欠けていくと思うのだろうか。穢らわしい生命は未だきちんとこびりつき剥がれずにそこに在ると云うのに。生きたいならば生きたいと言え。死にたいならば死にたいと言え。エレンがどちらを口にしたところで、最期には必ずリヴァイの腕がその躰を離すこと無く、拾うのだ。
けれどどっち付かずに成ろうとして、その危うさでバランスを取ろうと足掻いて。失敗の手本のような遣り方で愚かしく失敗している。
「どうせまた陽も昇りきらねえうちに、おまえは独りで唸るんだろう」
「……わかりません、そ、んなの…」
「監禁ごっこはおまえを満足させたのか」
「いいえ。…いいえ、俺は、」
「半端な破壊願望はそんなにも心地好いかよ。手放せねえくらいに」
「…何の話ですか」
「夢の話だろ」
「なん、の、」
「おまえのそのふたつの目が見てやがる夢だ」
「兵長に何が理解るんですか。俺の。何、が」
「理解してやる必要が了する程に無い。だから破壊してえものがあるなら迷ってねえで好きなだけ破壊して来い。それがおまえ自身であろうが俺は別にどうだって良い。どうせならさっさとぶっ壊れちまえ。自分が何者であったのかもわかんねえくらいに」
「────っ」
畳み掛けるリヴァイの詰め言さえこんなに耳障りが好いなんてわけがわからない。不意に、エレンは思い切り乱暴にリヴァイの腕をふりほどいた。がつりと痩身を冷ややかな壁に打ち付けて、萎えた手足で立ち上がる。そのまま、荒い呼吸で言う。
「俺が、兵長、貴方の、」
エレンは靜か泣きだしながら、殆ど声にならない声で、リヴァイにさえ届くかわからぬ程の消え入りそうなその震えた声で。けれど確かに哀哭した。それがエレンにとって精一杯の、それこそ甘えに見せ掛けた傲慢などより余程、心から、精一杯の──絶叫であった。
「貴方の。その舌の上で溶けて消えて失くなるためには…この躰が、氷で出来てりゃ良かったんだ」
けれどもそれではリヴァイが幸せになれない。
暫時を超えた、沈黙の末に。
リヴァイはひと言、そうか、とそれだけを言って。苦しくて仕方が無いような顔でリヴァイを見る、そのくせ呼吸することをやめないエレンを、ひっぱたいて蹴り倒してやりたい気持ちを抑えつけながら、リヴァイはエレンにふりほどかれた腕を引き寄せ胸にエレンの顔を埋ずめさせてから、その細い腕を、胸を、腹を、頭を、毎朝エレンが確かめていることと同じように順繰りと撫でた。なるべく優しく。蜂蜜の色を溶かしたその目はもうリヴァイを見ない。無理矢理に繋いだ手は冷たかったりあたたかかったり。明日は昨日より上等だったり劣悪だったり。異様さだけがさんざめいては、たくさんのものが散らばって。無情に流れる時間はリヴァイにエレンを不得意にさせる。
「……ッすみません兵長。吐きま、す…っ」
切羽詰った様子でエレンはリヴァイから逃れると蹲り、ベッドの傍に簡易トイレとして置いてあるペット用の容器に躊躇わず顔を突っ込んだ。
「っふ、う、ぐ、…あ゙ぁっ、ぅげっ、…ァ」
嘔吐いても、嘔吐いても、水分摂取しかしていないのだ。吐瀉物らしき吐瀉物なぞ出る筈も無い。せりあがるものは胃液だけである。込み上げて治まらない嘔吐感に何も吐けずに、なので余計に苦しく気持ちが悪い。天井に換気扇を付けてあると云っても閉塞的な地下空間はまたたく間に胃液の匂いに満たされた。
「っ…う、…はッ、かはっ……うぅっ、」
人間の胃液の主要成分はタンパク質分解酵素ペプシンで、キモシン、リパーゼと約0.5%の塩酸を含むpH1.0〜1.5の強酸性を示す水溶液がそれを活性化する。嘔吐くばかりのエレンの背をさすってやりながら、リヴァイはもうこのガキは無理なのだと嫌になる程考えたことをまた考えていた。いつになったら。いつになったら終いが来るのだろう。揉み合いの隙、引っ繰り返ったせいで空っぽになった皿が邪魔で、それは落として棄ててしまった。エレンはもう、人間が真っ当に食らう食事を、食べられない。与えてもいない花の香りに隠れる毒の持ち主。疾っくに有利も不利も存在しないと知っていた。あべこべの、継ぎ接ぎで傾倒する世界だ。
「今のうちに──俺が傍にいるうちに、食って吐け」
言いながらリヴァイは胃液すらまともに吐けなくなっているエレンの首根っこを掴み、己のほうへと向きを変えさせる。
「なにを、」
「何をじゃねえ。俺をだ。来い」
何らおぼめくこと無く予め理解っていたのだとでも云わんばかりに、リヴァイは自らの上着をずり落とす。丁度、棘上筋あたりから三角筋、上腕三頭筋、上腕二頭筋を見せ付ける程度に。
「…ぃ…や、です……」
「拒否権はもうねえっつったろうが。食え、エレン。何も全部食えと言っているわけじゃねえ。少し齧り付くだけだ。おまえが巨人化するときにその手を噛みちぎっていた程度で良い。今のおまえの状態はおまえが入団した頃から、要するに最初からハンジが危惧していた通りだ。監禁してみてからそれは確信に変わった。もう、おまえは、巨人化のし過ぎで人間しか食えなくなってんだろ。覚えも無く父親を──グリシャ・イェーガーを食ったときみてえに」
「嫌です! 食いたく無い!」
必死に拒絶を示しながら、エレンの喉は本人を裏切り勝手に鳴る。飢えた獣のように。涎が滴り落ちた。
「嫌だ! 嫌です兵長、いや、」
「うるせえと言ってんだろ愚図野郎、黙れ」
エレンの拒絶などかくも儚く、リヴァイに飛び込まされた腕のなかで。
「あ、あ、ぁ、やだ、やだ…ぁっ兵長……っ、ゃァア゙ア゙ァ…」
抗えない飢餓感。高鳴る鼓動。目の前がまわるような目眩に。襲い来る強迫観念。それらは只々、途方も無く。
「っつ…」
「んんっ、ぐ」
矮小で鈍く、だが生々しい音がぶつりと鳴るほぼ同時、リヴァイの鍛え抜かれた肉体が纏う皮膚にずぐ、とエレンの歯が沈む。甘噛みでしか無いが、そうか生きたまま喰われるとはこういう感じであるのかと、リヴァイは嘗て失った部下や仲間の死に顔を思い浮かべるが、どうにも腹立たしい程に浅い。これでは意味が無い。けれど口内に広がる肉の感触と芳香な血の匂いに、赤味の混じった唾液を啜り上げて直後エレンはふらつくまま渾身の力でリヴァイを突き飛ばし、ベッドに頭を突っ伏した。酷い怯えようだった。シーツを奥歯が軋む程擦り付けて噛み締め、しきりにごめんなさい、ばかりを繰り返し嗚咽を漏らす。リヴァイの肩に残された歯型はリヴァイが命じたそれより随分足りておらず、エレンの歯列にぴたりと嵌まる大きさの歯型からは玉のような血がぷつぷつと滲み、やがてささやかに滴り落ちていくだけであった。噛みちぎられてさえいない。
「ごめんなさ、ごめんなさい、兵長、ごめんなさい」
「ちっとも食えてねえじゃねえか。やり直せ、エレン」
まるで古城での当初、幾度も、出来が悪いとやり直させた掃除のときのような口調でリヴァイに咎められながら、エレンはその細い肩を小刻みに揺らしている。だがそれもリヴァイの予想した範囲内だった。エレンにリヴァイが食える筈も無い。仕方あるまい。
「エレン」
あたかも夜伽の最中のように呼び掛ける。
「…………はい」
答えたくない、とその痩せた後ろ姿が語っている。だがシーツに顔を埋ずめているせいでくぐもってはいるが返事は返る。リヴァイは問うことをやめなかった。
「クリームシチューを飲み込めなかったのは、わかっていたからか」
「……だ、って…あれは……死肉、でした…人間、の…」
舌に乗せられた、ただそれだけであれが何で出来たものであったのかがエレンにはわかってしまった。牛でも豚でも鶏でも無い。
「畜生殺しで処刑された悪人のものだ。そこに罪業妄想を持つなよ」
「…………」
そんなことを言われても困る。死刑囚の残骸だからと、はい、そうですか、とはいかない。ましてや死肉ならば良いということでも無い。どうせなら、壁外にて大量に見てきた無知性巨人のように何も食わずとも生きられるのであれば。ならばまだましであったかも知れない。エレンの躰は人間の食事も摂れず、疾うにそのどちらでも無く。リヴァイもそれはわかっていた。エレンを生かすことがどういうことであるのか。
「生きている人肉は今ここに俺しか無いんだが、おまえは俺を食うくらいなら死ぬんだろう」
「…当たり前……です。こんな、化け物には、俺が付き合って、いられない。……殺して、ください」
「それが出来りゃあさぞ楽だろうな、互いに。──その無駄にでけえ目は閉じておけよ。シーツに噛み付いたまま決して舌を噛むな。死ぬ程痛えだろうが死なねえ程度に加減する。我慢しろ。俺を齧りも出来ねえおまえが悪い」
「は、…?」
リヴァイはブレードをエレンの背から横腹に掛けて振り下ろす。曰く──まったく残念だ、と。
「ひッ!? あぁっぐ、ぁあ゙あ゙あ゙あ゙あ゙あ゙あ゙ッ──」
断末魔の叫びをあげてのたうつエレンに冷静に指示を出す、リヴァイは靜か血飛沫が壁と床を叩く音を聴く。思い知れ、と思った。エレンに対し、リヴァイにしか選べぬ、選び取る外に選択肢がひとつしか無いものをエレンは重く思い知るべきなのである。
「そのまま口を開けていろ、エレン」
「ひぁ、あ、あっ、ぐ、んっ、んあ、」
「言い忘れたが、目的意識を持つなよ。何も考えずただ飲み込め」
痛みと衝撃に喘ぐエレンの髪を掴んでその顔を上げさせる、洗ってからそう経っていないリヴァイの手は斬り裂いたばかりのエレンの生々しい傷口を抉りそこにある肉を血液ごと鷲掴んだ。シチューをそうしたようにエレンの口内に捻じ込むと咀嚼する暇も与えずに飲み込ませ、次の肉を同様に捩じ込んでは食わせていく。どうせエレンの躰は復元する。ならばエレン自身の血肉であろうと同じことだろう。そう、あたりをつけていた。それでも出来得る限りはそれを避けたかった。リヴァイが自分の身を齧らせようとしたのは伊達や酔狂からでは無かった。だがもう。もう無理なのだ。こうしてこうすればこうなるものだと知りつつ、そうした。だからまさに今目の前で、こうして、こうなった。ならざるを得なくなったのであった。ひく、ひく、と小さくしゃくり上げるその合間合間に、苦しげな呼吸音を漏らしながら、それでもエレンは恍惚とした表情で口のまわりどころかシーツや床も盛大に血まみれにして、食事を、している。
「ちょっと待ってろ」
自身の血のなかで歯を食い縛り泣きやまぬエレンをそのままに、リヴァイは地下室から出て行った。エレンは黙りこくっている。激痛に悶絶しながら、しかし、空腹感を満たす匂いに酩酊しながら。
巨人としても生きられずに、人間としても生きられない。迷いたくて迷えない。何ひとつとして決められない。だがすべてをリヴァイに委ねきることは出来れば楽になるのかと試してみても無駄だった。少しも楽になどならない。苦しみだけが嘆嗟いや増す一方であった。
エレンは、やがて戻ったリヴァイが地下室を出たときと同じ格好で同じ体勢で、鉄の異臭で噎せ返る地下室の血溜まりのなか壁に寄り掛かり、ぐったりと、緋色に染まったベッドに突っ伏していた。エレンがそのまま死んでいれば互い、真実に諦めもついたろうに、傷口からは蒸気が発生し早くも修復作業が始まっていた。一先ずリヴァイはエレンの手当をする。念の為に持っては来たものの、止血剤は要らなかった。陽を浴びられぬ生活で一層白く、蒼白くなっている筋肉の落ちた痩身に包帯を巻いてその耳元へと囁きを吹き入れる。
「エレン」
「…………」
「生きたいと言え」
返事は、肯定も否定も返らなかった。頷きのひとつさえ。横に振る首ひとつさえ。いったいいつになったら、終いが来るのだろう。同じことを考えている。ずっと。或いは初めからそうであったのかも、知れない。気が狂ったかのように自らの体躯を手弄りその未成熟な自身の肢体を、胸を、腹を、頭を、そうして順繰りと撫でまわしてみる後になって、漸く大きく深い呼吸をして、それから暫くし安堵した顔で再びベッドのなかへ潜り込む。それを、リヴァイは直ぐ傍でエレンの薄い肩越しに眺めながら何も言わずに、やがてまたベッドを軋ませ沈む背を、心底、穢らわしいと思い、憐れだと思い、憐れんでやることすら勿体無い程憐れ以上に憐れだと思い、そうしていつしか、この分かり易く可哀想な化け物の躰はほんとうに狂っていくのだろうと云う確固たる確信と、はやくそうなれば良いと云う思いも共々。ふたりして棄ててきた真っ当さを今更惜しんで何になる。
「諺はわかるか、Sprichwortだ」
「……わか、ん…な、」
「Der Mensch ist was er isst.」
「人間、とは…食べるもの…そのもの……?」
「人間はそいつが何を食うのかでわかる」
「…嫌味ですか」
「俺はな、エレンおまえが、死にてえと言うんならもうそれで良いと思っている。好きにすりゃあ良い。但しそのときは俺が傍に居るときにしろよ。死ぬなら目の前で死ね」
「は…、はは…そんな、の、」
この地下室に縛られた日がつい数時間前のことのように思える。リヴァイはいつだって正しい。エレンは狂笑する。
「……絶対に止めることを前提にしないでくださいよ…そんな話。──ねえ、兵長」
何に迷うか決まらないのは。迷っていたいからだった。でも迷いたいとは思っていることも嘘では無い、嘘では無いが、どうしようとも何に迷おうか決まらないのだ。いったいいつになれば、終いが来るのだろう。いつになれば。
「兵長、は…、分かり易く憐れな人です。こんなになっても……こんな、化け物より化け物になった俺をそれでもまだ、どうにか生かそうとして」
「それの何が悪い」
「悪いですよ。可哀想です」
「おまえよりもか」
「俺がずっと後ろ手に拘束されているふりをしていたのは、あれは、ふりじゃあ無い。いつでも俺は、貴方の前では抵抗せずに、貴方に、この身を傷付けられたかった。最期に俺を殺すのは貴方が良い」
「は。相変わらずイカレてやがる」
「…そうですね。だけど、俺にそうさせていたのは貴方です。兵長。すべて貴方のせいだという意味じゃ無い。だから、抱き締めて貰えませんか。背骨が折れるくらい。つよく」
「それは、抱き締めると言わねえよ馬鹿」
「どうせ勝手に修復します」
「治癒を繰り返せば繰り返す程、修復能力は衰えていくことは実証されている。おまえが死に近付くとわかっていてそうしろと?」
「はい。それで、どうせなら、俺の食事も、ブレードで斬るんじゃあ無くって、貴方のその手で傷付けられたい。抉り出されたい」
「それなら食うのか、エレン」
「Mit Liebe erreicht……」
嗤いながらエレンは呟く。互いの滑稽さに頭が酷く痛んだ。鎮痛剤は飲んだって仕方が無い。そんなものに治まる重痛では無いのだ。諺くらいエレンでも知っている。
「わかった。次からはこうしよう」
リヴァイは表情を変えること無く、エレンの左胸を手刀で貫く。穢らわしい返り血と飛散する血潮、裂けた傷口から、だくだくと溢れ零れいくエレンの生命。
「っ……ふ、…ッぐ」
指先に当たる内臓を握り締め引き抜けば、ごぷり、とエレンの唇からも溢れる。
「痛えか」
尋ねるリヴァイにエレンは首を振る。口端より赤い泡を零しながら、唇の動きだけで告げる。へいちょう、と。
「何だ」
『し』『あ』『わ』『せ』『で』『す』──微笑んでそんな台詞を吐く忌まわしき子供の口のなかへとリヴァイは掴み取った臓器の破片を突っ込んで飲み込ませた。もう黙れとその首を蹴り落としてしまいたかった。憐れ過ぎる程憐れである化け物が、リヴァイとエレンのどちらだかも、もうわからない。放置しようが何事も無かったかのように穴が塞がってしまう勝手な痩身を抱き締めると、リヴァイも勝手に舌打ちがついて出た。
「…汚えな」
エレンの血で汚れてしまった服を脱ぎ捨てバスタブに叩き込む。自給自足にだって必ず限界がやって来る。そのときにエレンが他人の肉を食えるか否かが目下、今後の課題となった。
ここまで互いに血だらけなのだ。構うまい。エレンの手がリヴァイを赤いベッドへ誘う。不快極まりないそこで互い何を確かめ合おうとする。エレンの心臓の音に耳を澄ませる。まだ。動いている。エレンはリヴァイに擦り寄る。まだ。生きている。だったら縺れ込んだベッドの上ですることなど決まっていた。ひとつしか無い。血が乾き碌でも無い唇でキスを交わした。いったいいつになったら、終われるのだろう? 鍵の開いた地下室からどこにも行けない。ほんとうはもう、手すりの無い階段を悠々と裸足で駆け上がってゆける躰では無いので、目を閉じて嘱望する更地の世界の大嘘に、気付いているふたりが失笑に値するのだ。上記のようにどうしようもないことを嘆く存在は互いに生きる糧となる。よってリヴァイはこれからも花に血をやるしエレンは有りもしない光を与えられていようとする。エレンが言い掛けて辞めた言葉はその夜以降、2度と、互いの口にのぼることは無かった。ただ確知しているものは微動ともせずに、もう無理なのだ、と云う事実だけなのだ。
Mit Liebe erreicht……────。
荒々しい男の下で少年の嬌声が響く。折檻のような後ろめたさは何れ程の夜を越えようとも慣れないが、数字を数えるのを辞めてしまってからは日付も何も数えない。数えたら負けてしまう。それが死であるのか生命であるのかはどうでも良い。そこから損なわれゆく何かを行儀悪く零していく。進行している。ネイビーブルーの瞳を持つ男がそんなふうに言うとき、殆ど完璧だと呼んで差し支え無い。今日も少年の狂気は美しくその蜂蜜色が蕩けるさまは綺麗だから、淡い面影は少しずつ失われる。遠いいつかを睨み首輪をして、夜闇かどうかも確かめぬ、歪つな求愛は純粋に汚い。
Mit Liebe erreicht man mehr als mit Gewalt.
愛は、力より、強い。それが自分の命さえ賭けずに、心に暇が有る誰かの戯言に過ぎないものだったのだとしても。憐れさに意味など無い。生き永らえることに意味など無い。死骸となり腐りいくことに意味など無い。喰らうことにもその逆にも意味など無い。寂しさに意味など無い。厭うことに意味など無い。何より、愛に意味など無い。それで漸く終われるのだと、知っているから終われと願って終えられない。永きに耐えた穢らわしき生命が今宵もへばり付き剥がれていかず。夜通しに手繰り寄せもしないまま、訪れる明朝にまた気が狂う。きっと気付かなかっただけで元よりヒトは巨人など存在しなくとも家畜以下だったのであろう、でも生まれてしまった濁悪。ずっと捜しているのは、いつも、正しい呼吸の仕方と、今日とは違う明日だ。それなのに、今日とは違う明日はどこにも、可笑しな程に見当たらなかった。いったいいつになれば、終われるのだろう。毎日。毎日毎日毎日毎日毎日毎日。薄暗い地下室に光など届かない。愛ならもっと届けられない。陽も昇りきらぬうちの、夜明け前が、1番、噬斉にてむごい。
ほのぼのリヴァエレの伝道師『よもぎ餅』のあすみさんが描いた痛く重い愛のイラストに衝撃を受けて。ざざざざ、と、その場で私の脳内に湧いた圧倒される程のインスピレーションと高揚感を、はやく、はやく、文章にしたい!と思いながら、此度漸く形にすることが出来ました。つまりあすみさんのおかげで書けたと言っても過言では無い…!あすみさん、ほんとうにありがとうございました!どうか受け取って頂けると幸いです。ていっ(ノ^_^)ノ”(愛)
<概略>
リヴァエレ/監禁/血表現・嘔吐表現有り/微妙なグロとカニバ/
鬼畜、SM、DVだけが痛い愛では無いと証明しようとしてラブくなりました。

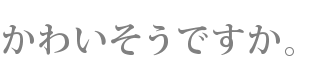
何に迷うか決まらない。迷いたいとは思っているのだが、何に迷おうか決まらないのだ。エレンはずっと己が尖ったふりをしてきた自意識があった。その実なまぬるく、我儘で、脆く頑固で、泣き虫で、半端な破壊願望に捕われて。そうでも無ければ生きられないと思い込んで今まで生きた。だから証明出来ない。エレンは今日もエレン自身を欺いているのかも知れない。証明され得ない。だからエレンは昨日エレン自身を死なせたのかも知れない。
「生きたいと言え」
なのでリヴァイにそう命じられたそのときエレンは、特に何の他意も無く、はァと濁して、曖昧に頷くことで流した。生きたいです、とは言わなかった。それが然こそ劣等であったのかも知れない。おそらく最後の壁外調査となる──壁外に居る巨人と直接闘うのはこれで終わりになるだろうという意味で──予定されている作戦は巨人化したエレンを餌に、群がる残り少ない巨人たちを一斉討伐すると云うもので、即ちエレンはいつかの如く足止めと生きたまま彼ら巨人たちに喰い尽くされる重要且つ不可欠な役を担うことになる。無論104期生を始めとする決して少なくは無い仲間である兵士たちからは非難の声があがったが、エレンはただ、永く続いた仲間たちの命の遣り取りが取り敢えず漸く落ち着くだろうことのほうに晏然としており、来たる作戦執行の日を前にして、あと何日くらい生きていられるんだっけ、と指折り数えながら平静的に日々を過ごし、憧れ敬愛し続けてきた兵士長に、部下として命の最期に何か、ひと言ふた言で良いので言葉を掛けて欲しかっただけであったのだ。兵士として生きて死ぬ者たちの左胸に心臓が無いようにエレンの左胸はがらんどうで心はどこにも無く、どこにでも有る。それが躰のなかの、どこであるのかがわからない。誰にも心臓を捧げぬリヴァイとは違いエレンの心臓はエレンのものでは無いのだ。人権も尊厳も根刮ぎ失って日々を経てきた今になり、何がどうしてこうなったのかと。誰も彼も拾うより手放す瞬間を快感と感じるよう造られた筈だった。
一見鋭利さだけが目立ち解り難いがよく見れば深く優しい色をしているリヴァイのネイビーブルーの瞳を覗き、そこに有るべき厳しさを求めたエレンにはリヴァイが何を考えているかなど考えもしていなかった。し、エレン自身、自分でも自分が何を考えているかをいまいち理解していなかったのだ。それにまさか規律も指示も約束も律儀な程に守り通すリヴァイが、このような謀反的とも呼べることをするとはまったく思い付きさえしなかったのである。
と云うわけで、エレンは己の命日になる筈であった日を、旧本部の古城でも無く無論調査兵団本部や審議所でも何でも無い、いったいここはどこなのか心当たりも無い、見知らぬ薄暗い地下室で迎えた。土壇場で起きたエレン・イェーガー失踪事件。兵士としてこの上無く不名誉なことに幾ら尖り吠えてはいても所詮齢15の少年兵、怖気付いたエレンによる逃亡かとも思われたそれをエレンは知り得ない。だが勿論それは、断じてエレンが自ら望み選んだわけではまるで無かった。死ぬために壁外へ行くのでは無い、救うために死ぬのだと、その前日、各兵団を掌握している上層部による温情によって、丸1日もの休息日となった。最期の。準備を終えたエレンはリヴァイの執務室へと自然に脚が向き最期の言葉を強請った、そんな殊勝なるエレンの後頭部を首ごと刈り取る勢いで蹴り上げて、昏倒させ、エレンを攫い拉致したのは兵士長たるリヴァイその人であったのだからエレンにはわけがわからない。
繰り返すがリヴァイという男はそれが如何に非人道的であったとしても、果たして自身が納得のいくものであれば、例えそれが最愛の恋人や妻子を殺す結果になろうと迷わずブレードを翳し振り下ろす男である。ましてやエレンはリヴァイ直属の部下には違いないが同じく生死の腹を括っている調査兵団組織の兵士なのだ。恋人でも無ければ妻子でも無く、生き別れで出逢った弟なぞと云うオチも無い。ただ性的な躰の関係ならば持っていたが。それも皆目、甘やかな逢瀬では無く時々互いに性欲を発散するためだけの、自慰行為の代用に過ぎぬ、単にそういうものだった。上官と部下で在りながら、監視役と監視対象で在りながら、ふたりがそういうことをする間柄になったのは、丁度ペトラたちの居た精鋭リヴァイ班が壊滅してしまってからだ。正確には思い出せない。それでいて丁度、などと云えるのはそれがいつまで経っても泣きやまぬエレンが、彼らの遺品をせめて遺族へ届けられるようにしたいとひとつひとつ大事そうに握り締め整理しながら、目を伏せる度に蜂蜜色の双眸を隠す、瞼を、真っ赤に腫らしていた介然たる姿に、リヴァイのほうが我慢ならなかったからであった。どう考えても真っ当では無い。けれどもそんなことを言い始めれば、真っ当かどうかなど引っ繰り返せば左右も前後も容易く変わる盤上の正義と均しく、どうでも良いことでは無いのかとリヴァイには思える。ひとりにつきたったひとつ限りの命を犠牲にすることが、それで大勢の人類の未来のための礎と成ることが、尊いだなんて戯言を、自らの命さえ賭けもしないで、誰が決めた。かたく信頼を寄せた最早数え切れない部下たちや仲間たちが無惨に殺されていくのが赦し難くて、巨人の正体が人間であったと解ってからも殺戮をやめなかった。殺戮は日常とイコールに、調査兵団に入団するよりずっと以前から、それこそ物心がつく頃からリヴァイの手は殺戮による穢らわしい返り血でいつも汚れていた。何れ程丁寧に洗い拭っても拭っても、それはずっと纏わりつく。おそらく死んでも。だから1番手近に存在し、1番死に急いでいるが1番この世界で、敵からも味方からも欲され必要とされ、つまり、1番死にそうに無い子供をリヴァイは自らの傍らに置いて寝るようになっていた。手っ取り早く。易きにつきて。そういうことであるのであれば、そういうことで良いと、エレンはすんなり受け入れた。互いにとって大切なのは、なるべく死なないものが寄り添うと云うことだけ、それに尽きた。だがそれは思うより意義深かった。その点では互いに幸いにも、相手を、1番手近な、1番、殺しても死ななそうなものだと、同じことを考えていたわけである。しかしながらまだ多少暴走気味に突っ走る傾向が有るエレンは、追い詰められると何を仕出かすか予測しづらい。とリヴァイは思っていたのだが、存外、癇癪を起こすことも無く、エレンはあくまでエレンだった。
「…あの。兵長」
エレンは上官であるリヴァイが手ずから整えた清潔なベッドの上で、両手を後ろ手に束ね碌に身動き出来ぬ状態でそれでも尋ねる。自由に動かせない。動けない不自由。ベッドの足許へと伸びている長い鎖がじゃらんと哭くがそこに繋がれているエレンの首輪はきつく締められてはいないので、然程、見目程の息苦しさは無い。寧ろ態々首周りを測り誂えたかのような剴切さだった。
「兵長、兵長、兵長って、」
「…うるせえな。何度も呼ぶな。何か用でも有るのか」
「用…っていうか……ええと…俺も躾覚悟で、失礼ながら申し上げますが。兵長、今、頭の悪い俺から見ても、残念過ぎるくらい、すっげえ頭悪そうなんですけれど。まるで悪夢でも見ている気分です」
ベッドに腰を掛けながら脚を揺らしているエレンの顎先を、未だ反抗期を脱していないエレンよりもずっと長くも過酷なる、道無き道を闘って進んできたのだと触れるだけで理解る、リヴァイの節榑立った無骨な指が緩慢に、丁重に、つうと撫でる。
「……あァ、残念なことに、俺自身、そう思う」
その言葉にエレンは悲しい程はっきりと蜂蜜色の瞳を攪動させた。その理由さえリヴァイにも理解りきっていた。
「でしたら。いつもの、聡明でつよくて、実は情に厚く巨人討伐は勿論、あらゆる才能に溢れた人類最強兵士であるリヴァイ兵士長に、はやく戻ってください。お願いですから」
「は。誰だそれは」
「貴方以外にそんな超人が居るわけ無いでしょう、兵長。ていうか兵長は、作戦において団長の判断には全面的に従うんじゃあ無かったんですか」
だがエレンはリヴァイが成し遂げた努力を悉皆にも知らず、リヴァイはリヴァイで何も説明さえしていない──しないでいられる限りはしたくない──ので、似合わない仏頂面をしたエレンから不満顕わに問われるのは仕方が無い。エレンは長い鎖で繋がれベッドの脚に結わえつけられている首輪の先を如何にも億劫そうに蹴っている。
「エレン、顔を上げろ」
「別に俺、俯いていませんが」
「違え。俺の顔を見上げろっつってんだ。クソガキ。目ェ逸らしてんじゃねえよ」
「……Jawohl , Herr Levi」
イエッサー、リヴァイ殿。
態と嫌味を込め恨みがましく、敢えて上官命令に従う部下らしく応えたエレンの逃れられない唇に、溜息をつきそれでもリヴァイは口付ける。ただのバードキスでは無い。舌を捩じ込み割った歯列の裏側から頬裏の粘膜までこそぐような、あついディープキスだった。それは旧本部の古城にてセックスに及ぶ際でも、そうそう滅多に落とされた覚えもあまり無い、喰いつくような口付けだ。途端狼狽するエレンにそのまま腰を押し付けてきたと思ったら押し倒され、そうやってリヴァイはエレンの躰の上に乗りかかり、らしくも無く非常に退廃的な表情でぐしゃりと皺になる程乱暴な仕種で自分のスカーフを握って引き抜く。
「えっ…兵長?」
警戒もせず呼び掛けながら、エレンは、やべえどうしようこれは本格的に兵長まじなんじゃねえのかよ、と思い痩身を強張らせた。まさかと思いたくも無い悪い予感が頭を過る。兵長は本格的に団長に──ひいては調査兵団や人類すべてに背いて俺を監禁するつもりなのかも知れない、と。
「そのクソ生意気な口は、幾ら躾けてやろうがいつまで経っても覚えが悪ィな。おい、エレン」
「はっ、…なっン、っ……ん、んぁ、あっふ……兵、長っ!」
深い口付けに気を抜けば意識を奪われてしまいそうなさなか、あれ? ちょっと待てよ、まじでこの人ほんとうにリヴァイ兵長なのか? 俺の知っている兵長で合ってんのか? 実は兵長のそっくりさん、とか、馬鹿か俺はこんな人が他にも居て堪るか誰だあんた。ふと、だがエレンはわりと真剣にそう思った。だって今までに及んだセックスは、いつも、どのようなときも、エレンが耐えきれずもう無理ですと泣いて拒まざるを得ない程度に、リヴァイは戦闘時と同様、発情すれば遣り過ぎるきらいはあったのだけれども、エレンの見てきた上官としてのリヴァイは地下街出身ゆえにまともな教育を受ける機会が無かっただのと宣うそのわりに、エルヴィンやハンジたちと代わり映えしない如何許りか頭がキレて機転が効いて、その場その場で要領良く合理的に対応する柔軟さも持ち合わせており、何より、言葉にも文書にもしないエルヴィンの真意まで正確に見抜き、読み取り、理解し、先々を見通し実行する、実戦では言わずもがな誰も追い付けぬレベルの実力派であって、商会を牛耳っていた基本的に金銭契約以外は信用しない肥え太った商人さえも、信頼に足る男だと賞賛したらしい程、常に任務に忠実であった、あのリヴァイが。そんなリヴァイが最後に必要だった作戦に使用する兵器であるエレンを掻っ攫い監禁している。などとそんなことは有り得ない。有ってはならないことだ。あまりの不審さに認められぬ思いを抱え込みながら、避けようも無く執拗な、深過ぎて息が詰まる口付けを受け取らされ、舌を絡め取られるがまま、エレンがリヴァイのブーツの脛あたりを裸足で──この地下室で目を醒ましたその時点でエレンは全裸に剥かれていた──とん、と合図のように軽く蹴るとリヴァイは驚愕した顔で漸くエレンから唇を小面倒に離した。視線が交わるとリヴァイもまさに、もしやおまえエレンじゃねえな? おい、てめえ本物のエレンをどこへやりやがった、とでも今にも吐き捨てそうな、疑心に満ち満ちた奇妙な表情を浮かべエレンを見ていた。そうなのだ。有り得る筈が無いのだ。本来のリヴァイが兵士長としての職務を放棄し、エレンを監禁なぞしないように。本来のエレンも兵士としての本分を放棄して、おとなしくリヴァイに監禁されたりしないに決まっている。だがそれにも拘らずふたりは結局そのまま色事に及んだ。火の点いた官能の濁流に抗う術無く呑み込まれる。動く度無粋にも錆びた音を立てる鎖へと、じゃらじゃらじゃらじゃらうるせえんだよクソが、などと自分で付けたくせにエレンの首輪から伸びるそれを邪魔臭そうにしていたが、リヴァイは最後まで、エレンを繋いでいる首輪の鍵を開け外してはくれなかった。けれど首輪を外す以外のことは何もかも全部、全部して、エレンを自力で浮上出来ない快楽の海に溺れさせた。理不尽にもエレンには、てめえが勃たせろと、容赦無く喉奥にペニスをぶち込み叩き付けてでもさせてきたくせに、その逆はいつだって、そんな汚えもん舐められるかよ、のひと声で絶対にリヴァイ自らはしようともしなかったフェラチオすら、した。普段から兵士らしからぬ佇まいである潔癖症で、性行為の最中であっても零すことを赦さない、アナルにペニスを突き入れられると直ぐに足腰から力が抜けて教え込まれた悦楽に、ぐにゃぐにゃになってしまうエレンとは真逆にも、絶倫な程続く体力で汗ひとつかかずに常々涼しい顔でエレンを苛んできたリヴァイが、このとき初めてエレンにも解る程の汗を均整の取れたその全身に滲ませ、懸命に、エレンの尻孔の内側、排泄器官に在るエレンの悦いところを探るよう動いて、エレンが何れだけ耐えようと堪えようと、喘ぎを奥歯で噛み締めてもその都度目敏く奥の奥まで穿ち、だらしのない若いペニスから迸る涎のような先走り汁と、達する度に散ってしまう、否応無き精液による汚れさえ咎めること無く抱く、優し過ぎる愛撫と激しい劣情の連続にエレンは意識を飛ばした。まさしく為落され巨人のことも作戦のことも頭から無理矢理に締め出されそうになる程、目の前が皓白に塗り潰される威烈なまでのセックスに、エレンはぐずぐずに蕩けて蕩けまくったのだった。
そうして、それから始まった監禁生活は数ヶ月にも数年にも把握出来ぬ期間に及ぶこととなる。
その間、リヴァイはずっとそのように努め、一途で、献身的に、今や手配書が出回っているエレンへと接していた。1番手近で、1番、死ななそうな相手。手っ取り早く。易きにつきて。女では無いためどう扱おうと孕む心配も要らず。合意の上であるので面倒も無い。それらはきっともう誰にも通じぬ言い訳となった。エレンは、実はこの人はほんとうは物凄く、物凄く、俺を欲していたのだろうか、欲してくれていたのだろうか、そんな馬鹿な話があるかよ嘘だ全部、と、監禁初日の翌朝、重くて立ち上がるどころかベッドの上で身じろぎするのもままならぬ、しかしそれでもまだ甘さの消えない腰をさすりつつ、不様に小さく唸りを漏らしながら、やっと気付いたのだった。腰と云わず首許と云わず尻と云わず喉も頭も全部含めて、体中が、叫びだしたい程到堪れずに、痛かった。
1日に1度だけ、必ずと云って良い頻度で、リヴァイはエレンへと食事と水差しを持って訪れた。それすら出来ないときは日持ちのする携帯固形食を、封を切り犬でも齧り付ける状態にして、多めに置いていく。監禁したエレンに対しいたずらに空腹感を与え態と何日も放置してみたり、暴力を振るってみたり、罵倒してみたり、等々の支配的な行為は一切しなかった。ばかりか暫く来られなくなるときには、それがどのくらいの日にちでどういう理由からであるかをいつも言い置き、約束をやぶることは仮にも倦憊する様子も無かった。監禁されている地下室の隅には小さめだが立派にバスタブが設置されており、そこにある壁に引っ掛けられているシャワーホースからは真水も適温の湯もきちんと出る。贅沢品である石鹸やら、ふかふかのタオルやらまで揃っている。ベッドから繋がれている首輪についた鎖は絶妙な長さで、エレンが跳ねてみようとも換気扇と出入り口にだけは届かない。ただ、後ろ手のままでは何れもエレンひとりではままならないため、リヴァイがエレンを驚く程優しく壊れ物を磨くような手付きで、背丈ばかりの未発達な躰のその隅々までを泡立てた手のひらでやわく包み撫ぜて清潔に洗い、トイレの世話までこなす。至れり尽くせりにも程がある。ベッドの傍にはご丁寧なことに深みのある簡易トイレのような、貴族が飼うペット用の吸収剤を敷き詰めた専用容器と、柔らかく上質な紙を切らさず用意されていた。勿論その取り替えすらリヴァイがするのだ。どうしてここまでするのだろう、エレンにはまったく意味が理解らなかったが、鎖の長さはエレンの身長と跳躍力から割り出された正確さで地下室から出られない。折につけ、リヴァイはエレンが望めば新聞を読み聞かせてくれるなど、甲斐甲斐しく、あたかも年端もいかぬ主人に仕える執事にでもなったかの如く、只々エレンに尽くす。外の情報を知り得ることはエレンにとって暇潰し以上に随分と有り難く意義の有ることだった。予定されていた最終決戦なる壁外調査は、エレンの不在により中止されていて、仲間の誰かが危険にさらされることも命を落とすことも、無かったらしい。それを知れただけでもエレンは胸を撫で下ろす気持ちであった。その上、当初は逃亡したと見られていたエレンの扱いも、新聞によるといつの間にか新たな組織による誘拐、拉致、となっていた。それは、別に新たな組織による犯行では無いと云うだけで、何ら間違いでは無いので、エレンとしては、へえ、と呟くくらいしか出来ないのだが。しかしてそのせいで調査兵団が、エレンの捜索に尽力しつつ通常任務や訓練をもこなさ無ければならざるを得なくなっている、と云うことについては吹っ切れぬ申し訳無さに罪悪感が募る。
兎に角エレンはリヴァイによって監禁され、そしてリヴァイは殆ど毎晩、可能な限りエレンの元へやって来ては食事から排泄まで世話を焼き、エレンを抱いた。古城に居た頃ですらされたことの無いことをされている。それでいてリヴァイは昼間、調査兵団の兵士長として行動し、誰の目にも、行方不明になった部下で有り調査兵団の最終兵器でも有るエレン・イェーガーのその身を案じながらも捜索を続ける、と云う無駄で無意味な演技を続けなければならない。そう思えば、よく心身共にもつなァ兵長タフ過ぎる、とエレンはいっそ感心さえしてしまう安穏とした非日常だ。けれど、も。
「兵長。いつになれば俺をここから出してくださるんですか?」
ものには限度と云うものがあるのだ。或る夜1度、セックスのあとで試しに尋ねてみれば、リヴァイは鬱陶しそうに舌打ちを響かせ、それまでエレンに覆いかぶさるようにしてベッドについていた手を離し美しく筋肉のついた小柄な躰を起こした。
「ふつう、そういう質問は初日にするもんじゃねえのか」
「兵長のことですから何か凄く特別な秘策や目的が有ってのことなのかな、って。でもどうやら違うようなので」
「あァ、違う。なら──俺が、エレンおまえを監禁することで独占したいだけだ、とでも言えば信じて納得するのか?」
「そもそも俺は兵長を敬愛はしていても、貴方のつよさ以外は信じていません」
「口の減らねえガキだな。何れだけ躾けても躾がなってねえのは、俺の責任か?」
「…赦されませんよ、こんなこと。幾ら貴方が兵士長であっても。つうか俺としては、とっとと巨人を殲滅したいので、はやく出して頂きたいんですが」
「元々おまえみてえな死に急ぎのクソガキなんざ居なくとも、俺が居ればあの程度の数の巨人、殲滅出来る」
「う、わァ……」
「何だよ」
「いや、嘘でしょう。嘘だ、勘違いだ。心から、俺の勘違いであって欲しいんですが。…まさかこの監禁、俺を殺されたくない兵長の、や、優しさ? とか云うやつ、ですか」
「今頃気付いたのか?」
「え、えー……? やっべえ…鳥肌立つくらい気持ち悪い」
「てめえの自業自得だ」
「何を仰っているんですか。兵長。…本気で気持ち悪いです。吐き気がします」
優しさ。優しさだと? それは独占欲よりずっとたちの悪いものである──エレンは全身に戦慄が疾る感覚を覚えた。正直に云って怖かった。リヴァイが何もかもを賭している。怖過ぎて、拘束されている現状に、勝手に怯える躰の震えが一向に止まらない。怖い。だが、怖い、という感情はつまり、自分に価値があると信じているから沸き起こるものであるのだ。信じられない、とエレンは思った。そんなものは疾うに、棄てたつもりでいた筈だからだ。女型に班を壊滅させられ、正体を暴かれたアニを追い詰め壁内で闘ったとき同時に、信じること自体すら、あの破壊された地下道に棄ててきた筈だったのだ。エレンはそれが怖くて、怖くて、仕方が無い(だって何をどうしようがそんな、そんなきれいには、いかない)。花では無いのだ。煽るように吹き荒ぶ風に弄ばれ、希望の光にも似た何かに、彷徨わされていただけであったのだとしても。はらはらはらりと、儚くきれいに散ることも出来ない。そう望めば望み通りに棄てることが出来るのだと思っていたのだ。何だって単純明快に手放せるのだと、それはまだ何も知らずにいられた先刻までのことだ。エレンはリヴァイに、生きたいと言え、と命じられたあのとき、生きたい、とは思わなかった。そんなことよりも、もう少しで仇が取れるのだと、もう少しで死ぬことを赦されるのだと、思い浮かべるその歓喜に目が眩みそうな愉悦を持った。それなのに。
エレンは考える。自分は、リヴァイの、まだ何を信じていてみたかったのだろうかと。まるで呪われているような地獄の門の手前で、用意された死へと堕ちていくのはまったく少しも怖くなど無かったのに──そうだエレンは今、リヴァイに鮮々しく恐怖している。
「……まともじゃ、無い」
震える声でエレンが言った。リヴァイは、はっ、と、馬鹿な子供を鼻であしらうように、嗤う。
「貴方は。…こんなのは、まともじゃあ無い……それくらい、貴方が最もよく、理解っている筈です。兵長」
「さァな? どうだか。おまえは俺を買い被り過ぎている。エレン。おまえは今、俺がまともじゃあ無いと言ってやがるわけだが、だったら、この世界で何がまともだったんだ? 俺はおまえの倍以上の歳月を生きちゃいるが生まれてこのかたただの1度も、未だにまともなものを見たことがねえ。なァおい、この世界にまともなものが、ひとつでもあったか?」
「少なくとも、俺が敬愛し続けていた兵長は、まともでした。でも、今それについては訂正します。──俺は、兵長を、貴方を、敬愛していたんじゃ無い、畏敬していたんだ」
束の間の大袈裟。くそったれ。巨人化する化け物として罪深く生きてきて、せめて最期くらいは誰かの役に立つ死に方で死ぬつもりでいたエレンを今更、人間だと思ってどうするのだ。
兵長、貴方は俺に。
「さっさとくたばれ。と、貴方は俺に。そう言うべきだ」
眉のひとつを顰めるわけでも無く首を振るわけでも無く、視線をリヴァイから外さずにじっと見ている、蜂蜜色の、大きな瞳。だからどうしようと証明出来ない。信じるほうが楽だなどと云うことが証明出来ない。あと何回を繰り返せば騙されないだとかそんなことすら。
「優しさは要りません。無意味に生かしたまま、腐って死ねってことですか。俺は、そんなこと1度だって、望んで無い、のに」
何なら土下座したって、構わない。その程度には。エレンが知るリヴァイとはそんな人間ではいけないのだ。どういう方法でも良い、エレンを痛め付けて、踏み躙り、時として嘘をつくような愛し方で。エレンにとって痛みを感じると云うことは、生きている実感を齎す実に簡単な方法なのだ。だからそうしていて欲しかった。リヴァイに優しくされる、その惨めさに泣きたくなる。どうか呼ばないで欲しい、愛さないで欲しい。エレンはリヴァイへとそれを伝えるためだけにこの場に存在しているのだ。いつか満たされるような、そんな謙虚さは生憎持ち合わせていないのだからと。
「成る程。まともじゃねえのは、てめえのほうだろう。違うか、エレン。まずはクソみてえに馬鹿げたハンストを、いい加減よせ。苛々する」
「してませんよ。ハンストなんか」
「ほう、よくもそんな虚言を吐けるもんだな。なぜ何も食わねえ」
「俺には必要の無いものだからです」
決然と言い放ちそれから視線を緩く逸らす、エレンは無駄に無意味に生き延びることには興味も無いしそれが生命ならば欲しくも無いのだと云うことを、宛ら、リヴァイにならば絶対に理解されるものである筈だと言外にはっきりと伝え続けてきたのだ。それがエレンによる、リヴァイへの精一杯の甘えなのでは無く、ただ呆気無く信用を棄てた傲慢であるのだと。いつだったろう、リヴァイは知っていた。気付いていた。それさえ見過ごしてきてやったのだ。こんなにも──永く。
リヴァイが提供し続けた食事をエレンが食べようとすることは無かった。1度も。無体に力任せに、スプーンを口のなかへ捩じ込もうともエレンはそれを飲み込まない。仕方が無いのでセックスの合間、キスといっしょに口移しで水を飲ませてはいたが、上官命令に替えようとそれだけは拒絶する。エレンは知ろうともしないのだ。リヴァイを舐めきったその蜂蜜色の眼球を抉り出して冷たく固い石床へと引き摺り倒したい、激情を、リヴァイが何れ程つよい意志で、堪えてきたのかを。
エレンは狂気と云うものを知らなかった。自身が狂気を孕んでいるのだと、いっそエレン自身が狂気のかたまりであるのだと。知らないままに初めて審議所の地下室でリヴァイに見せた両の目で、壮絶なまでの憎悪にぎらついたような、狂人足る笑みをも有識せずに零していた。それが狂気そのものであるのだと自覚することも無く。それを見ながら、その濁った双眸に見られながら、リヴァイは満足してもいた。そうなのだろう。なぜなら狂気と云うものは、ぞっとする程に、美しい。
「おまえの主張なんぞ知ったことか。俺が食えと言ったら食え。エレン」
それでも1番、食べやすそうである物を無意識に選んだリヴァイの右手は心底可笑しな物体であった。誰が死のうが生きようが何も変わらないのだと告げるようにエレンが居ようと居まいと変わらず同じ日を繰り返し、困窮し続ける世界で、身分の高い者だけにしか行き渡っていないバスタブを初めとする身の周りの贅沢な物品を、どこからこんなものが調達出来ているのかエレンには知る由も無いままに、小奇麗な皿に入った冷製シチューの具を汁ごと鷲掴み、それを捻じ付けるような強引さでエレンの口内に押し込む。とても潔癖症とは思えぬ程に汚くも、その指先とエレンの唇とでそれをそこで散々ぐちゃぐちゃに潰してから腕を引く。まるで血飛沫をきるようにしてリヴァイが腕を軽く振れば、そこからは赤色では無く牛乳とチーズをふんだんに使いつくられたクリームの白い水気と肉の欠片が僅かに石床に散った。もうそれだけで、取り敢えず嫌悪感に一杯になる程たくさんだった。
「てめえは時折、本気で張り倒したくなる程ずっと強情に過ぎやがる。頭の悪いクソガキだ」
言いながらリヴァイは立ち上がりシャワーホースへと歩みそこで手を洗い、拭う。何れ程執拗に潔癖を保とうとも辿り着く先は相も変わらずに、不衛生で、不健康で、不徹底な機械的唯物論。
「……だから、食いたく無いんですって」
「知っている。俺はおまえの上官として命じてんだよ」
「聞けません」
「ここまで譲歩してやったんだ。おまえに拒否権がまだ有るとでも思ってんのか?」
「聞きたく、ありません」
エレンは汚れた口許を拭うことも出来ずに口内に入ってしまったものをそこらへんに吐き棄て、言った。離れたリヴァイがすぐさま近付き、エレンとの距離を詰めてくる。いつだってこんなくだらぬことにのみ互い躍起になる。いったいこんなところで何ゆえ兵士がふたりして、戦のひとつもせずに挙句何をしているのだろうかとつくづくうんざりとするが、いつだってそれらの最中には何ひとつとして何もかもがすっぽ抜け引っ掛からないのだから、酷く可笑しい。エレンはもう少しばかりリヴァイに対し露骨に従順であるべきか、或いはもっと一欠片の感情もリヴァイに向けずに、媚びずにいるべきなのである。
「──だから俺は、作戦決行の前日に、生きたいと言え、と言ってやったんだ」
何が、だから、なのかとエレンは思う。生きたいなぞと思ってもいないときに、生きたいと言え、と言われたところで適当に相槌を返すより外に何があったろう。エレンは口端を上げたまま、リヴァイに、だが淡つかに言う。
「兵長は、俺を馬鹿にしているんですか。若しくはこのすべてが俺を馬鹿にしている行為だと理解っていて、まだ続けるんですか」
「おまえは元から馬鹿な上に頭のおかしい化け物だろうが。おまえこそその目で、俺を馬鹿にしてやがる。不敬罪で吊るしてやりてえ」
「……それもう根本的なところで何もかも間違ってらっしゃいますよ。兵長」
「今更だ。自業自得だと言っただろう。おまえも、俺も」
感慨深くそう言い募るリヴァイに、エレンは唾棄するようにたぶんリヴァイは今更だと思っていないだろうことを思い付く。
「では兵長。もし俺が貴方を心底嫌い憎めば、貴方はどうするんですか」
──その一瞬にリヴァイが浮かべた表情は、とてもでは無いがどうにもエレンには説明出来ない。ただそれはどのように形容しようとしても、エレンが蓋然的に想定していたものとは愈愈違った。
「クソが。……今のてめえにはもう俺しかいねえんだから、そんなことにはならねえだろうよ」
その言葉自体はどう聞いてもおかしいのに、じっとリヴァイの深いネイビーブルーを見ていたエレンにとって、それは然して問題にならなかった。相手の瞳から目が離せない。そのことには互いに気付いていたが、しかしそれまでふらふら迷っていた浮気なるエレンの瞳は、このときにして且つ且つと、リヴァイという人間そのものを理解するために根気よく見据え、見詰めることを、拒めていなかった。どうしても。
要らぬものだと言って幅からぬエレンが何も食べない。それは、エレンが巨人化能力のオプションとして持つ異常治癒力と同等のものであるのだろうと思われる仮説的な能力によって、簡単に云えば、食事をしないことがそのまま直ぐには餓死に直結しないのだから、リヴァイは苛立ちながらも別段、悩んではいないのだ。ただ巨人化しないままでは緩やかに衰弱していく。死がふつうの人間よりは遠くに在る、と云うだけで。しかしリヴァイはそんなことすらどうでも良い、只々只管、エレンのその頑なさが気に入らない。幾らエレンが化け物であろうとも、死ねばもうどこへも戻って来られない。の、に。
生かされる恐怖に震えているのだとエレン自身自覚している、そこに触れずともリヴァイには見透かされている、エレンの、その、手で、掴めるものなど何も無い。それは死を懇望されることよりも、思い付く限りの残忍な方法で殺されることよりも、おぞましくも重々しく、恐ろしく、て。どこまでいつまで互いに互いを愛しているふりを続けられるか。率直な問題はそこにあった。舞い上がる土埃も憎悪さえも無いままに。からっぽ、に。けれど真っ直ぐな臆病さに怯むのは、切り裂かれた過去と暴かれる皮膚の下に潜み在る、最果てだ。
「……なるべくなら話したく無かったんだが。おまえがあまりに喧しく憐れ過ぎるからもう良いだろ。教えてやる」
リヴァイは深々ともう何度めかもわからぬ溜息をついた。呆れさえ既に通り越し思い頽れる程の気分だった。エレンは訝しみながら瞬いた。
「何を、ですか」
「エレン・イェーガー失踪及び誘拐はエルヴィンの指示だ。そこに俺の意思は露とも含まれちゃいねえ」
「………………は?」
たぶやかに間を開けて、間の抜けた表情で、蜂蜜色の眼球が零れ落ちるのではあるまいかとリヴァイに思わせる程に両眼を見開き、エレンは尋ね返した。当然だ。リヴァイは厭いつつ物憂いし息嘯を漏らす。これから自分は大人げも無く、エレンを絶望させ傷付ける。
「最終目的はエレン・イェーガーの存在を大衆に忘れさせることだ。最初から、エレン・イェーガー含め、巨人化する面妖な兵士共なんざ、存在しなかったと事を進められるように。大体あんな阿呆でも思い付く馬鹿馬鹿しい作戦に、狡猾なエルヴィンの野郎が納得して乗ると本気で思うのか? 今までもずっと水面下で、そして現在においても、俺たちがしていることは、夥しく壁に硬化し塗り込まれた50m級の巨人を1匹残らずすべて、壁外の残党巨人共も合わせて、元の人間に戻してやる方法の模索と研究だ。そうするに当たり駆逐脳なおまえは邪魔でしかねえからな、事が落ち着くまでは監禁すると云うことになっていた。だが何も知らねえガキにそれは酷なんじゃねえのかと、幾ら何でも一方的過ぎやしねえかと、態々チャンスをくれてやったのに、それでもおまえは生きたいと言わなかった。寧ろ死んでいくことに歓喜してさえいるように見えた。…つまりは不合格、失格、だな」
「誤魔化さないでください」
初めから。初めから貴方は。俺がどう答えていようとも──。
「すべてが団長の指示だとはとても思えません。もしも仮に、巨人を人間に戻すことが出来たとしたら、覚えも無いまま人を喰らって、俺のようになる奴が絶対出てきますよ」
「だろうな。自傷行為で自ら巨人化する奴が」
「当たり前です。しかも超大型巨人や女型や鎧たちのように、意志と理由を持って人類を滅ぼそうとする奴らさえ出てくるかも知れない。それを懸念しない団長では無いでしょう? 壁内が大混乱になるだけの話では済まない」
「それこそ疾っくに想定済みだ。エルヴィンも、俺も、調査兵団幹部はな。結論から言って、そうなるならなったで構わん。いっそ自分の意志で巨人化して暴れてくれりゃあ、王政も全人類も合わせて何もかも、平等に更地になるだろう。更地になれば掃除もし易い」
「……そ、れは…もう、人類の存続を、諦めるって、ことですか」
「少し違う。が、おまえはそうとしか考えられねえんだろう、エレンよ。だったらもう、それで良い」
「なに、を……何…言って…………ッ何でそんな! そんなことになったら何れだけの罪無き人類が、犠牲になると思ってる!」
「うるせえ、吠えるな。吠えればそれだけ弱く見えるぞ、駄犬。勿論そいつらが民間人を襲いだせば直ちに調査兵団が、俺が、人間やめたそいつらを迷わず削ぎ殺す。だがエレン、これだけは覚えておけよ。人類のなかに、罪無き者なんざひとりも居ねえ。俺もおまえも同様にな」
エレンは以前にリヴァイについて、よく心身共にもつなァだの何だのとリヴァイのタフさに安穏と感心していたが、ぎりぎりのラインでかろうじて平静を装っていたのはいつもエレンのほうだった。昼間リヴァイが地下室に居ない間エレンは、癇癪を起こし暴れまわることこそ無かったが、ひとしきり髪を振り乱し左胸を爪に赤い皮膚が詰まる程掻き毟ってから、瀕死の重傷でも負っているかのように唸ったり呻いたり言葉にすらなっていない何かを喚いたりと相当情緒不安定で、果たしてこのような状態で突然に解放されたとしても、地上で正常な自分自身で有り続けることが可能であるのか、全身が痙攣を起こす程に甚だ疑問で自信も無かったのだ。だがエレンは、リヴァイの前でのみ完璧に欺き通していたつもりでいた。浅薄にも。そんなことは目にするまでも無くリヴァイには筒抜けであるに決まっているのに。嘘も上手くつけぬエレンに、リヴァイを欺くことなど、出来得る筈が無い。
「……ふざ、けんな…!」
握り締めた拳の内側を爪の先が傷付ける。
「それはこっちの台詞だ。てめえこそふざけんな」
リヴァイは徐ろに鍵を取り出し、エレンの目の前に置いた。
「何ですか今更、何のつもりで」
リヴァイはエレンの問いになぞ答えずに、けれどエレンの隣にぎしりと座っていた。身長差ゆえにどうしても上目遣いに見上げることになるそのネイビーブルーの双眸には、いつの間にか、エレンが狂気だと想像していた色が宿っている。もう。何もかもを信じたく無い。終わらせたい。終わりたい。エレンは黙って自分を見上げる三白眼のネイビーブルーを見る。見る、と云うことは同時に、見られている、と云うことと同義だ。リヴァイの舌がべろりとエレンの眼球を舐めた。蜂蜜のように甘そうでいてほんの少しも甘く無い。生理的な涙を含んだ粘膜の、塩っけのある不気味な味しかしない。エレンの手は鍵を拾わなかった。代わり、リヴァイが諦めたようにそれを拾った。そして、ガツン! と音がする程につよく、その鍵をエレンの頭に叩き付けぶつける、けれどもエレンは顔を横に背けただけだった。
「……たぶん俺は、おまえを愛している。と、思う」
リヴァイの薄い唇によって紡がれたその言葉は、エレンを那落へと突き落とした。言われたエレンのみならず、言ったリヴァイ本人さえもが瞠目し、ほんとうに驚いている。自分が相手に対して相手のようになれたなら、楽なのかも知れない。互いに何の興味をも持たなくなれば、互いのことを一縷も考えずに済むのであれば、その姿を見ずにいられるのであれば、楽なのかも知れない。相手が自分や他の人間に対してそうであるように、そう出来るので、あれば。
「無理だ」
たった今エレンに愛を囁いた口のなか、そっとリヴァイは呟いた。静寂が耳に痛い。今の声がこの地下室から外に漏れる筈が無い、けれども漏れなかったのかを知る方法も今は無い、それはエレンにもリヴァイにも判断は付かなかった。諦めの慨嘆が不快な吐息の塊となって、かすかに唇から漏れた気がした。
「命令を変える。──その両腕を、俺の前で無意味にも後ろ手に隠すのを、直ちにやめろ。エレン・イェーガー」
首輪の鍵さえ有れば楽々と外し出てゆける。鍵が無いとしても両手を使えば首輪くらいどうとでも出来る。最初から、リヴァイはエレンを圧抑なぞしていなかった。手錠を掛けていたわけでも、荒縄で手首を縛り付けていたわけでも無い、自由なエレンの両手は、この狭い地下室のなか、いつだって不自由さを選んでいた。何もかもを信じたく無い。終わらせたい。終わりたい。なのに終わりたくない。傍にいたい。矛盾したエレンの。そういう可哀想な子供の虚勢的で悲況で卑怯なる態度が、リヴァイには理解出来ずにそれでも黙して指摘することをしないでいたのは、茶番に付き合ってやれた程度には、苛立つくらい愛してみたかったからだった。憤懣やる方無いのだ。虫酸が走る程。だがもうそれもこれ以上は。
無理──だ。
力を抜き、だらんと垂らされたエレンの両腕は自由であるのに不自由そのものを如実に。リヴァイはその手を握る。
リヴァイの前でエレンはいつだって自身で演じる疑似拘束に陶然としていた。例えばいつも、朝の随分早い時間から夢現にもエレンは急に飛び起きた。と思うと気が狂ったかのように自らの体躯を手弄りその未成熟な自身の肢体を、胸を、腹を、頭を、そうして順繰りと撫でまわしてみる後になって、漸く大きく深い呼吸をして、それから暫くし安堵した顔で再びベッドのなかへ潜り込む。それを、リヴァイは直ぐ傍でエレンの薄い肩越しに眺めながら何も言わずに、やがてまたベッドを軋ませ沈む背を、心底、穢らわしいと思い、憐れだと思い、憐れんでやることすら勿体無い程憐れ以上に憐れだと思い、そうしていつしか、この分かり易く可哀想な化け物の子供はほんとうに狂っていくのだろうと云う確固たる確信を持ち始める。はやくそうなれば良いといつも思っていた。眠っている振りを続けながら。エレンが狂っていくさまを夢想してはどんどん愉快な気分に浸るようになる。勇ましく尖りを帯びたエレン・イェーガーは分かり易過ぎる程に可哀想なので、そのうち死んで、依存的で、臆病で、儚く散ってしまいそうな脆弱な何かに、容易く手折られ飾られるだけの、やがて枯れて落ちる花で良い、リヴァイの傍らで生まれ変わってそしてやっと生きる。そういうものに成れば良い。いつかきっとそう成ると疑う余地も無くリヴァイはそう信じている。だのにまだエレン・イェーガーはいったい何を捜しているのだろうか。金色の瞳のふちを赤くして、丁度、あのときのように、目を伏せる度に蜂蜜色の双眸を隠す、瞼を、真っ赤に腫らすまで泣きだすような哀しい眼をして、何をそんなにも必死に睨む必要が有る。まだ何を捜して何を待っているのだろうか。月明かりさえ届かぬ冷たい地下室で毎朝そうして自分の腕で自分の体躯を、その輪郭を確かめて、いったい何を捜しては、そこから、自分自身から、何が欠けていくと思うのだろうか。穢らわしい生命は未だきちんとこびりつき剥がれずにそこに在ると云うのに。生きたいならば生きたいと言え。死にたいならば死にたいと言え。エレンがどちらを口にしたところで、最期には必ずリヴァイの腕がその躰を離すこと無く、拾うのだ。
けれどどっち付かずに成ろうとして、その危うさでバランスを取ろうと足掻いて。失敗の手本のような遣り方で愚かしく失敗している。
「どうせまた陽も昇りきらねえうちに、おまえは独りで唸るんだろう」
「……わかりません、そ、んなの…」
「監禁ごっこはおまえを満足させたのか」
「いいえ。…いいえ、俺は、」
「半端な破壊願望はそんなにも心地好いかよ。手放せねえくらいに」
「…何の話ですか」
「夢の話だろ」
「なん、の、」
「おまえのそのふたつの目が見てやがる夢だ」
「兵長に何が理解るんですか。俺の。何、が」
「理解してやる必要が了する程に無い。だから破壊してえものがあるなら迷ってねえで好きなだけ破壊して来い。それがおまえ自身であろうが俺は別にどうだって良い。どうせならさっさとぶっ壊れちまえ。自分が何者であったのかもわかんねえくらいに」
「────っ」
畳み掛けるリヴァイの詰め言さえこんなに耳障りが好いなんてわけがわからない。不意に、エレンは思い切り乱暴にリヴァイの腕をふりほどいた。がつりと痩身を冷ややかな壁に打ち付けて、萎えた手足で立ち上がる。そのまま、荒い呼吸で言う。
「俺が、兵長、貴方の、」
エレンは靜か泣きだしながら、殆ど声にならない声で、リヴァイにさえ届くかわからぬ程の消え入りそうなその震えた声で。けれど確かに哀哭した。それがエレンにとって精一杯の、それこそ甘えに見せ掛けた傲慢などより余程、心から、精一杯の──絶叫であった。
「貴方の。その舌の上で溶けて消えて失くなるためには…この躰が、氷で出来てりゃ良かったんだ」
けれどもそれではリヴァイが幸せになれない。
暫時を超えた、沈黙の末に。
リヴァイはひと言、そうか、とそれだけを言って。苦しくて仕方が無いような顔でリヴァイを見る、そのくせ呼吸することをやめないエレンを、ひっぱたいて蹴り倒してやりたい気持ちを抑えつけながら、リヴァイはエレンにふりほどかれた腕を引き寄せ胸にエレンの顔を埋ずめさせてから、その細い腕を、胸を、腹を、頭を、毎朝エレンが確かめていることと同じように順繰りと撫でた。なるべく優しく。蜂蜜の色を溶かしたその目はもうリヴァイを見ない。無理矢理に繋いだ手は冷たかったりあたたかかったり。明日は昨日より上等だったり劣悪だったり。異様さだけがさんざめいては、たくさんのものが散らばって。無情に流れる時間はリヴァイにエレンを不得意にさせる。
「……ッすみません兵長。吐きま、す…っ」
切羽詰った様子でエレンはリヴァイから逃れると蹲り、ベッドの傍に簡易トイレとして置いてあるペット用の容器に躊躇わず顔を突っ込んだ。
「っふ、う、ぐ、…あ゙ぁっ、ぅげっ、…ァ」
嘔吐いても、嘔吐いても、水分摂取しかしていないのだ。吐瀉物らしき吐瀉物なぞ出る筈も無い。せりあがるものは胃液だけである。込み上げて治まらない嘔吐感に何も吐けずに、なので余計に苦しく気持ちが悪い。天井に換気扇を付けてあると云っても閉塞的な地下空間はまたたく間に胃液の匂いに満たされた。
「っ…う、…はッ、かはっ……うぅっ、」
人間の胃液の主要成分はタンパク質分解酵素ペプシンで、キモシン、リパーゼと約0.5%の塩酸を含むpH1.0〜1.5の強酸性を示す水溶液がそれを活性化する。嘔吐くばかりのエレンの背をさすってやりながら、リヴァイはもうこのガキは無理なのだと嫌になる程考えたことをまた考えていた。いつになったら。いつになったら終いが来るのだろう。揉み合いの隙、引っ繰り返ったせいで空っぽになった皿が邪魔で、それは落として棄ててしまった。エレンはもう、人間が真っ当に食らう食事を、食べられない。与えてもいない花の香りに隠れる毒の持ち主。疾っくに有利も不利も存在しないと知っていた。あべこべの、継ぎ接ぎで傾倒する世界だ。
「今のうちに──俺が傍にいるうちに、食って吐け」
言いながらリヴァイは胃液すらまともに吐けなくなっているエレンの首根っこを掴み、己のほうへと向きを変えさせる。
「なにを、」
「何をじゃねえ。俺をだ。来い」
何らおぼめくこと無く予め理解っていたのだとでも云わんばかりに、リヴァイは自らの上着をずり落とす。丁度、棘上筋あたりから三角筋、上腕三頭筋、上腕二頭筋を見せ付ける程度に。
「…ぃ…や、です……」
「拒否権はもうねえっつったろうが。食え、エレン。何も全部食えと言っているわけじゃねえ。少し齧り付くだけだ。おまえが巨人化するときにその手を噛みちぎっていた程度で良い。今のおまえの状態はおまえが入団した頃から、要するに最初からハンジが危惧していた通りだ。監禁してみてからそれは確信に変わった。もう、おまえは、巨人化のし過ぎで人間しか食えなくなってんだろ。覚えも無く父親を──グリシャ・イェーガーを食ったときみてえに」
「嫌です! 食いたく無い!」
必死に拒絶を示しながら、エレンの喉は本人を裏切り勝手に鳴る。飢えた獣のように。涎が滴り落ちた。
「嫌だ! 嫌です兵長、いや、」
「うるせえと言ってんだろ愚図野郎、黙れ」
エレンの拒絶などかくも儚く、リヴァイに飛び込まされた腕のなかで。
「あ、あ、ぁ、やだ、やだ…ぁっ兵長……っ、ゃァア゙ア゙ァ…」
抗えない飢餓感。高鳴る鼓動。目の前がまわるような目眩に。襲い来る強迫観念。それらは只々、途方も無く。
「っつ…」
「んんっ、ぐ」
矮小で鈍く、だが生々しい音がぶつりと鳴るほぼ同時、リヴァイの鍛え抜かれた肉体が纏う皮膚にずぐ、とエレンの歯が沈む。甘噛みでしか無いが、そうか生きたまま喰われるとはこういう感じであるのかと、リヴァイは嘗て失った部下や仲間の死に顔を思い浮かべるが、どうにも腹立たしい程に浅い。これでは意味が無い。けれど口内に広がる肉の感触と芳香な血の匂いに、赤味の混じった唾液を啜り上げて直後エレンはふらつくまま渾身の力でリヴァイを突き飛ばし、ベッドに頭を突っ伏した。酷い怯えようだった。シーツを奥歯が軋む程擦り付けて噛み締め、しきりにごめんなさい、ばかりを繰り返し嗚咽を漏らす。リヴァイの肩に残された歯型はリヴァイが命じたそれより随分足りておらず、エレンの歯列にぴたりと嵌まる大きさの歯型からは玉のような血がぷつぷつと滲み、やがてささやかに滴り落ちていくだけであった。噛みちぎられてさえいない。
「ごめんなさ、ごめんなさい、兵長、ごめんなさい」
「ちっとも食えてねえじゃねえか。やり直せ、エレン」
まるで古城での当初、幾度も、出来が悪いとやり直させた掃除のときのような口調でリヴァイに咎められながら、エレンはその細い肩を小刻みに揺らしている。だがそれもリヴァイの予想した範囲内だった。エレンにリヴァイが食える筈も無い。仕方あるまい。
「エレン」
あたかも夜伽の最中のように呼び掛ける。
「…………はい」
答えたくない、とその痩せた後ろ姿が語っている。だがシーツに顔を埋ずめているせいでくぐもってはいるが返事は返る。リヴァイは問うことをやめなかった。
「クリームシチューを飲み込めなかったのは、わかっていたからか」
「……だ、って…あれは……死肉、でした…人間、の…」
舌に乗せられた、ただそれだけであれが何で出来たものであったのかがエレンにはわかってしまった。牛でも豚でも鶏でも無い。
「畜生殺しで処刑された悪人のものだ。そこに罪業妄想を持つなよ」
「…………」
そんなことを言われても困る。死刑囚の残骸だからと、はい、そうですか、とはいかない。ましてや死肉ならば良いということでも無い。どうせなら、壁外にて大量に見てきた無知性巨人のように何も食わずとも生きられるのであれば。ならばまだましであったかも知れない。エレンの躰は人間の食事も摂れず、疾うにそのどちらでも無く。リヴァイもそれはわかっていた。エレンを生かすことがどういうことであるのか。
「生きている人肉は今ここに俺しか無いんだが、おまえは俺を食うくらいなら死ぬんだろう」
「…当たり前……です。こんな、化け物には、俺が付き合って、いられない。……殺して、ください」
「それが出来りゃあさぞ楽だろうな、互いに。──その無駄にでけえ目は閉じておけよ。シーツに噛み付いたまま決して舌を噛むな。死ぬ程痛えだろうが死なねえ程度に加減する。我慢しろ。俺を齧りも出来ねえおまえが悪い」
「は、…?」
リヴァイはブレードをエレンの背から横腹に掛けて振り下ろす。曰く──まったく残念だ、と。
「ひッ!? あぁっぐ、ぁあ゙あ゙あ゙あ゙あ゙あ゙あ゙ッ──」
断末魔の叫びをあげてのたうつエレンに冷静に指示を出す、リヴァイは靜か血飛沫が壁と床を叩く音を聴く。思い知れ、と思った。エレンに対し、リヴァイにしか選べぬ、選び取る外に選択肢がひとつしか無いものをエレンは重く思い知るべきなのである。
「そのまま口を開けていろ、エレン」
「ひぁ、あ、あっ、ぐ、んっ、んあ、」
「言い忘れたが、目的意識を持つなよ。何も考えずただ飲み込め」
痛みと衝撃に喘ぐエレンの髪を掴んでその顔を上げさせる、洗ってからそう経っていないリヴァイの手は斬り裂いたばかりのエレンの生々しい傷口を抉りそこにある肉を血液ごと鷲掴んだ。シチューをそうしたようにエレンの口内に捻じ込むと咀嚼する暇も与えずに飲み込ませ、次の肉を同様に捩じ込んでは食わせていく。どうせエレンの躰は復元する。ならばエレン自身の血肉であろうと同じことだろう。そう、あたりをつけていた。それでも出来得る限りはそれを避けたかった。リヴァイが自分の身を齧らせようとしたのは伊達や酔狂からでは無かった。だがもう。もう無理なのだ。こうしてこうすればこうなるものだと知りつつ、そうした。だからまさに今目の前で、こうして、こうなった。ならざるを得なくなったのであった。ひく、ひく、と小さくしゃくり上げるその合間合間に、苦しげな呼吸音を漏らしながら、それでもエレンは恍惚とした表情で口のまわりどころかシーツや床も盛大に血まみれにして、食事を、している。
「ちょっと待ってろ」
自身の血のなかで歯を食い縛り泣きやまぬエレンをそのままに、リヴァイは地下室から出て行った。エレンは黙りこくっている。激痛に悶絶しながら、しかし、空腹感を満たす匂いに酩酊しながら。
巨人としても生きられずに、人間としても生きられない。迷いたくて迷えない。何ひとつとして決められない。だがすべてをリヴァイに委ねきることは出来れば楽になるのかと試してみても無駄だった。少しも楽になどならない。苦しみだけが嘆嗟いや増す一方であった。
エレンは、やがて戻ったリヴァイが地下室を出たときと同じ格好で同じ体勢で、鉄の異臭で噎せ返る地下室の血溜まりのなか壁に寄り掛かり、ぐったりと、緋色に染まったベッドに突っ伏していた。エレンがそのまま死んでいれば互い、真実に諦めもついたろうに、傷口からは蒸気が発生し早くも修復作業が始まっていた。一先ずリヴァイはエレンの手当をする。念の為に持っては来たものの、止血剤は要らなかった。陽を浴びられぬ生活で一層白く、蒼白くなっている筋肉の落ちた痩身に包帯を巻いてその耳元へと囁きを吹き入れる。
「エレン」
「…………」
「生きたいと言え」
返事は、肯定も否定も返らなかった。頷きのひとつさえ。横に振る首ひとつさえ。いったいいつになったら、終いが来るのだろう。同じことを考えている。ずっと。或いは初めからそうであったのかも、知れない。気が狂ったかのように自らの体躯を手弄りその未成熟な自身の肢体を、胸を、腹を、頭を、そうして順繰りと撫でまわしてみる後になって、漸く大きく深い呼吸をして、それから暫くし安堵した顔で再びベッドのなかへ潜り込む。それを、リヴァイは直ぐ傍でエレンの薄い肩越しに眺めながら何も言わずに、やがてまたベッドを軋ませ沈む背を、心底、穢らわしいと思い、憐れだと思い、憐れんでやることすら勿体無い程憐れ以上に憐れだと思い、そうしていつしか、この分かり易く可哀想な化け物の躰はほんとうに狂っていくのだろうと云う確固たる確信と、はやくそうなれば良いと云う思いも共々。ふたりして棄ててきた真っ当さを今更惜しんで何になる。
「諺はわかるか、Sprichwortだ」
「……わか、ん…な、」
「Der Mensch ist was er isst.」
「人間、とは…食べるもの…そのもの……?」
「人間はそいつが何を食うのかでわかる」
「…嫌味ですか」
「俺はな、エレンおまえが、死にてえと言うんならもうそれで良いと思っている。好きにすりゃあ良い。但しそのときは俺が傍に居るときにしろよ。死ぬなら目の前で死ね」
「は…、はは…そんな、の、」
この地下室に縛られた日がつい数時間前のことのように思える。リヴァイはいつだって正しい。エレンは狂笑する。
「……絶対に止めることを前提にしないでくださいよ…そんな話。──ねえ、兵長」
何に迷うか決まらないのは。迷っていたいからだった。でも迷いたいとは思っていることも嘘では無い、嘘では無いが、どうしようとも何に迷おうか決まらないのだ。いったいいつになれば、終いが来るのだろう。いつになれば。
「兵長、は…、分かり易く憐れな人です。こんなになっても……こんな、化け物より化け物になった俺をそれでもまだ、どうにか生かそうとして」
「それの何が悪い」
「悪いですよ。可哀想です」
「おまえよりもか」
「俺がずっと後ろ手に拘束されているふりをしていたのは、あれは、ふりじゃあ無い。いつでも俺は、貴方の前では抵抗せずに、貴方に、この身を傷付けられたかった。最期に俺を殺すのは貴方が良い」
「は。相変わらずイカレてやがる」
「…そうですね。だけど、俺にそうさせていたのは貴方です。兵長。すべて貴方のせいだという意味じゃ無い。だから、抱き締めて貰えませんか。背骨が折れるくらい。つよく」
「それは、抱き締めると言わねえよ馬鹿」
「どうせ勝手に修復します」
「治癒を繰り返せば繰り返す程、修復能力は衰えていくことは実証されている。おまえが死に近付くとわかっていてそうしろと?」
「はい。それで、どうせなら、俺の食事も、ブレードで斬るんじゃあ無くって、貴方のその手で傷付けられたい。抉り出されたい」
「それなら食うのか、エレン」
「Mit Liebe erreicht……」
嗤いながらエレンは呟く。互いの滑稽さに頭が酷く痛んだ。鎮痛剤は飲んだって仕方が無い。そんなものに治まる重痛では無いのだ。諺くらいエレンでも知っている。
「わかった。次からはこうしよう」
リヴァイは表情を変えること無く、エレンの左胸を手刀で貫く。穢らわしい返り血と飛散する血潮、裂けた傷口から、だくだくと溢れ零れいくエレンの生命。
「っ……ふ、…ッぐ」
指先に当たる内臓を握り締め引き抜けば、ごぷり、とエレンの唇からも溢れる。
「痛えか」
尋ねるリヴァイにエレンは首を振る。口端より赤い泡を零しながら、唇の動きだけで告げる。へいちょう、と。
「何だ」
『し』『あ』『わ』『せ』『で』『す』──微笑んでそんな台詞を吐く忌まわしき子供の口のなかへとリヴァイは掴み取った臓器の破片を突っ込んで飲み込ませた。もう黙れとその首を蹴り落としてしまいたかった。憐れ過ぎる程憐れである化け物が、リヴァイとエレンのどちらだかも、もうわからない。放置しようが何事も無かったかのように穴が塞がってしまう勝手な痩身を抱き締めると、リヴァイも勝手に舌打ちがついて出た。
「…汚えな」
エレンの血で汚れてしまった服を脱ぎ捨てバスタブに叩き込む。自給自足にだって必ず限界がやって来る。そのときにエレンが他人の肉を食えるか否かが目下、今後の課題となった。
ここまで互いに血だらけなのだ。構うまい。エレンの手がリヴァイを赤いベッドへ誘う。不快極まりないそこで互い何を確かめ合おうとする。エレンの心臓の音に耳を澄ませる。まだ。動いている。エレンはリヴァイに擦り寄る。まだ。生きている。だったら縺れ込んだベッドの上ですることなど決まっていた。ひとつしか無い。血が乾き碌でも無い唇でキスを交わした。いったいいつになったら、終われるのだろう? 鍵の開いた地下室からどこにも行けない。ほんとうはもう、手すりの無い階段を悠々と裸足で駆け上がってゆける躰では無いので、目を閉じて嘱望する更地の世界の大嘘に、気付いているふたりが失笑に値するのだ。上記のようにどうしようもないことを嘆く存在は互いに生きる糧となる。よってリヴァイはこれからも花に血をやるしエレンは有りもしない光を与えられていようとする。エレンが言い掛けて辞めた言葉はその夜以降、2度と、互いの口にのぼることは無かった。ただ確知しているものは微動ともせずに、もう無理なのだ、と云う事実だけなのだ。
Mit Liebe erreicht……────。
荒々しい男の下で少年の嬌声が響く。折檻のような後ろめたさは何れ程の夜を越えようとも慣れないが、数字を数えるのを辞めてしまってからは日付も何も数えない。数えたら負けてしまう。それが死であるのか生命であるのかはどうでも良い。そこから損なわれゆく何かを行儀悪く零していく。進行している。ネイビーブルーの瞳を持つ男がそんなふうに言うとき、殆ど完璧だと呼んで差し支え無い。今日も少年の狂気は美しくその蜂蜜色が蕩けるさまは綺麗だから、淡い面影は少しずつ失われる。遠いいつかを睨み首輪をして、夜闇かどうかも確かめぬ、歪つな求愛は純粋に汚い。
Mit Liebe erreicht man mehr als mit Gewalt.
愛は、力より、強い。それが自分の命さえ賭けずに、心に暇が有る誰かの戯言に過ぎないものだったのだとしても。憐れさに意味など無い。生き永らえることに意味など無い。死骸となり腐りいくことに意味など無い。喰らうことにもその逆にも意味など無い。寂しさに意味など無い。厭うことに意味など無い。何より、愛に意味など無い。それで漸く終われるのだと、知っているから終われと願って終えられない。永きに耐えた穢らわしき生命が今宵もへばり付き剥がれていかず。夜通しに手繰り寄せもしないまま、訪れる明朝にまた気が狂う。きっと気付かなかっただけで元よりヒトは巨人など存在しなくとも家畜以下だったのであろう、でも生まれてしまった濁悪。ずっと捜しているのは、いつも、正しい呼吸の仕方と、今日とは違う明日だ。それなのに、今日とは違う明日はどこにも、可笑しな程に見当たらなかった。いったいいつになれば、終われるのだろう。毎日。毎日毎日毎日毎日毎日毎日。薄暗い地下室に光など届かない。愛ならもっと届けられない。陽も昇りきらぬうちの、夜明け前が、1番、噬斉にてむごい。
ほのぼのリヴァエレの伝道師『よもぎ餅』のあすみさんが描いた痛く重い愛のイラストに衝撃を受けて。ざざざざ、と、その場で私の脳内に湧いた圧倒される程のインスピレーションと高揚感を、はやく、はやく、文章にしたい!と思いながら、此度漸く形にすることが出来ました。つまりあすみさんのおかげで書けたと言っても過言では無い…!あすみさん、ほんとうにありがとうございました!どうか受け取って頂けると幸いです。ていっ(ノ^_^)ノ”(愛)