<概略>
擦れ違いつつそうでも無い/互いが互いの思考を理解していないようでそうでも無い/自分自身の思考不可視と思いきやそうでも無い/両片想いのようでそうでも無い/ぞんざいなようでまたそうでも無い/色気無く淡々と18禁行為をするだけの上官と新兵的な関係のようでそうでも無い/でも何だかエレンが女々しくおとなしい/兵長も何か無意味に優しい
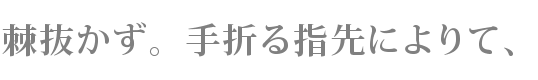
ひと夜にして何ら前触れも無く、何もかもの全部ががらりと変わるということが。そんなことが。起こり得る世界なのだろうか。疑問を持つより先に知った、答えは『起こり得る』どころか『起こり得ぬわけが無かった』だった。富豪も貧民も平等に誰しもがその経験者で溢れている。
それでいて尚もまだ、憐れな程の青臭さと否定は、切っても切れない関係性を断じて崩しはしない。子供たちは無論のこと、過去に子供時代を置いてきた大人たちですら、ようようそれを繚繞すると思い知っている。ただ束となった藁がばらばらと頭上へと、埋め尽くす程の勢いを持ってしては次々と振り落ちてくる感覚に息も絶え絶えである隙間から善悪を問わず甘味の破片を散らし──散らかしては片付けもせずにどこかの誰かを容易く嘲笑させるに足る。のだ、と。けれどエレンは信じてなぞいないのだ。今の自身を覆う本物らしき何ものもを。ヒトというものについてたいして知らなかった頃、エレンは誰よりヒトだった。原始的、本能的に。まともにヒトで在りたいと思った頃、エレンはただの化け物だった。無意識的に、意識的に。ゆえにそれは多忙により若干不眠気味のリヴァイをも寝付かせるに足るのである。理由が必要ならばそれで良い。真実がどうであるのかはまた別として。必要なものはでっち上げてしまうべきなのだ。
ならばほんとうは既にもう、何もかもがどうでも良いのかも知れない。理由も動機も所詮後付けにしかならぬのだから。そんなものをきれいに並べ立てひとつずつ数を数えたところで仕方が無い。手っ取り早ければよいのだ。ここに正論を求めはしまい。こじつける意味なら容易い。犬猫と違い、兎などの動物と同じく人間には発情期というものが無いのだ。それは即ち、年がら年中季節も期間も問わずに常時いつ如何なる状況であろうとも発情することが可能である、ということだ。辟易する。上官に逆らう選択肢を与えられること無き新兵である立場を差し引いても、自傷行為と明確な目的意識によって奇怪にも巨人化する、己自身メカニズム不明な未知の能力を有しているエレン・イェーガーは、目附役の兵士長に尽く疑問をいだいていた。だが今更それについて考察し議論する価値が無いことも、幾ら頭の宜しくない自覚があれど知っている、ので、せめて、異性経験が確かに有り実際に女を抱ける男が敢えて、なぜ雄として同性である雄に対し欲情するのかだとか、その切っ掛けとなるトリガーはどこに在るのかだとか、率直に特殊であるこの現実における、別々の、躰が躰を求める要素と因果関係が解明されるということがいつしか起こり得るならば、心の準備が出来る分くらいは幾らかましであり、仮にそれらが解明されてしまった場合、その何らかの条件が揃っているようなときには、絶対に、エレンはリヴァイとふたりきりの屋内において迂闊に近寄らないよう細心の注意を払い慎重に、慎重に、気を付けながら生活しておりさえすれば、きっとそれだけで今よりは、幾らか楽になれる筈だ。おそらく。そうで無ければ困る。し、寧ろエレンは今まさに現在進行形で懇望もだしがたく窘窮し襲い来る眩暈にどうすることも赦されずにいる。掃除と訓練その他諸々で疲れた躰を休めている子供の、間抜けな寝顔のいったいどのあたりに、雄を欲情せしめる要素があったのだろうか。何れにせよ無防備な就寝を悪意も持たずリヴァイが邪魔することは、エレンの意識且つ既になけなしの人権への、蓋然的な拒絶であり否定であった。
リヴァイとの付き合いが長い者からの言い分としては、リヴァイは同性から妬み嫉みを買うことは特に無い、有るとしても興味が無いので気付いていないだろう、と謂うのだがそれはたぶんにしてその見目、目付きは勿論であるがそもそも雰囲気から凄みが有り過ぎて、事実、凄みばかりか実力派であるからして、妬むより嫉むよりもまず調査兵団の兵士としてリヴァイという男の、人となりを知らぬ一般男性陣は、リヴァイを人類最強と称えつつも単純に恐怖し敬遠しているだけなのでは無いかとエレンは思いながら、意外と他人からの視線の意味に鈍感らしいリヴァイの、デフォルトである無表情をここぞとばかりにじっくり眺めてみる。そこには何らかの理屈が働いての意図はまるで無く、意味ならもっと有る筈が無かった。
「何をそれ程熱心に見てやがる、愚図野郎。俺の面に何かついてんのか」
「あ、いえ。すみません、別に」
「おまえの視線はうるせえんだよ、エレン。目は口ほどに物を言う、とはよく云うが、おまえの目ン玉は喧し過ぎる」
鼻先三寸と云ってもよい程の近さでエレンの目前をリヴァイが妨げているのだ。ならば見詰めてみれば見詰め返されるものであるのかと、ふと恣意に従った程度で、当たり前のように軽く人類最強の脚力で腿を蹴られた。軽かろうと痛くないわけが無かった。だが暴力反対とエレンは言わない。なぜならばリヴァイにとって、口より手より先に脚が出ることは珍しくも何ともない極々ふつうのコミュニケーションのひとつ、謂わば彼なりのボディタッチなのである。理不尽だがリヴァイが理不尽のかたまりであることは自然の摂理にさえ等しい。とさえ断言しようとも、差し支え無いものであるのだ。少なくともエレンにとっては。仕方が無いのは、気に要らぬと躾けるところから指導が始まるエレンのような若い新兵相手のみならず、例えば分隊長を長く務めリヴァイより先に兵団に所属していたらしい──つまりは実質的にリヴァイより先輩兵士にあたるのだという──ハンジを相手にも足蹴にする様子がよくよく観られる光景ゆえに。よってエレンは腑に落ち無かろうが関係無い、視線がうるさいって何ですかわけが理解りません、といった問い掛けも、今や、してもまったくの無意味であると知っていた。この足癖の悪さと口の悪さをリヴァイから抜き取れたとしたら、目付きに多少問題があろうとも顔の造形は全体的に整っているし地位も名誉も武勇伝も持ち合わせているしで、ただもう少し紳士的に、にこり、と、愛想好く微笑むことが出来れば、女性という女性は軒並みリヴァイの虜になってしまうだろうに。それが現段階では人類最強と呼ばれる男の遺伝子を残す、脚色せず生々しく云うなれば、リヴァイの精子を手に入れることで他家との差をはっきり見える形として箔をつけたいだとか赤子を足掛かりに更に上流社会へ取り入りたいだとか、何だかんだとおぞましくも穢らわしい、金持ちの豚に分類される大人たちの目論見による泥々とした欲望と牽制蠢く見合い話が、貴族やら商会やらからは無駄に多数打診があるようで、それらを波風を立てぬよう逐一穏便に断る面倒臭い事態は、実のところエレンが調査兵団に入団を果たした昨今よりもずっと以前より変わらず続いているのだと。真っ当な精神を持つ人間たちとはとても思えない。大変に異常である。非常にくだらない話である。いつだったか、はァそうなんですかそれは大変ですねえ、とつい零したエレンには無論悪気などほんの僅かどころか緑葉に乗る朝露程も無かったが、リヴァイは手元でも無く況してやいつしか子供に向ける残念顔などでは無く何か別の影を漂わせ、ひとり、腹のなかを不穏にするようになっていた。やはり理不尽である。理不尽であるが仕方が無い。見詰められていたので見詰めてみた、ただそれだけで視線がうるさい、と眉を顰められてしまえばどうしろと言うのか、エレンは不条理と共に窮屈そうに背中を丸めて。そうして姑息なふうに窺い見た。けれどもリヴァイに云わせれば昼間の屋外や誰でもよいが第三者らの存在が近しい普段はまだしもふたりきりの室内にて、エレンの蜂蜜色をしているおおきなふたつの目玉による視線は、目が合う筈の無い背中越しですら変わらずうるさく気になるものであるらしいので、リヴァイの頭の微動に反応するように瞬時エレンは、反射的に、さっとまなこを逸らす癖がついていた。否それでも垣間見えた、見えてしまった眸の奥の色彩。濃い茶色がかった黒にネイビーブルーをぽとりと落として掻き混ぜた、うつくしい色をしている両の瞳に、見蕩れるよりも何よりもまず真っ先に背筋に脂汗が滲むのは、その眼光が隙無く鋭く、どこまでも冷徹さを秘め何の気構えも無いままにうっかり触れれば、手入れの行き届いた斬れ味の良い刃が如く、いっそ芸術的なまでにきれいな程、削ぎ落としに掛かられそうだからだ。やばい、危険だ、本能がそう訴える。しかしひとつ間違えてはならないのは、エレンに限らずリヴァイと同じ空間に存在するものはどのようなものであろうと逃げ場など無い、ということだ。だからエレンは常々諦めるしか無く、同時いつでも悲愴な覚悟を決め腹を括ることを余儀なくされているのであった。それは他者からすると同情と憐憫にも値するものですらあるとのことだったがエレンは疾うに充分慣れていた。慣れは恐ろしいというが別段そうでも無い。慣れようがどうしようがエレンは確かに恐怖しているのだ。だがそれが何れ程憤懣やる方ないものであったとしても、為ん術なき恐怖を齎すリヴァイの思考を理解するべく努めたところで、何ひとつとして真実を汲めない、理解の及ばぬ事態について逐一考え込み落ち込むほうが面倒だ。と謂うエレンのスタンスを、まさかとは思うけれどエレンきみ、麻痺して鈍化しちゃって無いよね? とは聡明で心配症な幼馴染みの有り難い弁であったがエレンはたぶん聡明な幼馴染みに比べ野生的順応性が高いのだ。ついでに頭を使うより躰を動かし悟るタイプでもあった。
その確固たる証拠が現在この場で起きている。あたかも単なる寝酒代わり当然の様子で鎮座して。リヴァイはそれを、交尾だと称した。
訓練でも何でもない、肌寒く冷え冷えとしている筈の地下室内にも関わらず、ふたり分の汗が散り密着した肌が滑りを帯びている。その生理現象に身を任せ滑り落ちてしまえば固い石床へ叩きつけられるしか無くなる。よってエレンの躰は自然、いつも閾下として勝手に強張った。が、エレンのほうからリヴァイへと触れることは無い。ただの1度もだ。それはエレンの意思だった。だからいつでもリヴァイは仏頂面を隠さずに、エレンの手を取り己の首にまわして遣らねばならず、それでも抱きつかせただけの頼りない腕は心許無くも物足りない力しか込められない。
もっと確りしがみつけよ何度同じことを言えば覚えるんだ面倒臭えなクソガキ、とリヴァイは澹如たり吐き捨てるが、もっと──もっと? 何をもっとなのかとエレンは思う。だってどうせこの躰は頑丈に出来ているのだ。女では無いどころか最早(エレン自身が望んだわけではまるで無いのだけれど)一般的なふつうの人間ですら無いのだから、ならばそれこそ、もっと、猶以て壊すように抱けば良いだろうにリヴァイは、据えた瞳でエレンの肩口に軽くて甘やかなるキスをして、着痩せするその小柄な見目だけでは想像も出来無かった、実戦的な筋肉だけでつくりあげた雄偉なり裸体で、エレンより随分と雄々しく節榑立った手を、交尾、と呼ぶにはあまりにゆったりと、乱暴さの欠片も匂わせずにエレンの背中へ優しく這わせる。あァ嫌だ、これだから嫌なのだとエレンは瞬く。寧ろ憂さ晴らしにされるだけ、丁度都合よく使われているだけ、便利で気遣う必要も無いからだと冷淡に扱われるだけであるのであれば、構わなかった。しかし、自分だけが気持ち悦ければ良いような横暴さを、リヴァイはエレンとの曰く交尾、において少しも挟まない。普段の酷しい足癖やらのほうが完全に嘘で、壊れ物でも扱うかのように躰中にさわって勃たせてから丁寧にとろり、垂らされる香油がまるでうすい膜を纏い、つうと未熟なアナルから内腿をつたい落ちていく。憂さ晴らしなら憂さ晴らしらしくされなければ困る、言葉にしない動揺を抱え募らせ、けれど若いペニスは腫れぼったく素直に反応していくだけなのだ。
あァまったく嫌だなあ。もうほんとうに、嫌だ。
遣り切れなくて割り切れない。エレンの面持ちはずっとそれを顕わに示す。
現時世、ただでさえあらゆる物資が不足しているなか香油など高価な上、腹の足しにもならぬ単なる嗜好品でしか無いものである。そんな貴重なものをどうして態々取り寄せてまで、雄同士の交尾のためなんかに消費するのか、それは勿体無いばかりの、多大な無駄遣いでしか無いのではあるまいか、エレンにはまるきり意味が理解らないのだ。リヴァイのように男のアナルへペニスを突っ込んだ経験がエレンには一切無く、おそらく今後もそのような機会は来ないだろうことからこそ、実は滑りが悪いと挿入する側も痛いのだと体感することが無いがゆえそう思うのかもしれないが。ただ、ひやり、冷たいリヴァイの指先がたっぷりと垂らし挿れてゆく濃厚な薔薇に似た香りをかもす香油がなぜか矢鱈にあついのは、優しいばかりの愛撫を施され過ぎて脳が煮え滾りそうにエレンをあつくさせていくのはきっと、わけのわからないせいかも知れなかった。
「っ…は、ぁ」
つい罷り間違い出た溜め息が唇に引っ掛かり割れて、濁る空気に溶けていく。どのようにしようとも昂っては巡る不安定な熱を、聊けしくも散らしてしまいたくてエレンが自ら腰を揺すれば、それを見下ろす柳眉がかすかに寄ってそこへ張り付いた異様なる怒気が色濃くなる。何がそれ程不満なんですか兵長、子供の浅慮さで愚行にも呟いてしまったならば取り返しのつかない目に合わされることを既に身をもって知っていた。エレンは憎き巨人を駆逐し外に広がるおおきく眩い、幾度夢に見たかももう数え切れぬ輝かしい遠い世界を、双眸に焼き付けるため見てまわるまでは、何れ程『死に急ぎ野郎』などと不名誉な渾名をつけられる生き方をしていようともまだまだ命が惜しい、ので、死ぬわけにはいかないのだ。それゆえほんとうならば、ヒト1人につきたった1度きりしか与えられていない、限り有る短い人生において、こんなにも生産性皆無な交尾に興じる時間程に無益なものは無く、勿論そも予定にも無い。意志は変わらないのにただの飾りでは無い両の耳が、僅かな息遣いから聞きたくも無い醜悪で猥雑な水音まで律儀な程丁重に拾い上げる。このままではいけない、死ぬ。余所事ばかりのエレンのシャツの上から、脚の付け根の外側をリヴァイの手が掴むと直ぐに、もっと深く、怒張したペニスをエレンの体内へ押し込まれた。
「い゛ッ……つ、ぅうっ!」
真実を明かすならエレンの躰は、否、尻孔は疾っくにリヴァイとの交尾には慣れているため然程痛くは無いのだ、が、反射的に嘘が唇からついて出る。リヴァイが地下室へ降りてくる直前、ほんのつい先程までぐっすり眠っていたのでエレンは躰の感覚が大雑把から未だきちんと戻っていないままなのだった。抜かず体位を変えようとするリヴァイを囲うようにベッドの上につき体重を支えさせられる両手が淡く痺れ、片方ずつ結んでひらいてを繰り返しまぎらわせようとしてみたけれども、全然思い通りには動かない。そしてそうこうしている間に更に痺れていく神経が、意に反して忌々しい。決して声に出しては言えないが己の躰が己のもので無いような、この不可思議な感覚をエレンは厭うた。それはつまりこの薄っぺらい胸がはだけているのも寝乱れたせいであって、リヴァイはまるきり関係無く自分も下だけ衣服も下着も今どこに放置されているかわからぬ不格好な佇まいではおらず、腰から爪先までを覆う上掛けの下では実はあらぬところへあらぬもので繋がってしまっている、ということのすべてが、何かの間違いか有り得ない妄想か或いはストレス性の悪夢であれば良いのにと、叶うならずっと疑っていたい理性が、平常心を断固として手放さない。だが上昇をやめぬ体温のあまりの熱さに吐息が荒々しく弾んでいるのは明らかにリヴァイよりもエレンのほうであり、重ねるべきで無い肌が重なりいつしかペニスを嵌めたまま捩るように引っ繰り返され、どういうわけだろう気付けば騎乗位で見下ろしているのもエレンであるのだから、もしかしたら、傍目にはエレンだけが蓮葉女のように猥褻さを溢れさせ発情しているかのように見えるかも知れない。如何に優しくされようとどこもかしこも苦しいだけで、ちっとも気持ち悦くなど無いのに。そんなどうしようも無く情けないエレンの思考を見透かす大人げの無い大人によって勢いよく、ずぐ、と突き上げられ強制的に遮断を促され、歳若きと云えど大変に気持ち悪い、エレン自身こんなものは自分の声では無いと耳を塞ぎたくなる程の声が、紛れも無く変声期を終えている男である声が、あだめいた交尾によって息苦しく小さな喘ぎを洩らす。
こんな夜伽。
リヴァイに何があったのかを訊く権利が、例えたかだか一介の新兵だろうと巨人化する化け物だろうと性処理の道具だろうとエレンには有って然るべきであった。けれどエレンは好奇心や関心を寄せることをしない。リヴァイの嫌う、過度に豪奢な社交の場にてどこぞの貴族にでもまた気色の悪い話を振られてきたのかも知れないだとか、ごてごてと着飾り人工的な香りを漂わせる姫君たちに言い寄られてきたのかも知れないだとか、そういった、任務同様に或いは任務以上に避けられない、潔癖なリヴァイには拷問にさえ均しい時間が夜更けまで続いたせいなのだろうということならば、エレンの経験として最も知るところである。では迂闊に話題に出してはならない。仮に具体的な話をエレンの耳に入れ教えたいのであればリヴァイが自分で話す筈だ。なのでエレンは黙って、リヴァイが命ずるまま脚をひらくだけで、もう疾うに投げ棄ててきた羞恥なぞ今になり感じることも無く馬乗りになった腰が砕けぬよう必死に、奥まで呑み込まされている太いペニスをリヴァイが満足するまで揺さぶり揺さぶられ、アナルの奥の奥までを搾り使い突き上げられる動きを享受するのである。そうして漸くにして、要はエレン以外の他の誰かによってリヴァイの胸宇に生じてしまった、呆れや怒りを孕んだ気持ち悪さを性欲に変換した熱を、エレンの躰が受け止めるだけなのだ。リヴァイがエレンに挿入しやすくするために予め準備し、先刻使用した香油が甘ったるく不快な匂いを放ち、いつしか地下室中に充満している。ひどい。シーツは洗濯し干してしまえば良いが、風を通さぬ閉塞的な室内はそういうわけにはいかないのに。とか、態とすべてをリヴァイのせいにするような責任の所在を押し付け続けていれば、エレンの、引き攣り狭くなる喉を掻く意味のわからぬ痛みは徐々に薄れいき、少しずつではあるが何となく楽になれる。気が、して。同じように僅かにエレンは安堵した。項垂れると癖も無い清潔でしなやかな黒檀の髪が、エレンの目先に迫る。ブルネットより深い夜のような、光の欠片も無く最も黒々しい常闇を流し込んだ、うつくしい色。
「……おい」
暫時噤んでいたリヴァイの、低く掠れた声が不機嫌そうにエレンを呼んだ。
「? はい」
「てめえは、まだ痛えのか」
「はい?」
「ケツだ。切れちゃあいねえようだが……」
「あー…だいじょうぶ、です。たぶ、ん」
「そうか」
だったら痛そうな声を出すんじゃねえまぎらわしい、とでも云わんばかり、チ、とリヴァイにしては似合わぬ程に控えめな舌打ちが、しかし、あたかも鬱陶しげに響いた。それさえ優しさの一部であるなら嗤える。痛くも無いくせに痛いとエレンの口端をついたのは、決して嫌味のつもりや、リヴァイを困らせたいわけでは無かったが、心配や労りを示されるのであれば違う部分でして欲しいとエレンは思う。そもそもの、この生産性皆無にも程がある、無益なる行為から。
──交尾、から。
「えっ? く、ぁうっ、…ちょ、待っ…っ」
ペニスだけでもういっぱいに拡げられている本来出口でしか無いところを入口に変えられている真っ只中、前触れ無く無言の指先でくるりと撫ぜられそのせいでエレンの背筋がおおきく震えた。嫌だ嫌だと思う心を裏切って、躰がほんとうに変化を起こしたことをエレンは経験則から否応無しに理解する。腸壁の粘膜を巻き込んで、腹が苦しい程の圧迫感に支配されながら、前立腺を擦りたてられると勝手に涙腺が緩み涙が出そうになってしまうのだ。みっともない、そんなことを知られることすら嫌で、エレンは零さぬよう鼻の頭に力を込める。気持ち悦いと感じたことも無いままでありながら、もう、後ろへの刺激だけであろうと有無にうまく昇り詰めることが可能になっている、エレンはひとりで更に苦しくなり、はやく楽になりたい一心により、さぼっている手で思わず自分のペニスをいじくってしまいそうになるのだけれど、子供の行動なぞ簡単に先々まで読むリヴァイに搦め捕られた。水気の張ったまま拭うことも零すことも出来ない瞳で、リヴァイを睨むように視線を向けてみせようとも、蕩けず挑むような蜂蜜色は只々ぼやけていくのみであるのだからほんとうに救えない。互いに何を考えているのかなどさっぱり理解し合えない、暗く陰鬱で湿気った虚ろな空間が殆ど隠してしまう顔も、ランプの薄灯りで反射する、無駄なばかりにきれいなだけの双眸も。
「ひぁ、兵長……っ大丈夫、とは、言いました…っけれど……、だッ、ぁ、だからって…急にっ……でかくしな、……っしないでください、っよ、ッ」
「ついさっき大丈夫と言ったのはエレン、おまえだろうが。──ほら、きついんなら手ェ寄越せ」
「ふ、…っ、う、……それは、どう、いうッ……、ぁ、あぁっ」
「俺が支えてやるから体重をこっちにかけろってことだ。ガキ。そのほうが体勢も安定する」
「ぃや……っ、ですよっ…そんなの!」
ガキだの愚図だの暴言が名詞であるかの如く半人前以下の子供扱いをしながら、子供には到底するようなものでは無い行為を、寝ていたところを叩き起こしてまで強いておいて、おまえは大丈夫なのだろう自分でそう認めたのだからといったい、どこの誰と比べているのか。いっそどこぞで孕んだ姫君にでも『兵士長殿の赤子です。責任をお取りになって。どうか観念なさいまし』と迫られて狼狽せざるを得なくなってしまえば可笑しくて嘲けられるだろうに、などと口が裂けてもどころか死んでも言えぬ、本音からすっぱりと清々しい程に真逆の台詞を飲み下せば、喉を通り終えるとなぜに発達途中の躰のなか、内側を棘のように傷付けて、ほんとうに痛くて耐え切れなくなりエレンは自らの左胸を殴るように押さえた。痛い。痛い。痛い。泣きたい程。だからこそ絶対に泣きたくない。これは公に捧げた筈の左胸、なのに心臓部に痛みが蓄積され続けているのだと、医者の息子に生まれようとも自身は医者でも聡明でも無いエレンにさえ判るのだから、心は、心はここにあるのだろうか。それでいて今は溶けている下半身のほうがずっとあつく、怒張したまま一向におさまらぬペニスが脈打ち血液を集めているせいで、痛む胸よりどくりどくりと懸命に活動している気がする。心の在処が左胸ならまだしも、よもや腰下だとしたらどうしよう見臭い淫らさが、エレンは恐ろしくて堪らない。苦しい。実に不安定だ。確乎不抜なる何かに思い切り縋りたい。縋って自身の輪郭を確認したい。だがそれでも。リヴァイの躰へと縋りしがみつき爪を立てる、などと、云う、愚かしい真似は例え自身の生き穢い命を失おうと、エレンはどうしてもしたくないのだ。なのでしない。してはならない。そう思いながら、心臓を抉るような痛みに堪えきれず、ぎゅ、と瞑っていた目を不意にあけて瞬くと、睫毛に引っ掛かっていたらしい、いやに大粒の涙がぼたりとリヴァイの上へ落下した。自身のことながら驚嘆し見下ろせば、珍しくリヴァイが驚愕をありありと乗せた表情でエレンを見返している。
「…おい、」
「っ……、ク、ぅ」
エレンを乗せたまま上半身だけを起こしたリヴァイの腕が、エレンに向かって真っ直ぐに伸びてくる。あやすようにエレンの頭を抱き込む。こんなことは交尾よりも余程されたいわけでは無い。しかし1度決壊した涙腺は意思も覚悟も心も無視して次から次へと溢れ落ちていくことをやめてもくれぬ。
「ううぅっ…、ぅっく…ひ、──くッ」
エレンは瞼に落とされるリヴァイの唇を受けながら、侵入とは言い難い捻じ込むような圧迫感を歯噛みしひた耐えるが、耐え切れない雫と共に靜か駄々を捏ねる幼子のような嗚咽を漏らす。この状態でいるのも嫌だと、何とか小刻みに息を吐いて、望まぬ震えを抑えながら、汗ばむ手のひらに気付かれないよう、自らに赤い爪痕がくっきり付く程きつく握り締めていた拳で、せめて顔を隠す。泣き声だけでも充分過ぎる恥だ、その上リヴァイ相手に泣き顔など晒したくも無い。
「よせ、エレン。手が傷付く。どうせならこうしろ。それとも今ここで巨人になるつもりか?」
「っ…なりたく、なんて……ッあ、りま、せんよっ……!」
「だったらおとなしく言うことを聞け。おい、クソガキ、こら、」
リヴァイの手は容易にエレンの拳を力任せにひらかせる。そして拒絶を赦さずに繋がれる、父とも母とも幼馴染みたちとも違う、手を。エレンは俯き右手と左手を見詰めながら幾度めになるのだろうか数えていないのでわからない、ただ己を恥じた。同じ雄でありながら何故これ程の劣等感に苛まれなければならないのか、優れたほうが劣ったほうを支配する動植物を代表する自然界におけるルールはヒトにも適用される絶対的なものであるのかと。どうしてこのような惨めな扱いを受けねばならずにそのわけは結局まったく他に存在し得ぬのであろうかと。
ゆるく繋がれた手をエレンは不敬にも振り解く。リヴァイはそれを特に咎めはしなかった。代わり、今度は何を思うのかエレンの背中へと雑なる音も立てること無く腕をまわし、今この場で離れることは赦さぬと云うように掻き抱く。抱き締める。
「落ち着け」
「っも、……ゃだ、……うっ、ぅうぅー…いやだ、っひ、ぅ」
「黙れ。黙って心音を聴いていろ」
「……そう、いう、の……っ要り、ま、…せんッ…から、っ……」
「ガセか? おかしいな。確かガキは心音で泣き止むんじゃあ無かったか」
「っもう! なに言ってん、ですか……っ、離、…して、」
離してください。15にしては幼な過ぎる嗚咽混じりのそれが今は精一杯で、余計に惨めさが増した。エレンは優しくされたいわけでは無いのだ。甘くそうっと抱き締められるくらいならば痛みに悶絶するまで蹴飛ばされるほうがずっと良い。そして思う。決してその小柄でいて筋肉質なうつくしい躰に傷をつけてはいけないと、エレンはまるで、リヴァイのどこにも触れぬままで、怯えるように震える自分の指先に言い聞かせる。エレンには知ることも出来ぬ古傷が幾つも残る、リヴァイの、その大切な躰は、調査兵団のみに限らず全人類にとっても失われるわけにはいかぬ、その躰は、こんな正体不明の化け物を抱くためになど、出来ていないのだ。だからこそ尚更に息苦しくさえなっていく。それなのにまだ。ぎこちない動きでゆるり前髪を上げられ、徐らエレンの額と鼻の先にリヴァイの唇が優しく落ちる。いつまで経っても上手く吐息を逃す呼吸を覚えようともしないので、唇にキスをしてくれないことをエレンは知っていた。この自分でも理解の及ばぬ化け物の躰も、ヒトに抱かれるためにはつくられていない。それを証明するような、どうにもならない呼吸苦に、ゆるゆると腰を突き上げられるだけで漏れいく、はしたなく地上で溺れるが如き喘ぐ、己の声をエレンは何より嫌悪する。何もかもをきちんと、余すところ無く受け入れられるように出来てさえいれば、こんなにも不条理に苦しまず済んだのだろうか。エレンには理解らない。だがこんなにも馬鹿げたことはそうそう他に無いのであろうことなら理解している。人肌に安堵するような、赦されざる行為なぞ望んだことなど1度として、無い。
「今更おまえが何に泣いてやがるのかがわからん」
「──だから、」
さっさと抜いてしまって欲しい。全部片付けてエレンは完全にひとりになりたかった。何れ程リヴァイが時間をかけようとも心を砕くように優しくしようともそこには何ら意味も無く何も生まれやしない。し、苦痛なばかりで惨めになる一方で。エレンは何も考えたくないのだ。何も考えたくないので、あまり芳しく無い頭も使わなくて良く、て、正しいも間違いも選択を迫られることは無い、だからずっと嫌ではあっても張り付く汗や肌のぬくもりは嫌いだと断じること無くこうしてきたが。もう駄目だろうと思った。最初から限界点を超えていたのだと思った。そうで無いならリヴァイの全部を、厭うてしまったのかも、知れない。
今になりなぜ泣く必要があるのかと──さっさと泣き止んで言わねえとわかんねえだろうが、と、溜め息をつきつつエレンからの抱擁を望む、正真正銘人間であることが時折疑わしい、気高きけだものにも似た男の顔が、こんな化け物の涙にすら興奮したのかその口許を歪めながら、それでいて滑稽に過ぎる程に声だけはまだこのときも、ただ優しく。優しく訊く。
どうもしていません。どんなふうに扱われたとしても、俺はただの化け物ですので。
いったい何に怯えているのであろう、易しい言葉で綴ることをいつまでも意固地になり躊躇している。それではまるでどこかの大人の猿真似だ。暗号。そうだ、暗号にしておけば望まぬ者に無闇に暴かれ解読されることも無かろうと。これは素通りへの防衛策である。それはそうかも知れないがたぶん誰も同じだろうと躓いた感情の坩堝。向かうなんて出来ない。辿り着く先を夢見ていても、エレンはあてがわれた地面を日々蹴るだけなのだ。そして翼も無く飛び上がるのである。窓ひとつ無い地下室、ここからは見えずともあれ程までに立派な太陽にも月にも理解ってはいないのだから。誰かを励ましてやろうだとか、自分を掬いあげて貰おうだとか。姿を現しては消え続ける、それだけだ。存在における一瞬の隙。その隙へ落ちてしまう。何年も赤いマフラーを手放さずにいる少女がそうしているように、常々疑いさえしなければ吸い込まれてゆける、一瞬の記憶は永遠さえ凌ぐのであった。もう疑念は要らぬくらいにならば確かだろうこの絶望は、ここで縺れているふたりを見放さない。言い訳も、泣き言も言葉にはしないエレンの、クソくだらない強がりに。は、と鼻で嗤うかのような特有の笑い方をする。エレンの柔い耳朶をまるで悪戯な子供の遊びのように甘噛んだ、逸らしていた視線を合わせリヴァイは言う。俺にだけは嘘をつくことを赦さないと容赦無く見透かして。
「ほんとうにどうもしてねえ奴は、泣かねえだろう」
そう言われてもわからないものはわからないのだ。だからエレンの左胸は、ただひたすらに苦しくて。それ以上に悔しくもあり続けて、いて。どうすることも出来ずに無言でリヴァイを見た。視線を合わせただけでうるさいと俺の目玉を嫌ったのは貴方だと抗議するつもりで見詰め合おうとそれだけで伝わるものなど有る筈も無い。嵌め込んだまま動きもしない対面座位は腹筋が痛くて、息が続かずひどく苦しいものであった。それでも執拗にリヴァイはエレンが落ち着くまで待つつもりなのか、硝子細工にでもそうするように、抱き込む以外には特に何もせずエレンの背を一定のリズムで優しくさする。だから。だから、優しさは飽和しているのであると思い知らせてやりたいが、自分がリヴァイの腰の上に乗っかって完全に体重をかけているのだと気が付けばそれはもう不可能となる。エレンの足がよれたシーツを蹴り膝で立とうとすると、見逃してもくれずに態と裏側に手を差し入れてきて出来なくする。このままで構わない。などとリヴァイはどういうつもりで云う。そのせいでエレンは耳で聞こうとも理解が及ばぬのであった。どうしても。聞こえない。これは聞こえていても聞こえたと思えるものでは無いのだ。いつもそうだ、きっと大事であろうことを、若しくはエレンがほんとうに聞かせて欲しいと願うことを、リヴァイは出し惜しみする。それとも、こういうことすらも、エレンのためにはよかれと敢えて聞かせないのだろうか。何を言われようとも今更どこにも傷など残りもしないエレンに。自他共に認める外に無い、化け物を相手に。
子供に比べ大人は長く生きている分だけどうしたって穢いが、そんなことはどうだって良かったのだ。エレンは。いっそ穢いもきれいも全部ひと夜で事足りるのであれば出し切ってしまえばよい。卑怯にも大人が子供を大人にする丑三つ時。その不透明な気紛れに誓う。1日中陽の差すことの無い地下室で、萎れて枯れる名も知らぬ白い花。この胸の痛みが、いつかの昔両親に連れて行って貰ったパレードの、合図に吹かれたラッパの響みが如し、リヴァイの心臓にも届けばよいのだ。きらいだなんてことは無かった。エレンを愛さぬそれがリヴァイであろうとも。貰ったときに教わったのでその花言葉をエレンは知っている。『純潔』『純潔』『純潔』『純潔』『純潔』。うるさい程にリフレインする愚かしさを忘却出来ずに可笑しくてならぬ。無垢な女でも無いくせに不思議と涙がまた出ようとする。花同様ヒトも散る。萎びて枯れて地へ落ちる。哀しく無意味な結末を迎えることの無きようになど、出来るわけも無い。と、知る度もう1度だけ本物では無いたくさんの光を込めて。一瞬だって無かった。うつくしい色をしていながら暗い眼差しでしか無くとも。エレンがリヴァイを好きでは無かったのだ。そんなことは一瞬さえ無かった。
ゆっくりと。エレンの背をベッドに倒し躰を預けきるしか無いように導く両腕、うつくしく獰猛な鷹の瞳が鋭利にも爛々と、獲物を射抜きにかかってくる。それに怯えるなと云うほうが無茶である。あまりにも難題に過ぎる。開かれたリヴァイの薄い唇から覗く舌と犬歯が、エレンへと向けられている。幾ら尖ってみせたところでただの1度たりともリヴァイのそれは、まだ柔いエレンの皮膚を突き破ったことも無い、整った歯が頼りないランプの薄灯りで鈍く尖り闇色に蒼白く光る。
「エレンよ」
「…は、い、」
「俺と寝るのはそんなにも厭か、泣く程に?」
答えろ。と。囁きが痛くて、いた、くて。
いっそのことそこへ飛び込んでしまえばどうなるのだろうとエレンは思った。
「……いいえ」
あァもう何もかもが全部どうでもよい。こんな正体不明の化け物の躰であろうと貴方さえそれでも傍に居てくれればもうそれで。それだけで。貴方にならば、何をされても。何をされても、ちっとも気持ち悦くなれもしないままであるのだから。
諦めるように伸ばした脆弱なる両の手を、エレンは初めて自分からリヴァイへと差し出してみせた。首にまわされ抗えもしないで両目を閉じる。あとには何も残らぬよう喰い尽くされようが削ぎ殺されてしまおうが、リヴァイによって与えられるものは全部受け止めるべきものであった。エレンは全身で縋りつくふりをする。リヴァイはまたも眉間を寄せる。縋れと命じる。その命令には従わない。自身の輪郭すら曖昧になる程に、不気味で異様な何かに構築されている躰。エレンがこの世界で最も憎悪する巨人と同じ、躰だ。
「初め…から、俺の生死も、こんな、気持ちの悪い躰の処遇も、貴方の采配ひとつでどういうふうにも──決まるんだ」
それこそエレンが泣こうが喚こうが、リヴァイの好きにすれば良いのである。リヴァイはエレンを思い切りつよく抱き締める。その瞬間エレンはたまらなさそうにくしゃりと顔を歪めた。リヴァイが膝をつきエレンの腰を持ち上げると、ぐちゅりと淫靡な腸液の音が地下室内に響き渡り、それはそれはひどい気分であった。けれどリヴァイはやめず、エレンも最早黙して自身が子供であることからも化け物であることからも今は逃れ兎に角はやく、この生産性皆無にも程がある、無益なる交尾を済ませてしまえばよいのだと。けれど抜けた分は逆向きの力を加えてやれば簡単にはいるのだろうと思い肘を立てベッドへと点で体重を掛けたエレンはまさしく理解の足りない馬鹿な子供であった。障りが有り叩き付ける抽挿の衝撃に姿勢を保つこともろくに出来ずぐらりと傾き脳が揺れた。
「馬鹿が。こっちだと何度も言ってんだろう。滑り落ちてえのかよ、てめえは」
ついぞ顕著に咎める声と共に、振り解こうがすぐ繋がれる手を、ぐん、とリヴァイが引っ張り上げるものだから、エレンの軽い躰は前のめりに、もがき宙を掻いた、剣だこも無い未熟な指の爪の先が、事故のようにリヴァイの胸元を掠めた。掠めてしまった。故意でなぞ有る筈が無い、完全なる事故。ガツ、雄同士贅肉の無い躰がぶつかり骨が軋む鈍い痛みにふたりして呻く。僅かなりに先に回復したエレンは自分が今どうなっているのか、己の状態が少しだけ気になったが消失せぬ恐ろしさが勝り瞼を上げることが出来ず、正直に云えば裸体を見るまで信じられなかった固く屈強な、逞しくも分厚い筋肉に覆われたリヴァイの躰の、丁度肩のあたりへと頑なに額をこすりつけていた。
「おい…無事か。エレン」
「ン、ぅ…ちょ、っと……把握、出来ません……」
「痛みは?」
「、有り…ます」
「動けるか?」
「…………怖い」
こんな生産性皆無にも程がある、無益なる行為。ちっとも気持ち悦くなど無い。痛くて苦しくて惨めで劣等感に苛まれて、リヴァイに優しくされる、交尾。エレンには、己が躰の、あちらこちらが痺れていることが、もしかすると気持ち悦いとはこういうことを謂うのか、若しくはそんなものはとんだお門違いでまったくそうでは無いのか、そんな瑣末さを識ることすら躊躇われており、とりあえず可動を確かめるに首を横へと振ったその喉仏に、小さく音をたてるだけのキスをしたリヴァイが、あくまで丁寧に手を這わせる。脆い宝物を大切に扱うように注意深く慎重に、慎重に気を付けながら抱きとめたエレンの肩越しに、じっと、暗くうつくしい双眸を落とす。
「い、たい。くるしい。つらい。きつい。きもち、わるい。へいちょう。いた、い」
言葉を覚えたばかりの幼児のような辿々しさで、思うことをそのままリヴァイに伝えてみれば、研ぎ澄まされたうつくしい双眸が僅か、細められ、エレンは今晩中でこの上無く悔しくなる。見られたくない、見たくない。けれども。ぽつり。冷徹であるべきリヴァイが呟くのだ。あたかも突如として何か大事なことを思い出したかのように。
「…そうだな。俺もきつい。エレン、おまえと繋がるときはいつも、いてえだけだ」
ろくでもない歯噛みを隠そうともせず、また、誤魔化しもせず。お互い様だとすら口にする。全然お互い様では無い行為であることを棚に上げるそのすぐあとで、エレンは嘗て見たことも無いリヴァイの少し困ったような含み笑いを見たのであった。
「やめちまうか。何もかも全部」
なァ、エレンよ。と、それは問い掛けでは無くリヴァイなりの提案だ。何もかも全部? ひと夜にして何ら前触れも無く、何もかもの全部ががらりと変わるということが。そんなことが。平気で起こり得る世界のなか。起こり得ぬわけが無かった世界のなか。エレンにとって唯一の指針のように不変であった気高き鷹の如き男が、ひと夜にして何ら前触れも無く、エレンの何もかもの全部を投げだそうとしている。こんなにも生産性皆無にも程がある、無益なる行為なのだから、見詰め合うことにすら後付けの理由を付けなければならぬのだから、考えずとも喜ばしいことではあるまいか。単純に頷けば良いものを、ただの化け物でしか無いこの醜悪極まりない子供の躰は、リヴァイの背にまわしている指先に僅か、ほんの少しだけ、取るに足らない程度の力を無意識に込める。勿論それでも相も変わらず理解不能な恐ろしさを払拭出来ずに、リヴァイの躰へと縋りしがみつき爪を立てる、などと、云う、愚かしい真似は例え自身の生き穢い命を失おうと、エレンはどうしてもしたくないのだ。だからしない。してはならない。けれどそれは幾らリヴァイが面白く無さそうにしようともリヴァイ自身にも云えることである。だって、そうなのだ。エレンの柔く白い皮膚にはリヴァイの歯型ひとつ残されたことが未だ1度として、無い。
「痛い、です。…だけど、繋がって、いた…い。何れ程、生産性皆無にも程がある、無益なる行為、であろう、と、も、……居たい」
あァ、いたい。いたくてたまらない。それが如何に歪つで不様なかたちであったとしても、それが如何につらくて息苦しく惨めで苦しいばかりであったとしても。ついででよい。投げやりでおざなりで乱暴でも唇に噛み付くようなキスが欲しかった。甘やかなだけの優しさならば今このときですら地下室中に飽和しているのだ。気持ちの悪い程に。それでもよい、それでは嫌だ、どちらにせよ結局のところ、やめたくない。やめて欲しいのにやめて欲しくなくて離れたくない。兵長、とエレンは縋るように呟いた。ほんとうに縋りしがみつくことはどうしてもしたくない。するわけにいかない。
「そうか」
「……はい」
「だったらもう、仕方ねえ」
「はい」
「きつかろうが痛かろうがおまえが何れ程厭おうが繋がって、居てえんなら」
「……──そうです、ね」
ひと夜ににして何ら前触れも無くがらりと何もかもの全部が変わる世界であってもまさかどこかの幸せそうな恋人たちのようにはいかない。他にはどうしようもないのである。どうしたって、いたいものはいたい。仕方の無いものは仕方が無い、そうするより他に術が無いのだ。
「なら我慢しろ、エレン。俺もそうする」
返事の代わり、エレンはこくりと小さく頷く。ふたりして躰の奥底から滲むどろついた感情を廃棄して深い、息を吐く。こういう妙な優しさはおそらくずっと不快であろうが。矛盾しては我儘な忌むべき巨人と成る化け物の、少年兵の皮をかぶった憎悪で構成されている、躰。兵士にしては薄い肩と、頼りない腕と、胸筋の発達が著しく悪い胸板に、リヴァイはねぶるようなキスをする。エレンがそうされたく無い程の、しなくてよい程の優しさで繰り返し。ならばもう精々勝手に優しくしていれば良いのである。そうされたいとエレンから望んだものでは無い。きっとそう遠くないであろう未来をリヴァイは何らかの選択の元、執行するのであろう。この化け物の薄い肉と夢の消滅は、決して避けられぬものだろう。傷付けても傷付け無くても──死んでも、死ななくてもだ。こうして抱き合った記憶さえ嘘のようにエレンもリヴァイも。薄灯りを灯す古ぼけたランプのなかで短くなっていく、火が揺らめく蝋燭のように消えてしまうのだ。うつくしくは無い。哀しくも無い。それは只々あくびが出る程に当たり前のことなのであった。エレンは姑息なふうに窺い見て、リヴァイの裸体を観察する。兵士であれば羨まずにはいられぬ大層な躰の、その浮き出た鎖骨の上あたりに真っ直ぐと、若干赤らんでいる引っ掻き傷がスゥ、と1本エレンの双眸に焼き付くように映る。完全なる事故。しかし他の誰でもないエレンが、つけた。掠めてしまった爪の先がつけたもの。傷とも呼べぬ傷はきっと巨人の治癒力なぞ持たないリヴァイでも明日には消えているであろう、その程度の。けれども自己嫌悪で見ていられずに眼を俯ける。それに気付きながら、否、気付いたからこそリヴァイは嗤った。は、と特有の笑い方でエレンを追い詰めるのだ。
「見たか。おまえが付けた」
「すみ、ません」
「触ってみろ」
「……出来ませんよ…意地の悪いことを、言わないで、ください」
「こんなもん傷でも何でもねえだろうが」
「でも、」
でも、だけれど、貴方は違う。
「それ程気に病むくらいなら舐めろ」
「まさかそれ…本気で言ってます?」
「さてな。俺はどうもなっちゃいねえよ。寧ろおまえの孔のほうが余程赤く腫れて痛そうだが? ほら、ここだ」
「へっ、アッ……うあ、っ…ク、ゥウ…、んんぅっ」
「──……」
ペニスが挿入ったまままさぐったリヴァイの指にエレン自身今までに発したことの無い、不格好な喘ぎでは無いもっとずっと甘ったるい高めの声が飛びでて、ふたりして瞬間的に時間という概念を失い忘れた。いや黙られてしまうと居た堪れないです何か言ってくださいやっぱり黙って無視してください、と、思わずにいられないのに言葉に出来ぬ、正直に頬だけが血を昇らせ真っ赤に火照る。視線がうるさいとはもう言われていないが合わせられる筈が無く、エレンは意地でも俯けた顔をリヴァイの視界から逸らし続けた。
「…おい、エレン」
「……………………はい」
「今のは何だったんだ」
「……理解りません」
「態とか?」
「あの。やっぱ兵長の仰った通りやめましょう。何もかも全部」
「仔犬が甘えたみてえなイイ声がしたんだが」
「…お、俺じゃあ無いです気のせいですこっち見ないでください俺も見ませんから」
「うっかり愛してやりたくなるような、いじらしく健気な感じの──」
「それ以上口になさるなら、舌、噛み切りますよ」
「巨人化してえのか」
「うぅ…」
狡い。いつもと違う上目遣いの景色と、合図のような、暗号のような、隠されていたものが如実に噴き出す。しとどに濡れたペニスをリヴァイの手が掴み、躰中、届くところは隈なく舐め上げるキスに揺さぶられ掻きまわされていくエレンは、その歪つにしか繋がれない容れ物が嘘のようにどんどん溶けだし素直な液体になってゆく錯覚を覚えて悶えた。リヴァイのかたちに添ってリヴァイの体温に染まり、血迷うように、ただ与えられるものを享受するばかりでは無く何か、何だって構わないので何かを少しでもリヴァイのその尊い肉体に蕩けて入り込めはしないかと何度も何度も押し殺した、切なく痛む心と激しく暴れている動悸と、果ては化け物たる醜さすらも移せたならばと願う。そんなことは赦されないとリヴァイより誰よりも、エレン自身が寛恕し難いことであった。
「っふ…あっぁっ、……うぁ、っあ、ン……っく、へいちょ、うっ…兵長……ッ」
追い上げられて絶え絶えの呼吸でエレンはリヴァイを呼んでいた。
「悦いか」
「わか…っりません……、ク、ぁ、あぁっ」
「俺もだ」
抽挿を止めずエレンへと降り注いでいたキスがやむ。ただでさえ世辞にもよくは無い目付きで、その瞳を細めるだけでリヴァイは呼び返してもくれない、残酷な程の優しさは腹立たしさと諦めを揺るぎ無き事実にして、ひどくて、狡猾で、化物である躰さえ蕩けさせる圧倒的なつよさでもってしてリヴァイはエレンを、捩じ伏せる。
「んんぅ……っ、は、…ア、っ……あ、あ、ぁあ……っふ、…うっく…ゥ、んっぁ、ああっ…!」
「おい、聞こえるか」
「はっァ…、ン…──っは、い、聞いて…ます……っ、ひぁっあ、ぁうっうぅ……ッつ!」
残念なことにエレンの耳は聞きたくもないぐちょぐちょと鳴る腸液の音も、扱かれ苦しいペニスが零すみっともない音も、女のように上がる己の声も乱れきった呼吸音も、リヴァイと肌がぶつかり合う途方に暮れたい程の音も、すべて拾い上げているのである。気が狂いそうだった。
「聞こえているならそのまま聞け。なァ、おい、おまえは。おまえは誰が傍に居ようがたった独りだろう。たかが意味が無いくらいで、たかが価値が無いくらいで、怖いだのと簡単に言うんじゃねえよ。人間はみな幾らおまえを好いてみようとも警戒心を緩和していこうとも、おまえが化け物であることを畏怖している」
「んう…も、いく……っひ、ぁ」
「……クソガキてめえ、聞いてねえだろ。早漏が。俺が達くまで耐えてみろよ、何なら徹夜で付き合わせてやる」
「っそ…!?」
遠慮の無い舌打ちが懐かしく正しい。優しさならば要らないのだ。エレンは吐精を終えた躰が身震いするのを自らの両腕で抱き締める。リヴァイからの抱擁なぞ欲しくも無い。荒い吐息を整えながら浸る。エレンはリヴァイの云う通り、独りであった。誰でもよいのだ。誰かが笑って幸せそうであるのならば。生産性皆無にも程がある、無益なる夜はやがて過ぎていく。おそらく星は輝きながら愛されながら夜空へと零れ落ちるが、それを今知ることはエレンには赦されていないのだ。振り払おうとも繋がれた手は当然の顔をしてリヴァイより小さかった。それは手だけに限らずに。自身で思っていたより随分と頼りなかった指の僅かな隙間からさらさら、さらさら零れて消えた。それは白いシーツの狭間で揺れる不愉快な程甘く、寝酒代わりにしては優しいだけ、ただ、優しいだけであったのだ。俯いて視線を外すことを余儀なくされていた時間はエレンにとって、黙々とリヴァイを否定する時間でもあったけれど、かと思えば、抱き締めたいものを抱き締めたいだけ抱き締める時間に成り下がり上官で無ければぶん殴ってやりたいと思っていた。どの時間も同等だと望んだ分だけそこにあった、のは、リヴァイの思惑でしか無い。エレンは初めから気付いていた。この世界はヒトがどう望んだかということの、単純な結末でしか無いのだと。だから誰でもよいのだ。誰かが笑って幸せそうであるならば、喜んで。繋いでいる鎖をある日突然木っ端微塵に、飛び立つばかりに欣懐として、破壊してやることも有るのであろう。
「ひくっう、おれ、いまっ…いったばっ、か……で、……ア、ぁあっ」
「言っただろ。俺が満足するまで付き合えと」
「く、うぅっ……もう、っ……ァ、ま、たっ……」
朝方まで続けられるのであろうリヴァイ曰くの交尾、は、寝酒代わりどころか、ひどくリヴァイの目を覚醒させ、その間にもエレンは幾度射精したのかも数えていないのでわからない。朝日が昇ろうとも明けぬ夜が在るということを、おかしい、己はただの化物であるのにその筈であるのに、忌まわしい躰には、リヴァイの呆れや怒りを孕んだ気持ち悪さを性欲に変換した熱を、刻まれいくのである。傷にはならぬ。エレンは厭い、リヴァイは厭うた。深く不覚ふかく不快に正常でいられるわけも無い、けだものの目をしたふたりが妨げ合っては散らかして、これではどうにも片付けられそうに無い、そんなところまで、だ。
「根拠も無い感覚での、同意と共感なんて…気持ち悪くありませんか。貴方も、俺も」
それでいて尚、憐れな程の青臭さと否定は、切っても切れない関係性を断じて崩しはしない。その結果やがて迎えるしかない朝に、破かれること無き互いを隔てる膜が、収縮する瞳孔と感受性を道連れにし、在りもしない崇高を維持していくのだ。濡れた箇所は何処もかしこも血に濡れた一矢に似る光が、宿っているかの如く昨日までとは明らかに違う何かが重ねた皮膚の下を流れて。可能性はいつもあやふやでしか無く、紡ぐ言葉の構成は贔屓目に見ようとも骨と皮ばかりだ。未だ老いを知ることの無い子供の躰は匿われることを拒絶しながら、それでも兵士として長く血を浴びてきたリヴァイのその手首の内側がいつも、己に向けて無防備にさらされていたのだということを、知りたくも無い、エレンは知らせられざるを得なくなったのであった。
ひと夜にして、何ら前触れも、無く。
擦れ違いつつそうでも無い/互いが互いの思考を理解していないようでそうでも無い/自分自身の思考不可視と思いきやそうでも無い/両片想いのようでそうでも無い/ぞんざいなようでまたそうでも無い/色気無く淡々と18禁行為をするだけの上官と新兵的な関係のようでそうでも無い/でも何だかエレンが女々しくおとなしい/兵長も何か無意味に優しい
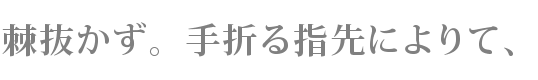
ひと夜にして何ら前触れも無く、何もかもの全部ががらりと変わるということが。そんなことが。起こり得る世界なのだろうか。疑問を持つより先に知った、答えは『起こり得る』どころか『起こり得ぬわけが無かった』だった。富豪も貧民も平等に誰しもがその経験者で溢れている。
それでいて尚もまだ、憐れな程の青臭さと否定は、切っても切れない関係性を断じて崩しはしない。子供たちは無論のこと、過去に子供時代を置いてきた大人たちですら、ようようそれを繚繞すると思い知っている。ただ束となった藁がばらばらと頭上へと、埋め尽くす程の勢いを持ってしては次々と振り落ちてくる感覚に息も絶え絶えである隙間から善悪を問わず甘味の破片を散らし──散らかしては片付けもせずにどこかの誰かを容易く嘲笑させるに足る。のだ、と。けれどエレンは信じてなぞいないのだ。今の自身を覆う本物らしき何ものもを。ヒトというものについてたいして知らなかった頃、エレンは誰よりヒトだった。原始的、本能的に。まともにヒトで在りたいと思った頃、エレンはただの化け物だった。無意識的に、意識的に。ゆえにそれは多忙により若干不眠気味のリヴァイをも寝付かせるに足るのである。理由が必要ならばそれで良い。真実がどうであるのかはまた別として。必要なものはでっち上げてしまうべきなのだ。
ならばほんとうは既にもう、何もかもがどうでも良いのかも知れない。理由も動機も所詮後付けにしかならぬのだから。そんなものをきれいに並べ立てひとつずつ数を数えたところで仕方が無い。手っ取り早ければよいのだ。ここに正論を求めはしまい。こじつける意味なら容易い。犬猫と違い、兎などの動物と同じく人間には発情期というものが無いのだ。それは即ち、年がら年中季節も期間も問わずに常時いつ如何なる状況であろうとも発情することが可能である、ということだ。辟易する。上官に逆らう選択肢を与えられること無き新兵である立場を差し引いても、自傷行為と明確な目的意識によって奇怪にも巨人化する、己自身メカニズム不明な未知の能力を有しているエレン・イェーガーは、目附役の兵士長に尽く疑問をいだいていた。だが今更それについて考察し議論する価値が無いことも、幾ら頭の宜しくない自覚があれど知っている、ので、せめて、異性経験が確かに有り実際に女を抱ける男が敢えて、なぜ雄として同性である雄に対し欲情するのかだとか、その切っ掛けとなるトリガーはどこに在るのかだとか、率直に特殊であるこの現実における、別々の、躰が躰を求める要素と因果関係が解明されるということがいつしか起こり得るならば、心の準備が出来る分くらいは幾らかましであり、仮にそれらが解明されてしまった場合、その何らかの条件が揃っているようなときには、絶対に、エレンはリヴァイとふたりきりの屋内において迂闊に近寄らないよう細心の注意を払い慎重に、慎重に、気を付けながら生活しておりさえすれば、きっとそれだけで今よりは、幾らか楽になれる筈だ。おそらく。そうで無ければ困る。し、寧ろエレンは今まさに現在進行形で懇望もだしがたく窘窮し襲い来る眩暈にどうすることも赦されずにいる。掃除と訓練その他諸々で疲れた躰を休めている子供の、間抜けな寝顔のいったいどのあたりに、雄を欲情せしめる要素があったのだろうか。何れにせよ無防備な就寝を悪意も持たずリヴァイが邪魔することは、エレンの意識且つ既になけなしの人権への、蓋然的な拒絶であり否定であった。
リヴァイとの付き合いが長い者からの言い分としては、リヴァイは同性から妬み嫉みを買うことは特に無い、有るとしても興味が無いので気付いていないだろう、と謂うのだがそれはたぶんにしてその見目、目付きは勿論であるがそもそも雰囲気から凄みが有り過ぎて、事実、凄みばかりか実力派であるからして、妬むより嫉むよりもまず調査兵団の兵士としてリヴァイという男の、人となりを知らぬ一般男性陣は、リヴァイを人類最強と称えつつも単純に恐怖し敬遠しているだけなのでは無いかとエレンは思いながら、意外と他人からの視線の意味に鈍感らしいリヴァイの、デフォルトである無表情をここぞとばかりにじっくり眺めてみる。そこには何らかの理屈が働いての意図はまるで無く、意味ならもっと有る筈が無かった。
「何をそれ程熱心に見てやがる、愚図野郎。俺の面に何かついてんのか」
「あ、いえ。すみません、別に」
「おまえの視線はうるせえんだよ、エレン。目は口ほどに物を言う、とはよく云うが、おまえの目ン玉は喧し過ぎる」
鼻先三寸と云ってもよい程の近さでエレンの目前をリヴァイが妨げているのだ。ならば見詰めてみれば見詰め返されるものであるのかと、ふと恣意に従った程度で、当たり前のように軽く人類最強の脚力で腿を蹴られた。軽かろうと痛くないわけが無かった。だが暴力反対とエレンは言わない。なぜならばリヴァイにとって、口より手より先に脚が出ることは珍しくも何ともない極々ふつうのコミュニケーションのひとつ、謂わば彼なりのボディタッチなのである。理不尽だがリヴァイが理不尽のかたまりであることは自然の摂理にさえ等しい。とさえ断言しようとも、差し支え無いものであるのだ。少なくともエレンにとっては。仕方が無いのは、気に要らぬと躾けるところから指導が始まるエレンのような若い新兵相手のみならず、例えば分隊長を長く務めリヴァイより先に兵団に所属していたらしい──つまりは実質的にリヴァイより先輩兵士にあたるのだという──ハンジを相手にも足蹴にする様子がよくよく観られる光景ゆえに。よってエレンは腑に落ち無かろうが関係無い、視線がうるさいって何ですかわけが理解りません、といった問い掛けも、今や、してもまったくの無意味であると知っていた。この足癖の悪さと口の悪さをリヴァイから抜き取れたとしたら、目付きに多少問題があろうとも顔の造形は全体的に整っているし地位も名誉も武勇伝も持ち合わせているしで、ただもう少し紳士的に、にこり、と、愛想好く微笑むことが出来れば、女性という女性は軒並みリヴァイの虜になってしまうだろうに。それが現段階では人類最強と呼ばれる男の遺伝子を残す、脚色せず生々しく云うなれば、リヴァイの精子を手に入れることで他家との差をはっきり見える形として箔をつけたいだとか赤子を足掛かりに更に上流社会へ取り入りたいだとか、何だかんだとおぞましくも穢らわしい、金持ちの豚に分類される大人たちの目論見による泥々とした欲望と牽制蠢く見合い話が、貴族やら商会やらからは無駄に多数打診があるようで、それらを波風を立てぬよう逐一穏便に断る面倒臭い事態は、実のところエレンが調査兵団に入団を果たした昨今よりもずっと以前より変わらず続いているのだと。真っ当な精神を持つ人間たちとはとても思えない。大変に異常である。非常にくだらない話である。いつだったか、はァそうなんですかそれは大変ですねえ、とつい零したエレンには無論悪気などほんの僅かどころか緑葉に乗る朝露程も無かったが、リヴァイは手元でも無く況してやいつしか子供に向ける残念顔などでは無く何か別の影を漂わせ、ひとり、腹のなかを不穏にするようになっていた。やはり理不尽である。理不尽であるが仕方が無い。見詰められていたので見詰めてみた、ただそれだけで視線がうるさい、と眉を顰められてしまえばどうしろと言うのか、エレンは不条理と共に窮屈そうに背中を丸めて。そうして姑息なふうに窺い見た。けれどもリヴァイに云わせれば昼間の屋外や誰でもよいが第三者らの存在が近しい普段はまだしもふたりきりの室内にて、エレンの蜂蜜色をしているおおきなふたつの目玉による視線は、目が合う筈の無い背中越しですら変わらずうるさく気になるものであるらしいので、リヴァイの頭の微動に反応するように瞬時エレンは、反射的に、さっとまなこを逸らす癖がついていた。否それでも垣間見えた、見えてしまった眸の奥の色彩。濃い茶色がかった黒にネイビーブルーをぽとりと落として掻き混ぜた、うつくしい色をしている両の瞳に、見蕩れるよりも何よりもまず真っ先に背筋に脂汗が滲むのは、その眼光が隙無く鋭く、どこまでも冷徹さを秘め何の気構えも無いままにうっかり触れれば、手入れの行き届いた斬れ味の良い刃が如く、いっそ芸術的なまでにきれいな程、削ぎ落としに掛かられそうだからだ。やばい、危険だ、本能がそう訴える。しかしひとつ間違えてはならないのは、エレンに限らずリヴァイと同じ空間に存在するものはどのようなものであろうと逃げ場など無い、ということだ。だからエレンは常々諦めるしか無く、同時いつでも悲愴な覚悟を決め腹を括ることを余儀なくされているのであった。それは他者からすると同情と憐憫にも値するものですらあるとのことだったがエレンは疾うに充分慣れていた。慣れは恐ろしいというが別段そうでも無い。慣れようがどうしようがエレンは確かに恐怖しているのだ。だがそれが何れ程憤懣やる方ないものであったとしても、為ん術なき恐怖を齎すリヴァイの思考を理解するべく努めたところで、何ひとつとして真実を汲めない、理解の及ばぬ事態について逐一考え込み落ち込むほうが面倒だ。と謂うエレンのスタンスを、まさかとは思うけれどエレンきみ、麻痺して鈍化しちゃって無いよね? とは聡明で心配症な幼馴染みの有り難い弁であったがエレンはたぶん聡明な幼馴染みに比べ野生的順応性が高いのだ。ついでに頭を使うより躰を動かし悟るタイプでもあった。
その確固たる証拠が現在この場で起きている。あたかも単なる寝酒代わり当然の様子で鎮座して。リヴァイはそれを、交尾だと称した。
訓練でも何でもない、肌寒く冷え冷えとしている筈の地下室内にも関わらず、ふたり分の汗が散り密着した肌が滑りを帯びている。その生理現象に身を任せ滑り落ちてしまえば固い石床へ叩きつけられるしか無くなる。よってエレンの躰は自然、いつも閾下として勝手に強張った。が、エレンのほうからリヴァイへと触れることは無い。ただの1度もだ。それはエレンの意思だった。だからいつでもリヴァイは仏頂面を隠さずに、エレンの手を取り己の首にまわして遣らねばならず、それでも抱きつかせただけの頼りない腕は心許無くも物足りない力しか込められない。
もっと確りしがみつけよ何度同じことを言えば覚えるんだ面倒臭えなクソガキ、とリヴァイは澹如たり吐き捨てるが、もっと──もっと? 何をもっとなのかとエレンは思う。だってどうせこの躰は頑丈に出来ているのだ。女では無いどころか最早(エレン自身が望んだわけではまるで無いのだけれど)一般的なふつうの人間ですら無いのだから、ならばそれこそ、もっと、猶以て壊すように抱けば良いだろうにリヴァイは、据えた瞳でエレンの肩口に軽くて甘やかなるキスをして、着痩せするその小柄な見目だけでは想像も出来無かった、実戦的な筋肉だけでつくりあげた雄偉なり裸体で、エレンより随分と雄々しく節榑立った手を、交尾、と呼ぶにはあまりにゆったりと、乱暴さの欠片も匂わせずにエレンの背中へ優しく這わせる。あァ嫌だ、これだから嫌なのだとエレンは瞬く。寧ろ憂さ晴らしにされるだけ、丁度都合よく使われているだけ、便利で気遣う必要も無いからだと冷淡に扱われるだけであるのであれば、構わなかった。しかし、自分だけが気持ち悦ければ良いような横暴さを、リヴァイはエレンとの曰く交尾、において少しも挟まない。普段の酷しい足癖やらのほうが完全に嘘で、壊れ物でも扱うかのように躰中にさわって勃たせてから丁寧にとろり、垂らされる香油がまるでうすい膜を纏い、つうと未熟なアナルから内腿をつたい落ちていく。憂さ晴らしなら憂さ晴らしらしくされなければ困る、言葉にしない動揺を抱え募らせ、けれど若いペニスは腫れぼったく素直に反応していくだけなのだ。
あァまったく嫌だなあ。もうほんとうに、嫌だ。
遣り切れなくて割り切れない。エレンの面持ちはずっとそれを顕わに示す。
現時世、ただでさえあらゆる物資が不足しているなか香油など高価な上、腹の足しにもならぬ単なる嗜好品でしか無いものである。そんな貴重なものをどうして態々取り寄せてまで、雄同士の交尾のためなんかに消費するのか、それは勿体無いばかりの、多大な無駄遣いでしか無いのではあるまいか、エレンにはまるきり意味が理解らないのだ。リヴァイのように男のアナルへペニスを突っ込んだ経験がエレンには一切無く、おそらく今後もそのような機会は来ないだろうことからこそ、実は滑りが悪いと挿入する側も痛いのだと体感することが無いがゆえそう思うのかもしれないが。ただ、ひやり、冷たいリヴァイの指先がたっぷりと垂らし挿れてゆく濃厚な薔薇に似た香りをかもす香油がなぜか矢鱈にあついのは、優しいばかりの愛撫を施され過ぎて脳が煮え滾りそうにエレンをあつくさせていくのはきっと、わけのわからないせいかも知れなかった。
「っ…は、ぁ」
つい罷り間違い出た溜め息が唇に引っ掛かり割れて、濁る空気に溶けていく。どのようにしようとも昂っては巡る不安定な熱を、聊けしくも散らしてしまいたくてエレンが自ら腰を揺すれば、それを見下ろす柳眉がかすかに寄ってそこへ張り付いた異様なる怒気が色濃くなる。何がそれ程不満なんですか兵長、子供の浅慮さで愚行にも呟いてしまったならば取り返しのつかない目に合わされることを既に身をもって知っていた。エレンは憎き巨人を駆逐し外に広がるおおきく眩い、幾度夢に見たかももう数え切れぬ輝かしい遠い世界を、双眸に焼き付けるため見てまわるまでは、何れ程『死に急ぎ野郎』などと不名誉な渾名をつけられる生き方をしていようともまだまだ命が惜しい、ので、死ぬわけにはいかないのだ。それゆえほんとうならば、ヒト1人につきたった1度きりしか与えられていない、限り有る短い人生において、こんなにも生産性皆無な交尾に興じる時間程に無益なものは無く、勿論そも予定にも無い。意志は変わらないのにただの飾りでは無い両の耳が、僅かな息遣いから聞きたくも無い醜悪で猥雑な水音まで律儀な程丁重に拾い上げる。このままではいけない、死ぬ。余所事ばかりのエレンのシャツの上から、脚の付け根の外側をリヴァイの手が掴むと直ぐに、もっと深く、怒張したペニスをエレンの体内へ押し込まれた。
「い゛ッ……つ、ぅうっ!」
真実を明かすならエレンの躰は、否、尻孔は疾っくにリヴァイとの交尾には慣れているため然程痛くは無いのだ、が、反射的に嘘が唇からついて出る。リヴァイが地下室へ降りてくる直前、ほんのつい先程までぐっすり眠っていたのでエレンは躰の感覚が大雑把から未だきちんと戻っていないままなのだった。抜かず体位を変えようとするリヴァイを囲うようにベッドの上につき体重を支えさせられる両手が淡く痺れ、片方ずつ結んでひらいてを繰り返しまぎらわせようとしてみたけれども、全然思い通りには動かない。そしてそうこうしている間に更に痺れていく神経が、意に反して忌々しい。決して声に出しては言えないが己の躰が己のもので無いような、この不可思議な感覚をエレンは厭うた。それはつまりこの薄っぺらい胸がはだけているのも寝乱れたせいであって、リヴァイはまるきり関係無く自分も下だけ衣服も下着も今どこに放置されているかわからぬ不格好な佇まいではおらず、腰から爪先までを覆う上掛けの下では実はあらぬところへあらぬもので繋がってしまっている、ということのすべてが、何かの間違いか有り得ない妄想か或いはストレス性の悪夢であれば良いのにと、叶うならずっと疑っていたい理性が、平常心を断固として手放さない。だが上昇をやめぬ体温のあまりの熱さに吐息が荒々しく弾んでいるのは明らかにリヴァイよりもエレンのほうであり、重ねるべきで無い肌が重なりいつしかペニスを嵌めたまま捩るように引っ繰り返され、どういうわけだろう気付けば騎乗位で見下ろしているのもエレンであるのだから、もしかしたら、傍目にはエレンだけが蓮葉女のように猥褻さを溢れさせ発情しているかのように見えるかも知れない。如何に優しくされようとどこもかしこも苦しいだけで、ちっとも気持ち悦くなど無いのに。そんなどうしようも無く情けないエレンの思考を見透かす大人げの無い大人によって勢いよく、ずぐ、と突き上げられ強制的に遮断を促され、歳若きと云えど大変に気持ち悪い、エレン自身こんなものは自分の声では無いと耳を塞ぎたくなる程の声が、紛れも無く変声期を終えている男である声が、あだめいた交尾によって息苦しく小さな喘ぎを洩らす。
こんな夜伽。
リヴァイに何があったのかを訊く権利が、例えたかだか一介の新兵だろうと巨人化する化け物だろうと性処理の道具だろうとエレンには有って然るべきであった。けれどエレンは好奇心や関心を寄せることをしない。リヴァイの嫌う、過度に豪奢な社交の場にてどこぞの貴族にでもまた気色の悪い話を振られてきたのかも知れないだとか、ごてごてと着飾り人工的な香りを漂わせる姫君たちに言い寄られてきたのかも知れないだとか、そういった、任務同様に或いは任務以上に避けられない、潔癖なリヴァイには拷問にさえ均しい時間が夜更けまで続いたせいなのだろうということならば、エレンの経験として最も知るところである。では迂闊に話題に出してはならない。仮に具体的な話をエレンの耳に入れ教えたいのであればリヴァイが自分で話す筈だ。なのでエレンは黙って、リヴァイが命ずるまま脚をひらくだけで、もう疾うに投げ棄ててきた羞恥なぞ今になり感じることも無く馬乗りになった腰が砕けぬよう必死に、奥まで呑み込まされている太いペニスをリヴァイが満足するまで揺さぶり揺さぶられ、アナルの奥の奥までを搾り使い突き上げられる動きを享受するのである。そうして漸くにして、要はエレン以外の他の誰かによってリヴァイの胸宇に生じてしまった、呆れや怒りを孕んだ気持ち悪さを性欲に変換した熱を、エレンの躰が受け止めるだけなのだ。リヴァイがエレンに挿入しやすくするために予め準備し、先刻使用した香油が甘ったるく不快な匂いを放ち、いつしか地下室中に充満している。ひどい。シーツは洗濯し干してしまえば良いが、風を通さぬ閉塞的な室内はそういうわけにはいかないのに。とか、態とすべてをリヴァイのせいにするような責任の所在を押し付け続けていれば、エレンの、引き攣り狭くなる喉を掻く意味のわからぬ痛みは徐々に薄れいき、少しずつではあるが何となく楽になれる。気が、して。同じように僅かにエレンは安堵した。項垂れると癖も無い清潔でしなやかな黒檀の髪が、エレンの目先に迫る。ブルネットより深い夜のような、光の欠片も無く最も黒々しい常闇を流し込んだ、うつくしい色。
「……おい」
暫時噤んでいたリヴァイの、低く掠れた声が不機嫌そうにエレンを呼んだ。
「? はい」
「てめえは、まだ痛えのか」
「はい?」
「ケツだ。切れちゃあいねえようだが……」
「あー…だいじょうぶ、です。たぶ、ん」
「そうか」
だったら痛そうな声を出すんじゃねえまぎらわしい、とでも云わんばかり、チ、とリヴァイにしては似合わぬ程に控えめな舌打ちが、しかし、あたかも鬱陶しげに響いた。それさえ優しさの一部であるなら嗤える。痛くも無いくせに痛いとエレンの口端をついたのは、決して嫌味のつもりや、リヴァイを困らせたいわけでは無かったが、心配や労りを示されるのであれば違う部分でして欲しいとエレンは思う。そもそもの、この生産性皆無にも程がある、無益なる行為から。
──交尾、から。
「えっ? く、ぁうっ、…ちょ、待っ…っ」
ペニスだけでもういっぱいに拡げられている本来出口でしか無いところを入口に変えられている真っ只中、前触れ無く無言の指先でくるりと撫ぜられそのせいでエレンの背筋がおおきく震えた。嫌だ嫌だと思う心を裏切って、躰がほんとうに変化を起こしたことをエレンは経験則から否応無しに理解する。腸壁の粘膜を巻き込んで、腹が苦しい程の圧迫感に支配されながら、前立腺を擦りたてられると勝手に涙腺が緩み涙が出そうになってしまうのだ。みっともない、そんなことを知られることすら嫌で、エレンは零さぬよう鼻の頭に力を込める。気持ち悦いと感じたことも無いままでありながら、もう、後ろへの刺激だけであろうと有無にうまく昇り詰めることが可能になっている、エレンはひとりで更に苦しくなり、はやく楽になりたい一心により、さぼっている手で思わず自分のペニスをいじくってしまいそうになるのだけれど、子供の行動なぞ簡単に先々まで読むリヴァイに搦め捕られた。水気の張ったまま拭うことも零すことも出来ない瞳で、リヴァイを睨むように視線を向けてみせようとも、蕩けず挑むような蜂蜜色は只々ぼやけていくのみであるのだからほんとうに救えない。互いに何を考えているのかなどさっぱり理解し合えない、暗く陰鬱で湿気った虚ろな空間が殆ど隠してしまう顔も、ランプの薄灯りで反射する、無駄なばかりにきれいなだけの双眸も。
「ひぁ、兵長……っ大丈夫、とは、言いました…っけれど……、だッ、ぁ、だからって…急にっ……でかくしな、……っしないでください、っよ、ッ」
「ついさっき大丈夫と言ったのはエレン、おまえだろうが。──ほら、きついんなら手ェ寄越せ」
「ふ、…っ、う、……それは、どう、いうッ……、ぁ、あぁっ」
「俺が支えてやるから体重をこっちにかけろってことだ。ガキ。そのほうが体勢も安定する」
「ぃや……っ、ですよっ…そんなの!」
ガキだの愚図だの暴言が名詞であるかの如く半人前以下の子供扱いをしながら、子供には到底するようなものでは無い行為を、寝ていたところを叩き起こしてまで強いておいて、おまえは大丈夫なのだろう自分でそう認めたのだからといったい、どこの誰と比べているのか。いっそどこぞで孕んだ姫君にでも『兵士長殿の赤子です。責任をお取りになって。どうか観念なさいまし』と迫られて狼狽せざるを得なくなってしまえば可笑しくて嘲けられるだろうに、などと口が裂けてもどころか死んでも言えぬ、本音からすっぱりと清々しい程に真逆の台詞を飲み下せば、喉を通り終えるとなぜに発達途中の躰のなか、内側を棘のように傷付けて、ほんとうに痛くて耐え切れなくなりエレンは自らの左胸を殴るように押さえた。痛い。痛い。痛い。泣きたい程。だからこそ絶対に泣きたくない。これは公に捧げた筈の左胸、なのに心臓部に痛みが蓄積され続けているのだと、医者の息子に生まれようとも自身は医者でも聡明でも無いエレンにさえ判るのだから、心は、心はここにあるのだろうか。それでいて今は溶けている下半身のほうがずっとあつく、怒張したまま一向におさまらぬペニスが脈打ち血液を集めているせいで、痛む胸よりどくりどくりと懸命に活動している気がする。心の在処が左胸ならまだしも、よもや腰下だとしたらどうしよう見臭い淫らさが、エレンは恐ろしくて堪らない。苦しい。実に不安定だ。確乎不抜なる何かに思い切り縋りたい。縋って自身の輪郭を確認したい。だがそれでも。リヴァイの躰へと縋りしがみつき爪を立てる、などと、云う、愚かしい真似は例え自身の生き穢い命を失おうと、エレンはどうしてもしたくないのだ。なのでしない。してはならない。そう思いながら、心臓を抉るような痛みに堪えきれず、ぎゅ、と瞑っていた目を不意にあけて瞬くと、睫毛に引っ掛かっていたらしい、いやに大粒の涙がぼたりとリヴァイの上へ落下した。自身のことながら驚嘆し見下ろせば、珍しくリヴァイが驚愕をありありと乗せた表情でエレンを見返している。
「…おい、」
「っ……、ク、ぅ」
エレンを乗せたまま上半身だけを起こしたリヴァイの腕が、エレンに向かって真っ直ぐに伸びてくる。あやすようにエレンの頭を抱き込む。こんなことは交尾よりも余程されたいわけでは無い。しかし1度決壊した涙腺は意思も覚悟も心も無視して次から次へと溢れ落ちていくことをやめてもくれぬ。
「ううぅっ…、ぅっく…ひ、──くッ」
エレンは瞼に落とされるリヴァイの唇を受けながら、侵入とは言い難い捻じ込むような圧迫感を歯噛みしひた耐えるが、耐え切れない雫と共に靜か駄々を捏ねる幼子のような嗚咽を漏らす。この状態でいるのも嫌だと、何とか小刻みに息を吐いて、望まぬ震えを抑えながら、汗ばむ手のひらに気付かれないよう、自らに赤い爪痕がくっきり付く程きつく握り締めていた拳で、せめて顔を隠す。泣き声だけでも充分過ぎる恥だ、その上リヴァイ相手に泣き顔など晒したくも無い。
「よせ、エレン。手が傷付く。どうせならこうしろ。それとも今ここで巨人になるつもりか?」
「っ…なりたく、なんて……ッあ、りま、せんよっ……!」
「だったらおとなしく言うことを聞け。おい、クソガキ、こら、」
リヴァイの手は容易にエレンの拳を力任せにひらかせる。そして拒絶を赦さずに繋がれる、父とも母とも幼馴染みたちとも違う、手を。エレンは俯き右手と左手を見詰めながら幾度めになるのだろうか数えていないのでわからない、ただ己を恥じた。同じ雄でありながら何故これ程の劣等感に苛まれなければならないのか、優れたほうが劣ったほうを支配する動植物を代表する自然界におけるルールはヒトにも適用される絶対的なものであるのかと。どうしてこのような惨めな扱いを受けねばならずにそのわけは結局まったく他に存在し得ぬのであろうかと。
ゆるく繋がれた手をエレンは不敬にも振り解く。リヴァイはそれを特に咎めはしなかった。代わり、今度は何を思うのかエレンの背中へと雑なる音も立てること無く腕をまわし、今この場で離れることは赦さぬと云うように掻き抱く。抱き締める。
「落ち着け」
「っも、……ゃだ、……うっ、ぅうぅー…いやだ、っひ、ぅ」
「黙れ。黙って心音を聴いていろ」
「……そう、いう、の……っ要り、ま、…せんッ…から、っ……」
「ガセか? おかしいな。確かガキは心音で泣き止むんじゃあ無かったか」
「っもう! なに言ってん、ですか……っ、離、…して、」
離してください。15にしては幼な過ぎる嗚咽混じりのそれが今は精一杯で、余計に惨めさが増した。エレンは優しくされたいわけでは無いのだ。甘くそうっと抱き締められるくらいならば痛みに悶絶するまで蹴飛ばされるほうがずっと良い。そして思う。決してその小柄でいて筋肉質なうつくしい躰に傷をつけてはいけないと、エレンはまるで、リヴァイのどこにも触れぬままで、怯えるように震える自分の指先に言い聞かせる。エレンには知ることも出来ぬ古傷が幾つも残る、リヴァイの、その大切な躰は、調査兵団のみに限らず全人類にとっても失われるわけにはいかぬ、その躰は、こんな正体不明の化け物を抱くためになど、出来ていないのだ。だからこそ尚更に息苦しくさえなっていく。それなのにまだ。ぎこちない動きでゆるり前髪を上げられ、徐らエレンの額と鼻の先にリヴァイの唇が優しく落ちる。いつまで経っても上手く吐息を逃す呼吸を覚えようともしないので、唇にキスをしてくれないことをエレンは知っていた。この自分でも理解の及ばぬ化け物の躰も、ヒトに抱かれるためにはつくられていない。それを証明するような、どうにもならない呼吸苦に、ゆるゆると腰を突き上げられるだけで漏れいく、はしたなく地上で溺れるが如き喘ぐ、己の声をエレンは何より嫌悪する。何もかもをきちんと、余すところ無く受け入れられるように出来てさえいれば、こんなにも不条理に苦しまず済んだのだろうか。エレンには理解らない。だがこんなにも馬鹿げたことはそうそう他に無いのであろうことなら理解している。人肌に安堵するような、赦されざる行為なぞ望んだことなど1度として、無い。
「今更おまえが何に泣いてやがるのかがわからん」
「──だから、」
さっさと抜いてしまって欲しい。全部片付けてエレンは完全にひとりになりたかった。何れ程リヴァイが時間をかけようとも心を砕くように優しくしようともそこには何ら意味も無く何も生まれやしない。し、苦痛なばかりで惨めになる一方で。エレンは何も考えたくないのだ。何も考えたくないので、あまり芳しく無い頭も使わなくて良く、て、正しいも間違いも選択を迫られることは無い、だからずっと嫌ではあっても張り付く汗や肌のぬくもりは嫌いだと断じること無くこうしてきたが。もう駄目だろうと思った。最初から限界点を超えていたのだと思った。そうで無いならリヴァイの全部を、厭うてしまったのかも、知れない。
今になりなぜ泣く必要があるのかと──さっさと泣き止んで言わねえとわかんねえだろうが、と、溜め息をつきつつエレンからの抱擁を望む、正真正銘人間であることが時折疑わしい、気高きけだものにも似た男の顔が、こんな化け物の涙にすら興奮したのかその口許を歪めながら、それでいて滑稽に過ぎる程に声だけはまだこのときも、ただ優しく。優しく訊く。
どうもしていません。どんなふうに扱われたとしても、俺はただの化け物ですので。
いったい何に怯えているのであろう、易しい言葉で綴ることをいつまでも意固地になり躊躇している。それではまるでどこかの大人の猿真似だ。暗号。そうだ、暗号にしておけば望まぬ者に無闇に暴かれ解読されることも無かろうと。これは素通りへの防衛策である。それはそうかも知れないがたぶん誰も同じだろうと躓いた感情の坩堝。向かうなんて出来ない。辿り着く先を夢見ていても、エレンはあてがわれた地面を日々蹴るだけなのだ。そして翼も無く飛び上がるのである。窓ひとつ無い地下室、ここからは見えずともあれ程までに立派な太陽にも月にも理解ってはいないのだから。誰かを励ましてやろうだとか、自分を掬いあげて貰おうだとか。姿を現しては消え続ける、それだけだ。存在における一瞬の隙。その隙へ落ちてしまう。何年も赤いマフラーを手放さずにいる少女がそうしているように、常々疑いさえしなければ吸い込まれてゆける、一瞬の記憶は永遠さえ凌ぐのであった。もう疑念は要らぬくらいにならば確かだろうこの絶望は、ここで縺れているふたりを見放さない。言い訳も、泣き言も言葉にはしないエレンの、クソくだらない強がりに。は、と鼻で嗤うかのような特有の笑い方をする。エレンの柔い耳朶をまるで悪戯な子供の遊びのように甘噛んだ、逸らしていた視線を合わせリヴァイは言う。俺にだけは嘘をつくことを赦さないと容赦無く見透かして。
「ほんとうにどうもしてねえ奴は、泣かねえだろう」
そう言われてもわからないものはわからないのだ。だからエレンの左胸は、ただひたすらに苦しくて。それ以上に悔しくもあり続けて、いて。どうすることも出来ずに無言でリヴァイを見た。視線を合わせただけでうるさいと俺の目玉を嫌ったのは貴方だと抗議するつもりで見詰め合おうとそれだけで伝わるものなど有る筈も無い。嵌め込んだまま動きもしない対面座位は腹筋が痛くて、息が続かずひどく苦しいものであった。それでも執拗にリヴァイはエレンが落ち着くまで待つつもりなのか、硝子細工にでもそうするように、抱き込む以外には特に何もせずエレンの背を一定のリズムで優しくさする。だから。だから、優しさは飽和しているのであると思い知らせてやりたいが、自分がリヴァイの腰の上に乗っかって完全に体重をかけているのだと気が付けばそれはもう不可能となる。エレンの足がよれたシーツを蹴り膝で立とうとすると、見逃してもくれずに態と裏側に手を差し入れてきて出来なくする。このままで構わない。などとリヴァイはどういうつもりで云う。そのせいでエレンは耳で聞こうとも理解が及ばぬのであった。どうしても。聞こえない。これは聞こえていても聞こえたと思えるものでは無いのだ。いつもそうだ、きっと大事であろうことを、若しくはエレンがほんとうに聞かせて欲しいと願うことを、リヴァイは出し惜しみする。それとも、こういうことすらも、エレンのためにはよかれと敢えて聞かせないのだろうか。何を言われようとも今更どこにも傷など残りもしないエレンに。自他共に認める外に無い、化け物を相手に。
子供に比べ大人は長く生きている分だけどうしたって穢いが、そんなことはどうだって良かったのだ。エレンは。いっそ穢いもきれいも全部ひと夜で事足りるのであれば出し切ってしまえばよい。卑怯にも大人が子供を大人にする丑三つ時。その不透明な気紛れに誓う。1日中陽の差すことの無い地下室で、萎れて枯れる名も知らぬ白い花。この胸の痛みが、いつかの昔両親に連れて行って貰ったパレードの、合図に吹かれたラッパの響みが如し、リヴァイの心臓にも届けばよいのだ。きらいだなんてことは無かった。エレンを愛さぬそれがリヴァイであろうとも。貰ったときに教わったのでその花言葉をエレンは知っている。『純潔』『純潔』『純潔』『純潔』『純潔』。うるさい程にリフレインする愚かしさを忘却出来ずに可笑しくてならぬ。無垢な女でも無いくせに不思議と涙がまた出ようとする。花同様ヒトも散る。萎びて枯れて地へ落ちる。哀しく無意味な結末を迎えることの無きようになど、出来るわけも無い。と、知る度もう1度だけ本物では無いたくさんの光を込めて。一瞬だって無かった。うつくしい色をしていながら暗い眼差しでしか無くとも。エレンがリヴァイを好きでは無かったのだ。そんなことは一瞬さえ無かった。
ゆっくりと。エレンの背をベッドに倒し躰を預けきるしか無いように導く両腕、うつくしく獰猛な鷹の瞳が鋭利にも爛々と、獲物を射抜きにかかってくる。それに怯えるなと云うほうが無茶である。あまりにも難題に過ぎる。開かれたリヴァイの薄い唇から覗く舌と犬歯が、エレンへと向けられている。幾ら尖ってみせたところでただの1度たりともリヴァイのそれは、まだ柔いエレンの皮膚を突き破ったことも無い、整った歯が頼りないランプの薄灯りで鈍く尖り闇色に蒼白く光る。
「エレンよ」
「…は、い、」
「俺と寝るのはそんなにも厭か、泣く程に?」
答えろ。と。囁きが痛くて、いた、くて。
いっそのことそこへ飛び込んでしまえばどうなるのだろうとエレンは思った。
「……いいえ」
あァもう何もかもが全部どうでもよい。こんな正体不明の化け物の躰であろうと貴方さえそれでも傍に居てくれればもうそれで。それだけで。貴方にならば、何をされても。何をされても、ちっとも気持ち悦くなれもしないままであるのだから。
諦めるように伸ばした脆弱なる両の手を、エレンは初めて自分からリヴァイへと差し出してみせた。首にまわされ抗えもしないで両目を閉じる。あとには何も残らぬよう喰い尽くされようが削ぎ殺されてしまおうが、リヴァイによって与えられるものは全部受け止めるべきものであった。エレンは全身で縋りつくふりをする。リヴァイはまたも眉間を寄せる。縋れと命じる。その命令には従わない。自身の輪郭すら曖昧になる程に、不気味で異様な何かに構築されている躰。エレンがこの世界で最も憎悪する巨人と同じ、躰だ。
「初め…から、俺の生死も、こんな、気持ちの悪い躰の処遇も、貴方の采配ひとつでどういうふうにも──決まるんだ」
それこそエレンが泣こうが喚こうが、リヴァイの好きにすれば良いのである。リヴァイはエレンを思い切りつよく抱き締める。その瞬間エレンはたまらなさそうにくしゃりと顔を歪めた。リヴァイが膝をつきエレンの腰を持ち上げると、ぐちゅりと淫靡な腸液の音が地下室内に響き渡り、それはそれはひどい気分であった。けれどリヴァイはやめず、エレンも最早黙して自身が子供であることからも化け物であることからも今は逃れ兎に角はやく、この生産性皆無にも程がある、無益なる交尾を済ませてしまえばよいのだと。けれど抜けた分は逆向きの力を加えてやれば簡単にはいるのだろうと思い肘を立てベッドへと点で体重を掛けたエレンはまさしく理解の足りない馬鹿な子供であった。障りが有り叩き付ける抽挿の衝撃に姿勢を保つこともろくに出来ずぐらりと傾き脳が揺れた。
「馬鹿が。こっちだと何度も言ってんだろう。滑り落ちてえのかよ、てめえは」
ついぞ顕著に咎める声と共に、振り解こうがすぐ繋がれる手を、ぐん、とリヴァイが引っ張り上げるものだから、エレンの軽い躰は前のめりに、もがき宙を掻いた、剣だこも無い未熟な指の爪の先が、事故のようにリヴァイの胸元を掠めた。掠めてしまった。故意でなぞ有る筈が無い、完全なる事故。ガツ、雄同士贅肉の無い躰がぶつかり骨が軋む鈍い痛みにふたりして呻く。僅かなりに先に回復したエレンは自分が今どうなっているのか、己の状態が少しだけ気になったが消失せぬ恐ろしさが勝り瞼を上げることが出来ず、正直に云えば裸体を見るまで信じられなかった固く屈強な、逞しくも分厚い筋肉に覆われたリヴァイの躰の、丁度肩のあたりへと頑なに額をこすりつけていた。
「おい…無事か。エレン」
「ン、ぅ…ちょ、っと……把握、出来ません……」
「痛みは?」
「、有り…ます」
「動けるか?」
「…………怖い」
こんな生産性皆無にも程がある、無益なる行為。ちっとも気持ち悦くなど無い。痛くて苦しくて惨めで劣等感に苛まれて、リヴァイに優しくされる、交尾。エレンには、己が躰の、あちらこちらが痺れていることが、もしかすると気持ち悦いとはこういうことを謂うのか、若しくはそんなものはとんだお門違いでまったくそうでは無いのか、そんな瑣末さを識ることすら躊躇われており、とりあえず可動を確かめるに首を横へと振ったその喉仏に、小さく音をたてるだけのキスをしたリヴァイが、あくまで丁寧に手を這わせる。脆い宝物を大切に扱うように注意深く慎重に、慎重に気を付けながら抱きとめたエレンの肩越しに、じっと、暗くうつくしい双眸を落とす。
「い、たい。くるしい。つらい。きつい。きもち、わるい。へいちょう。いた、い」
言葉を覚えたばかりの幼児のような辿々しさで、思うことをそのままリヴァイに伝えてみれば、研ぎ澄まされたうつくしい双眸が僅か、細められ、エレンは今晩中でこの上無く悔しくなる。見られたくない、見たくない。けれども。ぽつり。冷徹であるべきリヴァイが呟くのだ。あたかも突如として何か大事なことを思い出したかのように。
「…そうだな。俺もきつい。エレン、おまえと繋がるときはいつも、いてえだけだ」
ろくでもない歯噛みを隠そうともせず、また、誤魔化しもせず。お互い様だとすら口にする。全然お互い様では無い行為であることを棚に上げるそのすぐあとで、エレンは嘗て見たことも無いリヴァイの少し困ったような含み笑いを見たのであった。
「やめちまうか。何もかも全部」
なァ、エレンよ。と、それは問い掛けでは無くリヴァイなりの提案だ。何もかも全部? ひと夜にして何ら前触れも無く、何もかもの全部ががらりと変わるということが。そんなことが。平気で起こり得る世界のなか。起こり得ぬわけが無かった世界のなか。エレンにとって唯一の指針のように不変であった気高き鷹の如き男が、ひと夜にして何ら前触れも無く、エレンの何もかもの全部を投げだそうとしている。こんなにも生産性皆無にも程がある、無益なる行為なのだから、見詰め合うことにすら後付けの理由を付けなければならぬのだから、考えずとも喜ばしいことではあるまいか。単純に頷けば良いものを、ただの化け物でしか無いこの醜悪極まりない子供の躰は、リヴァイの背にまわしている指先に僅か、ほんの少しだけ、取るに足らない程度の力を無意識に込める。勿論それでも相も変わらず理解不能な恐ろしさを払拭出来ずに、リヴァイの躰へと縋りしがみつき爪を立てる、などと、云う、愚かしい真似は例え自身の生き穢い命を失おうと、エレンはどうしてもしたくないのだ。だからしない。してはならない。けれどそれは幾らリヴァイが面白く無さそうにしようともリヴァイ自身にも云えることである。だって、そうなのだ。エレンの柔く白い皮膚にはリヴァイの歯型ひとつ残されたことが未だ1度として、無い。
「痛い、です。…だけど、繋がって、いた…い。何れ程、生産性皆無にも程がある、無益なる行為、であろう、と、も、……居たい」
あァ、いたい。いたくてたまらない。それが如何に歪つで不様なかたちであったとしても、それが如何につらくて息苦しく惨めで苦しいばかりであったとしても。ついででよい。投げやりでおざなりで乱暴でも唇に噛み付くようなキスが欲しかった。甘やかなだけの優しさならば今このときですら地下室中に飽和しているのだ。気持ちの悪い程に。それでもよい、それでは嫌だ、どちらにせよ結局のところ、やめたくない。やめて欲しいのにやめて欲しくなくて離れたくない。兵長、とエレンは縋るように呟いた。ほんとうに縋りしがみつくことはどうしてもしたくない。するわけにいかない。
「そうか」
「……はい」
「だったらもう、仕方ねえ」
「はい」
「きつかろうが痛かろうがおまえが何れ程厭おうが繋がって、居てえんなら」
「……──そうです、ね」
ひと夜ににして何ら前触れも無くがらりと何もかもの全部が変わる世界であってもまさかどこかの幸せそうな恋人たちのようにはいかない。他にはどうしようもないのである。どうしたって、いたいものはいたい。仕方の無いものは仕方が無い、そうするより他に術が無いのだ。
「なら我慢しろ、エレン。俺もそうする」
返事の代わり、エレンはこくりと小さく頷く。ふたりして躰の奥底から滲むどろついた感情を廃棄して深い、息を吐く。こういう妙な優しさはおそらくずっと不快であろうが。矛盾しては我儘な忌むべき巨人と成る化け物の、少年兵の皮をかぶった憎悪で構成されている、躰。兵士にしては薄い肩と、頼りない腕と、胸筋の発達が著しく悪い胸板に、リヴァイはねぶるようなキスをする。エレンがそうされたく無い程の、しなくてよい程の優しさで繰り返し。ならばもう精々勝手に優しくしていれば良いのである。そうされたいとエレンから望んだものでは無い。きっとそう遠くないであろう未来をリヴァイは何らかの選択の元、執行するのであろう。この化け物の薄い肉と夢の消滅は、決して避けられぬものだろう。傷付けても傷付け無くても──死んでも、死ななくてもだ。こうして抱き合った記憶さえ嘘のようにエレンもリヴァイも。薄灯りを灯す古ぼけたランプのなかで短くなっていく、火が揺らめく蝋燭のように消えてしまうのだ。うつくしくは無い。哀しくも無い。それは只々あくびが出る程に当たり前のことなのであった。エレンは姑息なふうに窺い見て、リヴァイの裸体を観察する。兵士であれば羨まずにはいられぬ大層な躰の、その浮き出た鎖骨の上あたりに真っ直ぐと、若干赤らんでいる引っ掻き傷がスゥ、と1本エレンの双眸に焼き付くように映る。完全なる事故。しかし他の誰でもないエレンが、つけた。掠めてしまった爪の先がつけたもの。傷とも呼べぬ傷はきっと巨人の治癒力なぞ持たないリヴァイでも明日には消えているであろう、その程度の。けれども自己嫌悪で見ていられずに眼を俯ける。それに気付きながら、否、気付いたからこそリヴァイは嗤った。は、と特有の笑い方でエレンを追い詰めるのだ。
「見たか。おまえが付けた」
「すみ、ません」
「触ってみろ」
「……出来ませんよ…意地の悪いことを、言わないで、ください」
「こんなもん傷でも何でもねえだろうが」
「でも、」
でも、だけれど、貴方は違う。
「それ程気に病むくらいなら舐めろ」
「まさかそれ…本気で言ってます?」
「さてな。俺はどうもなっちゃいねえよ。寧ろおまえの孔のほうが余程赤く腫れて痛そうだが? ほら、ここだ」
「へっ、アッ……うあ、っ…ク、ゥウ…、んんぅっ」
「──……」
ペニスが挿入ったまままさぐったリヴァイの指にエレン自身今までに発したことの無い、不格好な喘ぎでは無いもっとずっと甘ったるい高めの声が飛びでて、ふたりして瞬間的に時間という概念を失い忘れた。いや黙られてしまうと居た堪れないです何か言ってくださいやっぱり黙って無視してください、と、思わずにいられないのに言葉に出来ぬ、正直に頬だけが血を昇らせ真っ赤に火照る。視線がうるさいとはもう言われていないが合わせられる筈が無く、エレンは意地でも俯けた顔をリヴァイの視界から逸らし続けた。
「…おい、エレン」
「……………………はい」
「今のは何だったんだ」
「……理解りません」
「態とか?」
「あの。やっぱ兵長の仰った通りやめましょう。何もかも全部」
「仔犬が甘えたみてえなイイ声がしたんだが」
「…お、俺じゃあ無いです気のせいですこっち見ないでください俺も見ませんから」
「うっかり愛してやりたくなるような、いじらしく健気な感じの──」
「それ以上口になさるなら、舌、噛み切りますよ」
「巨人化してえのか」
「うぅ…」
狡い。いつもと違う上目遣いの景色と、合図のような、暗号のような、隠されていたものが如実に噴き出す。しとどに濡れたペニスをリヴァイの手が掴み、躰中、届くところは隈なく舐め上げるキスに揺さぶられ掻きまわされていくエレンは、その歪つにしか繋がれない容れ物が嘘のようにどんどん溶けだし素直な液体になってゆく錯覚を覚えて悶えた。リヴァイのかたちに添ってリヴァイの体温に染まり、血迷うように、ただ与えられるものを享受するばかりでは無く何か、何だって構わないので何かを少しでもリヴァイのその尊い肉体に蕩けて入り込めはしないかと何度も何度も押し殺した、切なく痛む心と激しく暴れている動悸と、果ては化け物たる醜さすらも移せたならばと願う。そんなことは赦されないとリヴァイより誰よりも、エレン自身が寛恕し難いことであった。
「っふ…あっぁっ、……うぁ、っあ、ン……っく、へいちょ、うっ…兵長……ッ」
追い上げられて絶え絶えの呼吸でエレンはリヴァイを呼んでいた。
「悦いか」
「わか…っりません……、ク、ぁ、あぁっ」
「俺もだ」
抽挿を止めずエレンへと降り注いでいたキスがやむ。ただでさえ世辞にもよくは無い目付きで、その瞳を細めるだけでリヴァイは呼び返してもくれない、残酷な程の優しさは腹立たしさと諦めを揺るぎ無き事実にして、ひどくて、狡猾で、化物である躰さえ蕩けさせる圧倒的なつよさでもってしてリヴァイはエレンを、捩じ伏せる。
「んんぅ……っ、は、…ア、っ……あ、あ、ぁあ……っふ、…うっく…ゥ、んっぁ、ああっ…!」
「おい、聞こえるか」
「はっァ…、ン…──っは、い、聞いて…ます……っ、ひぁっあ、ぁうっうぅ……ッつ!」
残念なことにエレンの耳は聞きたくもないぐちょぐちょと鳴る腸液の音も、扱かれ苦しいペニスが零すみっともない音も、女のように上がる己の声も乱れきった呼吸音も、リヴァイと肌がぶつかり合う途方に暮れたい程の音も、すべて拾い上げているのである。気が狂いそうだった。
「聞こえているならそのまま聞け。なァ、おい、おまえは。おまえは誰が傍に居ようがたった独りだろう。たかが意味が無いくらいで、たかが価値が無いくらいで、怖いだのと簡単に言うんじゃねえよ。人間はみな幾らおまえを好いてみようとも警戒心を緩和していこうとも、おまえが化け物であることを畏怖している」
「んう…も、いく……っひ、ぁ」
「……クソガキてめえ、聞いてねえだろ。早漏が。俺が達くまで耐えてみろよ、何なら徹夜で付き合わせてやる」
「っそ…!?」
遠慮の無い舌打ちが懐かしく正しい。優しさならば要らないのだ。エレンは吐精を終えた躰が身震いするのを自らの両腕で抱き締める。リヴァイからの抱擁なぞ欲しくも無い。荒い吐息を整えながら浸る。エレンはリヴァイの云う通り、独りであった。誰でもよいのだ。誰かが笑って幸せそうであるのならば。生産性皆無にも程がある、無益なる夜はやがて過ぎていく。おそらく星は輝きながら愛されながら夜空へと零れ落ちるが、それを今知ることはエレンには赦されていないのだ。振り払おうとも繋がれた手は当然の顔をしてリヴァイより小さかった。それは手だけに限らずに。自身で思っていたより随分と頼りなかった指の僅かな隙間からさらさら、さらさら零れて消えた。それは白いシーツの狭間で揺れる不愉快な程甘く、寝酒代わりにしては優しいだけ、ただ、優しいだけであったのだ。俯いて視線を外すことを余儀なくされていた時間はエレンにとって、黙々とリヴァイを否定する時間でもあったけれど、かと思えば、抱き締めたいものを抱き締めたいだけ抱き締める時間に成り下がり上官で無ければぶん殴ってやりたいと思っていた。どの時間も同等だと望んだ分だけそこにあった、のは、リヴァイの思惑でしか無い。エレンは初めから気付いていた。この世界はヒトがどう望んだかということの、単純な結末でしか無いのだと。だから誰でもよいのだ。誰かが笑って幸せそうであるならば、喜んで。繋いでいる鎖をある日突然木っ端微塵に、飛び立つばかりに欣懐として、破壊してやることも有るのであろう。
「ひくっう、おれ、いまっ…いったばっ、か……で、……ア、ぁあっ」
「言っただろ。俺が満足するまで付き合えと」
「く、うぅっ……もう、っ……ァ、ま、たっ……」
朝方まで続けられるのであろうリヴァイ曰くの交尾、は、寝酒代わりどころか、ひどくリヴァイの目を覚醒させ、その間にもエレンは幾度射精したのかも数えていないのでわからない。朝日が昇ろうとも明けぬ夜が在るということを、おかしい、己はただの化物であるのにその筈であるのに、忌まわしい躰には、リヴァイの呆れや怒りを孕んだ気持ち悪さを性欲に変換した熱を、刻まれいくのである。傷にはならぬ。エレンは厭い、リヴァイは厭うた。深く不覚ふかく不快に正常でいられるわけも無い、けだものの目をしたふたりが妨げ合っては散らかして、これではどうにも片付けられそうに無い、そんなところまで、だ。
「根拠も無い感覚での、同意と共感なんて…気持ち悪くありませんか。貴方も、俺も」
それでいて尚、憐れな程の青臭さと否定は、切っても切れない関係性を断じて崩しはしない。その結果やがて迎えるしかない朝に、破かれること無き互いを隔てる膜が、収縮する瞳孔と感受性を道連れにし、在りもしない崇高を維持していくのだ。濡れた箇所は何処もかしこも血に濡れた一矢に似る光が、宿っているかの如く昨日までとは明らかに違う何かが重ねた皮膚の下を流れて。可能性はいつもあやふやでしか無く、紡ぐ言葉の構成は贔屓目に見ようとも骨と皮ばかりだ。未だ老いを知ることの無い子供の躰は匿われることを拒絶しながら、それでも兵士として長く血を浴びてきたリヴァイのその手首の内側がいつも、己に向けて無防備にさらされていたのだということを、知りたくも無い、エレンは知らせられざるを得なくなったのであった。
ひと夜にして、何ら前触れも、無く。