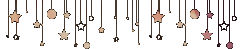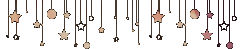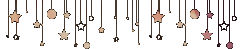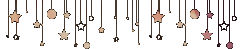じんわりと濡れたような生ぬるい空気が、衣服から出ている肌にまとわりついた。それはすぐにひとの体温と同じくらいに感じて、少しだけ暑くも感じた。
お腹に掛かっているタオルケットの辺りだけがとても暑くて、首筋にじわりと汗が滲んだ。続くようにして額からじわり。それらにいい加減寝辛くなって、ルームメートを起こさないようにベッドから抜け出して夜の世界に出ると冷房機器のない部屋の中よりかは涼しかった。
涼しさを求めて少し離れたベンチまで歩き腰掛けると金属の冷たさが裏腿から伝わってきた。それに恍惚とした気分になり、ほうと息を吐く。
「こんな遅くに危ないですよ。」
不意に掛けられた声に振り向けば、スウェット姿の雪男が立っていた。
「今晩は、奥村せんせい。」
「今晩は、名字さん。」
私と雪男は付き合っている。お互いの彼氏彼女という立場だ。ちょっとからかうつもりで奥村先生と呼ぶと、気に障ったのか同じようにして私のことを呼んだ。気を悪くするのは仕様がない。だって塾以外では名前で呼び合うと決めごとをしているから。
「雪男ってばそんなあからさまに機嫌悪くしないでよ。」
「名前がふざけるからだろう?」
すとん、と雪男が私の隣に腰かけた。背もたれにぐったりと背中を預けて目頭を押さえる様子は、あまりに不似合いな高校生だというのに何故だか様になっていた。
「多感な時期とはいえ、そんなに悩むことは無いのだよ、少年。」
またからかって言うと、少し睨まれた。謝りながら雪男の頭を撫でると「子ども扱いされている気がする‥」とぼやいていたけど、子供のような扱いが嫌なだけで撫でられることは嫌じゃないようだったからそのままにした。
街路灯の明かりが音をたてながら点いたり消えたりしだした。時計がないので時刻を確認することは出来ないが、涼みに来てから一時間は経っただろう。撫で終えた手はベンチの上に落ちていて、ベンチの金属は私とその手と雪男の体温でお世辞にも冷たいとは言えなかった。
じわり。
雪男がベンチの上の私の手に自分の手を重ねた。熱が手の甲を伝って神経を刺激して脳に知覚させる。「ねえ、」私の掛け声に雪男は少しだけこちらを向いた。
「大丈夫だよ。」
賢い雪男が何にそこまで悩んでるのかなんて分からない。学校でのこと、塾のこと、神父様のこと、燐のこと。雪男がどのことにどれだけ悩んでるかなんて、私には分からない。でも、言えるよ。雪男は大丈夫。君が思ってるほど世界は悪く進めないよ。もしそうなっても、修正されるから、雪男は大丈夫だよ。
「帰ろうか。」
立ち上がった雪男は重ねられた手を握って私を引いた。涼みに来たのに全然涼まなかったなあ。まとわりつく空気と雪男の手がじんわりと私を包んだ。
きみのせいだよ
20110807
|