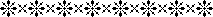 けんじゃととりのはなし たった一目でも良いから、と思う。 けれど会えたら、きっとあともう一度言葉を交わしたい、と願うだろう。 そして、言葉を交わせればその時間をもっと長くと求めるに違いない。 一つ叶えば、また一つ。 初めて切望した相手なら尚更に、きっとこれから流れていく時間をその人と共に過ごせないかと、共に在ることは出来ないのかと、どこまでも貪欲に想いは肥大していく。 彼に会う前だって、それなりに生きていた。 しかし、知ってしまったのだ。 ほんの一時、あのコドモとの邂逅と比べればそれまでの生活とは、眼を開けばまだ生きていたから続けていたとも言える時間であり、もう彼に会えないのだと思ったら、これからまた繰り返される生が、ただ無為に流れていく時間に過ぎないのではないのかと。 人ではない能力(チカラ)を見ても、驚いた後は飛べるって便利だなと笑い顔。 人ではない身になると知っても平気な顔。それどころか姿が変るなら俺と同じだな、とまた笑う。 『またな』 たった一言に、我が身に掛かった呪縛よりも深く捕らわれたと知った。 それは再びヒトとして眼を開いた先に、かのヒトの姿が見えず…もう会えないのか、と思った瞬間。胸に空いた大きな虚無感と―寂しさを全身が感じた瞬間のことだった。 ◆ ◆ ◆ 「よく考えたら、名前をお伺いしていなかったんですよねぇ」 窓枠に足を掛け、その真下に座り込んでいるコドモを避けて中に飛び込む。 そして、対面を果たした。 「…どうしました?」 「オメー…」 なんでいるんだ、と彼の眼は聞いていたので。 「また、と言ったじゃないですか」 笑って告げた。 ◆ ◆ ◆ 思わぬ相手の出現に、新一は呆然と白い姿を見上げた。 たった一晩、一緒に語り合って過ごした相手。 己を奇術師と言っていた。 人の身のくせに空を飛ぶ非常識な人間かと思えば、朝日を浴びて鳥に変化した非常識極まりない…鳥?いやはや人間? 「何で、きた」 「また、会いたくて。鳥らしく空を駆けて参った次第です」 胸元に手を宛て、帽子を脱いで一礼する。 白い手袋。その手に白いシルクハット。片目にはモノクル。以前には見なかった飾りが下がっている。纏うのは白のタキシード。靴もまた光沢ある白が月光にそっと光る。肩から降りるマントは静かに彼の背中を覆う。 「お名前を、賢者殿」 そっと膝を落とし視線の高さを合わせて、懇願めいた眼で相手は名前を強請った。 「新一」 「しんいち、…新一」 「オメーは?」 「キッド」 「…キッド」 呼び合う。 ただそれだけの事を、まるで奇跡が叶ったと、一瞬眼を閉じそれから緩んだ目元で優しく嬉しそうに笑う、白いひと。 とくり と鳴る音。胸の奥。 記憶をくすぐる、懐かしいような、ずっと会いたかったような。 嬉しいのに、泣きたいような。 全く彼は新一にとって不可思議な相手だった。 この男―キッドに抱えられ飛んだ夜。 あの鮮烈な飛行体験。 語らい続けた夜の時間。 知らない国の知らない世界の知らない話を、奇知な彼の思考を持って機知に富んだ話の中に稚気も紛れ込ませて。 とても楽しい夜だった。 久しぶりに新一の好奇心や興味を満たした相手。 新一の親友が阿呆な事を言い出す前は、よく一晩中答えなんて端から無い議論のような言い合いをしていた頃の、懐かしい感覚まであった。 だから、ずっと思い出さないように―あれはただの夢だったのだと言い聞かせていた。 彼に助けられる前まで、新一は焦っていた。 早く、早く、元の姿に戻らなければと。 けれど、その為にまた友人に会うのは億劫で。―苦しくて。 鬱屈した思いで、長年の友人である護衛でさえ鬱陶しいと、真っ暗な森の中を歩いていたのだ。あれは、そう…友人が―求婚者が旅先にまで送ってくる手紙を受け取った後のこと。 ―彼に出会った。 ―そして、初めて空を駆けた。 地表を離れ身体が浮いたとき。 森を見下ろしたとき。 夜が溶け空と森の境界が曖昧になっている果てない地平を見て、その広さを感じたとき。 大事な友人から逃げを打つような卑小さが、情けなくて。 ちっぽけな自身の存在に泣きたくなった。 ◆ ◆ ◆ 夜の帳は、地平の端が明るくなることで急激に上がっていく。 密やかに暗闇の中で行われたコドモと男との対話の終わりの時間。 朝日の照射。 眩しいな、と眼を細める。 視界の脇、隣に立って同じく眼を細め空を見る男は、「それでは、また」と呟いた。 肯き返して、新一も身体の変異に眼を閉じた。 「…ちっちゃい?」 再び眼を開いて、すぐ目の前に飛んできた白い小鳥に新一は目を丸くした。 以前確認した鳥の姿はそりゃもう大きかったはずだ。 新一を乗せて飛べるくらい。 友人が問答無用で矢を射掛けるくらい。 まさに怪鳥というべき姿だったのに、今新一の目の前にいるのは小鳥。 ―まさか、消えた? ―コイツは別の鳥? などと一瞬思ったが、忙しなく鼻先で羽をばたつかせて何やらアピールしてくる姿に、そっと手を差し出せば、すんなりと羽を降ろして来た。 「…これが、森で会ったっていう魔女の魔法か?」 夜の間、鳥の旅の話を聞いていた。 その中で彼が語った魔女の話。意識の無い昼間の不安さを緩和してくれたという。 随分親切なお嬢さんに会えたものだと、我が身にトンデモ状態を齎したアノ魔法使いとは大違いだなと思って聞いた旅の一節。 「キッド?」 名を呼べば、ピピピと可愛い囀りが返って来た。なるほど、本人―本鳥か。 「面白いなー、オメー」 とりあえず頭の上に乗せて、子供の姿では大きくダブダブだったローブ状の服の腰紐の位置を変えて締めなおし、伸びた黒髪を首の近くで革紐を使って一つにくくる。作業用の机に置いておいたショールで頭ごと顔を覆うように巻こうとすると、小鳥は肩に降りてショールの結び目に足を掛けた。 綺麗な白。可愛らしい姿。新一は無意識に眼を細めていた。 「…外に出ようか」 餌は何だろう?普通の鳥餌といえば、穀物か虫か。完全に鳥になっている姿だし、まぁ本能に従って食べられるものを食べてくれるだろう。 新一はすっかり引き篭もり場所になっていた塔から外に出た。 お城には入らずに、外周を歩いて、それとなく道案内のような国の紹介のような言葉を肩に乗った小鳥だけに聞こえるように囁きかける。確かに完全な野生に支配された鳥の状態ではないらしく、白い小鳥はひどく大人しく肩に留まったまま、新一の言葉に時折言葉を返すかのように小さく鳴いた。 「…あ」 そして、城門を出る前に―その門の柱に背を預けて立っている人物に気がついた。 「くど…姫やないか!」 「服部。何か用か?誰か呼び出しでもしてるのかよ」 大声で呼びかける単語を慌てて誤魔化したのは門番の眼を気にしたからか。最近になって不意に姿を見せるようになった賢者を称する女性(化した工藤)は、『隠されし賢なる姫』などと正体を知らぬ者から噂されていた。 賢者の遠い親戚だの、王がどこぞから見つけてきた他国の姫だのと。 「いや。待ってたんはお前や、工藤。昨日、…海の賢者からの手紙持ってきたんは俺や。…だから、気になってな」 なるほど、と新一は思った。 いつもながら気の優しい男だ。 「大したことは、…あったけどな。まぁ、オメーが気にすることじゃねーよ」 「ホンマか?…んん?あー!」 「ん、だよ」 「こんなトコにおったんかい!この鳥―」 服部は言い様に新一の肩に居る鳥に手を伸ばした。 パタ パタパタ… … 小鳥は軽く身体を浮かせてその手から逃れ飛んだ。服部は何度も何度も両手でその小さな飛行物体を捕えようと手を振ったが、ひらりひらりとかわされ―終いに新一の頭上に納まる小鳥の姿に、思わず拳を握る。 「何や、馬鹿にされてるみたいやねんけど」 「ハハハ、気のせいだろ。コイツがどうしたんだ?」 「ソイツ、和葉の鳥や」 「え?そう…なのか?」 視野外にいる存在に確認をしようと首を後ろに逸らすと、意を察したらしい小鳥が肩先に降りてきた。ピピ・・・と鳴きながら明らかに首を横に振っている。違う、と言いたいのだと新一には伝わってきたが、服部には鳥の意思表示などとは受け取れない。 「港で和葉が拾ったんや。飼ういうて、途中まで一緒にコッチに向かって来てんけど、夜の間に姿が見えなくなったんや」 「へぇ」 夜に姿を消した―という話に、思わず深く肯く新一である。 肝の据わったあの彼女だって、突然可愛らしい小鳥が消えて、代わりとばかりに真っ白な不審な男が出現したら大騒ぎすることだろう。 「じゃ、野良鳥なんだから、別に和葉さんのじゃねーだろ」 「でもなぁ…アイツえっらいガッカリしてたし…」 何だかんだと妹分以上の想いのある相手の様子を頭に浮かべたのか、服部がチラチラと視線を投げる。 「…とりあえず、見つかったって見せに行こうか」 そして、その場で小鳥の姿―新一に懐く様子―を見せるのが、穏当な妥協案だろうと新一が提案すると、ほんじゃ久しぶりにアイツんちでメシご馳走になろうや!と服部がニカっと笑った。 ◆ ◆ ◆ ―これは予想外 小さき身に宿る意識は人のソレ。ようやく出会えた人ともう離れるまいと、グッと足先に力を込めるよう念じれば筋肉が動いたのが伝わってくる。鳥の本能の邪魔にならない程度に、意識は殆どが鳥の視界の中でだけで働くような感覚。強く強く意思を肉体に伝達させて、ようやく意思通りに動かす事が出来るのだ。大分慣れてコントロールが効くようになった。 とはいえ、空腹時に虫に向かって嘴を突き出すことや、排泄に羽休めなどの本能的欲求には抗えないのが常態ではあるのだが。 ―この人は…友人、ですかね 港で目をつけた商人の娘の近くに居た男だった。最初の夜に小鳥を囲っていた籠から逃げはしたが、ずっと荷車の上や隅に潜んで―なんだかんだで、『城に行ってくるわ』というこの男の案内があったからこそ、キッドは昨夜のうちに新一の下へたどり着けたのだ。 あのコドモは王の近くにいるらしい人間だったし、魔女との約束の事もあったから、まず城に潜入した。 そこで、耳に入った会話はまさに導き。 『アイツ…賢者さんはどしてん?』 『いつものように、塔に篭ってるよ。いい加減、式の衣装合わせもしたいのに』 ―・・国の、王から求婚されている賢者。キッドが知るかの人に符合した相手が近くにいる、と確信したのだ。 飛び慣れぬ建物の周りを、用心深く、物陰に隠れながら見回りの兵士の死角を縫って、探して、探して、一際高い塔の窓の向こうにチラリと見えた跳ねた髪が特徴的な小さな頭。 我が身を振り仰いだ青い瞳はかつて見蕩れたモノと同じで、けれどあの時よりも、もっと深く夜闇を溶かした沈んだ色だった。 ようやくに呼ぶ名を与え合った後―『新一は、何を悩んでいるのです?』首をかしげて、問うてみたのだ。 この賢き君が膝を抱えるとは、きっと大問題に違いない。 「…大事な友達は、伴侶になれるもんかどうか」 「友達同士で結婚ですか。古今東西よく聞く話で」 「しかも、野郎が元は野郎の友達で。相手が愛人作る前提で」 「…それは、また。なかなかヘヴィーな」 何がどうして、そんな事態に。 気の良い友人だった男が王となり、変異する賢者を伴侶に望んでいる、という事しか知らなかったが、愛人? キッドは新一の隣に座る。 正面から覗き込むよりも話しやすい位置を取った。 窓を背にして二人で床に座り込んでポツポツと言葉を交わす。 「例の王様ですか?」 「そう」 「愛人というのは?」 「んー。別に王族が血筋保護の為に正妃の他に女作るってだけなんだけどな」 「…新一は、」 「産めないからな」 キッドは納得のいかない思いでジッと新一の横顔を見た。―おそらくキッドよりも納得していない顔がそこにはあった。 「では、産めさえすれば、構わない?」 「…どうにもならないなら。でも、アイツは友達なんだ」 ポツリと、淋しげな響きで。 「ずっと、友達だったのに」 「…ずっと。それは新一だけ?」 「みてー。ずっと我慢してたんだって、アイツは」 「新一が気になるのは、友達だから?」 「結婚とかする対象に考えた事がないってのが一番だけど。大体自分の身体が女になるとか在り得ない事態になったこともそうだし、そしたら、アイツがあんな事言うとか、全然考えた事なかったし」 一応、お前に会うまではさ、とにかく元に戻れば何とかなるって思ってたんだ…と諦め気味に紡がれる言葉に、キッドは思考をめぐらせる。 おそらく、王にとって、新一は。 「…男の、元の姿に戻っても、問題は変らないのでは、それは」 「…かもな」 「せいぜい、新一が女性の姿になったことなど切っ掛けに過ぎないのでしょう。ずっと、抑えていただけなのだから」 「……」 「ずっと抑えていて欲しかった?」 「…アイツが、辛いのとか我慢すんのは嫌だ」 「―優しいのですね、新一は」 「どこが」 吐き捨てるような強い口調。 ―逃げ道を探して、賢者なんてお飾りの頭くっつけて、何も出来ないでいる。 言葉よりも雄弁に、悔しげに唇をかみ締める姿が、―湧き上がる自身への怒りか、それともどうにも出来ない己のものではない友の心を思ってか―何かを堪えるような険しい眼が、新一の心情を示していた。 せっかく会えたのだから、笑ってはくれないか、とキッドは思う。 コドモには似合わない険しい顔。彼を笑顔にさせる術を探す。 この子は、この子の知らぬ世界の話を聞くのが大層好きそうだった。 「悩むのも賢者の仕事でしょう。いざとなったら、私が貴方を攫って飛んでいきます」 だから、今夜の悩みはそれでお終いに。 賢者は一瞬呆けた顔をして、それもそうか、と肯いた。 「では…今夜は旅のお話をしましょうか」 「…お前の?」 「もちろん」 夜の静寂に紛れて密やかに。 重なる会話が、隔たれていた時間を埋めていく。 変化するようになって以降、キッドが己の状態をコレはおかしいといくら言葉を重ねて訴えかけても、想像の外にある変身者と普通の人々との間では、時間をかけて話し合ったとしても隔たりは大きくなるばかりだったのに。 いつしか誰に語ることもやめて森に移り住んで、人との関りを諦め、人と言えぬ姿に身を落とす我が身に、自身ですら諦めていた。 それなのに、やはりこのコドモといると、楽しくて仕方ない。 「目が覚めたら夜じゃあ、ちゃんと行きたい場所になんか飛べなかったんじゃないのか」 「ちゃんとココに来たでしょう」 「地理に詳しいのか、オメー」 「さほどは」 あおい魔女に会うまでの旅路は楽でも楽しくも無かった。 思いながら、不思議な出会いを話せば、そのコ知ってるかも、と驚いた顔と返事。 彼女はお元気そうでしたよ、と告げれば嬉しそうに微笑んだ。 月が中空を過ぎた頃に、いつしかコックリコックリと隣で小さな頭が船を漕ぎ出した。 反対側に倒れないように、そぅっと身体を引き寄せて。 覗き込んだ顔は無防備な、まさしくコドモのものだった。 しばらく見つめているとうにゃむにゃと口元が動く。 「バー…ロ」 「さて?それはどなたの事なのでしょうね…」 寝てしまう前の会話。 そういえば、と。 最初に見たコドモが呟いていた文句の行き先が気になって聞いてみた。 「新一…どなたを馬鹿モノと?」 「…そうだな。俺の目の前にフラフラ飛んできた奴とかかな」 皮肉げにくいっと口元を引き上げて笑って言う賢き者の言い掛かりのような言い分に、キッドは軽く肩を竦めて見せた。 「何故?」 「俺は元に戻りてーんだぞ?オメーが必要だって言っただろ」 「ふむ。そんなこともありましたね」 「飛んで火にいる…とか考えるかもしれねーってのに」 「貴方に要る、と言われるなら嬉しいですよ。命ですか?それとも生き血が必要で?どうせなら提供しても生きていられる方が良いですが」 本心だったのでそう言って笑うと、コドモの身をした賢き者は、一瞬ぽかんとした顔をした。 すぐに、お人好しな事いうんじゃねぇ!と眉を吊り上げて怒ってこられて、今度はキッドが戸惑ってしまう。 会いたい、という願いのまま飛んで。 会って、―願いは叶って。 もっと話したいと思いはするが、それ以上、己でも言い表せない高鳴るばかりの言い様のない想いだの己の存在自体なんてものを、このコドモに背負わせる気など無かったから。ただ、ただ、また会えて、言葉を交わせる現状だけが、己の全てのような気持ちだった。 もとより死はキッドにとってごく身近にある奈落であり、人としての意識が散る瞬間、いつも落ちて消え行く感覚は―繰り返されるその死への誘いは―死への恐怖を鈍磨させるには十分すぎたのだ。 「怒らないで下さい…」 「おまえ、なぁ。…ああ、もう解ったから!」 しょんぼりと反省をして見せれば、膨れながらも許してくれる。 怒ったままの顔―膨れる頬がまさにコドモのモノで面白い。 キッドが指先でその膨らみをつつくと、ふっと口元から息が零れた。 ◆ ◆ ◆ 「あー!そのコどこで捕まえたん?!」 小鳥を肩に乗せたまま、服部の隣家で装飾雑貨と衣装屋を営んでいる遠山家に立ち寄ると、看板娘である遠山和葉が店先に飛んできて、小鳥を指差し叫んだ。 「捕まえた…というか、懐かれた?んだけどな」 「アタシかて、懐かれたんよー!」 むぅぅうと服部の隣に立つ新一を睨むポニーテール姿の少女は、新一が想像していたよりも、大分腹を立てているようだった。そんなに気に入っていたのだろうか。しかし、彼女は小鳥に無理に手を伸ばすわけでもなく、ジッと新一を睨んでくるばかり。 聡い賢者はその顔に嫉妬を見つけて、慌てて顔を半分ほど覆っていたショールを上げた。 ぱちくり、と少女は眼を見開いて、それから顔を赤くして慌てだした。 「あ。どこの別嬪さんかと思ったら工藤くんやったの!」 「何や、わからんかったんかい」 「だって、顔が見えんと雰囲気とか全然解らんやん。なのに、よう見えんでも美人さんなの丸解りやし」 「そうか…?」 「そこは同意や和葉。そんで自覚ないのもいい加減にせぇ、工藤」 トンデモ変身をした賢者について知るのは、お城の中の一部の者と昔馴染みくらいである。しかし、事情を知っていても、現在の工藤の姿は以前の少年とは印象からして全く異なっているから、見る者にとっては中々どうして、同一人物とは思えないのだ。 「あまり、この姿では出歩かないからな」 「ちゃうわ…」「工藤くん…」 昔から我が身ごとに鈍い友人の姿に、この国で最も賢いってどの辺が?と溜息を洩らさずにはいられない二人だった。 小鳥が新一から離れようとしないのを見た和葉は、今度は割りとアッサリと「だったら、工藤くんが飼ってかまへんよ。でも代わりにウチで世話用品買うてってな!」と言って笑った。 服部がいつもの気安さで朝食を強請ると、残りモンの処分ならさせたるわ!と言って―しかしそれなりに手の込んだ料理で持て成してくれたのだった。 仕入れの算盤弾きの武勇伝を交えながら、港の様子などを聞いて。一通り食べ、食後のお茶を戴いていると、そういえば、と和葉がおずおずといった調子で新一に問いかけた。 「結婚するってホンマなん?」 飲みかけていたお茶を辛うじて噴き出さずに飲み下したものの、新一はゴホゴホと咳き込んだ。 テーブルに降りて穀類を啄ばんでいた白い小鳥が心配げに、新一の周りを飛ぶ。 新一は咳き込んだまま、どうこの話題を流すか―誤魔化そうか考えようとしたが、続く言葉に更に呼吸がおかしくなりそうな事態に陥る羽目になった。 「実は…今回の仕入れに、めっちゃ上等な、真っ白の絹の布地が入っててん…」 神妙な語り口。 「あんまりに高級品やから、ちらっとしか見せてもらえんかったけど、あんな生地で作る衣装はもう、花嫁さんの、しかもごっつ上等な身分の花嫁さんしかおらんって!」 口調は段々と熱を帯びたものに変化していく。 「で、こっそり依頼主見たら、王室からになってたんよ?!これって、つまり―」 興奮に頬を染めた和葉は、懸命に下を向いて口元を押さえて、ついでに他にも色々抑えていそうな新一をジッと見た。 新一は何とかしてくれと、向かい側に座る服部をチラリと見たが、昔馴染みの友人はその視線を全力で避けてお茶を啜り捲くっている。 ―こんにゃろうッ! 「あー…、さーな。その辺は、俺は聞いてねーなー…」 「ええー?!そうなん?採寸とかされてへんの?」 「した覚えはねぇ。大体なんで、俺が」 「だって、婚礼の儀式が近いってもっぱらの噂やし。あの子が花嫁にしたいのは『隠された賢なる姫君』って言われてるし。それって工藤くんのことやろー」 単純にして明快なる三段論法? 昔から王子が賢者の子を好いていたのは、誰の眼にも明らかで。 詳しい事情は知らなくても、想像はつく、という少女の語り口は実に淡々としていた。今更何を、といった風情だ。 その言い分に、逆に工藤がショックを受け、ずぅうんと沈むの見て、流石に服部が口を挟んだ。 「何や、アイツならわざわざ計らんとも、工藤のサイズくらい見切りそうな気ィもするけどな」 何ひとつフォローになっていない。 だが、工藤は手で空になった湯呑をいじりながら肯いた。 「あー…そういうの得意だったな、アイツ」 女子の身体に興味を持ち始めの頃、何だかそんなサイズ当て的な事をして騒いでいた記憶があった。 特技なのか目が良いのか、三人でそんな遊びをした時は、あののほほんとした顔の王子がキリッと目元ついでに口元を引き締めて、精度の高い目算値を弾き出していた。(ただしその対象は、コドモの興味本位を受け入れてくれる年配の女性のモノが殆どだったが) 「アカンて!花嫁衣裳はそんな適当な採寸では作られへんよ」 身体に沿ったラインをどれだけ美しく見せられるかが、この国での正装の勝負になるんやから!と主張する少女に、一体何の勝負なのかと男と女(中身男)は首を捻った。 とりあえず分かることは、快斗による新一を花嫁にしてやろう計画は着々と進んでいることくらいだ。 新一は深く深く、溜息を吐く。 ピピピ…ピ、と囀りにも、新一は苦笑を浮かべるだけ。 白い小鳥はその様子をジッと見ていた。 それから和葉の家を辞した新一は、鳥を連れたまま数日ぶりに自宅へ戻る。 昼には適当なご飯を拵えて。 作った一部を小鳥に与えようとしたが、懸命に首を横に振るので食べさせるのを諦める一幕があったりしたが(炒めたご飯ではいけないらしい。色的には黒米に近かったのに)、昼過ぎからは、半端な睡眠しか取らなかった夜の分の睡眠を補おうと小鳥と共にベッドに入った。 どうせ、また夜になれば夜更かしをしてしまうことになると新一も―小鳥も思った。 ―・・・トントン、トン 「…誰だ?」 遠くから聞こえるノックの音。 新一が重たい目蓋を上げれば窓から差し込む光はすでに茜色に近く、ボンヤリと辺りを見回して―そういえば自宅だったな、と欠伸を一つ。 「はいはい、よーっと」 枕元のタオルを丸めただけの簡易な巣で、いまだ眠る小鳥に少し目を緩めて、ベッドから降りた。 再び出会った、とりとけんじゃのはなし  ×
|