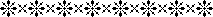 とりのはなし・幕間 眼下に広がる深い森。 深緑は幾重にも重なり、草花や森に棲むモノモノを濃い影の中に隠している。 影は目的地に進むほど、更に更に濃く…強くなっていくようで、本来なら闇を好む夜行性の動物さえも、影に怯えて深部に行くのを拒んでいるようだった。 山や森の影のかからぬ空中を飛ぶ鳥達さえも。 羽に風を受け気流にのり、高く舞い上がる姿が、かの国へ近づくにつれて不思議に−不自然に見えなくなった。 おかしい、と思い夕暮れも近い事もあり、森の高い木の枝に降り立つ。 太陽が遠い山の合間に消えていく。 横から差す陽光が木々や山の影を長く伸ばして周りを覆って―それは日の光の消失と共に夜の帳と同化した。 闇夜。 白い人影が、そっと地に降り立つ。 「…獣の気配が無い?」 進める道が無いかと眼をこらす。 だが、鬱蒼と茂った草木は不規則に生え、人どころか獣が踏み進んだ痕跡すら無さそうだった。 野生の動物たちは、彼らのテリトリーを示すために一定の場所を通り、ときに獣が獣を追うためにその通路を辿って、ひとつの獣道となる。と、いうのに。 「ま、いいか」 おかしい、とは思う。 だが、推測仕切れぬ事象を紐解くよりも彼には大事な事があるから。コレも一つの幸いだと思って、歩を進めることにした。 夜に飛んで進むのは、余程慣れた場所以外では結構な危険行為なのである(そも、人は飛ぶようなものではないから他者の目が気になるし、森に住む夜盗に矢を射掛けられた事もある)。 しかし。 一刻もたたないうちに、彼は足を止めることになった。 「…またですか」 念のためにと、森に降り立ったとき近くにあった木に印をつけた。 夜目が利かないわけではないが、迷ったときの事を考えたのだ。 木の幹に尖った石で簡単な目印。 木の天辺にも葉を蔦で結わえて、飛んだ時に確認出来る様に。 迷うような道ではなく、真っ直ぐ進んだはずなのに、十歩も進んだ辺りで、見た覚えの有る木の配列と人の歩いた跡。―己の痕跡。 まさかと、印をつけた気を探せば直ぐに見つかった。 それならば、と、今度は木に印をつけながら進めば、またも付けようとする前に、印の刻まれた木の幹。 明らかに、なにがしかの力が行く手を阻んでいる。 「…飛んでみるか?」 数日前に出会った可愛らしい魔女の言葉を考えれば、例の国を守るという魔力とやらのせいに違いないだろうし、他の鳥獣の姿が見当たらない以上、歩こうが飛ぼうが容易に森を抜けられない、というのは変らない気がした。 しかし、道を打開するには出来る限りのことをするしかない。 タン、と目印をつけた木の上にたった後、ひとまずただ真上に向かって飛んだ。 鳥の身で意識を保てるようになってまず試したのは、どの程度の高さを飛び、我が身がどんな大きさになれるのか、という事だった。 人の身で飛ぶときは、せいぜい人が一晩かかって越える山程度の高さを飛ぶのが精一杯で、それ以上を求めれば身体が悲鳴を上げた。急激な高山病にかかるようなものだ。 それが鳥の身では、始めこそ雲に近づいたときは翼が風に流されそうに為ったが、身体の大きさを替え、鳥の呼吸器―人の肺にはない気嚢呼吸―を使えば空気の薄い上空でも身体に異変は起こらず、気流さえ上手く掴めば軽く舞い上がる事ができたのだ。 身体も状況に合せてそれなりに大きさをコントロールが利く。 意識の無かったこれまでの昼の間が惜しい位に、魔女の魔法の加護を受けてからの旅路は順調だった。 夜の身は人。 鳥ほど飛ぶことは出来ない。しかし、眼は利く。 進める道があれば、朝を待って飛べばいい。 「行きたい方向は森ばかり…か。しかし」 四方に視線を巡らせれば、一辺だけ森が途切れたその先。 「海…」 陸路か空路か海路か。 −かの国の土地に掛かっているという魔力の及んでいなそうな道を選んだ。 潮騒の届かぬ上空からでも、陽に跳ねる飛沫がキラキラと眩しい。 鴎の群れの進路から身を逸らして、更に風を捕まえる。 岸壁から小動物を狙い弾丸のように飛んでくる海鷲から、素早く逃げ―追う気配がすれば数瞬だけ、彼を威嚇する大きさを取る。 獲物の変異に脅威を受けたか、白い腹を向けて遠く遠く離れていった。 ウミネコの鳴く声が増えた頃。 港が見えたのと同時に、目の端で捉えていた森の奥の奥に、城の尖塔らしき建造物の端っこが見えた。 直ぐにそこ目指して進路転換を図ろう翼を閃かせようとして− (いや、だめだ) 静かに高度を下げていく。 港を見下ろせる小高い場所にある一軒屋の屋根に降りた。 羽を畳む。 (結局は森に囲まれている―抜けるには、正しい道) 左右何度にも自在に動く鳥の首を巡らせる。 海を見下ろすように、河口をぐるりと囲む家々。 船から荷を降ろす人々。 (どれだ?道を知る者…入ることを許されている者は) かの国へ荷物を運ぶ荷車を探した。 ◆ ◆ ◆ 「和葉ー、何やその鳥」 「可愛いやろ!さっき、ウチの頭に降りてきてん。懐っこいわぁ」 「何や、お前の頭…ぼっさぼさやから鳥の巣に間違えられたんか?」 「ちゃうわ!」 「賢者さん、おったん?」 「ああ。仕事終了や」 「こっちも仕入れ終わったで」 「…やっぱり戻るんか?なぁ、やっぱり―」 「アカン!商人が店投げ出すとか、ありえへん。平次こそ、いくら重要文書だからって、配達係なんて。…実は降格でもしたんと違う?」 「アホいいなや。単なる通信文ならともかく、今回のは蝋封の刻印入りや」 「…それって」 「まぁ、多分…アレのことやろ」 「アイツ、どういうつもりなん?あんな子ぉやなかったのに」 「さぁなぁ。まぁ王と賢者が揃ってれば、国は大丈夫やろ」 「でも、…なんか、活気が無いんよね。港、久しぶりやけど、何やコッチの方が肌にあいそうや」 「―せやったら」 「でも、やっぱりウチはあの国が好きやねん」 「…さよか」 「ほな、行こか」 「で?そのアタマのはどうすんねん」 「丁度、籐籠の大きいの仕入れたから、ソレに入れて連れて帰るわ」 「飼うンかい…。籠だけやのうて、餌も忘れんとけよ。三日三晩籠の藁つつかせたら、途中で逃げんで」 「わかってますー!ほんま懐っこいし、喋ったら店の人気者になれるんやけどなー」 「ぴーぴーうっさいのは一人で十分やろ」 「誰のことや!」 ◆ ◆ ◆ 旅をするとりの話。  ×
|