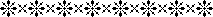 おうじさまのはなし 手元に届いた二通の手紙。 一通は先代付の賢者から。 一通は今の賢者の従者から。 まずは国王として、国政に影響する文書から目を通す。 「塩害か…。海流の向きは悪くないから、なんとかしねーとな」 この国の交易の要は海辺の砦の近く。 数年前から耕作地を増やし、海辺を単なる他国との窓口にするのではなく、独自に発達させられないかと模索中。 賢者が陣頭指揮を執ることで、魔法に守られた国の外へは出たがらない国民の中でも、商魂逞しき者や冒険心ある者、単純に海が好きだという者が、小さなコミュニティを作って少しばかり離れて暮らしている。 周囲と完全に独立しているこの国が、細々と繋いできた『外』との糸。 「とりあえず、物資の手配だけ回しとくか」 現時点で出来る手を考えて、そう呟いて。 ふぅと一息。 次に、そっともう一通を手にする。 誰より知りたい人の事が書いてある。 期待と不安とがない交ぜの心が、指先を震わせた。 ◆ ◆ ◆ おうさまになる前の ―まだ、おうじだったころ。 ほんの少し前の事なのに、とても遠くにある記憶。 遠くに感じてしまうのは、きっと隔絶があるから。 幼い王子だった己。 幼くとも賢者だった友。 顔の良く似たともだち。 いちばんの仲良し。 …本当はもう一人いたけど、あの子は、隣に住んでる女の子の。 ―ずっと一緒にいよう ―ずっと一緒だ 王と賢者は、この国で大切な役割を持っていたから、その子ども達は生まれながらにして、絡み合い続ける一生。 指切りだって要らない、ずっとの約束。 ―この国の続く限り 青くてキラキラ綺麗な瞳。 彼はいつだって、沢山の本に囲まれていた。 時々その隣に座って本を読んでみたり。 並んで椅子に腰掛けて彼の父親の講義を聞いたり。 でも、本や教師にばかり向けられる瞳がつまらなくて。大きな本を抱えたままの、その手を引いて外に出る。 青空の下で、青い瞳を見たかった。 何でも知っている、何だって見通してしまう頭の良いともだち。 ―雲の動きを見て、風のにおいで天気を予言。 いつだって当たっていた。 なのに、帰り道にかかる時間を読み間違えて、雨雲に追い付かれ濡れ鼠が二匹。 ―どこの茂みの木苺が食べごろなのか。 川魚のたくさん取れる暦月。 美味しい果実がたわわになる木。 野うさぎを狩る面白い仕掛け。 ―遅い帰宅に叱られる事数度の後、教会の鐘の音が聞こえなくても、あとどれくらい遊べるか時刻を知る方法。 迷った森で、行くべき方向を知る方法。 はぐれないように、手を繋いで。 喧嘩した後の、仲直りの方法。 最後には、また、手を繋ぐ。 何だって、知っていた君。 でも、そんな君でも知らない、ボクの心。 だって、こればかりは見えないでしょう? 口から出る言葉で誤魔化してしまえるでしょう? ―ずっとずっと好きだった 木漏れ日の下、歩きつかれて二人で昼寝。 蝶々が鼻をつついて起こした。 隣には、丸まってまだ寝ていた君。 蝶々が今度は君のほっぺたに。 『起こしたらだめ』 囁いて、ピッとひらひら舞う黄色い羽を叩き落す。 ひくりと動かなくなる羽虫。 燐粉が落ちて、頬が光った。 そっと息を吹きかけて払う。 『…ん』 くすぐったそうに、小さな声。震えるからだ。 『しーい?』 『…ぁんだよー、かい』 呼びかけにゆっくり開く瞳が不意に視界に入って、そのまま逸らせなくなった。 ―こんなに綺麗だったっけ 高鳴った心臓の音、不思議。 でも、えも言われぬ満ち足りた心。 ―あの青い瞳はボクのもの そう、決めた。 ◆ ◆ ◆ 「戻ったで」 「遅い。待ちくたびれたぜ?責任取れ」 「…どないせえっちゅうねん」 「大体さ、新一は?なんで服部くんが先かな」 「人前に出たくないんやろ。夜になったらくるゆーとったわ」 「…なら、いいか」 護衛からの報告を淡々と聞いていく。 おおよそは、早駆けの使者から聞いていたから、単なる確認。 「じゃ、白い鳥は諦めたのかー。残念だったなァ」 「……嬉しそうやな」 「えー?トモダチが悔しがってるのに、喜ぶなんて、そんな!」 「夜までに、そのにやにや顔捨てとけよ」 「はいはい」 じゃ、下がっていいよ、お疲れさーん、と。 およそ国王とも思えない適当な慰労の言葉を投げながら、手をひらひらさせるこの国の現王、黒羽快斗。 解ってはいたが、その飄々とした様子に幼な友でもある護衛は肩を落とした。 そうしていれば、昔の彼のままなのに。 「そっか。諦めたんだ」 護衛が締めた扉の向こう。 漏らす言葉に、声に、笑いが滲む。 いっそ彼に会うときに備えて、存分に笑っておこうか。 「約束は、約束だ」 約定を違える賢者ではない。 これで、ようやく―。 「式の日取り決めないとなぁ…」 「…誰のだ」 「!…もちろん、俺と貴女の」 音もなく先ほど締められた筈の扉が開いていて、逢いたかった人の姿。 王は最上の笑顔を浮かべた。 「おかえり」 「…ただいま」 ふわりと男は腕を広げたが、女がそこに飛び込むことはなかった。 仕方ないかと男は肩を軽く上下させてから腕を降ろす。 「浮かない顔だ。我が妃様は」 「賢者だろ」 「違うよ。俺のお嫁さんだ」 「バーロ」 たおやかで美しい、神聖な森の泉のその静けさの中に咲く一輪の青い薔薇のような姿なのに。 口から出る言葉は、昔から変らない、いつもの彼。 それが嬉しくて、けれど少し不服だ。 これからは、妃として民衆の前に立つ事も出てくるのだから、一通り淑女の嗜みを身につけてもらわないと。 「鳥を逃がしたんだって?折角のチャンスがあったって聞いたけど」 「…色々あってな。しょうがねぇ」 「では、約束だ」 「…なぁ、なんで服部と和葉さんの家に兵を向けた」 「保険だよ。仕事には緊迫感が必要だから。大切な賢者殿を守れぬ護衛に、守るべき家族も恋人も必要ないだろう?」 「本気で言ってるのか?」 「ああ」 きっぱりと、堂々と。 罪悪感の欠片も無い様に、賢者は言葉を失う。 他者を従える威厳。 敬愛し畏怖すべき存在。 賢者が旅立つ前より一層、王らしい姿。 けれど、昔ながらの友人が感じるのは、その頑なさ。 孤高であろうとする中に、強情な子供が隠れている。 「どうして」 「愚問だ、新一」 「でも」 「何度も言った。まだ足りない?信じない?」 「何度も言った!俺じゃ足りない、妃になれない!」 ああ、これでは彼が出て行く前と変らない。 変えられない、のだと思い知る。 王は、手法を変える。 一番使いたくなかった方法。 結局、頭の良い彼を言い包めるなど無理なのだ。 ―いや、そもそもが間違っている。全部、ぜんぶ それでも。 形だけでも。 ほんのひと時でも良いから。 「だったら、正室の他にも愛妾を入れるよ?」 「…てめぇ」 「そう言う事だろう?歴代王の中じゃ、持たないほうが少数だ」 「だったら、最初から俺は」 「でも、正妃は新一だ。そうじゃなきゃ駄目ー」 「…いつまで」 「子供が出来るまで?そしたら、魔法も解くよ」 「……」 押し黙る賢者に、笑いかけながら。 王は、唯一つ願う。 「愛してる。…傍にいて」 ひたむきに向けてくる視線の強さに、紙一重の脆さに、賢者は何も答えずに踵を返した。 王は追わない。 この国に縛られている彼に、逃げ場などないと知っているから。 逃げるつもりがあるのなら、本気で王の伸ばす手から逃げるつもりだったなら。 ―賢者は、鳥を騙してでも、殺してでも、必ず連れ帰らねば為らなかった。 ―賢者は、友に憎まれても、友の愛する全てを引き換えにしてでも、この国に帰ってきてはいけなかった。 優しい、優しい、賢く、―愚かな君。 「あいしてる…」 幼き賢者に恋をしたまま王様になったおうじさまの話。  ×
|