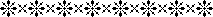 おうさまのはなし#4 民には避難をかけた。 警備隊長や兵達が、今頃懸命に一人の取りこぼしも無いように、新天地として用意していた未成熟な土地へと彼らを連れて行くだろう。 異変を感じた海にいる賢者も迎えに出てくれるに違いない。 最後の伝令者に「お前も早く馬に乗って、合流してくれ」と伝えたし。 あとは、この暴走する魔法を―国を閉じてしまうことだけだった。 「さぁって、行きますかね」 わざと声に出して快斗は言った。 軽口を叩くように、けれど心の何処かで死を意識しながら。 一旦は沈黙したあかい魔法は、まだ消えては居ない。 密やかに伝えられる、王以外の誰も代われない仕事があった。 いや、仕事のようでいて、それは王者たる人間の欲望を刺激する秘蹟。 愛した世界の終焉を、愛した者と迎えるのはかの魔女の最期の望み。 それを叶える、というものだ。 大丈夫、と快斗は思う。 例え此所で斃れても、後の面倒を見てくれる親友もいる。隣に、あの変な鳥男がいるのは大層腹が立つが、それでも、新一が少しでも楽になるなら、居ても構わない。無事戻った暁には、さっさと新一の傍から追い払うつもりであるが、保険は多いほうがいいのだ。 「駄目だったら、ごめん、な」 小さな呟きは風が消した。それでいい、これだけは誰にも知られてはならない秘密だった。 きっと新一は、快斗の今からの行動を怒るだろう。この秘密を守り通せて本当に良かった、と快斗は心底から安堵する。王の秘蹟が、全てを見通すと謡われた賢者ですら介入不可の秘密、として守られ続けてきたことに感謝を覚えた。 先程よりも明確に、闇がうねり不快な音を轟かせる回廊。 その奥できっとまた噴出しているであろうアレが待つ場へと、快斗は足を踏み出そうとした。 その時―不意に大きな風が吹いて―声がした。 「待って!あおこの、魔玉を持って行って!」 思わず振り返れば、白い鳥に乗った、一人の少女。 「な、に…?!君は―」 「この国で生まれ、けれどこの国に合わない青い魔法を統べる魔女、あおこです。久しぶりだわ…快斗王子様、いえ、王様。あのね、あおこ、この国を離れる際に、賢者と当世の王様に言われたの。この国にもしものことがある時には、魔法の力を貯めた魔玉をその代の王様に渡してって!」 「オジさんと、親父が?」 こくんと肯いた少女は、大切に胸に抱えた青く光る魔法の玉を王に渡す。 失礼します、と言って首に革紐を通し、不可思議な光を放っている水晶玉を王の首元へ。 「どうか、全ての力を、王様の守護に―」 魔呪の詞は端的に、切実な祈りの言葉で出来ていた。 途端に火花のように青い光が溢れ、快斗の身を包む。 「あおこの魔法は、生きる者の力を補助するの。命を守り、再生を促す力なの!王様は、まだ、やることがあるのでしょう?少しでも助けになると、いいんだけど」 「ああ。…そっか…、ありがとう、な」 ピィイ・・・と白き鳥が鳴いて、彼女を呼ぶ。 「さ、アイツに乗って、ここから―この国から出るんだ。王の命令だ、いいな?―あかこ、いるんだろう?お前もだ」 王の為に動くなどとは全く思えない白き鳥が、突然連れてきた魔女に、もう一人の魔女の姿を感じて、快斗は呼びかける。 「…いやよ。私は残るわ。そして見届けるの」 「あかこちゃん!呼んでくれて、鳥さんを向かわせてくれてありがとう!」 空間を割いて顕れた少女は首を横に振るけれど、王は冷たく突き放す。 「お前に、破裂するような紅い魔法を受ける力はない。俺は命令したんだ。行け!」 「……馬鹿!」 王の為に為せる力がないと彼女が無力さに唇を噛む。そうして堪えようとしたけれど、涙が溢れるのを止めることは出来なかった。 あかい魔法、あかい魔女、―魔女の宣託が、脳裏を巡る。 なぜ、彼の代でなければならなかったのだろう。 あおこが優しく、視界を揺らがせるあかこの手を引いて…そして彼女たちが、鳥の背に乗る。 ソレを確認し、快斗もまた再び向かうべき場所へと身体を翻そうとした一瞬―ほんの刹那、快斗の目と、白き鳥の視線が絡んだ。声に出さず、快斗は『たのむ』と、口を動かした。 鳥は肯くように首を一振りすると、翼をはためかせた。 ◆ ◆ ◆ 青い光に守られた王を見た魔女は―微笑んだように、快斗の眼には映った。 円陣から吹き上がる赤く黒い靄は、まるで炎が揺らいでいるようだった。その中で形作る誰かの影は、古き昔に在ったこの国の創世者の片翼。 愛する王が消えてしまっても、愛した血統を守ってきた力。 魔の性質に引き摺られ、いつしか血を啜り地力を啜って、ただ人柱を欲するようになった魔力。 (ともに、眠りましょう?) 頭に響いてきた言葉は甘く、まるで母親が幼子を昼寝に誘うかのような。 「ああ…。もう、束縛から解放されていいんだ。貴女も―」 「動けぬ石に杭打たれ見守る時は終った。―『俺』と来い」 王の一族だけのための秘蹟。 ―魔法陣を消す方法。 ―それは、『彼女』を当代の王がその身に移すことだった。 魔女という祝福の印を持って、最期の王となること。 国から魔法の守護を奪い、王のみが最大にして最期の力を得るのだ。 王の一族が治世の過渡する時期に争いごとを起こしていた最大の理由だ。 巨大な魔力を手に入れたがった者たちの欲望のぶつけ合い。 魔女を我が身に降ろし、大きな力を得る、という。 一子相伝となるべき秘蹟は時に、同じく魔力で繋がる者から、同じく血統ある者に洩らされ、争いの火種となった。 祭壇への鍵は唯一つ。 王たる資格があると認められた王にだけ渡されてきた。 渡したのは、この国の治世の為に、その為だけに魔力を求め、この国の中心から魔法を動かすことを良しとせず、常に魔法の在り処を監視してきた賢者と、その賢者に認められた王が、次代の王へと。 賢者は王が私欲に流れぬよう、魔法が途切れぬよう、血族が絶えぬよう、努めてきた。 そして、王と共に繁栄と安寧な世を求めて共に在った。 それでも、常に王の傍にあった賢者が知らぬ秘密。 賢者に呼ばれて、死期を間近に控えさせている父の枕元へ。 親子二人きりの、最期の時。 時折咳き込みながらも、彼の父は穏やかに微笑んだ。 『継ぐのなら、教えよう。秘密の言葉だ』 『どうしても、この国の魔法に匹敵する力が見つからなかった時の為の、この国の閉じ方だよ』 『決して、誰にも洩らしてはならない。…賢者にも。いや、…賢者だけには、決し、て、知られてはいけない、おうさま、だけの秘密だ』 『お、やじ!親父、シッカリ―』 最期の時は足音を立てて、父の傍らにあるようだった。 父が言葉を途切れさせるたび、快斗はその首に死神の鎌首が掛かっている幻影を見た。 『大丈夫だよ、快斗。彼女自身はお前の母親のようなもので、同時にお前を夫とするだろう』 『なんで、親父が、親父が!その守護でも力でも手に入れれば―』 『私に、は…お前が、いたから』 『なに…』 『守護を受けるということは、彼女が私に成り代わることに近い。彼女は、直系の子を手にかけた魔女なんだ』 『―そ、んなの』 『最期の王しか使えない秘蹟、というのはそういうことだ。…それでもいいかい?快斗』 魔法を、『彼女』を封じるのではなく、解放する秘蹟。 次代なる子を持たず、魔女をその身に呼び込み、伴侶のように共に有るのが最期の王の役目。 王の身体に呼び込まれた彼女は、王の寿命が尽きる時に、王と共にようやく天上の国へ還るのだ。 父は問う。 それで、お前はいいのかと。 『―いい。どうせ、俺はずっと叶わない恋をしてるだろうし』 『…』 『魔女だって、たとえこの身体に受け容れたって、俺の心まで渡してやる義理はねぇよ』 父親は、少し困ったように笑った。 魔女の力を見くびる気はなかったが、結局の所、我が身に移した魔女を最愛としていれば、思うままその魔力を使えるということなんだろう。もしはく意識ごと乗っ取られるのかもしれないが。 けれど、快斗は魔法など欲していない。必要なら、受容してやるだけ。だから心が変質する事などは考えなかった。 快斗にとって、新一に向ける想いは簡単ではないのだ。 身に移した魔女が、心を誰かに奪われている王に怒った所で構わない。 魔女がかつてそうしたように王が心を寄せる他者に凶手を伸ばしさえしなければ。もし、ソレをする―新一を傷つける存在になるのなら、彼女諸共消えてやるだけだ。 『お前は、強い、な』 『どんな時でもポーカーフェイスを忘れるな、つったのは親父だろ』 見えぬ死神に、泣きついて、連れて行かないでと請いたい思いをこらえて、快斗は笑った。 そして教えられた、短い不思議な音を持った詞。 「来いよ―呼んでやる、から」 果たして、こんな魔物に近い存在になった彼女が、大人しく快斗に収まるのか。 全く予想がつかなかった。 魔女が自身を封じると一緒に遺した力。 強すぎる思いを抑えるための。 しかしソレは同時に魔性のモノを呼び込む場になったのだろう。段々と変質していった力。 いつしか力の本来の意思にも背いて。 それでも。 あの魔法陣の根幹にいるのは、『彼女』なのだ。 快斗は今は使われていない古い詞を、唇にのせた。 ―それは魔女の本当の名前 『 』 ― ! 火が大きく爆ぜたような、弾けた光。 それは真っ直ぐに快斗に向かい― ついに、この身の内に魔女が来るのかと、唇を噛んでその衝撃を快斗は待った。 だが。 「な、っ!?」 身体を焼くのかと思った光は胸元で白く発光し、そのまま光は快斗の胸元の―少女が首から提げた魔玉へと吸い込まれたのだ。 「うわ…ッ!」 一体どういうことだと、胸元を見ようとしたが、突如目の前が赤く染まり、快斗は慌ててその発生源を見やる。 光が魔法陣から解かれた瞬間に、更に大きく赤く紅い炎が―大きな火柱があがったのだ。 一体何を焼いているのか。 魔女が遺した魔力か、それとも想いの残滓が暴走でもしているのか。はたまた−共に滅ぶための契約の証か。 「!ッ、マズイ、な」 業火が快斗の周囲を覆っていく。 簡単に退路を塞がれてしまいそうだ。 だが。 快斗に纏わっていた青い光が、強く強く―先程魔玉に飛び込んできた白い光も合わさって、青白く、炎のように立ち上った。 「?!あ、つく…ねぇ…」 目の前で炎が海のように波打つのに、快斗は熱さを感じなかった。無論、身を覆う青白い炎にもだ。いや、この青白い炎は、明らかに快斗を守るものだ。 「よくわかんねーけど、逃げるしかねーな!」 魔法を使う者ではない快斗としては、目の前の赤い炎からは逃げる以外の選択肢はない。 祭壇の間から出て、回廊へ。 赤い炎の手は、殆ど快斗を包んで共に外へと出ようと焼き進んでいくようだ。 けれど、快斗は走った。 普通なら煙に巻かれるか、熱さに倒れるか―焼かれるか、という状況で。 そっと、身を守る発光源である胸元の魔玉に触れてみる。 熱を感じない、冷涼な、不思議な手触り。 走っても疲れが薄いのはあおい魔法からで、業火の魔手から守るのは―… 「ありがと、な」 小さく再び名を呼べば、魔玉が小さく震えたような気配がした。 ◆ ◆ ◆ 城の深部からあふれ出した炎は、みるみるうちに、国中を包む業火となった。 轟々…ゴウゴウと風に身をよじり更に赤い魔手を伸ばす火。 どこかで何かが爆ぜる音―ぱちん ぱちん と木々が焼かれては倒れていく。 新一は、その様を眼下に見ていた。 飛ぶ白い鳥の上から。 避難の誘導の途中、王の所にどうしても行かねばならないと白き鳥に乗って行ってしまった少女が、行った時よりもう一人増え、戻ってきた。 二人の少女は王があの場所へ向かった事を賢者に教えてくれた。 新一は、入れ替わるようにその背に飛び乗って、再び飛ぶようにせがんだのだ。 遠い山の向こうの向こうの天辺に日が差し掛かっていた。 あまり時間が無かったが、どうしても、新一は快斗の所に行かなければならないような気がしていたから。 ―嫌な予感。 王は、後は少しだけ。俺の仕事があるだけだから、と言って笑っていたけれど。 「あの、嘘吐き野郎…!」 朝によく歩いた散歩道も、思索に耽るために寝転がった川辺も、花屋も、粉引き小屋も、なにもかもが、どんどんと業火に呑み込まれていく。 「…ど、して」 ―『俺はこれから魔法を止めるよ』 「かい、と」 ―『大丈夫。大元を止めさえすれば、唸りも止むさ』 「嘘だ、快斗」 ―『でも、一体どれ位の影響がでるか判らない。国の魔法なんだ。だから、頼む。―賢者よ』 「いやだ、快斗、快斗」 ―『民を頼む。海にもう一人の賢者が居る。今すぐ森を抜けてソッチを目指して、『全ての者』を、この国から一旦出してくれ。賢者のお前が』 ◆ ◆ ◆ 伝令系統は突貫であったが上手くいき、城の全兵士が―護衛も伝令も防人も近衛兵すら、賢者の命に従って、民を避難させる事に尽力し、城から黒い煙が見え出す頃には、国を見下ろす丘へと国の民を誘導できていた。緊急時に、王の意思が―その意を伝える賢者の言葉が、民にとって何よりも優先させる体制は、この国が王を絶対の一族と想えばこそ、可能になることだった。賢者へ反発を示す魔法使いもまた、国の魔法の異変に脅えたか、賢者の言葉を聞きいれ、不安定ながらに使える魔法を用いて―水晶球で残った者がいないか探し、身体の弱い者を補助し―避難の手伝いをしたのだ。 丘を登り、後は森を駆け抜けるばかりの移動の列のしんがりで、新一は黒煙に赤い火が混じり強くなっていくのを、ただ見ていた。 早く、火が―煙が収まればいいと。 だが、炎は煙の勢いを超え、大きくその凶手を広げだしたのだ。 呆然としていると、暫く傍を離れていた鳥の姿をしたキッドが、二人の少女を連れて、舞い降りた。 「お父さん!」 うち一人の少女が、共に民に声をかけ追い立てて後方での護衛を努めてくれていた中森をそう呼ぶ。中森は険しくしていた顔を緩め、「あおこ!?」と叫んだ。 「お前、どうして」 「水晶玉で異変を知らされて、それでこっちに向かってる途中でね、この鳥さんが来て、王様の所へ連れて行ってくれたの。前の王様との約束があったから―」 「快斗は?!」 親子の対面に新一は割り込んで、親友が一体何をしているのかを問う。 再び、回廊の奥へ向かったようだった、と聞いて、新一は身体と思考を硬直させる。 華奢な指先を手のひらに握りこんで作った拳だけがプルプルと震えた。 「…んで、そんな」 「王の仕事が、あるから」 「!」 「あかい約束は遥か昔からの、彼女と王の一族との取決めなのですもの」 紅い魔女の虚ろな言い方に、新一は気色ばむ。しかし、よくよく見れば、彼女の瞳は濡れていて、囁くような声が。 「あのひとを 助けて」 と。 新一は、キッドの背に飛び乗り、中森に二人を連れ、避難をするよう言い放つ。 彼ならば必ず安全な場所へと彼女達共々避難してくれるだろう。 「頼む、キッド!俺を快斗の所に連れて行ってくれ」 ピピィ―…と嘶き、翼がはためいて新一を空へ連れて行く。 炎の凶手を避け、進んでいった。 「ゴメン、疲れてるよな、でも」 快斗の所へ行かなくてはいけない、と新一は炎の熱さも感じないほどに逸る心で、そう思った。 「っ…も、少しだ、ってのに」 ゴホゴホと快斗は咳き込む。 熱さはそんなに感じない。 しかし、焼け散る城の内部に煙は勿論煤や小さな火花が身体を襲う。炎の熱で歪む視界と立ち込める煙が周囲を見えなくさせて、歩き慣れた場所でさえ、左右の感覚が怪しくなる。 「…くそ」 手取り早く―外へ。 そう思うも、ここは回廊の先の出口しかないのだ。 吸い込む息が、内部を焼く感覚。一瞬で冷涼な何かが、焼けついた粘膜を覆って癒そうとするが、呼吸がままならなくなるのではどうしようもない。 「まず、…っ」 ついに快斗は膝をついた。 口元に手をあて、息を整えようと試みる。 身を守る魔法が、感じる熱さや小さな火傷をすぐに治してくれても、次々に猛攻されれば快復が間に合わない。 一気に焼けた天井が落ちてきたら身体の快復を待つ前に、焼け死ぬだろう。 とにかく歩いて、でなければいけない。 そう思うのに、グラグラと視界すら揺れてくる。 ―いや、城が揺れて…?! 「し…い、ち」 焼け落ちるのか、と。 快斗は直感で理解した。 血を捧げず、魔女を解放し、魔法を捨てた代償なのだ、と。 せめて、我が身で揮える魔力を―魔女の力があれば何とかなったのかもしれない。 けれど、魔女は快斗ではなく、魔玉を選んでその身を移した。 国に沈殿してきた魔力は支配していた場所ごとその力を喪って。 ―王と共に滅ぼうとしている。 「ご…めん」 揺れに足を取られ、体勢を立て直せない。 視界の端、上から、崩れてくる壁が見えた。 思わず眼を閉じた。 衝撃を―死を覚悟した。 目蓋の裏に浮かんだのは、泣きそうな顔で怒っている愛しい人で― だが、その瞬間、聞こえてきた、声。 「快斗!このッバーロォッ!!」 「!?」 ハッと快斗は眼を見開く。 幻聴だろうか。 笑顔の幻視も無く罵倒の幻聴が走馬灯とはあんまりだ―などと考える暇があればこそ、壁の崩れを吹き飛ばし、赤い炎の海を拓いて、巨大な白い翼が飛んできた。 さいごのおうさまのはなし  ×
|