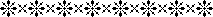 かれらのはなし#2 なんとも厄介な相手に惚れた厄介な男の姿に、鳥の身に宿った男は複雑な思いを抱かずにはいられなかった。 王という立場の者が、その全ての責務を放り出す所か、それすらも利用して成就させたかった想い。それは守るべき民の生活の場、彼らの生命を活かす為の世界を壊す事も厭わずにたった一人を求めた恋だったのだろう。 友達の変容に悩んでいた賢者の視点を通さずに眼にしたその求愛者の姿は、横暴のようでいて只管にひたむきで、傲慢とはほど遠く、報われぬ想いに地団駄を踏む切なさばかりが目に付いた。 そして、その行き過ぎた恋情に応えられないと言い放ちながら、傍に、共に在る事を当然だと主張した賢者。 生殺しもいいところだ。 その想いを抱いたままなら消えてくれと言われた方がマシな気がする。 それなのに、快斗と呼ばれた王は―恋をした男は笑った。 諦めた笑いではなく、ただ愛しさのままの、そんな顔で。 そして賢者もまた、笑い返すとは。 二人の重ねてきた年月がそうさせたのだろうか。割って入ることが出来ぬ二人の在りように、キッドが感じたのは焦燥のような、憧憬のような。妬心を燃やすには殉教するような眼を賢者に向ける王に、むしろ憐憫が沸いた。 報われなくても、構わない。 ただ傍に居る事ができるなら、とその眼は言っていた。 似たような思いを抱いているからか、身につまされる様な気がした。 だが、そのクセ、応えないと分かっても「愛している」などと言った男が、賢者の全てを奪い束縛することを決して諦めはしないだろう、とも予測がついたから、苛立ちもまた感じるのだ。 王のひたむきな思いは、賢者を、賢者の王を受け容れられないと言った言葉も気持ちも呑み込んで、賢者全てを包むものだ。いつかその事に気付いた賢者がゆっくりと心を開いていくのを待って、賢者の傍らに在り続けようとするに違いない。 同じ存在を欲するからこそ、キッドにとって王が最も厄介な存在になることが直感で理解できてしまった。 (全く、こんなにも手を焼きそうな困った人が…) 一人ではなく、二人である。キッドはどうにも前途多難な予感を覚えて鳥の身でありながら溜息を吐き出さずにはいられなかった。もっともその吐息は「ピュピィ…」と妙な鳴き声になってしまったが。 ―その時だった。 気の抜けた鳴き声を掻き消す叫びが祭壇の間に上がったのは。 「王よ、直ぐにそこをお退きなさい!」 異質な空間を肌で感じながら、ずっと意識はあの二人を追っていた。―だから、魔女が叫んだ瞬間、眼下の二人が弾かれたように動きを緊張させたのと同じくキッドもまた何事かと身を震わせた。 魔女のその場の異変を知らせる声は、叱り飛ばすような強い言葉だった。 「血を流した姿で、そこに入り込んでは駄目!早く!」 白く浮き上がる文字で囲んでいる円陣の端に、王の足が入り込んでいた。思わずといった風に下を向いて確認した王の口元から、ホンの少し赤い血がすぅっと顎を伝い、一滴にもならぬほど微かなソレが、 落ちた。 「!?」 「な、に…?!」 「―ッ!」 ―ピィ… 確かに白く紋様のように浮いていた古代の文字が、瞬間、赤く―黒く―染まった。 そして、円陣の中心から急激に立ち昇る靄。 物質ではない大きな煙のようでいて、ひどく粘性を帯びて見えるソレは、赤く黒くうねり、渦を巻き―そこから伸びる一部が円陣の上に在る王に―手を伸ばそうとしているように、上から見ていたキッドの目に映った。 ワケも分からずに、新一の手が、その靄が王の身体に触れる前に、その外へと引っ張った。 キッドも、ソレの異質さに、言い知れぬ不安と恐れを抱き、慌てて賢者の所へと舞い降りた。 「なんだ、これ…封印されている魔女、か?」 「多分な…飢えてるらしいから、反応しちまったんだろ」 儀式に立ち会ったことない賢者と儀式をしたことの無い王にとって、目の前の現象は、それぞれの立場から習得した知識だけが理解への手がかりだった。 異様な光景に慄きながらも、王と賢者は事態の把握をしようと試みる。 あかこ、と呼ばれていた魔女だけが、驚愕に―いや明らかな恐怖を顔に浮かべて、首を左右に振っていた。 「いや…駄目よ…駄目…!」 魔女の抑止する言葉を掻き消すような地響きが始まった。 「あかこ、これは?!」 「儀式の時に現れる、力の源泉を求める『彼女』の御手」 「つまり」 「貴方を望んでいるのよ、王」 「祀りあげる手間もいらねーってか」 「貴方ならば」 「…収めるには?」 「貴方は王にして、王とは彼女に識られていなかった存在。だから彼女は次の贄を求めながらじっと待っていた。彼女は知性ある魔力そのものだから。滅びへの警鐘が鳴らなかったのは、まだ『前』の分で魔力が足りていたからよ」 「へぇ。親父はそんなに美味かったのか」 「……まだ先だと思っていたのに」 「それは、」 「こんなに、また飢えているなんて―」 すぐ傍らに有る血族を認知したからか、靄はどす黒さを増してうねりを激しくしていた。 「力は削がれている、って聞いてるが」 「―そう思って貴方の父君は逝ったようだけれど」 「じゃあ…親父の死去の儀式での、異変は」 「彼女が、王の血族を求め、けれど与えられぬがゆえに地を辿って飢えを満たそうと魔力を持つ者からその力を奪おうとしたから起きた事よ。その現象を見かねた賢者が、王の一部を与えて、幸いにも『彼女』はソレだけで満ちたのか、靄は消えて事は収束したの」 お陰で赤の魔法使いは大部分が魔力を奪われて、自らの執り行なった魔法さえ解けなくなってしまったのだけれど。 魔女が新一を見ながらそう続ける事で、おぼろげに目の前の現象を理解した新一は、血相を変えた。 「それじゃ、この変なモンを収めるには、快斗の血がいるってことか?!」 賢者として儀式を行い続けることを王に請うのが在るべき姿なのだ、と頭では理解していた新一だったが、この目の前で漂い空間ごと軋ませるように顫動する得体の知れない何かが、快斗を取り込みその命の証を奪うのだと思ったら、激しい嫌悪と忌避が沸いた。 もっと静謐で、清浄な遣り取りであると考えていたのだ。 この国を守護するモノと、繁栄と祝福を約束された王との間にある儀式というものが。 それなのに。 これでは、生贄だ。 そう思った瞬間、新一は先代の思いも、己の父の思惑も、快斗が為そうとしていたことも、ストンと頭だけではなくその心で理解し受容できたような気がした。 「快斗、やるなよ」 そう言って、新一は祭壇と快斗の間に立った。 あの靄には触れさせてはいけない、と。 「やらねーよ。新一に許可も貰ったしな。もう、魔法はいらない」 「…王の一部を与える事が手っ取り早いけれど…ソレをしてしまっては、何のために先代が用心を重ねて儀式を見送りながら、魔法の呪縛を少しでも解こうとしてきたか、…」 「他に、方法は?」 「地を巡るほどの力がまだ残っているかが問題ね。また、あの時のように矢鱈に吸収を行うのなら…止められる力を持つ魔法使いがもう居ない以上、…魔力保持者が死ぬ程度で済めばいいけれど」 他人事のように言ってはいても、魔女の言葉の端々に震えがあり、それがどれだけの恐怖なのかは想像に難くなかった。 「でも」 あかい魔女の眼が大きく開かれ、美しきルビーの瞳から放たれる視線が真っ直ぐに白き鳥を射抜く。 「アナタなら、出来るのではないかしら」 円陣の上で漂うソレはその手をそうっと王へと伸ばしては―近づけずに、時に何かに弾かれたように手を拱いているように魔女の眼には映った。 一体なにがそうさせるのか?と見れば、王の傍らに守るように立つ彼女と―その彼女の傍ではためく白い翼。 白い鳥が靄を払うように翼をはためかせれば、まるでその微かな風に煽られたように靄が引く。 魔女は確信を持って、白き鳥に語りかけた。 「王の予定通りに、アナタの身をここに捧げてはくれないかしら?」 キッドにとって、魔女の言葉は予想の範囲内にあった。 だから、新一がその言葉に咄嗟に反論を返す前に、意識を集中させて、その身体をぶわりと巨大なものに変える。 「キッド?!」 ―キュィ…ピピ― 新一を、その背後にいる男もついでに、円陣の上でとぐろを巻くようにうねるソレから守るように。靄に対峙し、まずは大きく翼を振った。 ブワァアアァ・・・・・・ 巨大鳥の起こす空気の波に、靄が押されるように少し後退する。そのまま何度か風を送れば、少しばかり縮んだようにも見えた。 なるほど、己の身体に掛かった呪いは、この国の魔法とは相容れない、対抗しうる力なのだと、キッドは理解する。 円陣の周りを飛び、風圧を与えみる。 その際眼下に写ったのは、驚愕し、不安げに眉を寄せて、懸命にキッドを見上げて何かを叫んでいる賢者の姿。 鳥が自らが起こしている風のせいで聞こえないけれど、心配されているのだろうな、と思った。 長い髪が乱れ、ローブがはためいている。上から見下ろしているから、首元―襟ぐりから覗く肌が深く暴けそうで、少し焦った。新一の背後にいる男に見えやしないか。 場違いな不埒な思考を読んだのか、単なる偶然か、魔女が声を上げた。 「…さぁ、こちらに来なさい」 そっと魔女が手の中に忍ばせている銀の刃が、キッドの位置から一瞬、見えた。 しかし、抗う事もない。 人が手を伸ばせる程度の大きさに身を変えながら、その近くに降りる。 いいコね?と伸ばされる白い手―銀の刃がきらっと光った。 「なに、する気だ?!」 ジッとキッドの動向を追っていた賢者はすぐに気付いた。 「…また、暴走されては困るの。ここに王の亡骸はない。貴女も、王も儀式をする気もないようだし」 「だからって!」 「試してみようと、と言っているだけよ」 新一は魔女の手からナイフを取り上げようとした。 美女二人が刃物を取り合う姿は、なんともそら恐ろしい光景で。 慌ててキッドは割って入ろうした。その時、鳥が身につけている青い魔法の宿ったモノクルの飾りの一部がナイフの刃に触れ切れて、転がる。 すると。 「え?」 「収まった…?」 コロコロと、三角形の四葉模様の入ったソレが円陣の中に転がり込むと、途端に文字はまた石畳に書かれた白い線に戻り、靄もすぅと薄らいだのである。 あっけない沈黙に、その場の全員から力が抜けそうになる。 「これをくれた魔女が、強大な力の持ち主だったか―」 「魔力ある血潮じゃなくても、あかい魔法じゃない魔力を撥ね退けられないぐらい、弱っていたか?」 だが。 ゴゴゴゴォオオオオ・・・・ン ォオオオン ゴゴゴ… 地響きというよりも、唸り。 祭壇の間にある柱や天井は全く揺れても歪んでもいないのに、立っていられないぐらい、時折大きく足場が―部屋の床が揺れ、震え始めた。 「ッやっぱ、そう簡単じゃねーか」 「!」 「―羽根を、貰うわ」 異常を察し、しかし止める術を見つけた魔女はそう言って、鳥から羽を抜く。ピィイイイ―と突然の蛮行に鳥は叫んだが、逃げずに、その身から白い羽毛を魔女に分け与えた。 (本当に、あかい魔法以外の力に抵抗できないの、なら) 本当は、王がそうしようと言っていたように、呪の描かれた紋様の上に白き鳥の血潮を撒いて、消してしまえるかを試したかったが、それは危険な事に思えた。 力と力がぶつかり合う―この国の大地を覆う魔法がきっと抵抗するだろう。ついさっき、あんなにも揺らいだ大地。 贄を求めるのは『彼女』だ。ずっとそう紅い魔法はそうして在った。だが、地を這い他者の魔力を啜るのは、彼女に近くて、彼女ではないもののように思える。 やはり永すぎる時が、彼女を魔物じみた存在にさせたのか。 どちらにしろ、強大な魔女が秘めている力は、いくら衰退していても測り知ることは不可能。 生半可な力のぶつけ合いは―間違いなく崩壊に繋がるだろう。 ―それだけは、いけない。 魔女は己の持てる力と白き鳥の力を借りて、不穏な地響きを止める。 だが、それは一時しのぎに過ぎない、と王に告げた。 僅少な力しか持たぬ身でも感じる、祭壇の奥で先程と同じように唸りをあげ、荒れ狂っている魔を帯びた存在がある。 快斗はスッと眼を細めて暫く沈黙して。 それから、新一へ向き直った。 「新一…いや、賢者に、頼みたい事がある」 この国に居る民全てを連れて、この国の領域から離れて欲しい。 簡単に言いはしても、実行する事は非常に難度の高い頼みだった。 「あかこが言ったようなことがまた起こったら厄介だ。ただ、幸いな事に、森で囲まれたこの国の領域にしか、その力の吸収ってのは可能じゃないみてーだし。だったら、一時的でも良いから、とにかくココを離れてくれ。皆を連れて、だ」 「今すぐ、か」 「そうだ」 昼を過ぎ、民は野に出るものもあれば、午睡している者だっているだろう。 突然に、家や土地を離れる指示を出したとして、果たしてそんな事は可能なのか。新一はめまぐるしく、頭を働かせる。伝令を、すぐに。いや伝令役だけでは足りない。伝令者自身もまた非難をせねばならないのだ。その連絡系統を立てるには―。人は歩けるものは足を使えばよい。しかし、家畜はどうする―。家財一式の荷造りは待てない、だが、慌ただしさに紛れ魔がさし人様の財産に手を出す者が出てはいけない―。 可能かどうか、ではなく。 王が国の民の為に決断する事ならば、全て可能にしてみせるのが賢者だ、と。 新一は口元に手をあて、ありとあらゆる側面から、最も早く尚且つ安全に王令を忠実に実行する算段をつけ始めた。 「あかこ、お前もだ。この国の魔法使いが俺の意志に従うよう、魔力がまだ揮える者は王の依頼の為に動くように」 「…水晶を通して、御触れをお城を起点にして空間に反映させるわ。それで、大体の民は指示に従うでしょう。あとは点在する彼らに―」 最後に、王は白き鳥を見る。 大して言いたい事はない。始末できなくて残念だ、という気持ちがまだ大部分を占めていた。それでも。 「新一を守れよ」 言うまでもないだろう事だったが、あえて言ってやれば、当然だ、と応えるようにピィーと鳥は嘶いたのだった。 魔女と賢者に事細かく指示を与えながら、回廊を歩いていく。 それぞれが各々の持ち場へ、というところで、新一は快斗に聞いた。 「快斗、お前は」 「俺は、王だよ。新一が望むように、この国を―民を守る為にいる。俺になら出来る、いや俺にしか出来ない仕事をする」 「…なにを」 「王様が真っ先に逃げれるわけねーだろ?伝令を発して最後に伝わったことを受け取るのは俺の仕事だしな。なにより、ココを離れるワケにはいかねーよ」 「……なにを」 「一刻も早い避難完了の報を待ってるぜ?」 「何をするつもりだ―?なぁ、かい」 「んな、心配しなくったって、最後は俺の、王の仕事なんだ。だから、新一は賢者の仕事をしてくれ。―いいな」 嫌などといえるはずもない。 それでも、言い知れぬ不安を覚え、新一はジッと快斗を見た。 その視線に、ひとつ息を吐くと、快斗はポツリと言葉を洩らした。 「…弱ってる魔力を無理矢理にでも封じる方法だよ」 「出来るのか?!」 「多分な。王の秘蹟ってヤツ」 「それは…」 「秘蹟を訊ねられるのは、王権保持者だけの権限のはずよ、賢者殿」 一体どういうことだと聞き出そうとする賢者の言葉を止めたのは、先程から水晶球を覗いている魔女だった。 貴女もすべきことをしなさいな、と言われ新一はぐぅの音も出ない。 新一は、快斗が「俺は絶対生きて何とかしてみせるし。新一のことも諦めてないし。大丈夫だぜ。後でな!」と言って手を振るのを見て、それから駆け出したのだった。 同じくその背を追おうとしたキッドだったが、「待ちなさい」という脳裏に響いた魔女の鋭い言葉に翼をその場でバタつかせる。 「貴方に、お願いしたいことがあるの」 その場を立ち去って行く王の背中を見送った魔女が、切実な色を浮かべて、キッドを見ていた。  ×
|