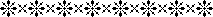 おうさまのはなし#3 石で囲われた部屋。 古い古い時を経て、けれども儀式の為に丹念に磨かれ続けてきた石室は、朽ち果てそうな印象など皆無。重厚な空気が敷き詰められ、どこか異界めいた雰囲気を漂わせた空間。 微かに灯る明りは、魔力によるもの。外の光など入らない。唯一外界へ抜けるのは、王の亡骸をー肉体からの呪縛を解かれ乖離してしまった魂を、空へと送るための煙取りの為の空気口だけだった。 大嫌いな場所。 直に入ったことはホンの数回。 何度も何度も見たのは、ココへ用があるからと、扉の向こうへ消えて行く父の背中。 そして戻ってきたその姿が、生気を奪われたとありありとわかる様子だったことを思い出す。大事な者の生命を奪うこの国の守護魔法など、快斗にとって魔物にしか思えなかった。 無論、恩恵を受けていた過去がありそれが今に続いていること。 領地を狭めながらも平穏な日々を支える存在に感謝はある。 そう教育もされてきた。 それでも。 王子として王の姿に畏敬するよりも深い部分。ただの子供として弱っていく父親の姿を見ることが、喪うことが、何よりも怖かった。 部屋の中央―この国の中心に在る、古語数奇を孕む文字により丸く囲われた祭壇の前に立つ。 念のために、決して円陣には触れない距離を取って。 「…新一なら、読めるのかな」 永い時を経ているのに、白く石畳から浮いている太古の文字。 描かれた文字は、その一つ一つが愛するものを縛る呪と聞いていた。 「…いや、読んでた…っけ?」 幼かった友達が、大きな図面のようなモノとにらめっこしていた時期があったな、と思い出す。父親に貰った暗号なんだ、と言っていたが。そういえば、円形になって描かれていた不可思議な記号の羅列は、快斗の目の前に在るソレに似ていたような気がした。 「別にいいか、…もうすぐ消えるかもしれねーし」 ふっと歪んだ笑いと共に小さく呟いた。 快斗はいつも不思議に思っていた。 この国を作った男は一体何を考えていたのかと。 世界創世を描く御伽話は、この国では民衆の為のものではなく、王の一族にのみ受け継がれる歴とした史実。 眠りの誘いに読み説かれる「最初の王」の話は、幼子だった快斗が出会う初めての不可解だった。 それが、今になって、少しだけ理解出来て、更に不思議は深まった。 愛する魔女を封じた? 自分の子供が襲われそうだったからって? 愛執に狂った魔女が世界に仇なしても、それでも男にとってその魔女が最愛だというなら、共に逝って遣れば良かったのだ。他は何も要らないと、愛を注ぐべき分身とも言える子孫すら疎ましいと愛されていたのに。それだけ強く思われていたのなら。 もし新一が、そんな身勝手な女のようになりふり構わず求めてくれたら、快斗は一体どれほどの幸福を覚えただろうと思う。 世界全部と引き換えにしてもお前だけだ、なんて言って貰えるなら、いくらだって何だって捨ててしまえる。新一の全てと引き換えになるなら、快斗自身の命すら惜しくはないのだ。思い切り抱いて、次の瞬間に快斗の息の根が止まったって、きっと幸せなまま逝けるだろう。 新一が唯一の思いで快斗を欲してくれるということは、快斗にとってそれだけの価値がある。 眼を閉じる。 「しんいち」と唯一つの名を呟いて。 けれども、目蓋の裏に浮かんだのは。 ーくらいくらい 暗闇だけだった。 その奥から呼ぶ声を聞いた気がした。 柔らかな、声音。 おいでと手招く白い手の幻影。 快斗はハッとして眼を開いて、頭を振った。 ふらりと足を踏み入れてはならない場所にいることを忘れてしまうのは危険だ。 「…どっちかってーと、王よりも魔女側なんだろうな、俺は」 嫉妬に狂って愛すべき者に、愛するものが心寄せる大切な何かに、手を掛ける愚かな魔女を笑えない己に快斗は気づいていた。 ―だからこの場所が、嫌いなのだ。 ―とてもよく分かるから。 愛した者のほんの一欠けらでも手に入れ続けたいと望む、貪欲な想いが。 愛しいものの為に心を傾けながら、全てを手に入れられないもどかしさに愛しさと相反する憎しみが沸く。いや悲しみかもしれない。あるいは怒りのようなどうにもならない激情だ。それは凪ぐようにある愛しいと思う気持ちと全く遠い、真逆であるかのような感情なのに、当たり前の顔で胸の中に居座っている。 魔女は王が憎かったのかもしれない。 彼女のものだけになってくれない男が。 「連れてきたわ」 棺を運んできた使いの者が去って暫くして、扉が開く。 視線を扉に向ければ、白い鳥を肩に乗せ黒いローブを纏った賢なる者。 不意に、小さな生き物が羽ばたいて、祭壇の上を飛び回りだした。 「なに?…コイツはどうなるか判ってて、きたの?」 鳥の行動に驚く新一の顔を見れば、どうやらここまで引導してきたのが魔女、というよりこの小憎たらしい鳥の方なのだと判った。 鳥はクルリと部屋を一度旋回したあと、再び新一の肩に止まった。 「キッド。お前は飛んで出て行けって…」 「煙取りの蓋は閉じてるからな。出られねーよ」 それに、と快斗は続ける。 「新一としちゃ、勝手に鳥がココにきて、身を捧げてくれたほうが良いんじゃネェの?」 「ふざけるなよ!ンなことなんかしねぇし、させねーぞ」 「どうして」 「当たり前だろ?!」 可愛らしくお怒りな様子に、快斗は溜息を一つ吐いた。 「だって。言っただろ?コイツを使えば新一にかかってる変な魔法が解けるかも、って」 そうして、快斗は父との秘密ごとにしていた『計画』を語り始めた。 ―発端は数代前に遡る。 そもそもの問題は、まず王家に生まれる子孫の数が減ってきたことだった。 代替わりの時期に、王の一族間で起こる王権争いが平和な世界を乱すことはままあったのだが、紅い魔法の守護を受ける王の一族は繁栄を約束された存在であるから、絶対数が減る事は殆ど無かった。 と、いうのに。 それなのに。 いつしか儀式で必要とされる―捧ぐべき血潮はより多くと求められ、早逝する王が出るようになったのだ。 それでもまだ国内に王の血縁者は数多おり、近親血族と婚姻をなし血を濃くしてはどうかと当時の王と賢者は考え、近親婚を推奨していったのだが。―だが、これは表には出せぬ精神や身体に異常を持って生まれる一族の存在を作る結果を招くことになった。外界の医療知識を知った先々代の賢者が、血が近すぎる者同士の婚姻は危険な因子を孕む事になると知った頃には、一子生まれれば良い、ぐらいに王の一族の繁殖能力は弱まっていたのだ。 合わせて進んでいった紅い魔法の守護の弱まり。 捧げられる力の源の少なさからか、外界との境目の緩みは広がり、嵐の襲来や天候の乱れが増え、土地が痩せ始め不作の季節も訪れて―そんな状態が何年も続いている。 それでも、王として、この国の為にと捧げ続けた命の証。 けれど、以前よりも減ったあかい魔法を扱う者の出現、それどころか、別系統の魔法を持つ魔女が生れ落ちることで、この地に宿った守護が非常に頼りなくなっていると悟らざるを得なかった。 ならば、と。 快斗の父親は考えたのだろう。 「この国の守護魔法は殆ど、今は意味を為していない。せいぜい周りを迷いの森で囲んで外敵を遠ざけてる程度だ。土地は痩せて天候も外と殆ど変わらない。それどころか、半端に魔法が暴走して、魔法使いの力を奪って、…それが新一の呪いを解けないようにまでした」 「…確かに、そんな事を彼女は言っていたが」 「おかしいと思わないか?本来はこの地を守護するべき魔法が其処に住む者に牙を剥くのは」 「……魔法をかけている『彼女』に、異変がある?」 「おそらく」 紅い魔法の掛かった土地は、国の歴史書によれば肥料が不足しても多くの実りを約束していた。 けれど数代前の頃―丁度王族の数が減り始めた頃から、土地はゆっくりと痩せ始めたのだ。 魔力が薄れるにしては、その理由は見当たらない。儀式は厳格に行われていた、と史書にはある。それなのに、血を求め―更には、地の力を吸い上げだした存在。 求めは増え、土地のやせ細りは多少収まっても常なる豊穣はなく―守護の魔法が『魔』のモノに近づいたか、はたまた何か魔物がとりつきでもしたのか、と不可思議な良くない兆候をその代以降の王は気にかけ続けた。 「魔法が魔物じみたモンになって、地や人の生命まで啜るようになったら…とんでもないことになるってな。大体にして、「外」とこの地の条件が大差ないなら、守護魔法に頼る時代は終ったってことだ」 「そんな…」 「新一に掛かった『魔法』も、異変のせいでおかしくなって解けないってんなら、それ自体を消してしまえば良いんだ。この国のあかの魔法使いの力の根源は、どうやらこの国の魔法らしいからな。だから、この国にかかっている魔法を解けば―」 「んな、こと」 「じゃぁ、問題は魔法をどうやって消すか?ってことだ」 「出来るわけがない!」 「賢者の役割からすれば、出来ないじゃなくて、出来てはならない、ってところだろ。―でも」 快斗はジッと聞き耳を立てているらしい鳥を嗤う。 「魔力を打ち消すには、より強い魔力でもってなら可能かもしないってさ」 ―だから親父はずっと密かにそんな存在がないか探してた。 本当は、この国の魔法を消してしまう最期の方法はあったけれど。 出来ればソレだけはしたくないから、と。 「出来るか出来ないか、試してみようぜ?新一」 楽しげに提案する王に向かい立ち、賢者は―己が全く目の前に居る王の『賢者』として用を成していない名ばかりの存在であることを知った。 本当なら、即位した王の傍について、この国のあり方を話し合い、儀式を取り仕切らねばならない立場なのに。 寝耳に水ばかりの話に、頭が混乱をきたしている。 親父の、と始まった話ならば、新一の父親もまたそんな計画に関わっていたのだろうか。 そもそも白い鳥を、と所望した王はその鳥をどうするかについては深く語らなかった。せいぜい賢者と仲の良くない魔法使いとの間を取り持つための献上品か、単に無理難題を押し付けただけか、と新一は考えていたのだ。 守護魔法を消す為の供物などとは―いや、そんなことが出来るのか? ―いや、可能かどうかじゃない させてはいけない、と新一は思考より先にそう判断した。 この国にかかる守護魔法は、この国の為に、ずっと在るべき存在だ。 簡単に王の恣意でどうこうして良いものであるはずがない。 その、はずだ。 「例え、力を喪いつつあっても、それでも魔法によって造られた森は外敵を寄せ付けないし、国土の地力は農耕の技術で補っていけるものだろう?意味がない、なんてことは―」 「なぁ、俺、即位してから儀式をしてないんだ」 「…?! 馬鹿、な。そんなことすりゃ、『魔女』の怒り、が」 「腹が減ったって騒ぎはしてもさ、昔話にあったみてーに、逆鱗に触れたがゆえの雷鳴の鉄槌も、地中から煮えたぎった炎の井戸が噴出す、なんてことも起きやしねーんだよ」 肩を竦めてとんでもないことを言い出した『王』に、賢者は度肝を抜かれた。 先代は父と共に、月に一度この祭壇の間で儀式を行い続けていたはずだ。 必ず賢者である父親が不在になる夜。 新月の真っ暗闇の中、儀式は行われていたはず。 「親父も結構サボってたんだぜ?最期の時に白状しやがった。一体どうなるのか、どうしても知らねばならなかったってさ」 「馬鹿な。だって、そんな―親父は」 「…半分くらいは知ってたと思う。先代王のしようとしていたこと」 快斗は眼を伏せ、ごめん、と一つ謝罪を口にした。 ゆっくりとした動きで、呆然としたままでいる新一に向かって足を向ける。 「本当ならさ、新一が称号を受けたときに、儀式の事も、先代からの引継ぎも全部俺が渡さないといけなかった。でも、俺は、新一に賢者としての役割よりも…新一にかかった呪いをどうするか、新一がどうしたいか…いや俺が新一にどうして欲しいのか、を優先させたんだ」 「それ、は」 何よりもまず賢者としてすべき行いを怠って、自分ごとの為に国を出た己の責である、と新一は思った。 見た目に―それによって生じた周りの変化に振り回されてしまったのだ。 「あの時、俺は、新一が単に『賢者』としてだけ傍に居る、なんてこと耐えられそうになかった」 だから、新一がさっさと旅に出たことは、そう仕向けたのは俺のせいだから。 いっぱい、内緒にしてて、ごめんな。 いいながら、快斗が新一に近づく。 「いつか、この国を共に支えるべき王と賢者が決裂するのは、もうずっと前から決まってたんだと思う。だって、新一だって知ってただろ?王の直系の血筋がもう俺だけで、下手をすれば絶えてしまう未来(さき)がくるかもしれないって」 賢者はこの国の守り手で、それは王さまなんかより、ずっと重くその使命を請け負っていて。 「もしそうなったら、いやそうならない為に一緒に考えて、決めていくべきことを、俺は俺の望みために新一にさせなかった」 「―快斗!」 語りかけながら静かに近づいていた快斗は、じっと言葉に耳を傾けていた新一から、その肩から小さき姿の生き物に手を伸ばす。 既に警戒していたのか、小鳥は素早くその手を逃れ羽を瞬かせて飛んだ。 「ッ…話はわかったんだろ?どーにも、鳥じゃなくて白いオバケの気配がぷんぷんしてやがるもんな。なぁ、わかったなら、俺の所へこいよ。お前の身で、お前の帰る場所の悩みが晴れるんだから、安いモンじゃねぇか」 舌打ちして、もはや新一を見向きもせずまたも鋭利な刃で鳥を狙おうとする快斗に、新一は巡り回る思考を放棄し、拳を握った。 そして、それを。 すぐ近くに居るのに、決して新一を見ようとしない相手に振り上げた。 「勝手なことばっかり、言いやがって…!」 背後で気配が動いたのが分かった。 きっと鬼のような形相で快斗を睨んでいるのだろう。 そんな怒りの表情もまた、その人の美しさを引き立てているだろうけれど、眼にするのは躊躇われたから。飛ぶ鳥を追いかけるべく、祭壇前の円陣上にある煙取りのあたりを旋回する小鳥へと足をむけようとして―だが、思いのほか強い衝撃が右頬を襲い、がちっと歯をかみ締めた一瞬後には快斗は図らずも祭壇の近くまで身体を飛ばすことになった。 「! ―ってぇッ」 か弱い乙女然とした外見を裏切る力任せの仕打ち。 ピピピ…と思わぬ光景に小鳥が新一の頭上を飛ぶ。 だが、そんな事は意に介さず、新一はたった今ぶん殴った相手へと駆け寄ると、その胸倉を掴んだ。 口の中でも切ったのか、唇の端から血を滲ませた快斗が新一を見上げた。 蒼い目は険しく、寄せられた眉は端で吊り上がり、長く流れる黒髪は逆立たんばかり。 美人が怒りを露わにする姿は、なんて恐ろしくて、そして―綺麗なのだろう。迫力に気圧されながら、そんな場合でもないのに、快斗は目の前の彼女に見蕩れてしまった。 「いいか、俺は賢者だ。」 「…知ってるよ」 「この国の、お前の、賢者なんだ」 「……俺、の?」 「俺はお前と居る。お前の望む形じゃなくても、ずっと傍に。お前が嫌がろうが、何だろうが」 「…嘘だ」 「嘘なんか言うかよ。俺は、俺だって、お前が大事なんだ」 「―しんいち、でも」 「俺は、お前がいちばん大事なんだ」 「でも、それは」 快斗が新一にむけるものとは、快斗が欲しいものとは違うもの、だ。と、そう快斗は言おうとしたが、真摯な眼差しを見返すことしか出来なかった。 虚勢も偽りも全てを見破って心の奥底を暴くその眼は、同じくその眼の持ち主の真実だけを相手に訴えかけていた。 真っ直ぐだった。 何も偽らない。 快斗が欲しい想いとは違うのに、間違いなく今目の前にいる新一の思いは、ただ一人快斗だけに向けられていた。 「なんだよ…信じることに、そんなに身体が必要か?!」 「違う。だって、抱いたって…きっと新一は判ってくれても、変ってはくれない、んだ」 同じ感情でなくても、確かに想いあっている。 同じ想いで交わらないことが、苦しくて仕方ないのに。 それでも、こんなにも近く、深く、想いを捧げる人が心を向けてくれている。 「ぐちゃぐちゃ考えてもしょうがねぇ」 「新一?」 「分かったよ。いいんだ。お前が要らないなら。それが王としての言葉だっていうなら。魔法も、それが覆う国土も捨てていい。その代償は、俺も負う」 「……っ?!」 賢者の、この国の賢者としてあり得ぬ言葉に、快斗は目を見開いた。 「お前は腐っても王なんだよ。民の為にお前が、王がいるんだ。でもそれは犠牲になれ、なんて事じゃねぇ」 「でも」 「いつか決裂する?しやしねーよ。少なくとも、俺の親父はとっくに王の意思通りに動いてるんだろ?!」 「…知って、た?」 「いいや、考えたら、それしか残らなかった」 国の活気は徐々に外へ移されていたこと。 移した先に父たる賢者がいて、王の傍に居ることよりも、新たな地を拓く事に腐心していたこと。 交易が増やされ、港へ家造りの者が新たな建築術を取り入れ、新たに建つ家々が人々を迎え入れる。 まずは外への興味を持っていた冒険心の強い者、商魂逞しい者たち、土地の改良を、新たな農園を作ってみたかった者。無論、住み慣れた地を離れることに懼れもあっただろう。 しかし、それ以上に外への興味を民に持たせて、夢を見せたのだ。 もっとも、それで動いたのはほんの一握りだろう。 獰猛な野の獣や夜盗、荒れ狂う嵐から家々を守ってくれる森、豊潤と言い難くても冬を越せるくらいの実りを与えてくれるこの土地から離れたがる民は多くない。 しかし、この国は何より王の一族と共に在った国なのだ。 筆頭が動けば、結局は民も付いてくる。 国移しをするなら、快斗が動けばいいだけ。 ただ、王が動く事を許さない呪縛が掛かっているだけ。 そして、呪縛を守るのはこの国を守りたい賢者。 しかし今、賢者は呪縛を否定した。 「新一はここが好きだろう?」 「自分を育んだ場所を、大事な思い出のある場所を、嫌いになる奴なんかいるかよ」 でもさ、でも、と新一は続ける。 「でも、大事なのは場所じゃねぇ。一緒にいた奴、―ずっと一緒にいたい奴がいるかどうかだろ」 「…どうして」 何度でも言うぞ?と新一は一つ前置きをして。 「俺は、お前の賢者だ。お前の助けに為る為に在るんだ。お前は、…お前の方こそ『この国』が大事だろう?」 飄々として、国を駆け回り、厄介事を見つけては笑って大丈夫と胸を叩いて、誰かの為に心を砕いて、手を差し伸べて。憧れてやまない父である王様の真似ごとながら、懸命に、誰かを笑顔にしようとしていた。 その姿は友の誇りでもあった。 「一緒に滅んでもいいぐらい大事なら、一緒に新しい世界を作ってくほうが、いいんじゃねぇの?」 面倒だろうけど。幾らだって、手を貸す。 お前が面倒なら俺がやる。 「それじゃ、新一はずっと俺に、この国に、縛られたままだ」 「必要なら」 「本当、に?」 「ああ」 「ずっと?」 「そうだ」 「俺の傍に?」 「お前が国を背負ってる限り、な」 「…ひでぇ」 「なんだよ?王制を廃止してぇのか。だったら、俺は賢者として王の傍にいるんじゃなくて、単に黒羽快斗の親友でいるだけだろ。オメーが王様でいようが、やめようが、それは変わんねーよ」 「もっとひでぇ!」 一生オトモダチ、と。 恋愛感情を持って、こんなにも求めて言い寄っている相手に。 そう、断言してくださったのだ。この人は。 まったく笑えないのに、笑うしかなかった。 「新一」 「…なんだよ」 「愛してる」 笑顔で告げた。 ちゃんと笑えていたか全く自信はなかったが。 ―本当はとても泣きたかったから。 「お前が変わらないように、俺も、変えられない。ずっと好きだった。きっと、ずっと、好きでいる。愛してる。―それでも俺は、お前の傍に居ても、いいか?」 少し目を見開いて、けれど親友も、そっと笑った。 「そうか。居ろよ」  ×
|