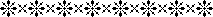 あかいまじょのはなし 時を見ていた。 移り変わる、此方を覗き込んでくる顔・貌・かお。 愛しい人の面影を探して、見えなくて。 けれど暖かな赤に潜むかの人の切れ端。 それだけを感じようと、目を閉じた。 いつしかどんな姿だったのかを忘れるほどに永い時の果て。 「おまえの欲しい相手は、とっくにこの世には居ないんだ」 捧げられるべき力の源の代わりにそんな言葉を聞いた。 そうかもしれない。 もう僅かな供物から、あの人を探すのも困難。 それでも、まだ、まだ、惹かれる何かが傍に在る。 おいで。 おいで。 共に眠りましょう。 ◆ ◆ ◆ 眠りを妨げるのは飢え。 足りない、力の源。 沢山の血潮を注がれれば、満たされて。 不安なく眠りに落ちたまま、愛した王の愛した世界の為だけに力を向けていられる。 足りなくなれば、愛を疑い、不安が目を開かせる。 開いた先に魔女を厭う者がいたら。 母なる彼女にその血をその身を捧げぬ王がいたら。 きっと魔女は怒りに失望に再び狂って世界を壊すだろう。 永い眠りの中で、たった一筋の想い。 ―宣託 古き魔女は王と、その血族と共に在る。 共に在るなら栄えよう。 滅ぶなら共に。 紅く染まった水晶を覗いていた脳裏に響いた声。 「共に在るがゆえに、王たちが消えてしまっても?」 冷えた呟きに、応える声は降りてこなかった。 「結局―早いか遅いかでしかない、の…ですか」 光の中、緑の森を駆け回る笑顔の眩しい少年の姿を思い出す。 生まれながらに地の力を受けたかのように歴代でも指折りの強い紅い魔力を見に宿した彼女は、いつも王城の隅にある塔で魔法書を読んでいた。 読み飽きて、窓から見下ろした先には、よく笑う男の子。 紅い魔法に深く関わる人間のクセに、紅い魔法に―魔性に属する彼女の妖艶な美しさに心捕らわれることのない王子様。 彼は彼の親友以外には、滅多に振り向いてくれない。 悔しくて。 でも、気になってしまって。 最初に笑いかけたのはソッチの癖に。 『お前もアイツみたいに、篭ってばっかりじゃ駄目なんだぜ?』 一度だけ、花壇の前で。 『綺麗な花はさ、ちゃんとお日様の光をいっぱい貰ってんだから』 ホラ、と。丁寧に剪定された花を一輪。 きっと彼は覚えていないだろう。 今も―枯れぬよう魔法をかけて、時に彼女の長い髪や胸元を飾るものがずっと同じ花だなんて。 王子が尊敬しているらしい賢者よりも、彼女こそがこの国の魔法の領分をよく知るのだと、声をかけたのも、気を引きたくて。 思惑は成功して。 けれど、想いは届かないまま時は過ぎた。 ◆ ◆ ◆ 「紅子、呪いの具合は?」 「仮にも、国の守護魔法を呪いなどと言うものではなくてよ」 「俺にとっちゃ、呪いでしかないだろう」 紅子と呼ばれた、現在この国で一番の力を持つという紅の魔女は、困ったものねと口だけで言いながら、困った風でもなく静かに微笑んだ。 お城の地下室。 時に魔法を厭う王の為に、儀式を監視する者として、現れる紅い魔法を統べる者―あかい魔女。 どういった基準で顕現するのか不明だったが、紅い魔法の守護を受けて―その魔力をも扱える者が、この国には生れ落ちる。 彼女もその一人。 守護を与える紅い魔法の言葉を聞いて、王に伝達する役割を負っていた。 本来なら王と賢者しか知らぬ事も、その水晶球で覗き見る必要も無く、魔力に影響される身体が勝手に教えてくれていた。 勝手に知ることだからと、勝手に王になってもいない少年にも秘密を漏らす。 「とても、弱くなっているわ…」 「へぇ」 「儀式は…滞りなく行っているのに」 「血が薄いんだろ」 「……」 「直系子孫が、もう俺一人だ」 「だから、早く―」 「断る。生まれてくる子供に、どうして生贄になれなんて言えるものか」 「賢者は許さないでしょう?」 「ああ。すっげぇ見合いの数持ってくるんだぜ?しかも、色気ねーの!この子は稀に見る兄弟が沢山いる多産家系だとか、安産型のケツが良いとか。親孝行は早く孫の顔を見せることだとか。まだ15のガキにさ」 「では、王子様はどうするつもりなのかしら。この国を」 グチグチと始まった口を遮って、魔女は問う。 「普通の国にする」 「では」 「血を啜る魔物じみた魔法に縋って生きる必要はない。今だって、備蓄のお陰で飢饉を乗り越える季節だってある。でも、民は元気に生きてるじゃねぇか。国力を上げる仕事、情勢を安定させる仕事、他国の脅威を避ける外交の仕事、俺が王になったら、何でもやってやるよ。だから、もう魔法はいらねぇ」 「本当に?」 「国を守るなら、そういう方法だっていいんだ。少なくとも、親父はそうしようとしてるんだろ。…命が保つかわかんねーけど」 小さく、苦しい声で最後に言った言葉は、一番王子が恐れていること。 敬愛する王がみまかる日がそう遠くない事は、王の傍にいる一部の者だけが気付いている。 「……賢者殿は、そのことは」 「知ってるだろうよ。でも、この国の賢者は、この国の為だけに在るようなモンだ。王の為のことは考えない。あっちこそ、紅の魔女一族だよな…血を捧げ続けろってさ」 「でも、次代の賢者は、貴方の友人でしょう?儀式を知れば、真の王の役割を知れば、貴方と同じ道を選びそうなものだけど」 「ああ。でも…もう、この国が、違う国になるって言ったら、きっとアイツは―」 王子の脳裏に浮かぶもの。 ―異国の書物を楽しそうに読んでいた友人。 いつか行ってみたいと目を輝かせて。 最近はついぞ口にすることはなくなったが、きっと本当は。 賢者を縛れるのは、魔法に守られた今のこの国。 けれど、彼は知るだろう。 この国の魔法の秘密を。魔法の力の源を。 生き血に拠って立つ国の在り様に、賢者の役割に。 きっと傷つく。そして、探すだろう、今の王や、王子が望む同じ道を。彼ならば、きっと。 だけど、だけど。 魔法をなくした国に、賢者は―彼は果たして居続けるだろうか? ソレをなくせば、これ幸いときっとどこかに行ってしまう。 そう、思う。 ―自由で探究心に満ちた、好奇心の塊のような人。 新しい事面白い事に、誰よりその青い目をキラキラと光らせて。 きれいで、だいすきな。 愛しすぎて、伝わらぬ想いがもどかしくて、それどころか、親を真似て早く他の誰かを娶れと言う姿に憎しみすらわく。 いや、無理矢理そう思って泣きたくなるのを誤魔化している。 想いのまま彷徨う視線を隠すように、目蓋をゆっくり数度瞬かせて。 王子は口を開いた。 「いいんだ、アイツは」 「誰より、次代の賢者殿にとって良くないから、貴方は魔法を捨てようとしているくせに」 「絶対に、言うな。俺が何とでもする」 硬質な声は王に近しい威厳すら含んでた。 本当によく似た親子だと、魔女は面白くて口の端を上げて笑う。 「そう…じゃあ、大変な王子さまに、一つ贈り物をしてあげてよ?」 「…やめろ、物騒だ。オメーの心遣いとか」 「あら、失礼ね。貴方が王となる時に、賢者の性が変る魔法をかけてあげる」 「はぁ?」 間の抜けた声。 久しぶりに聞いた気がする。 どんぐり眼は、可愛らしいくらいだ。 「そうすれば、妃に出来るわよ?安心して?変化は一番の得意術だから」 「…ふざけんな!」 「気に入らなければ、戻してあげるわ」 堂々と口説ける機会をあげるんじゃない。 その上で、駄目なら諦められるでしょう? からから笑う紅き魔女。 彼女は楽しいことが大好きだった。 一番楽しいと思うのは、ひとの揺れる心。 傾き揺らめく想いの天秤。 安定を欠いた姿は、目を楽しませてくれるから。 ホラ、今も。 「やめろ。アイツを変えるような真似は許さない」 「誰が変えようとしても、決して変らないのが賢者ではなくて?」 「…ったら、意味なんか―!」 丸い目は細められ険を含んで睨んでくる。 決して、彼が親友に向けるのと同じ目は向けられない。 知っていて。 解っていて。 その筈なのに、いつも苦しい。 だから、コレは意地悪だ。 彼も同じくもっと揺らいでしまえばいい。 決して本当にかれにとって悪いだけの話でもないのだから。 「意味を成すも為さぬも、貴方次第ではなくて?」 「やめろ。タチの悪ィ讒言ばっか吐きやがって」 「耳を貸さなくても、したいように、するわ。私は魔女だもの」 「やめろ…許さない」 そう言いながら、彼の瞳に波のように浮かんでは消える相反する心。 期待と怒り。 歓迎と拒絶。 希望と…絶望。 「王と王子次第では、魔女ではいられないかもしれないじゃない。私も無欲ではないもの。力のあるうちに、見たいものが沢山あるわ」 「徒に使うもんじゃねぇだろう」 「私の力を私の為に使うことに、一体何の憚りが要るのかしら」 叶いそうにない想いの前で揺らぐ王子を笑う。 叶うはずもない想いの前で虚勢を繕う己を嗤う。 ―数年後 そうして、王が倒れ、祭壇にその身が捧げられる時が訪れる。 紅の魔力が最も強くなるとき。 それは魔力の根源とも言える、王の身を灰まで喰らった魔石が力を溢れさせるのだ。 祭壇に王の棺が入っていくのを待って、その刻限に魔女は約束どおりに、賢者に魔法をかけた。 けれど。 「どうして・・・・!」 脳裏に火が見えた。 だから、チカラの増幅を感じなくとも、すぐに事は成せると思った。 増幅が無くとも、己の魔力だけでも完全だと思った。 それなのに。 大地を通して、逆に奪われていった魔力。 ―食われた おそらく、この国に在る紅魔法を持つ者が一様にその感覚に襲われただろう。 そして、急激に抜けていく魔力。―生命力。 「なんてこと!」 遊んでいる場合ではなかった。 「賢者は何をしているの!?」 いそぎ、お城の秘された祭壇に続く回廊を走る。 先ほどまで覗いていた水晶球の向こうで、罠に掛かった少年が魔法陣の中で衝撃に倒れ身体を震わせていたが、そんなことには構っていられなかった。 ・・・ギィィ 祭壇のある部屋の扉を開く。 目に映ったのは、祭壇の前で燃える棺。 祭壇の真上で為されなければならない儀式は―儀式として成立していなかった。 上手く、外へ向かって逃げない煙が部屋をけぶらせている。 広い部屋。 中央へ向かって天井の板は斜めに高く高く三角錐のような頂点を伸ばして、供物から溢れる血潮の匂いや煙を外へ逃がすようになっている。 部屋の中は何も置いていない。 あるのは、石床に描かれた円状の囲い。 魔力を音ならぬ言語で綴った、魔力そのもののような強大なかの女性を封じた円陣。 簡素な、冷たい石造りの祭壇。 しかし其処こそが、この国の中心だった。 「何てことを―」 ほしいほしい、と駄々をこねるような悲鳴。 求める意思は確かにずっと魔女に聞こえていた。 けれど、ここまで飢えていたとは。 求める力の源が傍にあるのに、それが遠ざかっていく気配に苛立って、矢鱈に地を伝って吸収する魔法を使ったのだ。 どんなに彼らにとって魔物じみていても。 『彼女』はいまだ意思を失っていない魔法。 「…ここに飛び込んでくるって事は―」 「ええ。紅の魔法は、地力と人の中の魔力を奪っているわ…!どうして、貴方という方がいながら…っ」 「つまり、王の身でもなくてもいいのかい?『彼女』にとっては」 魔女の震える声を遮った乾いた声。 冷徹な眼差しが、鋭く魔女の身を刺す。 「他の誰かの血でも良いなら、私が捧げるよ」 魔女は首を横に振った。 「いいえ、駄目よ。奪われたのは魔力だもの。たしかにソレは生命力に準じる。でも足りないわ。私は―魔力を宿す者は、地を通じて力を分け与えられただけだもの。この国全部の魔法使いの身を捧げたって、王の一滴には敵わない。まして、王でないものの血潮なんて、『彼女』は受け取らない」 知っていたはずでしょう?! 魔女の叫びを、賢者はただ聞いていた。 「…知っていたよ」 ややあって、ぽつりと落ちる言葉。 「でも、叶えてやりたかったものでね。…彼は友人だったから」 「貴方がたが何を図ったかは、…いいわ。それよりも、私が受けている力の搾取を止めさせます。退いてくださいな」 賢者は何も言わず、煙を上げる棺へ向き直った。 魔女も何も言わず、彼女の出来る事に集中した。 円陣を円陣で囲う。 魔女の中には生まれたての赤子だっている。 命を源泉とした魔力を、無抵抗に奪われるままになっていたら、時を待たず命に関わることになるだろう。 早く、止めなければいけなかった。 それなのに。 「駄目…」 「足りない…!」 呻く。 泣いて、地団駄を踏みたい気持ちだった。 震える手で胸元を押さえる。 指が飾られていた赤い花に触れて、花びらがはらりと落ちた。 ―外へ、奔放に外の魔力を吸収しようとする力は抑えた…でも けれど、円陣の中で飢え、不穏な気配を醸し出した『彼女』を抑える力など、魔女は持たなかった。いや、殆ど魔力といえるモノすら残っていない。 抑えるられるのは、王の一族だけ。 「どうしよう―!」 「…こうするんだろう?」 思わず顔を覆った魔女に、静かな声。 見れば、賢者は、炎の収まらぬ棺に手を掛けていた。 「!」 「すまない、な」 棺にだけ向かっての、謝罪が賢者の口から零れる。 そして、棺の中に手を突っ込んだ。 絡みつく炎にも、手を焼く熱さにも興味が無いように。 淡々と。 炭化したばかりのソレを取り出すと、円陣の中央に向かって投げ入れた。 「受け取れ―」 ◆ ◆ ◆ 「―それは、どういうことだ?」 ごめんなさい 失敗 したわ 告げるのに勇気が要った。 素直な謝罪を述べるなど一体いつぶりだろう。 詰られるか、怒られるか、いやそれだけならマシだ。 軽蔑されるだろう、と恐れた。 魔女は初めて、取り返しの付かぬ失敗に―断罪に怯えた。 「賢者の変化を解くことは出来ないの。出来るとすれば、それは」 不完全に掛かってしまった魔法。 解くべき魔女が魔力を喪い、解ける者は無くなった。 けれど、そも不完全になったのは、この国の魔法が揺らいだからだ。だとすれば、残った方法は。 方法とは。 「紅い魔法を―『彼女』を、永久に眠らせる」 「それは、つまり」 「この国を、終らせることよ」 「…なんだよ」 そんなことか、と王子は息を吐いた。 そもそも、彼や彼の父親が考えていた事だ。 「大変な事よ。大体そんな事―」 「王なら出来る。多分な。俺はそう聞いてる。方法が無けりゃ、親父だってやろうとしなかったさ」 「!」 「あ、これ以上は言えねー。つーか、それより失敗って」 その時、王子の部屋の扉が叩かれた。 「多分、『彼女』よ。」 「?侍女なら来ねーはずだけど」 「私は狭間に戻るわ」 「魔法使いって変なトコにいるよな。…覗きは大概にしろよ」 「残った力なんて、かくれんぼにしか使えないわ」 再び、強くノック音。 王子が入室を許す前に、扉が開く。 乱暴な闖入者を見た王子の眼もまた大きく開いた。 そして姿を消しかけていた魔女は、王子が『彼女』に向ける眼差しに、激しく揺れる想いの波を見た。 揺れ動く心の天秤。 傾いた器から、溢れ落ちる想い。 両端を支える箍が外れれば、比重のまま傾いて。 けれど本当は。 心の箍は、バランスを取るためではなく。 溢れる気持ちを、決壊寸前の想いを、ただただ封じていただけなのだとしたら。 王子様から貰った赤い花を、枯らしてしまった魔女の話。  ×
|