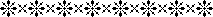 かれらのはなし#1 ぽたり ぽたり 末端の表層を傷つけただけだろうが出血は多く、小さい純白から赤い血潮が垂れていくのはそれだけで命を流しているようで、見ていて心肝震える光景だった。 ―その本当の姿を知る新一にとって。 だが、快斗は意に介さず、何もない空間に向けて王たる声を放った。 「おい、あかこ?いるんだろう―…『来い』」 呼びかけに応じて、ぶわりと空間の一部が歪んで、ひとりの魔女が姿を顕す。 「『呼ぶ』なんて、珍しいこと」 「聞こえてて何よりだ。かくれんぼしたまんまかと思ってた」 皮肉るでもなく言われ、僅少なる魔力しか持たぬ魔女は肩を竦めて王を見遣る。 「…何の用で呼んだのかしら?」 「コレ、をどう視る?」 「……まぁ」 口元に手を宛て眉を顰めながらも、コレと示されたモノをじぃっと観察した魔女は、ややあって目を瞬かせた。 「ヘンな鳥だこと」 「稀有なる鳥ってのか?」 「…かもしれないわ。…駄目ね、呼応すべき力がないから、なんとなく感じる程度…でも―」 「試してみるか」 目を細め薄く笑う男の姿に、魔女は眉を顰める。 それから、この場にいるもう一人の存在に一瞬だけ視線を向けた。 「彼女はソレを返して欲しいようだけれど」 「まさか!うまく行けば、元に戻れるのに?」 酷薄に笑う男は、そう言いながら決して彼女を見ない。 不自然な態度。 あれほど彼女に求愛をしていた人間の、あからさまな―。 では何を見ているか、と言えば、赤く羽を染めた鳥だ。明らかな憎悪を含んで視線で射殺すように。 「…今すぐ祭壇へ。この贄を捧げてみたい」 「―今すぐ?!」 「ああ。夜になる前がいい」 「無茶を言うわ。捧ぐ…って、貴方ではないそんなモノを捧げるなら、…楡の木で棺を作って目隠しをしないと、『彼女』は受け取らないのではいかしら。まぁ、どうしてもというなら、急いで持ってくるよう水晶から伝えてはみるけれど」 「そうか」 「快斗!!」 勝手に何がしかの話を進めようとする王と魔女に、身体と言葉を硬直させていた新一が慌てて割って入ろうとするが、快斗は完全に新一の存在を黙殺する。王にしか従わない魔女は、王の態度に不審さを、その手にしている生き物に興味を抱きながらも、王の会話に合わせて新一へはあえて意識を向けない。 「そいつを放せ、手当てをする」 「…邪魔されんのは困るから―あかこ、この部屋を禁じて、コイツ監視しながら用意をしてくれ。それぐらいは出来るだろ?」 「快斗、放せって!」 「……私が?」 「別に部屋の鍵はあるし、簡単にゃ出られねーしな。念のためだ」 「快斗!」 「新一、話なら後で祭壇で聞いてやるよ。それまでご自慢のアタマ使って考えていてくれ」 「…ンッだと」 「コイツを使えば、お前は元の姿に戻れる―多分、な」 そう言い置いて、快斗は部屋の扉に向かう。 新一は瞬間的に行かせてはいけない、と手を伸ばした。 「快斗!―キッド!」 快斗が手を跳ね除けようとした一瞬、くたりとしていた鳥が、ぶわりと姿形を変化させた。空間を歪ませるように、白い全身が震えぐわんと大きくなり、羽根が舞う。人の手ではその大きさは掴みきれず拘束が解け―その隙を逃さずに鳥は再び小さくなると、翼を使い新一の元へと駆けた。 「…そう。だったら、迎えが来るまでそこに居ればいい」 ぎゅうと服が赤く汚れるのも構わずに鳥を抱きしめる新一を一瞬だけ見て、眼を逸らし。 ―快斗は部屋を出て行った。 部屋から出ようとしたがガッチリと再度鍵が掛けられていて、扉は開かなくなっていた。 何度か扉を叩き―駄目か、と悟った新一は、ギリっと部屋に増えた存在を睨んだ。 「どういうことだ。アイツは、快斗は何を考えている」 「私が貴女の問いかけに答える義務があって?」 「あるだろ。…俺をハメたのは、お前、だ」 ジッと見つめる青い瞳に魔女は気圧される。 真実を見抜く、強き鋭い賢者の眼を欺くのは容易ではない。 『彼』であった『彼女』を直接見ることは、魔女の複雑な感情を―非常に複雑に刺激した。だが皮肉げな微笑を浮かべるに留めて、魔女は全く厄介な役割を押し付けてくれた男にその胸のうちだけで舌打ちし、それから苦々しく重い口を開いた。 「新しき賢者は、この国の魔法が現在どんな状態にあるのか、ご存知?」 ◆ ◆ ◆ 鋭利な刃物で切られた傷は、始め痛みよりも熱さを感じる焼けるような感覚だったが、新一が寝台の布を裂いて手当てをしてくれると、幾分かマシな状態になった。そして何より、美しい指先が傷口を労わるようになぞって身体を撫でてくれれば、幸福感が身体を満たし、痛みなど簡単に忘れる事ができた。 野生の力と、生きるものの本来の力を助けるという青い魔女がくれた魔石の効果もあるのか、実際傷はみるみる塞がっていっているようで、流れていた血潮が、受けた痛みからすれば拍子抜けするほど早く止まった。 新一がくれる一撫でごとに楽になった、とキッドには思えた。 キッドにとって、やはりこの人の存在は特別なのだと深く感じずにはいられない。 そして、考える。 幸せになって欲しいこの人にとって、己がしてやれることは一体なんであるかと。 魔女たちは言った。 『あかい魔法がかかっているの』 『貴女の身体にかかったのは不完全なあかい魔法なのよ』 『―・国では、紅い魔法以外は、うまく力を揮えないの。だから、あおこ―』 『飢え、揺らいでいる古き魔法が、暴走し、貴女をその姿にした。もはや呪いをかけた私の手には負えない』 そして、王の言葉。 『稀有なる力』 『魔力を帯びて―新一に掛かった魔法にも対抗できる力を秘めた特異なる白い鳥』 果たして己はそんな存在なのだろうか。 確かに昼の間完全に人の意識を闇に消してしまう、強い呪いなのだろう。森で出会った青い魔法使いも、完全な半変化なんて―と少々驚いていた。 キッドとて、呪いを受けた当時は一体我が身に何が起こっているのか正しく認識できなかった。夜に目覚めて、ぐちゃぐちゃになった部屋の中で何度もつまずいた。大量の大きな羽根が散らばって、ソレが昼の間の己が撒き散らしたものだと知ったのは、魔術を求めた奇術師にいい事を教えてやるよ、と与太話のような秘宝の在り処を洩らした旅芸人が、「お前は呪われて鳥の化け物になったんだ!」と叫んだからだった。 強い呪い―魔法。 他者に寄生し乗っ取って大空を舞う怪鳥は、ただ生きていたい、のか。飛んでいたい、のか。 種の違う奇異な存在を封じたあの洸玉は、一体どこの魔法使いが作ったものなのだろう。何の文献もなく言い伝えのような秘宝の存在の真相を知る者はいない。与太話から真実が出たと知った旅芸人は、祟りだ、呪いだと言って何処かに逃げてしまった。 キッドは、魔術を得るための秘宝欲しさに、秘宝があると噂される屋敷に忍び込んだり、時に怪盗と名乗り類似の宝石を盗んだこともある。役に立たない偽の秘石は丁重に返却していたが、他者を傷つける行為だったのは確かだ。それらの報いで呪われたのか、と―己の強欲への戒めなのだと、そう思ったこともある。 呪いに取り付かれたあの時。 しかしソレは同時に奇異なる魔法生物の持つ強さも取り込むことだったのか、キッドは怪我をしても長く苦しい思いをしたことは無かった。 ―いや、それだけか? 意識を向け羽根を『視る』。 傷つけられた部分の肉が早くも盛り上がりうっすらと皮膚が再生し始めている。 いくら何でも、傷の治りが異様に早い。 森で魔女の守護を受けた時も、矢を射掛けられた傷があったが、あの時は薬草で手当てもしてもらっていたのに―さっき受けた傷よりも掠っただけの擦り傷だったのに、こんなに早くは治らなかった。 この国に入ったら、あかい魔法があるから、青き魔女の守護が暴走するか効かなくなるかもしれないわ、と言っていたが、実際はそんな事は起こっていない。 ―弱っているこの国の守護魔法…それを、強大らしい別の魔法で… 打ち消すというのか。 手段は非常に荒っぽく思えるが、可能なのかもしれない。 しかし、そんな事を一国の国の主がしていいものなのだろうか。 土地にかかる魔法が暴走すれば、その上に暮らす民とて何らかの影響だって受けるかもしれないのに。 勝手な男だ―キッドは苦々しく、己に似た顔をした男を思い出す。 あの手がこの大切な人に触れていたのか、と思うと苛立ちと嫌悪が募った。 ピュイィ…と鳴いて、撫ぜてくれる手に頭を寄せた。 「ん?少しは楽になったか」 羽根から小さな頭を今度は撫でてくれる。向けられる青い瞳はとても優しくて…哀しい色をしているようにキッドには見えた。 ―この人の為に、できること…は 呪われながらも、美しい人―同時に、面白い子供。 キッドとしてはどちらも好きだし、勿体ないと思ってしまう。 けれど賢者の望みは元の姿に戻る事であったはずだ。そうすれば、あの王も昔のように友達に戻ってくれるのではないかと僅かな希望を捨て切れなくて。 賢者を元に戻すには、もはや魔女ではなく国の魔法ごと呪縛から解放しなければならないという。 そのための力が、この呪われた身にあるのだというなら。 ―モノクルを、取ってもらえば… そうすれば、人の意識は途切れるだろう。 かつてのように。 朝日を見て、コレが命の終わりに見る最後の朝焼けになるのかと、ぼんやりと思っていた時と同じに。 恐怖が無いわけではない…擦り切れてしまってはいても。 キッドとて生きているのだ。生存本能とは、生きている以上決して消え去ることのない根源的な生きていたい、という欲求なのだから。それは鳥の身に変わっても同じだろう。 むしろ必死に死へ抵抗する野生を押さえつける人の理性が必要になるかもしれない。だが。 ―きっと、泣いてしまう。…最期の時にそれは見るのは、嫌ですね その時が来たら、彼らの手に任せてしまうか、とキッドは思った。 じぃっと水晶玉を見つめている魔女に向かってキッドは嘶く。魔女、というのであれば、もしかしたら意思が通じるのかと考えた。 果たして考えは誤っておらず、魔女はキッドの言葉を新一に伝えたのだった。 ◆ ◆ ◆ 「この飾りを外しておあげなさい」 「…なに、何で」 「補助魔法ね。鳥の身でも人の意識を保つための…ご存じなかった?」 「いや、一応聞いてはいるが」 「ならば判るでしょう。…人の意識のまま供物になるのは残酷なのではなくて?」 「?!ッざけんな、させねぇ!」 ぎゅうと新一は胸に小さな白を掻き抱く。 柔らかな谷間に埋もれそうになりながら、鳥はピィピィと鳴いた。 「まぁ…随分余裕があるわね、命が危ういって時に」 「は?」 「貴女の胸の感触が大層素晴しいそうよ?」 ―?!言ってないです!ただ、苦しいと、飾りの位置を確認して欲しいと…! 「水晶球を通せば、その小鳥が青年なのはわかるわ。…その姿の賢者殿の肉体は刺激が強いそうよ?」 両手で妙な光をうねらせている水晶を支えて、魔女はそう嘯いてふふふと笑った。 新一はぎゅむっと鳥を両手で掴んで、目の前まで持ち上げ、胡乱な視線を投げた。 「嘘だろ…?」 ―キュイキュイ…ピピィ (魔女殿の嘘ですったら!) 「…ああ、コレか」 焦り身を震わせるキッドに向けた疑いの眼など直ぐに緩め―そして、羽毛に埋もれている飾り物に触れた。 「取ったら、勝手に逃げるかな…」 本来の姿は怪鳥ともいえる大きさだ。鉄格子を破る事はできるだろうか。 ―ピピ…(「?!」) ―ああ、そうだった。この子は、きっと喪われる命を見過ごせない 新一の呟きと動きに、キッドは慌てて、高い窓辺に飛ぶ。 人の意識を喪った己が、まかり間違ってこの人の傍を離れることは避けたかった。 「…身体をもっと小さくして、そこから出られないか?」 「勝手をしないで下さる?出しませんわよ―」 ―ピィピピ… キッドは、再び自分達を閉じ込めた相手が来るまで、彼らの頭上を飛び、手の届かない場所で羽根を休めることを繰り返したのだった。 ―一体どのくらいの時間が経過したのか。 儀式には手間が掛かるのか、監視役といわれた魔女は時折姿を消して何やら仕事をしているようだった。水晶球を見て、呪文を唱え―時折悔しげに唇を噛んでは、『逃げたら許さないわよ』と言って部屋の鍵を確認して任された場を離れる。 新一はどうしたことか手元に下りてこない小鳥と共にその様子を窺っていた。 しかし、昨夜殆ど寝ていなかったせいか、いつしか寝台の片隅でウトウトと船を漕ぎ出して―ハッと覚醒したのは、頭にバサリと何かを掛けられたからだった。 「…んだ?」 「着替えなさい」 唐突に言われ、新一は「?」を浮かべて魔女を見る。 頭に乗っていたのは黒い―魔法使いが良く着ているゆったりとしたローブ。 「血がついているわ。不浄なままで祭壇への回廊を歩かせるわけにはいかないの」 「―!キッド!?」 「……」 慌てて小さな小鳥を探す。魔女が無言で新一の手元を見た―もぞもぞ動くローブに驚いて眼を見開くと、ローブの隙間から白い羽。ぴょこりと顕れた姿に新一はホッと息を吐いた。 それから、天窓をみやる。 昼は疾うに過ぎたのか。それでもまだ日は高いようだった。 軽く空腹を覚え、そう監視役に訴えると、心底呆れた視線が向けられた。 こめかみをグリグリと指で押す魔女は軽い頭痛を覚えているようだった。 「…中身は全く、あの工藤新一、なのね。たおやかな形(なり)をしているクセに、こんなところで寝こけるわ、お腹がすいただの…!」 「残念ながらな、俺は俺なんでな」 魔法なんかで変えられるわけねーだろ、と尊大な物言い。 魔女はふるふると肩を振るわせた後―大きく肩を落として、「いいわ、簡単な食事を持ってくるから着替えていて!」と言うしかなかった。 魔女が部屋を出た後、新一は往生際悪く部屋の鍵をいじくりながら、キッドである小鳥に言葉を投げる。 「チッ、やっぱ開かねーか…。あ、おいキッド、大きくなれればでられないか?なぁ…。とりあえず、オメーは逃げろよ」 ピィピ…ピピピ 「だーから、下手にオメーが捕まったら困るんだ。アイツの様子じゃ命ごとあぶねーっぽいし。逃げろよ」 ピピッ― 「つつくな!あ、とりあえず着替えしねーと…」 賢者にモノ言いたげな小鳥の行動は、要するに新一が一緒でければ出るのは嫌だと言っているんだろうと察しがついたが、新一としてもこのままこの相手を命の危険に晒すのは嫌だった。 果たして部屋から回廊の間に逃がす事ができるか。 賢者として日の浅い新一は、まだ祭壇の間には殆ど入ったことが無かった。一度称号を受けるときに入りはしたが、祭壇の間には煙取りの空気口があるだけだったし、天井高い回廊に窓があるのかまでは覚えていなかったのだ。 しかもあの時は、父親である賢者がごく簡単に部屋の間取りと国にかかっている『魔法』の説明をほとんど御伽噺の内容程度にしただけだった。無論賢者として知るべき歴史的史実事は知っていた。だが、代替わりごとに、その代の王と賢者にしか分からぬことがその祭壇の前で行われてきたから、と。 あとは直接王に聞くように、と言われてそれまでだったのだ。 (あの回廊は明るかった…いや、でもあの時の時刻は…) 回廊には淡い光が上から注いでいたが、もしかしたら外の光ではなくて魔法の灯りかもしれない。 祭壇の間は王と紅い魔法の為の空間だ。 そのテリトリーに入る前にキッドを逃がしてしまいたかった。 しかし、現状では手が無いとみて、新一は赤い染みが茶褐色に変色しつつある服を脱ごうとした。 「…見てるのか?」 ふと、近くの燭台を止まり木にしていた小鳥が視界に入り、思わず聞いていた。 見られて困る事はないが、大抵この姿で肌を露にしたりすると色黒の友人を筆頭に同性(見た目は異性)は大慌てで視線を逸らしたり、無防備さを怒鳴りつけたりするものだったから、首をチョコチョコ曲げながらもジッとしている小鳥に、何だか居た堪れなさを感じる。 「おい?」 揶揄を含んだ魔女の言葉が思い出され、新一は再び胡乱な目つきでくりくりと小首を動かしている―妙にかわいこぶって何故か鳴くのもやめた小動物に、寝台のシーツを被せたのだった。  ×
|