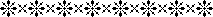 けんじゃのはなし 良き友よ。 生まれながらに祝福と死を約束されし君よ。 王城の一番高い部屋。 この国で最も高貴なる者が住む部屋。 天蓋のついたベッドに横たわる者は、今まさに息絶えようとしていた。 彼の息子を、次代の王たる王子を部屋に導かねばならないと思いつつも、これが最期ならばと、賢者は言いたい事をいってやろうと口を開いた。 「馬鹿野郎」 「……誹りは墓まで待ってくれ、いやせめて祭壇まで。逝く時くらい、優しくできないのかお前は」 「その分、お前の息子に優しくしてやろう。嬉しいだろう?有難いだろう?」 「涙がでそうなほどだよ、我が友。…ありがとう」 「…快斗くんを呼ぶ。泣くのは止めて置け」 もっと言いたい事があったと思う。 しかし、それ以上は言葉になりそうもなく、賢者は王子を呼ぶべく王に背を向けた。 部屋から出る数歩の間で滲む視界を正さねばならない。 なぜ、もっと早く言ってくれなかった? いくらだって、手伝ったのに。 胸を衝く痛み。 しかし、賢者は何に対する後悔かをよく解っていた。 彼は賢者に手伝わせていた。 ただ真実を隠して。 それと気付かせないように。 ―気付けたのに見逃したのは、賢者のほうだった。 それこそが後悔。 (国の為に賢者たるお前はいるんだろう?) 馬鹿な事を。 この国とは、お前のことだ。 お前以上に大事にすべきものなどないのだ。 この国の賢者は、いつも。いつの時代でも。 最も大切なことを、最も大切な相手に伝えない愚か者のことなのだ。 ◆ ◆ ◆ 「盗一、また病休か?」 「おや、これは賢者殿。病欠届けは要りますかな?」 「あまり、国を空けるものじゃない。新月の儀式までサボってからに」 面白がる目をしながら、咎める口調で、口元は苦々しく笑う、という器用な真似をする賢者を見て、王は笑った。 「なかなか見つからなくてね」 「彼女が育つまで待てないのかい」 「…彼女は、快斗の友だちだよ」 「言っておくが、魔力のことだぞ」 「…長い。私が保たない」 「…前王の身を全て捧げたのに…?」 「足りないのだろう。快斗まで、すぐだ」 「何故」 賢者には疑問があった。 歴代の王は長命のはずなのだ。 彼は―いや、彼とその先代ぐらいだ、こんなに早く身を患うなど。 この国の守護は、最も王とその一族を大切に守るはず。 「君は、誰よりも守護を受けるべき人間だ。多少儀式をすっぽかしても、曲がりなりにも王だろう?だいたい王子の頃に持病があったわけじゃない。一体何の病だい。それに、君の探し物は―」 慮る視線の中に猜疑を含める賢者を見て、その心うちを推察しながらも、王は静かに彼の意思のみを口にする。 「私は伴侶を喪ったときに決めたのだよ。それまでおかしいと思いながら、抵抗をしなかった己を責めたよ。私の父も苦しんだ。私もだ。せめて息子は苦しむのではなく、笑って出来る苦労を背負う者であって欲しい」 「それが、この地以外に新たな国の礎となる場所を作ることか?」 「魔力が弱まり森が拓かれていけば、国を守る地の利も弱体化するだろう?もともとこの国はそうやって小さくなっていった国だ。小さな領土にしがみついて外に怯えるよりも、人の力で今度は新たに国を広げていく、そういう時期が来たんだよ」 「…それは、新たな魔力を求める理由にはならないだろう」 「さぁて」 にやりと歪む目と口元。 考えるのは賢者(きみ)の仕事だ。 と、それは告げる。 賢者は、その深い知識と今の国の状態から、推論を披露する。 「ふむ…あの子の魔力を不思議がった時、お前が言っただろう」 『外敵内包か自浄作用か』 (己にとっての脅威を、自ら作り出したのが彼女なのか―それとも) (大地に巣食う紅い魔力の呪縛を排除するための自浄作用の顕れが彼女なのか…) (しかし、どちらにしても) 「この国の終焉が近い、と」 「そして」 「お前は、…お前が、ソレを為そうとしている」 「だから?」 「だから」 「終焉を早める為の、魔力を探している。この国の魔法にぶつけて、壊してしまえるくらいの」 笑みは更に深く刻まれ、賢者に向けられた。 ◆ ◆ ◆ 『快斗に伝えておくれ』 「快斗くん」 『紅の魔力は削いだ。あとはお前だけ』 「君は、君の父親がしようとしていたことを知っているかい?」 『探すべきモノはあと少し。けれど、探さなくても、賢者が示唆をくれるだろろう、と』 「知っているんだね。―君は、どうしたい?」 『お前は縛られなくて良い』 「私は君の味方になるよ。君の父親との約束だ」 『望む未来に進め、とね』 「王の役目を知っていても。…それでも、この国の王になるかい?」 今度こそ、後悔などしないために。 ◆ ◆ ◆ 「それじゃ、行って来るよ」 「海風は老体にゃ厳しいから、気をつけろよ」 「ははは!勝手に老人にしないでくれるかな?これでもダンディな小父様とお城じゃ人気なんだぞ」 笑いながら、姿の変ってしまった息子―今は娘の姿になっている我が子を見た。 一体どこの美姫だと、見るたびにハッとさせられる。 性差による体つきや顔つきの変化が、父親似だった子どもを母親寄りに似て見せているせいか。若かりし頃の愛する妻を彷彿とさせる。いや、今とて妻は可愛らしく美しいが。 置いていくのはかなり心配だ。 それは、もう。 しかし、己が国を離れるのに併せてこの子も『賢者』となるのだし、先だって即位したこの国の最高権力者―この子の親友が求婚したというのだから、滅多な虫は近寄ってこれないだろう。 「お前こそ、今の自分の状態をよく弁えて行動しなさい」 「わーってる」 「そうかい?まぁ、私としては花嫁の父親として呼ばれても仕方ないと思っているよ」 「は、な…って!誰が呼ぶか!つぅか誰がなるか!!」 「…新一」 求婚自体は真剣らしいが、それについては本人同士で解決する問題だろう。 父親としては些か複雑だが。 我が子が幼い頃には、子供達の前で教鞭を執ったこともある。 彼の子どもは賢者の言葉を注意深く聞いて隙あらば論戦を仕掛けるような子。対して、王子は非常に頭がよく、一を聞いて十を知るような吸収の早さを見せたが、一を聞いて十確かめ百を知ろうとするこの子とは違い、さっさと必要な事を覚えたら寝てしまうか、講義に飽きた他の子と遊びだすか、別の思考を始めるような子。 手に手を取ってその二人が遊びに出れば、最初にリードをとるのは王子で、けれど知識量や曲がりなりにも『賢者の子』としてのプライドがあったらしいこの子が、しっかりと手綱を取っていた。 撒かれた王子の従者が嘆いても、居なくなった!と騒ぐ彼らの友だちがいても、一人ではなく二人なら大丈夫だろうと笑ってやったこともある。 王子の父親が、頑なに二人目の妻を迎えないでいるから、父親への当てつけも兼ねて王子に見合いの話を持っていけば、困惑し、時に怒りを抑えて、何かを堪えて首を横に振っていた。 知っていた。 何かを言いたげに、賢者であり同時にこの子の父親である己を見ていた、あの子。 きっと息子がこんな姿にならなければ。 きっと彼は一生その望みを口にしなかっただろう。 どんな結果を二人が出したとしても、選ぶ答えが正しくなくとも。 「父さん?何だよ」 呼びかけておいて言葉を止めた父親を、首を傾げて伺う少女。 大変に可愛らしくて、少し頭痛がする。 「…迷った時はな、新一。お前にとって常に最良の答えを選びなさい。最悪を避ける為の最善でもなく、その場における最高でなくてもいい。お前が考え、それが良い、と納得できる答えを出せばいい」 「…なんだよ」 揶揄する声音を一転させて、ひたりと見据える『賢者』としての父親。 飄々とした態度の消えた姿は、見慣れていてもいつも気圧されてしまう。 しかし同じく賢者たる称号を受ける者は居住まいを正し、真っ直ぐに怜悧な眼を受けた。 「賢者とは何のために有る?」 「この国の平和と繁栄の為」 「では、この国とは」 「始祖なる王とその一族を愛し、共に歩む民すべて」 問答は定型文をなぞるように。 「…そうだね。賢者としては、まぁまぁかな」 どういう意味だと問う視線には答えずに。 仮にも彼とて賢者を名乗るのだから。 考えて、考えて。ひたすらに考えれば良い。 「有希子も待っているし、行ってくるよ」 この国に居ては出来ない仕事をしなければならない。 彼が仕えた王も、その跡を継いだ王もまたそれを望んだ。 ◆ ◆ ◆ 二週の時が経ったころ、国の留守を任されたもう一人の賢者―息子から手紙が来た。 元の姿に戻る為の何かを求めて国を空けると言う。 滅多に父親に頼ろうとしない彼からの手紙には、端的に旅の目的と―決意と、そして最後に『快斗を頼む』とあった。 しかし、直ぐに国に戻る気にはなれず、王からの手紙を待った。 賢者を動かせるのは、唯一人。 だが、親友の息子からは何の便りもなく、それを賢者は彼からの答えとした。 友によく似た男なのだろう。 強靭なる意志で立つ王に余計な口を出す暇があるなら、賢者は己の為すべき事をすべきなのだ、と。 そして、それから数巡りの時が経ち―国を離れ暮らす賢者の下に届けられた王からの手紙は、息子として育ててきた我が子を正妃に迎えたいという旨の王印がつけられた正式文書だった。 旅路の失敗や、その手紙が辿り付くまでの経緯には大層興味を引かれたが、しかし賢者はやはり彼の仕事を優先し、適当な返書で済ませたのだった。 人として 賢者として 親として ―友として 為すべき事を為さねばならない賢者の話。  ×
|