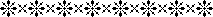 おうさまのはなし#1 生れ落ちた瞬間に、歩むべき道も、生の先の死の在り処も定められていることを、一体どう感じ受け容れていったのか。 あれこそが、という出来事は実はほとんど記憶に無い。 ただ、いつも目の前に在った父の背中を追っている内に、静かに自覚を促され、在るべき姿を幼いながらに写し取りながら、次第に己の存在の特異さを自覚しながらも、驕る事なく己を律する事を覚えていったのだ。 『王子様』 『王様』 そう呼んでくる人間の眼は憧憬と敬意とを混じらせた温かい眼をしていた。中には、隠しきれていない不遜な光を湛えたり、羨望と嫉妬を入り混じらせた眼をした者もいたけれど。 他者が己に向けてくるそういった視線は、生まれながらの地位を持った自身の在り方のひとつの指針となった。 ―けれども、本当に気にしていたのはたった一人の眼だけだった。 そうでなくては、こんな今があるはずがない。 たった一人。 そのヒトを獲得するために、この国全てを引き換えにしようとしているのだから。 日暮れ。 一日の最後に、燃え尽きるかのように真っ赤に山の端を赤く焼いて、その姿を眺める者をも赤く照らす。 「新一」 「…何だ」 「こっち見て」 近くにいるのに、己を見てくれない相手に焦れてそうせがめば、漸くに青い瞳に映ることが出来た。赤く染まった己に比べて、彼の清冽な青さはそのまま、快斗を見返す。 「…なんだよ」 しかし、それだけだ。 青い瞳はただ目の前の己を映すだけで、何の感情もそこには無い。 あえて言うなら、鬱陶しいとか、多分、そんな程度。 でも構わない、と快斗は思った。 それでいい、同じ想いを返されなくても、もう。 一度溢れてしまった想いは、言葉は、取り消すことも無かったことにも出来ないのだから。 だから、何度目かの懇願を―求婚をする。 「俺のに、なって」 強引に伸ばした腕に、簡単に収まってしまう華奢な身体。 椅子に座った状態の―低い位置にある新一の肩を抱いて、癖っ毛の跳ねる頭に顔を寄せる。 遠くで赤い陽が落ちていくのを視界の端に置きながら、快斗は言葉を継ぐ。 「別に新一がそんな見た目になったから、だから言ってるわけじゃない」 「んだよ、それ…」 「ずっとだ。もうずっと前から、俺は新一しか見てなかった」 「―…」 「言うつもりなんか無かった。叶わないって、受け容れてもらえないって、だから」 他の誰かと仲良くしていても。可愛い女の子に、綺麗な花を捧げても。 新一が気にしていたのは、いつだって、俺の心なんかじゃなくて。 『あの子は、多分もうすぐ国を出て行くぞ?この地と相性が悪いって聞いてる』 『魔法使いの子か。何かおっかなそうな雰囲気あるけど。ま、オメーが良いならいいんじゃねぇ?』 違う、そんな言葉を聞きたかったわけじゃない。 けれど、大好きな青い瞳の奥を覗いても、見つからない。 新一が他の誰かといたら、割って入っていくような。 新一の姿が見えなければ、すぐに探しに行くような。 快斗が新一に抱いているような。 そんな、同じ気持ちはどこにも、どこにも、なくて。 「でも、この姿のままで、もしそうやって生きていくんなら、誰にも渡したくない、って思ったんだ」 「っ俺は、」 「解ってる。元に戻るんだろ?でも、…俺は」 赤い陽は落ちた。 腕の中にいた麗しき佳人は、スッカリと姿を変えて、―快斗の目の前には、懐かしい姿の少年がいた。 「丁度、この位の頃だったと思う」 「…?」 「俺が、新一を好きだ、って思ったの」 肩に回していた腕は、今度は幼い子供の胴回りをぐるりと囲い、抱きしめる。 「青い瞳が綺麗でさ、いつも見蕩れてた。ずっと欲しいって思ってた」 「快斗…」 「ずっと隠してた。新一が気付かなかったのなら、俺って凄ぇよな?」 「かいと」 名を呼ぶ姿がその唇が愛しいと思うままに、そっと己の唇で触れた。 ◆ ◆ ◆ 「さぁって、どうすっか…」 月はとっくに視界から消えてしまった。 そうだ。 思考を停めて良い時間は疾うに過ぎた。 諾々と監禁などされて、快斗に良い様にされるワケにはいかないのだ。 ―誰よりも、快斗の親友として。 眼を閉じる。直ぐに脳裏に浮かんだのは、泣きそうなトモダチの顔。 ―大事だ。大好きだ。だからこそ。 賢者は見通さねばならない。そして最良の道を探す。それこそが賢者たる者の役割。 あの王が、狂った恋のままに道を見失うというのなら、決して自分だけは見誤ってはならない。 流されるわけにはいけないし、それに、そもそも― 「アイツはそこまで馬鹿なんかじゃねぇ」 なりきれるものなら、もっといくらでも強引な手でも何でも取れただろう。 幾つかの条件付け。 何かを握った上でギリギリの計算をして、賢者に挑んでいる。 ―もっと考えろ、思い出せ、見つけろ、と新一の内側から声がした。 白い鳥を見つけて来いと旅に出るよう仕向けられた。 呪いは解く事ができるよ、と言った言葉。その真偽。 帰ってきた国の雰囲気。妙に活気の失せていた理由。 港の話。 その近くに移居している父であるもう一人の賢者の動向。 「でも、…不味いな」 朝が来れば快斗はここに来るだろう。 そう、言った。 『抱くから』と。 何とか、この子供の姿に手を出そうとしたのは止められたが、どっちにしても体格差や体力的に負けてしまう。 部屋を見渡す。 無駄な物が置かれていない素っ気ない部屋。 燭台を壁から取り外して?ベッドの布地を固めて―?しかし、手枷と足枷はどうするか。 「問題だよな、この重さは」 両足の足首にそれぞれ重りのついた黒い鉄の塊。足首と足首を繋ぐ鎖は短い。完全に揃えられているわけではないから多少の移動は可能だが、俊敏な動きはどうやっても無理だ。 逆に手首に嵌められた枷は緩く軽く、間の鎖は長かった。 細い足首は、変身前後でほぼサイズが変わらないからピッタリしているのに対して、流石に手首は子供から大人になった際に結構違うからだろう。 快斗の他人の身体サイズを見切るという特技は、今なお磨かれているようだった。 「…ま、やってみるか」 手が―腕がある程度使えるのは僥倖だった。 新一の母親が、女性としての装飾品を新一に付けるように言い聞かせていたが為に、女性物の髪ピンが手元にあることも。 静まり返った暗い部屋の中で、微かな金属音と息遣い。 やがて―かちり と音がした。 ◆ ◆ ◆ 手に入れてしまおうと思った。 どんな姿だって『彼女』や『この子』が新一ならば何の問題もないのだ。 女の身よりもいっそう小さな身体は易々と快斗の腕に収まって、押さえつければ抵抗なんて意味がない。 それなのに。 「快斗、快斗、快斗」 懸命に名を呼ぶ。聞きたくない。 「快斗、俺を、見ろ」 微かに声を震わせながら、しかし怖がるでも嫌悪するでもない。 一つ一つを区切って、ちゃんと聞こえるように。 真っ直ぐに、大好きな青い瞳と同じに、どこまでも快斗の意識を捕える、彼の。 「かいと」 「…なに」 脚の間に埋めていた顔をノロノロと上げる。 覆いかぶさるようにして身を起こせば、彼の顔だけでなく全身が眼に入った。 纏めて拘束している腕の細さ小ささ―その稚さに、沸く罪悪感。 幼い肢体は白く艶かしく目に映るけれど、肌を吸ってつけた痕は扇情的とはいえず、痛々しいものだ。 口でいくら愛してみても、幼さからか―行為への拒絶からか、くたりと一切反応のない下肢。 「快斗。こんなんでヤッても、壊れるだけだぞ」 「……」 壊したくて、しているつもりなのに。 けれど、そう言われてしまって言葉に詰まるのは、結局のところ―この人が大切過ぎるからだろう。 「…いや、頑張るし」 「無理だろ。それともヤッたことあるのか?こんぐらいの子供と」 だったら心底軽蔑する、と綺麗な眼は語っていたもので、快斗は慌てて首を横に振る。 そうしながら、あ、マズイ!と思う。 コレは―新一の常套手段だ。 ―相手の意識を向けさせて、強硬でない柔らかな拒絶もしくは提案をして、相手の気を引き別事と話を摩り替える― 「一応とはいえ、女の身体だってあるのに。無理に、この身体をヤる意味はなんだ?」 「今すぐ欲しい」 「…一晩くらい待てねーか」 その手には乗るものかと、快斗は己の求めを明確に口にする。意味ならある。しかし、その求めの言葉に更に新一の言葉が被さってきて、快斗は動きを止めた。 「……」 溜息交じりの言葉は、快斗を油断させるものに違いない。 なにしろ相手は恐ろしく頭の回る人物なのだ。 それでも、じっと見詰めてくる瞳には逆らいがたくて。 最大限の譲歩として、枷をつけて寝台しかないような一室に彼を放り込んだ。 ―朝が来て、姿が変ったら、必ず抱くと宣言して。 「やっぱ待つなんて、しなきゃ良かった…」 不審者の去った窓辺に腰をかけ―周囲に警戒を張り巡らせ手にした鍵を弄びながら、全くどうしてあの人は己を筆頭とした厄介な相手に好かれるんだろうな、とタメ息を吐いた。 人の心を簡単に奪って、なのに彼の心は与えてくれない。 いや大事に想ってはいてくれるのだ、望むモノとは全然違う形だけれど。 「触れたら解るって、思うんだけどな」 全くもって、彼だけは―新一だけは、快斗が王様だろうが求婚者だろうが、何も変わらずに在るのだ。 悔しいくらい、変らずに。 だから、触れて、そうすることで彼を変えられぬものか、いや変えられなくとも、寸分違わずに快斗の抱く想い全部が伝われば―… 一時でもその心を奪って、ホンの少しでも同じ想いに染まってはくれないだろうか。 「朝、か」 果たして眠っていたのか、何かを思い返していたのか。 気がつけば、再び生まれ変わって登っていく日の光が窓から差し込んでいた。 一晩心を占めていたのは、たった一人のひと。 なのに、振り返り、何を考えていたかを思い出そうとしても、明確にはならない。 快斗は変わらず手の中にある鍵の感触に安堵しながら、新一のいる場所へと向かった。 ―その背後でパタパタと羽を振るわせた白い小鳥には気付かずに。  ×
|