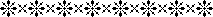 とりとおうさまのはなし 不審者だ。どう見ても。 しかし、何故か警笛や呼び声をあげて兵を呼ぶ気にはなれなかった。 怪しい事この上ないが、身のこなしは柔らかく、纏う気配に殺気だの害意は含まれて居ないようだ。何より、どこかで見たような、知っている誰かに(鏡で見たことのあるような…つまりは己に)非常によく似た印象を与えてくる姿。 向けてくる視線は面白がるような揶揄を含んでいて、口元もまたニィと吊り上っていた。 「誰だ。テメェは」 「突然の謁見をお許しいただきましょう、王よ」 「事後承諾か」 「あまり、この国の様式には詳しくないもので。無礼でしたかね?」 「…朝に出直せ、って言いたいところだな」 「残念ながら、時間が許さぬ身ですので」 得体の知れぬ男の口調は柔らかいのに、その声音は切迫した色を含んでいた。 見た目ほど余裕があるワケではないようだ。 「では、何の用だ?」 普通ならば侵入が出来ない場所。特殊な力に守られながら、更に護衛に囲まれ、矢を射掛けることも困難な高い場所に位置した部屋だ。そんな所へ易々と入り込んできた男に興味はあったが、相手をするには目的を明らかにした方が話が早そうだ、と踏んで快斗は尋ねる。 しかし返って来た単語に、快斗は一瞬で最大の警戒をした。 「新一は」 「……」 「賢者殿はいずこに」 「……誰だって?」 「新一です。城に行ってくると書き置きがありました。呼んだのは貴方でしょう?」 「テメェ…本当に、何者だ?!」 これは失礼を、と。 男は軽く身を正すとシルクハットを脱いで丁寧に一礼した。 「私は奇術師。夜に在って月下に姿を映す幻影のような者」 「幻影、な。…白いし。つまりオバケか。オバケが新一に何の用だ」 「我が…友たる賢者殿の、お迎えに」 「へぇ」 一体ドコでこんなの引っ掛けてきたんだ、新一!と快斗は内心でヒト誑しな友人に向かって叫んだ。 ◆ ◆ ◆ 冷えた部屋の中。 素っ気ない無地の絨毯が敷かれその上に寝台が一つ置かれただけの場所。 燭台の灯りは消されて、辛うじて頭上数メートルから落ちてくる夜を照らす月明りだけが、ほんのりと部屋に居る人間を照らしている。 「アイツ…大丈夫かな」 ぽつりと落ちた呟きは誰の耳にも届かずまた拾われることも無く、ぼんやりとした闇に転がって。転がしたまま―身体もまた転がしたままで、何となしに高い場所にある窓を見上げる。 月が鉄格子の嵌った囲いに捕らわれているように見えた。 もしくは格子の枠に収まる絵画か。 もっとも、現実は全くの間逆。 時が経てば月は悠々と囲いから逃れて視界から消えていくだろう。絵画はその主役を失って、残るのは微かな星の瞬きと闇。鉄格子で出来た枠は、また内に在る者を捕えるだけの素っ気無い存在に変る。 柔らかな月光をゆっくり呼吸と共に飲み込むようにして、新一はその姿をじっと見上げる。 「夜は動かないでいてくれると、良いんだけど、な」 しかし、『また』と言って別れた後に、再会が叶わなかったからと遥か遠くから空を駆けてやってきた男だ。 すぐ近くにいるとはいえ、また探しに来そうな気もした。 来て欲しいような気もした。 けれど。 同じくらい、今は彼の姿を見たくない、とも思った。 服部と小鳥と共に、他所で朝ごはんをご馳走になり、己の家に帰宅した日の夕方の事だ。太陽の傾きを気にしなければいけない時間帯の来訪者は、はっきり言って嬉しくもなければ迎えたくもない。 しかし、扉を隔てたままで誰何すると、相手は一応顔見知り城の使いだったから、しぶしぶと扉を開けた。 「何の用だ?元太」 「あの…ぅあー…ねーちゃん綺麗だな!俺のこと知ってるのか?!」 「…ああ」 もともと大きなドングリ眼を更に真ん丸くして見上げてくる年端の行かぬ少年。ちょうど、夜の身の新一と同じくらいの年齢の彼は、幼くして城へと奉公に出ている元太だった。 新一は、あっとコレは不味いと頭をかく。城に通信便の使者として仕え、よく父親との間の文を運んでくれたり、賢者から各所へのお使いをしてくれるこの少年は、新一と割りと気安く話し合う仲だった。だが、今の姿で対面するのはそういえば初めてだった気がする。 「賢者に用か?それとも『女人賢者』(わたし)に?」 「うん。女人だから、姉ちゃんのほうだな!あのさ、城まで来て欲しいって」 「…誰が?」 嫌な予感がして、新一は眉を顰める。 「快斗のにーちゃ、じゃなくて王様!一緒に行こうぜ!」 「……」 即位するまでは、王子のクセに下町に遊びに行っては厄介ごとを賢者の息子と解決したり、ついでに子供達の面倒を見たりしていたので、とりわけ現王は人望に厚く子供達から慕われている。それ自体は微笑ましいのだが、同じく慕われている賢者が子供達の頼みをすげなく断れないと知っての直接のお使いだなこれは、と新一はアタリを付けた。 なにしろ『一緒に』だ。 使うように提示されたであろう言葉は優しいが、連行してこい、という事である。 少年が任務を遂行できなければ、次に厳つい兵士が家に来るだろうと予想がついた。それに、そうなった場合の少年の今暦の給金は、間違いなく大幅に下げられるだろう。こと、新一に関する用事については厳しい快斗なのだ。尋ねた家が工藤の家である時点で少年もそれを察しているらしく、目の前の女性の素性などそっちのけで、とにかく頼むぜー!と既に両手を合わせて拝んでいる状態だ。 仕方なく、寝ている鳥の為に『所用が出来たから城へ行く。夜には戻る』と書き置きを残して、新一は家を出て再び元太と共に城へ向かった。 完全に日が落ちるまでに間はあったが、それでも急いで快斗の私室へ向かうと、待っていたのはなんと総勢十名程の仕立て屋とお針子だった。静々と眼を伏せて控えている。 部屋に入るなり、前方にズラリと並んだ女性達。 思わず後ずさると、いつの間にかしっかりと背後に回っていた呼び出し主兼部屋の主が新一の肩を掴んだ。 首元を締め上げたくなる衝動を堪えながら、低く呻く声音で新一は問いかける。 「おい…何の真似だ、コレは…」 「衣装の採寸」 「…?!」 クイッと快斗の指が部屋の片隅を指す。目を向ければそこには衝立にかけられた一目で上等のものとわかる白い布地。 今朝方聞いた商人の娘の話が新一の脳裏に甦る。 嫌な予感。 「……衣装ってーと」 「モチロン、花嫁の!」 ゆっくりと再び快斗を見れば、清々しい笑顔を浮かべていた。 「採寸だけ、この人数なら直ぐに出来るから、ちょっと付き合ってくれ」 「断る」 「駄目だって。俺はココから退かないぜ?」 快斗はトンと扉に背中をつく。 それから、新一を見据え、笑ったまま小さく小さく囁いた。 「さっさと計らなければ時間が足りなくなるんじゃねぇの?みんなの前で変身してみっか?」 「―?!テメッ」 明らかな脅しに、新一は目を吊り上げた。 しかし快斗は動じないどころか、より一層笑みを深くする。 「怒っても、綺麗だ」 「あ、のなッ」 「それとも俺が直々に押さえつけて、そんで測ってもらおうか?―ここんとこ、旅の間に打っ棄ってた仕事があるからって、塔に籠ってばっかで全然顔も見せてくれなかったし」 そっと腕を伸ばして、手が新一の頬を撫ぜた。 新一は憮然として、快斗を睨んだまま。 「―どけ」 「どかない」 静かな視線による攻防を破ったのは、背後から近づいてきた人物だった。 「これが、噂の隠されし賢なる姫ですのね!本当にお美しい!」 「ちょッ…!」 あ、私この度の花嫁様の仕立ての指揮を取らせていただくことになりました者ですわー、と歌うように楽しそうに話しかけてきた女性は有無を言わさずに、新一をズルズルと引っ張って衝立の向こうへ連れ込んだ。いや、俺は、と抗議の口を挟む隙など無い。それどころか、あれよあれよと言う間に新一の身体に手を回し、服を脱がしに掛かる。 冗談じゃねぇぞ!とその動き回る腕を掴んだ新一だったが、「あらあら、内気な姫でしたわね、これは失礼を〜」と笑顔で言われ、それではお手を伸ばして頂きましょうね、と彼女は逆に新一の腕を取って傍に控えていた侍女に指示を出し、そのまま腕の長さを採寸する。 見事な手際だった。 呆気に取られながらも、しかし更に計るための手が服を脱がしに掛かれば、新一とて抵抗を覚える。相手が女性である為、強行手段でこの場を脱するのは好ましくないと思いはしたが、流石にこれ以上は!と身構えると、不意に背後に回っていた女性が低い声で囁いた。 「王様から厳重なご依頼を頂いておりますの。直ぐに済みますから、ご辛抱を。私どもも、最低限にしか目も手も触れません」 ヒヤリとする響きは、先程の歌うような声音とは全くの別種のものだ。ハッとして彼女の眼を見れば、真摯すぎる眼がいっそ悲壮さを漂わせて新一の眼前に在った。 「姫―?無礼をされたんなら、計り手を直ぐに取り替えるよー?」 「……いや」 「女性の脱衣を覗くような事はいけませんわ〜。せっかく協力してくださる姫が測らせて下さらなくなります」 衝立越しに掛かる能天気な声にビクリと背筋を震わせた女性に、新一は一瞬だけ目を細めて「替えは不要だ。覗くな!」とだけ声を返した。 逃げ出す心配は無いと見たのか、快斗は、じゃ、あとは任せたよ、ここに居るとどうしても見たくなるからね。と言い残して部屋を出た。 ―その瞬間に、女性たちは慌ただしく動き始める。 新一も、もう口を出さず、ただ早く終らせるために人形のように彼女達の中心で立っていた。 貴重な生地で仕立てる前に安価な別生地で簡単な仮衣装を縫いたててから、本番に取り掛かる手順ですわと女性は言い、測りながら素早く布を合わせ、その場で裁断師が布を裁ち、お針子が急ぎ手を動かす。 それらの動きをジッと見ながら、新一への接触を一手に引き受けているらしい女性に、新一は小さく話しかけると、意を得たように彼女も答えてくれたのだった。 「王の指示は?」 ―「短時間で姫を不快にさせることなく素早く計測し、けれど美しい花嫁衣裳を作ること、ですわ」 「報酬は?」 ―「見合ったものを望むだけ」 「では、…罰は―」 ―「……屋号の剥奪と鞭打ちを、全員に」 「……」 ―「最高の素材を生かせぬ手は不要であろう、と」 「……そう、か」 ―「―賢なる姫、ですのね」 「いや。迷惑をかける」 ―「いいえ。最高の技術を至高なる存在に捧げられる事は喜びですわ」 「期日は」 ―「可能な限り早く」 「では、可能な期日は」 ―「……二週、もあれば」 ―… … … 窓から差し込む日が真っ赤になる頃、女性陣は部屋を出て行った。 ずっと立ちっぱなしだった新一は、少し休もうと、窓辺に置いてある椅子に腰をかける。そうしてから、ただ、立っていただけなのに、ひどく疲れていた事に気がつく。鉛のような何かが新一の胃の腑の辺りに押し込まれ、身体全体を沈ませているようだった。 赤い太陽の一部が山に掛かって、その姿をゆっくりと消していくのをジッと見ていた。 「お疲れ様」 「……」 戻ってきた部屋の主を振り返らずに、新一は視線を窓の外に向け続ける。 「新一」 「…何だ」 「こっち見て」 「…なんだよ」 仕方なく新一が近くにある気配を振り仰げば、そこに見えたのは。 赤く赤く照らされた顔は泣きそうな、まるで。 遠い昔、暮れていく森の中で迷子になった時のような。 そんな。 「俺のに、なって」 そう言った主が伸ばした両腕は、椅子に座ったままの新一を包んだ。 ◆ ◆ ◆ 「賢者殿の旅先で知り合った者ですよ。数日前よりこちらの国に滞在しております」 「…通行証を出せ」 快斗は、そう聞きながらも、おそらくこの相手にそういった形式は無意味なのではないか、という気がしてならなかった。コレはこの国に属さぬモノだ。そして、快斗にとって、喜ばしい相手では決して無い、とも。 現に目の前の男は肩を竦めて帽子をクイッと目深に被り直す仕草一つの反応しかしない。ソレを見て、快斗はとても、ムカっとした。 「身分も明らかに出来ねー奴の面会は受け付けてねーな、…帰れ」 「ええ、ですから。私は新一のところへ行きたいのです」 「……ンっだと?」 快斗の中で更にムカムカが増していく。 「帰る場所が、新一だとでも」 「そう聞こえませんでしたか」 敵だ、と確信した快斗の行動は早かった。 護身用にと絶えず身につけている非常に軽くしかし鋭利な短剣を懐から抜き、白いオバケに投げつける。しかし、白いマントが闇夜に閃いた一瞬、その姿は快斗の視界から消失した。一体どこへ跳んだかと耳を欹てながら、鋭く周囲を睨んで見渡せば、頭上に影が差す。ー影の先を見上げて、眉を寄せて呻いた。 飛んでいる、白い者。 「浮遊霊…だぁ?」 「実在は、しますよ」 「そら、実体はあるんだろうな。壁抜けて探し回るワケでもないってんなら、よ!」 言いながら、短剣を投げつける。だが、すんでの所で的は切っ先を避けた。 チッと快斗は舌打ちする。 ひらり、と白き者が跳んだ先は、素っ気無い出窓の枠が少しだけ外に張り出した窓の前。単に飾りとして付いているだけの出窓の先は、足場も何も無い建物の崖っぷちだ。 「逃げ場はねぇぞ?」 「さァて?」 いくらか開いている窓から流れ込む風が、白いマントを揺らした。 「教えていただければ、こちらも友好的に王宛にお預かりしている伝言を差し上げましたが―」 ―どうやら、我らは相容れぬ者のようだ。 言外に在った言葉は正確にその態度で快斗に伝わる。―否、快斗がそう考えた故の攻撃から、その意が相手に伝播したか。 「テメェに貸す耳は無ぇな。即刻、この国から出て行ってもらおうか」 「……」 白き者は何も言葉を返さずニィ…と口の端を上げて一笑すると、高い高い窓辺から―命綱も付けずに姿を消した。 「…オバケ、か」 暗闇だけが残った窓の外、念のために下を見下ろした。 だが見えるのは夜の底ばかり。暗いくらい、城壁と揺れる細い木々。あの白さなら上からでも眼で追えそうなものだろうに。目を凝らしても、もう何も見えなかった。 「新一…」 誰も応えないのを承知で、そう囁いて、呼んで。 それから胸元に潜ませた金属の感触を服の上から確かめる。―確かに、在る。 けれども。 それだけでは不安は拭えずに、そうっと取り出して―握り締めた鍵は、月光に冷えたまま、王と称される者の手に在った。 大切なモノをしまった宝箱の鍵。 たった一つしかない、同じものを欲するとりとおうさまの話。  ×
|