HNで呼ばないで11
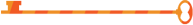
翌日、約束どおり家まで迎えに来てくれたアキラのワゴン車に乗って俺達は、山梨県にあるスキー場へとやって来た。
夜が明ける前に出発したから眠くて仕方なかったけれど、辺り一面の銀世界を見た途端、眠気なんか何処かへすっ飛んで、小さな子供みたいにはしゃいでしまいそうになる。
抜けるような青い空と、眩いばかりの白い雪。青と白のコントラストが見事な景色を作り上げていた。
こんなに沢山の雪も、ロッジも、リフトも見るもの全てが新鮮でわくわくする。
「なぁなぁ、ここで今日滑るのか?」
「当然だ。ほら、早くウェアを着ろ」
「うわっ」
ちょっと呆れた風に言って、ボフッと頭の上に紺色のウェアが降ってきた。
「これ、俺の?」
「そうだ。ボードと靴もあるぞ」
「!」
思わずわぁっと声が洩れた。
白い大きなスノボの板には雪の結晶のような模様が描かれていて真ん中に変な金具が付いている。
その金具にブーツを固定して滑るんだと、俺の手をとって丁寧に説明してくれた。
「ほらほら、着替えないと遊ぶ時間がなくなる」
当のアキラは既に着替えを終えて準備は万端。
どんな服でもかっこよく着こなせてしまうのが凄いところ。
手伝ってやろうか? なんて言われたけど、高校生にもなって着替えを手伝ってもらうのは恥ずかしすぎて慌ててウェアに袖を通した。
広いゲレンデでは既に大勢のスキー客が滑走していて、賑やかな声が聞こえてくる。
「ぅうっ、履けない〜っ」
早く滑ってみたいと言う気持ちばかりが先行してしまい、うまくブーツが足にはまらない。
情けない事に、暫くスノーブーツと格闘していたけど、結局アキラに手伝ってもらうハメになった。
午前中、スノーボードの基礎を徹底的に教え込まれ、ほんの少しだけなら滑れるようになった俺は休憩を兼ねて入ったレストランで、アキラに奢ってもらったアイスクリームを頬張っていた。
沢山汗をかいたから喉を通る冷たさが心地いい。甘くて濃厚なクリームが口中に広がってほわんと幸せな気分になれる。
「なぁなぁ、俺上手になった?」
「そうだな、ハルは上達が早いし、結構良いセンいってるんじゃないか?」
上達が早いって、つまり俺にはスノーボードのセンスがあるって事? そうなら凄く嬉しい。
颯爽と山道を駆け下りる自分の姿を想像して思わず顔がほころぶ。もしかして、午後からリフトに乗れたりして。
ちょっと乗ってみたかったんだよな〜。
「リフトはまだ無理だ」
「えぇ〜っ」
せっかくリフトに乗れると思ったのに、即答されて楽しみにしていた気分が一気に萎む。
つまらないと抗議してみたらアキラは困ったように眉を寄せ、仕方がないな。と短く息を吐いた。
「ファミリーコースなら、なんとかいけるかもしれない」
「えっ!? 本当?」
「緩やかなところだからそこまで危険はないと思うが……、でもハルはまだ超がつく初心者だから」
「大丈夫だよっ! 実戦で覚えた方が上達するってアキラも言ってたじゃないか」
思わず興奮して手を握ると、アキラは一瞬驚いた顔をして、静かに苦笑する。
「わかった。その代わり、わがまま言っても俺は助けてやらないからな」
「ガキじゃないんだからわがままなんか言わないって」
「アイスを頬に付けてるやつは充分ガキだと思うが?」
「っ!」
フフンッと鼻を鳴らし、俺の頬に付いたクリームをツイッと指で掬い、それをそのまま口に含む。
あまりのことに驚いてうっかりアイスを落としそうになった。
「あははっ、なんだよその間抜けな面は」
間抜けって、アキラがいきなり変な事するからじゃないか。頬に付いたクリーム舐めるなんてそんな事普通しないだろ。
アキラの行動は本当にいつも予測不可能で心臓に悪い。
そんな事が恥ずかしげもなく出来るアキラって、絶対変だ。
周りの目とか気にならないのかな?
ただでさえアキラは目立つから、さっきのも誰かに見られてしまったんじゃないかと気が気じゃない。
「鼻の頭にも付いてる」
「えっ、嘘!?」
「う、そ」
「え?」
あわあわと慌てて鼻を擦る俺を見てニヤリ。
うそ……って、またからかわれた。
「早く来い。置いてくぞ」
「ちょっ、待てよっ!」
俺は残ったアイスを強引に口に押し込むと、何事も無かったかのように店を出ようとするアキラの後を慌てて追い掛けた。