No title
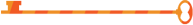
暗い夜だった。昼間は賑やかな声が響いていた公園も、今はひっそりと静まり返り、時折聞こえる木々のざわめきと、目下に広がる穏やかな波の音だけが辺りを包み込んでいる。
等間隔に置かれた街灯の明かりだけが、煌々と辺りを照らしていて伊月俊は備え付けのベンチに腰を下ろすとプルトップに指を掛けた。
よく冷えた炭酸飲料を煽ると深い溜息が洩れた。
夏の強化合宿に来て2日目。なんとなく部屋にいたくなくて、こっそり抜け出して来たものの行くあてなどあるはずも無く、ロードワーク中に見つけたこの公園にやって来てしまった。
何気なく空を見上げれば真っ暗な夜空に小さな星々がキラキラと輝いているのがわかった。
そう言えば、星が綺麗な場所があるから自由時間になったら一緒に行こうと、木吉が日向を誘っていたな。「誰が行くか! ダアホッ」なんて言っていたけれどきっと今頃は何処かでこの夜空を眺めているのかもしれない。
そんな二人の様子を想像してしまい、本日幾度目かの溜息をついて手にしていたジュースの缶を軽く揺する。まだほとんど手を付けていないそれは重い。もう一度溜息を吐いて、伊月は一口だけ飲んだ。
片思いがこんなにも苦しいものだとは思わなかった。
去年失ったチームの大黒柱の復活を待ち望んでいた筈だったのに……。
日向と木吉が二人でいるのを見るたびに、何とも言えないやるせない気持ちにさせられる。
自分にも木吉のような積極さと多少の強引さがあれば日向の気持ちを振り向かせることが出来ただろうか?
ウインターカップ前に木吉が戻って来てくれた事はチームメイトとして素直に嬉しいし心強くもある。
だが、自分が密かに好意を寄せている相手を目の前で奪われていくのは正直言って結構堪える。
練習中でも、プライベートでも側に居ることが多くなった二人は、見ないようにしようと思っていても勝手に視界に入って来るし、聞きたくない会話だって嫌でも耳にしないといけないわけで……。
こんなに苦しい思いをするくらいなら、さっさと日向に思いを伝えてしまえばよかったのかもしれない。
だが、自分には今まで培ってきた幼馴染と言うポジションを崩す勇気なんて何処にもない。
「……はぁ」
頬を撫でる生温い風が沈んだ気持ちをさらに重くさせているようで、知らず深いため息が漏れた。
「浮かねぇ顔してんな」
ふ、と頭上に影が差し、顔を上げるとオレンジ色のジャージが目に飛び込んで来る。
スラリとした長身の男が手にコンビニの袋をぶら下げ、少し長めの茶髪を掻き上げながらジッとこちらを見つめていた。
彼とはまだ直接話をしたことは無いが顔と名前くらいは知っている。秀徳高校の3年生、宮地清志だ。以前高尾が”宮地さん超怖いんだよ”と黒子達にボヤいているのを何度か聞いたことがある。
「伊月……だっけ? んなところに一人でいると危ねぇぞ」
「ハハッ、俺も一応高校生だし、大丈夫ですよ宮地さん。心配してくれてるんですか?」
そう尋ねたら「そんなんじゃねーけど……」とか、なんとか言いながらフイッと視線を逸らされてしまった。
「こんなところで、何やってんだオマエ」
「ちょっと、夜風に当たりたくて」
日向達がいちゃついているのを見ているのが辛くて部屋を抜け出して来ちゃいました! なんて、言えるはずもない。
「宮地さんは、こんな時間にどうしたんですか?」
「オレか? バカップル共が部屋でイチャついてやがるからウザくて抜けてきたんだよ!」
盛大な溜息を吐き、宮地がドカッと勢いよく横に腰を下ろす。
バカップル。と言うのは恐らくいつも一緒にいるアノ二人の事だろう。
誰、とは言わなくても想像できてしまうのがなんとなく可笑しい。
「そう、ですか……」
「……なんか、あったのか?」
顔を覗き込まれそうになって伊月は言葉に詰まった。
「いえ、何も……」
俯いて手元にある缶に視線を落とす。質問に答えるつもりはなかったし、出来ればそっとしておいて欲しかった。
宮地もそれはわかっているのか、それ以上深く追及してくることは無く、ゆっくりと視線を空へと向けた。
「別に無理に話せとは言わねぇけどさ、話して楽になる事だってあるんじゃねぇの?」
「え?」
「オマエPGだろ? チームの要がシケた面してたらチームの士気に関わってくるんじゃねぇかつってんだよ」
「!」
驚いて思わず顔を上げると、宮地は空ではなく真っ直ぐに伊月を見ていた。
何時になく真剣な眼差しに見つめられ息が詰まる。
「お節介かもしれねぇけどさ……オマエなんか無理してねぇ? 敵の俺が言うのもアレだけど、無理やり明るく振る舞ってるように見えたんだけど」
「……ッ」
鋭い言葉に無意識のうちにびくりと肩が跳ねた。
顔に出やすいと言う程ではないが、図星をさされてポーカーフェイスを決め込めるほど伊月は大人ではない。
出来るだけ平常心でいようと自分を誤魔化して来たけれど、敵チームにまで心配されるほど顔や態度に出ていたとは思わなかった。
確かに宮地が言うように、PGがこんな不安定な状態ではみんなに迷惑がかかってしまうかもしれない。
打ち明けて何かが変わるとは思えないけれど、宮地が言うように聞いてもらえばこの苦しい胸の内も少しは楽になるのだろうか?
手の内にある缶に視線を落とし、少し躊躇った後伊月は静かに口を開いた。
「……片思い、なんです。中学の時からずっと……」
はっきりと恋心を自覚したのはいつだったか、細かい事はもう覚えていないけれど。伊月の目指す先には常に日向が居て、これからもずっと側に居られるものだとばかり思っていた。
恋人になれるなんて最初から思っていなかったし、本人にこの気持ちを伝えるつもりなんて元からない。ただ、側に居られるだけで幸せだった。
もしいつか、彼に恋人が出来た時には、親友として応援してやろう。
きっと、応援してやれる。そう、思っていたのに……。
ポツリポツリと話始めた伊月の言葉を、宮地は黙って聞いていた。
勿論、相手が男であること、同じバスケ部に居る事等は焦点をぼかして話している。
話せば楽になるかと思ったのに、心はどんどん苦しくなっていくばかりで次第に口は重くなっていく。
「告んねぇの?」
「それは無理ですよ……アイツ、好きな人がいるんで。多分、両想いだし」
「多分、だろ?」
「……」
伊月は何も言い返せなかった。
はっきりと日向に聞いたわけでは無いがなんとなくわかる。
木吉と会話している時の表情、時折見せる照れたような仕草。
何より厄介なのは木吉の存在だ。
彼は天然なのか計算なのか定かではないがとにかく日向へのアピールが半端ない。
彼が日向を狙っていることは一目瞭然だし、部内では最早暗黙の了解のようなものが出来てしまっている。
自分が入り込める余地なんて残っていない。
「……仮に告白して10がダメなら0になるなんて、とてもじゃないけれど耐えられない……」
臆病者なんですよ、オレは。と呟いて、残っていた炭酸飲料を喉の奥に流し込んだ。きつい炭酸が体中に沁み渡って涙が出そうになる。
「すみません、変な話をしてしまって。オレなら、大丈夫ですから」
「んな顔して何が大丈夫なんだよ。轢くぞ」
これ以上話をしたら、本気でツラくなりそうだったので笑顔で誤魔化そうとしたのだが、厳しい声に一蹴されてしまった。
「オマエ、それで本当にいいと思ってんのか? 自分の気持ちもっと大事にしろよ馬鹿。好きな奴が他の野郎に取られんの指咥えて見てるだけなんて、キツイにきまってんだろうが! 無理してんじゃねぇよ」
怒ったようにそう言って、思いっきりおでこを小突かれた。衝撃で視界がぐらぐら揺れる。
なんで、この人が怒るんだろう? もしかしてやっぱり……。
「心配してくれてありがとうございます」
「はぁっ!?」
あまりにも予想外な一言だったらしい。目を丸くして信じられないものを見るような目で伊月を見ている。
何か可笑しなことを言っただろうか?
ほとんど話したこともない相手の悩みを聞いてくれたり、怒ってくれたり。きっと厳しいけれど、なんだかんだで良い先輩なんだと思う。
「宮地さんって結構優しいんですね。高尾達が慕うのもわかる気がします」
思ったままを口にする伊月に宮地は何か言いたげに二、三度口を開きかけたが結局口を噤んだ。
そして、長い溜息を吐きながら頭をガシガシと掻くと徐に立ち上がった。
「別に優しいわけじゃねぇし。偶々暗い顔して座ってたから声掛けてみただけだっつーの!」
ふいっとそっぽを向いてしまった宮地の耳がほんのりと赤く染まっていることに気が付いて、思わず口元に笑みが浮かんだ。
「――あぁ、そうだ。明日、この地域の夏祭りがあるらしいぜ。花火も上がるみたいだし、行ってみたらいい気分転換になるんじゃねぇか?」
どうせ、お前のところもまだ合宿続くんだろう?
言いながら、返事も待たずに宮地は行ってしまった。
「夏祭り……かぁ」
そう言えば今年は部活が忙しくて地元のお祭りにすら行けていない。
皆で行けばきっといい気分転換になるだろう。
状況は何も変わらないし、胸の奥にわだかまっている澱のようなものが消えたわけではないけれど、最初に一人でいた時よりは幾分か気分が軽くなったような気がする。
(やっぱり、優しい人ですよ。宮地さんは……)
去って行ってしまった後ろ姿にそっと心の中で呟いて、伊月もゆっくりと立ち上がった。