No title
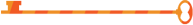
「んーっ! やっと授業終わった〜!」
長くて退屈だった授業もようやく終わり、大きく腕を伸ばして凝り固まっていた身体を解していると、緑間が呆れたように溜息を吐いた。
「お前は授業中ソワソワし過ぎなのだよ。もう少し落ち着いたらどうなんだ」
「えー? だって退屈じゃん? 特に数学なんて眠気との戦いでさぁ。起きてるだけでもキセキじゃね?」
我ながらよく頑張ったと思う。途中あまりにも眠すぎて、後ろの席に座っていた緑間にちょっかいをかけたがそうでもしないと猛烈な睡魔に負けてしまいそうになるのだから仕方がない。
「全く、何がキセキだ。普段から早寝早起きを心掛けていれば授業中に眠くなることなど――」
(あー、また真ちゃんの小言が始まったよ……ん?)
ぷりぷりと怒りを露わにする緑間の言葉を軽く受け流し、ちらりと窓の外へと視線を向ける。
丁度、裏庭へと続く小さな広場に見知ったシルエットを発見し、高尾の意識は一気にそちらへと傾いた。
スラリとした長身に少し長めの茶髪。口を開けば凶暴で怖いけれど、黙っていればイケメン。
女子の人気も高いと噂されるバスケ部一怖い先輩、宮地清志だ。
(宮地さん、あんなところで何やってんだ?)
何気なく見ていると、小走りに走ってくる女子の姿を捉えた。
そして、両手で抱きしめていた紙袋らしきものを宮地に手渡す。
ほんの少し照れくさそうに笑いながらその紙袋を受け取る姿に、胸がちくりと痛んだ。
人より視野が広いというのは、いいことばかりではない。
最近つくづくそう思う。
勿論、試合では役に立つし、危険予知もしやすいから便利ではあるけれども。
見たくないものまで見えてしまうのは正直言ってキツイ。
「――おい! 聞いているのか、高尾!」
突然肩を揺すられてハッとして我に返った。
そうだった、まだ緑間の小言の途中だ。
「あー、悪い。聞いてなかったわ」
「なんだと!?」
「真ちゃんの言いたいことはわかってるって。そんな事より、もうすぐHR始まっちまうぜ?」
「む?」
視界の端に先生の姿を捉え姿勢を元の位置に戻す。
この時間が終われば、待ちに待った部活の時間だ。
(宮地さん、あの子に何貰ったんだろうな……。嬉しそうな顔しちゃって)
宮地だって年頃の男の子なんだし、女の子にプレゼント貰ったら嬉しいに決まっている。
あの娘は宮地さん好みの可愛い顔をしていたし、もしかしたらこのままお付き合いに発展したり――。
黙ってじっとしていると、思考がどんどん嫌な方に行ってしまう。
(早くHR終わらねぇかな)
一刻も早く部活に行きたい。一心不乱に練習してこの嫌な気分を吹き飛ばしてしまいたい。
頬杖をついて先生の話を何げなーく聞きながら、ずっとそんな事ばかり考えていた。
「おい、高尾。まだやんのか?」
部活終了後、自主練をしようと一人体育館に残っていた高尾に宮地が声を掛けて来た。
「もう少し頑張りたい気分なんっす。鍵締めやっとくんで宮地さん戻っていいっすよ」
「根詰めすぎだろ馬鹿。お前の相棒はもうとっくの昔に帰っちまったぜ」
「そーっすね。でも、もう少しだけ……」
「なんか、あったのか? 今日のお前、変だぞ」
宮地の言葉にぎくりと身体が強張る。昼間のモヤモヤを未だ引きずっているなんて言えるわけもない。
「なんもねぇっすよ。つか、そんなに俺の事見てくれてたんっすか? ヤダー、どんだけ俺の事好きなんすか宮地さん」
「んなわけねぇだろ! 変な事言うな轢くぞ!」
凄みのある笑顔で言われ、ヒッと身が縮む思いがする。
「ハハッ、冗談っすよ。冗談。つかマジで戻ってていいって。ただ単にもう少しやっていきたいだけなんで」
「……ふぅん。じゃ、オレも少しやってくわ」
「へっ!?」
予想外の言葉に思わず間の抜けた声が洩れた。宮地は残る気満々な様子で、既にボールを手にしている。
「どうせ家帰ってもヒマだしな」
「受験生がヒマとか言っちゃっていいんすか? ずいぶん余裕っすね」
「ヤな事思い出させんじゃねぇよ! 焼くぞてめぇ!」
手にしていたボールを思いっきり投げつけられ思わず苦笑する。
(ま、二人きりで練習ってのも悪くねぇか)
悪くない。というよりむしろ嬉しい。
昼間のモヤモヤは相変わらず心に燻ったままだけれど、それでも好きな人と同じ時間を共有できるのは至福の時と言うものだ。
「宮地さん、今日、何の日か知ってます?」
「今日? 今日は平日だろ?」
自主練後、着替えをしている時に思い切って訊ねてみると、宮地はなんかあったか? と、首を傾げた。
「そーっすけど、実はなんと高尾ちゃんの誕生日でーす☆」
「ふぅん」
「ちょっ! 反応薄ッ!」
わざとおちゃらけて言ってみたのに、予想通り反応が薄くて面白くない。
「と、言うわけでなんかプレゼント下さい」
「ハッハー! てめぇ、自分で話といて何言ってんだよ轢くぞ!」
咄嗟にバシッと頭を叩かれた。これも予想の範囲内の反応だ。
「ま、いいけど。何が欲しいんだよ」
「えっ!? マジでいいんっすか?」
「あ? お前が言ったんだろ。言っとくけどあんま高いのはやれねぇからな」
何がいいんだよ? と問われて慌てて考える。まさかOKを貰えるとは思ってなかった。
「じゃぁ、コンビニで何か奢ってください」
「は? そんなんでいいのかよ」
「だって、金かかんない方がいいんすよね?」
正直、宮地から貰えるものなら何でも嬉しい。
「つか、そんくらいだったらもう一つ聞いてやるよ」
「マジで? 宮地さん太っ腹〜!」
「先輩なめんなよ。後輩の誕生日に菓子一個とかカッコつかねぇだろ」
ロッカーの扉を閉めながら顔だけで笑う。扉が閉まる瞬間、その中に例の紙袋が入っていることに気付いて胸がチクリと痛んだ。
「んーじゃぁ……宮地さんが着てるカーディガンが欲しい、です」
「コレか?」
宮地が羽織っているクリーム色のカーディガンを指さす。
「俺、カーディガン持ってないんっすよ。もー最近、寒くって」
「なんだそりゃ。トレーナーでも何でも着ろよ」
口ではそう言いながら、口調はいつもより優しい。
「えー、ダメっすか?」
「……ッ。わかったわかった。今度同じの用意しといてやるよ」
高尾は、小さく首を振った。
「いま宮地さんが着てるヤツがいいっす」
「使い古しだぜ?」
「それがいいんです」
「つか、どう見てもサイズデカいだろうが」
「大丈夫だって! 萌え袖出来るじゃないっすか」
「萌え袖ってお前……変わった奴だな。まぁ、欲しいっつーならやるよ」
「マジで? ラッキー☆」
ほらよ、と直に手渡されて思わず顔がにやけてしまう。同性の、しかも同じ部活の先輩が着ているものが欲しいなんて、変な奴だと思われたかも知れない。
それでも、たった今まで着ていた宮地の私物だ。それを譲ってもらうのは宮地の一部を貰ったみたいで、とても特別な事のように感じられる。
ほんの少しでも自分は彼にとって特別な存在だと自惚れてもいいだろうか。
早速宮地に貰ったカーディガンに袖を通すと仄かに彼の香りがする。
「すっげー暖かい」
「ぷっ、やっぱお前、サイズ合ってねぇじゃん。ブカブカだぜ?」
「いいんっすよコレで!」
クックックと、喉で笑われて胸が甘く疼いた。
他の人にはあまり見せない、気を許した人だけしか知らない宮地の笑顔。
昼間の彼女の前でもこんな風に笑うのだろうか?
そう思ったら、心の奥底に燻っていた嫌な感情がじわじわとせり上がってくる。
「ねぇ、宮地さんって今、好きな人居ます?」
「んだよ急に……オレが好きなのはみゆみゆに決まってんだろうが」
「フハッ、歪みねぇw じゃぁ付き合ってる人とか、居ないんっすか?」
真っ直ぐ彼の目を見ながら、思い切って聞いてみる。
素直に答えてくれるとは思ってないけど、どうしても確かめずには居られない。
「バスケ三昧の受験生に彼女作るヒマなんてねぇよ。あんま変な事聞くと埋めんぞ馬鹿!」
バシッと頭を叩かれて、思わず前につんのめった。
「って〜……宮地さん容赦ないっすね」
「当然の報いだろ」
「ひっでぇ。じゃぁさ……最後にもう一個聞いて欲しいな〜なぁんて」
「あ? お前、あんま調子に乗るなよ?」
なんて言いながらこめかみをヒクつかせ、先に立った宮地がドアノブに手を掛ける。
廊下からひやりと冷たい空気が吹き込んできて、思わず小さく身震いをした宮地の後姿に思い切って告げた。
「俺と……付き合ってください!」
「――は?」
ずっと、言いたくて言えなかった言葉を口にした瞬間、襲ってきたのは激しい後悔だった。
好意を持っていた相手の私物を貰えた嬉しさと、昼間の彼女の存在が気になって少々焦ってしまっていたのかもしれない。
別に自分の気持ちを打ち明けるつもりなんて本当は無かった。
本当は心の奥底に秘めて隠し通すつもりだったのに!
部活の後輩、しかも男に告白されたって普通気持ち悪いだけだ。
大体、好きだとも言っていないのに付き合って欲しいと言うのは、どう考えても変だ。
宮地はあまりにも突然の出来事に茫然として、無表情になってしまっている。
いっそのこと、いつものように”冗談っすよ”と笑い飛ばしてしまおうか。
今ここで振られるより、冗談で済ませてしまった方が傷が浅くて済む。
そうだ、そうしよう。きっとそれがお互いの為にいい選択だ。
「なぁんて、冗だ――」
「いいぜ」
「ふへっ!?」
笑って誤魔化そうとした高尾の耳に予想外の答えが響き、思わず変な声が洩れた。
「み、宮地さ……いま、なんて?」
聞き間違いでなければ、「いいぜ」と、言われたような気がするのだが。
「だから、付き合ってやってもいいつってんだよバーカ」
「!」
コツンとデコピンを食らわされ視界が歪む。
「ま、マジで?」
「ウソ吐いてどうすんだよ」
何か文句でもあるのか? と、問われ盛大に首を振って否定する。
文句なんて、あるわけがない。
「じゃ、決まりだな」
ひやりとした長い指先が頬を撫で仰向かされる。艶めかしい仕草にどきりとさせられる間もなく、唇が宮地のソレに触れた。
軽い水音と共にすぐにそれは離れ、魅惑的な笑みに心が奪われていく。
「み、宮――」
「早くいくぞ」
高尾が言葉を発するより早く、宮地は背を向けると外に出てしまった。だが、ドアの陰に隠れる一瞬、彼の耳まで赤く染まった首筋を見逃す高尾ではない。
「ぶはっ、宮地さん顔真っ赤……っ」
「うるせぇ! 余計な事言うと轢くぞ!」
ドスドスと凄い足音を立てながら宮地は先へ行ってしまう。
あの宮地が照れている――。
「宮地サン、かっわいい♪」
思わず二ヤついてしまいそうになる頬を抑えながら、宮地に貰ったカーディガンをジッと見つめる。
(やっべ俺超幸せかも!)
「何やってんだ! 早く来い高尾!」
「今行きますって!」
高尾和成16歳。幸先のいいスタートになったと、破顔せずにはいられなかった。