No title
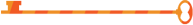
部活が終わると、それまで賑やかだった体育館は一気に静かになった。
秋の爽やかな風が蒸し暑かった室内の温度を幾分か下げてくれる。
「お疲れ、真ちゃん。今日もやっていくんだろ?」
あらかじめ用意していたスポーツドリンクを手渡して訊ねたら、「当然なのだよ」と何時もの答えが返って来る。
「高尾、お前は先に帰っていてもいいのだぞ」
「え〜、最後まで付き合うって! てか、俺がそうしたいんだよ」
真ちゃんが放るボールを目で追いながら、笑いかけた。
「だってほら、試合でシュートする時はやっぱ、パス出す相手が必要じゃん?」
新しいボールを手に取って指でくるくる回していると、早く寄越せと怒られてしまう。
毎日毎日おんなじ会話。だけど、二人で居られるこの時間が俺にとってはすげぇ愉しい。
やっぱ一分一秒でも長く、好きな奴とは一緒にいたい。
午後七時過ぎ、ようやく練習を終えた俺達は、散らばったボールを片付けモップを綺麗にかけなおしてから部室まで戻ってくる。
「帰りコンビニ寄ってこうぜ」
「あぁ、そうだな。だがその前に――」
汗で濡れたシャツを替えていると、不意に肩を引き寄せられた。
ハッとして振り返ると、俺の肩先へ顎を沿わせる高さに屈んでいた真ちゃんがするりと唇を寄せてくる。
「あ……」
ドキッとして、思わず目を閉じた。チュッと軽いキスが、唇に落ちる。
「ちょ、真ちゃ……俺まだ着替えの途中……」
「どうせ汗をかくからそのままでいいのだよ」
「……っ」
フッ、と小さく笑いながら顎をしっかりと固定され、一度離れた唇がまた重なった。
しっとりと唇を吸われ、首の後ろがざわっと粟立つ。
「……ん、んっ」
身体を真ちゃんの方へ向け直し、俺よりかなり大きなその背中に腕を回す。ロッカーを背もたれ代わりにして甘いキスを繰り返していると、全身から力が抜けるていく。
「……は、ぁ。真ちゃんってさ……絶対にムッツリだよな」
普段はこんな事全く興味ありませーんって顔してるくせに。二人っきりになるといつもこう。
悪戯っぽく訊ねてやったら真ちゃんが「嫌なのか?」って、訊ねてくる。
嫌なわけ、ないじゃん。
返事の代わりに微笑んで俺からキスしてやると、真ちゃんがはにかんだように微笑んだ。
俺だけが知ってる真ちゃんの笑顔。俺だけが真ちゃんの特別でいられるって気がして凄く好きだ。
真ちゃんの隣に俺が居る事。そんな当たり前の日常がとても幸せだと思う。