No title
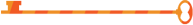
無機質な天井を眺めていると、ピピッと言う電子音が静かな室内に鳴り響く。
脇に挟んだそれを取り出し、確認すると『37.5』の文字。
高熱でもなく、微熱でもないなんとも微妙な数値に思わず深い溜息が洩れた。
ウインターカップを控えたこの大事な時期に熱出すとかマジで最悪。
回復したときに、笑顔でキレる宮地サンの顔が浮かぶようで、思わず失笑が洩れた。
なんで熱なんて出すかなオレ。自分の不甲斐なさに腹が立つ。
つか、こんくらいならなんとか行けんじゃねぇか?
ちょっと身体はだりぃけどんなモン気合いでなんとか――。
そんな事を考え起き上がろうとした正にその時。
静かだった保健室の扉ががらりと開いて、目立つ緑色の頭が入ってくるのが見えた。
「よぉ」
「高尾! もう具合はいいのか?」
「ん? おー、へーき、へーき。ピンピンしてるっての」
大げさなくらい身体を動かしてもう大丈夫だとアピールすると、腰を屈めた真ちゃんが突然オレの頬に触れた。
オレの大好きな左手が前髪を掬い上げ、綺麗な真ちゃんの顔がぐっと近づいて来る。
「――ッ」
真ちゃんのまつ毛すげー長い――。
息がかかりそうなほど近くに真ちゃんの存在を感じ、自分でもぶわっと体温が上がっていくのがわかった。
「む? まだ熱いのだよ。それに顔も赤い」
「そ、それはお前のせいだっっつーの!」
「俺のせい、だと?」
「そうだよ! お前がいきなり顔なんて近づけるから……ッ」
熱くなってしまった頬は熱のせいもあるだろうけど、絶対それだけじゃない。
跳ね上がってしまった鼓動を落ち着けるべく息を整え見上げると、何故か真ちゃんまで赤い顔をしている。
「全く、お前と言う男は何処まで……」
「?」
何を言っているのかわからずに首を傾げると、突然肩を掴まれた。
「ちょっ、なん――ぉわッ!?」
「いいから寝ていろ馬鹿め」
ぐわっとそのままベッドへと倒され視界がぐるんと回る。
「ちょ、大丈夫だって」
「お前は直ぐに無理をするからな。俺が見張っててやるのだよ」
「ぶはっ、ナニソレ」
近くにあったパイプ椅子を引き寄せ、どっかりと腰を下ろした真ちゃんが、オレの手をぎゅっと握ってくれた。
オレの手に重ねられた真ちゃんの手は、ひやりと冷たくてとても心地がいい。
笑いながらも、ちょっとだけ嬉しいと思ったりして。
「そういや、今授業中だろ? いいのかよサボって」
「問題ない」
「即答かよ」
「今日の授業の内容なら既に頭の中に入っているのだよ。それよりも、今はお前の方が心配なのだよ」
「……ッ」
突然のデレはマジで心臓にクる。「何がお前の方が心配だ」だよ!
このままじゃ熱下がるどころか上がっちまうっつーの。
ドキドキと早鐘を打ち始めた鼓動に気付かれないように、布団を目深に被るとほんの一瞬真ちゃんが笑ったような気がした。
そして、伸びて来たもう片方の手が、そっとオレの髪を梳くように撫でる。
ひやりとした手の感触と、そっと髪を梳かれる感覚は凄く、くすぐったい気分にさせられる。
「なんか、ガキ扱いしてね?」
「そうか? 妹が熱を出したとき、こうすると落ち着くと言われたことがあるのを思い出したのだよ」
「……あー、妹ちゃんね」
真ちゃんでも看病(?)するんだと思うとちょっと不思議な気分だ。
「いいからお前は目を瞑っていろ」
暫くはこうしていてやるのだよ。とかなんとか言いながら、真ちゃんはずっとオレの手を握ったまま離そうとしない。
コレは、オレが寝付くまで居座るつもりだ。と判断し、仕方なく全身の力を抜いた。