No title
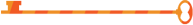
「なぁ、真ちゃん。たまにはマジバにでも寄っていかね?」
珍しく部活のない金曜日。ほとんど人の少なくなった放課後の教室で、俺は思い切って声を掛けた。
毎回、毎回おは朝の結果が悪いだとか、俺との相性が悪いとかで誘っても断られる事が多いから、真ちゃんをデートに誘うのはとてもタイミングが難しい。
おまけに普段は毎日遅くまで部活三昧。バスケは好きだけど、やっぱたまには息抜きも兼ねて二人っきりで出かけたいと思うわけで……。
今日はおは朝の占いもソコまで悪く無かった筈だし、相性だってバッチリのはずだ。
俺は今でも占いなんてあまり信じてねぇし、正直そんなんどうだってよくね? って思ってるけど、なんせ相棒が信じきってるからなぁ。
これが普通の恋人同士ならココまで気を使う必要もねぇんだろうけど、相棒というポジションを保ったままの片思いだから、デート一つ誘うのも一苦労だ。
「……別に、構わないのだよ」
「え、マジ?」
最初は断ってくるもんだと踏んでいた俺は、意外とあっさり真ちゃんからOKが貰えてしまったのでつい、聞き返してしまった。
「お前が誘っといてなんだ? 行きたくないのか?」
「あはは、悪い悪い。まさか真ちゃんがあっさりOKしてくれるなんて思ってなかったからさ。 よっしゃ! じゃぁ、さっさと行こうぜ!」
まさかの一発OKにテンションが上がり、ウキウキしながらカバンを肩に担ごうとしたその瞬間。
いきなり真ちゃんの携帯が盛大な着信音を奏で始めた。
「む? すまない。少し待っていろ」
「えー、ココで出ればいいじゃん」
「赤司からなのだよ」
別に俺は赤司だろうが青峰だろうが黒子だろうが、全然気にしないのに、真ちゃんは携帯片手にそそくさと教室を出て行ってしまう。
ちぇっ、なんだよ。コソコソと……俺に聞かれたくない話か?
つか、黒子や黄瀬君ならわかるとして、赤司が真ちゃんになんの用だろう?
こんなの、ヤキモチ妬いてるみたいでみっともないけど、早く出かけたかった俺としてはこの一分一秒が面白くない。
モヤモヤした気持ちのまま待っていると、不意に廊下の方から他のクラスメートが声をかけてきた。
「高尾ー。お前にお客さんだぜ」
「は、客? こんな時間に客ってなんなんだよ――おぶっ!?」
廊下の方を振り向こうとした瞬間、背後から手が伸びてきて突然視界が真っ暗になった。
「だーれだ?」
「――っ!? は? えっ? なんっ!?」
意味がわからないまま目隠しをされ、何処かで聞いたことがある声が耳元に響く。
「ちょっ宮地さん? それとも木村さんっすか?」
「あら、アタシの声、忘れちゃったの?」
耳元に息を吹きかけるように囁かれて、ぞわぞわっと全身の毛が総毛立つ。
アタシって……俺の知り合いにこんな声の女子いたか? 悪ふざけする男友達なら沢山いるけど誰だかわかんねぇ。
そもそも俺に気づかれず背後に回るなんてタダモンじゃねぇ。
でも確かにこの声には聞き覚えが。
「降参っす! 誰かわっかんねーや」
「えー? ま、仕方ないわね」
小さな溜息と共にひやりとした手がゆっくりと外される。
恐る恐る振り向くと、そこにいたのは――。
「は? えっ、ちょまっ……ええっ!?」
濃い紫がかった長めの髪、日に焼けていない白い肌。一見女性に見えなくもない程整った容姿。
京都にいるはずのこの人がなんでココにいるんだ?
「高尾クンに会いたくて、来ちゃった♪ ウフッ」
語尾にハートマークを付けながら頬を撫でられ、ぞわっと背筋が凍りつく。
「ウフッってw み、実渕さん!? なんでココにいるんっすか!?」
「よかった。覚えててくれたのね」
「や、覚えるも何も忘れらんねぇし」
いろんな意味で。実力の差を見せつけられて、苦い思いをしたのはつい3ヶ月ほど前だ。
そう簡単に忘れられるほど俺は人間出来ちゃいねぇ。
「高尾、モテるなー。そんな美人と知り合いなんて」
ニヤニヤと笑いながら野次を飛ばすクラスメートを睨みつける。そんなに羨ましいなら代わってやるよ! と、言ってやりたかったけれど、「お楽しみを邪魔しちゃ悪いから得るわ」なんて、言いながら教室を出て行ってしまった。
薄情なやつだよ。全く!
実は俺、結構こういうタイプは苦手だったりする。まして、一度対戦して実力の差を見せつけられたばかりだったから特にその意識が強い。
「美人だなんて、嬉しいこと言ってくれるわね、あの子。でも、タイプじゃないわ」
なんて言いながら見つめられて反射的に視線を逸してしまった。
「へ、へぇ……。そうっすか」
「つれない返事ね。あたしのタイプ知りたくない?」
距離を取ろうとした俺の肩に腕が回り、強い力で引き寄せられる。
やべぇよガチだよこの人、なんかマジ怖いんだけど!
「別にいいっス。つか、俺用事あるんで……」
「アラ。遠慮しなくていいのに」
普通遠慮するっつーの!
逃げようとしたけれど、この人の握力パネェ! 体がビクとも動かない。
ジリジリと距離を詰められて冷たい汗が背筋を伝っていく。
何が怖いって、顔は涼しい顔して笑ってんのに目がマジなんだよ。
肉食獣が獲物を狙ってる時の、目を合わせたら喰われる! って思わせるような獰猛な色。
「あのっ、実渕さん……もうそろそろ真……緑間が戻ってくるかも知れないからこういうのはちょっと……」
「……困る?」
「う……ハイ」
「でも、付き合ってるわけじゃないんでしょう? 私が見る限り、貴方の片想いっぽいし」
「……ッ」
伺うように顔を覗き込まれて、言葉に詰まる。
「見込みないわよ 彼、見るからに真面目そうだし」
「……」
そんな事、言われなくたってわかってる。
「気付かれたら、側にいられなくなるんじゃない?」
「緑間には俺の気持ち伝える気は無いっす」
「アラ、じゃぁこの先ずっと片思いする気?」
そんなの辛いだけでしょう? と、言われ、きつい言葉が胸にグサリと突き刺さる。
「思い続けるより、思われる方がずっと楽よ」
そんなの、わかってる。わかってるけど、俺には気持ちを伝える勇気も、相棒というポジションを失う勇気もねぇんだよ。
「ねぇ、そんな苦しい恋なんてやめて、アタシにしときなさいよ」
俯いていた顎に指がかかり、強制的に上向かされた。
あっ! と、思ったときにはもう、目前に実渕さんが迫っていて。
「ちょっ! 実渕さ……っ!」
キスされる。 咄嗟に避けきれないと思った俺は堪らずギュッと目を瞑った。
「……何をしている?」
「!?」
聞きなれた声がしたと思ったら突然肩を強く後ろに引かれた。息がかかりそうな程近かった気配がスッと消える。
何事かと目を開けてみると、俺と実渕さんの間に怖いくらいにマジな顔をした真ちゃんが立っていて、実渕さんをすごい形相で睨みつけている。
「し、真ちゃんあのっ、これは――ッ」
「高尾は黙っていろ!」
「……ッ」
言い訳しようとした言葉をピシャリと遮られ、ひゃっと体が竦んだ。
なんかよくわかんねぇけど、真ちゃんすっげー怒ってる!
「赤司が探していましたよ。 もう直ぐ、ココに着くそうですが……」
「アラ、もうバレちゃったの。残念〜」
パチンとウインクを一つして立ち上がる実渕さん。
その言葉に真ちゃんがイラついたのがなんとなくだけどわかった。
「実渕さん。コイツは、俺のなので手を出さないでもらえますか」
眼鏡を押上げながら、はっきりとした口調がそう言葉を紡ぐ。
「えっ!? ちょっ、真ちゃんっ!? な、な――っ!?」
「アラ? そうなの? ふぅん」
そんなの聞いてねぇよ?? いつから俺、真ちゃんのものになったんだよ!?
まさかの発言に面食らって、顔がぶわっと火照っていくのがわかった。
そんな俺にチラリと視線を送り実渕さんが小さくはぁっと息を吐く。
「仕方ないわね。今回は大人しく引き下がってあげるけど……アタシ、諦めないから」
不気味な言葉を残し、ひらひらと手を振って軽やかに教室を出て行く実渕さんを呆然と見送り、ホッと胸をなでおろす。
「――。なぁ、俺っていつの間に真ちゃんのモノになったんだよ?」
「お前は俺の相棒なのだよ。自分でいつもそう言っているくせに何を惚けたことを言っている」
「…………!」
一瞬、何を言われたのかわからなかった。
けど、直ぐに真ちゃんの言う「俺のモノ」発言の真意に気付く。
「ぶっ! あははははっ」
「なぜそこで笑う!?」
「や、悪い、悪い。だって……ふはっ」
自分の勘違い(つか、多分実渕さんも勘違いしたんだと思う)が可笑しくて、つい、笑ってしまう。
「全く、なんなのだよ一体」
俺やっぱ真ちゃんの事、すっげー好きだわ。そういう鈍い所も全部ひっくるめて。
「俺、真ちゃんのそういうトコ好きだぜ」
「……フン。行くぞ高尾」
「ちょっ! 人の告白無視すんなって!」
冗談っぽくならいくらでも「好きだ」って言えるのに。
確かに実渕さんが言うように、片思いなんて辛くて苦しいモノなのかもしれない。
けど、それだけじゃなくて……。真ちゃんの言動一個に振り回されて無駄にドキドキしたりガッカリしたり。
そういうのも結構楽しいから、片思いだって案外悪いもんじゃねぇと思う。
「何をしている。行かないのか?」
「あー、待てって! 今行くからっ!」
思い続けるより、思われる方がずっと楽かも知んねぇけどさ、俺は当分このままでもいいかな。