No title
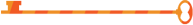
沿道には屋台がずらりと立ち並び多くの祭り客で賑わっているが、一本奥に入り込めばそこには表の喧騒が嘘のように静かな雑木林が広がっている。
人々のざわめきやお囃子の音色を何処か遠くに聞きながら、緑間は人気のない林の中を奥へ奥へと進んでいた。
辺りはすっかり闇に覆われ、沿道に飾られていた提灯の僅かな明かりが周囲を頼りなく照らしている。
「真ちゃん、ちょ、早いって。一体どうしたんだよ急に」
未だに事態が呑み込めていない高尾の様子に苛立ちを隠しきれず、半ば乱暴に手を離す。
「どうしたもこうしたもないのだよ。まったく。お前は俺をなんだと思っているんだ」
「え?」
「俺はお前が来たいって言ったからこんなトコまで来ているんだぞ! それなのに……宮地さんと一緒に行動するとか……冗談じゃない」
こんなのはただの子供じみたヤキモチだ。それは自分でもわかっている。
みっともないことを言っている自覚はあるが、それでも一度芽生えた感情は吐き出してしまわないと落ち着きそうにない。
「だいたい、なんで俺が宮地さんのグッズなんかの為にひと肌脱がないといけないんだ冗談じゃない」
案の定ぽかんと口を開けて聞いていた高尾の表情は、みるみるうちに歪んでいき、肩を震わせて笑いを堪えだした。
「何が可笑しい!?」
「い、いや……っだって、真ちゃんがヤキモチ妬くとか思ってなかったから……ぷぷっ」
目じりに涙まで浮かべながら笑われて、ますます腹が立ってくる
「……帰るぞ」
「おい、待てよ。冗談だって。つか、オレって真ちゃんにに随分愛されちゃってたんだな」
冗談めかして笑う高尾の表情が気に入らなくて、強引に肩を引き寄せるとすぐ側にあった大きな杉の木に押しつけた。
「今頃気付いたのか? 馬鹿め」
他ならぬ高尾が行きたいと言うので仕方なく来てやったのだ。
「だからお前は駄目なのだよ。他のヤツなんてどうでもいい。お前と二人っきりで見て回りたかったんだってなぜわからんのだ」
「ふはっ、真ちゃんがデレた」
「茶化すな!」
ポカリとデコを軽く小突いてやると高尾がおでこを押さえながら小さく呻いた後、クスリと笑った。
「へへっ、なんかすっげー嬉しい」
「デコ殴られんのが、か? 痛いのが趣味だったのか」
「ちげーし! だって真ちゃん、オレの事好きだって一回も言ってくれたことなかったし、普段冷たいから、もしかしたら好きだと思ってんのは俺だけなのかなってずっと不安だったんだぜ?……だから今、すっげー嬉しい」
はにかんだように笑いながら躊躇いがちに腕が回され、そっと寄り添うように体が密着する。
ふわりと香る石鹸の匂いが鼻腔を擽り鼓動がどきりと跳ね上がった。