No title
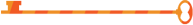
「口で説明するより、直接聴いた方が早いのだよ」
「?」
意味が分からずに首を傾げる高尾の目の前で、緑間はすぅっと息を吐き、眼鏡の位置を整えてから鍵盤に指を滑らせる。
綺麗な指先から奏でられるその曲は、高尾もよく知っている有名なラブソングだ。
バラード調の曲に合わせて、しっとりと歌い上げられぞわっと全身に鳥肌が立った。
――愛してるって言葉じゃ、足りないくらいに君が好き――。
何度も繰り返されるフレーズに胸がグッと苦しくなる。
なんで今、こんな曲を自分に聞かせるのか? それが理解できない。
聞かせるべきは自分なんかじゃなくて、あの彼女ではないのか?
「……っ」
そっと目を閉じると緑間と出会ってからの思い出が次から次へと走馬灯のように脳裏を駆けた。
ふざけながら思いを伝えた時の、緑間の驚いたような表情。目をこれでもかと言わんばかりに見開いて、僅かに頬を染めていた。
直ぐに逸らされてしまった視線が可笑しくて、ゲラゲラと笑ってしまい、彼を怒らせたのを覚えている。
幸せだった日々を思い出し、鼻の奥がツンと痛んだ。目頭が熱くなり、慌てて拳で目を押さえつける。
「……なんで、俺にこんな歌を聞かせたりするんだよ……」
最後まで聞き終えて、声を詰まらせながら問うと、緑間が身体の向きを変えた。
向き合うような体勢になり真っ直ぐに彼の瞳を見つめ返す。
「オレは、最近の歌はよくわからないのだよ……」
「それは知ってる」
緑間は基本、クラッシクか、ジャズしか聞かない。流行ものには疎くて、以前自分が持っていた音楽を聞かせた時には良さがわからないとバッサリ切り捨てられた記憶がある。
「加えて、自分の感情を素直に伝える事も苦手だ」
「……」
「伴奏を引き受けた時、合唱部の奴らに言われたのだよ。弾き語りしたらきっと似合うんじゃないかと。その時、ふと思ったのだよ。普段言えない思いを伝えるのには充分効果的ではないのか、と」
「それって、つまり……」
緑間の言葉を一つ一つ噛み砕いていったらとんでもないことを言われている気がして、思わず喉が鳴った。
緑間が足繁く通っていたのは、自分にこの歌を聴かせるため――?
「でも、それだったらなんで教えてくれなかったんだよ?」
「本人に種明かしをしたら何の意味もないだろう馬鹿め!」
「ハハッ。なんだよ、それ……」
緑間が言う事は筋が通っているような気がしたが、どこか釈然としない。
二人っきりになる理由が仮に、今言ったとうりだとしても手を握りあったり、自分の誘いを断ってまで一緒に帰ったりする必要はないのではないか。
「じゃぁ、昨日のアレはどう説明するつもりだよ」
それは、と緑間は言葉に詰まった。その「間」に微妙な苛立ちを覚えたが、ここで感情的になってはいけないと思い、高尾はぐっと堪えて緑間の次の言葉を待った。