
01
※この話は「トリカゴ」管理人のある様より頂いたネタを元に作った話となります。
*
お口を閉じて。しゃべってはだめ。
お外の人は怖い怖いバケモノだから。
何も言わないで。聞きたくないの。
部屋中に飛び散ったガラス片が、天窓から差し込む三日月の月光を乱反射している中、三対の鋭い瞳が、薄暗い部屋の中にぼうっと浮かび上がっている。床の大理石には古代ルーン文字で描かれた魔法陣が刻まれ、その周囲にはランプの代わりのロウソクがいくつも灯されている。まるで三百年も昔から刻が止まっているようなその部屋の奥のベッドには、絹のようなぬばたまの髪を震わせて怯える、幼い少女の姿があった。その手足は縄できつく縛られている。
この人たちは、悪い人。
外から来た、怖い怖い、バケモノたち。
割れた窓から吹き込んだ風が、ベッドの脇に灯されたロウソクを揺らし、少女を見つめる三対の瞳に映り込んだ橙色の炎が、緊迫した空気の中チロチロと踊る。
「捕まえてから一言もしゃべりゃあしねえ」
眉のない長身の強面の男が大きな手を少女の頭にぽんと乗せ、恐る恐る顔を上げを少女をぐいと覗き込んで「なあ?」と追い打ちのように問い掛ける。
「喋れないのか?」
薄闇から、身の毛のよだつほどの怜悧な印象を放つ黒髪の男が、姿を現す。ベッドの側にあるロウソクが瞳の中に映りこんでまるで暖炉のように炎がちらちらとまたたいていたが、その目には全く熱がなかった。
「オレが知るかよ」
少女の頭をぽすぽすと叩いてから後ろに戻った眉なしの男を横目に見ながら、黒髪の男がずいと前に足を進める。男の冷淡な瞳の中に、口を真一文字に結ぶ少女の顔が映り込んだ。
答えろ、と促されているのだと少女はすぐに理解したが、それでも、沈黙を守った。喋れない。そういうことにしておこうとの考えだった。
「文字は分かるか?」
男はコートのポケットから本を取り出し表紙を少女に向ける。そこには『レイチェルの憂鬱』と、共通語として浸透しているハンター文字でタイトルが書かれていた。
そのタイトルを見つめる少女の表情に変化はない。しかし、その小さな頭の中では「どうしよう」との言葉が忙しなく駆け巡っていた。
どうしよう。どうしよう。どうしよう。
判断を間違えればあたしは殺されてしまう。
どうしよう。絶体絶命だ。
無知を装い素知らぬ振りを続けるべきか、それとも偽りをせず男の問い掛けに従順に答えるべきか、何が最善か分からない中、少女は一つの選択をし、口を閉じたまま首をこてんと傾げた。
「シャル、パクはいつ着くと言っていた?」
少女の「文字を知らない」とのジェスチャーに男は落胆を見せるわけでもなく、ゆっくりと少女から目を逸らすと、自身の背後に控えていた金髪の長身の男へと声をかけた。
「明日のお昼頃だって」
鬱屈とした建物には不釣り合いなしゃきしゃきとした明るい声が部屋に落ち、シャルと呼ばれた金髪の男は、にんまりとした笑みのまま少女に歩み寄る。ロウソクの炎に照らされはっきりと浮かび上がった男の顔は、鍛えられた二の腕からは想像し難い、童顔と言って差し支えのないほど幼く見えた。
その後ろから黒い目の男に探るような目付きで見られ、少女は逸らしたら負けだと心の内の動揺を悟られないよう必死になりながら漆黒の瞳を見返した。
「――……っ」
少女の気丈な態度に、黒い目の男が初めて笑みを見せた。しかしそれは笑みといっても口角を吊り上げただけの薄い笑みで、怖いと思うわけではないのになぜか背中にゾクゾクとした悪寒を覚え、少女は思わず出そうになった声を辛うじて飲み込んだ。
その緊張は、黒い目の男が立ち上がってシャルと呼ばれた男の元へ背を返して歩いていっても続き、少女はその後ろ姿をずっと凝視し続けていた。
「団長、こいつどうすんだ?」
頭上からふいに男の大きな声が降り、頭頂に温かい手が置かれる。少女がまるで石化が解けたようなハッとした顔で上を見上げると、そこには眉なし男がいた。砕けた感じで少女の頭を撫でているその男は、数メートル先にいる黒い目の男へと信頼と敬愛に満ちた目を向けていた。
この男がリーダーなのだろう。団長、と呼ばれていることからも間違いない、と思いながら少女は黒い目の男の背に掲げられている逆十字をじっと見つめる。
神への反逆の証とも悪魔崇拝の象徴とも言えるその逆十字の紋様を、少女はしばしばこの部屋で目にしていた。それはこの部屋に訪れる黒いフードを目深に被った男たちの首から下がっていたり、差し入れられる銀食器の裏に刻まれていたりと様々であったが、それは少女の身近にあるデザインのひとつと言えた。
しかし、男の背にある逆十字を目にした少女の内に広がったのは、親近感でも安堵でもなく、畏怖の念だけであった。
怖い怖いバケモノたち。
災厄を持ってくる、悪いモノ。
信じてはいけない。
心を許してはいけない。
特に、あの黒い目のバケモノには――。
「どうもしない。なにか要求があるようなら取り次げ。少し寝る」
振り返りもせずにそう答えると、黒い目の男は三人を室内に残したまま部屋の扉だった枠から姿を消した。
「っんだよ、めんどくせーな」
嫌々ながらもどこか親しみのある声が盛大なため息と共に落ちた時、頭上に乗せられていた大きな手の質量がふわりとなくなり、少女は再度上を見上げた。
「なんかあったら誰でもいいから呼べよ。あー、しゃべれないんだっけか」
少女の視線を感じたからだろうか、男は頭を掻きながら困った声色でひとり言のように呟くと、きょろきょろと辺りを見渡した後、拾い上げた瓦礫を少女の足元へと置いた。
「これ蹴ったらいいからな」
怖い人相とは裏腹の優しい声色に、少女の頬から緊張が抜ける。合図をしない限り、しばらくは何も起こらないということだろう。
三人の男が暗闇に紛れるほど離れたのを見届けてから、少女は縛られた体のままベッドに倒れこんだ。極度の緊張で疲弊していた身体は、直ぐに安寧の睡眠へと少女をいざなった。
*
ザナルカンド公国ヤルタイナ地方にあるリオングラードは、昔から裕福な地域として名を馳せていた。16世紀にペストが大流行した時も、17世紀の魔女狩りが横行した時も、18世紀の世界的大飢饉が起こった時も、リオングラードは富んでいた。肥沃な大地がもたらす豊穣の実りがその地に興隆と富とをもたらしていると長年考えられていたが、近年の研究で、リオングラードの土地はそれほど良い土壌ではないと明らかになっていた。
しかしながら、乏しい土地にも関わらずリオングラードは毎年豊作を迎える。その結果、リオングラードには人が集まり、街は広がり、商売は盛んになり、長い年月を経た今なおこの地は交易地として賑わっている。
また、リオングラードはその有益性により、古来から渇望の地として周辺諸国から狙われ続けていたが、戦果の報酬として譲渡されるなどして領主や国主が変わろうとも、実際にリオングラードで血が流れたことは一度としてなかった。
戦火の多いヨルビアン大陸においてそれは稀有なことであり、人々は豊穣と平和をもたらすこの地を、特別な土地だとして「神に愛された地」と呼んだ。そして、リオングラードが神に愛された土地であるのはこの地に「神から遣わされた聖霊」が宿っているからだと信じ、その精霊を信仰する独自の宗教体系を作り上げた。
その聖霊は『テレジア』と呼ばれ、何か良い事が起これば聖霊『テレジア』へその加護を感謝し、何か悪い事が起きれば『テレジア』への信仰が足りなかったとさらに祈る。そんな独特の風習が今なおリオングラードには息づいている。
中でもリオングラードの名士である『ワーグナー』一族は熱心に聖霊『テレジア』を祀っており、リオングラード内外にいくつも礼拝堂を建てていた。
クロロ・シャルナーク・フィンクスが侵入した建物は、そんな礼拝堂のひとつであった。
*
「団長、今到着したわ。その喋れない少女とやらの場所に案内してちょうだい」
礼拝堂に侵入した次の日の午後、タイトなスーツに身を包んだ豊満な肉体な女性が、カツカツとヒールを鳴らして現れた。
彼女の名前はパクノダ。クロロ率いる幻影旅団の一員で、手に触れた対象の原記憶を読む能力を有していた。
「こっちだ」
色褪せたステンドグラスの嵌められた礼拝堂の中で長椅子に座っていたクロロは、パクノダの登場に読んでいた本を閉じると立ち上がって右手奥にある古びた扉を開け、その先にある廊下へと歩いて行った。
祭司の待機室や談話室と思われる質素な部屋を通り抜けて、一見では扉と認識できないような木枠を下から押し上げて中に入り、さらに奥にある細い階段を登り廊下を歩き、そうして辿り着いた部屋の前で足を止めた。
「ここだ」
「これは、随分と……」
さながら映画館の映写室のように礼拝堂からは見えにくい場所に位置しているそこは、入り口が巧妙に隠されていることも相まって、長年この礼拝堂に通う信者でさえも部屋の存在に気づけないような入り組んだ造りになっていた。
「どうだ」
「どうもこうも、変わりゃしねえよ」
クロロは室内にいるフィンクスへと声を掛けている。
そんな中、破壊された扉をくぐったパクノダの目に入ったのは、部屋の中央に刻まれた禍々しい魔法陣だった。切り出した岩を積み重ねて造られた、年季の入った黄土色の岩壁と相まって、その部屋はまるで中世の地下牢のような陰気な空気が立ち込めていた。
「これは……」
陰鬱とした部屋の雰囲気とは対照的に、奥にあるベッドには人形やぬいぐるみ、絵本などの女児用玩具が、数え切れないほど置かれている。そのアンバランスさが、その部屋の異様さをさらに強めていた。
「初めまして。私はパクノダよ」
手足を縛られながらもベッドの縁にちんまりと座っている少女に、パクノダはにこやかな笑顔で話し掛ける。しかし、少女は顔を上げて濃緑色の瞳を向けるだけで何も言葉を返さなかった。
「さてと、団長。私は何を尋ねれば良いのかしら?」
「お前は何者か、だ」
「分かったわ。ねえ、あなた。あなたは何者かしら?」
パクノダはそう言って少女の肩に手をそっと置いた。パクノダは触れることにより対象者の心を読むことができる。パクノダが読む記憶は対象者の記憶の底に沈む『原記憶』であり、それを読めるということはつまり彼女の前では一切の偽証が不可能だということだった。
「う……ん。団長、これは少し難しいわ」
「どういう意味だ」
「彼女は『自分が何者であるか』、把握していないようだわ。自分の名前も、年齢も、どうしてこの場所にいるのかも分かっていないみたい」
「では、どれくらいの間ここにいるのか、聞け」
「……この場所には時間を記録するものが一切ないから、彼女も何年何ヶ月この場所に居るのか分かっていないわ。ただ、この場所に連れて来られた時の姿は今より三つくらい幼いわ」
「いつもここで何をしている?」
「何もこうも……ここではいつも本を読んだりお人形遊びをしたりその小さな窓から外を見たり……そんなことを毎日繰り返しているわ。……あ、待って。時折黒いフードを被った人たちが赤ワインと一切れのパンを持ってこの部屋にやって来るみたい。その床に刻まれた魔法陣にロウソクを灯して何やら呪文を唱えているわ」
「そいつらは何者だ?」
「……ここにお祈りに来る人達、って言ってるわ。それと、『ワーグナー』と」
「ワーグナー? この礼拝堂を建てた一族だな。他には何と?」
「……何も。団長、この子からは取り留めのない事柄しか浮かんでこない。この子は何も知らないわ」
「そうか。では最後に――、精霊『テレジア』とは何だ?」
「……この地を守護する精霊様、皆の願いを聞き入れて叶えてくれる尊いお方。……この街で呆れるほど聞いてきた答えと同じだわ」
そう言って頭を振りかぶると、パクノダは少女から手を離した。その顔には落胆の色が浮かんでいる。
「何だよ、ここまで来てハズレだったのかよ」
パクノダと団長の様子を後ろで見ていたフィンクスがぶっきらぼうに言う。その言葉に、シャルナークが異論を唱えた。
「ちょっと待ってよ、ハズレなはずないんだ。ねえ、団長? オレは確かに情報を掴んだ。このリオングラードの異様な発展と、それを統べるワーグナー一族の興隆。そして、それを守護する精霊『テレジア』の存在。リオングラードの発展はただ単に運が良かったなんて話じゃない、砂漠で密林を育てるような不自然さだ。だからこそ、それを支えるような存在が――、念具や宝具、特異な念が絡んでいる可能性があるってことでこの場所に来たじゃないか」
自身の情報収集能力に並々ならぬ自負を持っているシャルナークは、自分の集めた情報にケチを付けられたのが癪だったのだ。シャルナークはさらに言葉を続ける。
「そして、それはビンゴだった。街外れにある寂れた礼拝堂にこんな強固な隠し部屋があるのだっておかしいし、そこに人がいるってのもおかしい。この部屋にもこいつにも絶対に何かあるはずだよ、ねえ、団長?」
矢継ぎ早に畳み掛けるシャルナークにクロロは口元に手を当てて数秒考え込み、そして、そっと口を開いた。
「不可解な点がいくつかある。まず一つ目は、この部屋の生活感の無さだ。生活感が無いのは監禁されているからとも言えるが、食糧に当たるものがこの部屋には一切無いのは不自然に思える。毎日これに食事を与えに来る人間が居るのかとも思ったが、一日ここに居てもそれらしき人間は訪れなかった。週に一度日曜日の礼拝時に仕入れるとしても、今日は水曜日、あと四日分の食糧がこの部屋になければいけないのに、それがここにはない。それと、フィンクス」
「ん、なんだ?」
「それを見張っている間、そいつは排尿排便等の生理的現象を催したか?」
「いんや。そういや無かったな、置いた石を蹴ることも無かったし」
「監禁部屋にも関わらず、この部屋には排尿排便に対応する物が存在しない。そこの窓からしている可能性もあるが、それの身長では届かない位置にあるし、第一嵌め込まれたあの窓を道具なしに開閉することはそれには無理だ。そう――、それには人間としての機能が欠如している」
「でも、団長、この子は人間よ? オーラで具現化された人間型の念獣ではないし、体温も心臓の鼓動もあるわ」
「――そう、だから不可解だと言っている。そして、不可解な点の二つ目は、この床に刻まれている魔法陣と古代ルーン文字だ。そう言ったデザインだと一蹴しても良いが、こんな隠し部屋にそんなデザインを施す意味があるとは思えないし、微弱だがこれからオーラを感じる。現在使用されている念文字とは異なるが、オレは、このルーン文字が念文字と同等の能力を持っているのではないかと予測している」
「ん?そうなのか? 団長、これにどんな意味があるってんだよ?」
フィンクスが床をぐりぐりと踏みながらクロロに問い掛ける。
「それは解析中だ。情報が足りな過ぎる。そして、不可解な点の最後だが……」
そこで言葉を切るとクロロはコツコツと音を鳴らして少女に歩み寄り、じろりとその怜悧な瞳を少女に向ける。
「こいつは何かを隠している――」
その言葉に少女がビクリと身体を震わせた。唇は小さくわななき、目は落ち着きなく左右に揺れている。
「では、私の能力で――」
前に進もうとするパクノダをクロロは手で制止して言う。
「いい、パクノダ。漠然とした質問をしたところで答えは先ほどのような結果になるだけだ。もっと真理に近づくような質問をしなければ意味がない。それに今日は水曜日だ。次の礼拝の日曜日まで丸三日ある。シャル、礼拝の時以外、ここに人は来ない。そうだな?」
「え? ああ、そうだよその通りだよ、その辺は三カ月かけて調べたんだから間違いない」
「――だそうだ。時間はまだたっぷりある。こいつと、この部屋のカラクリについて、楽しい楽しい謎解きと行こうじゃないか」
そう言ってクロロはにんまりと笑った。その笑みは見る者全ての背筋を凍えさせるような冷たさがあったにも関わらず、そこにはまるで悪魔の微笑みのように完成された美しさがあった。
部屋の温度が一瞬で数度下がった気がして、少女は黒曜石の瞳の奥にチラリと映る獰猛な光にただただ震え、精霊『テレジア』へと祈りを捧げるばかりであった。
第1話、完
[ *prev | back | next# ]
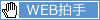
*
お口を閉じて。しゃべってはだめ。
お外の人は怖い怖いバケモノだから。
何も言わないで。聞きたくないの。
部屋中に飛び散ったガラス片が、天窓から差し込む三日月の月光を乱反射している中、三対の鋭い瞳が、薄暗い部屋の中にぼうっと浮かび上がっている。床の大理石には古代ルーン文字で描かれた魔法陣が刻まれ、その周囲にはランプの代わりのロウソクがいくつも灯されている。まるで三百年も昔から刻が止まっているようなその部屋の奥のベッドには、絹のようなぬばたまの髪を震わせて怯える、幼い少女の姿があった。その手足は縄できつく縛られている。
この人たちは、悪い人。
外から来た、怖い怖い、バケモノたち。
割れた窓から吹き込んだ風が、ベッドの脇に灯されたロウソクを揺らし、少女を見つめる三対の瞳に映り込んだ橙色の炎が、緊迫した空気の中チロチロと踊る。
「捕まえてから一言もしゃべりゃあしねえ」
眉のない長身の強面の男が大きな手を少女の頭にぽんと乗せ、恐る恐る顔を上げを少女をぐいと覗き込んで「なあ?」と追い打ちのように問い掛ける。
「喋れないのか?」
薄闇から、身の毛のよだつほどの怜悧な印象を放つ黒髪の男が、姿を現す。ベッドの側にあるロウソクが瞳の中に映りこんでまるで暖炉のように炎がちらちらとまたたいていたが、その目には全く熱がなかった。
「オレが知るかよ」
少女の頭をぽすぽすと叩いてから後ろに戻った眉なしの男を横目に見ながら、黒髪の男がずいと前に足を進める。男の冷淡な瞳の中に、口を真一文字に結ぶ少女の顔が映り込んだ。
答えろ、と促されているのだと少女はすぐに理解したが、それでも、沈黙を守った。喋れない。そういうことにしておこうとの考えだった。
「文字は分かるか?」
男はコートのポケットから本を取り出し表紙を少女に向ける。そこには『レイチェルの憂鬱』と、共通語として浸透しているハンター文字でタイトルが書かれていた。
そのタイトルを見つめる少女の表情に変化はない。しかし、その小さな頭の中では「どうしよう」との言葉が忙しなく駆け巡っていた。
どうしよう。どうしよう。どうしよう。
判断を間違えればあたしは殺されてしまう。
どうしよう。絶体絶命だ。
無知を装い素知らぬ振りを続けるべきか、それとも偽りをせず男の問い掛けに従順に答えるべきか、何が最善か分からない中、少女は一つの選択をし、口を閉じたまま首をこてんと傾げた。
「シャル、パクはいつ着くと言っていた?」
少女の「文字を知らない」とのジェスチャーに男は落胆を見せるわけでもなく、ゆっくりと少女から目を逸らすと、自身の背後に控えていた金髪の長身の男へと声をかけた。
「明日のお昼頃だって」
鬱屈とした建物には不釣り合いなしゃきしゃきとした明るい声が部屋に落ち、シャルと呼ばれた金髪の男は、にんまりとした笑みのまま少女に歩み寄る。ロウソクの炎に照らされはっきりと浮かび上がった男の顔は、鍛えられた二の腕からは想像し難い、童顔と言って差し支えのないほど幼く見えた。
その後ろから黒い目の男に探るような目付きで見られ、少女は逸らしたら負けだと心の内の動揺を悟られないよう必死になりながら漆黒の瞳を見返した。
「――……っ」
少女の気丈な態度に、黒い目の男が初めて笑みを見せた。しかしそれは笑みといっても口角を吊り上げただけの薄い笑みで、怖いと思うわけではないのになぜか背中にゾクゾクとした悪寒を覚え、少女は思わず出そうになった声を辛うじて飲み込んだ。
その緊張は、黒い目の男が立ち上がってシャルと呼ばれた男の元へ背を返して歩いていっても続き、少女はその後ろ姿をずっと凝視し続けていた。
「団長、こいつどうすんだ?」
頭上からふいに男の大きな声が降り、頭頂に温かい手が置かれる。少女がまるで石化が解けたようなハッとした顔で上を見上げると、そこには眉なし男がいた。砕けた感じで少女の頭を撫でているその男は、数メートル先にいる黒い目の男へと信頼と敬愛に満ちた目を向けていた。
この男がリーダーなのだろう。団長、と呼ばれていることからも間違いない、と思いながら少女は黒い目の男の背に掲げられている逆十字をじっと見つめる。
神への反逆の証とも悪魔崇拝の象徴とも言えるその逆十字の紋様を、少女はしばしばこの部屋で目にしていた。それはこの部屋に訪れる黒いフードを目深に被った男たちの首から下がっていたり、差し入れられる銀食器の裏に刻まれていたりと様々であったが、それは少女の身近にあるデザインのひとつと言えた。
しかし、男の背にある逆十字を目にした少女の内に広がったのは、親近感でも安堵でもなく、畏怖の念だけであった。
怖い怖いバケモノたち。
災厄を持ってくる、悪いモノ。
信じてはいけない。
心を許してはいけない。
特に、あの黒い目のバケモノには――。
「どうもしない。なにか要求があるようなら取り次げ。少し寝る」
振り返りもせずにそう答えると、黒い目の男は三人を室内に残したまま部屋の扉だった枠から姿を消した。
「っんだよ、めんどくせーな」
嫌々ながらもどこか親しみのある声が盛大なため息と共に落ちた時、頭上に乗せられていた大きな手の質量がふわりとなくなり、少女は再度上を見上げた。
「なんかあったら誰でもいいから呼べよ。あー、しゃべれないんだっけか」
少女の視線を感じたからだろうか、男は頭を掻きながら困った声色でひとり言のように呟くと、きょろきょろと辺りを見渡した後、拾い上げた瓦礫を少女の足元へと置いた。
「これ蹴ったらいいからな」
怖い人相とは裏腹の優しい声色に、少女の頬から緊張が抜ける。合図をしない限り、しばらくは何も起こらないということだろう。
三人の男が暗闇に紛れるほど離れたのを見届けてから、少女は縛られた体のままベッドに倒れこんだ。極度の緊張で疲弊していた身体は、直ぐに安寧の睡眠へと少女をいざなった。
*
ザナルカンド公国ヤルタイナ地方にあるリオングラードは、昔から裕福な地域として名を馳せていた。16世紀にペストが大流行した時も、17世紀の魔女狩りが横行した時も、18世紀の世界的大飢饉が起こった時も、リオングラードは富んでいた。肥沃な大地がもたらす豊穣の実りがその地に興隆と富とをもたらしていると長年考えられていたが、近年の研究で、リオングラードの土地はそれほど良い土壌ではないと明らかになっていた。
しかしながら、乏しい土地にも関わらずリオングラードは毎年豊作を迎える。その結果、リオングラードには人が集まり、街は広がり、商売は盛んになり、長い年月を経た今なおこの地は交易地として賑わっている。
また、リオングラードはその有益性により、古来から渇望の地として周辺諸国から狙われ続けていたが、戦果の報酬として譲渡されるなどして領主や国主が変わろうとも、実際にリオングラードで血が流れたことは一度としてなかった。
戦火の多いヨルビアン大陸においてそれは稀有なことであり、人々は豊穣と平和をもたらすこの地を、特別な土地だとして「神に愛された地」と呼んだ。そして、リオングラードが神に愛された土地であるのはこの地に「神から遣わされた聖霊」が宿っているからだと信じ、その精霊を信仰する独自の宗教体系を作り上げた。
その聖霊は『テレジア』と呼ばれ、何か良い事が起これば聖霊『テレジア』へその加護を感謝し、何か悪い事が起きれば『テレジア』への信仰が足りなかったとさらに祈る。そんな独特の風習が今なおリオングラードには息づいている。
中でもリオングラードの名士である『ワーグナー』一族は熱心に聖霊『テレジア』を祀っており、リオングラード内外にいくつも礼拝堂を建てていた。
クロロ・シャルナーク・フィンクスが侵入した建物は、そんな礼拝堂のひとつであった。
*
「団長、今到着したわ。その喋れない少女とやらの場所に案内してちょうだい」
礼拝堂に侵入した次の日の午後、タイトなスーツに身を包んだ豊満な肉体な女性が、カツカツとヒールを鳴らして現れた。
彼女の名前はパクノダ。クロロ率いる幻影旅団の一員で、手に触れた対象の原記憶を読む能力を有していた。
「こっちだ」
色褪せたステンドグラスの嵌められた礼拝堂の中で長椅子に座っていたクロロは、パクノダの登場に読んでいた本を閉じると立ち上がって右手奥にある古びた扉を開け、その先にある廊下へと歩いて行った。
祭司の待機室や談話室と思われる質素な部屋を通り抜けて、一見では扉と認識できないような木枠を下から押し上げて中に入り、さらに奥にある細い階段を登り廊下を歩き、そうして辿り着いた部屋の前で足を止めた。
「ここだ」
「これは、随分と……」
さながら映画館の映写室のように礼拝堂からは見えにくい場所に位置しているそこは、入り口が巧妙に隠されていることも相まって、長年この礼拝堂に通う信者でさえも部屋の存在に気づけないような入り組んだ造りになっていた。
「どうだ」
「どうもこうも、変わりゃしねえよ」
クロロは室内にいるフィンクスへと声を掛けている。
そんな中、破壊された扉をくぐったパクノダの目に入ったのは、部屋の中央に刻まれた禍々しい魔法陣だった。切り出した岩を積み重ねて造られた、年季の入った黄土色の岩壁と相まって、その部屋はまるで中世の地下牢のような陰気な空気が立ち込めていた。
「これは……」
陰鬱とした部屋の雰囲気とは対照的に、奥にあるベッドには人形やぬいぐるみ、絵本などの女児用玩具が、数え切れないほど置かれている。そのアンバランスさが、その部屋の異様さをさらに強めていた。
「初めまして。私はパクノダよ」
手足を縛られながらもベッドの縁にちんまりと座っている少女に、パクノダはにこやかな笑顔で話し掛ける。しかし、少女は顔を上げて濃緑色の瞳を向けるだけで何も言葉を返さなかった。
「さてと、団長。私は何を尋ねれば良いのかしら?」
「お前は何者か、だ」
「分かったわ。ねえ、あなた。あなたは何者かしら?」
パクノダはそう言って少女の肩に手をそっと置いた。パクノダは触れることにより対象者の心を読むことができる。パクノダが読む記憶は対象者の記憶の底に沈む『原記憶』であり、それを読めるということはつまり彼女の前では一切の偽証が不可能だということだった。
「う……ん。団長、これは少し難しいわ」
「どういう意味だ」
「彼女は『自分が何者であるか』、把握していないようだわ。自分の名前も、年齢も、どうしてこの場所にいるのかも分かっていないみたい」
「では、どれくらいの間ここにいるのか、聞け」
「……この場所には時間を記録するものが一切ないから、彼女も何年何ヶ月この場所に居るのか分かっていないわ。ただ、この場所に連れて来られた時の姿は今より三つくらい幼いわ」
「いつもここで何をしている?」
「何もこうも……ここではいつも本を読んだりお人形遊びをしたりその小さな窓から外を見たり……そんなことを毎日繰り返しているわ。……あ、待って。時折黒いフードを被った人たちが赤ワインと一切れのパンを持ってこの部屋にやって来るみたい。その床に刻まれた魔法陣にロウソクを灯して何やら呪文を唱えているわ」
「そいつらは何者だ?」
「……ここにお祈りに来る人達、って言ってるわ。それと、『ワーグナー』と」
「ワーグナー? この礼拝堂を建てた一族だな。他には何と?」
「……何も。団長、この子からは取り留めのない事柄しか浮かんでこない。この子は何も知らないわ」
「そうか。では最後に――、精霊『テレジア』とは何だ?」
「……この地を守護する精霊様、皆の願いを聞き入れて叶えてくれる尊いお方。……この街で呆れるほど聞いてきた答えと同じだわ」
そう言って頭を振りかぶると、パクノダは少女から手を離した。その顔には落胆の色が浮かんでいる。
「何だよ、ここまで来てハズレだったのかよ」
パクノダと団長の様子を後ろで見ていたフィンクスがぶっきらぼうに言う。その言葉に、シャルナークが異論を唱えた。
「ちょっと待ってよ、ハズレなはずないんだ。ねえ、団長? オレは確かに情報を掴んだ。このリオングラードの異様な発展と、それを統べるワーグナー一族の興隆。そして、それを守護する精霊『テレジア』の存在。リオングラードの発展はただ単に運が良かったなんて話じゃない、砂漠で密林を育てるような不自然さだ。だからこそ、それを支えるような存在が――、念具や宝具、特異な念が絡んでいる可能性があるってことでこの場所に来たじゃないか」
自身の情報収集能力に並々ならぬ自負を持っているシャルナークは、自分の集めた情報にケチを付けられたのが癪だったのだ。シャルナークはさらに言葉を続ける。
「そして、それはビンゴだった。街外れにある寂れた礼拝堂にこんな強固な隠し部屋があるのだっておかしいし、そこに人がいるってのもおかしい。この部屋にもこいつにも絶対に何かあるはずだよ、ねえ、団長?」
矢継ぎ早に畳み掛けるシャルナークにクロロは口元に手を当てて数秒考え込み、そして、そっと口を開いた。
「不可解な点がいくつかある。まず一つ目は、この部屋の生活感の無さだ。生活感が無いのは監禁されているからとも言えるが、食糧に当たるものがこの部屋には一切無いのは不自然に思える。毎日これに食事を与えに来る人間が居るのかとも思ったが、一日ここに居てもそれらしき人間は訪れなかった。週に一度日曜日の礼拝時に仕入れるとしても、今日は水曜日、あと四日分の食糧がこの部屋になければいけないのに、それがここにはない。それと、フィンクス」
「ん、なんだ?」
「それを見張っている間、そいつは排尿排便等の生理的現象を催したか?」
「いんや。そういや無かったな、置いた石を蹴ることも無かったし」
「監禁部屋にも関わらず、この部屋には排尿排便に対応する物が存在しない。そこの窓からしている可能性もあるが、それの身長では届かない位置にあるし、第一嵌め込まれたあの窓を道具なしに開閉することはそれには無理だ。そう――、それには人間としての機能が欠如している」
「でも、団長、この子は人間よ? オーラで具現化された人間型の念獣ではないし、体温も心臓の鼓動もあるわ」
「――そう、だから不可解だと言っている。そして、不可解な点の二つ目は、この床に刻まれている魔法陣と古代ルーン文字だ。そう言ったデザインだと一蹴しても良いが、こんな隠し部屋にそんなデザインを施す意味があるとは思えないし、微弱だがこれからオーラを感じる。現在使用されている念文字とは異なるが、オレは、このルーン文字が念文字と同等の能力を持っているのではないかと予測している」
「ん?そうなのか? 団長、これにどんな意味があるってんだよ?」
フィンクスが床をぐりぐりと踏みながらクロロに問い掛ける。
「それは解析中だ。情報が足りな過ぎる。そして、不可解な点の最後だが……」
そこで言葉を切るとクロロはコツコツと音を鳴らして少女に歩み寄り、じろりとその怜悧な瞳を少女に向ける。
「こいつは何かを隠している――」
その言葉に少女がビクリと身体を震わせた。唇は小さくわななき、目は落ち着きなく左右に揺れている。
「では、私の能力で――」
前に進もうとするパクノダをクロロは手で制止して言う。
「いい、パクノダ。漠然とした質問をしたところで答えは先ほどのような結果になるだけだ。もっと真理に近づくような質問をしなければ意味がない。それに今日は水曜日だ。次の礼拝の日曜日まで丸三日ある。シャル、礼拝の時以外、ここに人は来ない。そうだな?」
「え? ああ、そうだよその通りだよ、その辺は三カ月かけて調べたんだから間違いない」
「――だそうだ。時間はまだたっぷりある。こいつと、この部屋のカラクリについて、楽しい楽しい謎解きと行こうじゃないか」
そう言ってクロロはにんまりと笑った。その笑みは見る者全ての背筋を凍えさせるような冷たさがあったにも関わらず、そこにはまるで悪魔の微笑みのように完成された美しさがあった。
部屋の温度が一瞬で数度下がった気がして、少女は黒曜石の瞳の奥にチラリと映る獰猛な光にただただ震え、精霊『テレジア』へと祈りを捧げるばかりであった。
第1話、完
[ *prev | back | next# ]