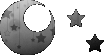 アクゼリュス崩落:02 アクゼリュス崩落:02
─────---- - - - - - -
バットやスケルトン等の魔物が徘徊していたが、素早く背後を通り戦闘を避ける。
呼吸するたび肺が痛むのはやはり瘴気のせいなのだろう。
胸を押さえ、ナツキは苦い顔をした。
奥に行くほど段々と紫色の霧が見えるようになってきた。
瘴気が視覚できるほど濃くなってきているのだ。
「ぁ……大佐!」
「おや、ナツキ、貴方には街の入り口の救出を任せたはずですが」
動けない人を抱えながら、ジェイドが鋭い目で睨むように此方を見た。
その視線にナツキはぎくりとしながらも答える。
「いえ、パイロープさんが此処はもういいから坑道の方を、と」
「……そうでしたか。ではナツキ、この方の治療を」
ジェイドが地面に寝かせた男に駆け寄り、譜術を唱える。
この辺りの人達は濃い瘴気にさらされ続けたせいで入り口付近の人達よりも酷かった。
一度や二度、いやもうナツキの譜術では殆ど回復を見込めない。
それでも僅かな望みにかけて治療を続ける。
暫く治療を続けていると上の方が騒がしくなってきた。
「……上の様子が可笑しい。見てきます」
貴方は此処で治療を続けてください。ジェイドはナツキに言い、坑道を走っていってしまった。
ジェイドひとりでもこの辺りの魔物ならば退けることは容易いだろう。
自分と同じでジェイドは譜術だけでなく、槍も使えるのだから。
完全に上司の背が見えなくなったところで、ナツキは坑道の奥に視線をやった。
ルークとイオンが奥へと向かおうとしている。
彼ら二人では少々不安を覚え、ナツキは男の治療を途中で切り上げ、ルークの背を追い奥へ向かった。
「ルーク!イオン様!」
「!……何だ、ナツキか」
驚いたように振り返り、声の主がナツキだとわかるとルークは落胆したようだった。
親善大使となってからのルークの行動は酷いものだった。
"親善大使"という肩書きに酔いしれ、仲間の輪を乱し、呆れられても我を通す。
ルークはアクゼリュスのこの状況を見ても手伝おうともしなかった。
伝染る、と言ったときにはナツキは何のために此処に来たんだお前は、と思ってしまった。
ルークよりもナタリアが親善大使となった方が絶対に良かっただろう。
ナツキはルークを一瞥し、イオンに軽く頭を下げた。
「具合は大丈夫ですか?」
「ええ、平気です。心配してくれてありがとう、ナツキ」
にこりと微笑んだイオンを見る限り体調はよいのだろう。
瘴気に当てられているナツキよりも具合はよさそうに見える。
「丁度いいや、ナツキも師匠を探してくれよ」
「謡将を?何故?」
「師匠なら俺がどうすればいいか教えてくれるからな」
ナツキは無言でルークを見た。
ルークの事あるごとに"師匠"と連呼するのは今に始まった事ではない。
が、少々異常すぎる気がする。
"師匠"が教えてくれるから、とルークは自分で考えることを放棄しているように見える。
ヴァンが好きではないナツキはルークを眺め目を細めた。
こんな時ですら、ヴァンに教えてもらわなければ行動できないルークを哀れんだ。
「……ヴァン謡将は恐らく奥にいると思いますよ」
先遣隊として来たのであればもう少し奥に進んでいても可笑しくはない。
しかし、どうして先遣隊の姿が少しも見えないのだろう。
そのことに疑問を覚え、首を傾げる。
ルークはナツキの答えに意気揚々と歩き出した。
坑道の奥、そこにヴァンはいた。
おかしな事に他の先遣隊の姿は見えない。
ヴァンはルークを見やり不気味に口元をゆがめ、それからナツキを睨んだ。
その視線を真っ向から受け止めナツキは睨みかえした。
「ヴァン師匠!こんなところにいたのか。他の先遣隊は?」
「別のところに待機させてある。導師イオン、この扉を開けて貰えますか?」
「……ヴァン謡将、セフィロトに続く扉を開けてどうなさるおつもりで?」
一歩前に出て、ナツキはヴァンに尋ねた。
セフィロトの扉を開けたところで瘴気が止まる訳でも止めれる訳もない。
「このアクゼリュスを再生するために、必要なのですよ」
その意味を量りかね、ナツキは閉口した。
イオンがヴァンに促され、鮮やかな色の扉に近づいた。
イオンは少し不審そうな顔をしながらも頷き、扉に手を翳した。
ダアト式封呪がイオンにより解かれる。
鮮やかな扉が徐々に光を失い、先に進む道が現れた。
「導師イオン、ルーク、先に奥へ行ってなさい。私はクロフォード中佐と話がある」
「ああ!じゃあ待ってるからな!行こうぜ、イオン!」
イオンがうんというよりも先にルークは手を引き奥へ駆けていってしまった。
奥はセフィロトだ。行った事はないが、魔物の類はいないだろう。
でなければ、ヴァンがイオンとルークだけで行かせない。
「少し着いて来て貰えるか?」
「えぇ、構いません」
セフィロトの扉とは逆方向にある穴の方へ歩き出す。
ヴァンの背を追いかけて、ナツキも歩く。
奥は行き止まりだった。
掘りかけなのだろう。壁にスコップが突き刺さっている。
そこでヴァンは足を止め、ナツキに振り返った。
「……話、とは?」
「貴方は預言を憎んでおられる。違いますか?」
ナツキは答えることも頷くこともせず、ヴァンを鋭く睨んだ。
「ホド戦争、あれは預言に詠まれていた。崩落することも。だから皇帝はホドを捨てたのです」
「だから、俺が預言を憎んでいる、と?」
えぇ。ヴァンは短く肯定した。
"預言"全てを記した外れることのない未来史。
それにホド崩落が書かれていたのは、とうの昔に知っていた。
確かに知った当初は怒り、預言を憎んだ。
けれども、それよりもナツキは父と母を、家庭を壊したキムラスカが憎かった。
預言は二の次だったのだ。だからといって預言が好きなわけではない。
今はもうキムラスカに対しても預言にしてもそこまで憎しみを抱いていない。
時間がナツキの傷を徐々に消してしまったのだろう。
「……謡将、逆に聞くが……貴方は預言を憎んでいるのか?」
ヴァンはナツキの問いかけに黙った。
そして、少しの間を置いてから口を開いた。
「憎んでいます。故郷を壊した預言と知っていたのに見捨てた世界を」
教団の者らしからぬ発言だ。
教団は預言を崇拝している。そして預言士を各地に送っているのだ。
そんなところに所属する者が預言を憎んでいる等と口にするとは、思いもしなかった。
「……ヴァン謡将、貴方とは相容れないようだ」
ナツキはヴァンを睨みつける。
「貴方が何をしようとしているのか知らないが、ここで何か起こそうというのなら俺が貴方を殺す」
右腕に静電気のような光が迸り、レイピアが握られる。
ナツキが武器を握ったのを見てヴァンが小さく鼻で笑い、腰に付けた剣の柄に手をかけた。
「そのような身体で私に勝てるとでも?」
「……やってみなくては分からないだろう?」
「それもそうだな……」
ヴァンが剣を抜き、振りかぶってきた。
その攻撃を後ろに下がって避け、攻撃直後の硬直を狙って鋭い突きを繰り出す。
「牙突!」
ガキンッ――
剣の腹でナツキのレイピアを防がれる。
右腕に強い衝撃が走りびりびりと痺れ、ナツキは顔を顰め後退した。
ヴァンが怯んだナツキに駆け寄り、剣を振るう。
キィン――
「チッ――」
剣とレイピアがぶつかり合い鋭い音を立てた。
鍔迫り合いになり、ナツキは顔を顰める。
右腕だけでヴァンと鍔迫り合いをするには少々力が足りない。
たとえ両腕を使えたとしても、純粋な力比べではヴァンのほうが強い。
舌打ちをして必死に負けじと剣を押し返す。
「この勝負、負ける訳にはいかないのでな……!」
「っく……」
ヴァンが力を込め、剣を振りぬいた。
乾いた音を立ててナツキの手からレイピアが弾き飛ばされ、くるくると回って坑道の壁に突き刺さる。
一瞬気を抜き、無防備になったナツキに向けてヴァンは剣を突き出した。
「ぁ……っ」
ずぷり、と腹に深々と剣が突き刺さった。
一気に身体から力が抜け、ナツキはヴァンの剣に支えられるような形になる。
目の前がちかちかとして、強烈な気持ち悪さに襲われる。
ヴァンがにやりと哂って剣をナツキの腹から引き抜いた。
それと同時にせき止められていた血がどっと溢れ出す。
内臓損傷で口からも赤い液体があふれ出る。
地面に倒れ込み、ナツキはヴァンを見上げた。
冷たい目をしたヴァンが此方を見下ろしている。
負けたのだ。
それを理解して、ナツキは心の中で悪態づいた。
「お休み、我が同郷の者よ」
優しく、ヴァンはナツキの頭を一撫でしてから、足早にもと来た道を戻っていった。
残されたナツキはぼやける視界のなか何とか動こうと地面を掻く。
右手だけでは匍匐前進も思うようにできず、地面に引っかき傷が出来ただけだった。
自分にファーストエイドをかけるものの傷が深すぎ、殆ど意味を成さない。
(馬鹿な事をするなよ、ルーク……!)
心の中でルークに呼びかけた。
ナツキはヴァンがルークを使って何かとんでもない事をしでかそうとしているのだと予想した。
セフィロトで何をするのかまでは予想できないが、恐らく大きな事……例えば崩落、とか……。
そこまで考えたときだった。
ド、ドドドドド――
大きな地鳴りが響き、地面にひびが入った。
驚き声を上げるまもなく、地面が割れはじめる。
「――!!?」
とんでもない衝撃が体を襲った。
地面が崩れ体が自動的に浮く。切られた傷跡に鈍痛が走り、痛みに耐え切れずうめき声が口から漏れた。
「くそ……」
悪態をつきながら俺は重力に従い落ちていく。
傷口を押さえながら、遥か下を見る。紫色をした海が眼下に広がっていた。
一体アレは何なのだろう。良くないものではないことは確かなのだが。
カーティス大佐は無事だろうか。血を流しすぎたせいでぼんやりする頭で上司のことを考えた。
死霊使いとまで呼ばれた大佐が死ぬというのはあまり想像できないが、彼とて人間。
この高さから落下しては無事ではいられないだろう。
(……俺、死ぬのか……?)
迫り来る紫から意識を逸らしたくて、俺は目を閉じた。
風を切る音だけが聞こえてくる。体がそろそろ限界だった。意識が遠のいてくる。
─────---- - - - - - -
prev ◎ next
|
アクゼリュス崩落:02
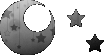 アクゼリュス崩落:02
アクゼリュス崩落:02