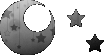 タルタロス襲撃:06 タルタロス襲撃:06
─────---- - - - - - -
セントビナーへの道を歩いているときだった。
突然イオンが膝をついた。
「おい、大丈夫か!?」
傍にいたルークが慌ててイオンに声をかけ、ティアが背に手を添えて身体を支えた。
イオンの顔色は青い。どうやら禁止していたダアト式譜術を使用したらしい。
「すいません……僕の身体はダアト式譜術を使うようにはできていなくて……」
ティアに支えられながら、イオンは眉を下げ謝罪した。
俺は屈み込みイオンの様子を見て、大佐に進言する。
「大佐、休憩した方がよさそうです」
このままではイオンの寿命を縮めてしまいそうだ。
ただでさえ、イオンは身体が弱いのに。
ジェイドも同じことを考えていたようで、小さく頷いた。
「そういや、自己紹介がまだだったな。俺はガイ。ファブレ公爵のところでお世話になっている使用人だ」
軽くガイに今回の件の任務の説明をしてから、今度は彼の自己紹介が始まった。
ガイは胸に手を当てて名乗った。
イオン、ジェイド、俺の順で彼と握手を交わした。
続いてティアが握手をしようとしたときだった。
彼は仰け反るようにしてティアから距離をとった。
その様子にティアが手を差し伸べたままぽかんとしてガイを見つめた。
いや、全員がガイの妙な動きに呆然としていた。
「……ひっ」
ガイは上ずったような声を上げた。
不思議そうな顔をして全員がガイを見つめる。
そんな中彼を良く知るルークが説明した。
「……ガイは女嫌いなんだ」
「というよりは、女性恐怖症のようですね」
ルークの言葉を聞いてから、ジェイドが自分の見解を口にする。
「わ、悪い……キミがどうって訳じゃなくて……その……」
ガイはティアから距離をとりながら、引きつり気味に笑った。
ジェイドの言葉を否定しないところからすると冗談ではなく本当に女性恐怖症らしい。
「私のことは女だと思わなくて良いわ」
ティアはそう言いガイに近づく。
ガイはティアが近づいた分だけ離れた。
……それが何度か繰り返された後、ティアは諦めたようにため息を付いた。
いや、俺としてはティアを女としてみるなという方が、難しいのだが。
ティアは割りと、こう……ぼん、きゅ、ぼん……というか出るとこでてるし……ナイスバディだ。
それに綺麗な顔をしている。可愛いというか美人系だ。
それをどうやって男と思ってみろというのだろう。
「わかった。不用意にあなたに近づかないようにする。それで良いわね?」
何だか少し怒っている。
拒否されたのがムカついたのだろうが、彼の体質上しょうがない。
「すまない……」
ガイは心底申し訳なさそうに、謝罪した。
暫く話していると、鎧の軋む音が遠くから聞こえた。
はっとしてそちらを見ると、神託の盾兵が此方へ駆けて来る。
俺達を追いかけてきたようだ。
「ゆっくり話している暇はないようですね」
面倒そうにジェイドがため息をついた。
背後からルークの怯えた呟きが聞こえてきた。
やはりルークは足手まといだ。タルタロスでのあの言葉はやはり強がりだったのだ。
レイピアを構え、ルークを背後に庇う。
「下がってろ!お前じゃ人を斬れない」
震えるルークを巻き込み、戦闘は始まった。
戦闘中のルークの動きは非常に悪かった。
敵を斬るのに躊躇して殆どダメージを与えれていない。
背後の不注意のせいで何度もガイがフォローに回っていた。
「ルーク、止めを」
目の前に膝をついた神託の盾兵をルークは震える目で見つめ、そして目を閉じて剣を振り下ろした。
それが、いけなかった。ルークの大振りの攻撃は敵に見切られ、剣が弾かれた。
ルークの手から弾かれた剣はくるくると回って、数メートル離れた地面に突き刺さる。
何が起こったのか理解できていないルークは敵を目の前に硬直する。
(――不味い)
反射的に俺は地面を蹴っていた。
「ボサッとすんな!クソがっ!――ッ」
思い切りルークを突き飛ばして庇う。
振りかざされた剣先が腕を掠めた。
俺と同時に駆けたガイが神託の盾兵を斬り倒した。
敵が一掃されたところで、斬られた箇所を押さえがくと膝をついた。
「お、おい、だ、大丈夫かよっ!?」
「……これくらい、平気だ」
怪我をした訳でもないのにあわあわとするルークを睨んだ。
ティア、治療を。ジェイドが落ち着いた声色でティアに声をかけた。
そっとティアの手が傷口に添えられた。
「癒しの力よ、ファーストエイド」
ふわりと薄緑色の光が発され、じわりと傷が治っていく。
大した怪我ではなかったため一回治癒譜術を使っただけでほぼ完治した。
アップルグミをひとつほおばり俺はまだ放心気味のルークに声をかけた。
「恐れていては何も守れない」
「――……えっ?」
回りの様子を見てきます。ジェイドにそう声をかけて、俺はさっさとその場を去った。
ルークの視線がずっと背中に突き刺さっていたけれど俺は気付かない振りをした。
焚き火を中心にイオンやルーク、ティアがそれぞれ座り込んでいた。
セントビナーまでは少々遠い。今日はここで野宿をすることになったのだ。
すっかり日も暮れて空には星が瞬いている。
ナツキは傍にあった木を背もたれにし、腕組みをして立っていた。
何かあったときのためにすぐに動けるようにだ。
夜だから神託の盾兵の追っ手が来ないとも限らない。寧ろ夜の方が奇襲は仕掛けやすい。
あり合わせの食材でほんの少しの夕飯を食べた。
緊急だったため殆ど食材を持っていなかったのだ。
ルークは愚痴を零していたが、その顔にいつものような傲慢さはない。
どうやら昼間自分が原因で怪我をさせてしまったのを気にしているようだ。
軍人にとっては本当に大したことのない傷だったのだが、ルークはかなりショックだったらしい。
「……なあ」
「何ですか?」
ルークが此方へそろそろと歩み寄ってきた。
眉を下げいつもとは正反対の泣きそうな表情でルークは俺に声をかけた。
「……人を斬る時、どんな気分だ?」
思いつめたようなルークは随分と重い質問を投げかけてきた。
ナツキは暫く何も言わずにルークの顔を見つめた。
――人を殺す、覚悟を決めようってか。
ジェイドやガイ、ティアにも何か尋ねていた。
恐らく似たようなことを尋ねていたのだろう。
俺は小さく息を吐き出し、視線を焚き火にうつした。
赤い炎の向こうに過去を思い浮かべながら――。
「……今はもう何も感じません」
「……」
落ち着いた声で言うと、ルークは驚いたように目を丸くした。
「そうですね、それでは答えになりませんので……昔は、怖かったですよ。もう血は付いていない筈なのに、手が汚れているような錯覚があって何度も手を洗ったときもありました」
薄笑いを浮かべ、ため息混じりに俺は手のひらを見つめた。
ルークも俺に釣られて手のひらを見る。
「でも、俺が手を汚すことで誰かが笑顔になってくれる、少しでも多くの人を守れるんだと思えば気持ちが楽になりましたよ」
「……守る、か……そっか……」
ありがとう、ルークはそれだけ言うと、俺から離れ先ほどと同じように焚き火の傍へと腰掛けた。
その晩はガイ、ジェイド、俺が代わる代わるに見張り番をした。
大して眠ることはできなかったが、問題はない。
─────---- - - - - - -
prev ◎ next
|
タルタロス襲撃:06
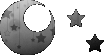 タルタロス襲撃:06
タルタロス襲撃:06