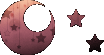 かゆい、うま:02 かゆい、うま:02

クリスにも飼育係の日記を読んでもらった。
最後の数ページに近づくにつれ、クリスは眉間に皺を寄せ険しい顔をする。
日記を閉じクリスは険しい顔のまま成る程な、と頷いた。
「この館の何処かに事件の原因である研究所があるって事か……」
「……そう、だろうな」
瑞希はあえて、曖昧に答えた。研究所へ続く道がホールの中央階段裏手から続いている事を知っているが、それをクリスに言うにはあまりに瑞希は臆病だった。
読み終わった日記をクリスは腰のポーチに大事そうにしまいこんだ。此方としてはこのまま捨ててしまってほしかった。
日本人の研究員が瑞希だとは気づかなかったようだが、不安要素は少ない方が良い。
「じゃあ、行くか――ミズキ?」
「あ、ああ、行こう」
「本当に大丈夫か?顔色が悪いぞ」
「……そりゃ、こんな気味の悪い館にいたら顔色も悪くなるさ」
顔色を指摘され、瑞希は自らの頬に手を当てた。氷のように頬も手も冷え切っている。
こんなに冷たいと、きっと顔色もとても酷い色なのだろう。それは館に潜む奴らだけでなく、色々な要因が積み重なっているせいに違いない。
心配するな、と瑞希は笑みを貼り付けて、心の底でため息をついた。
血なまぐさい部屋からさっさとおさばらして瑞希達は一度ホールへと戻る。
相変わらずホールには誰もおらず、閑散としていて天井に取り付けられた豪華なシャンデリアが煌々としていた。
「……誰も、いない、か……」
互いに顔を見合わせ、落胆したように息を吐き出す。仕方ない、と別の場所に調査に行こうとしたときだった。
背後からぎぃと扉の軋む音がした。ぎくりとしながら瑞希は振り返る。
見覚えのある姿が見えて、瑞希とクリスは同時に叫んでいた。
「「ジルッ!」」
二人の叫び声に険しい顔をして何か考え込んでいたらしいジルは驚いたように勢いよく顔をあげる。
時間にすればほんの一時間程度の事だというのに随分長い間会っていなかったような錯覚がした。
ジルは二人の姿を認めると目を丸くし、此方へ駆け寄ってきた。
「ミズキ!クリス!無事だったのね!」
「ジルも無事みたいだな」
ジルの姿を足元から順に見ていき、怪我がない事を確認した。
肩のアーマーだけをつけた身軽なジルの服には所々血痕があるものの、それは大した量ではないところから恐らく奴らの返り血なのだろう。
ええ。ジルは頷き、小さく笑う。その笑顔に安心した。
「ところでバリーはどうしたんだ?」
「バリーとは別行動してるの。その方が効率的でしょう?」
「まあ、そうだが……」
当然、と言わんばかりにジルは言う。効率的なのは確かだがその分危険度は上がる。
今まで二人で行動していた自分たちよりもジルの方が幾らか男前に見えたのは気のせいではない。
それはさて置いて、出逢えたのならお互いの情報を交換するべきだ。
「ジル、何かわかった事はあるか?」
瑞希の問いかけにジルは少しの間を置いた後に答えた。
「奴ら、ごく稀にだけれど凶暴化するみたいね……」
「……凶暴化?」
クリスが鸚鵡返しに言うと、ジルは小さく頷く。
凶暴化という言葉にすぐ検討が付いた瑞希は目を細くし顎に手を当てた。
瑞希が研究員だった頃に出来たt-ウイルスの変異体だ。確か"V-ACT"と名づけられていた気がする。
これに感染するとまずゾンビになり、殺されたりして意識を失わせると細胞を活性化させ身体組織の再生と改造が行われる。
つまりゾンビの身体が強化されるのだ。素早さ、筋力は通常のゾンビの数倍で、更に凶暴化しているためかなり危険だ。
研究員数人が犠牲になったという噂を耳にした事がある。因みにV-ACTによって強化されたゾンビをクリムゾンヘッドという――
そこまで考えてから瑞希は顎から手を離した。
ジルからクリムゾンヘッドの説明を聞いていたクリスは苦い顔をしている。
「――だから、気をつけてね」
「ああ、わかった、ありがとうジル」
「後、こんなものを見つけたのだけれど……何か分かるかしら?」
ポーチから取り出したのは、鈍い光を放つ不気味な形相をした仮面と六角形をした手のひらほどのクレストだった。
瑞希が仮面を、クリスがクレストをそれぞれ受け取り、ひっくり返したりして眺める。
仮面は目の部分が潰されている以外は特に変わった点はない。
「あの本に書いてあったあれだな……そのクレストは知らないけど」
すぐにその仮面がどこに使うのか見当が付いた。墓場の地下のあの部屋だ。
クリスは思い当たるのに暫し時間が掛かったようだが、やがて思い出したようにああと声を上げた。
「ならそれは貴方達に渡しておくわ」
「オーケイ。代わりにこれをどうぞ」
仮面を貰い、お返しにハンドガンのマガジンを一つプレゼントする。
此方はクリスと一緒にいるからある程度弾の余裕はある。もし弾が無くなってもナイフを持って二人で応戦すれば良い。
瑞希のプレゼントにジルは微笑み、ありがとうと礼を言った。
「……そう、それから……」
――フォレストが死んでいたわ……。酷く言いづらそうにジルが告げた。
フォレストはブラヴォーチームのOMだった。クリスと同じくらい射撃が上手で瑞希も時々練習に付き合ってもらっていた。
そんなフォレストが、死んだと告げられ瑞希は何も言わずに顔を歪める。
エドワード、ジョセフ、ケネス、フォレスト――仲間がどんどんと死んでいく。
「……そう、か……」
目元を手で覆いながら、ただそれだけぽつりと零す。
すり抜けていく、亡くしていく虚無感を心中に感じながら、瑞希は長く重い息を吐き出した。
涙は出なかった。ただ逝ってしまった仲間たちが瑞希を怨んでいるような錯覚がして、恐かった。
緩く頭を振り、瑞希は目元から手を離す。
「悪いな、そろそろ行こう」
「……えぇそうね、じゃあ私は東側の一階を調べるわ」
「なら俺たちは二階を調べる。さっきいけなかった所があったからな」
調査をする場所を決め、瑞希達は動き出す。
ホールの一階の東側に二つあるうちのひとつの扉にジルが向かっていく。
「それじゃ、二人ともまた後でね」
くるりと振り返り、気丈に笑顔を浮かべるジルに瑞希とクリスは中央階段を上りながら、軽く手を上げた。

prev ◎ next
|
かゆい、うま:02
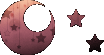 かゆい、うま:02
かゆい、うま:02