ワタルの夏バテさっぱりおうどん
これは俗にいう夏バテというものなのだろうか。
食欲がなくてランチを抜いてしまった。だけれども全く活動に支障はない、すこしいつもより気だるいような感じがするがその程度。ぼんやりとテレビを見ていれば夜は更けていく、夕飯の時間を過ぎているがやはり食欲がわかない。胃は空っぽなのに、食べ物を見てもなんというか…食指が動かないのだ。
「おなかすいた」
ブラッシングを終えたオオタチが、わたしの周りをくるくると忙しなく駆け回っている。しばらくはそうして一匹マラソン大会を開催していたが、満足したのか突然ぴたりと止まってハアハアと爽やかな顔で息をついている。良く解らないが楽しそうだ。短い足で一生懸命クシクシしているのを見守っていると、後ろでからりと戸が開く音がした
「ミシャ」
「んー?」
「何か飲み物を貰ってもいいか」
「うん、返してくれるならねー」
生返事だったが、ワタルさんは気にした様子もなく勝手にキッチンに入っていく。がこと冷蔵庫を開ける音がする、コップの場所は…まあ見れば解るだろう。少し気を逸らしたのが気に入らなかったのか、オオタチがポケじゃらしを咥えてすり寄って来た。受け取って先についたふわふわでオオタチの鼻先を擽ると、楽しくなったオオタチがまたくるくる回り始める。愛いやつめ。
「随分慣れたな」
「ふふ、もうわたしがこの子のお母さんですよ〜」
生まれてこの方ずっとパートナーポケモンがいなかった、でも興味がないわけではなかったのだ。ただタイミングがなかった。そういって曖昧笑ったわたしを、ワタルさんが引き合わせてくれたポケモンがこの子だ。正確を期せば元オタチ、いまでは立派なオオタチになった。
事情があってセンター預かりになっていたこともあり、最初の内は警戒心が強く中々慣れなかった。それがいまでは、わたしのベッドの上でお腹丸出しで眠っている。最初の警戒心は一体どこへやったのだろう、すっかりかわいい我が子である。
コップで麦茶を流し込んだワタルさんが、隣に座り込んでオオタチの顎下を撫でる。そうされると堪らないようで、オオタチはポケじゃらしを片手に握り締めたままへにゃんとフローリングの上に転がってしまう。
「キッチンのフードパッケージが前のものと違ったが、変えたのか?」
「うん、すこし肥満気味なのでお肉成分が少ないのにしたの」
「運動をさせていないだろう、バトルをしてやれ」
話しているうちにワタルさんの手が止まってしまったのか。オオタチが気持ちよさそうに閉じていた目を開いて、彼の手をがしりと掴んだ。そうして長い体を器用にくねらせ、ワタルさんの腕から肩へと登る。オオタチは米袋一つ分…30キロ近くあるのだが、それが乗っても体幹が揺らがないのは流石というべきか。
「バトルは…ちょっと、」
「苦手だと避けてばかりいて上達するものじゃないぞ」
ぐうの音もでない。黙ってそっぽを向いてしまったわたしの顎下を、ワタルさんがオオタチにしたように指でちょいちょいと擦る。止めてください、わたしはオオタチではありません。そうしているとワタルさんの腕を伝ってきたオオタチがわたしにちゅうと鼻先を押し当てた。かわいい、優勝。
ぎゅうううとオオタチを抱きしめて倒れたわたしを見て、ワタルさんが「良い匂いがしたのかもな」と笑う。
「夕飯はなにを食べたんだ」
「まだなにも ____、」
…っはと、口を掌で覆っても遅い。足元で座っているワタルさんが、なんだかとても怖いことになっている気がして見られない。
「なにも?」
「…」
「ミシャ、昼はなにを食べたんだ ン?」
怒らないから言ってごらん。とワタルさんは言うけれど、その声はどう聞いても怒る準備ができている人のそれだ。嘘をつけない性分なので、そっぽを向いて無言を貫こうとしたが。無言、そここそは神が与えたもうと肯定とも否定ともない万能の答え…。だが長くは持たず、コラと足を掴まれた。暴力!反対!
「ミシャ」
「〜〜〜〜っ たべてないえす」
ずりずりと引き寄せられて、上に被さってきたワタルさんが額を付き合わせて名前を呼ぶ。これなんて拷問。追究するグレイの瞳に耐え切れず白状すれば、ワタルさんは深くため息を着いた。呆れの色を纏ったそれを吐き出すと、わたしの肩をぽんと叩いて立ち上がった。…な、なんだったんだってばよ。
ひとりでオオタチを抱えてドキドキしていると、ワタルさんが腕まくりしながらキッチンへと入った。そうしてコンロ下の棚から小さなお鍋を取り出す。
「わ、ワタルさん…なにを、」
「うどんくらいなら食べられるか?」
「う、 うーん…」
ざあざあと鍋に水をいれながら、ワタルさんが訊いてくる。曖昧な答えのわたしに何も言わず、ふむと考えながら冷蔵庫からトマトを取り出す。
「わ、ワタルさん…」
「座っていろ」
「でも、その… ワタルさん、料理できるの…?」
湧いて出た素朴な疑問だった。キッチンカウンター越しにワタルさんが少しだけ顔を歪ませていた。頬に心外だとマジックで書いてあるような顔だ。
「これでも独り暮らしは長い方だと思うが」
「だって今まで一度も料理なんてしなかったじゃない」
「…代わりに、後片付けをしているだろう」
ぺりとうどんの袋を破いて、沸騰した湯の中に泳がせている。それを菜箸で捌きながら、忠告するように言った。
「先に言っておくが、君みたいに凝ったものはできない。あまり期待しないでくれ」
…いつも自信満々なワタルさんにしては、珍しい低姿勢。茶化すのも悪い気がしてこくんと頷けば、ワタルさんは少しだけ困ったように笑った。
とりあえず大人しく待っていることにしたけれど、ダンダンダンって音がキッチンから聞こえてきた時には、正直キッチンが壊されるかもしれないと少し覚悟したことは黙っておこう。
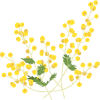
「できたぞ」
テーブルの上に運ばれたのはおうどんだった。おうどんの上にはトマトやキュウリといったカット野菜の他、たっぷりと大葉が乗っている。端にたたき梅も、なるほどさっきの包丁の音は冷蔵庫の梅を叩いている音だったのか。
「冷やしうどん」
「…出汁をかけて、切ったものを乗せただけだが」
「ううん、美味しそう! いただきます」
手を合わせて、お箸をとる。ドキドキしながら一口食べる、つるんと入ってくるもちもちのおうどん。それに、夏野菜と大葉がさっぱりしていて食べやすい。少し早いがたたき梅に手を伸ばす。少しだけ混ぜてつるんと一口、う〜ん 梅の風味が堪らなく美味しい。
「とっても美味しいですよ、ワタルさん」
わたしの言葉に安堵したのか、ワタルさんが止めていた息を吐いて「そうか」とほほ笑んだ。その腕に抱えられていたオオタチが、ぼくもぼくもと足をバタつかせているがそうはいかない。君もうご飯食べたでしょう。
最後の一口まで頂いてごちそうさまと言えば、ワタルさんが「お粗末様」と言う。せめて食器は洗おうと思ったが、ワタルさんがやってくれるらしい。なんだか今日はいたせり尽くせりで、お姫様になった気分だ。カウンター越しに、ワタルさんが洗い物をしているのを見ていると袖を捲ってほしいと言われた。
慌てて後ろに回ってずり落ちていたスウェットの腕を捲る。泡だらけで抵抗できないことを良いことに、背伸びしてワタルさんの襟足を擽ったら笑いながら止めてくれと言う。
「あれ、オオタチは…?」
「ん、君と一緒にいたんじゃないのか」
何もすることがないのでワタルさんの背中に寄りかかっていたのだが、はたとお騒がせ大将がいないことに気づく。ぽかぽかと暖かいワタルさんから離れたがらない身体にぐっと鞭を打ち、リビングに戻る。オオタチと呼んでみるけどどこにもいない、どこにいったのだろうと振り返って____宵闇に光る二つの目を見つけて、ギョッとした。
狭いベッドの下の隙間を、ぴっちりと埋めるように収まったオオタチが、じいいいいと静かにわたしを見ていた。その顔にはぼくを忘れていたね…ぼくには一口もくれなかったね…という恨みが見えた気がして、乾いた笑みがこぼれる。
洗い物を終えたワタルさんがやってきて「どうかしたか」と不思議そうに尋ねてくる。そうしてわたしの視線を何気なく追って、同じように恨みオオタチをみつけたのだろう。声こそあげなかったものの、ワタルさんの身体がわたしと同じようにビクリと震えたのを見逃さなかった。
その後、オオタチにはすこしだけおやつをあげて仲直りしました。ダイエットには程遠そうだ。