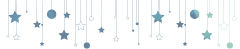
2
マネージャーの仕事が終わり、家に帰ろうと体育館を出た。昼間の暑さに比べたら夜は比較的涼しい。
梟谷のマネージャーさんはとっくに帰っていて、掃除が終わったあとも雑用をこなしていたらこんな時間になってしまった。
時計の針は8を指していた。
ここから家まで遠くはないし、この辺りは比較的明るい。怖くないわけではないが、最寄りの駅までついたら親が迎えに来てくれるらしい。
「利根川さん」
「うわっ!」
後から声をかけられ変な声が出てしまった。私の隣にきたのは研磨君だった。私はふーっと息を吐いた。よかった、幽霊じゃなくて。
「怖がらせるつもりじゃなかったんだけど……ごめん」
私は立ち止まった。それに続けて彼も歩みを止めた。
「ううん、大丈夫だから」
研磨君の隣を歩いているということに緊張してきて上手く喋れるか不安だ。意識してしまったらもう、彼の目を真っすぐ見ることもできない。
「もしかして、一人で帰るの?」
「うん、でも最寄りの駅までついたら親が迎えにきてくれるって」
いつも皆と接するように振る舞った。
「そっか……でも、そこまで送ってく」
そこまでと言うのはきっと駅までだろう。でも、研磨君にそこまでさせられないし、黒尾先輩に一言言っておかないとまずいのではないだろうか。研磨君は私の考えていることが分かったのか、大丈夫と呟いた。
「もう、クロには言ってあるから」
「そ、そうなの!?」
一体いつの間に……さっき黒尾先輩に帰りの報告をした時はそんな話一言も言っていなかった。
でも、妙に機嫌がよかった気が……
「行こう」
研磨君は私の手を掴み、歩きだす。研磨君の手はほのかに暖かく、気持ちがよかった。華奢な体型なのに、手は大きく男なんだと再認識してしまう。
また、心が高鳴った。彼とは距離が近く、この心音が聞こえませんようにと一心に願うだけだった。
門を出て試合のことや新作のゲームについて話をする。その様子はいつもと
変わらなかった。
数分歩き、研磨君はふと立ち止まる。私も立ち止まり、研磨君の顔をそっと覗き見た。
「……研磨君?」
街灯の明かりが私と研磨君を明るく照らす。車の通りはゼロで、歩いている人もいなかった。
「っ!?」
研磨君はおもむろに私の頭を撫で始めた。さっき整えた髪の毛がまた乱れる。
「ど、どうしたの研磨君!?」
研磨君は私を見下ろし、どこか切なそうな顔をしていた。
そして、手は止まりその手は私の手をまた握る。
「この間は、ごめん……」
この間のことを思い出して、心臓がうるさく鳴る。
何も答えずに俯いていると研磨君が呟いた。
「おれは、ずっと藍のこと見てるから」
彼はグイッと私を引き寄せ抱きしめた。彼のぬくもりが伝わってくる。
「け、研磨君……」
こんな時、どうしたらいいのだろう。誰かにこんなことをされたのは初めてで、どう対応すればいいか分からない。分からないどころか、これ以上されたら倒れてしまいそう。
それに、名前……研磨君が私のことを名前で呼んでくれた。いつもは名字呼びなのに。
「ここまっすぐ行けば着くから……おやすみ利根川さん」
ゆっくりと体が離れていく。
「お、おやすみ……気をつけてね」
うんと研磨君は頷き、私は手を振った。まるで時間が止まったかのようだった。
***
家に帰り、ゆっくりとお風呂に浸かる。頭から離れないのは研磨君のさっきの言葉。
「ずっと、見てる…か……あっ、もしかして! 保護者的な立ち位置で見守っているってことなのかも!」
そうだ、そうに違いない。意識しちゃだめだと頭を振る。
明日から研磨君とどうやって接したらいいのだろうか。普通に接したらいいのだけれど、はたしてできるだろうか。
「私は、研磨君のこと……」
好きなのかもしれない。”かもしれない”ではなく、好きなんだ。
20141207
戻る