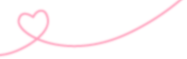学年末考査で部活が休みの今日。帰って勉強しようなどと考えながら靴を履いていたら、いきなり着信を知らせるバイブレータが響いた。 何の気無しに携帯を開いて見ると、新着メール一件の文字。メールの贈り主はアフロディのようだ。文面はシンプルに、『今から部室に来て』だけだった。 アフロディの提案や頼みを無視して放っておくと、後々厄介なことになるのは承知済みだ。少しだけ顔をだせば問題ないだろう。どうせ大したことではない。 靴のまま、屋外にあるサッカー部の部室へと向かう。底冷えするこの天気の中、何が楽しくて寄り道などしなければならないのだろうか。 白い溜め息を吐きながら扉を開けると、そこにはサッカー部の面々が勢揃いする光景が広がった。 「来たぞ、アフロディ」 「あ、ようやく来た。遅いよーヘラ、ほら早く早く」 アフロディが手招きするテーブルの中央には、見慣れない器具が置いてある。そしてそれを取り囲むように鎮座するメンバーたちの手に握られているものを見て、俺は自身の顔が引き攣るのを感じた。 「…これは一体どういう事だ、アフロディ」 「見て分からないかい?チョコフォンデュセットだよ。この日のために僕が仕入れておいたんだ。中々立派だろう?」 アフロディが両手を広げた大仰な仕草で、自慢げに説明する。確かに大それた物品なことは確かだ。まるで噴水のように流れ落ちるチョコレートは艶々と美しい光沢を放ち、さながら一流ホテルのレストランにあるような雰囲気を醸し出していた。どう見ても中学生が私有するものではない。 「今日はバレンタインだからね。僕からみんなへのサービスさ」 「…お前、こんな物どこから仕入れたんだ…」 チョコレートのかかったマシュマロをアポロンに食べさせながら、にっこりという擬音でもつきそうな笑顔でアフロディは言う。だがその金の出所が不穏でならない。訝しげに言えば、秘密だと言わんばかりに唇に人差し指を当てて微笑まれた。完全に俺の疑問をシャットアウトしてのけたぞこいつ。 「…先輩、気持ちは分かりますけど、ここはとりあえず合わせておいた方が…」 「お前も被害者かアテナ…」 「はは……」 勝手気ままに騒ぐアフロディたちを横目に、アテナが苦笑気味に耳打ちする。真面目で素直な分断りづらい一年をも巻き込んだか。 「アテナ、これ美味しいだろう?ヘラにも教えてあげてよ」 「そ、そうですね…素晴らしいと思います…」 「アテナは可愛いなあ。おいでおいで、チョコシューあげるよ」 半強制的だった。間違いなく。アテナの苦笑いから「助けてください」というSOSサインが感じ取れたが、強制的に連行されてはもう日が暮れるまでこのままだろう。心の中で合掌した。 「今日という日は本当に素晴らしいよ。テスト期間だから余計な荷物がいらない分、こんなにも沢山のプレゼントがもらえて」 「テストだという自覚はあるのか…」 「何、自分がチョコもらえないからって、得意の嫉妬かい?それに、君には渡したいものがあるんだよ」 棒に刺さった苺を俺の頬にグリグリと押し付けながら、アフロディはしかめっ面で言った。それを押しのけて見れば、アフロディの傍らにはいくつもの紙袋が置かれていた。中身は確認するまでもないだろう。するとおもむろにアフロディが自身の鞄の中から何かを取り出した。 「それは…」 「いつも君には迷惑かけてしまっているからね。ほんの気持ちさ」 アフロディの桜色の唇が弧を描き、目が細められる。柄にもなく目を奪われた、その一瞬だった。 アフロディの手に乗った何かが、俺の右頬にクリーンヒットした。 「ハッピーバレンタイン、ヘラ」 「……アフロディ……」 頬に張り付いたそれは、特大のシュークリーム。まるで語尾にハートでも付いているかのように、軽やかにアフロディは言った。目の前で小首を傾げるアフロディは、まさに天使の皮を被った悪魔だった。 「いい加減に、しろおぉおおッ!!」 わなわなと震える両手を抑え、魂の底から叫んだ声が、真冬の空気に響き渡った。  ――― しまったハロウィンの晴矢の二の舞だ |