その日は朝から曇り空で、コートが必要になる位に寒かった。夕方からは晴れるらしいが、そんなの夕日が眩しく目に刺さるだけで有り難くも無い。黄瀬涼太は、曇りの日が好きな人間だ。……自分が太陽の似合う人間だなんて思わないから。 「――判ってるっスよ、スキャンダルなんて……。馬鹿馬鹿しい。二流のタレントがする事じゃないっスか」 電話の向こうでマネージャーが釘を刺す。歌手デビューが控えた大事な時期だ。ターゲット層は若い女性。顔と愛嬌しか無い若いモデル、スキャンダルなんて起こせば誰も応援してくれない。 「オレは三流だから、警察沙汰かな?」 そんな冗談を言えば、受話口の向こうから喧しく吠えたてられた。警察のお世話になる予定は無いし、自分を三流だとも思っていない。卑下してやる気の出る人間じゃない。 ……オレは一流だ。 心の中でそう叫び、黄瀬は通話を切った。そうして周囲を見渡せば、噴水が無駄に水を吐くだけの粗末なオブジェに見えた。閑静な公園には似合わないダイナミックな噴水。またの名を税金の無駄遣い。 「くっだらねぇ」 天を仰ぎそう呟けば、遠くからヒールがアスファルトを叩く足音が聞こえた。 「話って、何?」 呼び出されたB美はウンザリしたような口振りで姿を現した。馬鹿な女で良かった。事務所からバックダンサーの個人情報を失敬して電話を掛けたら、何も疑問に思わず出向いて来た。警戒心の無さは、仲良くなった時に説教してやろう。 偉そうに両腕を組み、モデル立ちをした。ご自慢のお見足は黒いストッキングで包み、白いコートで隠す。 「……一ヶ月」 コートのポケットに手を入れた黄瀬は、その高身長から見下す視線を投げ、そう言った。 「は?」 「今日から一ヶ月で、アンタを落とす」 B美は黄瀬の宣言を鼻で笑う。その仕草は生意気で、傲慢で、美しかった。 「……笑わせないで。悪いけど、私彼氏とラブラブなの」 「だから一ヶ月必要なんだよ。フリーだったら、三日も要らねっス」 自信満々に言い放ったこのモデルは、ちょっと本気を出せば落ちなかった女が居ない。今回も、本当は言い一ヶ月掛からないだろうとも思っていた。余裕の黄瀬は彼女に質問をする。 「彼氏、写真無いの?」 「画像検索すれば? 有名だから、すぐ出て来るよ」 ハハハ……と苦笑いした男は、有名人を相手に立ち回らなければいけない事を少しだけ面倒だと思う。 「二ヶ月掛かるかも……。名前は?」 スマートフォンを取り出し検索を掛けようとした黄瀬に、B美は交際相手の名を告げた。……心底自慢気に。 「青峰大輝」 綺麗なアーモンド型の瞳を限界まで開いた黄瀬は、予想外の名前に口角を吊り上げる。ライバルには謙遜無い……それ所か、世界で一番戦いたい男の名前であった。 「了解。知ってる、ソイツ」 喉を鳴らして笑う黄瀬は、ライバルの彼女を奪う事に決めた。寝取るにしても何にしても、全力で無ければ青峰に失礼だ。 「バスケ観るの?」 「まぁ、そっスね。かじる程度には」 正直、黄瀬は高笑いしそうになっていた。こんな馬鹿げた展開を与えてくれた神に感謝をしよう。黄瀬がその青峰大輝と同じチームに居て一緒にプレイしていたと知ったら、彼女は驚くだろうか。 青峰は、自分が『キセキの世代』なんて名付けられ、尊敬と憧れの対象だった事を彼女に話していないようだ。まぁ、そんな過去の栄光を得意気にベラベラ話すつまらない人間では無いだろう。どんな名誉ある事でも、過去は過去だ。 「デート行きましょ? 海とか」 気が変わった黄瀬は、B美を誘った。行き先は何処でも良い。彼女が望むのなら、地球の果てでも見に行こう。 「今日一日で惚れても良いんスよ?」 返事を出さずに眉をしかめるB美は、呆れて溜め息を吐いた。 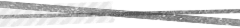 「遺書は、書いたか?」 火神のマンションに通されるや否や、緑間はそう言って命令していた遺書の提出を最速した。その後ろに立つ二名の人物も彼に続き、玄関から室内に入り込む。 「――久しぶりだ、大輝」 「赤司……」 出迎えた褐色肌の男が遠い昔に疎遠となった赤司征十郎を睨む。本当に彼が今回の主犯だと言うのなら、一発でも整った涼しい顔に拳を叩き込みたくなる。 「久しぶり〜。峰ち〜ん」 気が抜ける朗らかな声で再開の言葉を告げる紫原に、黒子が間違いを教えてやる。 「コッチが青峰君です」 そうして火神大我の身体を三人の前に誘導する。無言の紫原が二股に分かれた眉毛を抜けば、青毛の方が怒りを見せた。 「抜くなよ! 紫原ァ!」 「めんどくさ……」 指先に摘まんだ眉毛を息で吹き飛ばした紫原敦は、自分はこの場に用が無さそうなので帰宅を催促した。 「火神君と青峰君、心配じゃないんですか?」 不安を拭えない黒子が彼にそう聞くと、集団の中で背の高い男は首を傾げた。 「だって、オレが居ても何もしてやれないもん」 赤毛の男は、その返事に笑った。紫原の答えは凄く彼らしくて、懐かしくもあった。 「――お前ら……小学生からやり直した方が良いのだよ」 リビングの椅子に腰掛けた緑間は、眼鏡を外し目頭を押さえた。彼の手から二人の遺書を奪った赤司は、その内容の悲惨さに溜め息と冗談を漏らす。 「頭を良くする方法は、ボクも知らない」 その嫌味に口を尖らせた赤毛の男は、特徴的な二股眉毛を潜めた。 「何だって良いだろ? さよならの四文字でも構わねェよ、オレは」 「桃井に見せるのにも、か?」 横から口を出した青毛の男は、向こうが汚い字で殴り書きした"遺書的な何か"を読む。文章を書く習慣が全く無い青峰大輝の遺書は、主語も述語もハチャメチャで、国語が苦手な火神は頭にハテナを沢山浮かべた。 「……書き直しゃ良いんだろ?」 リアクションと桃井に見られるのが恥ずかしいのか、赤毛の男は褐色の手から遺書を奪って丸めた。 「青峰君って、扱いやすいですね」 「脳ミソまで筋肉なのだよ。シナプス走ってるかも甚だ疑問だ」 「走ってるよ! 馬ァ鹿!」 二人の友人から馬鹿にされた【青峰大輝】は、火神の顔で怒った。 「……なぁ、何時始めるんだ?」 青毛の男が久々に会う赤司に質問をした。 「ボクは何時でも構わない。先に手法の説明は要るか?」 「あぁ、頼む。頭痛くてイライラして来たぜ」 テーブルに座り遺書を書き直している赤毛の男がそう言うと、赤司は馬鹿でも判るように噛み砕いた解答を始めた。 「お前達はベッドに寝た後、薬を盛って仮死状態となる。後は戻るのを待つだけだ。五分以上仮死状態が続けば、脳は死ぬ。仮に息を吹き返しても、一生寝たきりだ」 「そんな方法しか無いんですか?」 至極あっさりした方法に驚いた黒子は、更に不安そうな顔をした。 「まるでお伽噺みてェだな」 赤毛の男はそう言い手法に呆れ、青毛の男は溜め息を吐いてこう言った。 「……最悪だぜ」 「最悪より、もっと下だ」 緑間はそう告げ、落ち込む二人にアドバイスをする。 「仮死状態になる寸前、何か強く自分の身体に戻りたい理由を作るのだよ。ソレが道標になる」 「漫画かよ? 笑わせんな」 青毛の男はソファーに座り、足を組んだ。隣に座っていた赤司は彼の大柄な態度を気にもせず、緑間の発言を批判する。 「少し非科学的過ぎるんじゃないかい?」 「信じなければ、道は開かれないのだよ」 「何を信じるんだよ? 神か?」 作文に飽きてペンを回し始めた赤毛は、緑間にそう聞いた。その疑問に答えたのは、不安そうに指先を遊ばせる黒子テツヤだった。 「……自分を信じるしか無いんですよ。青峰君」 「一番正しい答えだ、黒子」 青毛の男は膝を叩き、再び立ち上がる。そしてジーンズのポケットからスマートフォンを取り出して軽く振った。 「……電話して来て良いか?」 「手短にするのだよ」 ――これが最後かもな……。 言えなかった言葉を胸に戻した緑間は、中学から見てきた彼の広い背中から青い頭髪を視線で送り出した。 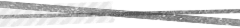 ――A子は野外で呆然としていた。空には灰色の曇り空が広がり、不安気な自身の心境とマッチしていた。着信が彼女を呼び出し、慌てて鞄からスマホを取り出す。しかし、手を滑らせ土の上に落とした。少女の前に立つ人物がソレを笑う。 「ど、どうしたの!?」 挙動な声が出てしまい、恥ずかしくなったA子は前髪をくしゃりと掴む。 『今日、元の身体に戻る』 「……え?」 電話をくれた人物は、甘く低い声を電波に乗せる。その声は、愛しい人のモノでは無い……。中身は【火神大我】だと何度も言い聞かせたが、未だに慣れる事が出来ない。 『やっと会えるな! 待たせて悪かった!』 弾む声が受話口から聞こえる。距離を置いてくれと言われてから、長い年月が経ったような気がした。しかし、A子は素直に喜べない。灰色の空は、押し潰しそうに色が重い。 「火神君、あのね! 私ね……!」 『……あぁ、オレも嬉しい。また、幸せにしてやる』 話を聞かないのは、やはり火神らしい。嬉しかった。A子は、その言葉が欲しかったのだ。……でも、今はソレすら辛い。 「――……もう、無理だよ……」 数秒の沈黙の後、火神は彼女の求めていない声で問い質して来た。 『……何がだよ?』 誰かの手がA子からスマートフォンを失敬する。何も言えない彼女は、口角上げて通話を始めた相手を眺める事しか出来ない。 「久し振りじゃね? 火神」 『…………高尾か』 向こう側の相手は、声だけでA子の傍に居た人物を当てた。 「あれ? 火神ってこんな声だったっけ?」 『ざけてんじゃねぇよ』 「オレが話したいのは青峰じゃなくてさぁ、火神なんだけど?」 喧嘩越しの台詞に喧嘩越しで返す。それでも高尾の顔から笑みは消えない。彼の細長い目は、頭上にある灰色の空を眺めている。 『お前、隠れて何してんだよ』 「ねぇ、オレの台詞なんだけど? ソレ」 向こうはコチラの出方を探っているように無言になった。 「火神と青峰、何か隠してるよね?」 『お前に言うつもりはねぇよ』 「それでA子ちゃん泣かせてんなら、オレ容赦しないよ?」 火神には先日戦線布告をした。だから、本気を出せる。……欲しいモノを手にした火神大我から、ようやく"彼女"を奪える。 『高尾!!!』 着信切った高尾和成は、寝不足でフラフラする頭を振りA子にスマホを返した。目の下の隈が疲労の色を隠せずにいたが、彼はにこやかに笑う。 「こ・れ・で、もう泣かなくて済む」 A子は高尾の身を案じ、また不安になれば何時でも駆け付けてくれる優しさに少女漫画に出て来るヒーロー像を重ねた。火神も優しくて頼もしい理想の彼氏だが、最近は寂しさが彼との思い出を砂のように崩していた。 無言で俯くA子を見た高尾は息を吐いて、彼女の額に指先を合わせた。 「……オレ本気だからさぁ、考えといてっ」 ――"本気"とは、そういう事だ。火神から着信があった数分前、高尾は彼女に男女間交際の告白をしていた。理由は教えてくれない。彼氏が居ると言っても『距離置いてるなら、居ないのと同じだ』と持論を展開していた。 「正直、今すぐ色々すっ飛ばしてキスとかエッチとかしたいけどね。ダメ?」 「……それは」 困惑するA子の姿に清楚と世間知らずを見た高尾はゲラゲラ笑った。あまりに楽しそうな笑い声を上げるモンだから、彼女は顔を赤くしただけで不快には思わなかった。 「冗談だって、ごめん」 誰も居ない公園は、二人だけの秘密の場所になっていた。――火神の知らない……密会場所。胸が痛んだA子は唇を噛む。愛しい火神が戻って来る。でも、だからって高尾和成を突き放すのは……すがれるモノが無くなるのは怖かった。 「でも、ちょっとだけ本気……」 高尾はA子の指先で顎を持ち上げた。多分、睡眠が足りていない脳が男の思考を停止させているのだ。客観的にしか自分を見れなくなった男は、ドラマでも観ている気分になった。 他人の所有物と唇を合わせたのは、その数秒後……――。 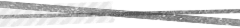 「赤司、何を考えているのだよ」 リビングのソファーに腰掛ける赤司にそう尋ねたのは、室内を無意味に動き回る緑間だった。黒子は火神と青峰を寝室で看ている。睡眠導入剤で二人を眠らせるのが、彼の役目だ。後は違法な薬を規定量だけ体内に注入してやれば良い。その量は、赤司と緑間の二人が知識を総動員させ数日で叩き出した。処方の仕方も論理も数式も独学で、ソレが緑間の不安を煽る。 「ソレは何度目の質問だい?」 赤司は真逆で緊張していないのか、悠々と火神が買ったバスケットボール誌を読んでいた。 「……入れ替わりで何がしたいのだよ」 「あんなのは、只の初期段階でしか無い」 雑誌をテーブルへ放った赤司は、代わりに数枚のレポート用紙の束を手に取った。 「次のフェーズが成功しないと、ボクは何も得られない。大輝の身体だったら成功しそうだ。ドッチのお陰なのかな、この場合」 愉快そうな赤司を見るのが辛い緑間は、声を荒げる。 「人が死に掛けてるんだぞ!!!」 「正確には、一度死んでいる」 カッとなった緑間は赤司の襟首を掴み、彼を持ち上げた。普段からクレバーな緑間だ。こんな事を一度もした事が無い。それなら何故かと理由を言えば、彼は初めて経験する"死の影"に怯え、また困惑しているのだ。 乱暴する手を離した緑間は、ソファーに座り項垂れながら「スマン……」と謝る。眼鏡を外し目頭を押さえた彼は、赤司にこう問いた。 「……何がしたい。戻った青峰は、どうなる」 赤司は緑間と黒子のまとめたレポートを眺める。几帳面で綺麗な字が時系列に沿って簡単に書いてあった。 指を滑らせた赤司は、黒子の筆記で書かれた『青峰君が戻る?』の文字で動きを止める。 「大分苦しむだろうね。大輝は」 鼻血を出し、割れそうな頭痛と戦っている彼の身体は、戻る事により、更に過激な苦痛に直面するかもしれない。肉体的にも……精神的にも。 「……なんせ、ひとつの身体に二人の人間が住むんだからね」 赤司は数枚綴りのレポートを宙に投げ、舞い落ちるA4サイズの紙を眺めた。 |