「火神、お前最近バスケしてんのか?」 晩飯時の賑やかな店内。その喧騒に紛れ問い掛けられた青毛の男は、噛み切れない脂肪の筋を無理矢理に飲み込み、質問に答えようとする。カチャリと音を立て、すっかり冷えた鉄皿にナイフとフォークを置く。 「まぁ、そりゃあ。……でもこの身体になってからは全然だ」 答えながらに青毛の男は、歯に詰まった赤身の筋を取ろうとカスターセットから爪楊枝入れを手に取った。 「……しろよ。ちゃんと、使いこなせ」 そう告げ、ミートスパゲッティを口に放り込もうとする向かいの赤毛。彼は割り箸で啜るようにパスタを食していた。きっといちいちパスタを巻くなんて、そんな面倒な事が嫌いなのだろう。 青毛の相手から「何でだよ?」と質問をぶつけられ、ジーンズのポケットからガラパゴス的な携帯を取り出した赤毛は、咀嚼しながら携帯を操作し"あるメール"を呼び出した。その後、テーブルの上で電子機器を滑らせ、青毛が手に取ったソレにはこう書かれていた。 【いつになったら今リーグは練習に来るんだ】 赤毛の男は唇に付いたミートソースを紙ナプキンでゴシゴシと拭くと、食べ終わってソースが汚く広がる平皿の上にゴミとなったソレを投げた。 「プロの試合、経験して来いよ」 メール画面から目線を離し【火神大我】を見た【青峰大輝】は、細い目を限界まで見開き驚きを体現する。 「……"オレ"が? お前の身体で?」 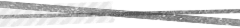 都内のスタジオは、雑居ビルが並ぶ街の一角にあった。決して大きくは無い。入り口のドアを開けたB美は、キャップを目深に被り直す。指定された階に着けば、スタッフが控え室を指差す。薄暗い廊下の奥に手書きで【関係者控え室】と書き殴られた貼り紙があった。 扉を開けると、狭い八畳の化粧室に五人の女性ダンサーが各々の顔に化粧を施していた。既に支度を終えていたB美は、テーブルに鎮座する段ボール箱から自分の名前があるビニールを取り出す。ヒップホップらしいチューブトップにカーゴパンツだ。ノロノロと着替えた少女は、退屈を紛らわしたくてスマートフォンを手に取る。 当たり前だが、彼氏からのメッセージは入っていなかった。あの朝勝手に部屋を出て行ったっきり、一切の連絡を寄越さないままだ。【大事な用】が何かも聞かれなかった。多分、その位に自分へ興味が無いのだろう――。 :: :: :: スタッフに連れられスタジオに入ると、既にスタンバイを終えた男性のダンサー達が緑のカーテンで覆われたステージを眺めていた。 「スタンバイお願いしまーす!」 眩しいライトの前で本日の主役がスタイリストに全身チェックを受けている。黒いハットに着崩したスーツがまるで昔のマフィアみたいで可笑しかった。本人も『動きやすい格好が良かった』的な事をぼやく。 殺風景な緑カーテンの前で配置に付けば、監督がプロモーションビデオのコンセプトを伝える。CGで背景を後入れするから、廃倉庫に居るつもりで踊ってくれと言われても……そんなの判らない。挙げ句メイクが顔に泥を塗り始めた。せっかく二時間掛けて肌をカバーして来たのに――。土臭くてザラザラした感触が面白くないB美は、不機嫌がMAXにまで昂っていた。 そんな最悪な気分の中、リハーサルがスタートした。振り付けは昨日このメンバーで練習した。主役の男の代わりにダンス講師が立ち、完璧な動きを見せていた。だからこそ、バックダンサー達は踊りやすく、振りをマスター出来た。 しかし、今前に居る男は違った。――その男のダンスは"完璧過ぎた"。 彼の長い手足は振りを大きく魅せ、その癖ストップモーションは指の一本一本まで洗練されていた。リズムの誤差は、コンマ数秒レベルだろう。全てが凡人には到底出来ない、プロの動きだ。 彼はパフォーマーでは無い。"パフォーマンスそのもの"だ。こんなの、有り得ない。背筋が粟立ち、男がロボットに思えた。音楽なんか頭に入らない。まるで台風の中を歩行しているようだ。尖った神経が雑音となり、振りを収縮させる。 芸術に見本を付けるなら、完璧過ぎてはいけない。何故なら人は"ソレ"を追い越せないと悟り、手を付ける前に諦めてしまうからだ。 B美は更に驚愕した。表情や顔の角度まで計算されたような動きだった。彼女はここまで魅力を最大にまで導き出すダンスを見た事が無い。圧倒的な敗北を感じた。恐らくはここでバックダンサーに呼ばれた全員がそう感じている筈だろう。――霞む、自分が。私なんか、子供のお遊戯会だ……。これがリハーサルで良かった。俯いて、前を見れなくなったB美は唇を強く噛んで涙を堪える。 きっとあの男は生まれてから今日まで毎日飽きる程に踊り、嫌になる程の努力をして来たに違いない。そうじゃなきゃ、やってられない。 リハーサルが終わりダンサー達を振り向いた主役は、眩い笑顔で頭を下げた。監督に呼ばれ、カメラチェックに向かおうとした男は金髪の髪を掻き上げてその場で固い表情をしていた全員にこう告げた。 「スンマセン。オレ、昨日振り付け覚えたばかりなんで……下手っぴっスよね? ダンスも今回が"初めて"だし」 :: :: :: バックダンサー達は鏡の前で一生懸命練習をしている。少しでも主役に近付こうと足掻いているのだ。しかしB美だけは控え用に設置された長テーブルの前に座り、スマホを弄っていた。彼氏へのメッセージを書いては消して、消しては書いてと繰り返す。そんな止めどない無駄な事に夢中になっていれば、目の前に人が立っているのにも気付かない。 「……アンタもこういうの、初めてっスか?」 「――……は?」 そこに立っていたのは本日の主役であり、完璧過ぎるダンスを魅せた【黄瀬涼太】だった。 大方、『やる気が無いなら帰れ』と言いに来たのだろう。B美は全身を緊張させながらも、表情だけは決して変えずに興味無さそうな振りをした。『帰れ』と言われたら帰るつもりで居たし、今更燃やす情熱も無くなってしまった。 「慣れてない感じがしたから。……でも一番巧かったっスよ」 B美からしたら、予想外の台詞だった。そう言って黄瀬は少女の隣に腰掛ける。恐ろしく長い足を投げ出し、丸椅子の上で身体を伸ばした。 「……話し掛けないで」 飛んできた辛辣な言葉にパチパチと瞬きをした黄瀬は、ショックを受ける事も怒り出す事もなく鼻で笑った。 「女に冷たくされたのも、久しぶりっス」 「立派な控え室あるんでしょ? ソッチ行けば?」 「別に? 動くの面倒臭いし」 ダンサー全員のプライドを完膚無きまでに叩きのめしたこの男は、ヘラヘラしながらテーブルに置いてあるクッキーを口にした。 「何であんなに踊れるの……? 本業じゃないじゃん!」 流した目線でB美を見た黄瀬涼太は、クッキーを噛みながらシンプルに答える。 「天才だから」 「何それ?」 B美はスマホから目を離し、身長高くスタイルの良い男を睨む。 「オレの憧れた人がすぐそう言う。『天才だから』――。それで、真似してみただけっスよ」 「変な人達」 「人と違うから【天才】って言われるんスよ」 黄瀬は綺麗な指で整った顔を支え、テーブルに頬杖を付いた。ニヤニヤした顔は癪に障るが、何故か気にせずには居られない。 「その人も、モデルなの? ……憧れてる人」 気付けばそんな質問をしていた。こんな凄い男が憧れるなんて……一体どれだけの才能を持ち合わせているのか、知りたくなった。 「全然? 中高の知り合いっスよ」 「……今は、憧れてないの? 何の天才かは知らないけど」 突然真面目そうな顔になった黄瀬は、少し目線をB美から外すのだが、すぐ笑顔を見せて席を立った。 「――……憧れ過ぎて、もう憎い」 黄瀬はそう呟き、右手を流し別れを告げた。スポットライトが照らさなくたって、彼は眩しい。きっとプライベートでも輝いているのだろう。その光が潰える事は、恐らく無い。 :: :: :: 黄瀬涼太はムシャクシャしていた。理由は知っている。知っているからこそ、ムシャクシャするのだ。 ――"憧れ"とは、それ即ち敗北を意味する。勝てる要素が無いと自覚しているから、対象をそうやって崇めるのだ。初めてチームメイトになったあの日から、黄瀬はずっとその存在に憧れていた。一時は憧れを捨て、その男を超えるつもりで挑んだ事もある。今は駄目でも、何時かはきっと超えられる。そうやって後ろに着いて走れば、何時から抜ける日が来ると信じていた。 高校二年生の時に、一度だけその男を出し抜いた事がある。簡単だ。ソイツが好きだと言った女を奪った。いつも応援してくれる、同校の先輩だと聞いていた。 『アンタの気持ちに気付いていたのに……オレ……』 そう偽りの懺悔を告げれば、頭を掻いた男は興味無さそうな顔をして肩を竦めた。 『――まぁ、お前の方がイイ男だからな?』 そんな余裕ぶった台詞や行動の、一瞬前に見せた絶望を表した表情。――ソレを見た瞬間、初めて勝利したのだと拳を握り顔が綻ぶのに耐えた。悔しいんだ? たかだか顔で男を選ぶような女を奪われて――……。 そうして頭に浮かんだ【灰崎祥吾】が皮肉めいた顔で自分を嘲笑った。嫉妬から女を奪われた人間は、気付いたら奪う側になっていたのだ。 ――本当に、皮肉だよな? 「どうしたの? 黄瀬君」 持ち場に付いても無表情のままにライトを眺める黄瀬へ、少しだけ"カマ"の入ったスタイリストが声を掛けた。 「アレ……眩し過ぎるんで、落として下さい」 眺めたライトを指差し、ボンヤリと遠くを見るような目線のままに細かい衣装直しを受ける。 「オレ、自分より輝いてるモノ……全部嫌いだから」 黄瀬が下らなそうにそう呟けば、スタイリストはその"冗談に似た台詞"を笑って、彼から離れた。 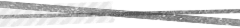 自室のアパートにある古いベッドの上で俯せのままに微睡んでいれば、陳腐なベルが来客を伝える。 「――何してんだよ、そんな所で」 ドアを開けながらに赤毛の男は、玄関前に立っていたA子を睨み付ける。今日も地味な色合いのチュニックにロングスカートだ。そんな派手には程遠い少女は胸の前で手を握り、オドオドしながら口を開いた。 「……あの、かが、み君に相談があって」 「"オレ"は火神じゃない」 赤毛の男はそうやって冷たく突き放すのだが、A子は玄関から決して退かない。 「私にとって……火神君は、貴方だから」 「頑固だな、お前」 溜め息を溢し、ドアを限界まで開放した男は自分の巨体でストッパーの役割を果たした。腕を組み、渋い顔をしてA子を牽制する。 「"オレ"の中に火神を探すのは、止めろ」 「…………火神君」 泣きそうな声色で呟かれた名前は、予想の通り"自分のモノ"では無かった。少女は器でしか彼氏を認識出来ないようだ。 「――高尾に何か言われたのか?」 ふと昨日の高尾和成を思い出した赤毛の男は、何気無しにA子へ問うのだが――どうやらビンゴのようだ。鞄の持ち手を握り、俯いた頬がやたらに赤くなっている。あまりの分かりやすさに息を深く吐いた男は、長話を懸念して中に誘導した。 「入れよ。"オレ"には関係ねぇけど、話位なら聞いてやる」 :: :: :: 「何だよ、メシに誘われただけかよ」 高尾からのメッセージを見た赤毛の男は頭を垂れる。それでも【既読】が付いたまま放置しているメッセージにどう返せば良いのか、A子はずっと悩んでいるようだった。 「私……男の人に誘われるの、滅多に無いから……」 ベッドに並んで腰掛けた二人の間には微妙な距離があり、男は腕を伸ばしてスマートフォンを持ち主に返した。 「火神ん時は?」 「それが初めてだったの! 緊張、した……!」 まごまごした話し方で、少女は自分の男性経験の浅さを露見して来た。だから男はテキトウにアドバイスをしてやる。 「会えば? 高尾に」 顎に手を置いて首を傾げるA子は、火神の中に居る男へ"ある質問"をし出す。 「……青峰君の彼女さんって……、あの綺麗な女の人だよね?」 「アイツは見た目だけだ」 そうだ。B美は見た目だけの、空っぽな女だ。何かを欲しがる癖に、素直じゃない。――でも、その見た目に群がった自分はソイツ以下の存在でしか無い。 「火神君のマンションにね……髪の毛、落ちてたの。ベッドに。この間、カフェで喧嘩してたよね? そういう事だよね?」 ポツリポツリと、彼女なら耳を覆いたくなる話を始めたA子は今日も長いスカートを握り締め、感情溢れるのに耐えているようだ。 「……気にすんな。お前だって似たような事してたんだから」 頬杖を付いて、慰めにしては酷く歪な言葉をぶつける。しかしA子は頭を横に振り、火神の顔を真っ直ぐに見た。 「悲しくないの。全然、ちっとも。――……でも、私多分……貴方が他の女の人と一緒に居たら……泣くと思い、ます」 「…………そうか」 だから、A子は今日ココに来たのか。先日、三人でセックスをした。その時が最後だと思ったし、今だってそのつもりだ。コイツはこの身体に【火神大我】を見ている。『違う』と言っても、彼女は探ろうとする。だってコイツは賢い……――。 「私は、見た物を見たままにしか捉えられないから」 「――帰れ。今日は帰った方が良い」 女がこの先何を言うのか悟った男は、腰を浮かし離れようとする。特徴的な眉を下げ、困ったような顔でA子を必死に諭す。 「ココに来るなとは言わねぇ。でも、火神――アイツはお前を大事にしてるんだよ。……ナリはオレだけど、でも中身はちゃんと火神だ」 「『好きだ』って言われたら、嬉しい筈だよね? でも嬉しいって思えなくて……。――だって、あの人は"火神君"じゃない……」 シャツの裾を掴まれた男は、少女の泣きそうな顔を見て緊張する。この手が隣に座るA子を押し倒す前に、相手の肩を掴み軽く揺する。――諦めて欲しいんだ、拒絶されたいんだ。再び一線を越える前に……――。 「必ず元に戻るから、待つんだ。いいな? 頼む……。"オレ"に来ないでくれ……」 向こうからしたら悲痛で残酷なお願いだろう。案の定、防波堤が決壊したようにA子の目から涙が溢れて頬を濡らし始めた。 「――そんな事……言わないで……?」 掴んでいた腕の力を抜くと、少女は胸元に崩れてきた。しゃくり上げながら着ている布地を握り、シャツ越しに体温を感じる。頭を撫でれば、柔らかい髪の毛が指の隙間を滑った。 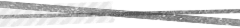 「青峰君、電話に出ません」 留守電に切り替わるメッセージを聞いた黒子テツヤは、呼び出したい人物の一人が欠ける事へ溜め息を付いた。国道沿いのコンビニ前に集合した黒子と青峰は、やって来ない火神を待っていた。 「折り返しを待てば良いだろ」 在り来たりな提案をした褐色肌の男は、また鼻から垂れ始める血液を親指と人差し指で擦った。一昨日より量は減ったが、こうやって知らぬ間に垂れるのは、行動に支障と制限が出る。 「…………火神君、鼻が」 気付いた黒子が、反応薄いながらも僅かに驚いたような顔で、青峰を見つめる。 「一昨日からだ……。この時間は、こうなる」 青峰はポケットからティッシュを取り出し、お座なりな止血を始めた。鼻に押し当てるだけの、形だけの処置だ。 「何で言わないんですか? 死にたいんですか!!」 「騒ぐなよ。鼻血だけだ」 黒子が必死そうな顔で背の高い男を心配する。 「青峰君の方が進行が早い筈です。もしかしたら、もっと酷いかもしれません」 微妙に顔を歪ませた黒子は、この場に居ない赤毛の男を心配して落ち着きを無くす。この問題を知ってから、黒子テツヤは人間らしい表情や仕草を見せる。それが【火神大我】からしたら新鮮だった。 「昨日会った時は普通だったぜ?」 昨晩ディナーと呼ぶにはフランクな店で一緒に食事をした時の様子を伝えてやれば、色素の薄い少年は疑心そうな眼差しを向ける。 「オレの身体だ。オレが一番よく知ってる」 「……本当ですかね?」 歩き出した二人の身体を、車のヘッドライトが照らす。流れるように同じコースを、黄色い光が絶えず照らし出した。 「アイツ、どうせ部屋で寝てんだろ? 起こしてやりゃあ良いんだよ、寝坊助野郎は」 青峰の契約しているアパートへ進路を決めた高身長で肌の黒い男は歩を進めるのだが、途中立ち止まった黒子は携帯を握ったまま、先を行く青毛の男へ問い掛ける。 「今から行くって、連絡入れなくて良いんですか?」 首だけを捻り黒子を視界に入れた青峰は、親切にも男に連絡を入れない理由を教えてやる。 「寝てる人間が、そんなの見るかよ?」 :: :: :: ギシリと音を立てベッドから立ち上がった男が部屋の明かりを付けると、A子は肩から下を隠した。十分恥ずかしい事をしたと言うのに、少女は裸を見せるのを拒む。 「……もう良いだろ? 遅くなる前に帰れよ」 汗ばんだ身体のままにカーペットの上に座れば、A子の方に脱がせた服を放る。丸まって紐のようになったパンツを手に取れば、女は小さく悲鳴を上げた。下着を手に取り全て布団の中に隠した少女は、可愛い我が儘を告げる。 「……泊まりたい!」 頬から耳を真っ赤にしたA子は、布団に顔を埋め唸った。 「大胆になったモンだ」 鼻で笑い飛ばした赤毛の男は、割れた腹筋と見事な胸筋を撫でながら立ち上がる。A子が顔を上げたと同時に偶然見えた股間は、縮んではいたが逞しく、とてもセクシャルなモノに見えたのか、恥ずかしそうな顔をした。 「水しかねぇけど、飲むか?」 女が首を縦に振るのを確認した男は、キッチン横にある冷蔵庫を開け、残り三本になっていたミネラルウォーターのペットボトルを手に取る。 「ホラ、飲みきってくれよ。勿体ねぇから」 細く白い指でキャップを開け一口だけソレを飲んだA子は、再びキャップを締め大事そうに両手で持った。細かい水滴が表面に纏い、手のひらを濡らす。 「………今も、青峰君は彼女と会ってるの?」 ペットボトルを彼女の手から奪い、ベッドに再度腰掛けた男は、ニヤリと笑うと小さな顎を軽く掴み顔を近付ける。そうしてキスを寸でで止めた火神は、囁くように質問の答えを告げる。 「聞かない方が良いぜ? そういうの」 相手が何かを思う前に、強引に似た強さで深いキスを始めた赤毛の男は、たった今……玄関の向こうへ"二人の来客"が訪れた事に、まるで気付かない。 |