日差しが厚いカーテンの隙間から射し込めば、看板の向こうには薄青く綺麗な空が広がっていた。男は身体を起こすのだが、ギシリと関節が痛む。重い頭を無理に振って、意識を覚醒させる。 室内に掛けられた時計は短針が10を指していた。成る程、彼は十時間も眠りこけていたらしい。頭と身体を襲う鈍い痛みも、寝過ぎた為だろう。 大量に汗を吸ったパーカーはほんのりと異臭を放っていた。せめて肌着を着るべきだったと、赤毛の男は余裕を持った判断が出来るようにまで回復していた。 細い梯子に足を掛ければ、素足に食い込む足場の不安定さを感じる。昇降する度にいつか壊すのでは無いかと考えるのだが、今回も無事なようだ。 シーツの上で家主の姿を見付けられなかった男は、部屋を見渡すとベッドの下に毛布の塊を見付ける。少しだけ捲れば、B美がそこに居た。感染予防にマスクを着けた少女は眉も無く細い目を閉じ、眠りの世界に居るようだ。 「……ったく、起こしてくれよ」 未だ痛む声帯を震わせ、声を発した火神は軽く頭を掻く。化粧の施されていない顔は、薄っぺらで特徴が無かった。最初見た時は驚き、その後に爆笑したモノだ。ビンタされた時の張り詰めた痛みは張り未だに覚えいる。 起こすのも可哀想だと、化粧道具と空き缶で乱雑になったテーブルの上を見れば、鍵を見付けた。だから赤毛の男はソレを手にし、部屋を出る。施錠したらポストから鍵を滑らせ室内に落とす。 同じようなドアが幾つも並ぶ集合住宅は、質素な癖に生活感を感じさせた。すぐ傍の公園からは楽しそうな子供の声が聞こえた。そのキャアキャアした喜びの中に赤ん坊の泣き声が混じれば、昨夜B美に弱さを打ち明けみっともなく泣き尽くした事を思い出す。 ――ただ、温もりが欲しかった。体感的なモノでは無くて、心の安らぎが欲しかったんだ。弓のように張り詰めた精神が切れた男は、ずっと泣きたいのを我慢していた。だから、都合の良いの元をB美を訪れた。 「……そういう男なんだよ。オレは」 誰に伝える訳でもないその言葉を呟き、ボタンでエレベーターを呼べば、ドアは直ぐに開き四角い箱が口を開けて待っていた。 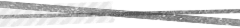 「――珍しいな。お前がオレを呼び出すなんて」 その緑多い公園は賑やかだった。風が冷たくなってきた今は、晴れの日でも過ごしやすい気候だ。【火神大我】を呼び出した高尾は、やって来た赤毛の男を見た瞬間に顔を綻ばせた。噴水前のベンチに腰掛けていた黒髪の男は手を伸ばし握手を催促するのだが、火神はソレを無視した。 「旧友との再開を懐かしみたくもなるよ」 "旧友"なんて小洒落た言葉を鼻で笑い飛ばした火神は、高尾の横に腰掛ける。目の前の噴水が定時を報せる為に噴き出した。 「んで? 何の用? 金なら貸さねぇけど」 人聞きの悪い冗談を告げた火神は、上着のポケットに両手を入れた。 「…………こないだ会ったA子ちゃんさぁ、好きなの? 彼女でしょ?」 高尾を横目ながらに上から下まで眺める。緑色のロンTには派手な図柄が印刷されていて、下はクリーム色のチノパン。ラフながらに難しい組み合わせを着こなした高尾を心の中で称賛しながら、赤毛の男は、素っ気なく言葉を返した。 「質問の意味が分からねぇな」 半年前、予約に苦労して手に入れたこの黒いスニーカーは、火神の身体には似合わない気がした。そんな下らない事を考えながら足元を眺め、赤毛の男は先の台詞を呟いた。 「………あの子、二人から奪って良い?」 「"オレ"に言うなよ」 ジロリと隣を睨むと、台詞とは裏腹に高尾和成の顔は笑っていた。その表情に気付いているのか、気付いていないのか、黒髪の男は言葉を続ける。 「影でコソコソ出し抜くの……嫌いなんだよね、オレ」 「大層立派な心掛けだな」 正面の噴水を眺めながら、当てこすりを言えば高尾は黙る。不機嫌と言うよりは、こちらの出方を伺っているようだ。だから赤毛の男は非難するように口を開いた。 「でも、そんな優しい理由じゃねぇんだろ?……本当は」 「人聞き悪い事言わないでよ」 口を曲げてコミカルに不満を露にした高尾は、整った一重の下にある瞳を二つとも火神に向ける。 「オレらより『自分の方が上だ』って……証明してぇんだよな? 高尾、お前はそういう人間だ」 目が合えば、お互いが相手を睨む。強者と強者がぶつかれば、どちらも身を引かない。それなら相手を退かすまでだ。 「――まさか。A子ちゃんに、惚れただけだよ」 無言を打ち破ったのは黒髪の男で、笑顔のままに視線をずらした。 「真面目で地味な人間同士、お似合いだぜ? 案外お前と付き合った方が、アイツも幸せかもな」 それは【青峰大輝】の本音だった。恐らく、火神は恋に恋をしている状態だろう。青春の全てを競技に注いでしまったあの男は、男女交際に夢を見ているに違いない。まるで女子高生と何等変わりが無い。 「かがみん、冷たいんだね。――彼氏なのに」 「見え見えの喧嘩を買う余裕がねぇだけだ」 ハハハ……と笑った高尾は、その場に漂う緊張した空気を紛らわしたくて「その台詞、格好良いね」と冗談を口にした。その余裕さに伝えたい事が終わったのだと察した火神は、ポケットに手を入れたままベンチから立ち上がる。 「用事がそれだけなら、帰るぜ? オレ」 「……何か食べてかない? 幾らでも奢るよ?」 男二人でランチする趣味が無い赤毛の男は、ストレートに断りを入れる。 「嫌だ、勘弁しろ。病み上がりなんだよ」 「かがみんって、具合悪くなるんだ」 皮肉に似た質問をぶつけられたのだが、それに答えられず口を閉ざした火神は、噴水が跳ねるのをじっと見る。 隣に座ったまま動かない高尾をジロリと見下ろした赤毛の男は、最後に質問を投げ掛けた。 「――"アイツ"には、言うのか?」 「峰っちね? オレから言った方が良い?」 見上げた視線が再度ぶつかり、二人は目で互いを探る。特徴的な黒い眉を上げた赤毛の男は、面倒臭そうな顔で溜め息を吐いた。 「止めとけ。殴られてぇなら別だけどな?」 「……オレ、火神に殴られると思った」 いつものふざけたあだ名では無く、名前を呼ばれた瞬間に肩が震えた。――そうだ。"オレ"は【火神】なんだ……。すっかり"火神"と呼ばれるのに慣れ、その入れ替わった事実を忘れていた。そして気付かぬ内に【青峰大輝】を露見していたは赤毛の男は、自分の失態に唇を噛んだ。 「――……病み上がりだって、言っただろ」 そう誤魔化す言葉を呟き、最後に視線を流した火神は背中を丸め噴水前を後にする。その猫背を最後まで見送った高尾は、違和感の正体を探り出した。 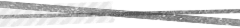 ――鼻の奥が熱い。褐色肌した男は、風呂上がりに脱衣場で身体を拭く。湿った温風が浴室から抜けてきた。まるで顔面をぶつけたような痛みに辟易した瞬間、鼻腔からタラリと何かが垂れるのを感じる。 「……鼻ん中までだらしねぇのかよ。この身体は」 ティッシュを手に取り、鼻から出る体液を拭けば熱い感触が繊維に広がる。捨てる為に丸めたソレは、白の中に赤を主張していた。 慌てて鏡を見れば、右の穴から赤黒い血液が流れ出している。腕で擦り液体を拭けば、手首から手の甲に向かい赤い線が出来る。 急に咳き込みが酷くなり、腰を曲げ洗面台の排水口と向かい合う。涙で視界が滲み、赤い液体が飛ぶ。咳の度に横隔膜が激しく伸縮し、肺を圧迫する苦しさに悶える。胃が揺さぶられ、洗面台に吐瀉物を落としズルズルと座り込めば、鼻から流れた血液が辺りに飛付していた。 ハァハァと息も荒く肩を抱いて小さくなれば、褐色肌が割れた腹筋を包み、陰毛が生えた一帯が見える。生殖器は縮こまり、先端が不気味に黒い。ソコに一滴の赤い液体が落ちる。 口を閉じる気力も無い青毛の男は、己の身に起こった変化に気付かず裸のまま脱衣場へ身を置く。急に身体が薄くなる気がした。 ――違う……拒絶しているんだ。この身体が"オレ"を……。このままでは身体が起こした恐怖に、精神がやられるだろう。その前に拭い去りたい男は、携帯を手に取ろうと脱衣場を後にする。 『――もしもし? 火神……君?』 「…………愛してる。A子――」 スリーコールで出た"最愛の女性"へ愛を伝えた【火神大我】は、鼻を擦った。 『ありがとう』――。電話の向こうで聞こえた愛に、恋愛へ不慣れな男は心の底から喜びを感じた。 |