今の時代は便利だ。分厚い六法全書なんか無くても、タブレットひとつで勉強が出来る。昼過ぎの閑静なファミレスで食事を済ませた黒髪の男は、知人の到着を待っていた。食べた食器は下げられ、今はドリンクバーのグラスだけが置かれている。 やがて入口から来客を歓迎する言葉が聞こえ、一人の男が入ってきた。背は恐ろしく高く、特注のビジネススーツをバシッと着こなしたイケメンは店員に愛想を振り撒き、タブレットと睨めっこをしている男の元へとやって来た。 「高尾ォ。何なの? オレ、暇じゃねぇんだけど」 挨拶と云う名の罵倒を繰り出し、目の前の椅子に腰掛けたスーツの男は、高尾の前に置いてあるグラスを勝手に飲み干す。中身はコーラで、一緒に飛び込んだチップアイスをガリガリ噛む。 「こんな相談出来るの、宮地さん位しか思い付かないんですよ」 「間違ってないチョイスだったら許してやるよ」 そう言って上着を脱ぎネクタイを緩めた高尾の連れは、左手に嵌めた腕時計を眺めた。高校時代に比べたら茶髪寄りにトーンダウンしたその髪の毛は、当時から長さが変わっていない。 「人ってどうやって騙すんスか?」 「刺すぞ」 相変わらずの反応速度を見せた男は、ランチメニューを開きながら目の前の黒髪を睨む。 「法学部行きやがったお前の方が得意だろ? そんなの」 「文系から一流商社入った宮地さんには負けますよ」 見え見えのヨイショに悪い気しない【宮地清志】は、ニヤリと口角を上げた。それを見た高尾は口を尖らせ言葉を続ける。 「結局顔なんだよなぁ……? じゃなきゃこんなアウトローな人、ヤクザにならなきゃオカシイですよ?」 「轢葬してやろうか?」 物騒な台詞は、言い回しだけが変化し中身は六年前から変わらない。商社マンの男は胸ポケットから煙草の箱とライターを取り出すと、一本を喰わえ火を付けた。 「大坪さんが知ったら、怒りますよ」 「キャリア付きの自衛官様は、頭がお堅いからな?」 そうやって元チームメイトを野次り、クツクツ笑った宮地は煙を吸い込んだ。肺に浸透したソレを逃がすのに、上を向き煙を吐く。 引退試合であるWCは決勝トーナメントで強豪・洛山に敗退。結局宮地はバスケを辞めた。彼は競技に全てを捧げた三年間を「就活の良いネタになるな」とおどけて話したのだが、内心は煮え切らない思いを抱えている筈だ。敗北は、人を強くも弱くもする。たまたま宮地は"後者"であっただけだ。 大学を経て商社に勤めるこの男は、毎日終電過ぎまで接待と称し飲み歩き、休憩は煙草を吸う事で補う企業戦士になった。イケメンに分類される甘いマスクや体型は、高校時代から何も変わらないが、身に纏う"情熱"は純粋な赤の中にドロドロした黒を抱えているようにも見える。 大人になった宮地も魅力溢れる人間だが、当時の高尾が抱いた憧れは色褪せていた。それなら、同じようにバスケから遠退いた自分も同じだろう。あのコートに立った時に感じる背筋から脳に突き抜けるような高揚感は、もう実感出来そうにない。 だからこそ――【火神大我】や【青峰大輝】が羨ましい。妬ましい。 四年前。最後の大会に感じたソレは、最後に味わった"圧倒的な敗北感"だった。醜くても構わない。高尾和成は、内にある"嫉妬"と云う感情を初めて許容する事にした。 高尾は何時もの明るい調子を脱ぎ去り、重々しい口調で宮地を頼る。 「相談、あるんですよ」 「早く本題出せよ。火ィ付けるぞ」 煙草を口から離した宮地が人差し指と中指で挟んだソレを親指で叩けば、灰皿が残骸を受け止めた。 「恋人が居る人間を、奪いたいんです」 一瞬驚いた顔をした宮地は、直ぐ様嬉しそうな笑顔を作った。背徳的なゴシップは人を喜ばせる。 「イイコちゃんのお前が!?」 「リベンジっス。オレ、恨み深い蠍座ですから」 「星座って、緑の真ちゃんかよ? 懐かしいなぁー」 宮地がその名前を出すのも、酷く昔な気がした。それでも『会いたい』と言わない辺りから、彼が過去に囚われていない事を伺えた。 「どんな女なの? アイドルみたいなら紹介して?」 「普通っスよ?」 タイプに該当しなさそうなその女に興味を失った宮地は「んだよソレ」とぶっきらぼうに言うと煙草を灰皿に押し付けた。 「彼氏が居るって言うか……二人の男が取り合ってるんだよねぇ」 独り言のようにそう呟いた黒髪の男は、電源切れ画面が黒くなったタブレットを眺めた。反射して写る自分は何だか大人になりきれない子供のように無邪気にも見えた。 「何? ソコにお前も混ざんの? よっぽどの"恨み"を買ったみたいだな?」 鏡のようなタブレットから目を離し、向かいに座る男と目を合わせた高尾は、口元に弧を描いた。 「そんな感じっス。――でも次は、負けない」 その企みを含んだ笑顔は、六年前にコートの上で見せたモノと同じだった。高尾和成もハンターだ。逃げるモノは追いたくなるし、手に入らないモノこそに価値を見出だす。恋愛はゲームだ、それならゲームメイクをしなくてはいけない。数多くの女を泣かせてきた宮地をコーチに招いた彼は、あの日カフェで何年振りに見た彼等を思い出して闘志に震えた。 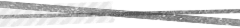 青い頭を抱え背中を丸めた褐色肌の男は、ベッドに腰掛け己の行動を戒めていた。欲に任せ犯し、彼女を傷付けるような真似をしてしまった。今ではもう、三ヶ月以上待った意味が何も無くなっていた。 腹部に"破瓜の血液が混じる精液"を飛ばされ困った顔をしたA子は、現在シャワーを借りている。 「…………火神どうすんの? 訴えられたら」 ボクサーパンツを履き、カーペットの上に胡座を掻いた赤毛の男はそう問い掛ける。単純明快な"火神"からすれば、訴えられる程嫌われていた方がいっそ楽だろう。 「オレ、駄目だな……。頭がカーッとなったんだよ」 シーツに付いた赤い染みを眺め溜め息を吐いた赤毛は、尚も項垂れる青毛に声を掛ける。 「昔からだろ? お前が暴走すんのは」 特徴的な眉を潜めた男がそう告げると同時に、ガチャリと浴室の空いた音がした。青毛の男は腰を僅かに上げ不安そうな顔で廊下を見た。 ヒタ、ヒタ……と素足でフローリングを歩く音がした。髪を濡らしたA子が部屋に戻り、青峰宅にあったXLのTシャツをワンピースのように羽織っていた。 「お風呂、ありがとうございました」 少女は頭を下げ、家主にお礼を告げる。しかし、腰は戻しても顔を上げる事は無かった。 「……悪ィ、本当に。い、痛いよな?――送ってくから、おんぶしてやる」 褐色肌した青峰が心配を口にするのだが、顔を上げないままA子は首を横に振る。それは自分を安心させる為に振ったのか、拒絶する為に振ったのか――意図が読めない青毛の男は唸った。 「……下、何か履いて?」 「あ、あぁ。そうだな」 男性器はすっかり小さくなっていたが、全身を隠しもしない青峰大輝の姿は、少女からしたら恥ずかしくて耐えられなかったようだ。床に脱ぎ捨てた黒いボクサーパンツを履いた男は、再度ベッドに腰掛けた。 「送って下さい。痛いので……」 "痛い"と云う単語にギクリとした褐色肌の男は、唸った後に慌てて服を着た。そうして依然胡座を掻き座る赤毛の男に目配せをすると、テーブルに置いた鍵を手に取った。 「……Tシャツ、今度返してくれ」 現在の家主であり、服の持ち主である赤毛の男がそう告げる。A子を取られるのが嫌なのか、青毛の男は眉を下げて困った顔をして玄関に向かった。だから情けない顔したソイツを指差して「アイツ経由でも良いから」と言葉を添えてやる。 「……ありがとう、かが……アオミネ君」 「慣れねぇよな? こんな事……」 立ち上がると少女の背は低くて、酷く切なくもなる。こんな男二人を相手にした女は、無理に挿入された痛みを我慢しているに違いない。頭を撫でると、初めてA子は顔を上げた。後頭部を押し、胸元に引き寄せようとすれば、玄関に立った"本来の自分の声"が少女の名前を呼んだ。一度だけ恋人のように視線を合わせた二人は、これが最後だと悟る。 「A子」 ワンルームから出て行こうとする相手の背中に声を掛ける。彼女を手離したかった。だって、それが"当たり前"だと思ったからだ。このまま付き合いを続け、彼女が自分の中に【火神大我】を求めてるのなら、それはお互いが幸せになれない。 「――……弁当、美味かった」 最後の言葉は、相手に届いたのか判らない。いや……こんな不条理な関係なら、届かない方が良い。少女は振り向く事無く部屋を後にした。 ――嵐が過ぎたようだ。結局、彼等二人は【青峰大輝】の中を散らかして乱して行った。今までアチラさんが所持していた"自分の携帯"を手に取り、ダイヤルを掛ける。どの位待っただろうか。コールが消え、相手が応答した。 「――来いよ。会いたい、今から……。アパートの方」 受話の向こうは何も言わずに、半ば強制的に通話を終了した。 :: :: :: 「久しぶりだな」 本日二回目の出迎え。玄関の向こうにはB美が立っていた。来るとは思っていたが、もしかしたら来ないかもしれない。こんな風に半信半疑にする事で、予防線を張った【青峰大輝】は、相手が答えてくれた事に安堵した。コイツに拒絶されたら、自分は独りぼっちになる。 「興味無いって言ったじゃん……」 「グダグダ言うなよ。気が変わったんだ」 眉毛だけを描いた薄い化粧に、やる気の無いジャージ姿。だけど紫のラインが入った黒いソレは、彼女が泊まりに来る時によく着て来るモノだ。二人の間にあった無言の約束事。それが懐かしく思えた男は、少しだけ笑った。 「大我は?」 すまして腕を組んで立つ彼女は、向こうの身体を気に掛ける。少しだけイラッとした赤毛の男は、しゃがれた"その男の声"で返事をした。 「今頃、本当の彼女と盛ってんじゃねぇの? オレの身体で」 大きな目を見開いたB美は、その言葉に驚きを隠せないようだ。 「でも、ギクシャクするから終わるって……」 「ギクシャク? してたかもな、なんせイケメンになっちまったからな?」 下らなそうな口調で"自分の本体"を褒めた男は玄関の柵に手を掛け、唸る女を眺めた。 「…………男って、最低。口ばっかり」 「火神と付き合う気で居たの? 浮気性だな、お前」 意地悪な台詞を振れば、気の強そうな瞳で睨まれた。 「まぁ、良い。入れよ。んなトコ突っ立ってても仕方ねぇだろ」 気の利いた言葉も言えない、ぶっきらぼうな男はそうやって仕方無さそうにB美を部屋に招く。『何で呼び出したの?』と聞かれても、きっと【青峰大輝】は答えられない。自分が理解していない事は、他人に教えられない。 「水しかねぇや」 ベッドの上で体育座りをしていたB美へ、ペットボトルのミネラルウォーターを差し出してやる。常温のソレを、この女は飲みきった事は無い。そして置き忘れて帰る。それが"いつものパターン"だ。今回だってきっと置いてきぼりにするのだろう。 「大学、ちゃんと行ってんのか? 進級出来んの?」 缶ビールのプルを開けた男は、冷えた液体を体内に流し込んだ。火神が聞いたら驚くだろうがB美は自分達より学年も歳も二つ下である。だからこそアソコまで我が儘を言えるのだろう。相手が年上なら、自分が"年下"である事を免罪符に出来ると云う訳だ。 「そっちは……?」 「四回生なんて、する事もねぇよ」 炭酸ガスを喉から抜けるのを無理矢理飲み込めば、逞しい胸元が膨らんだ。息を吐くと、アルコールと麦の香ばしい香りが抜ける。程度良く酔いが回っている間に女の唇を奪おうと顔を近付ければ、意外にもソレは拒否された。 「――や……やだっ」 「慣れとけよ。火神と付き合いてぇなら、戻った時にこの身体なんだから」 キスしようとすれば強引にも出来る。だけど赤毛の男は紅い瞳でB美を見つめた。目の前の彼女からこの厚い唇を求められたら、全てを奪いたくなるだろう。 「――……別に、大我とは、付き合いたいとか」 もしB美が火神に心変わりしたのなら、奪い返してやる。急に湧いた【嫉妬心】が彼を焦がした。 「"オレ"がシてェんだよ……。大人しく、抱かせろよ」 顎を掴み、強引に唇を奪う。くぐもった声が相手の口内で反響するのだが、気にせず舌で押し込めた。さっきA子を貫いた"痕"が残るシーツをそのままに、華奢な女を押し倒し上にのし掛かれば、二人分の体重にベッドが激しく軋んだ。 手首を掴み、ジーンズの上へ誘導すれば五本の指で優しく撫でられた。ベルトを外され、下着越しにも熱を感じる程に勃起した性器を引っ張り出され、上下にシゴかれる。 辛抱堪らない男はスカートを捲り、下着をずらすと愛撫も無い女性器に肉棒を押し込む事にした。勿論避妊具なんて付けてはいない。B美のソコは、自分を迎える程度には濡れていた。 巨体の下で喘ぎ足掻く女は気付いていない。自分の腰元に赤い染みが点々としている事に――。 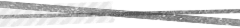 本日の学習塾も閉校し、職員準備室には数名の社員とアルバイトが在室していた。その中で、怖い顔をした緑間が色素の薄い少年の前に新聞を置いた。テストの採点も途中に手を止めた黒子テツヤは、顔を上げて背の高い男を視界に入れる。差し出された新聞を赤ペンで指しながら。 「……これは?」 その返答の代わりに、人差し指で叩かれた小さな記事の見出しはこうだ。 【女子中学生二名が自殺。殺人か】 緑間が自分に声を掛ける理由なんてひとつしか思い浮かばない黒子は、新聞との関連性を問う。 「火神君達の件と、関係あるんですか?」 緑間はキョロキョロと周りを見渡すと腰を曲げ肘を付き、デスクの前に座る黒子へ顔を近付けた。 「同じベッドで、一緒に死んでいたのだよ。――首を絞め合ったようだな」 唸るような低い声で緑間はそう告げた。驚いて記事を読めば、確かにそうとも読み取れる文章が記されていた。 「……中学生ですよ? 出来る筈が無い。入れ替わるにしても、動機が無い」 「恐らくだが……達成で得られる結果を【入れ替わり】から別のモノ変えたのだろう。――例えば、『永遠の友情が得られる』なんて言われれば、その位の年代の女子には魅力的なのだよ」 「誰かが、人為的に噂を流しているって事ですか?」 今までは都市伝説が一人歩きしているのだと思っていた。しかし緑間の発言を聞く限り、どうやらそんな単純なモノでは無いようだ。人が噂に誘き寄せられていると思っていたが、そうじゃなく――噂の方が人の元にやって来ているようだ。 それならば全国を探せばこのような事件が沢山あるのかもしれない。こうやって噂に惑わされ、失敗して命を落とした犠牲者が大勢居るのかもしれない。尊い命がこんなにも簡単に蔑ろにされる。それが恐ろしく、背筋に冷たいモノが走った。大切な相棒だって酔った勢いで実行してしまった。彼等は恐ろしく運が良かっただけだ。下手したら今頃は肉体を燃やされ、骨だけが土に埋まっていたのかもしれない。 「火種が無ければ、火事は起こるまい」 緑間は新聞を彼に押し付け、デスクを離れた。しばらく採点途中の答案用紙から目を離せなかった黒子は、昨日の青峰が言っていた台詞を思い出していた。その台詞と、この記事の共通点――。それが、重要な突破口な気がした。 『……覚えてねぇんだ。でも、火神の記憶にあったんだよ。オレが、コイツの首絞めてた』 |