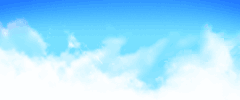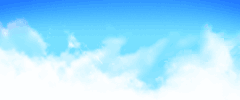
本日の青い反転世界より
「レイさん、か」
ページにはレイという名前が記されているだけで、所在地だとか、どんな見目形だとかの記載はなかった。黒影はいつもこんな風に重要なことを僕に知らせない。もしも女性だったならどうしたらいいのだろう。僕はその時を思って身震いした。姉のせいで女性という生き物に対する嫌悪感と恐怖感が拭えないのだ。部下にも女性のような奴はいるが、彼は性別上は男なので平気である。彼はそれを指摘されると酷く怒るのだけれど。そういうわけで、極限まで女性との接触機会を減らした僕にとっては、このレイさんという未知の存在が不安で仕方ないのだ。もう一つ不安の理由を付け加えるとするならば、この書類を作成したのは黒影である。
行く宛もないままに僕は反転世界を彷徨った。飛び回っていたせいで疲労感が溜まっているため、すぐそばの道へ降り立つ。重力がないように曲がりくねった建物や道が多い中で、ここはまっさらで表の世界とそう変りないように見えた。せっかくだ、時間もあるし探し人がてら観光でもしようかと、僕は歩きはじめた。この世界にはギラティナが多く存在していると書類には書いてあったはずなのだが、そんな気配は一つもない。どこからか遠く、水が流れるような音が聞こえるだけで静かだ。さわさわと風が吹くと、道の側に咲く花が揺れる。あぁ、なんていい世界なのだろう。喧噪からも様々なしがらみからも解放された気分に浸ることができる。目を閉じて近くの椅子に腰かけた。そういえばこんな風に心穏やかになれたのは久し振りな気がする。ちょっとだけ仕事を忘れてみるのもいいのではないだろうか。日頃頑張っている僕へのご褒美として、いいのではないだろうか。あぁ、そう考えたら、なんだかとても眠く――
「おーい、そこのポエマーくん」
なんだよ、僕は今眠たいんだ。誰だよ話しかけてくるのは。
「いや、うん、君、心の声が駄々漏れだからなあ」
はぁ? 何を言ってるんだかわからないよ。心の声が漏れるなんてそんなことある訳ないじゃないか――と考えて、僕の意識は現実に一気に引き戻された。
「はっ、ああ!?」
思わず素っ頓狂な声を上げてしまい、あわてて口を噤む。見られてしまった。聴かれてしまった。僕はなんて恥ずかしい奴なんだ。羞恥心で顔が真っ赤に染まる。視線を自分のふとももに下げているせいでよくわからないが、目の前に誰かがいるようだ。そのひとは面白そうにくつくつと笑っている。
「うーん、お前中々面白い奴だな。で、何してるんだ? ナンパか? 生憎とこの辺にまともな女はいないぞ」
ナンパじゃない仕事なんだ、と言いたいところだが、まだ羞恥心から抜け出せない。顔を上げられないでいると、目の前のその人はあ、そうだ、と小さく呟いて右手を僕の視界に入るように伸ばしてきた。手には紙が載せられている。よく見てみればそれは僕が今日持ってきた書類の一部だった。
「そこに落ちてたからな。お前のかと思って持ってきておいたんだよ。どう? 合ってた?」
「あ、は、はい、ありがとうございま…」
お礼は目を見て言うものだとダニエラに常日頃言われていた言葉が染みついている僕はバッと真っ赤に染まった顔を上げた。が、目の前のひとの顔を視界に入れた瞬間、赤は一気に青に染まった。
「ん? なんだ? もしかして私をナンパしようって魂胆かな」
「あ、ぅ、う……」
女性だ。 誰がどう見たって、女性だ。上を見ても、下を見ても、女性を象徴するそれと丸みを帯びた曲線が否が応でもその事実を僕に認めろと言ってくる。紙を受け取ろうとしたはずの手は空中を彷徨う。焦点が定まらずふらふらする。なんて情けない姿だ。見ず知らずの女性を前にこんなに狼狽えてしまうだなんて。かろうじてわかるのは、このひとは僕と同じ種族であることぐらいのものだ。
挙動不審な僕の様子を見て女性はきょとんとしていたが、すぐにふっ、と笑うような声を出した。笑われてしまった。当然だろう。それでも僕は女性が苦手なんだから。必死に頭で言い訳を繰り返しながら僕は鞄の紐をぎゅうと握りしめてこの状況を耐えようとした。
「ははは、お前さてはシャイなんだな? 心配するなよ兄ちゃん。私はそういうの気にしないから」
「ヒッ!?」
その女性はあろうことか笑いながら隣に座ってきて、僕の肩にその細い腕をがっしりと回してきたではないか。僕はまたも素っ頓狂な声を上げて露骨に怯えてしまう。シャイじゃない、シャイなわけじゃないのに。そう伝えたくても、今僕に触れているのは女性なのだというただそれだけの事実が僕を苦しめる。僕がそんなことを考えているなんてつゆ知らずな様子で女性はなおも朗らかに声をかけ続けてくる。
「今何してるんだ? 観光か? ここは何にもないところだよ、なんならもっとマシなところに案内しようか」
「い、いえ大丈夫です、仕事で来ただけですので」
「仕事? へぇ、そういえばお前みたいな奴はこの辺じゃ見かけないけど…もしかして別のとこから来たギラティナくんかな?」
「はい、そ、そうです、すみませんあの手を……」
「へえ、やっぱりそうかぁ。ねぇねぇ、仕事が終わったら私とお茶しないか? いいお茶を淹れる奴がいるんだよ知り合いに」
「けけけっこうです僕仕事が」
「まぁそういうなよ、もう私とお前の仲じゃないか」
どんな仲だ!!! と力の限り叫んでやろうとしたが、のどから出たのは情けない呼吸音だけだった。マシンガントークをひたすら僕にぶつけてくる女性は僕の反応が面白いのかどんどん距離を縮めてくる。それはつまり、胸にあたるやわらかな感触が強くなっていくというわけで、それはつまり、僕のトラウマを抉りだすものだということで。さっきまでの穏やかな気持ちはどこへやら、僕の脳みそは悪い記憶をどんどん掘り起こして的確に僕を苦しめていく。もうやめてくれ、僕は仕事がしたいだけで、ちょっと休みたかっただけで、だから遊んでいる暇などないのだ。そう思った途端、僕はスクッと勢いよく椅子から立ち上がっていた。
「お、なんだ? 行く気になったか」
「僕は仕事中ですのでいきません、レイさんというお方に用事があるんです。仕事を長引かせる訳にはいきません。せっかくのお誘いですがお断りさせていただきます。それではさようなら」
「何? レイはわた……」
まくしたてるように早口でそう告げると僕は今までにない速度で空を飛び立った。仕事? そんなもの知るか。こんな気分のままで出来る訳がないじゃないか。帰ろう、屋敷へ。そうするのが今の僕には一番の薬だ。先ほどの自分の発言と矛盾した思考を巡らせながら、僕はひたすらに美しい青の世界を飛んで行った。
――そういえば別れ際、あの女性が何かを言おうとしていた気がするが… もう今の僕にはどうだってよかった。
「うーん……シャイな兄ちゃんだ」
私は右手に握られたままの紙切れを見つめながら呟いた。彼の言うことが本当なら、レイは私なのだけれど。それを聞く前に飛び立ってしまったのでどうにもならなかった。
ああいうタイプには中々出会ったことがなかったのでいい記念になったと思いつつその紙切れの文字に目を滑らせていく。対して重要なことでもあるまいと思っていたのだが、最後の行にサインを見つけて視線を止める。ひどく小奇麗な字でシヴァとあった。シヴァ。どこだかの国でいう、破壊神の名。妻を何百と持っていたとも言われていたような気がする。が、とてもあの青年にそんな印象はなかった。
なんと見た目に反した名前だろうか。名付け親は皮肉を込めたのか、それともただ語感が気に入っただけなのか。いずれにせよ、久し振りに見つけた面白い存在だ、忘れることはしばらくないだろう。
私は彼が”レイ”に会える日を心待ちにしながら、彼の消えていった青い青い世界を見つめた。
八咫さん宅ギラティナ♀寄り レイさんをお借りしました。口調とか間違ってる気がするゥウウ