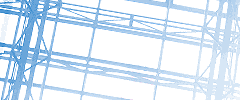
ちいさいころは、水溜まりに自ら飛び込んでいったのに、今では服の裾が濡れるのを気にして、避けて通っている。
随分と臆病になったものだと、要は思う。
昨日の豪雨の尾を引いてコンクリートはしめやかに濡れていた。そこを五人、道に広がって歩いていく。いくつもの自転車がベルを鳴らし、通勤通学の人々が無表情に隙間を縫って通り過ぎる。それをぼうっと見送っていた。
「もー要っち、聞いてんの!?」
「え?…ああ悪い、何の話だっけ」
「要が幼稚園の時にかっこつけて、ジャングルジムてっぺんまで上って、降りられなくなった話」
「そういやありましたね〜そんなこと」
「えーっ、要っちダッサー!」
「知らねぇよ!…っつぅか今そんな話してなかっただろ!」
「確か、かおり先生の前だからって張り切っちゃったんだよね」
「そーそー。駄目だよ悠太、そんな要なんかについてのどうでもいいことは忘れて、俺の好きなアイスの種類覚えてよ」
「お前それ絶対悠太パシらせる気だろ」
「頼まれても俺は行かないよ…。ていうか、要なんかって言われたことはもういいの?」「よくねぇよ」
また一つ、水溜まりの上をまたぐ。並んだ一番端からバシャッと音がして、何すんの千鶴水かかったじゃん。ごめんってばゆっきー、つい童心が騒いで…うわっ!はいお返し。ちょっと二人とも子供じゃないんですから、
「不思議だよね」
隣で悠太が呟いた。
「昔できたことが
今できない、なんて」
「…ああ」
きっと、悠太も要と同じなのだろう。その大人びた横顔は、まつげの陰影と相まってどこか悲しげである。そんな顔するなと面と向かって言えないあたり、やはり本能を手放しかけているのか。
幼い自分なら―
否、幼い自分は知らなかった。
「確かにそうだ。でも…今だから気づいたことはある」
噛み締めるように言葉をつないだ要を見て、悠太は
「それを伝えることはできないのに?」
小さな水溜まりを飛び越えて微笑んでみせた。
色が変わるほど袖を濡らしたい