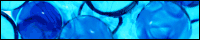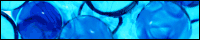
「え゙」
屋台の若い兄ちゃんに、すっかりお馴染みの種類を告げると、祐希が信じられない、とでも言いたげな視線を寄越してきた。さっきからずっと俺の髪の毛を焼き続けている太陽光線みたく、遠慮なんてものは食べたことがないようだ。非常に良く照り返しなさる地面様のおかげで、むき出しの肩がじりじり痛い。ちなみにここは、白砂美しいビーチなんかじゃなく、商店街を少し外れたところに昔から、そう俺達が生まれた時にはもうあった、かき氷屋だ。
この人はいったい何代目になるんだろう。タオルを首にラップよろしくぴっちり巻きつけている。絶対暑いでしょ。
あ、俺はいちごね。祐希が首だけ前に出してつけ加えた。汗だくの兄ちゃんは笑って応える。
ガガガガ、と機械が唸って砕氷が始まった。セミをも凌駕する大音量。そして俺は案外、この音が好きだ。夏を彩る重要なスパイスのひとつ。
「ねぇ」
「なに?」
はっと我に返ってすぐ、俺は約15分前の自分がとんでもない失敗を侵したことに気がついた。俺の肩はどうやら、他の不可視光線にも焼かれていたらしい。やっぱりタンクトップを選んできたのは間違いだったのだ。俺は祐希の熱視線に触れないように、そっと体の向きを変えるが、はたして無意味だった。
「ねぇ悠太、なんでそんなにえろい格好してるの。そんなに肌だして…全く、とんだ子に育っちゃって」
「…」
この夏、正式に、俗に言う交際関係になった。それからというもの、祐希の脳みそは暑さにやられて、溶けるか沸くかの二極化状態だ。最初のうちは俺自身も満更でなく照れたり何やらしていたが、それも今となっては昔のこと、どうやって逃げるかが目下の俺の課題となっている。別に双子だし兄弟だし、この後に及んで祐希のことを嫌いになった訳じゃない。ただ、大きな声では言えないが、ちょっぴりしつこいのだ、祐希のキスは。
程なくして二つのかき氷が完成した。対極の色のシロップが何だか可笑しい。
また口を開きかけた祐希を敢えて無視し、俺はさっさと備え付けのベンチに座る。それは木製のくせに熱がこもっていて、俺は悲鳴をあげそうになった。
「悠太、最近ブルーハワイばっかりじゃない?」
ぶす、と氷の山にストロー状のスプーンを差して祐希が問う。このベンチによる異常な熱伝導をもってしても、祐希の無表情は崩せない。それでも、この距離から見れば、首筋の辺りにうっすら汗粒が浮いているのがわかる。ごく自然に光るその粒達は、俺の鬱憤をいささか晴らしてくれた。
「そうだっけ?」
しらばっくれて、毒々しいかき氷をぱくりと口に含む。祐希が「あ゙ーあ…」と残念そうに小さく呻いた。心の中だけで、あっかんべー。俺の舌はさぞかし、おぞましく変色していることだろう。相変わらずそんなに美味しいとは思えないけど、機嫌ベクトルが急上昇した俺は、すっかり勝ち誇って続けた。
「祐希、青って、ダイエットに向いてるんだって。食欲を失わせる色だから」
「だから最近俺の前で青いものばっか食べるんでしょ。気づいてたよ。俺、悠太のことなら何でもわかるもん」
キィン。
冷たさが電光石火の勢いで脳を走り回った。口内の青いシロップが急にべたつく。それをやっとの思いで飲み込んだ。
ばれてた?全部?
「…怒ってる?」
「別に。だって、俺にはそれ、全然効果ないみたいだから。こないだ京都行ったときも、ブルーベリー味の八ツ橋とか普通に食べれたし。
ただ、そんなん正直に試して、実際そんなの意味ないのに、わざわざ苦手なの我慢して食べて、俺のことずっと意識しちゃって、ゆーたってば、お馬鹿カワイイ」
呆気にとられる俺、じりじり視界を埋める祐希の悪くてずるい顔。ミーンミーン…あんなに賑やかだった蝉の鳴き声はいつのまにか、随分遠い。
あ、駄目。頭がぼうっとしてきた。
「ね、いまキスしたら、
舌むらさきになるかな。やってみていい?」
どうやら俺の憂…祐鬱は、夏が終わっても終わりそうに、ない。
青の憂鬱
back
|