
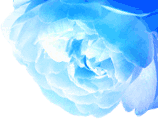

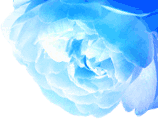
アンサンブル 日々の激務から隔離された、穏やかな午後。入れたてのアフタヌーンティーと香ばしいクッキーのなんとも良い香りが、昼を食べたばかりだというのに小腹を空かせてくる。 一枚サクサクとクッキーを頬張りながら、碧は鏡越しに自分とルカを見た。 「こういうのは私じゃなくて、もっと相応しい方がいると思うんですがねぇ…。」 「まあ、そんなにご自分を卑下しなくても宜しいのではありませんこと?」 凄く似合ってますわよ、と品の良い笑みに諭され、碧はそれ以上何も言えず黙ってクッキーを嚥下した。 鏡に映る自分が、自分じゃない気がして何とも複雑な気持ちだ。しかしやはりこういったヒラヒラキラキラした洋服は、自分よりルカと共にいるヤマトに着せた方が似合う気がする。 根本的にいうと、何故自分はルカの着せ替え人形にされているのだろうか。特別彼女と仲が良い訳ではない。顔を合わせれば挨拶や会釈をするぐらいだ。彼女と同じ任務にアサインされたこともない。 そう碧からして、ルカ・アタラクシアという人間は良く解らない存在なのだ。文字通り彼女は神出鬼没で、気が付くとラウンジにいたりする。何時も何をしているのだろうと、生活リズムすら見えない正に謎の人。 「少し顔を上げて下さる?」 「…へ? あぁ、すみません。」 少し耽っている間に髪は纏め上げられ、次に髪飾りを施され様としていた。それにしても人に髪を梳かされるというのはなんと心地良いのだろう。うっかり気を抜けば寝落ちてしまいそうだ。流石にそれは不味いだろうと碧は口を開く。 「ルカさんって器用なんですね。」 「そんなこと無いですわ。貴女の髪が整えやすいから、そう見えるだけよ。」 「それは…どうも。」 鏡越しに見るルカの楽しげな表情を見ながら、碧は二枚目のクッキーに手を伸ばした。 *** ヤマト+フィルネちゃん 「はい、遠慮しないでどうぞ。」 ラウンジの一角。テーブルの上にズラリと並べられたお菓子はまるで宝石の様だ。カラフルでどれも美味しそうだ。食べ物は視覚からの情報も重要だと誰かが言っていたが、これは正にその通りだとフィルネは思う。それと同時に同僚であるアキラの姿を思い浮かべていた。 「…いや私も人のこと言えないか……。」 「何処か具合悪い?」 「い、いいえ! なんでもないです大丈夫です頂きますっ。」 手近なところにあったケーキの皿を取り、フォークで一口にカットし口に運ぶ。 「美味しい…!」 「良かった。沢山あるから好きなの食べてね。」 「有難う御座います。…でも何でこんなにしてくれるんですか?」 「親睦を深めるのにそれ以上の理由は要らないんじゃない?」 ただ単に君に興味あるのよ、とヤマトはフィルネの口端についたクリームを取りながら柔らかく笑った。 *** サクラ+白ちゃん 「散らかって済まないな。今片付けるから適当に掛けててくれ。」 とは言うものの、サクラの部屋は整理整頓されていて、とても散らかっている様には見えない。テーブルの上にはタブレット端末に書類やファイルが散乱しているが問題は無いと思う。自分も報告書やらなんやらを提出しなければならない時に、同じ状態になるからだ。 「サクラ、お構い無く。」 「そうはいかないさ、身内でも礼節は弁えろとジジイに言われて生きて来たのでな。」 幼少期より叩き込まれた習慣は中々抜けるものではない。以外と真面目なんだな…と白はサクラを見る。ヤマトからサクラの導火線は短く火が着きやすいと聞いていたが、とてもそうには見えなかった。 人数分のティーカップを用意し、ケトルを火にかける。炎と同じ真紅の髪がゆらゆら揺れる。 「で、パジャマパーティは構わないが、実際何をするんだ?」 「眠くなるまで皆で喋ったり…。うん、なんか色々。」 その時その時で内容は違うらしい。でも白は殆ど聞き専で、気が付いたら寝落ちていると言う。 「だから今日は皆が寝るまで起きてる。」 「そうか。無理はするなよ。」 と言っていた白は、皆が集まる前にソファで寝落ちてしまったのだった。 ―――――――――――― 和水さんお待たせしました。今回も企画に参加して下さり有難う御座います。 リクエストの女子達でわちゃわちゃどうしようか迷いに迷った挙げ句、提案して下さったシチュを全部書いてみました(笑)← その上で余り絡んだことがない組み合わせで書いてみたのですが如何でしょう? 少しでもお気に召して頂けると幸いです。 改めて企画にご参加頂き有難う御座いました! ※お持ち帰りは和水さんのみ可。 ← |