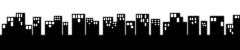ス
タ
┃
ラ
イ
トと逃避行
人は死んだら星になるんだよ。
そうやって言われた時はただ「嘘」だ、なんてだけ思って、それが迷信だっていう事は知らなかった。
あたたかい缶コーヒーを両手で握りながら息を吐く。別に白くなんてならない。冬なんかじゃないし。
ぼんやりと見上げた空は星なんて本当にあるのかってくらい真っ暗。まあ、春なんてこんなものかもしれない。俺はヒロトさんみたいに星や宇宙(っていうか天体)に詳しくなんてないから、夏と冬が天体観測にいいって事くらいしか分かってない。
真っ暗な空を見ていると、何だか心が静かに跳ね上がる。多分深夜に出歩く自分に咎めとか良心の訴えとか興奮とかしてるんだろう。落ち着かないままに指先をこすり合わせて、そういえば爪切らなきゃなと気付く。でも夜だから控えないといけない。
何でかって親の死に目に会えなくなるらしいから。
これも迷信。親の居ない(っていうか孤児院暮らしな)俺にとっては何とも言いようのないものだけど。この迷信を教えてくれたのはヒロトさんじゃなくて、剣城くんだから、仕方ない。その時は剣城くんは、俺の家庭事情ってヤツは、知らなかったもんだし。俺はチームメイトにそういうのを伝えてなんかいないし。
でも俺はカマキリ妖怪が襲いにやってくるってのがいいかな。そっちの方がガキンチョ共に教えやすい。
びゅうと風が吹いて、ばっさばっさと髪が揺れる。俺の髪はもさもさしてて微妙に長いから、目に入ったり口に入ったりして鬱陶しい事この上ない。適当にヘアゴム拝借して結んでくれば良かったな。
ざざあざざあと木の葉が風に吹かれてざわめく。俺は結構この音が好きだ。
自分でも矛盾していると思うけど、俺は人がうるさく喋ってるのが嫌いな癖に、誰も何も喋らずに無音が生まれるのも本当に苦手だ。無音は、正直に言うと、こわい。
自分の息だけがはっきりと耳に入って、あ、俺今ひとりなんだ、なんて思う。
一人は嫌いじゃない。怖くもない。でもそれはどこかで誰かの存在を感じている筈だ。でも無音に囲まれたその時、俺は本当にひとりなんじゃないかと錯覚する。だから木々のざわめきでも何でも、俺は音がある事に安心する。
(それにしたって)
遅いじゃないか。俺は目の前の望遠鏡を見つめる。ヒロトさんはあと一時間で迎えに来るぞ。一時間で天体観測が満足にできると思うなよ。
心の中で呟いてから、ああ暇だなあと平らな木製の、古びたベンチに寝転んだ。
缶コーヒーはまだ一応あたたかい。額の上にそれを乗せて目をつむる。
いつかの見たような星が瞼の裏でちかちか光る。きらきらきらきら。
―――人は死んだら星になるんだよ。
何でか口を緩めて俺に囁いたヒロトさんの言葉が頭に響いて、だったら俺はすっげー小さい星だろうなあと考える。
俺みたいなつまんないヤツはきっと世界のどこにでも居るもんだ。きらきら輝いてんのは、そうだなあ、円堂監督とかヒロトさん、あと俺の私的意見としては、天馬くん。
でも天馬くんが死んだとしたら、天馬くんは。風になりそう。
だったら。剣城くんは。
そう考えていたらガサガサ音がして。目を開けた。
目の前に剣城くんが居た。
「……おっそ」
「悪い」
ぼそっと呟いたら素直に謝罪の言葉が返ってきた。でも実際俺はホラーみたいな剣城くんの登場に心臓が未だバクバク脈打ってる。
「ジョギングがてら来ようと思っていたんだが」
お、言い訳ですか。俺は寝転んでいた体を起こしてウンウン頷いた。そんな俺をしらと見てから剣城くんは少し黙り込んで。意を決したように口を開いた。
「…考え事している内に、普段の道を走っていた」
「…それは……まあ…」
練習熱心な事ですね…。なんて返したらいいのか。言葉が見つからない俺に気付いたのか、剣城くんはもう一度「すまない」と謝ってから、それからは何ともなさそうな顔で続けた。
「あと時間はどれくらいあるんだ」
「一時間くらい」
「…そうか」
「言っとくけど、天体観測するには短いからね」
はい急いで探そう!
そう言って立ち上がった俺に剣城くんは眉を寄せる。
「見つけてないのか」
「めんどーだったし」
(一人で探しちゃ意味ないだろ)
缶コーヒーはさすがに生ぬるくなっていたからベンチに置いて、俺は剣城くんの腕を引っ張って望遠鏡へと歩いていく。ぶっちゃけると望遠鏡のセットっていうか、準備っていうか、何かそういうのもヒロトさんがやってくれたものだ。だから実際俺はここに来てから何もしてないんだけど。なんて。
河川敷の下、木に囲まれてガキが居るなんて思わない場所。少し開けた木の枝たちのおかげで、真上らへんだけは真っ暗な空が見える。
剣城くんは一人で来たって事だから、度胸あるよなあ。俺だったら無理だ。ビビる。警察が来ないかとか、変質者が来ないか、とか。…考えたら怖くなってきた。迎えもヒロトさんに頼んで、剣城くんと一緒に来れば良かった。例えクールで万能そうに見える剣城くんだって、大人には敵わない。後悔してきた。これからはこんなムチャ言わない事にしよう。
密かに決心した俺をよそに、剣城くんはてくてくと望遠鏡の傍まで自分から歩き出して、それからそっと。望遠鏡に触れる。ちょっと恐る恐るだ。
「別に壊しても怒られは……するだろうけど、も少し乱暴に扱っても大丈夫だよ」
びくりと途中で震えた背中に思わず本当の所を告げてしまったけど、まあいい。とにかく俺は天体観測をしたい。
せっつく俺に剣城くんもようやくいつものクールっぷりを取り戻して望遠鏡を覗き込んだ。それを後ろから見ながら、両手を頭に回してあくびを飲み込む。
全くどうしてこんな季節に天体観測なんて。おかしそうに笑ったヒロトさんを思い出して、同じように。夏とかじゃなくてか、なんて問いかけてきた剣城くんの事も考える。
春だ。まだ夜は少し肌寒い。それでも俺は夏でも冬でもそれまで待つ気にならなかったのは、ヒロトさんや剣城くんには、ただ単にひねくれているだけだと思われていたい。
桜は随分前に散ってしまって、葉がなんていうか、アオアオとしているってヤツ。そんな中にぽつねんと居る俺と剣城くんは、何だかとてもさみしい存在のような、それでいて酷く特別な存在のような。
考えるだけじゃつまらなくなって、無言の剣城くんの背中から目を外して地面を見る。なかなかの雑草の量。半ズボンで来てたら足をくすぐって痒くて仕方なかっただろう。良かった良かったと一人安心する。
「あ」
剣城くんが声を上げた。
「見つけたかもしれない」
「マジで」
「多分」
そう言って近付く俺に場所を退けてくれた剣城くんは、「それ。動かすなよ」なんて言ってハラハラしてる。流石に動かさねーよ。見れなくなるだろ。思う俺はけれど「ウン分かった」とおりこーさんの返事をしておいた。それにしても剣城くん、何も教えてないのに遠近うんぬん分かったのか。あのズームとかしてくの。途中で根を上げて俺に使い方の教えを求めてくると思ったのに。ツマンネ。なんて思ってる事が露見したらたまらないので、俺はとにかくコッソリと望遠鏡を覗き込んだ。片目をつむる。そうするとぐらぐら揺れる視界の奥の方に、小さく小さく、一つ。
「星だ」
「合ってたか」
「うん。すごいね」
「で、それ、どうやったら近付くんだ」
「え」
ちょっとレンズから目を離してよく見ると、確かにズームなんかされてなかった。
「…えっと、こう」
何だか少し罪悪感を抱きながら、レンズに目をもう一度くっつけて調節していく。
「あ」
「どうした」
「近くにもっとちっさい星あった」
「本当か」
「マジマジ」
何だかさっきも同じやり取りをしたような。思う俺をよそに真上を見ながらソワソワしてる剣城くんに場所を譲ってやる。
「…おお」
静かな感嘆の声に少し得意げな気分になる。
大きな光の傍に頼りなさそうに光るもう一つの小さな光は、寄り添ってるみたいに一緒になってる。…それでも望遠鏡なしじゃ、見つけられないほどに、遠くで。
「狩屋」
低い声が耳に届く。
はっとして逸れていた視線を戻すと、剣城くんは首を回して俺を見ていた。
見透かすような目だった。胸が詰まるような感覚。
そんなものを受けている俺の事なんか知ってる訳もなく、剣城くんは問いかける。
「何がしたいんだ」
「…何って?」
さあさあとやっぱり風は木を騒がして、俺はそれに安心しながら、言葉を返す。
「天体観測だよ。星見たかった」
「……お前がしたいのは、本当にそれか」
(ひっでぇの)
「何で言わせようとすんだよ」
そういう所ホント剣城くんは、ムカつく。何で君は俺の隠そうとするものばかり暴こうとするんだろう。俺のやましいものも苦しいものも全部、奥底に沈めたそれを、引きずり出そうとするんだろう。
嫌になって地面を覆うくらいに生えている雑草を見下ろすと、すぐに剣城くんがいつもの声で俺に言う。
「空を見に来たんだろ」
上向けってか。黙ってゆるゆると顔を空に向けていくと、剣城くんは溜め息を吐いた。
「…で、お前は。俺を呼んで、何をしたかったんだ」
追求すんのかよバカヤロウ。思わず舌打った俺は、けどもう逃げ切る事は出来ないなと目をつむった。
真っ暗。開けていた頃と違って本当に視界がなくなってしまった感じ。星が見えない見えないって言っていたけど、小さく小さく、明かりは届いていたんだろう。
「望遠鏡の中の、2つの星さ」
「ああ」
「そいつらは見えない所で一緒に居るんだ。望遠鏡で探してやっと見つけられるくらいの遠くに、居るんだよ」
目を開けたら剣城くんが望遠鏡を覗き込んでいた。その星たちは2りきりだ。―――小さな星でしかない俺と、大きく輝く、きみ。
「人は死んだら星になるんだよ」
「…迷信だろ?」
「そうだけど」
いいなって。
音をなくして口だけ動かしたそれは、背を向ける剣城くんには届かない。
(それでいい)
どうにもならない事を願う情けない俺を、暴かれたくない。弱虫で強がっているのはどうせ見透かされているし、それはもう諦めているけど。でもこんなに惨めな事だけは。これだけは、どうしても、俺は。
そうやって固まっていたら、剣城くんはこっちを向いて手招きをした。
「お前全然見てないだろ。何の為に来たんだ」
「あ…、うん」
意識しない内にうろうろ歩いていたから、剣城くん(というか望遠鏡)は少し遠くに突っ立っていた。両手をスボンのポケットに突っ込んでこっちを見てる剣城くんの傍へと歩いていく。がさがさ音をうるさく立てる草に、もうこんな所絶対来てやんねぇと心の中で毒づいた。
「俺とお前が死んだら」
ぼそりと呟かれた。
その言葉にひゅっと心が冷える思いがして、それでも何でもないフリをして近付いていく。
(死んだら)
剣城くんは見えない星をなぞるみたいに真っ暗な空を見上げてる。
(死んだら、きみと)
「誰も見つけられない星に―――」
「剣城くんっ」
声を上げた俺に驚いて弾かれたようにこっちを見たその―――その大バカヤロウに、だきつく。
「っ狩屋…!?」
「剣城くんは酷いっ」
「は」
「きみは!きみは何でそんな事言えるのっ」
「狩屋」
「俺は言えない、だって、だってそんなの叶いっこない、こんなのすぐに終わるんだ、いつか絶対きみは俺を」
(置いていく!)
「お前と生きるさ」
額がぶつかる。
目が合った。
暗闇の中で睨み付けるみたいに俺を貫く目。その中にきらきらしてる光を見つけた気がして、はっと息を呑む。(……ほしだ)
なあ、と剣城くんの口が動いてる。目に釘付けになって頭がうまく動かない。
「狩屋」
甘やかす声。しがみついていた俺の髪をくしゃくしゃにして、すぐそこの近い距離で目を細める。
「お前はどうだ」
「死にたい訳じゃない」
「ああ」
「ただ、―――ただ、当たり前に寄り添える存在に」
なりたい。
かすれるように消えてく声が惨めでたまらなくて、浮かんできた涙を、白い指先がすくっていく。
「俺は、お前が隣に居るのを当然だと思ってるから」
笑いもせずに真面目くさった顔して、剣城くんは慰めるみたいに俺に声をかけている。星が詰まってるようにきらきら光ってる瞳、に、じわじわと心臓が溺れていく感覚。
「でも俺ときみは男だから」
呟いた俺に剣城くんの溜め息。
「…星って、あの望遠鏡の中で近くても、実際はあの2つも遠いんだろ」
「…うん」
「なら、周りの目があっても、お前に触れられる方がいい」
「………」
「狩屋」
「…うん」
ぶつかっていた額が離れる。少しさみしくなったなんて死んでも言ってやらないけれど、思わず見上げた空が真っ暗だったから、溜まった涙がこぼれてしまった。
「逃げ出したかったんだ。剣城くんと」
「そうか」
「誰も見つけられない所だったら、こんなに苦しくならないんじゃないかと思って」
「それで?」
「…わかんね」
べしんと叩かれた。
「痛っ」
「また見に来よう」
「ええ」
「嫌か」
そう言いながら剣城くんは少し笑ってる。
それが何だか気恥ずかしくなって、誤魔化すように望遠鏡を覗き込む。(…来てやんないって思ったんだけどな)
小さな視界の中で並ぶ2つの星に、頬をゆるめた。
「どうしてもって言うなら、来てやってもいーよ」
(20120521)
テンプレお借りしました
|
|
|