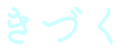そこは「出る」という噂で有名なアパートだった。にもかかわらず不思議と入居者が絶えないのは、俺のような苦学生が安さにひかれて住むからだろう。生まれてこのかた心霊現象に一度も縁がなかった俺は、もちろん即決で入居を決めた。霊なんてもの、気づかなければいいのだ、気づかなければ。
まず、つつがなく三ヶ月を終えた。
特にこれといった事象は起こらず、むしろ俺を悩ませたのは真下の部屋の住人による騒音だった。
毎夜毎夜笑い声が響く。それも二時三時まで。床にせんべい布団を敷いて寝ているため、笑い声はひどく耳に障った。
眠れない。
「あら、おはよう」
「おはようございます」
ゴミ出しの朝、きまって顔を合わせるそのおばさんは、今朝も両手に特大ゴミ袋をふたつ抱えていた。毎度のことながら相当な量だ。家庭があるといろいろかさばるゴミもあるのだろう。
「ゆうべもうるさかったわねぇ」
「ああ……そうっすね」
おばさんは俺と同じく、真下の住人の騒音に悩まされているうちのひとりだ。何号室なのかは知らないが、角部屋である俺の隣ではないから、おそらく斜め下、つまり問題の部屋の隣あたりだと勝手に推測している。
おばさんはどっしりと重そうにゴミ袋を置いた。
「ほんと、どうにかしなくっちゃ」
「……はあ」
どうにかしてほしい、ではなく、しなくては、と言ったことが引っかかる。
大家に陳情? それともまさか直接文句を言う気か。
なんにせよトラブルに巻き込まれるのはごめんだ。
俺はそそくさと会話を切り上げ、部屋へ戻った。
玄関を開ける際、隣の郵便受けが目についた。封筒が差し込まれたままになっている。
隣の住人は確か、就活中の学生だ。何度も落ちているのか、その都度壁や家財に当たり散らす声をたまに聞く。
合否の知らせなら、すぐにでも開封するだろうに……昨日から不在なのだろうか?
不思議に思いながら、俺は玄関の戸を閉じた。
――まただ。
今夜も、聞こえる。
うとうとと入眠しかけた俺の脳に、耳に、無作法に入ってくる笑い声。
ぎゃはは、とかがはは、とか、……そう飲み屋の喧騒のような。
ああ、うるさい。
「下の部屋がうるさい?」
俺はどうにも辛抱たまらず、以前このアパートに住んでいたという友人に相談してみた。単なる愚痴でしかなかったが、友人は話を聞いてくれた。
「そう、〇〇号室。男が住んでいるだろ?」
毎夜響く声は明らかに男の声だ。
しかし友人は怪訝な顔で否定した。
「いや、俺がいたときはそこ空き室だったけど」
「……じゃあお前が出てから入った住人なんだ。とにかく毎晩うるさくて」
「案外それが幽霊だったりして」
「まさか。ほかに迷惑がっている住人もいるし、毎日玄関の開閉音だって聞こえるんだぞ」
その開閉音もまた響いてしかたないのだが、安い賃貸だ、それしきの生活音は我慢する範囲だろう。
「あんまりつらくなる前に部屋を出たほうがいいんじゃないか。そんな怖い部屋、俺なら耐えられないね」
「べつに怖くは……。お前幽霊とか駄目なのか?」
「そうだよ。だから出たんだ。安かったから飛びついたけど、あれを見ちゃったらもうダメでさ」
「あれ?」
聞き返すと、たちまち表情を曇らせた。
「ああ……うん。俺が見たのはさ、ゴミなんだ」
「ゴミ、か」
「笑わないでくれよ?」
「笑わないさ」
こうして俺の愚痴に付き合ってくれているんだ、茶化すわけがない。
「……袋がさ、開いてたんだ。すこし。結び目がゆるかったらしくて」
「ああ」
「たまたまなんだ。なんとなく見ただけ。通りすがりに。ちょっと。あーゴミ出すの忘れたなーなんて思って、そっちのほうを見た。そしたら」
――頭が、見えたのだと言った。
真っ黒い長い髪を垂らした、頭が。
顔が見えたわけではない。
友人の目に留まったのは、髪だけだ。
ならばなぜ、頭だと思い込んだのか――
「……そのときは気づかなかったけど、あとから思い返したら、それ、つむじが、あったんだ。ただの毛髪なら、つむじなんかないだろ?」
「カツラだったのかも。人形とか」
「俺もそう考えた。考えたけど、一回『そう』思っちゃったらもうダメだった。あれは人の頭で、誰かがゴミ袋に入れて捨てたんだって、……それしか考えられなくて」
それが本当なら警察に通報する事案だ。
「うん。うん……けど、あそこは『出る』アパートだろ? ゴミ置き場に、人の頭。現実でも幽霊でもどっちでも怖かったから、次の日にはすぐ退去したよ」
俺はどう答えたらいいのかわからなかった。
「もしかしたら、俺が見たものは髪ですらなかったのかもしれない。なんか、黒い、糸とか、光の反射で、髪に見えただけで俺が勝手に怯えただけなのかもしれない。でもさ」
友人は俺の名を呼んだ。ひどく不安そうに。そして、
「――気づいちゃったら、もう戻れないんだ」
くれぐれも無理はするなよ、との忠告をいただいて、俺は友人と別れた。
夕暮れどき、アパートの駐車場脇で、ふと気になって建物全体を見上げた。明かりがついている部屋はない。どこも出払っているらしい。
二階への階段をのぼり、ポケットから鍵を取り出す。隣の郵便受けには、まだ封筒が挟まっていた。
玄関の鍵を開けて、明かりを点す。無造作に上着を放り出し、六畳間にどかんと腰をおろした。
部屋の内装は家賃のわりに小綺麗だ。妙な染みもなければお約束のお札もない。今まで一度も遭遇してないんだ、きっと俺には霊感というものがないんだろう。それに今俺を悩ませているのは現実のご近所トラブルだ。幽霊じゃない。
ごろん、と横になった。天井の木目はどう穿って見てもただの木目でしかなかった。もちろん人の顔にも見えない。
なんだかどっと疲れて、俺は目を閉じた。心地好い倦怠感が睡魔を運び込み――
俺は、ふたたび目を開けた。
いる。
下にいる。
声が聞こえる。いつもの、あの耳障りな。
いや、でも。下の部屋は明かりがついていなかったはずだ。俺とほぼ変わらない時刻に帰宅した? 扉の開閉音は聞こえないこともままある。おそらくそうに違いない。
そこで俺は初めて、騒音に対しての行動を起こした。
大家に陳情? 違う。それにはもう時間が遅すぎる。もちろん殴り込みもしない。
代わりに、からりと静かに窓を開け、俺はベランダに出た。手すりから身を乗り出して、下を――見る。
明かりは、ついていなかった。
階下はみな無人のように薄暗く、俺の部屋の明かりだけが白々しく夜を照らしている。
……どういうことだ。
真っ暗ななか酒盛りをしているとでも?
今だって、今このときだって、声は聞こえているのに。
がはは、と、太くて厚みのある、壁をつたって部屋を揺らす、男の声が。
その日は朝まで一睡もできなかった。
「あら、おはよう」
今日は不燃ゴミの日だ。
「おはようございます」
「元気ないわねぇ」
おばさんは呆れたように笑った。その手にはいつもと同じ、特大のゴミ袋。ただ今朝は、結び口から、薄汚れた金属バットの持ち手が突き出していた。
「バットですか」
「そうなの。もうだいぶ使いこんじゃったから、別なのにしようかと思って」
相当豪快に扱われたらしいバットはなるほど大きなへこみと、赤茶色い錆びで見るからに満身創痍であった。
おばさんはやはりどっしりと重そうにゴミ袋を置く。
「ゆうべもひどかったわねぇ」
「ああ……」
「困っちゃうわぁ、帰ってくるなりずっとでしょう? まったく、それまでは静かだったのに」
「……そうっすね」
なにか引っかかる物言いだと感じた。だが、連日の寝不足のせいで頭の回転がすこぶる悪く、どこのなにがおかしいのか、いまいち判然としなかった。
泳いだ視線が、ゴミ袋でとまる。
「……結び目、ゆるんでますよ」
(――袋がさ、開いてたんだ。すこし。結び目がゆるかったらしくて)
なにも今。思い出さなくてもいいのに。
「あらほんとだわ。悪いけど結び直してもらえる? なんだかうまく結べないのよぉ」
バットがつっかえているのだ。これでは転がしただけで中身が落ちてしまう。
俺は言われるがまま屈み、ゴミ袋へ手をのばした。
(――真っ黒い髪が)
いったん結び目をほどく。
(――人の頭が)
広げると酒の臭いが鼻をついた。
(――つむじが)
(――)
……中は、空き缶がつまっていた。
知らず知らず止めていた息が、静かにもれる。早鐘を打っていた鼓動が、しだいに平静を取り戻していく。
なにを馬鹿げた妄想をしているんだ。
自身を軽く叱咤し、俺はこころもち目を伏せた。よその家のゴミをまじまじとあらためるのは失礼というものだ。
それでも視界には入ってしまうもので、ビールや酎ハイのような酒の缶の隙間から白く固いものがときおり覗くのが見えた。バットと缶をひとまとめにするくらいだから分別もぞんざいなのだろう。少し、意外な気がした。
ゴミ袋を固く結ぶ。
友人の言を疑ってはいない。
ただ、まさかこんな日常のなかで訪れるとはとうてい思えないだけだ。
あいつだって言っていたじゃないか、なにかを髪に見間違えただけで、自分が勝手に怯えてしまったのかもしれないと……。
「ああ、助かるわ。ありがとう」
「いえ、これくらい」
「……中身、見た?」
背筋が粟立った。
「え……?」
振り仰いだおばさんは、いつもと変わらない。
「中身、見た?」
変わらない、はずだ。
「い、いえ……」
正直、直視できなかった。
「あらそう。いやぁねぇ、頼んどいてなんだけど、家庭ゴミってほら、生活まるわかりで恥ずかしいじゃない?」
「そ……っすね、見て、ないです」
それだけ言うのが精一杯だった。
「よかったわあ! この先気まずくなったりしたら困っちゃうわよね」
それじゃあやり残しの家事があるから、とおばさんは部屋へ戻っていった。
ぽた、と地面に汗がしたたる。嫌な汗だ。無言でぬぐうと、いくらかましな気分になった。
俺も自分の部屋へ、帰ろう。
帰って、支度して、学校へ行こう。
そちらへ足を向けたのは、気まぐれだった。
ただ、なんとなく。
(――たまたまなんだ。なんとなく見ただけ)
いつもなら上る階段を過ぎ、のろのろと棟の端へと歩く。身体が妙に重い。眠くはないが、ぼうっとした疲労感に包まれているようで、ひどく気だるい。
一階一番奥の、角部屋。
今朝はもう出勤なり通勤なりしたあとだろうか。開閉音がしたかどうかも曖昧だ。
ジーンズの尻ポケットが震えた。
友人からだった。こんな朝早くに珍しい。
「はい」
「ああよかった起きてたか!」
声音で緊急の件だと知れた。だが心当たるものがない。
「昨日、お前と話しただろ。アパートで、笑い声がうるさいって話。あのあと俺も気になってさ、大家に電話で聞いてみたんだ」
「なにを?」
通話しているうちに目的の部屋へたどり着く。
「入居希望ってことにして、聞いてみたよ。今、どのていど部屋が埋まってるのか」
「? ……ああ」
頷いて、俺はなにげなく、その部屋の郵便受けを見た。
「……え?」
……意味が、わからなかった。
なぜ? なんで? どうして?
全身が疑問の渦に飲み込まれる。その向こうで、俺の耳は確かに聞いた。
真実を告げる、友人の言葉を。
「よく聞いてくれ。そこは、そのアパートは、今、お前と、お前の隣部屋しか入居者はいないんだ。お前が聞いた笑い声は、聞こえるはずがないんだよ」
目の前の郵便受けには、空室用の投函防止ステッカー。
空室、用の。
かしゃん、と携帯が落ちる音がした。
ここに、誰も住んでないだと?
そんな。嘘だ。だって。
……待て。
入居者は、俺と俺の隣、だけ?
ぎぎ、と錆びたブリキ人形みたいな動作で、俺は眼球を動かした。
俺の部屋の、真下。その隣。いつもゴミ出しの日に、会う、あの――
俺の期待を嘲笑うように、果たしてやはり投函防止のステッカーはそこに存在していた。
知らず知らず後ずさる。
わなないた足がなにかにつまづいて、俺はぺたりと座り込んだ。
目の前に立つのはごく平凡な安アパートだ。俺が三ヶ月過ごしたところで、今はここが俺の帰る場所だ。
……そうだ。俺はここへ住むと決めたとき、自分自身に言ったじゃないか。
霊なんてもの、気づかなければいいのだ、気づかなければ。
そう、気づきさえしなければ。
呆然とアパートを仰視する俺の頭に、昨日聞いた友人の言葉がじわりと浮き上がった。
「――気づいちゃったら、もう戻れないんだ」
その意味が今は、痛いほどよく理解できた。
fin.