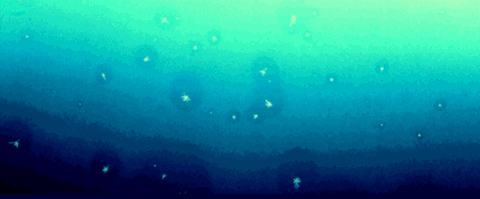30分ほど夢中で片付けに励み、漸く最後のゲームを棚に置き永遠にも感じた掃除は終わりを迎えた。ごちゃごちゃしていた床が綺麗になり、案外部屋が広かったことに驚く。あ、ツナを呼ばないといけないんだった。
「終わったよ」
「え!?もう?」
慌てながら部屋に駆け込んできて、すご!とかオレだったら3時間は…とか言って部屋の隅々を見回すツナ。これって誉められてるのかな。少しこしょばゆい。
「ありがとう!母さんが片付けろってうるさかったんだよなー」
「お世話になってる間は私がやるから、任せて」
「うっ、逆に汚せない…」
苦虫を噛んだような表情を浮かべるツナがおもしろくて、笑えてるかな。と思ったけど表情は変わらない。それもそうか。ずっと笑ってなかったし、笑い方なんて忘れてしまった。今まで人と関わらなかったことに今更ながら悲しいような、切ないような、あやふやな気持ちになる。
「麻哉ってさ、何ていう苗字?」
「白咲」
「へえ、いい名前だね」
「そう?」
「うん。それっぽい」
どんな顔だよ、と思ったけどあえて何も言うまい。ツナは、と切り替えると小首を傾げた。
「中学生だよね」
「うん、並盛中」
「並盛…あの雲雀さんがいる学校?」
「知ってるの?」
「さっき会ったから。短気だった」
「えええ会ったの!?何もされなかった!?」
「…ノーコメント」
「何だよそれ!」
「それよりツナ」
「(無視ーー!?)」
「改めて宜しくね」
ぽかんと一瞬呆気に取られた次に、すっと右手を差し出された。ツナを見たらこちらこそ、って言われたので自分の右手をツナの右手に重ねた。あったかいけどやっぱり男の子の手だった。
「ありがとう」
今日は一日に人の温かさを沢山知る日だ。じんわりと広がる気持ちに目を細める。優しくて、温かい人に会えてよかった。
――不気味なんだよ。
「っ…」
「どうしたの?」
「なんでも、ない」
――消えろ
――ー何その目
――バッカじゃないの
幸せに、近づけばいつだってその声が聞こえる。きっとまた離れていく。期待なんてするな。今は優しいツナだって、奈々さんだって、すぐに気味悪がって私を嫌う。ならば心を開かなければいい。落ち着け、私。
「顔色悪いよ、母さんに薬貰ってくる!」
「いい、放っておいて」
搾り出すように言えば、ツナは眉を歪めてうんと呟いた。
「ツナ、##NAME1##、ご飯できたわよー!」
「はーい!行こう、##NAME1##」
「…うん」
トタトタと階段を下りてリビングに行けば、いい匂いが部屋を満たしていた。机に並べられたのは、ハンバーグにサラダに野菜炒めにスープ。張り切っちゃった!と笑顔で更に焼肉を机に並べた奈々さんは、鼻歌交じりに座るように促した。
「ビアンキちゃん達遅いわねぇ、出来ちゃったわ」
「どうせランボが迷子にでもなってるんだろー」
「まあ大変!早く帰って来るといいわね」
心配そうに頬に手を当てた奈々さんは玄関の方を見つめた。いい人だな、なんて考えればまた言葉が頭を過ぎる。ダメだ、考えないようにしないと。
「麻哉ちゃんも座っていいのよ」
「ありがとうございます」
そっと椅子を引いてツナの正面の席に座らせてもらった。ご飯はもう少し待ってね、といわれたので頷く。そのビアンキさん達も同居している人なのだろうか。
「麻哉ってさ、何歳なの?」
「ツナと同じ」
「え!じゃあ中学生?」
「うん」
「学校は?」
「行けない。住んでた場所から遠いし」
正確には世界が違うかもしれないのだから遠いとかそんな次元ではない。高校ももう卒業したし。中学に通う理由が無い。
「じゃあさ、並盛に来たら?」
「どうして」
「だってほら、勉強とかオレも苦手だけど大切だし…行かないとマズいんじゃないかな」
「そういうものなの?」
「そりゃそうだよ!」
「でも保護者も居ないし、手続きする人も居ないから行けないよ」
そっか…、と肩を落とすツナにありがとうとだけ言っておいた。奈々さんの手を煩わせたくないし、第一血の繋がりもない。料理が冷めるんじゃないか、なんて考え始めた頃に玄関が急に騒がしくなった。
「ガハハハハ!!ランボさんのお帰りだもんね!!」
「こらランボ!手を洗いなよ!」
「*△◎×!!」
「ただいま、ママン」
「今帰ったぞ」
「おかえりみんな、ご飯の支度できてるわよ!」
ぞろぞろとリビングに入ってきた人達。小さい子が四人いるけど、ツナの弟…かな。妹も居る。ピンクの髪の人はお姉さんかな。
「あれ〜?知らないやつがいる〜」
「初めまして。本日からお世話になります、白咲麻哉です」
「しっかりした子ね。ツナも見習いなさい」
「そうだぞ」
「ボクフゥ太!麻哉姉って呼んでもいい?」
「うん」
「やった!ありがとう麻哉姉!」
「□▼%#〜〜!!」
個性的な人だ。特に一番気になったのが、赤ちゃんなのにスーツを着て流暢に喋る子。最近の赤ん坊はすごい。それともそういう世界なのか。何かが頭につっかかっては消える。
「みんな揃ったし夜ご飯にしましょう」
「ランボさん一番乗りー!!」
「こらランボ!」
「あはは…ごめん煩くて」
「気にしないで。こういうの、憧れてたし」
家族らしいことなんて殆どできなかった。父親なんて生まれたときから居ないし、お母さんはずっと働いて急死。正確には死体は見てないから消息不明だけど。ずっと一人で生きてきたから、こんな賑やかな家庭に居る自分は酷く浮いているのではないかと思った。
「麻哉!ランボさん膝に乗る!」
「うん、おいで」
「あんまり甘やかすな」
ぴょん、と膝に乗ったランボ君に私の分のハンバーグを上げたら、嬉しそうに食べてくれた。元々あんまり食べれないからそのままあげたかったけど、折角奈々さんが作ってくれたので二口だけあげて自分で食べる。バタバタと膝の上ではしゃぐランボ君を撫でると温かい手で手を握ってくれた。
「麻哉の手、氷みたいだじょ」
「冷え性だから」
「ひえしょう?」
「生まれつき温まりにくい体ってことだよ」
「へへーん知ってるもんねー」
「(さっき知らないっていってたじゃん!)」
ツナが向かい側でショックを受けた顔をしていたのがおかしくて、ランボ君もそれに気がつき笑い飛ばす。黙々と二人の世界に居るスーツの子とお姉さんが煩わしそうに、でもどこか楽しそうにその光景をみていた。これが、家族というやつなのか。…羨ましいと思う反面、自分には似合わないと思った。
*
「麻哉ちゃん、お手伝いありがとう」
「いえ」
「本当に娘みたいで嬉しいわ」
「娘なんてそんな、」
こんな娘を持っても何も幸せじゃないのに。とは思ったけれど口には出さなかった。奈々さんの気分を害したくはない。いつかは嫌われると分かっていても、やっぱり嫌われたくないと思う自分が居る。
「ツナのお部屋も掃除してくれたのよね、ありがとう。
ツナったら中々片付けようとしないのよ」
「そうなんですか」
「男の子ってどうしてあんなに適当なのかしらね…」
「はい」
比べて##NAME1##ちゃんはお手伝いまでしてくれて、見習って欲しいわ!と奈々さんが笑った。お世話になってるのだからこの位は当然だろう、とも言わない。淡々と続けていた皿洗いは終わり、奈々さんがありがとうと御礼を言ったので「はい」と頷いておく。
「ツナの部屋にお布団運んでおかないとね!
明日一緒にベッドを買いにいきましょう」
「そんな、大丈夫です、ありがとうございます」
「遠慮しないで、女の子を床に寝かせるなんて出来ないでしょ!」
妙なところで頑固な奈々さんは何度断っても聞かなかったので、かなり申し訳ないけど私が折れた。それじゃあ明日お洋服も買いましょう、と笑って追加されたのでもう罪悪感がマックスで承諾した。どこまで優しい方なのか。何度も御礼をいったらそんなの良いのよ、と答えられる女性が何人存在するのだろう。
「明日はお休みだから、ツナにも付き合ってもらいましょうね」
「折角のお休みを無駄にさせたくありませんので、大丈夫です」
「無駄なんかじゃないわよ!ツナも喜んで着いて来るわ」
「そ、そうでしょうか」
ツナごめん、断りきれなかった。一言嫌だとツナの口から言えば収まるだろうけど、やっぱり何だか申し訳ない。ツナに言っておいてね、お休みなさいと奈々さんに言われたのでワンテンポ遅れて頷きおやすみなさい、と返す。こんな挨拶すら久しぶりすぎて慣れない。リビングから出て階段を上がると、扉の前にツナが立っていた。
「どうしたの」
「いや、なんていうか…ちょっと入りにくくて」
「?」
ガチャリとドアを開けたら理由が分かった。ビアンキさんがさきほどくれた下着やら替えの服やらが置いてあり、確かにツナからしたら居心地が悪いだろう。全てを纏めてあらかじめ与えられていた箱に整頓したら、タイミング良くツナが入ってきた。顔が少し赤い。
「ご、ごめん見ちゃって…」
「謝るな、ここは元々ツナの部屋なんだから。スペース取ってごめん」
「いや全然大丈夫だよ!」
「それじゃあ私はお風呂借りるね」
バスタオルとハンドタオル、下着とパジャマを持って教えられたお風呂場へ向かう。扉の向こうでツナの緊張の解れたような溜息が聞こえた。階段を下りて曲がり、お風呂場の扉を開けるとそこには先にビアンキさんが入っていた。お邪魔しました、と閉めたら中からビアンキさんの声が聞こえてきて足を止める。
「一緒にどうかしら?」
「…いいんですか?」
「女同士よ、何も問題はないわ」
それでは失礼しますと衣服を脱いでたたみ、籠の上に丁寧に置いた。スライド式のドアを開ければ湯気が視界いっぱいに広がる。
「そんなに固くならないで頂戴」
「すみません」
「ふふ。謝らなくていいのよ」
サアー、とシャワーの音が響く。冷たい滴が天井から落ちてきて肩を冷やす。
「白いのね」
「え?」
「肌が。とても綺麗」
浴槽の淵に肘をつき顔を支えながら離しかけてきたビアンキさん。そうですか?と返したらええ。と大人な返事が戻ってきた。
「貴女、訳アリみたいね」
「…」
「何も言わなくてもいいわ。いつか信用してくれた時に聞くから。ここに居る人は大体何かを抱えているもの」
「……すみません」
「だから謝らなくていいのよ。何も悪いことなんてしていないでしょう。
それより貴女の事を何か聞きたいわ」
上で束ねられた綺麗な髪が、数本はらりと落ちる。初めて見る大人な雰囲気の美女に少しドキドキしながらも、何も面白い事なんてないですよと呟く。本当に、何一つ無い。
「話せる事で良いわ。何でもいいの」
「何でも…ですか」
「ええ」
どうしよう。本当に何も無いのだ。人と会話すらろくにしてこなかった私は、相手がどんな事で楽しめるのかも知らないし、話す事すら思いつかない。取り敢えず今までで一番幸せだった事を話してみようか。
「私には、優しいお母さんが居たんです」
「…」
「とても気さくで、ずっと私を愛してくれました。
だけど私の目が…不気味だと、言われていて。お母さんは最後までごめんね、と繰り返して心配をかけてしまった」
黒髪黒目の純日本人のお母さん。だったらこの目はお父さんから譲り受けた遺伝子なのだ。生まれる前にはもう居なかったお父さんを、お母さんは愛していた。――本当に、愛していた。私の紫色の目はお母さんにとってはお父さんを見る唯一の光であり、道だった。でも、私は恨んでしまった。あんなに大切にしてくれた母でさえも。こんな目に生まれなければ、周りのみんなともっと話せたかもしれない。一人ぼっちではなかったかもしれない、と。
「だけど居なくなる前、最後に言ったんです。"貴女はどんな姿でも、私の宝物。貴女は愛されて、祝福されて生まれたのよ"って」
「…そうだったのね」
「すみません。暗い話しか出来なくて」
「辛い思いをしたのね、とても、とても。
大丈夫よ。ここの家の人は誰も貴女を傷つけたりはしないわ。勿論私もね」
「ありがとうございます」
だけど信じきれない。心の奥底で、何重にも鍵が閉められて受け入れられない。もう傷つくのが恐い。期待して、突き落とされることが恐くてたまらない。
「背負いきれなくて潰れてしまう前に、誰かに頼りなさい。
もっと求めたっていいのよ」
「…はい」
――ごめんなさい。
心の中でビアンキさんに謝り、シャンプーを手にとって髪へ落とした。
はじめまして
ごめんなさい、