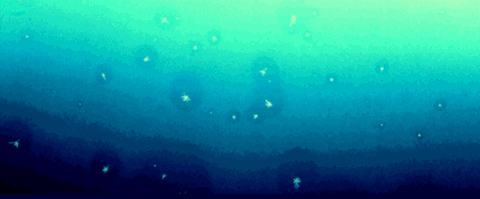物心ついた頃には一人ぼっちが当たり前だった。
どう見ても周りとは合わない、異質な存在。
紫色に光る目を見るたびに自己嫌悪に浸った。
別に、人が嫌いなわけじゃない。
少なくても私に話しかけてくれる人がいたけれど、すぐに私の元なんて去っていく。
何で?
どうして?
誰かに助けを求めたくて手を伸ばしても、掴めるのは空気。孤独。
いつからだったか私からは表情が消えた。笑顔が消えた。
でも押し殺しきれない『寂しさ』を抑えるように一人が好きだと。孤独が向くと言い聞かせて人を避けるようになった。
――信じてた。
どこかにきっと幸せと呼べる何かが待っているんだと。
けれどそんな都合のいい夢なんて泡のように消えて、垣間見せることすらなく消えていく。
もう、最初からなにも期待せずに生きることが私の常識となり、意識となったのだ。
*
人生の転機はいつ訪れるかは分からない、とは良く言ったものだ。18歳になり、大学の入学を目前にした3月。事はなんの前触れもなく訪れた。
私は、18歳にして亡命した。
死因は信号無視のトラックに跳ねられた…と思う。うん、間違いなく最後に見た。ドン、とぶつかる音がやけにリアルで耳にこびりついてもいる。ただ不思議と体の痛みが無かったのを感じた。
だからなのか、あれは夢だったのかもしれない。見ず知らずの景色に囲まれて、久しぶりに頭を使った。
「町のよう…だが…、」
人気はまあまあ。平和な雰囲気の溢れるどこにでもあるような町。先ほどまで大通りにいたはずなのに、今は普通の広くも狭くも無い道路の上に居る。一体これは、どうなっているんだ。思い出そうと記憶を刺激するものの可笑しな事に事故以前の記憶がない。今までどうやって生きてきたのか、自分はどこで生まれたのか。全く分からない、答えられない自問自答。唯一覚えているのは自分の名前#neme1##白咲#、だ。見慣れない景色に混乱が半分にどこかワクワクするような気持ちが半分。取り敢えずここで立ち止まっていても何も進まない。振り切るように足を一歩踏み出したところで、突然肩を叩かれた。
「ねえ君、ちょっとオレらと遊ばない?」
「どうせ暇だろ〜?」
へらへらした笑顔に思わず虫唾が走り、腰に手を回されてようやく此れがナンパだと気付いた。じ、人生初体験…!と感動することもできずに、断り方を知らない私はその手を無理やりどかして逃げるよう走る。
「何で逃げるんだよ?」
「かっわいー!」
なんでそうなる!段々恐怖に酷似した感情が湧き上がり、自然と足に篭る力が強まる。
あれ、私ってこんなに足速かったっけ。なんて考える暇はない、兎に角逃げて走って前方に見えた学校へと一気に駆け抜ける。
「おい、あの学校…」
「あんな奴に出くわしたら最悪じゃねーか!」
正に尻尾を巻く、と表現するのが相応しい。トン、と敷地に入って振り向けば慌てた様子で逃げていく後姿が見えた。…良くわからないけど、どうやら撒けたらしい。完全に姿が見えなくなったのを確認して踵を返し、校門を抜けようと踏み出せば前のめりにつんのめった。視線を落として自分の足元を見たら、誰かの靴が見えてそのまま上へ上へと視野を広げると、
「ねえ君、」
そこには黒い髪の少年が居た。
「な、何でしょう」
この学校の生徒だろうか。少しあどけないような、でも大人びたような端整な顔。むすっと不機嫌そうな顔をしたので、私も思わずぴくりと眉が動いた。
「不法侵入だよね。僕の学校に何の用だい」
貴方こそトンファーなんて物騒なものを持って何のようですか。と喉まで出かけた言葉を引っ込めた。私だって命は惜しい。太陽に照らされたそれは獲物を狩る獣のごとくぎらつく。さすがの私も顔が歪んだ。微かにだけど口角が。
「えっと、しつこい人から逃げてきて…」
「その先がこの学校だなんてふざけてるよ、君何歳?」
「18ですが」
「ワォ。年齢詐称は犯罪だよ」
「…本当なんですけど」
そのいかにも疑うような目は今すぐ止めてほしい。それに学校って避難所にもなるでしょ。どうして逃げ込んだらいけないの。なんて見せ付けるように光るトンファーのせいで言えないけれど。
「もう少しマシな嘘つきなよ」
「失礼ですね、本当に」
言葉が止まった。そういえば声が少し幼い気がした、視界もいつもより低い気もする。まさかと思い鏡を所持していないかと少年に尋ねたら、すっと無言で鏡を差し出された。
「…え、」
少し大人になってきた顔つきは一変、幼さののこる顔へと若返ったいた。見覚えがある。そこに映るのは中学生のときの私だった。
「待って、だって、こんな」
「そろそろ返してもらってもいい」
「あ、すまない…」
差し出す手が震えていた。さすがにこれは動揺する、だってこんなこと有り得ないのだから。ピリリと左の目の調度下辺りが小さく痛む。ケガは見えなかったのに、なんだというのだろう。
「私、中学生になってる」
「大丈夫かい、頭」
「うざいんですけど」
まず私は何故ここに来たのだろう。天国でないことは何となく分かった、勿論地獄でもない。ならばここは一体どこなのか。――ふと校門の向こう側に視線を移した。並盛と書かれた看板が立っている。
…並盛?
「ここって、並盛っていうんですか」
「なにその冗談。笑えないよ」
「至って本気なんですが…」
何気に少年に向けた目が無意識に開いた。そういえばこの顔を私は知っている気がして。なんだったっけ。思い出せなくてモヤモヤする。
物語は始まる