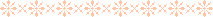君の心に
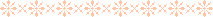
細くたなびく白い煙は、都から取り寄せた線香から。特注のその品は、香りも雅で、特性のもぐさの香りと相まって、室内に落ち着いた雰囲気を醸し出していた。
「殿様、お加減はいかがでしょう?」
私は、線香を線香立てに置きながら、傍らにうつ伏せている、我が主〈あるじ〉に問いかけた。
「うむ。名前のもぐさは、やはりいいわい。痛みが和らぐ」
着物の上半身を脱ぎ、裸の背中のあちこちにもぐさの山を載せているのは、この小田原城の主である北条氏政さま。私の今の雇い主だ。
氏政様は腰痛持ち。先祖から伝わる大きな槍を振り回しておられるから、なかなか治らない。それなら、軽い武器に持ちかえられては? などと、下々の者は思うけれど、ご先祖様を崇拝する殿様としては、安易に変えられぬということで、腰痛はいっかな良くならない。
なので、北条家は、いつも、腕のいいお医者や鍼士、灸士を探している。
私の家は、家伝として伝わる効き目のよい軟膏ともぐさがあり、私はその調合を知っていた。その腕の良さを買われ、今は小娘の身でありながら、小田原城主、北条氏政様のお抱え灸士としてお仕えしている。
「それでは、もぐさを追加しますね」
「うむうむ。名前のおかげで、今日は腰の調子が良いわい」
ご満悦の氏政様は、フォフォフォと笑い、白い髭をしごいた。 と、黒い羽がふわりと天井から舞い降りる。
「うむ、風魔か」
氏政様が言い終わらぬうちに、黒い影が、私と氏政様の前にうずくまる。何の物音もないのに、威圧感だけがぐぐっと肌身に感じられ、私は緊張に身をすくめた。
黒い鉄甲で顔の半分を覆った、細身でありながらも筋肉がみっしりついている長身の男。北条家自慢の忍び、風魔小太郎が参上した。
私は慌てて低頭し、後ずさる。
「よい、名前。そなたはそのままで、次のもぐさを準備しておけ」
氏政様は変わらずのんびりした声をかけた。その声には、いい加減、この男の登場に慣れるがよいという響きがある。私は、こくりと頷き、緊張して乾いた唇を舐めて落ち着こうとした。そして、目を伏せ、いつも通り、もぐさを手でもみほぐす作業をすすめていく。
「…………」
風魔の小太郎様は、ちらりと私を見たようだが、その視線は甲の中で伺うことはできない。ただ、私の首や頬の辺りが視線でチリチリしただけ。そう、視線だけでも、この方は、人をひるませることができるのだ。
「風魔よ。今川の動きはどうじゃな?」
氏政さまはそんなことは全く気にならないのか、寝転がったまま、鷹揚に聞く。これほどすごみのある男が目前にいても、さっきまでの態度と変わらない。ある意味、このお殿様も大物かもしれないと思う。
私は違う。緊張して指が震えてしまう。でもそれを悟られるのも怖い。恥ずかしい。だから、何でもありませんというように、目を決してそちらに向けないようにして、目の前の作業に集中するようにしている。
小太郎様は懐から何か紙を取り出し、黙って指さしていた。
それだけで、氏政様は分かるらしく
「ほう。そこに配備しおったか。して、主力はどこじゃ?」
などと、一人相づちをうっている。
私はおずおずと視線を、無口な忍びに向けた。
ここに勤めて一年ほど。最初は殿様の側にもおられない身分で、ひたすら蓬からもぐさを作る裏方作業ばかりだったけれど、その効能が良く、またツボを探すのが巧いと氏政さまに気に入られ、こうして部屋にいることを許されたのは半年ばかり。
どんな怖いお殿様かと思えば、氏政様は何とものんびりした温厚な方だった。はっきり言って、こんな戦乱の世に武将と名乗れるの?というぐらい、怖さのない方で。
その分、側に仕える者たちが、怖さを纏うようになるのかもしれない。この、風魔小太郎様のように……。
(不思議な人だ……)
数日に一回、不意に現れるこの人の声を、私は聞いたことがない。多分、誰も聞いたことがないのだろう。
誰とも話さず、誰とも関わらず、用のある時に姿を現すこの黒装束の男が、私は気になってしょうがなかった。もしかしたら、普段は別の格好で、違う仕事をこなして殿様の側にいるんじゃないかと思って、キョロキョロしてしまうこともある。勿論、そんな姿を見たことはないけれど。でも、遠くにいるんじゃなくて、実はいつも近くで殿様を見守っているんじゃないかと、私は感じているのだ。
怖いけれど、恐ろしい仕事をするけれど、個人では、そんなに冷酷じゃないかもしれない。私は勝手にそう思っている。いや、そう思いたいのかもしれない。
毎朝、殿様の散歩する庭に、鳥の餌を置いているのは貴方じゃないですか?
いつか、聞いてみたいのだけれど、やはり本人を前にすると、私は緊張して怖くなって、何も言えなくなってしまうのだ。
このまま、ぬるく淡々とした毎日が過ごせればいいのに……。私はそう思っているのだけれど
「ふむ。では、この地を狙っておるのだろうな」
「…………」
のんびした声だけれど、内容は不穏だった。
「だが、そこは譲れぬ。ここは主要な街道ゆえ。では、その手前の集落で相手をとどめるようにしよう」
その集落が戦場になるのですか?
私は心の声で、殿様に呼びかける。それより、人家のない草っぱらで戦うようにしてもらえませんか?
集落ということは、そこに誰かがいて、泣いて笑って働いているということ。誰かが生きているということなのでしょう?
「まずは、家と畑を焼き払い、敵を威嚇し、それから手に入るモノはないということを相手に知ら示て、様子見じゃな」
避難はさせるのですか? そこの人々の生活はどうなるのですか?
氏政様は、優しい声でそう指示すると、目の前の紙をくるくる巻いて仕舞った。それから相変わらずのんびりした声で、私に話しかける。
「これ、名前。手が止まっておるぞ」
「は、はいっ。申し訳ありませぬ……」
私は慌てて手を突いて、平伏した。こめかみがドクドクいう。今、聞いた話で耳に血が上る。本当はクラクラする。また戦だ。また戦で、どこかの村が焼かれるのだ。そして人が巻き込まれ、死んでしまうのだ。そう、私の住んでいた村のように……。
「名前。喉が乾いたな。そこの水差しのを汲んでくれ」
私は水差しの水を茶碗に注ぎ、殿様に差し上げようとした。
つと、視線をあげれば、そこに風魔小太郎様がいた。私が捧げ持つ茶碗に手を伸ばす。
「えっ……」
私が茶碗を両手に持つ上から、暖かい大きな手が添えられた。その暖かさと意外な優しい触れ方に、びっくりする。
「フォフォフォ。風魔よ、この者が、儂の水に毒を入れることはなかろうよ。案じることはなかろう」
ああ……。忍びの方だもの。全てを疑うのがお仕事だもの。私が、殿様に害なすことを考えても仕方のないことだ。
「…………」
小太郎様は黙って、私の茶碗を取り上げ、そして中の水を飲んだ。
普段隠れている首が見え、喉仏がゴクリと動く。
ただの毒味のはずなのに、私は鉄甲と黒い着物の間から見える、男の肌にドキマギしてしまい、自分自身が、この人に飲み込まれるような気がして、今度は違うクラクラした気持ちになった。
「…………」
黙って茶碗を返される。私は受け取り、手巾で拭い、また水を入れて、殿様に差し上げた。
「やれやれ、風魔の用心深いことよ」
感心半分、呆れ半分の氏政様は、そう笑って水を飲み干した。
いいえ、いいえ。殿様。杞憂ではありません。だって、もう日常は、温い毎日はもうおくれませんもの。やっぱり、何事もない毎日なんて、この世にはないんです。さっきの事で私は気づいてしまったんです。ああ、今は戦乱の世なんだなぁって……。
水屋(台所)には、すでに殿様のお膳が並べられていた。毒味は済まされている。
氏政様ほどのご身分だと、毒味も丁寧にされているから、椀も焼き物も、もう湯気はたっていない。
氏政様付きの侍女は、最初のお膳を運んでいるところで、こちらに背中を向けていた。
私はふいと目をつぶる。ああ、あの人の気配がする。多分、あの人は見ているのだろう……。
私は懐から紙包みを取り出した。中にあるのは粉末。それをパラリと汁椀に落とす。すぐに溶けて見えなくなり、私はその場を離れた。
渡り廊下を通り過ぎた頃、ふわりと黒い羽が見えたと思ったら、目の前に現れる大きな黒い人影。
覚悟はしていたけれど、音もなく現れるその姿は、やはり恐ろしくて、私は恐怖で声を出すことも出来ず、立ち尽くした。
あっという間に、腕を逆手に捻りあげられる。
「あっ ううっ」
痛みに呻くが、大きな声を出したくなくて、私は反対側の手で自分の口を押さえた。
「…………」
風魔の小太郎と呼ばれる北条随一の忍びから、冷たい殺気が吹き出す。その冷たさに私の口は凍り付きそうだったけれど、それでも何とか口を動かした。
「あれは……、甘草(漢方薬の調和によく使われる薬草)です。体に害はありませんっ」
「…………」
腕を捻りあげられたまま、顎を掴まれ、上を向かされる。
風魔の小太郎様は、私の目をのぞき込んだ。鉄甲で、私はこの方の目をしかと見ることは出来なかったけれど、それでも視線がかち合ったことは感じられた。
腕を離され、私はよろめく。よろめいた体を小太郎様はぐっと掴み、私は悲鳴をあげる間もなく、一緒に跳躍していた。
廊下から、庭の木へ。木から塀へと私を抱えたまま、小太郎様は飛んでゆく。その早さに私はクラクラして、ただしがみついているだけだった。
ストン
と、着地音と共に、私は堅いところに下ろされる。見ると、余り使われることのない倉の中だった。格子窓が開いている。
ああ、人目を避けたのだなと、分かった。私は覚悟を決めて、息を整えた。
「…………」
小太郎様は、私を下ろし、それから腕を組んで立っていた。さっきまでの殺気は消えているけれど、それでも警戒は解かれないだろう。それでいい。
「私が入れたのは確かに、害のない薬です。でも、本当に入れなくてはいけなかったのは、こちらです」
私は懐から、さっきとは違う紙包みを取り出した。
小太郎様が腕をずいと伸ばす。その手のひらに載せると、あの人は包みを解いた。
「吸い込まないようにしてください。劇薬ですから」
私が言うと、包みの中の粉をしげしげと見ていた小太郎様が、私に顔を向けた。そして、ん?というように首を傾げる。
お前は何をしたいのだ?という問いかけのように思えた。