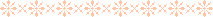知ってるよ、好きだから
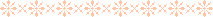
例えば彼女を見かけた時の小さな表情の変化とか、冷たい瞳の中にある青白い炎のようなじわじわとした熱とか、ふいに目を伏せる仕草とか。そして伏し目がちなその瞳はまた同じ方向にそっと持ち上がり、また伏せる。繰り返される本当に小さな小さな動作を私はもう、何百回、何千回と見たことだろう。はっと息を飲み込んでは静かに漏れ出す吐息の音は、きっと私しか知らない。
最初は彼を、柴田勝家を応援していたのだ、私は。いつも無表情な彼が、私に彼女の話を持ちかけるとき、ふっと無色透明に見えるその表情に色が付くのだ。その感覚と言っていいのかわからないけれども、様子を私は綺麗だと思った。そして酷く羨ましかった。私は恋を知らない。恋はするものではなく、おちるものだ。好きな作家の執筆した小説にあった一文である。彼を見ていると、恋と言うものはすごく美麗で甘美な響きすら感じた。今までと生活ががらりと変わるのだろう。生き方も、考え方も。
「名前」
「なあに、」
彼が私の名を呼ぶ。静かに耳に響く、落ち着いた声音で。下校時刻はとっくに過ぎ去った後、校門前にいるのは私と勝家くんだけ。とっぷりと日が暮れて辺りは真っ暗だ。私たちを照らすのは、街頭と時折やってきては過ぎていく車のライトだけ。呼んでくれた彼の、見えない表情を窺うように私よりもずっと高い位置にある顔を見上げる。彼が手を伸ばす。私の腕を捕えて、その手を背中にまわり、そして、一気に抱き寄せた。突然のことに驚きはしたが、拒みはしなかった。ずっと彼の横にいたから、ずっと彼の親友をやっているから分かる。その、漏れた吐息の震えに、私は気付く。
「名前は恋をしたことがないと言ったな」
「うん、そうだよ。ねえ、勝家くん、恋ってどんな感じなの。どんな色をしていて、どんな味がするの。私、わからないの」
「…私は名前が羨ましい…恋慕の情など…いっそ消えて無くなって仕舞えばいい…」
きゅっと強く。私の背に回された彼のその腕が、力を込めた。私の顔が彼の胸に押しつぶされる。とくりとくりと心臓の音が聴こえる。それが恐ろしいほどに、心地良かった。
私はもう一つ知っている。どれだけ彼が彼女を強く想っていることの他にもう一つ。彼女にはもう大切な好い人があり、決して勝家くんにその気持ちが向かないということを。天地がひっくり返らない限り、勝家くんは報われないということを。けれどもその辛さはわからない。私は、彼ではないのだから。
「名前は、私から離れないか…消えて仕舞わないか」
「どうしてそんなこと聴くの。私の一番は勝家くんだよ」
間髪入れずに答えれば、やっぱり彼の顔は見えないけれどふっと表情が緩んだ、と思う。私よりも長くて角ばった指がそっと私の髪を梳く。その指が私の耳に触れた瞬間、私は気付いたのだ。私も、この人を手放したくないと。
彼の胸の中で私は考える。私は彼女に恋する彼が好きだったのだ。恋い慕う表情を、私に見せてくれる彼が。あまりにも無謀すぎる恋に崩れ落ちる前に、精神安定剤の代わりに私を抱きしめる彼が。
落ちる瞬間どころか、私は既に落ちていたのだ。恋に恋をしていた私は、いつの間にか恋をする彼に。
知ってしまった。知ってしまった。だがそれがどうなるというのだろう。どれだけ願っても彼が望むのは雲の上の遠い人で、私はただの、彼の精神安定剤に過ぎないのだ。だから言えない。彼女の代わりに私はなれないだろうか、なんて。もしそれで貴方が泣きそうな目で私を見たら。私から離れてしまったら。耐えられない、耐えられるはずが無いではないか。
ああ、これが恋なのか。甘美なものか。苦しいだけではないか。溺死寸前のような感覚しか無い。息をするのでさえ、躊躇ってしまうまでに鼓動が鳴り響いて、それで。
「ごめん、ごめんね」
私も彼の背に手を回してぎゅっと力を込めれば、ああ、きっと彼は今その切れ長の目が少し見開かれていることだろう。何故謝る、と尋ねる彼に、私は何も答えられなかった。
知ってるよ、好きだから