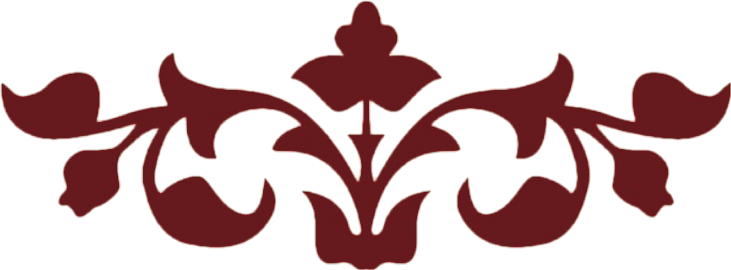
I love…?
翌日、彼は予定通り東京に帰って行った。…と思う。見送りに行っていないから正確には帰ったかどうか分からない。当初の予定では見送りに行く筈だったのだけれど、まさか昨日の今日で笑顔を振り撒きながら見送ることなんて私にはできなくて。鏡に映っているのは泣き腫らした見すぼらしい顔で、自分を嘲るように笑うことしかできなかった。積み重ねてきた年月はあっと言う間に崩れ落ちて、今の私には何も残っていない。幸か不幸か、ここ最近は元々ほとんど連絡を取り合っていなかったから日常生活に大きな支障をきたすことはなかった。
当たり前のことながら、彼からの連絡はひとつもない。ああ、本当に終わってしまったんだなあ。私と彼は、もう赤の他人なんだなあ。日を追うごとにそれを実感して、その度にじわりと涙が滲む。しかも、彼は有名なバレーボール選手だから、なんとなくつけているテレビに映ることもよくあって、忘れようにも忘れられない。
一端の社会人として、プライベートでの出来事を仕事に持ち込むようなことがあってはならないと気を引き締めてはいたけれど、その甲斐虚しく先輩に、調子悪いなら休んでも良いけど、と指摘されてしまった。
好きだった。別れて数日が経っても、1人で泣きじゃくってしまうほどには。彼のどこが好きだったのだろう。どうして好きになったのだろう。答えてくれと言われても今となってはそれすらも分からない。優しいところが好きだった。けれど嫌いだった。私のことを一番に考えてくれるところが好きだった。けれどそういうところも結局は嫌いだった。私は彼に何を望んでいたのだろう。
「それでは、ここでインタビューです!」
あまりにも酷い顔でもしていたのだろうか。疲れているようだからと心配され、なんとも珍しくいただけた3連休。今日はその初日なのに、仕事に行く時と同じぐらいの時間に目が覚めてしまった。
平日の朝、優雅にコーヒーを飲むことができるなんていつぶりか分からない。習慣化しているテレビをつけるという行為はなかなか抜けなくて、なんとなく音のするそちらの方に目を向けると、タイミング悪く今最も見たくない男の顔が映った。
一体何の試合なのかは分からないが、爽やかに汗を拭いながらカメラ目線で笑顔を向ける彼の姿からは目が離せない。テレビを消すことだってできる筈なのに、そうすることもできず、画面の向こう側にいる遠い存在の彼に釘付けになる。
「今日も大活躍でしたね!」
「ありがとうございます」
「この数日は以前にも増して精度が上がったと言いますか…調子が良さそうな印象ですが?」
そうなのか。私と別れてから、彼の調子は上がったのか。そう思うと、別れたのは彼のためになったのかもしれないと、少し自分が救われた気分になる。
「そうですかね…まあ気合いは入っていると思います」
「それはまたどうしてでしょうか?」
「頑張って今以上の選手にならないといけない理由がありまして」
「及川選手は今でも十分素晴しい選手だと思いますが?」
会場中から女性達の黄色い声援が飛ぶ。そりゃあそうだ。学生時代から、彼は女の子にモテモテで引く手数多だったのだから。プロのバレーボール選手として認められている彼は、元々のキラキラした容姿と相俟って以前よりも女性ファンが増えているのだろう。やはり遠いな、と思いながらぼんやりとテレビを見ながらコーヒーを啜る。ああ、苦い。
「今のままじゃまだダメなんです。日本一の…いや、世界一のセッターになって迎えに行きたい人がいるんで」
どよめきがテレビ越しにも伝わる。私の心臓はバクバクと急に鼓動を速めていて、いつのまにか身体が前のめりになっていた。そんな、まさかとは思う。つい最近別れたばかりで、迎えに行きたい人がいるだなんて。二股されていた?それとも、それとも?不安と期待が渦巻く中、インタビューというよりは単なる質問タイムが始まった。
「それは…彼女ということでしょうか?」
「いえ。違います」
「及川選手の片想いということですか?」
「はは…そうですね」
フラれちゃったんで、と。へラリと笑う彼に、胸が疼く。フラれたって。もしかしなくても、私のことなのだろうか。会場にいる女性達の騒ぐ声が聞こえてくるけれど、私にはそんなことどうでもよかった。
片想いって、どういうこと?好きだなんて、付き合ってる時に一言も言ってくれなかったよね?それは、私に対する想いで本当に間違いないの?じゃあどうして、あの時、別れを受け入れたの?尋ねたいことは沢山あるけれど、当たり前のことながらテレビの向こう側にいる彼には届かない。
「それでは最後に、メッセージをどうぞ!」
「いつも応援ありがとうございます。これからも頑張ります。それから、」
へラリと笑っていた顔が一変、途端に真剣な顔つきになった彼は真っ直ぐにカメラを見つめる。そんなことがあるわけないのに、まるで見つめられているかのような、射抜くような視線に、なぜか緊張してしまい、ごくりと唾を飲み込む。
「見てるか分かんないけど。ちゃんと迎えに行くから、待ってて」
ありがとうございましたー!というリポーターの声と盛大な拍手に包まれる中、彼は画面からフェードアウトしていった。画面は野球の話題に切り替わってしまったけれど、私の心の中は騒つくばかりだ。
あのメッセージは私に向けられたものだと自惚れても良いのだろうか。迎えに行くっていつになると思ってるの?今でも十分すぎるぐらいすごいセッターで日本一との呼び声も高いというのに、それ以上にならないと迎えに来てくれないの?私、そんなの待ちくたびれちゃうよ。
彼のこととなるとどうにも涙腺が馬鹿になってしまうようで、いつからか私はボロボロとみっともなく涙を流していた。ただでさえ連日のように泣いているから目はパンパンだし、見れたもんじゃないと思う。けれど、泣くのはきっとこれで終わり。だって、私が今からするべきことは決まっているから。
ふと思い出してカレンダーを眺める。ああ、こんな運命ってあるんだなと場違いにも笑いがこぼれた。私は椅子から立ち上がると、飲みかけのコーヒーを流しに捨ててマグカップを洗う。ひどい顔だということは百も承知だけれど、何度も顔を洗ってなんとか見れる程度には化粧をして誤魔化した。服も、いつもは着ないような綺麗めの白いワンピースに袖を通して、髪も綺麗に整えれば準備は完了。私は少し高めのヒールのパンプスに足を滑りこませて家を出た。
「行かなくちゃ、」
これはただの独り言。自分に言い聞かせるための、単なる決意表明みたいなもの。私が行かなくちゃいけないところなんてただひとつだ。会ったのは、たったの数週間前だっただろうか。つまり、別れてからもそれぐらいしか経過していない筈なのに、その期間が途轍もなく長い時間に思えて。私には彼が、及川徹という人間が必要だと思い知らされた。それでも、徹に必要とされないならばいっしょにいる意味はないと、そう思っていたからこそ、泣きながらでも現状を受け入れようとしていたのに。
徹は、ずるい。優しくてずるい。そんなところが嫌いで、愛おしかった。なんという矛盾だろう。
新幹線に飛び乗って目指すのは東京。片手で足りるほどしか行ったことのないその土地の地理はよく分からない。正直、どこに行けば徹に会えるのかも分からないけれど、行ってびっくりする徹の顔が見たいのだ。
新幹線の中でもそわそわする気持ちは抑えられず、手持無沙汰に携帯をいじる。衝動に駆られるまま飛び出してきて、もしも私に対するメッセージじゃなかったら大恥だけれど。私、本当は、愛されてるって心のどこかで感じてたんだよ。だから、信じてもいいよね?
ガラスの靴だって履いていないし、カボチャの馬車にも乗っていない。王子様の迎えを待つような健気な性格でもない。でもね、徹。私、ずっとあなただけの特別なお姫様になりたかったのかもしれない。我儘でごめんね。素直になれなくてごめんね。行ってどうなるかは分からないけれど。ただあなたに、今でも好きですと伝えることを許してくれませんか。